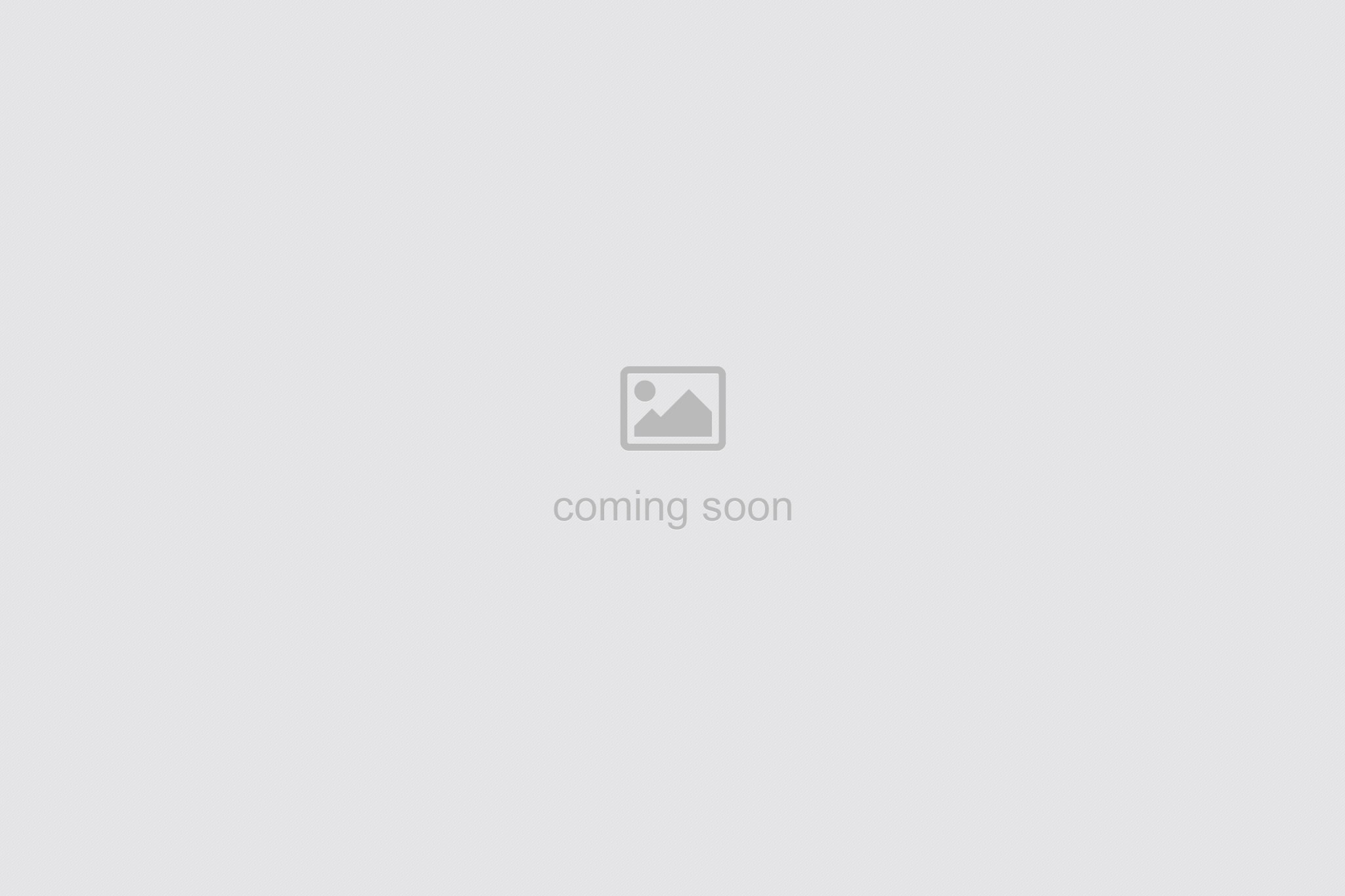2012年9月議会 田中市議 一般質問
2012-09-13
●そこで最悪を覚悟して、最善を尽くすことが危機管理の災害に強いまちづくり・人づくりになると考えますが、いかがですか。
寝屋川市の地域防災計画を見直しのため防災会議が開かれようとしていますが、
●実情にみあった地域防災計画の見直しに取り組むためにも従来の枠をこえ、市民参画での取り組みを具体化すべきです。答弁を求めます。
●また、綿密な計画を作成するためには、各地域の状況、環境に応じた地域防災計画が必要と考えます。見解をお聞きします。
●地域の独居老人や、障害者を把握しておく上でも、個人情報を守ることを前提に情報をつかみ、いざというときには安否確認をできる体制が必要です。この点についてどのようにお考えですか。
障害者の福祉避難所についてです。
東日本大震災は避難所で障害者が一緒に避難できないことが、大きな問題となりました。
補聴器装用の難聴者が周りの人から補聴器のハウリング音がうるさいと言われ、終日避難所の外で時間を過ごし、寝る時だけ避難所に戻る人がいたこと。また、避難所ではハンドマイクで食事や入浴時間の連絡があっても聞こえないため食事・入浴ができないこともあったこと、
心臓機能障害者の場合、寒さに耐えられない、感染症への心配などがあり、避難所にいてもすぐに出ざるを得なかった。また、常時服薬している薬によっては、利尿作用を引き起こす人もあり、そうした人にはトイレの不自由さは大変なストレスになったこと、
精神障害者にとっては、避難所生活は過酷で症状を悪化させ、大声を上げたりして、避難所から精神障害者は出ていってほしいと言われていた等が指摘されています。
●障害児者が安心して生活できる福祉避難所は、第3期寝屋川市障害福祉計画において設置する方向となっています。早期の設置を求めます。物資の確保はもちろんのこと、十分対応できる人材を確保することを求めます。見解をお聞きします。
●同時に、高齢者が安心して生活できる福祉避難所の設置と人的体制を求め、見解をお聞きします。
地域のコミュニティ活動での行政が果たす役割についてです
近年は高齢化や人口の流出・移動によってコミュニティ活動の担い手も少なくなり、またプライバシーを優先する生活形態を異にする集合住宅の進出などもあって地域社会の状況は大きく変わりました。いわゆるコミュニティー活動の衰退という現象です。
地域事情を直視することなく、住民に過大な防災活動を分担させる考え方は、結局、地域防災力の充実には結びつきません。
●こうした問題にどのように対応していくかが大きな課題となっていますが、市としてどのような役割を果たすのか。お聞きします。
予防(減災)対策についてです
予防は減災に向けての取り組みに直結します。地震は自然現象でありますが、地震による災害の多くは人災であると言えます。
●津波や火災、地震などから避難する時間短縮 ・災害時要援護者の安全を行政の責任で対策を行うべきと考えますが、どのように検討されているのですか。お聞きします。
東日本大震災では、家具などの転倒により逃げ遅れて命を落とした人も少なくありません。東京都では今回の東日本大震災の教訓を踏まえて、いち早く家具転倒防止器具設置への助成を全区で普及されました。
西東京市では、65歳以上の1人・2人世帯、障害者世帯へ無料で取り付けています。あわせて、土建組合と連携して、高齢者世帯などでの取り付け支援なども具体化しています。
●家具転倒防止策の奨励や補助金制度を実施すべきです。見解をお聞きします。
大地震の後、火災による被害が起こっています。 初期消火などを徹底することが求められます。
●そこで、倒壊家屋からの発火を防ぐ感震ブレーカの設置助成制度を求めます。見解をお聞きします。
次に生活保護についてです
政府は来年度予算の概算要求基準を閣議決定し、本格的に社会保険関連予算の削減の方向をうちだしました。
特に生活保護基準の引き下げ等を引き金にして、社会保障全体を切り崩そうとしていることは重大です。
生活保護利用者と生活保護費は年々増加しています。それは、不安定・低賃金の非正規労働者が全労働者の3分の1を超え、失業率も高止まりしていることに加え、高齢化が急激に進んでいるにもかかわらず年金制度が脆弱で生活保障機能が弱いことなどに起因しています。この中で、貧困の拡大による負荷が生活保護制度にかかっていることが問題です。
マスコミ等による生活保護バッシングの嵐を作り、当事者が声を上げづらい状況の中で、それに乗じた生活保護削減は、国民のくらしをいっそう困難にするものです。
生活保護基準は、介護保険料の減免や非課税、基礎年金、就学援助金利用の基準となっているからです。基準が引き下げられれば、様々な助成が使いづらくなり、国民のくらしを困難にします。
憲法25条が保障する生存権を具体化した「最後のセーフティネット」である。生活保護制度をしっかり、機能させることを基礎に、国民のくらしを守るための施策の拡充が求められます。
第1に住民生活の実態把握についてです
09年3月18日厚生労働省通知では、次のように述べています。
生活困窮者の中には、極度に困窮した状態になるまで行政機関等に相談することがなく、結果として労働施策や福祉施策等による支援を受ける時間的余裕がない者もいます。このような方については、本来、その前段階で、行政機関等が生活相談を実施し、必要な公的支援を紹介、または実施することが必要であります。
このため、保護の実施期間においては、保健福祉部局及び社会保険・水道・住宅担当部局、ハローワーク、求職者総合支援センター等の関係機関並びに民生委員・児童委員との連携をはかり、生活困窮者の情報が福祉事務所の窓口につながるような仕組みづくりを推進すべきです。
●この通知をうけ、市としてどのような対応をしていますか。お聞きします。
第2に孤立死対策等についてです
今年に入って全国で餓死・孤立死が頻発する事態となっています。とくに、家族が複数の世帯へ増加しており、単身世帯以外にも、孤立死へのリスクが高まっています。
(1)ライフライン事業者等との連携強化による緊急対応についてです。
孤立死にいたる過程では、ほとんどの場合、ライフラインの途絶という過程をたどっています。厚労省、資源エネルギー庁も、福祉事務所とライフライン事業者との連携を求めていますがほとんど実効性があがっていません。
●独自に事業者と協力をすすめ、連携している自治体もあります。本市としても具体化をもとめ、見解をお聞きします。
(2)「リスク層」に対する積極的アプローチについてです。
本来は、ライフラインなどの料金滞納等にいたる前段で、そのようなリスクの高い市民に対して、行政機関の側が積極的にアプローチし、生活保護をはじめ関連する福祉サービス情報を個別に提供し、諸制度の活用による安心、安全な生活を保障することが必要であります。
この意味で、東京都港区での取り組みは注目されています。同区では、一人暮らし高齢者の中から、介護保険や区の福祉サービスの認定はうけているが、利用がない人、(港区では生活保護水準未満の一人ぐらし高齢者が32%を占めている)後期高齢者の中で1年以上の未受診者、ライフライン停止などの緊急性のある人を対象にして、2012年度から区を5地区に分け、各地区の「ふれあい相談室」に各2名配置されたが対象世帯を訪問して必要なサービスにつなぐ活動を行っています。孤立した市民を行政の側が発掘して福祉サービスなどにつなげるシステムを構築した優れた取り組みといえます。
●このような取り組みに学び、寝屋川市での具体化をもとめ、見解をお聞きします。
(3)行政内部の連携強化についてです。
一連の事件では、世帯員の中に障害児者や高齢者がいて障害にかかわる年金や手当を受給していたり、要介護認定を受けたりもしています。こうした世帯においては、その困窮状態を行政内の障害者所管部署や地域包括支援センターが把握できた可能性が有り、行政内部において情報の共有化と連携が行われて、例えば生活保護所管課において生活保護の適用が成されていれば悲劇を妨げたと思われます。
●行政内部の連携の強化についてどのように考えますか、見解をお聞きします。
生活保護申請権の保障についてです
そもそも行政のマニュアルである生活保護の実施要領には、下記のように記されています。「厚生労働次官通知第9 生活保護は申請に基づき開始することを原則としており、保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われる行為も厳に慎むこととしている」福祉事務所職員には、生活保護の相談に訪れたものに対して、保護申請権の存在を助言・教示の上、申請意思を確認すべき法的義務があります。さらに、2009年には、厚労省が作成する生活保護法施行細則準則の標準書式の面接表に申請意思確認欄が設けられました。これにより、福祉事務所の初回面接員は、相談に来た市民に対して「保護の申請をするかどうか」の確認をしなければならなくなりました。
●これをふまえて市としての具体的なとりくみの状況をお聞きします。
●申請権を保障するため次の2つの点を提案します。①福祉事務所の窓口の誰もが手に取れる場所に生活保護申請書を備え置くこと、②相談の最初に保護申請書を示し、生活保護は誰でも無条件に申請する権利があること、原則として申請に基づいて開始されるものであること、申請があれば原則として14日以内に要否判定をし、書面による決定がなされることなどを記載した説明文書を交付したうえで助言・教示するなど行うべきですが、いかがですか。
生活保護ケースワーカーはじめ、必要な職員配置と専門性の向上についてです
生活保護の運用を改善するためには、ケースワーカーの増員、専門化の推進をすすめ、ケースワーカーが迅速かつ効果的に生活保護の相談者及び利用者の問題に対処できる体制づくり等もすすめるべきです。
①ケースワーカーの増員、②社会福祉の専門職採用及び配置、③他法他施策を含めた生活保護・社会福祉全般の研修の充実、④生活保護業務の経験蓄積ができる人事異動の展開などをはかる必要があると考えますが、以上4点について見解をお聞きします。
国への要望についてです
●①保護費の全額国庫負担を実現すること、
②ケースワーカー増員のために現在「標準」数となっているケースワーカーの配置基準を以前のように「法定」数にもどすこと。
③ケースワーカーの専門職採用を促進するために運用指針を示すこと。
市は国に対して求めるべきと考えます。以上3点について、見解をお聞きします。
次に障害福祉についてです
06年に導入された障害者自立支援法は障害者が生きていくために不可欠な支援を「益」と見なして障害者に原則1割の応益負担を強いる過酷な制度であり、障害者らが廃止を強く訴えました。
民主党政権は「自立支援法廃止」と新法制への実施を約束しました。障害者が当事者として会議メンバーにくわわった障がい者制度改革推進会議、総合福祉部会は、新たな法制の骨格提言をとりまとめました。
ところが、6月に成立した障害者総合支援法は、原則無償化を見送り、対象とする難病患者の拡大も一部にとどめました。「骨格提言」が廃止を求めていた「障害程度区分」も盛り込んでいます。障害者の生活実態や支援の要望が反映されない仕組みです。障害者・家族の総意を無視した姿勢は許されるものではありません。
改めて、障害者支援の原則無料化をはじめ障害者、関係者の願いにこたえる法律の実現が強くもとめられていることを指摘します。
第1に障害者・家族の実態把握についてです
障害者と家族の高齢化、生活困難な状況が続いています。
●このような障害者のおかれている状況の把握が必要不可欠となっていますが、どのように把握していますか、お聞きします。
第2に相談支援機能の充実についてです
障害者の実態を把握し、必要な施策につなげる上で、総合的・継続的な相談支援が重要です。
●基幹的な機能を持つ相談支援センターの早期の設置を行い、障害のちがい、程度に応じた相談機能の充実をはかることを求めますが、いかがですか。
福祉事務所の相談機能の強化についてです
●専門職の配置をふやし、障害者への支援強化をはかるべきと考えますが、いかかですか。
第3に基盤整備についてです
入所施設の新設を大阪府に求めることについてです。
重度重複障害者など、家庭ではなかなか対応できないケースがあります。
●そのため大阪府などに入所施設の新設を求めるべきです。見解をお聞きします。
次にショートスティの拡充です。
●受け皿が足りないので希望しても利用できない方が出ています。利用できる施設を増やすこと。病院やケアホームでの併設の具体化をすすめることをもとめます。見解をお聞きします。
次にケアホームの整備と住宅の確保・生活支援についてです。
「施設・病院から在宅へ」が障害者施策の流れとされています。しかし、受け皿が足りない状況です。
●ケアホームを増やすことを求めます。見解をお聞きします。
●住宅を確保し、障害者の生活支援のとりくみをすすめることを求めます。見解をお聞きします。
虐待防止センターが10月から設置されます。
●24時間対応。 個別の対応支援に見合う条件整備を具体的に明らかにすることを求めますが、いかがですか。
次にリフォーム助成制度についてです
地域経済の活性化へ波及効果の大きい「住宅リフォーム助成制度」が全国3県531市町村にひろがり約3割の自治体実施率となり、2004年12月時点の87自治体の6倍強と飛躍的な増加を見せています。実施しているところでは、地域経済の活性化にプラスとなっています。
住宅リフォーム助成制度が実施されている自治体では、工事を地元の中小建設業者に発注することが条件のため、不況による仕事減で困っている業者から歓迎されています。住民からも「助成制度のあるこの機会に思い切ってリフォームを」と歓迎され、申請が増えています。
「リフォーム助成制度は助成総額に対して10~25倍程度の地域への経済効果があり、住民の住環境の向上・整備という側面だけでなく、地域経済の活性化や雇用安定にも大きく貢献するものです。地元中小企業への発注が要件となっていれば、仕事確保につながります」との関係者の声もよせられています。
大阪府内では、藤井寺市、貝塚市で制度化がはじまっています。
藤井寺市は、①建築後5年経過した住宅。②市内に事業所を有する施工業者で行う。③対象工事費30万円以上(消費税抜き)の工事。④対象工事費(消費税抜き)の10%で、最高限度額10万円等の条件となっています。
貝塚市では、今年3月に市長判断で耐震化とセットの住宅リフォーム助成制度が成立しました。
4月にはさらに中小業者が耐震化とリフォームでは利用がしにくいため、耐震とは別で単独での機能改善住宅リフォーム助成を要望し、制度化となりました。①市内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム工事に対する補助金 ②対象工事に要する経費の20%以内(上限20万円)です。仕事おこしになり、市民も業者も喜んでいます。
●寝屋川市において、リフォーム助成制度を実施することを求めます。見解をお聞きします。
次になみはやドームプール利用補助事業についてです
市民プール廃止の激変緩和措置とされた、なみはやドームプール利用補助事業は、寝屋川市在住の方であると確認できれば、利用できます。各市民センター、市役所サービス処ねやがわ屋、市民課、健康増進課で登録並びに、券発行を行っていますが、6月から8月末までの登録は、大人540人、子ども393人、合計933人です。券発行数は、大人932枚、子ども634枚で、合計1,566枚にとどまっています。
発行された券の利用期限は2015年3月31日までとしていますので実際にこの3ヶ月で利用された実数は、わからない状況です。
寝屋川市民プールの利用実績は、昨年は7月、8月の2ヶ月で延べ3万人を超え、それまでは毎年5万人近くの利用となっていました。
●なみはやドームプール利用補助事業はこれまでの市民プールの代替えとしての役割が果たせているといえますか、見解をお聞きします。
その他で最後に8月14日の短時間集中豪雨についてです
4年前、香里園地域でゲリラ豪雨があり、成田西町では床上浸水が起きました。その後、市は南前川の側壁をブロックを2段積み上げたり、下水管のつまりがないように掃除を行い、また、三ツ池への流れをよくするために幅を広げたり手だてを行ったと聞きます。
しかし、8月14日未明の短時間集中豪雨で、再び床上浸水となりました。南前川の側壁から水があふれ、前回想定外と言われていたことがわずか4年後に起きました。もう想定外とは言えません。
●成田西町住民のみなさんは、今回の浸水状況の説明と今後、どのような浸水対策を考えているのか、聞きたいと、市に説明会を開催するよう求めておられています。どのように対応されますか、見解をお聞きします。
寝屋川市の地域防災計画を見直しのため防災会議が開かれようとしていますが、
●実情にみあった地域防災計画の見直しに取り組むためにも従来の枠をこえ、市民参画での取り組みを具体化すべきです。答弁を求めます。
●また、綿密な計画を作成するためには、各地域の状況、環境に応じた地域防災計画が必要と考えます。見解をお聞きします。
●地域の独居老人や、障害者を把握しておく上でも、個人情報を守ることを前提に情報をつかみ、いざというときには安否確認をできる体制が必要です。この点についてどのようにお考えですか。
障害者の福祉避難所についてです。
東日本大震災は避難所で障害者が一緒に避難できないことが、大きな問題となりました。
補聴器装用の難聴者が周りの人から補聴器のハウリング音がうるさいと言われ、終日避難所の外で時間を過ごし、寝る時だけ避難所に戻る人がいたこと。また、避難所ではハンドマイクで食事や入浴時間の連絡があっても聞こえないため食事・入浴ができないこともあったこと、
心臓機能障害者の場合、寒さに耐えられない、感染症への心配などがあり、避難所にいてもすぐに出ざるを得なかった。また、常時服薬している薬によっては、利尿作用を引き起こす人もあり、そうした人にはトイレの不自由さは大変なストレスになったこと、
精神障害者にとっては、避難所生活は過酷で症状を悪化させ、大声を上げたりして、避難所から精神障害者は出ていってほしいと言われていた等が指摘されています。
●障害児者が安心して生活できる福祉避難所は、第3期寝屋川市障害福祉計画において設置する方向となっています。早期の設置を求めます。物資の確保はもちろんのこと、十分対応できる人材を確保することを求めます。見解をお聞きします。
●同時に、高齢者が安心して生活できる福祉避難所の設置と人的体制を求め、見解をお聞きします。
地域のコミュニティ活動での行政が果たす役割についてです
近年は高齢化や人口の流出・移動によってコミュニティ活動の担い手も少なくなり、またプライバシーを優先する生活形態を異にする集合住宅の進出などもあって地域社会の状況は大きく変わりました。いわゆるコミュニティー活動の衰退という現象です。
地域事情を直視することなく、住民に過大な防災活動を分担させる考え方は、結局、地域防災力の充実には結びつきません。
●こうした問題にどのように対応していくかが大きな課題となっていますが、市としてどのような役割を果たすのか。お聞きします。
予防(減災)対策についてです
予防は減災に向けての取り組みに直結します。地震は自然現象でありますが、地震による災害の多くは人災であると言えます。
●津波や火災、地震などから避難する時間短縮 ・災害時要援護者の安全を行政の責任で対策を行うべきと考えますが、どのように検討されているのですか。お聞きします。
東日本大震災では、家具などの転倒により逃げ遅れて命を落とした人も少なくありません。東京都では今回の東日本大震災の教訓を踏まえて、いち早く家具転倒防止器具設置への助成を全区で普及されました。
西東京市では、65歳以上の1人・2人世帯、障害者世帯へ無料で取り付けています。あわせて、土建組合と連携して、高齢者世帯などでの取り付け支援なども具体化しています。
●家具転倒防止策の奨励や補助金制度を実施すべきです。見解をお聞きします。
大地震の後、火災による被害が起こっています。 初期消火などを徹底することが求められます。
●そこで、倒壊家屋からの発火を防ぐ感震ブレーカの設置助成制度を求めます。見解をお聞きします。
次に生活保護についてです
政府は来年度予算の概算要求基準を閣議決定し、本格的に社会保険関連予算の削減の方向をうちだしました。
特に生活保護基準の引き下げ等を引き金にして、社会保障全体を切り崩そうとしていることは重大です。
生活保護利用者と生活保護費は年々増加しています。それは、不安定・低賃金の非正規労働者が全労働者の3分の1を超え、失業率も高止まりしていることに加え、高齢化が急激に進んでいるにもかかわらず年金制度が脆弱で生活保障機能が弱いことなどに起因しています。この中で、貧困の拡大による負荷が生活保護制度にかかっていることが問題です。
マスコミ等による生活保護バッシングの嵐を作り、当事者が声を上げづらい状況の中で、それに乗じた生活保護削減は、国民のくらしをいっそう困難にするものです。
生活保護基準は、介護保険料の減免や非課税、基礎年金、就学援助金利用の基準となっているからです。基準が引き下げられれば、様々な助成が使いづらくなり、国民のくらしを困難にします。
憲法25条が保障する生存権を具体化した「最後のセーフティネット」である。生活保護制度をしっかり、機能させることを基礎に、国民のくらしを守るための施策の拡充が求められます。
第1に住民生活の実態把握についてです
09年3月18日厚生労働省通知では、次のように述べています。
生活困窮者の中には、極度に困窮した状態になるまで行政機関等に相談することがなく、結果として労働施策や福祉施策等による支援を受ける時間的余裕がない者もいます。このような方については、本来、その前段階で、行政機関等が生活相談を実施し、必要な公的支援を紹介、または実施することが必要であります。
このため、保護の実施期間においては、保健福祉部局及び社会保険・水道・住宅担当部局、ハローワーク、求職者総合支援センター等の関係機関並びに民生委員・児童委員との連携をはかり、生活困窮者の情報が福祉事務所の窓口につながるような仕組みづくりを推進すべきです。
●この通知をうけ、市としてどのような対応をしていますか。お聞きします。
第2に孤立死対策等についてです
今年に入って全国で餓死・孤立死が頻発する事態となっています。とくに、家族が複数の世帯へ増加しており、単身世帯以外にも、孤立死へのリスクが高まっています。
(1)ライフライン事業者等との連携強化による緊急対応についてです。
孤立死にいたる過程では、ほとんどの場合、ライフラインの途絶という過程をたどっています。厚労省、資源エネルギー庁も、福祉事務所とライフライン事業者との連携を求めていますがほとんど実効性があがっていません。
●独自に事業者と協力をすすめ、連携している自治体もあります。本市としても具体化をもとめ、見解をお聞きします。
(2)「リスク層」に対する積極的アプローチについてです。
本来は、ライフラインなどの料金滞納等にいたる前段で、そのようなリスクの高い市民に対して、行政機関の側が積極的にアプローチし、生活保護をはじめ関連する福祉サービス情報を個別に提供し、諸制度の活用による安心、安全な生活を保障することが必要であります。
この意味で、東京都港区での取り組みは注目されています。同区では、一人暮らし高齢者の中から、介護保険や区の福祉サービスの認定はうけているが、利用がない人、(港区では生活保護水準未満の一人ぐらし高齢者が32%を占めている)後期高齢者の中で1年以上の未受診者、ライフライン停止などの緊急性のある人を対象にして、2012年度から区を5地区に分け、各地区の「ふれあい相談室」に各2名配置されたが対象世帯を訪問して必要なサービスにつなぐ活動を行っています。孤立した市民を行政の側が発掘して福祉サービスなどにつなげるシステムを構築した優れた取り組みといえます。
●このような取り組みに学び、寝屋川市での具体化をもとめ、見解をお聞きします。
(3)行政内部の連携強化についてです。
一連の事件では、世帯員の中に障害児者や高齢者がいて障害にかかわる年金や手当を受給していたり、要介護認定を受けたりもしています。こうした世帯においては、その困窮状態を行政内の障害者所管部署や地域包括支援センターが把握できた可能性が有り、行政内部において情報の共有化と連携が行われて、例えば生活保護所管課において生活保護の適用が成されていれば悲劇を妨げたと思われます。
●行政内部の連携の強化についてどのように考えますか、見解をお聞きします。
生活保護申請権の保障についてです
そもそも行政のマニュアルである生活保護の実施要領には、下記のように記されています。「厚生労働次官通知第9 生活保護は申請に基づき開始することを原則としており、保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより、申請権を侵害していると疑われる行為も厳に慎むこととしている」福祉事務所職員には、生活保護の相談に訪れたものに対して、保護申請権の存在を助言・教示の上、申請意思を確認すべき法的義務があります。さらに、2009年には、厚労省が作成する生活保護法施行細則準則の標準書式の面接表に申請意思確認欄が設けられました。これにより、福祉事務所の初回面接員は、相談に来た市民に対して「保護の申請をするかどうか」の確認をしなければならなくなりました。
●これをふまえて市としての具体的なとりくみの状況をお聞きします。
●申請権を保障するため次の2つの点を提案します。①福祉事務所の窓口の誰もが手に取れる場所に生活保護申請書を備え置くこと、②相談の最初に保護申請書を示し、生活保護は誰でも無条件に申請する権利があること、原則として申請に基づいて開始されるものであること、申請があれば原則として14日以内に要否判定をし、書面による決定がなされることなどを記載した説明文書を交付したうえで助言・教示するなど行うべきですが、いかがですか。
生活保護ケースワーカーはじめ、必要な職員配置と専門性の向上についてです
生活保護の運用を改善するためには、ケースワーカーの増員、専門化の推進をすすめ、ケースワーカーが迅速かつ効果的に生活保護の相談者及び利用者の問題に対処できる体制づくり等もすすめるべきです。
①ケースワーカーの増員、②社会福祉の専門職採用及び配置、③他法他施策を含めた生活保護・社会福祉全般の研修の充実、④生活保護業務の経験蓄積ができる人事異動の展開などをはかる必要があると考えますが、以上4点について見解をお聞きします。
国への要望についてです
●①保護費の全額国庫負担を実現すること、
②ケースワーカー増員のために現在「標準」数となっているケースワーカーの配置基準を以前のように「法定」数にもどすこと。
③ケースワーカーの専門職採用を促進するために運用指針を示すこと。
市は国に対して求めるべきと考えます。以上3点について、見解をお聞きします。
次に障害福祉についてです
06年に導入された障害者自立支援法は障害者が生きていくために不可欠な支援を「益」と見なして障害者に原則1割の応益負担を強いる過酷な制度であり、障害者らが廃止を強く訴えました。
民主党政権は「自立支援法廃止」と新法制への実施を約束しました。障害者が当事者として会議メンバーにくわわった障がい者制度改革推進会議、総合福祉部会は、新たな法制の骨格提言をとりまとめました。
ところが、6月に成立した障害者総合支援法は、原則無償化を見送り、対象とする難病患者の拡大も一部にとどめました。「骨格提言」が廃止を求めていた「障害程度区分」も盛り込んでいます。障害者の生活実態や支援の要望が反映されない仕組みです。障害者・家族の総意を無視した姿勢は許されるものではありません。
改めて、障害者支援の原則無料化をはじめ障害者、関係者の願いにこたえる法律の実現が強くもとめられていることを指摘します。
第1に障害者・家族の実態把握についてです
障害者と家族の高齢化、生活困難な状況が続いています。
●このような障害者のおかれている状況の把握が必要不可欠となっていますが、どのように把握していますか、お聞きします。
第2に相談支援機能の充実についてです
障害者の実態を把握し、必要な施策につなげる上で、総合的・継続的な相談支援が重要です。
●基幹的な機能を持つ相談支援センターの早期の設置を行い、障害のちがい、程度に応じた相談機能の充実をはかることを求めますが、いかがですか。
福祉事務所の相談機能の強化についてです
●専門職の配置をふやし、障害者への支援強化をはかるべきと考えますが、いかかですか。
第3に基盤整備についてです
入所施設の新設を大阪府に求めることについてです。
重度重複障害者など、家庭ではなかなか対応できないケースがあります。
●そのため大阪府などに入所施設の新設を求めるべきです。見解をお聞きします。
次にショートスティの拡充です。
●受け皿が足りないので希望しても利用できない方が出ています。利用できる施設を増やすこと。病院やケアホームでの併設の具体化をすすめることをもとめます。見解をお聞きします。
次にケアホームの整備と住宅の確保・生活支援についてです。
「施設・病院から在宅へ」が障害者施策の流れとされています。しかし、受け皿が足りない状況です。
●ケアホームを増やすことを求めます。見解をお聞きします。
●住宅を確保し、障害者の生活支援のとりくみをすすめることを求めます。見解をお聞きします。
虐待防止センターが10月から設置されます。
●24時間対応。 個別の対応支援に見合う条件整備を具体的に明らかにすることを求めますが、いかがですか。
次にリフォーム助成制度についてです
地域経済の活性化へ波及効果の大きい「住宅リフォーム助成制度」が全国3県531市町村にひろがり約3割の自治体実施率となり、2004年12月時点の87自治体の6倍強と飛躍的な増加を見せています。実施しているところでは、地域経済の活性化にプラスとなっています。
住宅リフォーム助成制度が実施されている自治体では、工事を地元の中小建設業者に発注することが条件のため、不況による仕事減で困っている業者から歓迎されています。住民からも「助成制度のあるこの機会に思い切ってリフォームを」と歓迎され、申請が増えています。
「リフォーム助成制度は助成総額に対して10~25倍程度の地域への経済効果があり、住民の住環境の向上・整備という側面だけでなく、地域経済の活性化や雇用安定にも大きく貢献するものです。地元中小企業への発注が要件となっていれば、仕事確保につながります」との関係者の声もよせられています。
大阪府内では、藤井寺市、貝塚市で制度化がはじまっています。
藤井寺市は、①建築後5年経過した住宅。②市内に事業所を有する施工業者で行う。③対象工事費30万円以上(消費税抜き)の工事。④対象工事費(消費税抜き)の10%で、最高限度額10万円等の条件となっています。
貝塚市では、今年3月に市長判断で耐震化とセットの住宅リフォーム助成制度が成立しました。
4月にはさらに中小業者が耐震化とリフォームでは利用がしにくいため、耐震とは別で単独での機能改善住宅リフォーム助成を要望し、制度化となりました。①市内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム工事に対する補助金 ②対象工事に要する経費の20%以内(上限20万円)です。仕事おこしになり、市民も業者も喜んでいます。
●寝屋川市において、リフォーム助成制度を実施することを求めます。見解をお聞きします。
次になみはやドームプール利用補助事業についてです
市民プール廃止の激変緩和措置とされた、なみはやドームプール利用補助事業は、寝屋川市在住の方であると確認できれば、利用できます。各市民センター、市役所サービス処ねやがわ屋、市民課、健康増進課で登録並びに、券発行を行っていますが、6月から8月末までの登録は、大人540人、子ども393人、合計933人です。券発行数は、大人932枚、子ども634枚で、合計1,566枚にとどまっています。
発行された券の利用期限は2015年3月31日までとしていますので実際にこの3ヶ月で利用された実数は、わからない状況です。
寝屋川市民プールの利用実績は、昨年は7月、8月の2ヶ月で延べ3万人を超え、それまでは毎年5万人近くの利用となっていました。
●なみはやドームプール利用補助事業はこれまでの市民プールの代替えとしての役割が果たせているといえますか、見解をお聞きします。
その他で最後に8月14日の短時間集中豪雨についてです
4年前、香里園地域でゲリラ豪雨があり、成田西町では床上浸水が起きました。その後、市は南前川の側壁をブロックを2段積み上げたり、下水管のつまりがないように掃除を行い、また、三ツ池への流れをよくするために幅を広げたり手だてを行ったと聞きます。
しかし、8月14日未明の短時間集中豪雨で、再び床上浸水となりました。南前川の側壁から水があふれ、前回想定外と言われていたことがわずか4年後に起きました。もう想定外とは言えません。
●成田西町住民のみなさんは、今回の浸水状況の説明と今後、どのような浸水対策を考えているのか、聞きたいと、市に説明会を開催するよう求めておられています。どのように対応されますか、見解をお聞きします。
2012年9月議会 中林市議 一般質問
2012-09-13
関電管内で、最も電力が多かったのは、2682万キロワットで、関西広域連合が「原発なしで供給可能」とした、2714万キロワットを下回りました。
関電の「最大3015万キロワット」という予測が過大だったことは明らかです。
福島原発事故は、未だに収束せず、原因究明も尽くされていません。全国どこであっても、原発を安全に運転できる保証はありません。
本市にも、原発ゼロの会が発足しました。
重要なことは、国が原発からの撤退を決断し、節電や自然エネルギーを推進と、原発に依存しない体制をつくることです。
この立場から、市として、
1,政府に、「原発ゼロの日本」への政治決断をもとめること。
2,関西電力に対し、
①大飯原発3.4号機の即時停止と、
②今年の電力需給を、気温、節電などの実態に即して検証することを求めること。
以上、見解をお聞きします。
● 次に、自然エネルギーの取組についてです。
「都会の電力のために、私たちが犠牲になるのはいやです。エネルギーは地産地消にしてください。」これは、福島原発の被害者の声です。
自然エネルギー社会の実現にむけては、風車、太陽光、バイオマス、地熱など、各地域・自治体で、さまざまな取り組みが広がっています。
本市での、太陽光パネルの設置については
1.市役所庁舎、学校、保育所、幼稚園、体育館など、公共施設への設置を具体的に 検討すること。
2,市内の民間保育所や、介護施設などの改築に活用できる、施設整備補助制度の
周知をはかること。
3.府内16自治体で実施している、市民や民間が利用できる設置補助制度を
本市で創設すること。 以上の見解をお聞きします。
次に、自然空間の少ない都市部における取り組みについてです。
東京メトロ線は、2つの駅のホームの屋根に、太陽光パネルを設置し、もう1駅を検討中です。
コンビニやスーパー、野球場やサッカー場への設置、また、路線バスの屋根にも設置できます。
超小型の水力発電器は、落差のある支流、農業用水などに簡単に設置できます。
マットや床下に設置する振動発電は、電車の改札口やビルの自動ドアなど、人が歩く振動で電気を生み出すことができます。
市民からは、第2京阪道路の蓋かけ部分などを活用して、太陽光パネルが設置できないかなどの声も寄せられています。
都市部での、自然エネルギーのとりくみについては、市民の提案や意見を聞く場を設けるなど、市民的な取り組みができないか、お聞きします。
● 次に、熱中症対策についてです。
今年も昨年同様に猛暑となりました。
熱中症、または熱中症の疑いで、救急搬送された寝屋川市民は、7月で44人、8月で35人となっています。重傷の80才の女性が、熱中症の疑いで死亡されました。
以下、取り組みついて、お聞きします。
1,一人暮らしの高齢者に、訪問などによる熱中症予防の啓発をおこなうこと
2,公共施設などを活用して、避難所の設置や、保冷剤などの配布をおこなうこと
3,エアコンの未設置世帯への、設置費用の貸し付けについては、社会福祉協議会の 貸し付けが利用しにくい実態があります。活用できるよう、改善を求めます。
● 次に、本市の幼保一体化施策についてです。
今議会には、市立すみれ保育所を認定子ども園にしないでほしい。池田幼稚園を廃園にしないでほしいという請願が15184筆の署名を添えて提出されています。
この請願は、保育所型認定こども園 仮称すみれこども園の開設について、保健福祉部こども室が、4月にすみれ保育所保護者に、口頭で、明らかにしたことをうけてのものです。
さらに、7月25日教育委員会定例会で決められた、「保育所型認定こども園の開設に伴う池田幼稚園の廃園」については、池田小、2中校区の、幼稚園教育がよくなるとは到底思えない。また、長期間の工事は、園児の幼稚園教育をうける権利を、狭めるものであり、やめてほしいという当たり前の、保護者の願いが込められたものです。
本市がすすめる、幼保一体化としての「保育所型」認定こども園と、池田幼稚園の廃園については、多くの問題があります。
★第1は、認定こども園は、これまでの保育所の民営化とは違うという点です。
児童福祉法では、保育の実施責任は、市町村にあるとしています。
それを可能としているのは、市町村が、入所児童・保育料の決定や、保育計画に責任をもっているからこそです。
保護者の所得に関係なく、保育の質が確保されること、保育に欠ける児童の緊急性に応じて、入所が決定されること、保護者の事情に関係なく保育が継続されること、「待機児解消計画」の作成などが、行政の責任で行われることが大事です。
現在、寝屋川市内の認可保育所は、民間も公立も同じように、こういったことが行われています。
こども室は、すみれ保育所保護者に「保育所型だから、何も変わらない」といいます。しかし、認定こども園は、法的には、全くの別枠になります。
保護者と事業者との直接契約となり、入所児童も、保育料も決定権は、市ではなく、事業者になります。
行政が関われるのは、募集要項でできるだけ条件をつけること、但し書きで、協力をお願いすること、入所手続き・保育料徴収事務の委託を受けることまでです。
市は、「募集要項に入れる、但し書きでお願い」して、今と同じようにすると言いますが、開設当初は可能だとしても、期限の保証はありません。
例えば、高石市の取石認定こども園は、公立保育所と公立幼稚園が一体化した「幼保連携型」です。公立の良さを継続させるために、市と事業者が44項目にわたる協定書を締結していますが、協定期間は、現保育所児が卒園する5年間に限られました。あとは、事業者次第ということです。
以下お聞きします。
1、「認定こども園」の根拠法、設置基準などについて、保護者や地域に説明し、今までの民営化との違いを明らかにすべきです。なぜ、しないのかお聞きします。
2、市の公立保育所の民営化方針では、「公立保育所の保育水準を維持すること」を明確にしています。認定子ども園で、何を根拠に、いつまで、公立保育所の水準を守るというのか、お聞きします。
★第2は、「保育所型」についての問題です。
認定子ども園は、4種類あり、地域の実情に応じて、都道府県が認定するとしています。
4類型のうち、幼保連携型は、認可保育所と認可幼稚園が一体的な運営をするタイプで、幼稚園型は、認可幼稚園に保育機能をつけ加えたもの、保育所型は、認可保育園に幼稚園をつけ加えたもの、地域裁量型は、幼稚園も保育園も無認可です。
大阪府下では、26園の認定こども園がありますが、幼稚園型が1園、保育所型は、1法人だけで、3園を運営しています。
この法人が運営する「保育所型」の特徴は、有名私立小学校への進学実績をかかげ、オプション式で、英会話、ペン習字、体育指導、学習指導、ピアノ講習などをおこなっていることです。お金がなければ通えないと言われています。視察したこども室は、「寝屋川には合わない」との答弁でした。
認定こども園のスタートから3年目に、国の「認定こども園制度の在り方検討会」は、「4類型のうち、教育・保育の質の維持・向上を図る観点からは、将来的には幼保連携型が望ましい」と報告しています。
5日の文教常任委員会で、認定こども園で「幼児教育の低下につながらないのか」と聞かれ、教育委員会は「低下ではなくて、さらに良くなるとの認識のもとで、認定こども園の開設に賛同の上、すすめていく」と答弁しました。
しかし、「保育所型」は、幼稚園は無認可です。保育所型であっても、認定こども園の幼稚園は、幼稚園教育要領に基づいて実施されます。しかし、教育委員会は所管しません。
また、私学助成がなく、幼稚園収入は、保育料だけになり、会計面でも、充実どころか、大きな後退となります。
このような問題をもつ「保育所型」についての説明や議論は、7月25日の教育委員会定例会では、一切されていません。
5日の文教常任委員会の審議では、「保育所型認定こども園」を決めたのは、保健福祉部であり、教育委員会ではない、教育委員会は「もろてをあげて賛同しただけ」との答弁でした。
こども室は、当初、認定子ども園 4類型のうち、幼保連携型が望ましいと考えていたと聞きます。今年1月頃、大阪府に相談したら、私立幼稚園の定員が空いている状態では、認可はできないと言われ、保育所型しかなかったと経過を説明しています。
以下、お聞きします。
1,「保育所型」を選択すれば、この地域の幼稚園教育が大きく後退することを、承知の上で決めたのでしょうか? 現時点でどのように考えているのか、市長部局と教育委員会、両方からの答弁を求めます。
2,「保育所型」で、現在の公立の幼稚園教育をどう継続していくのか、見解をお聞きします。
3,公立幼稚園と公立保育所を幼保一体化で、「保育所型」認定こども園にしたケースが、全国で1件でもあるのかどうか、調査の上、見解をもとめます。
★ 第3は、保育所児と幼稚園児の合同保育の問題です、
こども室は、すみれ保育所保護者に、1日の保育の流れを説明して、納得できない保護者に対して、「保育内容は変わらない、何も心配することはない」とくり返し言っています。
しかし、4.5歳児では、保育所児と幼稚園児の混合クラスになります。
保育所と幼稚園の大きな違いは、保育時間と夏休みなどの休暇による、保育日数の違いです。
早朝から夜まで、保育所を生活の場として、すごす保育所児と、主に午前中の短時間を就学前教育として教育をうける幼稚園児では、1日の過ごし方が違います。
朝9時から昼過ぎまでの短時間の幼稚園児は、密度を濃くしても集中できます。午後から、自宅ですごすことができるからです。
一方、朝8時から夕方6時までを、保育所ですごす保育所児は、長時間保育の中で静的、動的動きのバランスに配慮しながら、長い1日を家庭に変わる生活の場として保育所ですごします。
この1日の違いを見ないで、短時間児に合わせて、午前中の活動を尊重すれば、保育所児の昼からの活動を、どう保証していくのかということが問題になります。
また、幼稚園児がいない夏休みなどの保育内容の問題、運動会、生活発表会、お泊まり保育、クラス懇談会、保護者会とPTA、文字指導・扱う楽器の違い、行事の日程や時間、取り組み方の違いなど、多くの課題が現実にあります。
先ほど紹介した、取石認定こども園では、開設2年目でも、保育所児と幼稚園児は、別クラスで、運動会や生活発表会の出し物も、保育所の4歳児、幼稚園の4歳児というように、別になっています。
すみれ保育所の現行の保育の継続については、民営化だけでも難しいのに、同じ施設内に、長時間児と短時間児が一緒にいる中で、保育内容が何も変わらないというのは、何を根拠にしてのことなのか、説明をもとめます。
★ 第4に、幼保一体化を進めるための、庁内での検討や準備、市民の合意形成についてです。
幼保一元化は、幼稚園と保育所を今後どうしていくのかという政策であり、課題です。 戦後、幼稚園教育と保育所保育は、別々の道を歩んできました。
近年、幼保一元化が取りあげられてきた背景には、少子化の中で、働く女性が増え、保育所ニーズが高くなってきたことがあります。
幼稚園の定員が空いているのに、近くの保育所では、待機児童がいる状況が、出てくる中で、特に地方では、幼稚園の経営が困難になり、1つの施設で共用できないかとの方向が探られています。
しかし、幼稚園は、学校教育法に基づき、文部科学省が所管し、保育所は、児童福祉法に基づき、厚生労働省の所管です。
就学前の教育・保育をどう考えて行こうかというのが、幼保一元化の課題です。
この課題を十分に検討しないまま、予算の削減を狙いとして、保育所と幼稚園の制度をそのままにして、06年にスタートしたのが、幼保一体化の、認定こども園です。
当初2000カ所の予定が、現在911カ所しかなく、京都府には、認定子ども園は1園もありません。
認定こども園の開設については、行政の押しつけ的な流れの中にあっても、幼保一体化をどう進めていくのかということで、「幼保連携のあり方検討会」や審議会の設置、新たに「幼保連携課」などの担当課を創設して、進めているのが全国の実態です。
本市の幼保一体化だけが、他市と比べ、拙速で、何より、こどものことを考えていないものであることは、今や市民の目にも明らかです。
まず、教育委員会と保健福祉部は、連携ができていません。
教育委員会は、第24回幼児教育振興審議会から「当面新しいタイプの幼児教育施設は検討しない」この新しいタイプとは、当時の議論から、幼保一体化の施設のことですが、そういう答申を受けていながら、認定こども園の開設に賛成しました。
しかるに、認定こども園の幼稚園教育は、どのようになるのかとの質問に、「所管が違う」と答弁しません。これでは、幼保一体化は名ばかりで、池田小校区、及び2中校区内の、幼稚園教育を切り捨てる扱いではありませんか。
以下お聞きします。
1,認定こども園の開設を決める前に、こどもにとって「良いのかどうか。」「何がが良くて、実施したらどんな問題が生じるのか」などの、検討がされていません。
なぜ、「十分な検討」や「保護者や市民合意を得ること」などの事前準備を怠り、今の事態になっているのか、お聞きします。
2、本市で、今、認定こども園の開設が必要かどうかについてです。
保護者のニーズに合ったものだと、教育委員会は答弁しましたが、本市では、そのようなニーズ調査は、おこなっていません。
傍聴した保護者から、「幼保一体化の要望はしていない」との声がよせられています。見解を、お聞きします。
3,これまでの公立保育所の民営化は、行革の一環として、効果額の試算まで出して、廃止してきました。今回の、池田幼稚園の廃園について、教育委員会は、「行革ではない」と答弁しましたが、幼稚園教育の充実より、廃園を優先したのではないですか。首脳会議での議論の内容と見解をお聞きします。
4,寝屋川で初めての「幼保一体化」をぶっつけ本番で始めれば、一番被害を受けるのは、幼いこども達です。どのようにお考えかお聞きします。
★第5に、そもそも、認定こども園を導入する過程に、問題があったと思います。
昨年6月の、首脳会議で、新システムの総合施設を、国で決まっていない段階で、十分な検討もせずに、決めたこと自体は、問題です。見解をお聞きします。
その後、総合施設法案が取り下げられ、3党合意の修正法案である「こども子育て関連法案」に変わりました。 資料1(全保連・修正法案に対する見解)をご覧下さい。
この「関連法案」自体は、問題をもつものですが、評価できる修正点もあります。
保育所、幼稚園については、今のまま存続できること、民間保育所は、現行通り、市町村が保育の実施義務をおうように、修正されました。
一方、認定こども園については、修正されず、市町村の義務とはなっていません。
「総合施設法案」が取り下げられ、認定子ども園の修正案が提案されました。4つの類型は残りますが、「幼保連携型」以外では、施設の認定基準が緩和されるなど、保育内容に格差が生じることが懸念されます。また、保育所型は、株式会社の参入ができることとされました。
「総合施設法案」が取り下げられた時に、認定子ども園を白紙にもどべきでした。そうすれば、すみれ保育所は、市の実施義務をおう、民間保育所として残れたのです。また、保育所型を見直すこともできたはずです。先を見通した見極めができなかった理由をお聞きします。
第6に、市民への説明責任についてです。
本市の幼保一体化施策である、認定こども園の開設については、市の説明責任は、まったく果たされていません。
昨年8月のすみれ保育所保護者への、民営化の説明会では、(会議録を見ますと)、新システムでの総合施設のことが少しでてきます。参加名の話では、その時は、民営化そのものが問題であって、総合施設への理解はなかったといいます。
こども室は、昨年12月には「総合施設ではなく、現行の認定こども園にしたい」と説明し、すみれ保護者から内容を聞かれて、「視察して、勉強してから説明する」としています。
今年2月の説明会では、両方の施設を使って保育所型にしたいとしました。保護者に認定子ども園への理解がない中で、資料は、堺市、高石市、茨木市などの幼保連携型でした。保育所型との違いについては、一切説明されていません。
7月5日の説明会では、池田幼稚園を増築して、保育所型で開設することが、首脳会議で決まったと説明しました。
昨年9月に、民営化をを決めるときには、首脳会議で総合施設を決めておきながら、保護者には十分な説明をせず、3か月後には、現行制度での「保育所型認定子ども園」に変更、事業者募集10月を控えて7月には、池田幼稚園を増築しての、開設場所の変更となりました。
すみれ保育所保護者は、幼保一体化や認定子ども園の開設について、十分な説明をうけないまま、度重なる市の方針の変更に、ほんろうされた1年でした。
この間の民営化に関わって、最高裁判決は、行政の裁量権の逸脱について、
行政が、説明をつくさず、拙速にした場合、または要求しても拒んだ場合、そのことで、不利益をうける人があれば、処分の違法性を認め、賠償金の支払いを命じています。資料2(大東市上三箇保育所の廃止・民営化での裁判結果)を参照ください。
保護者、市民に対して、大きな負担をかけながら、初めての幼保一体化で、認定こども園を、十分な検討もなしで決める、こんな無責任な進め方は改めるべきです。見解をお聞きします。
次に、池田幼稚園の廃園と工事についてです。
池田幼稚園の保護者は、7月5日、すみれ保育所の説明会で、来年7月から2月までの増築工事を知りました。
保護者が、子どもへの影響を心配して、説明会の開催を求めて、再三、議会へ要請いただきました。就学前のこどもの、豊かな成長を願う保護者の気持ちは、痛いほどよくわかります。
保護者から、地域を閉め出して行われた、8月27.30日の説明会の議事録と音声テープが、市議会に届きました。
説明会の最後に、保護者代表が参加者全員に「2日間の説明で、教育委員会・こども室の説明に納得できなかった方、ご起立願います」と聞いたら、全員が起立しています。
さらに、続けて
「これが、私たち保護者の気持ちです。この説明会において、来年度に、必ずしも、工事が必要であるという、理由は見受けられません。廃園そのものも、幼保一体化とは、言い難い「保育所型での認定こども園」という選択は、公立幼稚園を失う立場の地域から見て、理由にさえなっていないと言えます。地域の方々を閉めだし、廃園案の内容を隠し、議会にかけようとする行為も、まったく、市民として理解しがたい、詐欺に等しい行為です。以上をもって、保護者代表の意見とします」と締めくくっています。
教育委員会は、池田幼稚園の保護者に、説明が遅れたことに対し、反省と謝罪をしています。反省しているというなら、まず、せっ速な進め方を見直し、来年の工事は、やめるべきです。廃園も9月議会で決めるべきではないと思います。
以下、お聞きします。
1,そもそも、保護者や地域が、再三求めた説明会を拒否し、9月議会で、廃園を決めてからしか、説明しようとしなかったことについては、どのように考えているのか、お聞きします。
2,保護者や地域の要請のもと、ようやく開かれた説明会に参加しようと、地域、OB,来年度入所希望の市民などが、足を運んだのに、2回にわたり、約20数名を閉め出したと聞きました。地元への説明はされていません。地元の誰もが参加できる説明会を、25日本会議までに開くよう求めます。
3,池田幼稚園の保護者の理解も得ない状態で、来年度工事をしなければ、認定こども園が開設できないなら、開設は見合わせるべきと考えます。
4,この間の幼保一体化施策、認定こどもの開設の進め方は、園馬場市長が公約した「市民との協働のまちづくり」や「みんなのまち基本条例」(の透明性の確保、市民の意見、要望に誠実に応答すること、政策の立案などをわかりやすく説明すること、市民参画での意見を検討し、市政に反映すること)からも、大きく逸脱するものです。見解を求めます。
関電の「最大3015万キロワット」という予測が過大だったことは明らかです。
福島原発事故は、未だに収束せず、原因究明も尽くされていません。全国どこであっても、原発を安全に運転できる保証はありません。
本市にも、原発ゼロの会が発足しました。
重要なことは、国が原発からの撤退を決断し、節電や自然エネルギーを推進と、原発に依存しない体制をつくることです。
この立場から、市として、
1,政府に、「原発ゼロの日本」への政治決断をもとめること。
2,関西電力に対し、
①大飯原発3.4号機の即時停止と、
②今年の電力需給を、気温、節電などの実態に即して検証することを求めること。
以上、見解をお聞きします。
● 次に、自然エネルギーの取組についてです。
「都会の電力のために、私たちが犠牲になるのはいやです。エネルギーは地産地消にしてください。」これは、福島原発の被害者の声です。
自然エネルギー社会の実現にむけては、風車、太陽光、バイオマス、地熱など、各地域・自治体で、さまざまな取り組みが広がっています。
本市での、太陽光パネルの設置については
1.市役所庁舎、学校、保育所、幼稚園、体育館など、公共施設への設置を具体的に 検討すること。
2,市内の民間保育所や、介護施設などの改築に活用できる、施設整備補助制度の
周知をはかること。
3.府内16自治体で実施している、市民や民間が利用できる設置補助制度を
本市で創設すること。 以上の見解をお聞きします。
次に、自然空間の少ない都市部における取り組みについてです。
東京メトロ線は、2つの駅のホームの屋根に、太陽光パネルを設置し、もう1駅を検討中です。
コンビニやスーパー、野球場やサッカー場への設置、また、路線バスの屋根にも設置できます。
超小型の水力発電器は、落差のある支流、農業用水などに簡単に設置できます。
マットや床下に設置する振動発電は、電車の改札口やビルの自動ドアなど、人が歩く振動で電気を生み出すことができます。
市民からは、第2京阪道路の蓋かけ部分などを活用して、太陽光パネルが設置できないかなどの声も寄せられています。
都市部での、自然エネルギーのとりくみについては、市民の提案や意見を聞く場を設けるなど、市民的な取り組みができないか、お聞きします。
● 次に、熱中症対策についてです。
今年も昨年同様に猛暑となりました。
熱中症、または熱中症の疑いで、救急搬送された寝屋川市民は、7月で44人、8月で35人となっています。重傷の80才の女性が、熱中症の疑いで死亡されました。
以下、取り組みついて、お聞きします。
1,一人暮らしの高齢者に、訪問などによる熱中症予防の啓発をおこなうこと
2,公共施設などを活用して、避難所の設置や、保冷剤などの配布をおこなうこと
3,エアコンの未設置世帯への、設置費用の貸し付けについては、社会福祉協議会の 貸し付けが利用しにくい実態があります。活用できるよう、改善を求めます。
● 次に、本市の幼保一体化施策についてです。
今議会には、市立すみれ保育所を認定子ども園にしないでほしい。池田幼稚園を廃園にしないでほしいという請願が15184筆の署名を添えて提出されています。
この請願は、保育所型認定こども園 仮称すみれこども園の開設について、保健福祉部こども室が、4月にすみれ保育所保護者に、口頭で、明らかにしたことをうけてのものです。
さらに、7月25日教育委員会定例会で決められた、「保育所型認定こども園の開設に伴う池田幼稚園の廃園」については、池田小、2中校区の、幼稚園教育がよくなるとは到底思えない。また、長期間の工事は、園児の幼稚園教育をうける権利を、狭めるものであり、やめてほしいという当たり前の、保護者の願いが込められたものです。
本市がすすめる、幼保一体化としての「保育所型」認定こども園と、池田幼稚園の廃園については、多くの問題があります。
★第1は、認定こども園は、これまでの保育所の民営化とは違うという点です。
児童福祉法では、保育の実施責任は、市町村にあるとしています。
それを可能としているのは、市町村が、入所児童・保育料の決定や、保育計画に責任をもっているからこそです。
保護者の所得に関係なく、保育の質が確保されること、保育に欠ける児童の緊急性に応じて、入所が決定されること、保護者の事情に関係なく保育が継続されること、「待機児解消計画」の作成などが、行政の責任で行われることが大事です。
現在、寝屋川市内の認可保育所は、民間も公立も同じように、こういったことが行われています。
こども室は、すみれ保育所保護者に「保育所型だから、何も変わらない」といいます。しかし、認定こども園は、法的には、全くの別枠になります。
保護者と事業者との直接契約となり、入所児童も、保育料も決定権は、市ではなく、事業者になります。
行政が関われるのは、募集要項でできるだけ条件をつけること、但し書きで、協力をお願いすること、入所手続き・保育料徴収事務の委託を受けることまでです。
市は、「募集要項に入れる、但し書きでお願い」して、今と同じようにすると言いますが、開設当初は可能だとしても、期限の保証はありません。
例えば、高石市の取石認定こども園は、公立保育所と公立幼稚園が一体化した「幼保連携型」です。公立の良さを継続させるために、市と事業者が44項目にわたる協定書を締結していますが、協定期間は、現保育所児が卒園する5年間に限られました。あとは、事業者次第ということです。
以下お聞きします。
1、「認定こども園」の根拠法、設置基準などについて、保護者や地域に説明し、今までの民営化との違いを明らかにすべきです。なぜ、しないのかお聞きします。
2、市の公立保育所の民営化方針では、「公立保育所の保育水準を維持すること」を明確にしています。認定子ども園で、何を根拠に、いつまで、公立保育所の水準を守るというのか、お聞きします。
★第2は、「保育所型」についての問題です。
認定子ども園は、4種類あり、地域の実情に応じて、都道府県が認定するとしています。
4類型のうち、幼保連携型は、認可保育所と認可幼稚園が一体的な運営をするタイプで、幼稚園型は、認可幼稚園に保育機能をつけ加えたもの、保育所型は、認可保育園に幼稚園をつけ加えたもの、地域裁量型は、幼稚園も保育園も無認可です。
大阪府下では、26園の認定こども園がありますが、幼稚園型が1園、保育所型は、1法人だけで、3園を運営しています。
この法人が運営する「保育所型」の特徴は、有名私立小学校への進学実績をかかげ、オプション式で、英会話、ペン習字、体育指導、学習指導、ピアノ講習などをおこなっていることです。お金がなければ通えないと言われています。視察したこども室は、「寝屋川には合わない」との答弁でした。
認定こども園のスタートから3年目に、国の「認定こども園制度の在り方検討会」は、「4類型のうち、教育・保育の質の維持・向上を図る観点からは、将来的には幼保連携型が望ましい」と報告しています。
5日の文教常任委員会で、認定こども園で「幼児教育の低下につながらないのか」と聞かれ、教育委員会は「低下ではなくて、さらに良くなるとの認識のもとで、認定こども園の開設に賛同の上、すすめていく」と答弁しました。
しかし、「保育所型」は、幼稚園は無認可です。保育所型であっても、認定こども園の幼稚園は、幼稚園教育要領に基づいて実施されます。しかし、教育委員会は所管しません。
また、私学助成がなく、幼稚園収入は、保育料だけになり、会計面でも、充実どころか、大きな後退となります。
このような問題をもつ「保育所型」についての説明や議論は、7月25日の教育委員会定例会では、一切されていません。
5日の文教常任委員会の審議では、「保育所型認定こども園」を決めたのは、保健福祉部であり、教育委員会ではない、教育委員会は「もろてをあげて賛同しただけ」との答弁でした。
こども室は、当初、認定子ども園 4類型のうち、幼保連携型が望ましいと考えていたと聞きます。今年1月頃、大阪府に相談したら、私立幼稚園の定員が空いている状態では、認可はできないと言われ、保育所型しかなかったと経過を説明しています。
以下、お聞きします。
1,「保育所型」を選択すれば、この地域の幼稚園教育が大きく後退することを、承知の上で決めたのでしょうか? 現時点でどのように考えているのか、市長部局と教育委員会、両方からの答弁を求めます。
2,「保育所型」で、現在の公立の幼稚園教育をどう継続していくのか、見解をお聞きします。
3,公立幼稚園と公立保育所を幼保一体化で、「保育所型」認定こども園にしたケースが、全国で1件でもあるのかどうか、調査の上、見解をもとめます。
★ 第3は、保育所児と幼稚園児の合同保育の問題です、
こども室は、すみれ保育所保護者に、1日の保育の流れを説明して、納得できない保護者に対して、「保育内容は変わらない、何も心配することはない」とくり返し言っています。
しかし、4.5歳児では、保育所児と幼稚園児の混合クラスになります。
保育所と幼稚園の大きな違いは、保育時間と夏休みなどの休暇による、保育日数の違いです。
早朝から夜まで、保育所を生活の場として、すごす保育所児と、主に午前中の短時間を就学前教育として教育をうける幼稚園児では、1日の過ごし方が違います。
朝9時から昼過ぎまでの短時間の幼稚園児は、密度を濃くしても集中できます。午後から、自宅ですごすことができるからです。
一方、朝8時から夕方6時までを、保育所ですごす保育所児は、長時間保育の中で静的、動的動きのバランスに配慮しながら、長い1日を家庭に変わる生活の場として保育所ですごします。
この1日の違いを見ないで、短時間児に合わせて、午前中の活動を尊重すれば、保育所児の昼からの活動を、どう保証していくのかということが問題になります。
また、幼稚園児がいない夏休みなどの保育内容の問題、運動会、生活発表会、お泊まり保育、クラス懇談会、保護者会とPTA、文字指導・扱う楽器の違い、行事の日程や時間、取り組み方の違いなど、多くの課題が現実にあります。
先ほど紹介した、取石認定こども園では、開設2年目でも、保育所児と幼稚園児は、別クラスで、運動会や生活発表会の出し物も、保育所の4歳児、幼稚園の4歳児というように、別になっています。
すみれ保育所の現行の保育の継続については、民営化だけでも難しいのに、同じ施設内に、長時間児と短時間児が一緒にいる中で、保育内容が何も変わらないというのは、何を根拠にしてのことなのか、説明をもとめます。
★ 第4に、幼保一体化を進めるための、庁内での検討や準備、市民の合意形成についてです。
幼保一元化は、幼稚園と保育所を今後どうしていくのかという政策であり、課題です。 戦後、幼稚園教育と保育所保育は、別々の道を歩んできました。
近年、幼保一元化が取りあげられてきた背景には、少子化の中で、働く女性が増え、保育所ニーズが高くなってきたことがあります。
幼稚園の定員が空いているのに、近くの保育所では、待機児童がいる状況が、出てくる中で、特に地方では、幼稚園の経営が困難になり、1つの施設で共用できないかとの方向が探られています。
しかし、幼稚園は、学校教育法に基づき、文部科学省が所管し、保育所は、児童福祉法に基づき、厚生労働省の所管です。
就学前の教育・保育をどう考えて行こうかというのが、幼保一元化の課題です。
この課題を十分に検討しないまま、予算の削減を狙いとして、保育所と幼稚園の制度をそのままにして、06年にスタートしたのが、幼保一体化の、認定こども園です。
当初2000カ所の予定が、現在911カ所しかなく、京都府には、認定子ども園は1園もありません。
認定こども園の開設については、行政の押しつけ的な流れの中にあっても、幼保一体化をどう進めていくのかということで、「幼保連携のあり方検討会」や審議会の設置、新たに「幼保連携課」などの担当課を創設して、進めているのが全国の実態です。
本市の幼保一体化だけが、他市と比べ、拙速で、何より、こどものことを考えていないものであることは、今や市民の目にも明らかです。
まず、教育委員会と保健福祉部は、連携ができていません。
教育委員会は、第24回幼児教育振興審議会から「当面新しいタイプの幼児教育施設は検討しない」この新しいタイプとは、当時の議論から、幼保一体化の施設のことですが、そういう答申を受けていながら、認定こども園の開設に賛成しました。
しかるに、認定こども園の幼稚園教育は、どのようになるのかとの質問に、「所管が違う」と答弁しません。これでは、幼保一体化は名ばかりで、池田小校区、及び2中校区内の、幼稚園教育を切り捨てる扱いではありませんか。
以下お聞きします。
1,認定こども園の開設を決める前に、こどもにとって「良いのかどうか。」「何がが良くて、実施したらどんな問題が生じるのか」などの、検討がされていません。
なぜ、「十分な検討」や「保護者や市民合意を得ること」などの事前準備を怠り、今の事態になっているのか、お聞きします。
2、本市で、今、認定こども園の開設が必要かどうかについてです。
保護者のニーズに合ったものだと、教育委員会は答弁しましたが、本市では、そのようなニーズ調査は、おこなっていません。
傍聴した保護者から、「幼保一体化の要望はしていない」との声がよせられています。見解を、お聞きします。
3,これまでの公立保育所の民営化は、行革の一環として、効果額の試算まで出して、廃止してきました。今回の、池田幼稚園の廃園について、教育委員会は、「行革ではない」と答弁しましたが、幼稚園教育の充実より、廃園を優先したのではないですか。首脳会議での議論の内容と見解をお聞きします。
4,寝屋川で初めての「幼保一体化」をぶっつけ本番で始めれば、一番被害を受けるのは、幼いこども達です。どのようにお考えかお聞きします。
★第5に、そもそも、認定こども園を導入する過程に、問題があったと思います。
昨年6月の、首脳会議で、新システムの総合施設を、国で決まっていない段階で、十分な検討もせずに、決めたこと自体は、問題です。見解をお聞きします。
その後、総合施設法案が取り下げられ、3党合意の修正法案である「こども子育て関連法案」に変わりました。 資料1(全保連・修正法案に対する見解)をご覧下さい。
この「関連法案」自体は、問題をもつものですが、評価できる修正点もあります。
保育所、幼稚園については、今のまま存続できること、民間保育所は、現行通り、市町村が保育の実施義務をおうように、修正されました。
一方、認定こども園については、修正されず、市町村の義務とはなっていません。
「総合施設法案」が取り下げられ、認定子ども園の修正案が提案されました。4つの類型は残りますが、「幼保連携型」以外では、施設の認定基準が緩和されるなど、保育内容に格差が生じることが懸念されます。また、保育所型は、株式会社の参入ができることとされました。
「総合施設法案」が取り下げられた時に、認定子ども園を白紙にもどべきでした。そうすれば、すみれ保育所は、市の実施義務をおう、民間保育所として残れたのです。また、保育所型を見直すこともできたはずです。先を見通した見極めができなかった理由をお聞きします。
第6に、市民への説明責任についてです。
本市の幼保一体化施策である、認定こども園の開設については、市の説明責任は、まったく果たされていません。
昨年8月のすみれ保育所保護者への、民営化の説明会では、(会議録を見ますと)、新システムでの総合施設のことが少しでてきます。参加名の話では、その時は、民営化そのものが問題であって、総合施設への理解はなかったといいます。
こども室は、昨年12月には「総合施設ではなく、現行の認定こども園にしたい」と説明し、すみれ保護者から内容を聞かれて、「視察して、勉強してから説明する」としています。
今年2月の説明会では、両方の施設を使って保育所型にしたいとしました。保護者に認定子ども園への理解がない中で、資料は、堺市、高石市、茨木市などの幼保連携型でした。保育所型との違いについては、一切説明されていません。
7月5日の説明会では、池田幼稚園を増築して、保育所型で開設することが、首脳会議で決まったと説明しました。
昨年9月に、民営化をを決めるときには、首脳会議で総合施設を決めておきながら、保護者には十分な説明をせず、3か月後には、現行制度での「保育所型認定子ども園」に変更、事業者募集10月を控えて7月には、池田幼稚園を増築しての、開設場所の変更となりました。
すみれ保育所保護者は、幼保一体化や認定子ども園の開設について、十分な説明をうけないまま、度重なる市の方針の変更に、ほんろうされた1年でした。
この間の民営化に関わって、最高裁判決は、行政の裁量権の逸脱について、
行政が、説明をつくさず、拙速にした場合、または要求しても拒んだ場合、そのことで、不利益をうける人があれば、処分の違法性を認め、賠償金の支払いを命じています。資料2(大東市上三箇保育所の廃止・民営化での裁判結果)を参照ください。
保護者、市民に対して、大きな負担をかけながら、初めての幼保一体化で、認定こども園を、十分な検討もなしで決める、こんな無責任な進め方は改めるべきです。見解をお聞きします。
次に、池田幼稚園の廃園と工事についてです。
池田幼稚園の保護者は、7月5日、すみれ保育所の説明会で、来年7月から2月までの増築工事を知りました。
保護者が、子どもへの影響を心配して、説明会の開催を求めて、再三、議会へ要請いただきました。就学前のこどもの、豊かな成長を願う保護者の気持ちは、痛いほどよくわかります。
保護者から、地域を閉め出して行われた、8月27.30日の説明会の議事録と音声テープが、市議会に届きました。
説明会の最後に、保護者代表が参加者全員に「2日間の説明で、教育委員会・こども室の説明に納得できなかった方、ご起立願います」と聞いたら、全員が起立しています。
さらに、続けて
「これが、私たち保護者の気持ちです。この説明会において、来年度に、必ずしも、工事が必要であるという、理由は見受けられません。廃園そのものも、幼保一体化とは、言い難い「保育所型での認定こども園」という選択は、公立幼稚園を失う立場の地域から見て、理由にさえなっていないと言えます。地域の方々を閉めだし、廃園案の内容を隠し、議会にかけようとする行為も、まったく、市民として理解しがたい、詐欺に等しい行為です。以上をもって、保護者代表の意見とします」と締めくくっています。
教育委員会は、池田幼稚園の保護者に、説明が遅れたことに対し、反省と謝罪をしています。反省しているというなら、まず、せっ速な進め方を見直し、来年の工事は、やめるべきです。廃園も9月議会で決めるべきではないと思います。
以下、お聞きします。
1,そもそも、保護者や地域が、再三求めた説明会を拒否し、9月議会で、廃園を決めてからしか、説明しようとしなかったことについては、どのように考えているのか、お聞きします。
2,保護者や地域の要請のもと、ようやく開かれた説明会に参加しようと、地域、OB,来年度入所希望の市民などが、足を運んだのに、2回にわたり、約20数名を閉め出したと聞きました。地元への説明はされていません。地元の誰もが参加できる説明会を、25日本会議までに開くよう求めます。
3,池田幼稚園の保護者の理解も得ない状態で、来年度工事をしなければ、認定こども園が開設できないなら、開設は見合わせるべきと考えます。
4,この間の幼保一体化施策、認定こどもの開設の進め方は、園馬場市長が公約した「市民との協働のまちづくり」や「みんなのまち基本条例」(の透明性の確保、市民の意見、要望に誠実に応答すること、政策の立案などをわかりやすく説明すること、市民参画での意見を検討し、市政に反映すること)からも、大きく逸脱するものです。見解を求めます。
2012年9月議会 太田議員 一般質問
2012-09-13