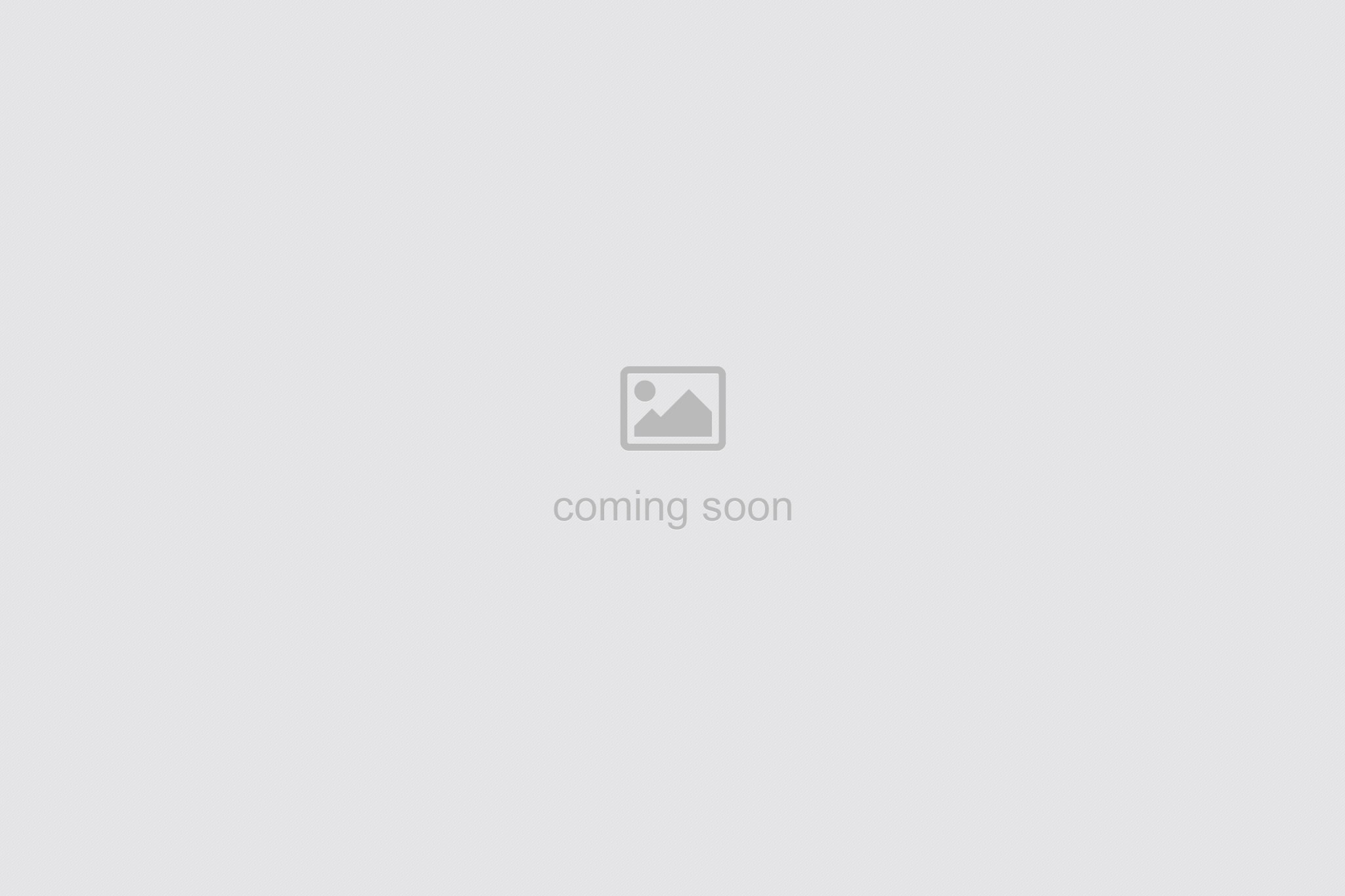次に、旧明徳幼稚園についてです。地域では、幼児向けに開放して欲しいとの声もあります。以前から第2京阪道路の建設に伴って発掘された文化財を大阪府文化財センターから譲り受け、寝屋川市が保管し、研究調査をすすめて市民への公開を含む活用を行うよう求めてきました。2階を収納場所に、1階を施設開放するよう検討を求めます。市民の財産を市民、住民に意見を聴くことなく市が勝手に処分すべきではありません。見解をお聞きします。
○次に、中学校給食実施の検討についてです。
この間、約4ヶ月近くにわたって6回の検討委員会が開催され、最終報告書が教育長に提出されました。すべての委員会を傍聴しましたが、中学校給食の早期実施と日課表に大きな変化をもたらさないことを主眼に、実施方式を比較検討することに終始したと思います。結果として、当初からデリバリー方式ありきだったのかとの印象さえ持ちました。傍聴し、最終報告書を見て、不足していたと感じるいくつかの点についてお聞きします。
最終報告書は、学校教育法をふまえて、「はじめに」と述べています。委員会では、学校給食法にもとづく議論はありませんでした。
・学校給食法は、「目的」として、①児童・生徒の心身の健全な発達、②食育の推進、を謳っています。また、目標として掲げられた7項目は、学校給食が教育の一環であることを具体的に示しています。
学校給食実施基準では、当該学校に在学するすべての児童・生徒に対する実施を謳っています。また、実施回数、個別の健康状態への配慮、栄養内容について述べています。摂取基準の適用については、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること、とあります。
次に、学校給食衛生管理基準として、(第1)国連食糧農業機関・世界保健機関の合同食品規格委員会の考え方に基づき、(第2)学校給食施設や設備とそれらの衛生管理、また、(第3)調理過程等における衛生管理基準として、献立作成や食材購入、食品の検収・保管等、さらには調理過程、配送及び配食、検査及び保存食等、定期検査と実施記録の保管、(第4)衛生管理体制に係る衛生管理基準として、学校や教育委員会の衛生管理体制、学校給食従事者の衛生管理、、健康管理、食中毒の集団発生の際の措置、定期検査と実施記録の保管、(第5)日常及び臨時の衛生検査、(第6)雑則として、記録の1年間保存、クックチル方式実施の場合の留意事項など、多項目にわたって厳しい内容が定められています。
こうしたことをふまえた議論は、残念ながら委員会ではまったく不十分だったと言わなければなりません。実施にあたって、学校給食法に基づく十分な検討が必要と考えます。市教委として、実施にあたっての基本と位置づけている、学校給食法に照らしての重要な点があれば、明らかにして下さい。
・次に、「寝屋川の給食をよくする会」が中学校給食の実施に関しての見解を表明していますが、実施検討にあたって、子ども・保護者・市民などの意見をよく聞くことが必要です。予定している計画を明らかにして下さい。
・先にあげた衛生管理基準の内容からも、学校給食には何よりも安全・安心が求められます。検討委員会の報告では、民間調理業者に委託するデリバリー方式が望ましいとされています。学校給食法を読む限り、共同調理を委託する場合でも、学校給食専用施設にする必要があると感じました。仮に委託業者が衛生管理基準をクリアーできない場合は、基準を満たすために必要な改修とその費用はどこが負担することになるのか、見解をお聞きします。
・検討委員会では、小学校の給食が全国的にも高く評価される実践を蓄積してきたことが意見としてくり返し出されました。命にかかわるアレルギー対応では、除去食にとどまらないで代替食を行う水準となっています。その土台に自校直営方式の学校給食がありました。教育の一環として実施するためには、自校直営が最善と言えます。1校でも2校でも可能であれば、そうした検討を行うべきと考えます。検討委員会で示されたグラウンドに限らずに、敷地全体の中で、使っていない建物の建て替えも含めて検討する余地があると考えますが、いかがですか。
・次善の策としては、直営の給食センター方式があると考えます。旧明徳幼稚園の活用について、先に述べましたが、提起した構想の検討がまったくない場合、旧明徳幼稚園と旧明徳小学校の一部を合わせて市立給食センターに建て替えることも一案ではないでしょうか。自校方式であれ、給食センター方式であれ、雇用対策としても重要と考えます。見解をお聞きします。
・学校給食として実施する限り、生徒全員に提供する必要があります。生活保護はもちろんですが、就学援助の扶助対象にもすべきと考えます。見解をお聞きします。
・検討委員会やこの間の行政視察を通じて、配膳員などの配置が必要と感じました。教職員全体でとりくむことと合わせて実施に向けて、配膳員の配置をどう考えているのか、明らかにして下さい。
・学校給食では、栄養士や栄養職員の配置が不可欠です。見解をお聞きします。
○次に、廃プラ健康被害についてです。
・通告していました4市専門委員会に関連しての質問については、建設にあたっての参考値とされた1400μg/m3がすでに高濃度の汚染と指摘されていた柳沢意見書をふまえて、健康被害を多数の住民が訴える現状に照らして必要と準備をしましたが、別の機会にすることにします。
・大阪高裁判決後、廃プラ施設周辺の住民を中心に、2つの施設稼動以後の健康被害を訴える51名が、国の公害等調整委員会に「原因裁定」を求める申請を行っています。今後、第2次申請も検討していると聞いています。
これまでも多くの健康被害の訴えを紹介してきましたが、今回の質問にあたって、新たにお聞きした方を含め、何人かの訴えを紹介します。
①太秦地域の廃プラ施設から400mのところに住んでおられる建設関係の方です。日中は仕事に出ていますが、それ以外の時間は家で過ごしています。
平成17年の終わり頃から、プラスチックの焼けるような嫌な臭いがよくするようになりました。夜の9時から10時くらいに臭いがきつく、夏場など、窓を開けていると家の中まで臭います。仕事から帰って、妻と毎日1時間くらい、犬の散歩に行きます。住宅街を通って治水公園というのがコースです。治水公園の付近で臭いがした日は気分が悪くなります。臭いは日によって違いますが、天気が悪い日は特に臭います。平成18年頃が一番きつかったと思います。
滅多に風邪もひかず、いたって健康でしたが、平成18年の春から、むせるようなぜん息の発作のような咳が出るようになりました。横になると咳が止まらなくなるので、寝るときも壁にもたれて、うつらうつらするしかない時期もありました。ヒィーヒィーとぜん息の息づかいになることもしょっちゅうでした。
関西医大では原因がわからないと言われました。半年後、他の病院に通院するようになり、沢山の種類の薬を飲んでいます。咳を抑えて気管を広げる薬や痰切れをよくする薬の効き目か、ぜん息の発作は出なくなりました。咳をすると、人に風邪と間違われて嫌な顔をされるので、人と話しにくくなってしまいました。今も2ヶ月に一度CTやレントゲンを撮る検査を受けています。
今年家を改築するため、半年ほど妻と廃プラ施設から1.2km離れたところに住みました。そこでは臭いもせず、症状も和らぎました。娘と孫は、施設から700mほどのマンションに住みましたが、症状は改善しませんでした。改築が終わり、夏に自宅に戻ったところ、家族全員に症状がぶりかえしました。
②太秦地域の30代女性です。15年近く、廃プラ施設から600mのところに住んでいます。大阪市内の勤務から現在は転勤で京都の方に通勤しています。
廃プラ施設が稼動して以来、母は甘酸っぱい臭いがするとか、眼が痒い、鼻がむずむずするとか、いろんな症状を訴え始めました。私も会社から帰宅の際、自宅近くのバス停に降りた瞬間、猛烈な廃プラ臭にであい、息を止めて猛ダッシュで家に帰り、「死ねということかと思った」と家族に話したほど、ひどい臭いでした。そんな悪臭に濃淡はありますが、帰宅途中のバスの中で、窓が開いていないのに車中の空気が変わるのを感じたり、降車の際に廃プラ臭にでくわしたり。我が家も引っ越した方がいいのでは?と話したこともあります。
廃プラ工場が稼動してからは、風邪引き後の咳が長びきます。伊豆の山の上のホテルに泊まったとき、咳が不思議に出なくなりました。一番驚いたことは、今年の1月から健康のためにと、バス通勤を止め、寝屋川市駅まで歩いていました。3月中旬、足首等に湿疹ができ、体中に広がって皮膚科の薬でも治りませんでした。25日には突然顔が赤く腫れ上がり、ショックでこの先どうなるのか不安で、その晩は眠れませんでした。信頼している医師の指示で大阪市内のホテルに1ヶ月ほど宿泊をし、徐々に回復をして自宅に戻りました。
③太秦地域の20代女性です。今のところに住むようになったのは、幼い頃からよく風邪をひいていた私に自然が豊かで環境が良いと両親が思ってくれたからです。
こちらに来てからは風邪をひくこともなく、毎日治水緑地などで遊んでいました。しかし、平成16年暮れから風邪をひくようになり、治りかけても息苦しさや全身の怠さ、無気力感がひどくなり、かかりつけ医からは、「体が回復していない」とほぼ毎回注射を打ってもらっていました。変な臭いを感じ始めた頃から、風邪をひくと呼吸困難に陥るようになりました。薬を飲んでも一向に治る気配がありませんでした。学校の勉強も霞がかかったように何も頭に入らず、得意だった音楽のやる気も起こらなかったほどでした。今年から大阪市内で子ども相手に仕事をしていますが、仕事場に行くと呼吸がとても楽になります。しかし、寝屋川に帰ってくると息が苦しくなり、家の近くになると咳が止まらず、眼の痒みや鼻水も止まらなくなります。一番しんどいのは、仕事柄子どもたちと遊ぶので毎日とても疲れますが、寝て2時間ほどすると咳が出て起きてしまいます。そこからは眠ることもできず、ほとんど寝ずに出勤する毎日です。処方される薬も強くなっていくので、体にも負荷ががかかり、今では薬がないと呼吸するのさえままならないほどです。
思い起こすと、健康悪化は、廃プラ施設の操業が始まって6ヶ月ほど経ったとき、外に出ると変な臭いを感じ始めた頃でした。最近は、「味覚」を感じなくなり、食欲も低下してきています。また、「手足が攣る」ことが多くあり、忘れ物がひどくなったり、年齢では考えられない症状が出てきています。貧血や目まいもあり、本当に毎日暮らしていくのがしんどいです。
・これまでも症状が重くなった人は、財産の多くを持って行くこともできずに引っ越さざるを得なくなったり、別荘がある人は週末避難をくり返し、顔の湿疹が出なくなってきたという声もありました。
今回、症状を伺うために他にも何人か訪ねましたが、臭いがしたときには、環境政策に連絡をしているという人もいました。最近は夜に焦げた臭いがよくすると言います。廃プラの臭いの苦情件数がどれだけあるのか、どう処理しているのか、明らかにして下さい。
環境疫学の津田敏秀岡山大学教授は、平成18年と平成22年の調査結果から、「何度やっても同じだ」と言われました。さらに詳細に聞き取った症状を、皮膚粘膜刺激症状の主な症状として、共通する症状を、眼症状、皮膚症状、咽頭症状、呼吸器症状の4つにまとめておられます。そのうえで、有意差から、廃プラ工場に近いほど眼症状、皮膚症状、呼吸器症状の倍率が高いことを示しました。また、神経障害に関わると思われる症状が増えているのが気になると、「冷や汗をかく」「身体がカッとなって汗をかく」などの症状は、放出されるVOCの中に、神経毒性のある物質が含まれている点をふまえると、非常に懸念すると述べておられます。
原因物質は特定されていないけれど、大変なことが起きている。健康被害の訴えの多くの事実について、どう認識していますか。見解をお聞きします。
・寝屋川市はこれまで「健康被害が明らかになれば、廃プラ施設の稼動の停止を求める」と答弁してきました。今もこの答弁に変わりはありませんか。
・廃プラによる健康被害はないと、健康調査を否定し続けていますが、健康調査をせずに健康被害がないと断言する科学的な根拠は何ですか。
・2008年6月2日の参議院行政監視委員会で日本共産党の山下芳生議員が寝屋川病と言えるほどの深刻な事態として、、廃プラスチックリサイクル工場周辺の健康被害の訴えをとりあげています。
大事な点は、環境問題への対応としての予防原則、すなわち完全な科学的確実性がなくても深刻な被害をもたらすおそれがある場合には対策を遅らせてはならないという考え方を、環境大臣も、厚生労働大臣も認識したうえで答弁していることです。環境大臣は、「病状等がいろいろと新たに起こってくるようでしたら、しっかりと予防原則に沿って、これは特に自治体が主体でありますけれども、我々も注視しつつ連携をさせていただきたいと、こういうふうに思います。」と述べ、厚労大臣は、「保健所(は)地域住民の健康を守るために必要な調査研究を行うことができる・・・(略)・・・まだ臭いがするとかいろんな状況があれば更に踏み込んだ調査があってしかるべきだろうと思います・・・(略)・・・保健所としては自治体の市と連携を取りながらそういうことをきちんとやって、今環境大臣がおっしゃたように、ひょっとしたら今までの基準値に挙げていない新たな物質が、化学物質が発生しているかもしれないんで、私は国民の生命をしっかり守るという立場で厚生労働行政をやっていますけれども、・・・(略)・・・基本的にはやはり地域にしっかりしてもらいたいですね。その限りにおいて我々は、もちろん連携して協力をする・・・」「現に健康被害を訴える方がおられれば、そういう方の立場に立って、何ができないかじゃなくて、何ができるかという形での行政をやっぱりやるべきだというふうに思います。」
寝屋川市として、国会での政府答弁をどう受けとめているのか、国会は国の最高機関であり、大変重い内容です。健康被害の訴えに対して、住民の命・健康・安全に責任を負う自治体として、このことをふまえた対応があらためて必要と考えます。答弁を求めます。
・ごみ収集のあり方について
これまでも廃プラ健康被害の訴えを通じて、汚れた廃プラごみは可燃ごみとして処理することが確認されてきました。しかし、市民への周知徹底が不十分なため、カラスの格好のえさとして、ごみの散乱につながっている様子を見ることが多くなっています。
また、北河内4市リサイクル施設でつくられた再商品化基準適合物を日本容器包装リサイクル協会を通じて再商品化業者に引き渡すにあたって、4市の昨年度実績を見ても5億円以上の公的資金が支払われています。大半を引き受けているイコール社は約35万枚を超える再生パレットを生産しています。リサイクル率60%を目指していますが、現状は半分に満たない状況です。住民の中で言われている1枚600円として、2億1千万円以上の収入となります。容リ協からの収入と合わせて7億円を超えます。4市の収集運搬費用を含めれば、健康被害の発生源と示唆されている民間業者の利益のために、もう1つの発生源になったとされる4市施設と合わせ、まさに多額の税金と公的資金が使われている経済的な非効率は、見直しが必要な大きな問題です。再生プラは、強度が弱く、劣化も早く、商品的には欠陥と言えます。健康被害解消のためにも、有償で引き取ってもらえるペットボトルやトレイなどを除いて、可燃ごみにすることが課題となっています。廃プラごみの分別収集は、容器包装リサイクル法では努力義務とされているだけであり、義務ではありません。完全に燃やせば、多種多様な化学物質が発生する心配もなく、水と二酸化炭素になるだけとの学者の意見もあります。廃プラのその他プラごみを生ゴミと同時に収集したときに、市の費用の増減はどうなりますか。説明して下さい。
長い目で財政を考えたとき、負担の軽減、解消につながります。時期を失せず見直すべきと考えます。見解をお聞きします。
○第2京阪道路などの環境行政について
・大阪府が府内14箇所の大気観測局にPM2.5測定器を設置するため、業者の入札を行ったと聞いています。寝屋川市役所局にも設置されます。住民の願いを受けた施策として歓迎します。同時に、大阪府が検討していると聞きますが、住民の環境に大変化をもたらした巨大道路、第2京阪道路沿道にこそ、環境行政に位置づけられた大気汚染防止法に基づく常時監視局の設置が必要であり、PM2.5の測定が必要です。設置場所としては、複合汚染が心配されるトンネルの京都側坑口部がふさわしいと考えます。国や大阪府への要望は当然ですが、市としての設置も含め、見解をお聞きします。
・昨年11月の交通量と較べて、今年6月の交通量は一般部の大型車を除いて、小型車、大型車ともに増加しています。とくに、専用部の増加が目立ちます。交通量予測の約8万台に近くなっていますが、専用部の大型車の混入率は予測を大きく下回っています。交通量予測との関係で現状をどう見ているのか、大気汚染、騒音、振動等の環境影響について、現状と将来の見通しをどう分析しているのか、明らかにして下さい。
・第2京阪道路の大気汚染や騒音、振動などの影響は、環境基準をクリアーしているとはいえ、NO2データでは、供用前と較べて、供用後、寝屋南局、小路局とも市役所局を上回るようになっています。浪速国道事務所が住民に説明していた寄与濃度の予測値の5倍以上の大気汚染をもたらしています。また、騒音についても平均値では基準をクリアーしていても、深夜などに走る瞬間的な爆音が安静な生活に影響を与えています。振動についても、個人差もあり、寝ている枕元を通して感じる日もあります。長期にわたる観測と生活への影響調査が必要と考えます。見解をお聞きします。
・この間、環境政策課として3ヶ月ごとにNO2の簡易測定が行われています。そうした努力は率直に評価したいと思います。8月から測定されている第8中学校は、学校の健康調査で、アレルギー性結膜炎が受診者の3割近く、アレルギー性鼻炎が2割を超える年があり、測定結果も11月調査では、測定箇所の中で高い方でした。子どもたちの健康状況が心配される学校園や保育所など、汚染が心配される市内全域での測定を行うよう求めます。見解をお聞きします。
○高宮廃寺等の文化財の活用調査と専門職員の配置について
今年度の教育委員会の主な9事業の1つに高宮廃寺跡の活用調査があります。第2京阪道路建設にあたって大量に発掘された文化財、寝屋川市域にある貴重な文化財などと合わせて活用調査を行うには、寝屋川市の専門職員の絶対数が不足しています。加えて、新たに(仮称)イオンモール四條畷店の建設予定に伴う新家での発掘調査が行われています。近隣の四條畷市や交野市では、新採用によって複数体制を維持しています。また、枚方市は4人の職員と2名の非常勤の6名、さらに関係の財団法人が新規採用を行って3名の職員と2名の非常勤の5名と聞きます。市として、埋蔵文化財を含む貴重な文化財の研究調査と市民への公開などの活用検討をすすめる事業推進のために、新規採用を含む専門職員の増員が不可欠と考えます。見解をお聞きします。
○学童保育(留守家庭児童会)事業について
・今回の保育料徴収条例の委員会審査の中で、施設設備等の条件整備とともに、4年生以上の障がい児入所が保護者、関係団体からの強い要望であることが示されました。今回の条例提案を受けて、寝屋川市の状況とともに、大阪府内の状況を調べました。寝屋川に限らず、共通して重大な課題になっていることを痛感しました。寝屋川では、現在、希望者は、全員入所できていると聞いています。しかし、中には、希望する児童会に入会できていないため、保護者の状況によっては、ファミリーサポート制度を利用したり、障害福祉を活用したり、送迎にかなりの困難を抱えている事情も耳にします。大阪府内の自治体によっては、障がい児については小学校6年生までと明記しているところもあります。障害とは、生きるうえでの社会的ハンディキャップを持つことです。だからこそ、社会的な支援が必要と考えます。公平・平等とは、一律に同じようにすることではありません。実態としての平等を実現するためには、特別の支援が必要です。来年度の入所の具体的解決を要望するとともに、基本的施策とするよう、検討を要望します。
・次に、指導員についてです。正職員の配置はなくなりましたが、障がい児に対する研修とともに、集団生活の中での子どもたちの発達・成長をめざして、充実した研修が毎年行われていると聞いています。また、指導員を通じて、その成果を実感することがよくあります。しかし、せっかく専門性を豊かに身につけても、指導員にとっての現実は正職員採用の道はありません。教育委員会にとっても、系統性・継続性を必要とする事業のために、せっかく専門力量を身につけた指導員を育成しても、今の労働条件のままでは、優秀な指導員を失うおそれが常にあります。一定以上の能力、実績を持った指導員については、正採用の道を検討すべきではありませんか。見解をお聞きします。
・次に、全員入所の要望に応える条件整備です。カギは、国の補助金が最も高く設定されている36人~45人の複数学級制を基本にすることです。また、放課後の児童健全育成事業が概ね10歳と謳っていることから、現行の3年生を4年生とすることで、学校の規模にも地域の実状にもよりますが、2学級、3学級と設定することで、可能性がうまれると考えます。ぜひ検討を求めます。
・次に施設・設備の充実についてです。現在、寝屋川市は、学校体育館のトイレの改修を計画的に進めています。しかし、体育館トイレについては、学校間格差があり、男子の小用がほとんど使えないところもあると聞きます。応急措置が必要です。調査のうえ、早急な対応を求めます。
・最後に、土曜日の開設と保育時間の延長です。9月議会での他議員の質問を受けて、アンケート調査が行われていると聞きます。調査状況と検討結果を明らかにして下さい。子どもにとって、長時間が決して良いとは思いませんが、残念ながら労働環境はまったく好転していません。他市では、土曜日の利用者、時間延長の利用者に追加負担を求めているところもあります。保護者や関係団体との協議、合意が必要と考えますが、検討を求めます。見解をお聞きします。
○その他
8日の建設水道常任委員会で、市民プール廃止に関する審査が行われました。その中で、当初の提案理由と異なる説明がありました。プールの利用にあたって、安心・安全な提供を確保できないというものでした。年間200人のけがの被害があるといいますが、夏に日本共産党議員団が視察した際には、看護師から「ほとんど利用がない」という話がありました。被害記録があると思います。提出を求めます。また、耐震性に問題があり、危険が大きいとの議論もありました。耐震性を確保する改修費が7,500万円と理解していましたが、建て替えに5~6億円の答弁もありました。体験上最大の地震だった1995年の阪神大震災の時の被害状況、5~6億円の根拠になる調査、検討内容を明らかにして下さい。早急な資料提出を求めます。
○次に、中学校給食実施の検討についてです。
この間、約4ヶ月近くにわたって6回の検討委員会が開催され、最終報告書が教育長に提出されました。すべての委員会を傍聴しましたが、中学校給食の早期実施と日課表に大きな変化をもたらさないことを主眼に、実施方式を比較検討することに終始したと思います。結果として、当初からデリバリー方式ありきだったのかとの印象さえ持ちました。傍聴し、最終報告書を見て、不足していたと感じるいくつかの点についてお聞きします。
最終報告書は、学校教育法をふまえて、「はじめに」と述べています。委員会では、学校給食法にもとづく議論はありませんでした。
・学校給食法は、「目的」として、①児童・生徒の心身の健全な発達、②食育の推進、を謳っています。また、目標として掲げられた7項目は、学校給食が教育の一環であることを具体的に示しています。
学校給食実施基準では、当該学校に在学するすべての児童・生徒に対する実施を謳っています。また、実施回数、個別の健康状態への配慮、栄養内容について述べています。摂取基準の適用については、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること、とあります。
次に、学校給食衛生管理基準として、(第1)国連食糧農業機関・世界保健機関の合同食品規格委員会の考え方に基づき、(第2)学校給食施設や設備とそれらの衛生管理、また、(第3)調理過程等における衛生管理基準として、献立作成や食材購入、食品の検収・保管等、さらには調理過程、配送及び配食、検査及び保存食等、定期検査と実施記録の保管、(第4)衛生管理体制に係る衛生管理基準として、学校や教育委員会の衛生管理体制、学校給食従事者の衛生管理、、健康管理、食中毒の集団発生の際の措置、定期検査と実施記録の保管、(第5)日常及び臨時の衛生検査、(第6)雑則として、記録の1年間保存、クックチル方式実施の場合の留意事項など、多項目にわたって厳しい内容が定められています。
こうしたことをふまえた議論は、残念ながら委員会ではまったく不十分だったと言わなければなりません。実施にあたって、学校給食法に基づく十分な検討が必要と考えます。市教委として、実施にあたっての基本と位置づけている、学校給食法に照らしての重要な点があれば、明らかにして下さい。
・次に、「寝屋川の給食をよくする会」が中学校給食の実施に関しての見解を表明していますが、実施検討にあたって、子ども・保護者・市民などの意見をよく聞くことが必要です。予定している計画を明らかにして下さい。
・先にあげた衛生管理基準の内容からも、学校給食には何よりも安全・安心が求められます。検討委員会の報告では、民間調理業者に委託するデリバリー方式が望ましいとされています。学校給食法を読む限り、共同調理を委託する場合でも、学校給食専用施設にする必要があると感じました。仮に委託業者が衛生管理基準をクリアーできない場合は、基準を満たすために必要な改修とその費用はどこが負担することになるのか、見解をお聞きします。
・検討委員会では、小学校の給食が全国的にも高く評価される実践を蓄積してきたことが意見としてくり返し出されました。命にかかわるアレルギー対応では、除去食にとどまらないで代替食を行う水準となっています。その土台に自校直営方式の学校給食がありました。教育の一環として実施するためには、自校直営が最善と言えます。1校でも2校でも可能であれば、そうした検討を行うべきと考えます。検討委員会で示されたグラウンドに限らずに、敷地全体の中で、使っていない建物の建て替えも含めて検討する余地があると考えますが、いかがですか。
・次善の策としては、直営の給食センター方式があると考えます。旧明徳幼稚園の活用について、先に述べましたが、提起した構想の検討がまったくない場合、旧明徳幼稚園と旧明徳小学校の一部を合わせて市立給食センターに建て替えることも一案ではないでしょうか。自校方式であれ、給食センター方式であれ、雇用対策としても重要と考えます。見解をお聞きします。
・学校給食として実施する限り、生徒全員に提供する必要があります。生活保護はもちろんですが、就学援助の扶助対象にもすべきと考えます。見解をお聞きします。
・検討委員会やこの間の行政視察を通じて、配膳員などの配置が必要と感じました。教職員全体でとりくむことと合わせて実施に向けて、配膳員の配置をどう考えているのか、明らかにして下さい。
・学校給食では、栄養士や栄養職員の配置が不可欠です。見解をお聞きします。
○次に、廃プラ健康被害についてです。
・通告していました4市専門委員会に関連しての質問については、建設にあたっての参考値とされた1400μg/m3がすでに高濃度の汚染と指摘されていた柳沢意見書をふまえて、健康被害を多数の住民が訴える現状に照らして必要と準備をしましたが、別の機会にすることにします。
・大阪高裁判決後、廃プラ施設周辺の住民を中心に、2つの施設稼動以後の健康被害を訴える51名が、国の公害等調整委員会に「原因裁定」を求める申請を行っています。今後、第2次申請も検討していると聞いています。
これまでも多くの健康被害の訴えを紹介してきましたが、今回の質問にあたって、新たにお聞きした方を含め、何人かの訴えを紹介します。
①太秦地域の廃プラ施設から400mのところに住んでおられる建設関係の方です。日中は仕事に出ていますが、それ以外の時間は家で過ごしています。
平成17年の終わり頃から、プラスチックの焼けるような嫌な臭いがよくするようになりました。夜の9時から10時くらいに臭いがきつく、夏場など、窓を開けていると家の中まで臭います。仕事から帰って、妻と毎日1時間くらい、犬の散歩に行きます。住宅街を通って治水公園というのがコースです。治水公園の付近で臭いがした日は気分が悪くなります。臭いは日によって違いますが、天気が悪い日は特に臭います。平成18年頃が一番きつかったと思います。
滅多に風邪もひかず、いたって健康でしたが、平成18年の春から、むせるようなぜん息の発作のような咳が出るようになりました。横になると咳が止まらなくなるので、寝るときも壁にもたれて、うつらうつらするしかない時期もありました。ヒィーヒィーとぜん息の息づかいになることもしょっちゅうでした。
関西医大では原因がわからないと言われました。半年後、他の病院に通院するようになり、沢山の種類の薬を飲んでいます。咳を抑えて気管を広げる薬や痰切れをよくする薬の効き目か、ぜん息の発作は出なくなりました。咳をすると、人に風邪と間違われて嫌な顔をされるので、人と話しにくくなってしまいました。今も2ヶ月に一度CTやレントゲンを撮る検査を受けています。
今年家を改築するため、半年ほど妻と廃プラ施設から1.2km離れたところに住みました。そこでは臭いもせず、症状も和らぎました。娘と孫は、施設から700mほどのマンションに住みましたが、症状は改善しませんでした。改築が終わり、夏に自宅に戻ったところ、家族全員に症状がぶりかえしました。
②太秦地域の30代女性です。15年近く、廃プラ施設から600mのところに住んでいます。大阪市内の勤務から現在は転勤で京都の方に通勤しています。
廃プラ施設が稼動して以来、母は甘酸っぱい臭いがするとか、眼が痒い、鼻がむずむずするとか、いろんな症状を訴え始めました。私も会社から帰宅の際、自宅近くのバス停に降りた瞬間、猛烈な廃プラ臭にであい、息を止めて猛ダッシュで家に帰り、「死ねということかと思った」と家族に話したほど、ひどい臭いでした。そんな悪臭に濃淡はありますが、帰宅途中のバスの中で、窓が開いていないのに車中の空気が変わるのを感じたり、降車の際に廃プラ臭にでくわしたり。我が家も引っ越した方がいいのでは?と話したこともあります。
廃プラ工場が稼動してからは、風邪引き後の咳が長びきます。伊豆の山の上のホテルに泊まったとき、咳が不思議に出なくなりました。一番驚いたことは、今年の1月から健康のためにと、バス通勤を止め、寝屋川市駅まで歩いていました。3月中旬、足首等に湿疹ができ、体中に広がって皮膚科の薬でも治りませんでした。25日には突然顔が赤く腫れ上がり、ショックでこの先どうなるのか不安で、その晩は眠れませんでした。信頼している医師の指示で大阪市内のホテルに1ヶ月ほど宿泊をし、徐々に回復をして自宅に戻りました。
③太秦地域の20代女性です。今のところに住むようになったのは、幼い頃からよく風邪をひいていた私に自然が豊かで環境が良いと両親が思ってくれたからです。
こちらに来てからは風邪をひくこともなく、毎日治水緑地などで遊んでいました。しかし、平成16年暮れから風邪をひくようになり、治りかけても息苦しさや全身の怠さ、無気力感がひどくなり、かかりつけ医からは、「体が回復していない」とほぼ毎回注射を打ってもらっていました。変な臭いを感じ始めた頃から、風邪をひくと呼吸困難に陥るようになりました。薬を飲んでも一向に治る気配がありませんでした。学校の勉強も霞がかかったように何も頭に入らず、得意だった音楽のやる気も起こらなかったほどでした。今年から大阪市内で子ども相手に仕事をしていますが、仕事場に行くと呼吸がとても楽になります。しかし、寝屋川に帰ってくると息が苦しくなり、家の近くになると咳が止まらず、眼の痒みや鼻水も止まらなくなります。一番しんどいのは、仕事柄子どもたちと遊ぶので毎日とても疲れますが、寝て2時間ほどすると咳が出て起きてしまいます。そこからは眠ることもできず、ほとんど寝ずに出勤する毎日です。処方される薬も強くなっていくので、体にも負荷ががかかり、今では薬がないと呼吸するのさえままならないほどです。
思い起こすと、健康悪化は、廃プラ施設の操業が始まって6ヶ月ほど経ったとき、外に出ると変な臭いを感じ始めた頃でした。最近は、「味覚」を感じなくなり、食欲も低下してきています。また、「手足が攣る」ことが多くあり、忘れ物がひどくなったり、年齢では考えられない症状が出てきています。貧血や目まいもあり、本当に毎日暮らしていくのがしんどいです。
・これまでも症状が重くなった人は、財産の多くを持って行くこともできずに引っ越さざるを得なくなったり、別荘がある人は週末避難をくり返し、顔の湿疹が出なくなってきたという声もありました。
今回、症状を伺うために他にも何人か訪ねましたが、臭いがしたときには、環境政策に連絡をしているという人もいました。最近は夜に焦げた臭いがよくすると言います。廃プラの臭いの苦情件数がどれだけあるのか、どう処理しているのか、明らかにして下さい。
環境疫学の津田敏秀岡山大学教授は、平成18年と平成22年の調査結果から、「何度やっても同じだ」と言われました。さらに詳細に聞き取った症状を、皮膚粘膜刺激症状の主な症状として、共通する症状を、眼症状、皮膚症状、咽頭症状、呼吸器症状の4つにまとめておられます。そのうえで、有意差から、廃プラ工場に近いほど眼症状、皮膚症状、呼吸器症状の倍率が高いことを示しました。また、神経障害に関わると思われる症状が増えているのが気になると、「冷や汗をかく」「身体がカッとなって汗をかく」などの症状は、放出されるVOCの中に、神経毒性のある物質が含まれている点をふまえると、非常に懸念すると述べておられます。
原因物質は特定されていないけれど、大変なことが起きている。健康被害の訴えの多くの事実について、どう認識していますか。見解をお聞きします。
・寝屋川市はこれまで「健康被害が明らかになれば、廃プラ施設の稼動の停止を求める」と答弁してきました。今もこの答弁に変わりはありませんか。
・廃プラによる健康被害はないと、健康調査を否定し続けていますが、健康調査をせずに健康被害がないと断言する科学的な根拠は何ですか。
・2008年6月2日の参議院行政監視委員会で日本共産党の山下芳生議員が寝屋川病と言えるほどの深刻な事態として、、廃プラスチックリサイクル工場周辺の健康被害の訴えをとりあげています。
大事な点は、環境問題への対応としての予防原則、すなわち完全な科学的確実性がなくても深刻な被害をもたらすおそれがある場合には対策を遅らせてはならないという考え方を、環境大臣も、厚生労働大臣も認識したうえで答弁していることです。環境大臣は、「病状等がいろいろと新たに起こってくるようでしたら、しっかりと予防原則に沿って、これは特に自治体が主体でありますけれども、我々も注視しつつ連携をさせていただきたいと、こういうふうに思います。」と述べ、厚労大臣は、「保健所(は)地域住民の健康を守るために必要な調査研究を行うことができる・・・(略)・・・まだ臭いがするとかいろんな状況があれば更に踏み込んだ調査があってしかるべきだろうと思います・・・(略)・・・保健所としては自治体の市と連携を取りながらそういうことをきちんとやって、今環境大臣がおっしゃたように、ひょっとしたら今までの基準値に挙げていない新たな物質が、化学物質が発生しているかもしれないんで、私は国民の生命をしっかり守るという立場で厚生労働行政をやっていますけれども、・・・(略)・・・基本的にはやはり地域にしっかりしてもらいたいですね。その限りにおいて我々は、もちろん連携して協力をする・・・」「現に健康被害を訴える方がおられれば、そういう方の立場に立って、何ができないかじゃなくて、何ができるかという形での行政をやっぱりやるべきだというふうに思います。」
寝屋川市として、国会での政府答弁をどう受けとめているのか、国会は国の最高機関であり、大変重い内容です。健康被害の訴えに対して、住民の命・健康・安全に責任を負う自治体として、このことをふまえた対応があらためて必要と考えます。答弁を求めます。
・ごみ収集のあり方について
これまでも廃プラ健康被害の訴えを通じて、汚れた廃プラごみは可燃ごみとして処理することが確認されてきました。しかし、市民への周知徹底が不十分なため、カラスの格好のえさとして、ごみの散乱につながっている様子を見ることが多くなっています。
また、北河内4市リサイクル施設でつくられた再商品化基準適合物を日本容器包装リサイクル協会を通じて再商品化業者に引き渡すにあたって、4市の昨年度実績を見ても5億円以上の公的資金が支払われています。大半を引き受けているイコール社は約35万枚を超える再生パレットを生産しています。リサイクル率60%を目指していますが、現状は半分に満たない状況です。住民の中で言われている1枚600円として、2億1千万円以上の収入となります。容リ協からの収入と合わせて7億円を超えます。4市の収集運搬費用を含めれば、健康被害の発生源と示唆されている民間業者の利益のために、もう1つの発生源になったとされる4市施設と合わせ、まさに多額の税金と公的資金が使われている経済的な非効率は、見直しが必要な大きな問題です。再生プラは、強度が弱く、劣化も早く、商品的には欠陥と言えます。健康被害解消のためにも、有償で引き取ってもらえるペットボトルやトレイなどを除いて、可燃ごみにすることが課題となっています。廃プラごみの分別収集は、容器包装リサイクル法では努力義務とされているだけであり、義務ではありません。完全に燃やせば、多種多様な化学物質が発生する心配もなく、水と二酸化炭素になるだけとの学者の意見もあります。廃プラのその他プラごみを生ゴミと同時に収集したときに、市の費用の増減はどうなりますか。説明して下さい。
長い目で財政を考えたとき、負担の軽減、解消につながります。時期を失せず見直すべきと考えます。見解をお聞きします。
○第2京阪道路などの環境行政について
・大阪府が府内14箇所の大気観測局にPM2.5測定器を設置するため、業者の入札を行ったと聞いています。寝屋川市役所局にも設置されます。住民の願いを受けた施策として歓迎します。同時に、大阪府が検討していると聞きますが、住民の環境に大変化をもたらした巨大道路、第2京阪道路沿道にこそ、環境行政に位置づけられた大気汚染防止法に基づく常時監視局の設置が必要であり、PM2.5の測定が必要です。設置場所としては、複合汚染が心配されるトンネルの京都側坑口部がふさわしいと考えます。国や大阪府への要望は当然ですが、市としての設置も含め、見解をお聞きします。
・昨年11月の交通量と較べて、今年6月の交通量は一般部の大型車を除いて、小型車、大型車ともに増加しています。とくに、専用部の増加が目立ちます。交通量予測の約8万台に近くなっていますが、専用部の大型車の混入率は予測を大きく下回っています。交通量予測との関係で現状をどう見ているのか、大気汚染、騒音、振動等の環境影響について、現状と将来の見通しをどう分析しているのか、明らかにして下さい。
・第2京阪道路の大気汚染や騒音、振動などの影響は、環境基準をクリアーしているとはいえ、NO2データでは、供用前と較べて、供用後、寝屋南局、小路局とも市役所局を上回るようになっています。浪速国道事務所が住民に説明していた寄与濃度の予測値の5倍以上の大気汚染をもたらしています。また、騒音についても平均値では基準をクリアーしていても、深夜などに走る瞬間的な爆音が安静な生活に影響を与えています。振動についても、個人差もあり、寝ている枕元を通して感じる日もあります。長期にわたる観測と生活への影響調査が必要と考えます。見解をお聞きします。
・この間、環境政策課として3ヶ月ごとにNO2の簡易測定が行われています。そうした努力は率直に評価したいと思います。8月から測定されている第8中学校は、学校の健康調査で、アレルギー性結膜炎が受診者の3割近く、アレルギー性鼻炎が2割を超える年があり、測定結果も11月調査では、測定箇所の中で高い方でした。子どもたちの健康状況が心配される学校園や保育所など、汚染が心配される市内全域での測定を行うよう求めます。見解をお聞きします。
○高宮廃寺等の文化財の活用調査と専門職員の配置について
今年度の教育委員会の主な9事業の1つに高宮廃寺跡の活用調査があります。第2京阪道路建設にあたって大量に発掘された文化財、寝屋川市域にある貴重な文化財などと合わせて活用調査を行うには、寝屋川市の専門職員の絶対数が不足しています。加えて、新たに(仮称)イオンモール四條畷店の建設予定に伴う新家での発掘調査が行われています。近隣の四條畷市や交野市では、新採用によって複数体制を維持しています。また、枚方市は4人の職員と2名の非常勤の6名、さらに関係の財団法人が新規採用を行って3名の職員と2名の非常勤の5名と聞きます。市として、埋蔵文化財を含む貴重な文化財の研究調査と市民への公開などの活用検討をすすめる事業推進のために、新規採用を含む専門職員の増員が不可欠と考えます。見解をお聞きします。
○学童保育(留守家庭児童会)事業について
・今回の保育料徴収条例の委員会審査の中で、施設設備等の条件整備とともに、4年生以上の障がい児入所が保護者、関係団体からの強い要望であることが示されました。今回の条例提案を受けて、寝屋川市の状況とともに、大阪府内の状況を調べました。寝屋川に限らず、共通して重大な課題になっていることを痛感しました。寝屋川では、現在、希望者は、全員入所できていると聞いています。しかし、中には、希望する児童会に入会できていないため、保護者の状況によっては、ファミリーサポート制度を利用したり、障害福祉を活用したり、送迎にかなりの困難を抱えている事情も耳にします。大阪府内の自治体によっては、障がい児については小学校6年生までと明記しているところもあります。障害とは、生きるうえでの社会的ハンディキャップを持つことです。だからこそ、社会的な支援が必要と考えます。公平・平等とは、一律に同じようにすることではありません。実態としての平等を実現するためには、特別の支援が必要です。来年度の入所の具体的解決を要望するとともに、基本的施策とするよう、検討を要望します。
・次に、指導員についてです。正職員の配置はなくなりましたが、障がい児に対する研修とともに、集団生活の中での子どもたちの発達・成長をめざして、充実した研修が毎年行われていると聞いています。また、指導員を通じて、その成果を実感することがよくあります。しかし、せっかく専門性を豊かに身につけても、指導員にとっての現実は正職員採用の道はありません。教育委員会にとっても、系統性・継続性を必要とする事業のために、せっかく専門力量を身につけた指導員を育成しても、今の労働条件のままでは、優秀な指導員を失うおそれが常にあります。一定以上の能力、実績を持った指導員については、正採用の道を検討すべきではありませんか。見解をお聞きします。
・次に、全員入所の要望に応える条件整備です。カギは、国の補助金が最も高く設定されている36人~45人の複数学級制を基本にすることです。また、放課後の児童健全育成事業が概ね10歳と謳っていることから、現行の3年生を4年生とすることで、学校の規模にも地域の実状にもよりますが、2学級、3学級と設定することで、可能性がうまれると考えます。ぜひ検討を求めます。
・次に施設・設備の充実についてです。現在、寝屋川市は、学校体育館のトイレの改修を計画的に進めています。しかし、体育館トイレについては、学校間格差があり、男子の小用がほとんど使えないところもあると聞きます。応急措置が必要です。調査のうえ、早急な対応を求めます。
・最後に、土曜日の開設と保育時間の延長です。9月議会での他議員の質問を受けて、アンケート調査が行われていると聞きます。調査状況と検討結果を明らかにして下さい。子どもにとって、長時間が決して良いとは思いませんが、残念ながら労働環境はまったく好転していません。他市では、土曜日の利用者、時間延長の利用者に追加負担を求めているところもあります。保護者や関係団体との協議、合意が必要と考えますが、検討を求めます。見解をお聞きします。
○その他
8日の建設水道常任委員会で、市民プール廃止に関する審査が行われました。その中で、当初の提案理由と異なる説明がありました。プールの利用にあたって、安心・安全な提供を確保できないというものでした。年間200人のけがの被害があるといいますが、夏に日本共産党議員団が視察した際には、看護師から「ほとんど利用がない」という話がありました。被害記録があると思います。提出を求めます。また、耐震性に問題があり、危険が大きいとの議論もありました。耐震性を確保する改修費が7,500万円と理解していましたが、建て替えに5~6億円の答弁もありました。体験上最大の地震だった1995年の阪神大震災の時の被害状況、5~6億円の根拠になる調査、検討内容を明らかにして下さい。早急な資料提出を求めます。
2011年12月議会 一般質問 太田議員
2011-12-14
まず最初に、国民健康保険についてです。
働いて保険料を納めていても、窓口負担が高すぎて医療機関にかかれない。こんな深刻な実態を全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)が12月3日、記者会見で明らかにしています。中味を紹介しますと、
加盟病院のソーシャルワーカーが昨年4月から1年間に受けた医療・介護費の相談事例など3029件(45都道府県)について調査、分析した相談事例調査です。
調査結果では、「医療費が支払えない・不安がある層」で「保険料の滞納がない層」が約3分の1を占めています。これまでの調査では、「高すぎる国民健康保険料が払えず、窓口負担も払えない」ことが問題となっていました。しかし、今回は「被用者保険など保険料を納めても、窓口負担が払えない」問題が見えてきています。
被用者保険に加入する労働者も低賃金で医療費が払えない相談が増えています。失業による困窮も広がっています。失業の内訳トップは解雇。解雇の理由で一番多いのは病気。失業で収入が断たれ、受診できずさらに病気が悪化。そんな悪循環が調査の集計から浮き彫りになりっています。
全日本民医連の藤末衛会長は、政府による負担増の動きを批判し、「窓口負担ゼロを目指して引き下げを求める運動を他の医療団体と共同して進めたい」と述べています。
「医療費・介護費相談調査」からは、あらゆる年代で医療費の支払いが困難な生活困窮の実態も浮かび上がっています。
働いても低所得のため医療費の支払いが困難で、医療から縁遠くなっている実態が明らかになりました。
相談者の世帯に「就業者がいる」のは39%で、「いない」が31%、「不明」が30%です。就業者の雇用形態を見ると、「非正規」が7割を占めます。相談者の収入は、15万円未満が全体の4分の3以上を占めます。無収入が869件、約3割です。
運送会社のトラック運転手の男性(35)の場合、収入の大半が生活費に消え、入院費の支払いが困難だと相談がありました。
相談後、死亡した事例は、141例にも。「医療費の負担増に耐えられず、命に直結する医療へつながれない状態だ」と指摘しています。
会社の寮に住み、仕事をしていた66歳の男性は、国民健康保険料を滞納。胃の不調を感じ、市販薬を服用していました。6カ月間のみ有効の「短期証」を手に入れ、受診し、胃がんが判明。入院し手術を受けましたが、状態が悪化し12日後、死亡しました。
相談者3029件のうち無料低額診療事業を利用したのは、1227件(40・5%)でした。
無料低額診療事業は社会福祉法第2条などに基づき、医療費の支払いが困難な人を対象に医療費減免を行う制度です。全日本民医連に加盟する事業所のうち254事業所が行っています(8月10日現在)。
失業中の透析患者(男性・41)の母親は、糖尿病と心臓病で、医療費の負担が重く、4年前から受診を中断。自己判断で、息子の薬を服用していました。男性が相談し、母親は同事業を利用し、受診継続となりました。
「被保険者本人が3割の医療費窓口負担をしなければならない実態はもはや“公的保険”とはいえない」「医療費の窓口負担ゼロを目指して引き下げを求める」と記者会見で強調しています。
今回の調査結果を受けて残念ながら納得をしたことがあります。それは、寝屋川市の国保加入者の医療給付がなぜ大阪府下の自治体の中で低いところに位置しているのかということです。いままで、医療給付が府下でも低いのに保険料が高いのはおかしいと質問もしていましたが、今回の調査で寝屋川市の国保加入者が高い国保料負担で、窓口負担が重くて病院へいけていない。その結果として、一人あたりの医療給付が大阪府下の中でも低くなっていることの説明が付きます。現実に寝屋川市民からも窓口負担が重いために、病院の通院の回数を減らした。一週間分の薬を2週間に分けて飲んでいる等の相談を聞く事があります。せっかく高い保険料を納付して正規の保険証を手にしていても十分な医療を受ける事が困難な状況が寝屋川市内にすでにありそして広がっているのではないでしょうか。
高い保険料の引き下げ、窓口負担の軽減で医療を受けることを保証する。社会保障としての国保の役割が今こそ求められています。
そこでお聞きしますが、窓口負担が原因で診療を控えている市民の実態を寝屋川市としてどれくらいつかんでいますか。寝屋川市の国保加入者の一人あたりの医療給付が大阪府下でも低い方に当たる理由を市としてどのように考えていますか。実態把握に努めて、市民の医療を守る施策の充実を求めます。現実的には大規模なアンケート活動など早急に現状をつかむ事が非常に難しいと思いますが、各医療機関の一部負担金の未払い件数など市としてすぐに把握出来ることからはじめ、援助をすることも必要ではないでしょうか。すこし話はずれますが、窓口負担の未払いについては医療機関が努力をしても回収ができない場合は、保険者に任せる事が出来るとなっています。以前も一度聞きましたがその後、市にそのような要請はありましたか。今後窓口負担が引き上がると滞納が増え市への要請も出てくることも考えられます。回収に費用をかけるより最初から窓口負担の軽減をすることで市の負担を減らす事の方が賢いのではないでしょうか。
現実的には高額療養費制度、一部負担金減免制度の周知や、ジェネリック医薬品の普及などで窓口負担の減額を図ることが求められます。市として制度の周知と制度の拡充を求め答弁を求めます。
また、無料低額診療を行う医療機関を寝屋川市内でも開設していただく事が必要と考えますが、市としてどのような対策をとっているのかお答えください。無料低額診療所は現在北河内には、門真にしかありません。寝屋川市民で門真の無料低額診療所の利用実績があるのかお答えください。現在、寝屋川市内の医療機関が無料低額診療に向けて準備をしているとも聞いています。すべて、医療機関の持ち出しとするのではなく、市としても市民の健康を守る立場での援助が必要と考えます。市の答弁を求めます。
現在、3割の窓口負担が重たい負担となっている中で、政府・与党は「税と社会保障の一体改革」で医療費の受診時定額負担を検討しています。これは、高額療養費の負担軽減の財源を捻出すると称して、受診のたびに100円を現行の医療費負担に上乗せするものです。日本共産党の田村智子議員は12月1日の参院厚生労働委員会で、「患者同士で負担を分かち合えというものだ。(国民全体で支えあう)医療保険制度の原則に反する」と批判しました。政府の審議会に出された資料でも受診抑制を招くことを認めていると追及しました。辻泰弘副大臣も、「受診時定額負担によって、受診行動が変化することを見込んでいる」と認めました。 田村氏は、低所得者の歯の健康は全国平均より悪いとした全日本民主医療機関連合会の調査を示し、「受診時定額負担は低所得者ほど負担がのしかかる。健康格差を深刻化させる」と強調しました。
小宮山洋子厚労相は「病気の人が病気の人を助けるのはおかしいとの指摘もうかがっている。各方面の意見をうかがいながら検討したい」と答えました。
田村氏は、健康が悪化すれば医療費を増大させることになり、早期治療や医療費負担の軽減こそが求められると述べています。
現在、受診時定額負担は、計画が出た時点で多くの国民の反対の声で今回は見送りとなったようですが、寝屋川市として、市民の健康を守る立場から受診時定額負担に反対をして下さい。答弁を求めます。
70歳から74歳までの窓口負担です。すでに2割負担にすると決まりながら、なんとか、特例措置で1割負担が続いています。1割から2割に負担が変わると二倍の窓口負担となります。なんとか今国会で来年度についても1割負担とする事が決まりましたが、寝屋川市としても高齢者の負担軽減を図るため市として国に求めるよう求め答弁を求めます。
大阪府の府特別調整交付金についてです。11月16日に大阪府は府特別調整交付金の評価基準の考え方(案)を公表しました。大阪府が広域化方針を作ったことで、今年度から国の保険料の徴収率によるペナルティはなくなりました。しかし、今後、新たに府が評価基準を決め特別調整交付金の配分を決める事になります。今回評価基準の考え方が明らかになりましたが、現時点で寝屋川市にとって、どれだけの額が影響してくるのか、また、現時点で項目ごとの点数と合計点をお答えください。最終的には大阪府下すべての市町村と比べて交付金の額が決められると思いますが、予定収納率の設定等、保険料設定に大きく影響を及ぼす項目もあります。市として、調整交付金は国保加入者の人数と所得階層によって、より低い所得階層の自治体に多くの交付金を配当するように要望することが必要と考えます。市として府の特別調整交付金の評価基準を寝屋川の国保加入者にとってよりよい形へと変えるべく府へ求めて下さい。
介護保険について
まず最初に、第5期計画についてです。厚生労働省は8月末に第5期介護保険料試算ワークシートを都道府県を通じて全市町村におろしています。しかし、不備が多く、結局10月12日に厚労省は専用ホームページを開設し、市町村から直接データを厚生労働省に集め都道府県ごとに集計した上で都道府県に10月末に情報提供をするという異例の措置となりました。
今回、大阪府に対して厚生労働省が情報提供した資料のすべてを大阪社保協が大阪府に対して情報公開請求し公開されています。そこでは、寝屋川市もワークシートに給付費や予定収納率等の数字を入れて報告をしています。そして来年度保険料が4337円と試算されています。これは、現行の4240円より97円高くなっています。この間の市長答弁では来期の介護保険料については引き下げを行うと明言をされています。今回、厚生労働省に提出した第五期計画の予想からどのように保険料を引き下げるのかを明らかにして下さい。答弁を求めます。
今回の試算では介護給付費準備基金を100%繰り入れして試算がされています。この事については、介護給付費準備基金は取り過ぎた高齢者からの介護保険料です。全額取り崩しを一貫して求めてきたことから評価をしたいと思います。今後も介護保険の運営しているなかで介護給付費準備基金を積み立てた場合は次期計画で取り崩すことをルール化することを求めます。答弁を求めます。
そして、大阪府財政安定化基金約194億5000万のうち、約82億8000万を「必要額」として温存し、約111億7000万円を取崩し、その3分の1にあたる、約37億2500万円を府内の41市町村に介護保険料軽減財源として交付する事も明らかとなりました。しかし 大阪社保協の試算では、約37億2500万円の保険料軽減効果は 第1号被保険者数195万1124人(2011年7月)で割ると一人当たり1,908円となり、第5期介護保険料3年間の軽減にあてはめると第1号被保険者数を同じとして、1908円÷36月=53円程度となります。(実際は3年間で第1号被保険者数は増加するので、一人当たり軽減額はもっと少なくなります)もし、194億円全額を取崩し、その全てを保険料軽減に回せば、第1号被保険者一人当たり9,968円月277円程度の軽減になり、大阪府の「試算値」ではその5分の1の軽減効果にしかなりません。寝屋川市として大阪府財政安定化基金の全額取り崩しと、国、府負担分も合わせた全額の介護保険会計への繰り入れを国・府に求めて下さい。答弁を求めます。
介護保険料利用料の減免についてです。
寝屋川市はこの間お隣枚方市と比較して、保険料の段階が多い、第一段階、第二段階共に0.5倍としている事で低所得者に優しい保険料となっていると説明をしてきました。しかし、実態として寝屋川市の普通徴収の保険料の徴収率は大阪府下でも最悪に悪い状態となっています。今回第五期計画のワークシートに書かれている保険料の予定収納率もおおむね他市が98%台であるのに対して97.4%と低く見積もられています。特別徴収は基本100%ですので、やはり普通徴収の収納率の悪さが影響をしています。普通徴収の収納率の悪さは寝屋川市の高齢者の生活の厳しさの反映ではないでしょうか。そこには無年金、無収入の人からの保険料の徴収は無理がある事を示しています。
そこで今ある介護保険制度をしっかりと活かして滞納を減らす努力が必要ではないでしょうか。寝屋川市においては境界層措置の適用、所謂、境界層減免の利用があまりにも少ないのではないでしょうか。寝屋川市のHPを見ましても申請書のダウンロードは出来てもどのような方が利用できる制度であるのかは全然分かりません。また、申請書には関係書類を添えて申請をしますとなっていますが、どのような関係書類が要るのかも全然明記がありません。寝屋川市内には生活保護基準以下で暮らしている高齢者もたくさんいるのではないでしょうか。制度の説明周知をして、介護保険料の滞納とならないよう市として援助をする必要があるのではないでしょうか。市としての制度の周知と減免申請への援助を求めて答弁を求めます。
利用料についても、せっかく介護認定を受けてケアプランを立てたのに利用料負担のために介護保険を利用出来ないでいる実態もよく聞きます。そこで、(社会福祉法人等による利用者負担軽減について)についてです。介護保険の円滑な実施のための特別対策として、介護サービスを提供する社会福祉法人が、特に生計が困難な利用者について、利用者の住所地の市町村に申出て、その助成を受け、負担を軽減する事業で、市町村事業として位置付けられています。寝屋川市としてこの制度の周知を更に進めて頂きたいと思いますが、現在の市の周知方法と制度の利用状況、市内事業所の何箇所が利用をしているのかお答えください。
そして現在ある制度で救済が出来ない高齢者に対して市独自の保険料、利用料の減免制度を設ける事が必要です。第五期計画に合わせて制度の創設を求め答弁を求めます。
水道事業について
寝屋川水道ビジョン第二期実施計画の水道料金の検討では、水道料金に平成22年度に大阪府営水道の用水供給単価が値下げされたことに伴い、大阪府内で水道料金の値下げが実施された市町村があります。本市においても、今後、水道施設等の更新・維持管理、香里浄水場休廃止に伴う施設の撤去等に多額の費用が必要となる中、料金体系の見直し、改定方法等、水道料金のあり方について検討を進める必要があります。とあり、今年10月から水道料金が10%の引き下げが行われました。
また、大阪広域水道企業団の将来構想では、第3節 持続的な事業運営 1経営の効率化 目標 安定給水と健全経営を維持しつつ、料金値下げを追及する。とされています。
また、 大阪府知事選挙、大阪市長選挙が終わりどちらも維新の会の知事、市長となりました。維新の会の市長選公約には、大阪市水道局を大阪広域水道事業団に統合し、大阪全域で上水事業を一本化。事業を効率化することにより水道料金の値下げを目指します。
知事選公約では大阪市水道局を大阪広域水道企業団に統合させ、府域全域のワン水道を実現することで、施設、人員を統合整理し、合理化を図ります。これにより、経費の削減を行い、水道料金の値下げを行います。とあります。
今後の寝屋川市の水道料金の見通しをお示しください。また、大阪水道事業企業団が大阪市営水道と統合をする事は知事の判断で出来るのか、企業団としての意思が優先をされると思いますが、事実関係を示して下さい。
東日本大震災以降、防災に対する市民の関心が高まってきています。大阪水道企業団 将来構想では、平成31年度には震災時にも一日あたり60万・(最低限の日常生活を維持)平成41年度には一日あたり100万・(最低限の社会経済活動を維持)を供給できる施設の更新が目標とされています。寝屋川市の水道ビジョンにも災害時の給水目標が必要と考えますが、寝屋川市の目標と現在の状況をお応えください。
寝屋川市水道ビジョンでは香里浄水場を2014年度末で廃止する計画となっています。その後、現状でいきますと、大阪市営水道、大阪広域水道企業団からの水の供給を受けることとなります。市内の飲料水兼用耐震性貯水等の整備は大切ですが、大元の用水の配水施設の耐震化も非常に重要となってきます。平成22年度の大阪広域水道企業団のポンプ所耐震施設率は98.1%ですが、浄水施設耐震率は32.3%、管路の耐震化率は29.1%浄水(配水)池耐震施設率は10.4%と非常に低いまま推移しています。寝屋川市も広域水道企業団の一員として、100%の耐震化へ向け積極的に発言をしていくよう求めます。現在、寝屋川市が広域水道企業団対して行なった要請等があればあわせてお応えください。
中小企業振興について
最初に産業振興条例についてです。市長は6月の市政方針で産業振興条例については「商業、工業、農業の活性化を図るため、産業振興に関する基本的な考え方を明らかにした(仮称)産業振興条例を制定します。」としています。そして、2011年度 市民生活部運営方針では◎商業、工業、農業の活性化を図るため、産業振興に関する基本的な考え方を明らかにした(仮称)産業振興条例の制定に向け、検討を進めます。となっています。
お隣大東市では2011年6月23日、大東市地域産業振興基本条例が全会一致で制定されました。そして条例制定に至るまで、「産業振興市民会議」を学識経験者・商工業者・商工団体の代表者・公募市民・行政機関の代表者により市民会議を設置し、会議を重ね、条例案が検討されています。また「産業振興シンポジウム」を行う等、商工業者や市民が主体になって条例制定にこぎつけています。
現時点で、産業振興条例の制定に向けての具体的な進展状況と今後のプログラムを明らかにして下さい。条例の制定には多くの市民、業者、商売人、農業従事者等の関係各位の知恵と力を結集して、進めていくことが必要です。条例にむけて、市民の意見の集約や、参加をどのような形で行っていくのか明らかにして下さい。
次に、住宅リフォーム助成制度です。私は地域の中小零細業者の仕事確保、市域内の産業活性化、営業を守るためにも住宅リフォーム助成制度が今こそ必要であると考えています。すでに一部自治体で始まったこの制度は、既に多くの成果をあげ全国の自治体へ広がってきている試され、結果が出ている制度です。市として調査研究をすること、そして制度の創設を求め答弁を求めます。
働いて保険料を納めていても、窓口負担が高すぎて医療機関にかかれない。こんな深刻な実態を全日本民主医療機関連合会(全日本民医連)が12月3日、記者会見で明らかにしています。中味を紹介しますと、
加盟病院のソーシャルワーカーが昨年4月から1年間に受けた医療・介護費の相談事例など3029件(45都道府県)について調査、分析した相談事例調査です。
調査結果では、「医療費が支払えない・不安がある層」で「保険料の滞納がない層」が約3分の1を占めています。これまでの調査では、「高すぎる国民健康保険料が払えず、窓口負担も払えない」ことが問題となっていました。しかし、今回は「被用者保険など保険料を納めても、窓口負担が払えない」問題が見えてきています。
被用者保険に加入する労働者も低賃金で医療費が払えない相談が増えています。失業による困窮も広がっています。失業の内訳トップは解雇。解雇の理由で一番多いのは病気。失業で収入が断たれ、受診できずさらに病気が悪化。そんな悪循環が調査の集計から浮き彫りになりっています。
全日本民医連の藤末衛会長は、政府による負担増の動きを批判し、「窓口負担ゼロを目指して引き下げを求める運動を他の医療団体と共同して進めたい」と述べています。
「医療費・介護費相談調査」からは、あらゆる年代で医療費の支払いが困難な生活困窮の実態も浮かび上がっています。
働いても低所得のため医療費の支払いが困難で、医療から縁遠くなっている実態が明らかになりました。
相談者の世帯に「就業者がいる」のは39%で、「いない」が31%、「不明」が30%です。就業者の雇用形態を見ると、「非正規」が7割を占めます。相談者の収入は、15万円未満が全体の4分の3以上を占めます。無収入が869件、約3割です。
運送会社のトラック運転手の男性(35)の場合、収入の大半が生活費に消え、入院費の支払いが困難だと相談がありました。
相談後、死亡した事例は、141例にも。「医療費の負担増に耐えられず、命に直結する医療へつながれない状態だ」と指摘しています。
会社の寮に住み、仕事をしていた66歳の男性は、国民健康保険料を滞納。胃の不調を感じ、市販薬を服用していました。6カ月間のみ有効の「短期証」を手に入れ、受診し、胃がんが判明。入院し手術を受けましたが、状態が悪化し12日後、死亡しました。
相談者3029件のうち無料低額診療事業を利用したのは、1227件(40・5%)でした。
無料低額診療事業は社会福祉法第2条などに基づき、医療費の支払いが困難な人を対象に医療費減免を行う制度です。全日本民医連に加盟する事業所のうち254事業所が行っています(8月10日現在)。
失業中の透析患者(男性・41)の母親は、糖尿病と心臓病で、医療費の負担が重く、4年前から受診を中断。自己判断で、息子の薬を服用していました。男性が相談し、母親は同事業を利用し、受診継続となりました。
「被保険者本人が3割の医療費窓口負担をしなければならない実態はもはや“公的保険”とはいえない」「医療費の窓口負担ゼロを目指して引き下げを求める」と記者会見で強調しています。
今回の調査結果を受けて残念ながら納得をしたことがあります。それは、寝屋川市の国保加入者の医療給付がなぜ大阪府下の自治体の中で低いところに位置しているのかということです。いままで、医療給付が府下でも低いのに保険料が高いのはおかしいと質問もしていましたが、今回の調査で寝屋川市の国保加入者が高い国保料負担で、窓口負担が重くて病院へいけていない。その結果として、一人あたりの医療給付が大阪府下の中でも低くなっていることの説明が付きます。現実に寝屋川市民からも窓口負担が重いために、病院の通院の回数を減らした。一週間分の薬を2週間に分けて飲んでいる等の相談を聞く事があります。せっかく高い保険料を納付して正規の保険証を手にしていても十分な医療を受ける事が困難な状況が寝屋川市内にすでにありそして広がっているのではないでしょうか。
高い保険料の引き下げ、窓口負担の軽減で医療を受けることを保証する。社会保障としての国保の役割が今こそ求められています。
そこでお聞きしますが、窓口負担が原因で診療を控えている市民の実態を寝屋川市としてどれくらいつかんでいますか。寝屋川市の国保加入者の一人あたりの医療給付が大阪府下でも低い方に当たる理由を市としてどのように考えていますか。実態把握に努めて、市民の医療を守る施策の充実を求めます。現実的には大規模なアンケート活動など早急に現状をつかむ事が非常に難しいと思いますが、各医療機関の一部負担金の未払い件数など市としてすぐに把握出来ることからはじめ、援助をすることも必要ではないでしょうか。すこし話はずれますが、窓口負担の未払いについては医療機関が努力をしても回収ができない場合は、保険者に任せる事が出来るとなっています。以前も一度聞きましたがその後、市にそのような要請はありましたか。今後窓口負担が引き上がると滞納が増え市への要請も出てくることも考えられます。回収に費用をかけるより最初から窓口負担の軽減をすることで市の負担を減らす事の方が賢いのではないでしょうか。
現実的には高額療養費制度、一部負担金減免制度の周知や、ジェネリック医薬品の普及などで窓口負担の減額を図ることが求められます。市として制度の周知と制度の拡充を求め答弁を求めます。
また、無料低額診療を行う医療機関を寝屋川市内でも開設していただく事が必要と考えますが、市としてどのような対策をとっているのかお答えください。無料低額診療所は現在北河内には、門真にしかありません。寝屋川市民で門真の無料低額診療所の利用実績があるのかお答えください。現在、寝屋川市内の医療機関が無料低額診療に向けて準備をしているとも聞いています。すべて、医療機関の持ち出しとするのではなく、市としても市民の健康を守る立場での援助が必要と考えます。市の答弁を求めます。
現在、3割の窓口負担が重たい負担となっている中で、政府・与党は「税と社会保障の一体改革」で医療費の受診時定額負担を検討しています。これは、高額療養費の負担軽減の財源を捻出すると称して、受診のたびに100円を現行の医療費負担に上乗せするものです。日本共産党の田村智子議員は12月1日の参院厚生労働委員会で、「患者同士で負担を分かち合えというものだ。(国民全体で支えあう)医療保険制度の原則に反する」と批判しました。政府の審議会に出された資料でも受診抑制を招くことを認めていると追及しました。辻泰弘副大臣も、「受診時定額負担によって、受診行動が変化することを見込んでいる」と認めました。 田村氏は、低所得者の歯の健康は全国平均より悪いとした全日本民主医療機関連合会の調査を示し、「受診時定額負担は低所得者ほど負担がのしかかる。健康格差を深刻化させる」と強調しました。
小宮山洋子厚労相は「病気の人が病気の人を助けるのはおかしいとの指摘もうかがっている。各方面の意見をうかがいながら検討したい」と答えました。
田村氏は、健康が悪化すれば医療費を増大させることになり、早期治療や医療費負担の軽減こそが求められると述べています。
現在、受診時定額負担は、計画が出た時点で多くの国民の反対の声で今回は見送りとなったようですが、寝屋川市として、市民の健康を守る立場から受診時定額負担に反対をして下さい。答弁を求めます。
70歳から74歳までの窓口負担です。すでに2割負担にすると決まりながら、なんとか、特例措置で1割負担が続いています。1割から2割に負担が変わると二倍の窓口負担となります。なんとか今国会で来年度についても1割負担とする事が決まりましたが、寝屋川市としても高齢者の負担軽減を図るため市として国に求めるよう求め答弁を求めます。
大阪府の府特別調整交付金についてです。11月16日に大阪府は府特別調整交付金の評価基準の考え方(案)を公表しました。大阪府が広域化方針を作ったことで、今年度から国の保険料の徴収率によるペナルティはなくなりました。しかし、今後、新たに府が評価基準を決め特別調整交付金の配分を決める事になります。今回評価基準の考え方が明らかになりましたが、現時点で寝屋川市にとって、どれだけの額が影響してくるのか、また、現時点で項目ごとの点数と合計点をお答えください。最終的には大阪府下すべての市町村と比べて交付金の額が決められると思いますが、予定収納率の設定等、保険料設定に大きく影響を及ぼす項目もあります。市として、調整交付金は国保加入者の人数と所得階層によって、より低い所得階層の自治体に多くの交付金を配当するように要望することが必要と考えます。市として府の特別調整交付金の評価基準を寝屋川の国保加入者にとってよりよい形へと変えるべく府へ求めて下さい。
介護保険について
まず最初に、第5期計画についてです。厚生労働省は8月末に第5期介護保険料試算ワークシートを都道府県を通じて全市町村におろしています。しかし、不備が多く、結局10月12日に厚労省は専用ホームページを開設し、市町村から直接データを厚生労働省に集め都道府県ごとに集計した上で都道府県に10月末に情報提供をするという異例の措置となりました。
今回、大阪府に対して厚生労働省が情報提供した資料のすべてを大阪社保協が大阪府に対して情報公開請求し公開されています。そこでは、寝屋川市もワークシートに給付費や予定収納率等の数字を入れて報告をしています。そして来年度保険料が4337円と試算されています。これは、現行の4240円より97円高くなっています。この間の市長答弁では来期の介護保険料については引き下げを行うと明言をされています。今回、厚生労働省に提出した第五期計画の予想からどのように保険料を引き下げるのかを明らかにして下さい。答弁を求めます。
今回の試算では介護給付費準備基金を100%繰り入れして試算がされています。この事については、介護給付費準備基金は取り過ぎた高齢者からの介護保険料です。全額取り崩しを一貫して求めてきたことから評価をしたいと思います。今後も介護保険の運営しているなかで介護給付費準備基金を積み立てた場合は次期計画で取り崩すことをルール化することを求めます。答弁を求めます。
そして、大阪府財政安定化基金約194億5000万のうち、約82億8000万を「必要額」として温存し、約111億7000万円を取崩し、その3分の1にあたる、約37億2500万円を府内の41市町村に介護保険料軽減財源として交付する事も明らかとなりました。しかし 大阪社保協の試算では、約37億2500万円の保険料軽減効果は 第1号被保険者数195万1124人(2011年7月)で割ると一人当たり1,908円となり、第5期介護保険料3年間の軽減にあてはめると第1号被保険者数を同じとして、1908円÷36月=53円程度となります。(実際は3年間で第1号被保険者数は増加するので、一人当たり軽減額はもっと少なくなります)もし、194億円全額を取崩し、その全てを保険料軽減に回せば、第1号被保険者一人当たり9,968円月277円程度の軽減になり、大阪府の「試算値」ではその5分の1の軽減効果にしかなりません。寝屋川市として大阪府財政安定化基金の全額取り崩しと、国、府負担分も合わせた全額の介護保険会計への繰り入れを国・府に求めて下さい。答弁を求めます。
介護保険料利用料の減免についてです。
寝屋川市はこの間お隣枚方市と比較して、保険料の段階が多い、第一段階、第二段階共に0.5倍としている事で低所得者に優しい保険料となっていると説明をしてきました。しかし、実態として寝屋川市の普通徴収の保険料の徴収率は大阪府下でも最悪に悪い状態となっています。今回第五期計画のワークシートに書かれている保険料の予定収納率もおおむね他市が98%台であるのに対して97.4%と低く見積もられています。特別徴収は基本100%ですので、やはり普通徴収の収納率の悪さが影響をしています。普通徴収の収納率の悪さは寝屋川市の高齢者の生活の厳しさの反映ではないでしょうか。そこには無年金、無収入の人からの保険料の徴収は無理がある事を示しています。
そこで今ある介護保険制度をしっかりと活かして滞納を減らす努力が必要ではないでしょうか。寝屋川市においては境界層措置の適用、所謂、境界層減免の利用があまりにも少ないのではないでしょうか。寝屋川市のHPを見ましても申請書のダウンロードは出来てもどのような方が利用できる制度であるのかは全然分かりません。また、申請書には関係書類を添えて申請をしますとなっていますが、どのような関係書類が要るのかも全然明記がありません。寝屋川市内には生活保護基準以下で暮らしている高齢者もたくさんいるのではないでしょうか。制度の説明周知をして、介護保険料の滞納とならないよう市として援助をする必要があるのではないでしょうか。市としての制度の周知と減免申請への援助を求めて答弁を求めます。
利用料についても、せっかく介護認定を受けてケアプランを立てたのに利用料負担のために介護保険を利用出来ないでいる実態もよく聞きます。そこで、(社会福祉法人等による利用者負担軽減について)についてです。介護保険の円滑な実施のための特別対策として、介護サービスを提供する社会福祉法人が、特に生計が困難な利用者について、利用者の住所地の市町村に申出て、その助成を受け、負担を軽減する事業で、市町村事業として位置付けられています。寝屋川市としてこの制度の周知を更に進めて頂きたいと思いますが、現在の市の周知方法と制度の利用状況、市内事業所の何箇所が利用をしているのかお答えください。
そして現在ある制度で救済が出来ない高齢者に対して市独自の保険料、利用料の減免制度を設ける事が必要です。第五期計画に合わせて制度の創設を求め答弁を求めます。
水道事業について
寝屋川水道ビジョン第二期実施計画の水道料金の検討では、水道料金に平成22年度に大阪府営水道の用水供給単価が値下げされたことに伴い、大阪府内で水道料金の値下げが実施された市町村があります。本市においても、今後、水道施設等の更新・維持管理、香里浄水場休廃止に伴う施設の撤去等に多額の費用が必要となる中、料金体系の見直し、改定方法等、水道料金のあり方について検討を進める必要があります。とあり、今年10月から水道料金が10%の引き下げが行われました。
また、大阪広域水道企業団の将来構想では、第3節 持続的な事業運営 1経営の効率化 目標 安定給水と健全経営を維持しつつ、料金値下げを追及する。とされています。
また、 大阪府知事選挙、大阪市長選挙が終わりどちらも維新の会の知事、市長となりました。維新の会の市長選公約には、大阪市水道局を大阪広域水道事業団に統合し、大阪全域で上水事業を一本化。事業を効率化することにより水道料金の値下げを目指します。
知事選公約では大阪市水道局を大阪広域水道企業団に統合させ、府域全域のワン水道を実現することで、施設、人員を統合整理し、合理化を図ります。これにより、経費の削減を行い、水道料金の値下げを行います。とあります。
今後の寝屋川市の水道料金の見通しをお示しください。また、大阪水道事業企業団が大阪市営水道と統合をする事は知事の判断で出来るのか、企業団としての意思が優先をされると思いますが、事実関係を示して下さい。
東日本大震災以降、防災に対する市民の関心が高まってきています。大阪水道企業団 将来構想では、平成31年度には震災時にも一日あたり60万・(最低限の日常生活を維持)平成41年度には一日あたり100万・(最低限の社会経済活動を維持)を供給できる施設の更新が目標とされています。寝屋川市の水道ビジョンにも災害時の給水目標が必要と考えますが、寝屋川市の目標と現在の状況をお応えください。
寝屋川市水道ビジョンでは香里浄水場を2014年度末で廃止する計画となっています。その後、現状でいきますと、大阪市営水道、大阪広域水道企業団からの水の供給を受けることとなります。市内の飲料水兼用耐震性貯水等の整備は大切ですが、大元の用水の配水施設の耐震化も非常に重要となってきます。平成22年度の大阪広域水道企業団のポンプ所耐震施設率は98.1%ですが、浄水施設耐震率は32.3%、管路の耐震化率は29.1%浄水(配水)池耐震施設率は10.4%と非常に低いまま推移しています。寝屋川市も広域水道企業団の一員として、100%の耐震化へ向け積極的に発言をしていくよう求めます。現在、寝屋川市が広域水道企業団対して行なった要請等があればあわせてお応えください。
中小企業振興について
最初に産業振興条例についてです。市長は6月の市政方針で産業振興条例については「商業、工業、農業の活性化を図るため、産業振興に関する基本的な考え方を明らかにした(仮称)産業振興条例を制定します。」としています。そして、2011年度 市民生活部運営方針では◎商業、工業、農業の活性化を図るため、産業振興に関する基本的な考え方を明らかにした(仮称)産業振興条例の制定に向け、検討を進めます。となっています。
お隣大東市では2011年6月23日、大東市地域産業振興基本条例が全会一致で制定されました。そして条例制定に至るまで、「産業振興市民会議」を学識経験者・商工業者・商工団体の代表者・公募市民・行政機関の代表者により市民会議を設置し、会議を重ね、条例案が検討されています。また「産業振興シンポジウム」を行う等、商工業者や市民が主体になって条例制定にこぎつけています。
現時点で、産業振興条例の制定に向けての具体的な進展状況と今後のプログラムを明らかにして下さい。条例の制定には多くの市民、業者、商売人、農業従事者等の関係各位の知恵と力を結集して、進めていくことが必要です。条例にむけて、市民の意見の集約や、参加をどのような形で行っていくのか明らかにして下さい。
次に、住宅リフォーム助成制度です。私は地域の中小零細業者の仕事確保、市域内の産業活性化、営業を守るためにも住宅リフォーム助成制度が今こそ必要であると考えています。すでに一部自治体で始まったこの制度は、既に多くの成果をあげ全国の自治体へ広がってきている試され、結果が出ている制度です。市として調査研究をすること、そして制度の創設を求め答弁を求めます。
幼保一体化に係る文章
2011-12-13
2011年9月議会 一般質問 田中議員
2011-09-21