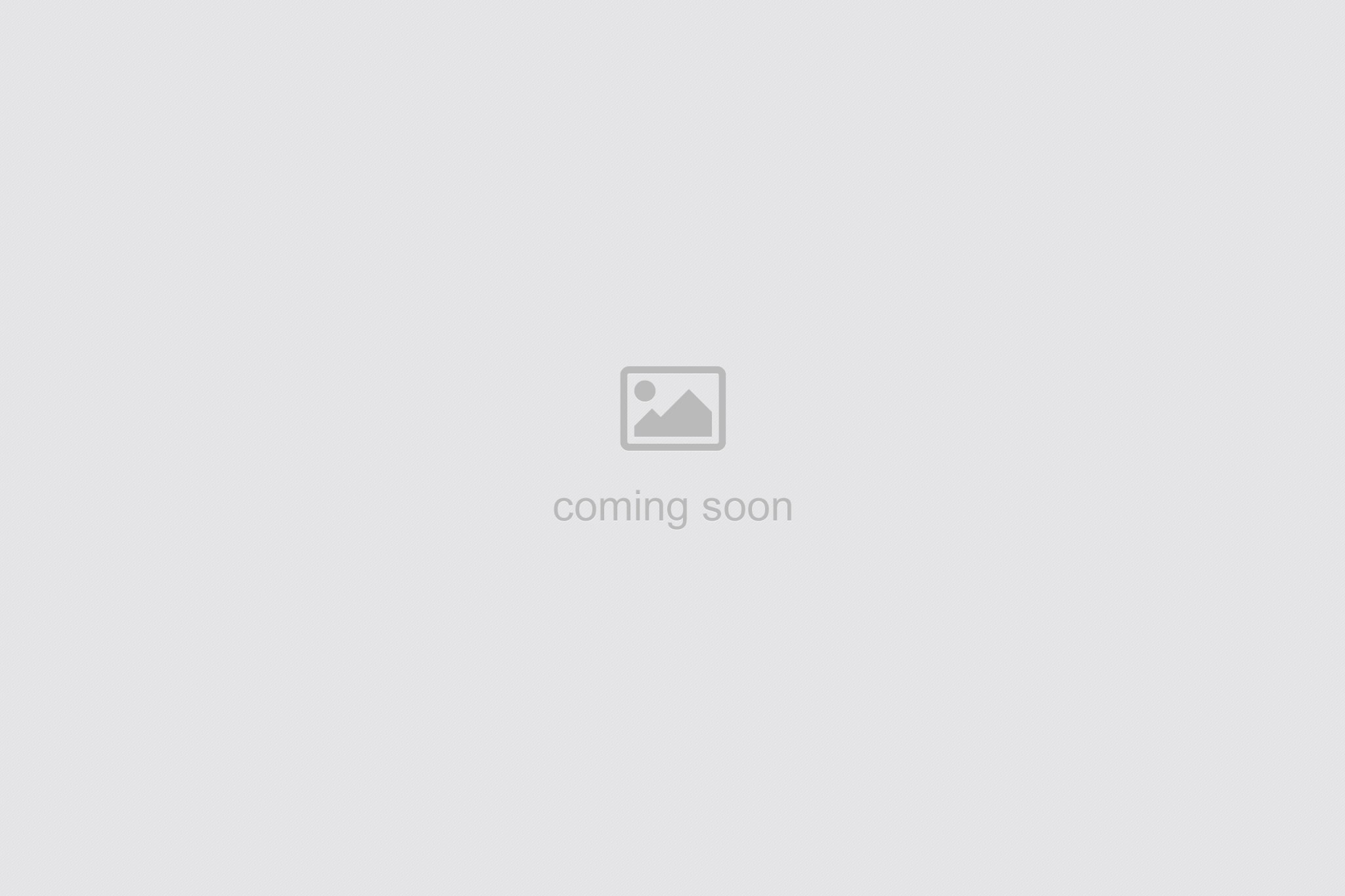枚方寝屋川消防議会 田中議員 一般質問
2010-07-30
北河内4市リサイクルプラザ「かざぐるま」の火災について一般質問させて頂きます。
今年6月14日の午前9時57分頃、寝屋川市寝屋南にある北河内4市リサイクルプラザ「かざぐるま」以下略して「かざぐるま」とさせて頂きます。この「かざぐるま」から出火、20台の消防車、71名の隊員が出動。枚方寝屋川消防組合の覚知は、10時07分であり、鎮火は14時48分となっています。覚知から鎮火まで約4時間40分かかっています。
損傷程度は、4階天井約10㎡焼損、受け入れホッパーの一部、供給コンベア、破袋機、粗選別機およびごみ1トンが焼損、1階から4階水煙損、消火にあたって屋根および窓ガラス等破損とされています。
出火原因は、簡易ガスライターによるものと推定とされています。
簡易ライターは頻繁に廃プラに混入されているとお聞きしています。収集段階での分別徹底も必要でありますが、今後、火災が二度と起きない保証はありません。廃プラ処理施設に設置する消防用設備等の基準については、充たされていたとお聞きしましたが、火災が起きても、迅速に鎮火できる設備等の指導や設備等の基準の見直しが求められます。その2点についてお聞きします。
次に消火活動にあたってのマニュアルについてです。
3年前、発泡スチロール製品を扱っているトーホー工業株式会社くずは工場において火災が起き、焼損面積は4,200㎡と「かざぐるま」より広かったようです。4階建て、耐火構造という点では、「かざぐるま」と同様ですが、鎮火に6時間費やしたと聞きました。化学製品という点では、同様であります。「かざぐるま」においても発泡スチロール、廃プラ、ペットボトルなどを扱っています。廃プラ処理施設などでの火災を迅速に消火できるためのマニュアルを作成すべきではありませんか。
また、消化活動にあたってです。「かざぐるま」では、TーVOC総揮発性有機化合物・トルエンの数値を市民に公開するために道路からすぐの玄関口に設置された電光掲示板があります。
火災当日は、住民への広報活動はされていないとお聞きしました。
火災の際、ペットボトルからはアセトアルデヒドやベンゼンが発生します。アセトアルデヒドやベンゼンは、発ガン性があり、目やノドなどの粘膜を刺激します。頭痛などの原因にもなります。
また、ポリエチレン(PE)からはアセトアルデヒド、アクロレイン(アクリルアルデヒド)、メチルアルコール、ホルムアルデヒド等が発生します。ひどい症状では、意識を失うなど、中枢神経を冒されることもあります。日頃から、廃プラ施設周辺の住民からは健康被害の訴えがあります。
廃プラから発生する化学物質には、未だに有害性が解明されていないものが多くあります。周辺住民に注意勧告など広報活動を行うべきだったと考えますが、いかがですか。
10年 6月議会 一般質問 中谷光夫議員
2010-06-25
はじめに、鳩山首相の突然の辞任をどうみるか。新しい菅内閣と民主党の政治をどうみるか。明らかにしておきたいと思います。鳩山さんは、辞任にあたって、「国民が聞く耳を持たなくなった」と言いました。事実は、鳩山さんと民主党が「国民の声を聞く耳を持たなくなった」ために、あいつぐ公約の裏切りに、国民の怒りが鳩山内閣と民主党を包囲した結果です。新しく内閣総理大臣となった菅さんは、鳩山さんと小沢さんの辞任で、「普天間基地問題」と「政治とカネ」の問題は、一件落着、けじめがついた、と言いました。マスコミ報道の影響から「脱小沢」人気で、内閣支持率も民主党支持率も急回復したことから、民主党は、国会延長をせず、内閣が代わったにもかかわらず、予算委員会の開催も拒否をして、選挙日程を優先しました。しかし、民主党が幹事長を誰にするかは、党内問題であり、国政の根本問題ではありません。
菅内閣とこの間の民主党の動きからは、鳩山さんが辞任に追い込まれた失政を反省し、国民の立場から政治を見直す姿勢はまったくありません。菅首相は、いち早くオバマ米国大統領と電話会談をおこない、5月28日の日米合意をふまえることを表明しました。はじめから沖縄県民の総意を裏切りました。枝野幹事長が最初に赴いた先は、日本経団連会長でした。民主党の成長戦略を報告に行ったといいます。政府と与党の要の2人の顔が代わっても、政治の中身はまったく変わっていません。実際、世論調査の政策支持は1割に過ぎません。国民の期待に反し、公約を裏切り続ける菅民主党内閣の正体は、早晩明らかになると考えます。
日本共産党は、雇用・労働の問題で、財界・大企業に、普天間基地の問題で米国政府に、国民の立場できっぱりと声を届けてきました。今政党に問われているのは、財界・大企業と米国に国民の立場でものを言う政治の実現です。
菅首相は所信表明で、「強い経済、強い財政、強い社会保障」を強調しました。一方で、昨年総選挙で訴えた「国民生活第一」は、言葉としても消えました。誰にとって強いのかが問われます。早速、その正体が見えてきました。法人税減税とセットの消費税大増税です。私たち日本共産党は、自民・公明政治に逆戻りするような今の菅民主党内閣の政治を許すことはできません。
日本共産党は、党をつくって88年になります。戦前、国民主人公の旗を掲げ、侵略戦争に反対したために大変な弾圧を受けました。戦後の出発にあたって、日本共産党以外の政党は、侵略戦争に協力・推進したために、名前を変えなければなりませんでした。国民主権・基本的人権の尊重・戦争放棄などを根本にした日本国憲法の成立にも力を尽くしてきました。日本共産党の党名には、戦前からの不屈の歴史と資本主義の先にあるすべての人間が自由で平等に大切にされる政治と社会をめざす理想が込められています。企業・団体からの政治献金や政党助成金を受け取る政党では、徹底した国民の立場に立つことはできません。私たち日本共産党は、7月11日投票で行われる参院選挙で、国民主人公へ、政治を前に進めるために、比例5議席以上、東京、大阪などの選挙区での必勝を期して全力を尽くす決意です。
それでは、一般質問を行います。
1.廃プラ処理、ごみ・環境問題について
①廃プラ問題について
【4市施設の火災事故について】
去る14日、4市リサイクル施設「かざぐるま」で火災が発生しました。日 本共産党議員団は、その日の午後、緊急に3点の申し入れを行いました。
①施設の安全の点検、確認と廃プラごみ収集の緊急措置を明らかにすること。
②火災の原因究明を早期に行い、その報告を議会と市民に明らかにすること。
③周辺住民への健康影響を把握し、今後の対策を明らかにすること。
以上の内容ですが、その後の経緯と現状を明らかにしてください。とくに、 火災事故について、判明している内容を詳細に説明してください。
当日、私も急行し、消防が鎮火にあたる前に、排煙に苦労している現場をみ ましたが、黒煙が大量に発生し広い地域にまで流れていました。施設の職員、 従業員に大きな被害が出なかったことは、不幸中の幸いですが、現地で私も顔 が火照りだし、気分が悪くなりかけたため、市役所にもどりました。周辺住民 への健康影響が心配と思ったところへ、住民から訴えが入りました。環境対策 へ連絡し、市として市民に煙等への注意を促す広報活動をするよう要請しまし た。その後まもなくして、市民5人が控え室に来られました。市の対応の悪さ、 火災の影響が宇谷小などの子どもたちに心配ないか、先生たちは、子どもたち を屋内に避難させてくれたのかなど、こもごも訴えられました。煙の影響が心 配と言うけど、空気は吸わな生きていかれへんがな。私たちは、毎日、心配な 空気を吸っているんですよ。まさに切実な訴えでした。
寝屋川市として、当日、火災が起きて、市民に対して安全対策として行った ことを明らかにしてください。危機管理対策にも通じると思いますが、市とし て、今回のような事故が起きたときに、どう対応するか、方針を持っています か。あれば、内容を明らかにしてください。
今回の火災を受けて、4市組合に次の点を緊急提起するよう求めます。
①プラスチック類は、化学変化が起きたときに、多種多様な有毒ガスを発生し ます。今回の火災では、長時間にわたったことから、多くの被害者の発生が心 配されます。周辺住民と職員、従業員などの健康影響の調査を徹底して行い、 施設の安全性が確認されるまで、操業停止すること。
②リサイクルのための廃プラ収集は、ペットボトルに限定した分別収集の協力 を市民に呼びかけ、その他プラについては、各市で焼却処分すること。
市の見解をお聞きします。
【柳沢幸雄東大大学院教授の大阪高裁証言を参考に】
柳沢教授は、健康被害の集団発生が明らかな「寝屋川病」と言われる廃プラ 公害がなぜ起きたのか。不幸にも次の3つの悪条件が重なったと証言しました。
1.汚染空気が淀みやすい温度逆転が頻繁に起きる地形の地域である。
2.温度逆転層の中に、有害物質を排出する廃プラ施設が立地し操業している。
3.その近くに多くの住民が住んでいる。
年間1万トン以上の廃プラを処理する施設が2つもあり、3つの悪条件が重 なる地域の例が全国にありますか。明らかにしてください。
柳沢教授による1年間にわたる空気の分析結果については次の通りです。
1.廃プラ施設周辺の空気は、未同定物質の割合が高く、規制対象物質の割合 が低い。未同定物質の中には多くの危険性の高い化学物質が含まれていると 推定することが重要です。
2.廃プラ施設周辺の空気には、脂肪族炭化水素やアルデヒド類が多いことが 確認された。これらは、東大研究室での実験により、プラスチックの集積・ 溶融工程から排出された可能性が高いことが明らかです。脂肪族炭化水素や アルデヒド類は、皮膚や粘膜に対する刺激性を有することが知られており、 住民の粘膜刺激症状や皮膚症状の訴えに注意する必要があります。
3.岡山大・津田教授による住民の健康調査の報告書で、のど、呼吸器、眼、 皮膚の症状が示されています。これらはすべて空気に触れる部分です。この ような刺激症状は、脂肪族炭化水素あるいはアルデヒドによる影響であると 考えて間違いないです。
住民の中には、専門の医療機関の診察で、化学物質過敏症として診断される 共通の症状がかなりの人にみられることも聞いています。
住民の訴えに聞く耳があれば、健康調査の実施、また、柳沢教授が行った環 境調査を少なくとも行政として実施すべきではないでしょうか。
「寝屋川病」患者をこれ以上増やさないために、考えられる対策はつぎの3 つです。
1.人がいなければ病人は出ません。この地域の人々をすべて強制移住させる。 2.温度逆転層が頻繁に形成されないように、地形をフラットに改変する。
3.温度逆転層の起こる地形内で有害物質を排出する工場の操業を止める。
3つの中で、社会的コストが安く、患者を増やさない、社会正義に合致する 対策は操業を止めることです。市の見解を求めます。
【廃プラごみの収集について】
寝屋川市はこの間、「環境基本計画改訂に係る基礎調査報告書」と「寝屋川市 一般廃棄物処理基本計画策定に係る基礎調査報告書」を発行しています。
「環境基本計画の進捗状況の整理及び課題の抽出」のところで示された進捗 状況の表の中で気になったのは、「有害化学物質・未規制化学物質対策の充実」 の項です。取り組み内容を見ると、「環境法令で規定されている有害物質につい ては、市・府による立入検査等により環境中に排出されないよう指導している」 とあり、以前、柳沢教授が寝屋川市の環境基本計画を評価された未規制化学物 質対策に取り組んだ内容はありませんでした。ここに、廃プラ公害の訴えにま ったく耳を貸さない寝屋川市の姿勢を見た思いがしました。
ついでながら、後で質問する「第二京阪沿道のまちづくり」については、「適 正な土地利用の誘導等」として、「寝屋南土地区画整理事業等、第二京阪道路沿 道にふさわしい計画的なまちづくりを推進しているほか、環境に配慮した道路 となるよう整備を行った。他の地域についても、区域区分と用途地域の変更を 検討した。」と記述しています。緑と自然を壊し、必要以上に第二京阪道路に多 くの道路をアクセスしたために交通事故の多発が心配される状況からは、違和 感を覚えます。
さて、廃プラ問題と関わってごみ問題の基本について考えてみたいと思いま す。「寝屋川市一般廃棄物処理基本計画」の改訂のために、今回の「基礎調査報 告書」が出されました。2000年度に策定された「基本計画」は、環境低負 荷・資源循環を追求する暮らしと事業活動をめざし、ごみの発生抑制、資源化 から収集・運搬、中間処理、最終処分までのごみ処理行政の基本となってきま した。
ごみ処理は、個人であれ、家庭であれ、企業であれ、自治体であれ、自己処 理が基本です。そのうえで、生活様式や社会のあり方が変化する中で、社会問 題としての解決が求められている課題です。特に、自然界になかったごみの発 生は、安全な処理方法を明らかにして取り組む必要があります。また、ごみの 大量発生の背景にある大量生産・大量消費、使い捨てには、何よりも生産者責 任、流通者責任の大きさを指摘しなければなりません。ごみ処理のあり方や処 理費用についても大きな責任や応分の負担を求める必要があります。今日のご み問題の解決のためには、ごみの発生抑制のために、リデュース、リユース、 リサイクルなどの資源循環型社会を形成するとともに、地球環境を守るための 温暖化防止や低炭素社会の構築が世界的な緊急課題になっています。
寝屋川市でごみ減量を考えたとき、自然に戻せる生ゴミは堆肥化の徹底が課 題となります。くり返し使える物は、回収を徹底することが課題です。自動車 や家電製品など、法律の対象になっている物についても、消費者責任でなく、 生産者責任にすることが徹底のうえからも課題です。アルミ缶・スチール缶、 瓶、紙類、ペットボトル、白色トレイなど、リサイクルできる物は、業者の回 収努力を求めながらの分別収集が課題です。
問題は、事業系ごみの分別協力の徹底と、廃プラごみのその他プラの扱いで す。容器包装リサイクル法の趣旨の中心は、生産や流通の責任業者に、リサイ クルの名でごみ処理の応分の負担を求める点にありました。今日、その他プラ といわれる廃プラスチックごみについては、品質的にリサイクルに適しない問 題と非効率な経済性の問題から、見直しを求める声が日本容器包装リサイクル 協会の幹部からも広がっています。また、杉並や寝屋川のように、揮発性の有 毒ガスによる健康被害が廃プラ処理施設の周辺で集団発生しています。
東京では、廃プラごみを可燃ごみとして扱い、焼却処理する自治体が増えて います。焼却炉の性能の向上によって、ダイオキシンは出なくなったと言われ ます。今回の火災事故を契機に、廃プラごみについては、分別収集をやめ、可 燃ごみとして見直すことが求められていると考えます。強い機械的圧力や溶融 による化学変化で多種多様な有害ガスを発生する危険から、焼却処理に変える ことで、水と炭酸ガスという心配不要な物質にすることができます。健康被害 を訴える住民はそのことを願っています。市の見解をお聞きします。
【クリーンセンター建て替えについて】
次に、クリーンセンターの建て替え問題についてです。
3月の代表質問でも明らかにしましたが、市の基礎的資料は、形式的に5カ 所の候補地をあげて比較対照しただけであり、恣意的に行政に都合の良い評価 を行い、「初めに現在地ありき」の結論を示しているものと言えます。現在審議 会がつくられ検討が始まると思いますが、市民にとって公正・公平な審議が行 われるよう、とくに事務局になる市当局に強く求めるものです。こうした施設 の建設は数も少なく多額の費用がかかります。業者との不正な癒着を指摘され る事例もあいついでいることからも、市民的にも十分な公開・透明性を求める ものです。また、現在のクリーンセンターに近い自治会などから市に対して要 望書が提出されています。私たちは、施設の広域化には反対の考えですが、少 なくとも建て替え検討箇所の周辺住民への説明と意見聴取を行うべきと考えま す。市の答弁を求めます。
2.第2京阪道路と沿道まちづくりについて
①第2京阪道路について
3月20日、第2京阪道路が開通しました。市外への交通の便が良くなった
ことは確かですが、巨大道路によって交通が寸断され、近くに行くのが不便に なった地域も生まれ、苦情も寄せられています。騒音は、道路そばの人はやは り深夜よく眠れないと聞きますが、少し離れた所では、遮音壁があるため、予 想外にましだと聞いています。他市では、道路より高い場所に住宅地があると ころでは、騒音問題が課題になっています。また、必要以上に道路をアクセス したことと、遮音壁による車線の合流箇所の見通しの悪さなど、交通事故の多 発が心配な状況があることも指摘をしておきます。
私は、遮音壁設置や騒音低減効果のある高機能舗装などは、住民運動と行政 努力の結果と考えています。同時に、1兆円を超える莫大な費用を湯水のよう に使って造られた点や、住民対策とはいえ、大阪側の全線を遮音壁を設置しな ければならなかったことから、あらためて、高速道路建設を中心とする巨大道 路建設を、多くの住民が沿線に住む地域に造ったことに、問題も感じました。
今後の問題は、何よりも環境調査と環境対策です。市内2カ所に事業者によ る測定局が設置されています。維持管理は、寝屋川市が行うこととなっていま す。測定データについては公表することで、8者協の「監視のあり方に関する 検討会」で合意と答弁していますが、事前測定のデータを含め、交通量調査な ど、入手している限りの状況を明らかにしてください。また、PM2.5について、 国の動向をみながら府に求めるとの姿勢ですが、状況によっては、市独自の測 定も必要と考えます。昨年、6月議会では、交野市が1989年から独自に調 査を実施してきた例を示し、寝屋川市としての努力を求めました。国に、大気 汚染防止法にもとづく道路沿道の常時監視局の設置を求めるとともに、せめて 市として、PTIO法による窒素酸化物の調査を行うよう求めます。ちなみに、 交野市では、85地点で実施された実績があることを紹介しておきます。
次に、緑・自然の再生についてです。「緑立つ道」「地域に愛される道」を掲 げて造られた第2京阪道路ですが、現状はスローガンが泣きます。市として、 沿道の緑化計画についてどう考えているのか、明らかにしてください。また、 事業者が、養生中を理由に閉じている公園の開放時期はいつになるのか、明ら かにしてください。
以上、見解をお聞きします。
②沿道まちづくりについて
次に沿道のまちづくりについてです。この10年来、国、府、西日本高速道 路株式会社、沿線5市、(財団法人)大阪府都市整備推進センターによって検討 会が作られ、市街化調整区域を市街化区域に編入する開発型のまちづくりが推 進されてきました。第2京阪道路建設がそのための契機とされてきました。そ の典型が、寝屋南土地区画整理事業です。
寝屋南土地区画整理事業の現況について明らかにしてください。また、大規 模商業施設の建設が予定されていますが、市内業者との商業調整など、現在わ かっている内容を日程を含めて明らかにしてください。
次に、都市計画道路の整備についてです。地域からも、「東寝屋川駅前線」の 早期実施をはじめ、「梅ヶ丘黒原線」「寝屋線」の早期整備の要望が市に提出さ れています。しかし、予定地の住民の中でもまったく状況を知らない人も多く います。必要な道路整備は当然ですが、道路建設は、多額の費用がかかります。 人口減少時代を迎え、従来の産業開発型、人口急増型の開発優先から、農地の 保全や自然、緑の再生を優先するまちづくりが求められています。とりわけ、 第2京阪道路建設で、寝屋川・四條畷地域で甲子園球場4個分、16㌶以上の 農地、自然が失われただけに、寝屋川でも貴重な農地、緑、自然が残る地域を これ以上壊すべきではないと考えます。不要不急の事業については、住民合意 をふまえながら見直すことも必要と考えます。市の見解をお聞きします。
3.教育について
最後に教育について、3点お聞きします。
1.教職員配置についてお聞きします。
市教委資料によれば、寝屋川市に配置された年度当初の新規採用教職員数 は、小学校で47名、中学校で26名、定数内講師が配置される欠員数は、 小学校で35名、中学校で69名となっています。講師頼みの教職員配置は 橋下府政の反映です。一部教科で講師の未配置があると聞きますが、現状を 明らかにしてください。
また、報道によれば、豊中市などの豊能地域で、小中学校の教職員の採用 人事などの大阪府からの権限委譲が伝えられています。寝屋川市の現状を見 る限り、地域主権や地方分権を口実に、まともな教職員採用・配置を行わな い大阪府の無責任をそのままに権限委譲など、論外だと考えます。市、市教 委としての見解をお聞きします。
2.部活動について
2012年完全実施の学習指導要領では、前回記述がなかった部活動が、「学 校教育の一環」として総則の中で取り上げられています。部活動に関わる課 題や問題点はさておいて、教育課程外にある部活動を、「学校教育の一環」の 枠組みにおさめるとすれば、自主的活動の中で、文化・スポーツを学び、自 治の力を育む場としなければならないと考えます。また、部活担当者を監督 やコーチと呼ばず、顧問としている意味もそこにあります。根底には、「部活 動の主体は生徒であり、教師は生徒を指導するのではなく、相談にのる役割 である」との考え方があると思います。
学校教育の目的は、「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成 者として必要な資質」の育成です。教師の本務は、教育課程(各教科、道徳、 特別活動、総合的な学習の時間)の遂行と生徒指導を基本とし、また、これ らと関連する事務的職務です。
教師の多数は、「文化・スポーツ活動は社会教育で」と考えており、そのう えで、「社会教育が発達していないので当面学校が担っていかざるを得ない」 のが現実です。教職員の多くは、早朝練習や休日の活動など、生徒や保護者 の要求に半ばボランティア的に奮闘しています。その大きな要因は、施設不 足、不十分さにあります。社会教育で行うにしても、施設環境の条件整備は 重要な課題です。
以上のことから、部活動が学習指導要領で「学校教育の一環」と位置づけ られたことをもって、学校や教師に強制することはもちろん、教師の本務と 位置づけてはならないと考えます。市教委の見解をお聞きします。
3.校区問題審議会、教科書選定委員会などの構成の見直しについて
現在、学校教育の基本にかかわる校区問題審議会や教科書選定委員会に、 一般教職員の代表が入っていません。いずれも従来は選ばれていました。教 育分野は専門性を必要とする。議員の立場になって、あらためて痛感してい ます。ユネスコなどの国際的な専門機関からも、くり返し、日本の教育行政 に対して、専門家としての教員の地位の向上についての勧告が出されてきま した。現在の寝屋川市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の構成は、市 教委関係から3人、校長2人、PTA関係2人です。教育に直接責任を持つ 一般教職員代表が必ず入るべきと考えます。審議会や委員会の委員に選ばな くなった理由、現在、任命ないし委嘱していない理由は何ですか。今後見直 しをすべきと考えます。市教委の見解をお聞きします。
菅内閣とこの間の民主党の動きからは、鳩山さんが辞任に追い込まれた失政を反省し、国民の立場から政治を見直す姿勢はまったくありません。菅首相は、いち早くオバマ米国大統領と電話会談をおこない、5月28日の日米合意をふまえることを表明しました。はじめから沖縄県民の総意を裏切りました。枝野幹事長が最初に赴いた先は、日本経団連会長でした。民主党の成長戦略を報告に行ったといいます。政府と与党の要の2人の顔が代わっても、政治の中身はまったく変わっていません。実際、世論調査の政策支持は1割に過ぎません。国民の期待に反し、公約を裏切り続ける菅民主党内閣の正体は、早晩明らかになると考えます。
日本共産党は、雇用・労働の問題で、財界・大企業に、普天間基地の問題で米国政府に、国民の立場できっぱりと声を届けてきました。今政党に問われているのは、財界・大企業と米国に国民の立場でものを言う政治の実現です。
菅首相は所信表明で、「強い経済、強い財政、強い社会保障」を強調しました。一方で、昨年総選挙で訴えた「国民生活第一」は、言葉としても消えました。誰にとって強いのかが問われます。早速、その正体が見えてきました。法人税減税とセットの消費税大増税です。私たち日本共産党は、自民・公明政治に逆戻りするような今の菅民主党内閣の政治を許すことはできません。
日本共産党は、党をつくって88年になります。戦前、国民主人公の旗を掲げ、侵略戦争に反対したために大変な弾圧を受けました。戦後の出発にあたって、日本共産党以外の政党は、侵略戦争に協力・推進したために、名前を変えなければなりませんでした。国民主権・基本的人権の尊重・戦争放棄などを根本にした日本国憲法の成立にも力を尽くしてきました。日本共産党の党名には、戦前からの不屈の歴史と資本主義の先にあるすべての人間が自由で平等に大切にされる政治と社会をめざす理想が込められています。企業・団体からの政治献金や政党助成金を受け取る政党では、徹底した国民の立場に立つことはできません。私たち日本共産党は、7月11日投票で行われる参院選挙で、国民主人公へ、政治を前に進めるために、比例5議席以上、東京、大阪などの選挙区での必勝を期して全力を尽くす決意です。
それでは、一般質問を行います。
1.廃プラ処理、ごみ・環境問題について
①廃プラ問題について
【4市施設の火災事故について】
去る14日、4市リサイクル施設「かざぐるま」で火災が発生しました。日 本共産党議員団は、その日の午後、緊急に3点の申し入れを行いました。
①施設の安全の点検、確認と廃プラごみ収集の緊急措置を明らかにすること。
②火災の原因究明を早期に行い、その報告を議会と市民に明らかにすること。
③周辺住民への健康影響を把握し、今後の対策を明らかにすること。
以上の内容ですが、その後の経緯と現状を明らかにしてください。とくに、 火災事故について、判明している内容を詳細に説明してください。
当日、私も急行し、消防が鎮火にあたる前に、排煙に苦労している現場をみ ましたが、黒煙が大量に発生し広い地域にまで流れていました。施設の職員、 従業員に大きな被害が出なかったことは、不幸中の幸いですが、現地で私も顔 が火照りだし、気分が悪くなりかけたため、市役所にもどりました。周辺住民 への健康影響が心配と思ったところへ、住民から訴えが入りました。環境対策 へ連絡し、市として市民に煙等への注意を促す広報活動をするよう要請しまし た。その後まもなくして、市民5人が控え室に来られました。市の対応の悪さ、 火災の影響が宇谷小などの子どもたちに心配ないか、先生たちは、子どもたち を屋内に避難させてくれたのかなど、こもごも訴えられました。煙の影響が心 配と言うけど、空気は吸わな生きていかれへんがな。私たちは、毎日、心配な 空気を吸っているんですよ。まさに切実な訴えでした。
寝屋川市として、当日、火災が起きて、市民に対して安全対策として行った ことを明らかにしてください。危機管理対策にも通じると思いますが、市とし て、今回のような事故が起きたときに、どう対応するか、方針を持っています か。あれば、内容を明らかにしてください。
今回の火災を受けて、4市組合に次の点を緊急提起するよう求めます。
①プラスチック類は、化学変化が起きたときに、多種多様な有毒ガスを発生し ます。今回の火災では、長時間にわたったことから、多くの被害者の発生が心 配されます。周辺住民と職員、従業員などの健康影響の調査を徹底して行い、 施設の安全性が確認されるまで、操業停止すること。
②リサイクルのための廃プラ収集は、ペットボトルに限定した分別収集の協力 を市民に呼びかけ、その他プラについては、各市で焼却処分すること。
市の見解をお聞きします。
【柳沢幸雄東大大学院教授の大阪高裁証言を参考に】
柳沢教授は、健康被害の集団発生が明らかな「寝屋川病」と言われる廃プラ 公害がなぜ起きたのか。不幸にも次の3つの悪条件が重なったと証言しました。
1.汚染空気が淀みやすい温度逆転が頻繁に起きる地形の地域である。
2.温度逆転層の中に、有害物質を排出する廃プラ施設が立地し操業している。
3.その近くに多くの住民が住んでいる。
年間1万トン以上の廃プラを処理する施設が2つもあり、3つの悪条件が重 なる地域の例が全国にありますか。明らかにしてください。
柳沢教授による1年間にわたる空気の分析結果については次の通りです。
1.廃プラ施設周辺の空気は、未同定物質の割合が高く、規制対象物質の割合 が低い。未同定物質の中には多くの危険性の高い化学物質が含まれていると 推定することが重要です。
2.廃プラ施設周辺の空気には、脂肪族炭化水素やアルデヒド類が多いことが 確認された。これらは、東大研究室での実験により、プラスチックの集積・ 溶融工程から排出された可能性が高いことが明らかです。脂肪族炭化水素や アルデヒド類は、皮膚や粘膜に対する刺激性を有することが知られており、 住民の粘膜刺激症状や皮膚症状の訴えに注意する必要があります。
3.岡山大・津田教授による住民の健康調査の報告書で、のど、呼吸器、眼、 皮膚の症状が示されています。これらはすべて空気に触れる部分です。この ような刺激症状は、脂肪族炭化水素あるいはアルデヒドによる影響であると 考えて間違いないです。
住民の中には、専門の医療機関の診察で、化学物質過敏症として診断される 共通の症状がかなりの人にみられることも聞いています。
住民の訴えに聞く耳があれば、健康調査の実施、また、柳沢教授が行った環 境調査を少なくとも行政として実施すべきではないでしょうか。
「寝屋川病」患者をこれ以上増やさないために、考えられる対策はつぎの3 つです。
1.人がいなければ病人は出ません。この地域の人々をすべて強制移住させる。 2.温度逆転層が頻繁に形成されないように、地形をフラットに改変する。
3.温度逆転層の起こる地形内で有害物質を排出する工場の操業を止める。
3つの中で、社会的コストが安く、患者を増やさない、社会正義に合致する 対策は操業を止めることです。市の見解を求めます。
【廃プラごみの収集について】
寝屋川市はこの間、「環境基本計画改訂に係る基礎調査報告書」と「寝屋川市 一般廃棄物処理基本計画策定に係る基礎調査報告書」を発行しています。
「環境基本計画の進捗状況の整理及び課題の抽出」のところで示された進捗 状況の表の中で気になったのは、「有害化学物質・未規制化学物質対策の充実」 の項です。取り組み内容を見ると、「環境法令で規定されている有害物質につい ては、市・府による立入検査等により環境中に排出されないよう指導している」 とあり、以前、柳沢教授が寝屋川市の環境基本計画を評価された未規制化学物 質対策に取り組んだ内容はありませんでした。ここに、廃プラ公害の訴えにま ったく耳を貸さない寝屋川市の姿勢を見た思いがしました。
ついでながら、後で質問する「第二京阪沿道のまちづくり」については、「適 正な土地利用の誘導等」として、「寝屋南土地区画整理事業等、第二京阪道路沿 道にふさわしい計画的なまちづくりを推進しているほか、環境に配慮した道路 となるよう整備を行った。他の地域についても、区域区分と用途地域の変更を 検討した。」と記述しています。緑と自然を壊し、必要以上に第二京阪道路に多 くの道路をアクセスしたために交通事故の多発が心配される状況からは、違和 感を覚えます。
さて、廃プラ問題と関わってごみ問題の基本について考えてみたいと思いま す。「寝屋川市一般廃棄物処理基本計画」の改訂のために、今回の「基礎調査報 告書」が出されました。2000年度に策定された「基本計画」は、環境低負 荷・資源循環を追求する暮らしと事業活動をめざし、ごみの発生抑制、資源化 から収集・運搬、中間処理、最終処分までのごみ処理行政の基本となってきま した。
ごみ処理は、個人であれ、家庭であれ、企業であれ、自治体であれ、自己処 理が基本です。そのうえで、生活様式や社会のあり方が変化する中で、社会問 題としての解決が求められている課題です。特に、自然界になかったごみの発 生は、安全な処理方法を明らかにして取り組む必要があります。また、ごみの 大量発生の背景にある大量生産・大量消費、使い捨てには、何よりも生産者責 任、流通者責任の大きさを指摘しなければなりません。ごみ処理のあり方や処 理費用についても大きな責任や応分の負担を求める必要があります。今日のご み問題の解決のためには、ごみの発生抑制のために、リデュース、リユース、 リサイクルなどの資源循環型社会を形成するとともに、地球環境を守るための 温暖化防止や低炭素社会の構築が世界的な緊急課題になっています。
寝屋川市でごみ減量を考えたとき、自然に戻せる生ゴミは堆肥化の徹底が課 題となります。くり返し使える物は、回収を徹底することが課題です。自動車 や家電製品など、法律の対象になっている物についても、消費者責任でなく、 生産者責任にすることが徹底のうえからも課題です。アルミ缶・スチール缶、 瓶、紙類、ペットボトル、白色トレイなど、リサイクルできる物は、業者の回 収努力を求めながらの分別収集が課題です。
問題は、事業系ごみの分別協力の徹底と、廃プラごみのその他プラの扱いで す。容器包装リサイクル法の趣旨の中心は、生産や流通の責任業者に、リサイ クルの名でごみ処理の応分の負担を求める点にありました。今日、その他プラ といわれる廃プラスチックごみについては、品質的にリサイクルに適しない問 題と非効率な経済性の問題から、見直しを求める声が日本容器包装リサイクル 協会の幹部からも広がっています。また、杉並や寝屋川のように、揮発性の有 毒ガスによる健康被害が廃プラ処理施設の周辺で集団発生しています。
東京では、廃プラごみを可燃ごみとして扱い、焼却処理する自治体が増えて います。焼却炉の性能の向上によって、ダイオキシンは出なくなったと言われ ます。今回の火災事故を契機に、廃プラごみについては、分別収集をやめ、可 燃ごみとして見直すことが求められていると考えます。強い機械的圧力や溶融 による化学変化で多種多様な有害ガスを発生する危険から、焼却処理に変える ことで、水と炭酸ガスという心配不要な物質にすることができます。健康被害 を訴える住民はそのことを願っています。市の見解をお聞きします。
【クリーンセンター建て替えについて】
次に、クリーンセンターの建て替え問題についてです。
3月の代表質問でも明らかにしましたが、市の基礎的資料は、形式的に5カ 所の候補地をあげて比較対照しただけであり、恣意的に行政に都合の良い評価 を行い、「初めに現在地ありき」の結論を示しているものと言えます。現在審議 会がつくられ検討が始まると思いますが、市民にとって公正・公平な審議が行 われるよう、とくに事務局になる市当局に強く求めるものです。こうした施設 の建設は数も少なく多額の費用がかかります。業者との不正な癒着を指摘され る事例もあいついでいることからも、市民的にも十分な公開・透明性を求める ものです。また、現在のクリーンセンターに近い自治会などから市に対して要 望書が提出されています。私たちは、施設の広域化には反対の考えですが、少 なくとも建て替え検討箇所の周辺住民への説明と意見聴取を行うべきと考えま す。市の答弁を求めます。
2.第2京阪道路と沿道まちづくりについて
①第2京阪道路について
3月20日、第2京阪道路が開通しました。市外への交通の便が良くなった
ことは確かですが、巨大道路によって交通が寸断され、近くに行くのが不便に なった地域も生まれ、苦情も寄せられています。騒音は、道路そばの人はやは り深夜よく眠れないと聞きますが、少し離れた所では、遮音壁があるため、予 想外にましだと聞いています。他市では、道路より高い場所に住宅地があると ころでは、騒音問題が課題になっています。また、必要以上に道路をアクセス したことと、遮音壁による車線の合流箇所の見通しの悪さなど、交通事故の多 発が心配な状況があることも指摘をしておきます。
私は、遮音壁設置や騒音低減効果のある高機能舗装などは、住民運動と行政 努力の結果と考えています。同時に、1兆円を超える莫大な費用を湯水のよう に使って造られた点や、住民対策とはいえ、大阪側の全線を遮音壁を設置しな ければならなかったことから、あらためて、高速道路建設を中心とする巨大道 路建設を、多くの住民が沿線に住む地域に造ったことに、問題も感じました。
今後の問題は、何よりも環境調査と環境対策です。市内2カ所に事業者によ る測定局が設置されています。維持管理は、寝屋川市が行うこととなっていま す。測定データについては公表することで、8者協の「監視のあり方に関する 検討会」で合意と答弁していますが、事前測定のデータを含め、交通量調査な ど、入手している限りの状況を明らかにしてください。また、PM2.5について、 国の動向をみながら府に求めるとの姿勢ですが、状況によっては、市独自の測 定も必要と考えます。昨年、6月議会では、交野市が1989年から独自に調 査を実施してきた例を示し、寝屋川市としての努力を求めました。国に、大気 汚染防止法にもとづく道路沿道の常時監視局の設置を求めるとともに、せめて 市として、PTIO法による窒素酸化物の調査を行うよう求めます。ちなみに、 交野市では、85地点で実施された実績があることを紹介しておきます。
次に、緑・自然の再生についてです。「緑立つ道」「地域に愛される道」を掲 げて造られた第2京阪道路ですが、現状はスローガンが泣きます。市として、 沿道の緑化計画についてどう考えているのか、明らかにしてください。また、 事業者が、養生中を理由に閉じている公園の開放時期はいつになるのか、明ら かにしてください。
以上、見解をお聞きします。
②沿道まちづくりについて
次に沿道のまちづくりについてです。この10年来、国、府、西日本高速道 路株式会社、沿線5市、(財団法人)大阪府都市整備推進センターによって検討 会が作られ、市街化調整区域を市街化区域に編入する開発型のまちづくりが推 進されてきました。第2京阪道路建設がそのための契機とされてきました。そ の典型が、寝屋南土地区画整理事業です。
寝屋南土地区画整理事業の現況について明らかにしてください。また、大規 模商業施設の建設が予定されていますが、市内業者との商業調整など、現在わ かっている内容を日程を含めて明らかにしてください。
次に、都市計画道路の整備についてです。地域からも、「東寝屋川駅前線」の 早期実施をはじめ、「梅ヶ丘黒原線」「寝屋線」の早期整備の要望が市に提出さ れています。しかし、予定地の住民の中でもまったく状況を知らない人も多く います。必要な道路整備は当然ですが、道路建設は、多額の費用がかかります。 人口減少時代を迎え、従来の産業開発型、人口急増型の開発優先から、農地の 保全や自然、緑の再生を優先するまちづくりが求められています。とりわけ、 第2京阪道路建設で、寝屋川・四條畷地域で甲子園球場4個分、16㌶以上の 農地、自然が失われただけに、寝屋川でも貴重な農地、緑、自然が残る地域を これ以上壊すべきではないと考えます。不要不急の事業については、住民合意 をふまえながら見直すことも必要と考えます。市の見解をお聞きします。
3.教育について
最後に教育について、3点お聞きします。
1.教職員配置についてお聞きします。
市教委資料によれば、寝屋川市に配置された年度当初の新規採用教職員数 は、小学校で47名、中学校で26名、定数内講師が配置される欠員数は、 小学校で35名、中学校で69名となっています。講師頼みの教職員配置は 橋下府政の反映です。一部教科で講師の未配置があると聞きますが、現状を 明らかにしてください。
また、報道によれば、豊中市などの豊能地域で、小中学校の教職員の採用 人事などの大阪府からの権限委譲が伝えられています。寝屋川市の現状を見 る限り、地域主権や地方分権を口実に、まともな教職員採用・配置を行わな い大阪府の無責任をそのままに権限委譲など、論外だと考えます。市、市教 委としての見解をお聞きします。
2.部活動について
2012年完全実施の学習指導要領では、前回記述がなかった部活動が、「学 校教育の一環」として総則の中で取り上げられています。部活動に関わる課 題や問題点はさておいて、教育課程外にある部活動を、「学校教育の一環」の 枠組みにおさめるとすれば、自主的活動の中で、文化・スポーツを学び、自 治の力を育む場としなければならないと考えます。また、部活担当者を監督 やコーチと呼ばず、顧問としている意味もそこにあります。根底には、「部活 動の主体は生徒であり、教師は生徒を指導するのではなく、相談にのる役割 である」との考え方があると思います。
学校教育の目的は、「人格の完成」と「平和で民主的な国家及び社会の形成 者として必要な資質」の育成です。教師の本務は、教育課程(各教科、道徳、 特別活動、総合的な学習の時間)の遂行と生徒指導を基本とし、また、これ らと関連する事務的職務です。
教師の多数は、「文化・スポーツ活動は社会教育で」と考えており、そのう えで、「社会教育が発達していないので当面学校が担っていかざるを得ない」 のが現実です。教職員の多くは、早朝練習や休日の活動など、生徒や保護者 の要求に半ばボランティア的に奮闘しています。その大きな要因は、施設不 足、不十分さにあります。社会教育で行うにしても、施設環境の条件整備は 重要な課題です。
以上のことから、部活動が学習指導要領で「学校教育の一環」と位置づけ られたことをもって、学校や教師に強制することはもちろん、教師の本務と 位置づけてはならないと考えます。市教委の見解をお聞きします。
3.校区問題審議会、教科書選定委員会などの構成の見直しについて
現在、学校教育の基本にかかわる校区問題審議会や教科書選定委員会に、 一般教職員の代表が入っていません。いずれも従来は選ばれていました。教 育分野は専門性を必要とする。議員の立場になって、あらためて痛感してい ます。ユネスコなどの国際的な専門機関からも、くり返し、日本の教育行政 に対して、専門家としての教員の地位の向上についての勧告が出されてきま した。現在の寝屋川市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会の構成は、市 教委関係から3人、校長2人、PTA関係2人です。教育に直接責任を持つ 一般教職員代表が必ず入るべきと考えます。審議会や委員会の委員に選ばな くなった理由、現在、任命ないし委嘱していない理由は何ですか。今後見直 しをすべきと考えます。市教委の見解をお聞きします。
10年 6月議会 一般質問 太田市議
2010-06-25
国民健康保険について
最初に国民健康保険料についてです。08年度の毎日新聞の全国調査で寝屋川市の保険料が4人家族のモデルケースで一番高いと報道されました。09年度は報道を受けてか保険料が下がったことを実感できるように引下げをするということで、一定の減額が行われましたが、依然モデルケースでは所得に対して20%を超える高い保険料となっています。
そして、10年度の保険料について、市長は3月議会で「国民健康保険料についてですが、保険料算出の基本となる賦課総額の求め方は、国の通知により定められておるところでございます。計算式に用いる予定収納率は実行可能な収納率を設定すると示されております。しかしながら、保険料の決定には被保険者の理解が得られることが重要と考えておりますので、予定収納率の見直し、条例減免の在り方等検討する中で、持続的に安定した保険運営が維持できる保険料を算定してまいりたいと考えております。」と答弁をされています。そこで伺いますが、今回の保険料率を算出するにあたって被保険者の理解が得られることが重要と述べておられますが、実際にどの程度の保険料なら市民の理解を得ることができると考えているのか、また、その根拠はどこにあるのかお答えください。あわせて予定収納率についても言及されていますが、昨年今年と予定収納率は85%で計算されているのではないでしょうか。ここに市長としての考えがどのように反映されたのか合わせてお答えください。市民の方とお話をしていて感じるのは、国民健康保険料については、支払いたいと思っている市民がたいへん多いということです。しかしその一方で、支払うことができない高額な保険料によって生活自体がきびしくなっている実態があることです。ある、高齢のご婦人は、よく病院を利用しているので保険料は支払うことは当然だと思っている。しかし、年金に対して保険料が重すぎる。介護保険と合わせて天引きされると、夕食を抜くなどの節約をすることが多くなると訴えておられました。市民は高すぎる保険料を負担し続けているのです。
10年度の保険料が決定され市民へ納付書が送付されています。昨年度に比べわずかに保険料が下げられていますが、重い負担であることに変わりがありません。更なる保険料の引き下げに一般会計よりの繰り入れを行うことを求めます。09年度の決算見込みが出ていますが、国民健康保険特別会計において単年度で約5億円の黒字が計上されています。累積赤字解消のための収支改善3億円も一定理解できますが、黒字分は保険料を引下げるための財源として考えることも必要ではないでしょうか。答弁を求めます。
続いて保険料の減免についてです。国も失業者に対する保険料の減免について通達を出しています。寝屋川市として通達にそって条例減免の中でさらに減免額を大きくするような特別な措置を取るように求めます。また、国は、減免に対する交付税措置を取るとされていますが、寝屋川市は減免をしても全国平均保険料より高いために、交付税措置の対象外となっています。ここでも、保険料が高すぎることが問題となっています。せめて減免をすることで、支払うことが可能な金額への減免が必要です。減免をしても高い実態の改善を求め答弁を求めます。
保険料の分納相談についてです。窓口で国保料の分納相談をした市民から、到底支払うことができない金額で約束をしてしまったと、相談を受けることがあります。相談に行く市民の方は少しでも払いたいという思いで窓口に行っています。そして、分納をお願いすることに後ろめたく思っているのです。そんな中で、窓口の職員がこの額でなら分納できると金額を示されると、実際には支払うことができなくても、あきらめて署名をしてしまうそうです。前年所得で計算される国保料は、現実の生活実態に合わない金額となることがあります。社会保障である国民健康保険の制度がその重たい保険料負担で生活を破壊している現実を直視して、少しでも払っていきたいと分納の相談に来ている市民に払うことが不可能な金額の提示はやめて下さい。窓口で市民に提示する金額はどのように検討をしたうえで出されていますか。生活実態をよく聞き市民が納得をし、支払うことができる金額の提示を求めます。
短期保険証・資格証明書についてです。7月より高校生以下の世代に6か月の短期保険証の交付を行うとされています。寝屋川市では4月末時点で、対象人数が資格証明書世帯73人、短期保険証世帯259名 合計332名となっています。これにより、寝屋川市内には、正規の健康保険証、6か月の短期保険証、3か月の短期保険証、資格証明書と国保加入者が4種類に分けられる状態となり、その上に無保険の人たちがいます。市民の中にも混乱を生むのではないでしょうか。国保は社会保障ですので、すべての加入者に正規の健康保険証を交付することを求めます。滞納対策と保険証の交付は分けて考えることが必要ではないでしょうか。
この間、新型インフルエンザを契機に資格証明書に係る様々な通達等も出されています。その中で、病院に診察に行く状態は、特別な状態にあたり資格証明書の発行対象とならない特別な状態と示されています。昨年度、資格証明書での受診が32件で約58万円の窓口負担が行われていますが、本来この方たちには資格証明書の発行はできないのではないですか。市内の医療機関に協力を求め、資格証明書での受診をなくすように行政としての努力を求め答弁を求めます。
市内の無保険状態の方の把握はどのようにされていますか。基本的に無保険となっている人が加入することになる保険は国保になると考えられます。市内の無保険者の把握と無保険での受診の実態も合わせてお答えください。
介護保険について
日本共産党国会議員団が介護保険制度見直しにむけたアンケート結果を6月9日公表しました。その中で介護事業所アンケートの結果と特徴では、「サービス利用を抑制している人がいる」が7割を超えています。また、「要介護認定について問題点がまだある」が8割を超えています。居宅介護サービスの充足状況では、「サービスが足りず我慢強いられている人がいる」が6割近くに上っています。介護現場の改善については、訪問介護事業所の7割が人手不足、この間行われた3%の介護報酬の引き上げは「ほとんど効果がない」が約7割となっています。このアンケート結果は全国的なものですが、このように問題となっていることは寝屋川市内の介護施設・利用者にも共通しています。
先日、寝屋川市内の介護施設のケアマネージャーにお話を伺いますと、ある高齢者の方が介護認定を受けられ、ケアプランを制作した。しかし、ケアプランを元にお話をしていると、このサービスはいくらかかる。このサービスはいくらかかると質問されていく中で、結局この方は、介護サービスの利用を取りやめたとききました。現実に保険料は取られているしかし、利用料が負担できなくて利用できない方が多くいるのではないでしょうか。寝屋川市には介護給付費準備基金が12億3千7百万円あります。これを利用して、介護が必要な方が必要な介護を経済的な心配をせずに受けることができるよう、利用料金の減免制度の創設を求めます。
また、障害者自立支援法については今年四月より住民税非課税世帯は原則無料となりました。ところが、65歳以上になりますと、障害者自立支援法から介護保険に移り一割負担になってしまいます。同様のサービスを受けながら64歳までは無料なのに65歳になると一割負担に変わるのは矛盾しています。介護保険における障害者の住民税非課税世帯の無料化は急務の課題です。国の施策を待つことなく市として無料化を行って下さい。
「遺影を拭(ふ)くのはダメ」「お供えの花を買いに行くのも『NO』」。大阪府寝屋川市が市内の訪問介護事業所に対し、こんな指導をしている。法令では明確に禁止されていない事項だが、市は「日常生活の援助には該当しない」としている。関係者からは「介護保険の利用を不当に制限している」と批判の声も上がっている。と5月7日毎日新聞で寝屋川市の介護保険サービスのローカルルールが報道されました。
寝屋川市では07年4月、過去に介護保険適用に関する問い合わせがあった事例を「Q&A」形式にまとめ、事業所に配布しています。事例によると、「保険利用者が眼鏡を調整するため、一緒に店に行ってもよいか」との質問に「眼鏡は日常生活に必要だが、眼鏡の調整は日常生活には含まれず不可」。扇風機やストーブの出し入れ、衣替えに伴う押し入れやたんすの衣服入れ替えも「大がかりな非日常行為で保険算定できない。有償ボランティアなどを利用するように」と指導しています。この間、市議会の中でも取り上げてきましたが、寝屋川市は過去に出したQ&Aや連絡文章は変わっていないという立場をとっています。そんな中いくら現場で必要な介護が受けられるよう指導をしていると言っても文章化され公にされない限り多くの介護保険利用者、介護施設が対応に戸惑うのではないでしょうか。この間、大阪社会保障推進協議会が北河内7市の介護事業やケアマネ・ヘルパーに介護保険に関するアンケートをしていますが、寝屋川市内のケアマネージャーから、同居家族がいることで制限を受けたことがあるや散歩や外出が介護保険で認められなかったなど、大阪府の改定されたQ&Aでは認められていることが市内では制限されているとアンケートにはしるされています。寝屋川市では、国の介護保険の法律で定められていること以上に現場では介護サービスが制限されているのか、また、大阪府のQ&Aについてどのように介護事業所、ケアマネジャーに伝えているのかを明らかにして下さい。また、この間、寝屋川市は新たなQ&AをつくりHPに掲載をすると言ってきましたが未だ掲載されていません。早急に市民に明らかにするように求めます。
介護保険料の引き下げについてです。藤井寺市では3年計画の途中であったけれども、介護給付費準備基金の取り崩しで保険料の引き下げを行いました。このことで寝屋川市の介護保険料準備給付基金の取り崩しの割合は大阪府で一番低い自治体となったのではないでしょうか。基金はすべて被保険者の納めた保険料です。早急に基金を取り崩し保険料の引き下げを求めます。寝屋川市内の高齢者からは寝屋川市は泥棒か、取りすぎた保険料ぐらいすぐに返してほしい。2年も3年も先のこと言われても今生活がしんどい。来年なんて生きてるか分からないと。声も上がっています。基金を使って保険料の引き下げ、利用料・保険料の市独自の減免制度の創設を求めます。
子育て支援についてです。
日本共産党は4月30日に「待機児童問題を解決し、安心して預けられる保育を実現するために」と緊急提言を行いました。
「夫はリストラで失業、働きたいのに入れない」「育休あけまでに保育所がみつからないと仕事を失う」。保育団体の電話相談「保育所ホットライン」には深刻な訴えが全国から寄せられました。やむなく幼い子どもに乳児をゆだね、不安のなかで働く父母もいます。いま全国で認可保育所に入所を希望し、実際に入所の手続きをしながら待機している子どもだけでも5万人近くおり、潜在的には100万人ともいわれています。
また、やっとの思いで入った保育所でも、定員を超えた詰め込みで保育のゆとりと安全が脅かされています。「廊下でお昼寝」「全員で食事を取るスペースもない」という環境で、子どもがストレスをためているようなところもあります。
保育士の過重負担も深刻で、5人に1人は身体の不調を訴えています。「1人でも多くの子どもに保育を保障したい」「子育てに悩む若い父母の力になりたい」という保育関係者の努力はもう限界です。
こうした深刻な事態は、自公政権が「規制緩和」「民間委託」「民営化」をかかげ、必要な保育所をつくらず、定員をこえた詰め込みや認可外の保育施設を待機児童の受け皿にした安上がりの「待機児童対策」の破たんを示すものです。民主党政権は、この路線の転換をはかるのではなく、すでに自公政権で破たんした保育分野の「規制緩和」の流れをいっそうすすめようとしています。これでは国民の願いにこたえることはできません。いま必要なのは、「規制緩和」路線を根本的に転換し、国と自治体の責任で認可保育所の本格的な増設をすすめることです。
保育所がないために、子育て中の若い世代が就職できない、仕事を失い生活苦におちいるなどという事態は、政治の責任で一刻も早く解決しなければなりません。
待機児童の85%は3歳未満の乳幼児です。とりわけ産休あけ、育児休業あけのゼロ歳児、1歳児の入所希望が切実です。そもそも、保育所運営費の基準が低いうえに、自公政権がゼロ歳児保育のための補助金の減額・廃止をしたことは、低年齢児の受け入れ枠の拡大や、年度途中からの受け入れのために保育士を確保しておくことを困難にしてきました。運営費の増額と補助金の復活・拡充などをはかり、保育士の配置などを手厚くし、産休あけ、育休あけから安心して預けられるようにしていく必要があります。
そこで伺いますが、5月1日現在で寝屋川市内の保育園では多くが定員を超えて子どもたちが入所をしています。今後さらに保育需要も伸びることを考えると、待機児童が今後市内に増えていくことが容易に予想できます。市として新たな認可保育所をつくることが必要ではないでしょうか。この間、認可保育園の新設を考えているかのような答弁もありました。具体的な今後の予定をお答えください。
また、無認可保育所への支援制度を作ることが必要です。
無認可保育所は、低年齢児を中心に23万人もの子どもを全国で受け入れています。しかし国の支援がいっさいないため、保育料の父母負担が重く、財政的にも困難ななかで保育士らの献身的努力で保育を支えているのが実態です。寝屋川市内でも無認可の共同保育所が待機児を長年受け入れてきた実態があります。そして、現在でもその役割を果たしていることは明らかです。市として補助を復活するように求めます。
民主党政権はこの4月、自公政権がすすめてきた保育所定員の「規制緩和」をさらにすすめ、年度当初は定員の115%、年度途中は125%などと、これまで受け入れの上限として残されていた基準さえすべて取り払ってしまいました。また、今年から給食を外部施設から搬入できるようにすることも決めました。そのうえ民主党政権が今国会に提出した「地域主権改革」一括法案では、国の保育所最低基準そのものをなくし、都道府県の条例に委任するとしています。避難用すべり台の設置義務がなくなるなど、子どもの命にかかわる規制まで緩和され、東京や待機児童を抱える自治体では、子ども1人あたりの面積の基準を引き下げられるようにしています。
こうした「規制緩和」による待機児童対策では、待機児童解消ができないばかりか、子どもたちの健康と安全をおびやかし、保育所の保育環境と保育士の労働条件を大きく悪化させ、安心して預けられる保育への父母の信頼を失わせてしまうものです。
「規制緩和」の流れをストップさせ、定員超過の解消にただちにとりくむとともに、子どものゆたかな発達を保障する保育条件や保育士の労働条件の改善こそ必要ではありませんか。そして、地域の基準となる公立保育所の役割はますます大切になっています。国に対して制度の改善を求め、市としての市内の保育水準の維持向上のために独自の加算を求めます。
次に中学校給食についてです。全国的には80%を超える実施率ですが大阪では約8%と低い実施率となっています。しかし、北河内内を見ますと、門真市、交野市、四条畷市において中学校給食が実施されています。子どもの貧困が社会問題となっている中、中学校における完全給食は、子どもたちの成長にとって今改めて有益な事業として見直されているのではないでしょうか。寝屋川市はブランド戦略を打ち出していますが、かつての寝屋川市のように子育てするなら寝屋川市と、市民の住みやすさこそが寝屋川市のブランドとなるのではないでしようか。ぜひ、中学校給食の実施に向けて検討を始めるよう求め答弁を求めます。
こども医療費の無料化の拡大についてです。
現在、寝屋川市は外来、入院ともに小学校入学前まで所得制限付きながら行っています。中学校卒業までを対象にした都道府県が増えている中、更なる子ども医療費無料化の対象年齢引き上げを所得制限なしで行うよう求めます。
妊産婦健診の無料化について
今年四月より初回のみ7500円と前年より5000円の補助金アップで総額40000円です。全国平均の約85000円には全然足りません。実際には総額で約11万円かかります。飛び込み出産などが社会問題となる中で、妊産婦健診の無料化が求められています。寝屋川市は府下でも早くに健診回数を増やしてきました。しかし、国の措置が取られてからは府下平均並みで全国平均より大きく遅れています。現実の問題として、いくら補助金が出ると言っても、窓口でいくら支払うのか分からない、妊産婦健診の負担は重いものがあります。安心して受けるためには窓口負担ゼロ無料化が必要です。安心して子育てできる寝屋川市へ妊産婦健診の無料化へ市の施策を進めて下さい。
今回、北河内夜間救急センターが廃止されるにあたり多くの市民と話をしましたが、#8000の認知度はかなり低い物がありました。せっかくの施策を市民が知らないために利用できていないことが多くあるのではないでしょうか。 こんにちは赤ちゃん事業から就学援助、高校の奨学金まで、子どもに関する様々な施策の情報を、必要とする市民に知らせるためのパンフレットの作成や、ホームページの改善に力を尽くして下さい。市として知らなくて使えなかったという市民を出さないための努力を改めて求めます。
その他
市内の銭湯について質問します。
昨年4月に下水道料金の値上げの後、高柳2丁目にあった「高柳温泉」平池町にあった「大和温泉」が廃業しました。特に大和温泉については、地域に残されているお風呂のないアパートの住民から大きな苦情も寄せられています。
中央老人福祉センターには無料で開放されたお風呂がありますが、平池からは遠くて利用することが困難です。今、地域の銭湯は廃業が進んでいます。寝屋川市の市営住宅にはお風呂がなく、地域の銭湯には税金も投入され運営されています。銭湯がなくなった地域に住んでいる人たちが、中央老人福祉センターに行こうとしても足がなくて厳しい状況があります。シャトルバスの運行など、検討して下さい。
また、地域に残された銭湯は地域社会を形成する大きな役割を担っています。地域の社交場でもある銭湯の維持は大変重要です。下水道料金値上げの際にも申し上げましたが、現在残っている銭湯の維持に市の援助が必要ではないでしょうか。上下水道料金の減免などの対応を求めます。
災害時の公共住宅への入居について
寝屋川市では火災などが起きた場合に市営住宅や、府営住宅への緊急の入居の紹介を行っていますが、現実には3カ月と期限を切った入居により多くの被災者が利用をしていません。しかし公営住宅の入居について緊急に入居をした方でも、入居基準を満たしていればそのまま住み続けることができるというのが現在の公営住宅法の趣旨に沿った対応ではないでしょうか。過去の被災者の公営住宅の入居とその後の居住実態について明らかにして下さい。今後、被災者には入居基準を満たしている方については住み続けることができることとし説明をして下さい。答弁を求めます。
また現在、寝屋川市内の公営住宅の空いている件数と災害時の緊急避難で入居することができる件数を明らかにして下さい。
議会での答弁と現実に行われる施策の違いについて
3月の厚生常任委員会で、ヒブワクチンやインフルエンザ、肺炎球菌の予防接種の予算が審議されるにあたり、私は、市民の利便性を考え、窓口で減額された金額を払えば済むようにしてほしいと要望をしました。しかし、市は「事前に来ていただくということは可能と考えております。医療機関から直接請求するということであれば、医療機関は多岐にわたっておりますので、1回、2回される場合とか、あるいは肺炎球菌におきましては5年間接種できないということになっております。だから医療機関だけでやりますと、毎年あるいは2年か3年、忘れててまた打ちに行ったとか、いろんなことがございますので、そういったトラブルあるいは体にかかわることでございますので、来てうちの方で申請されたかどうかということをきちっと確認をする必要があるので、大変不便な面もあろうかと思いますけれども、その辺のところを確認した上で実施すると。やる以上は市の方が責任がございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。」と答弁をしていました。ところが、現在、事業実施にあたり説明に来た段階では、事前申請はなし、窓口で市の補助金額を引いた支払いで済むことになっています。3月議会の答弁と全く食い違っています。市民の利便性が向上したことですので評価しますが、議会答弁と実施方法が全く異なることについては理解することができません。やる以上は市の責任があるとまでいっていた事前申請がなぜなくなったのか、経過を踏まえてお答えください。
最初に国民健康保険料についてです。08年度の毎日新聞の全国調査で寝屋川市の保険料が4人家族のモデルケースで一番高いと報道されました。09年度は報道を受けてか保険料が下がったことを実感できるように引下げをするということで、一定の減額が行われましたが、依然モデルケースでは所得に対して20%を超える高い保険料となっています。
そして、10年度の保険料について、市長は3月議会で「国民健康保険料についてですが、保険料算出の基本となる賦課総額の求め方は、国の通知により定められておるところでございます。計算式に用いる予定収納率は実行可能な収納率を設定すると示されております。しかしながら、保険料の決定には被保険者の理解が得られることが重要と考えておりますので、予定収納率の見直し、条例減免の在り方等検討する中で、持続的に安定した保険運営が維持できる保険料を算定してまいりたいと考えております。」と答弁をされています。そこで伺いますが、今回の保険料率を算出するにあたって被保険者の理解が得られることが重要と述べておられますが、実際にどの程度の保険料なら市民の理解を得ることができると考えているのか、また、その根拠はどこにあるのかお答えください。あわせて予定収納率についても言及されていますが、昨年今年と予定収納率は85%で計算されているのではないでしょうか。ここに市長としての考えがどのように反映されたのか合わせてお答えください。市民の方とお話をしていて感じるのは、国民健康保険料については、支払いたいと思っている市民がたいへん多いということです。しかしその一方で、支払うことができない高額な保険料によって生活自体がきびしくなっている実態があることです。ある、高齢のご婦人は、よく病院を利用しているので保険料は支払うことは当然だと思っている。しかし、年金に対して保険料が重すぎる。介護保険と合わせて天引きされると、夕食を抜くなどの節約をすることが多くなると訴えておられました。市民は高すぎる保険料を負担し続けているのです。
10年度の保険料が決定され市民へ納付書が送付されています。昨年度に比べわずかに保険料が下げられていますが、重い負担であることに変わりがありません。更なる保険料の引き下げに一般会計よりの繰り入れを行うことを求めます。09年度の決算見込みが出ていますが、国民健康保険特別会計において単年度で約5億円の黒字が計上されています。累積赤字解消のための収支改善3億円も一定理解できますが、黒字分は保険料を引下げるための財源として考えることも必要ではないでしょうか。答弁を求めます。
続いて保険料の減免についてです。国も失業者に対する保険料の減免について通達を出しています。寝屋川市として通達にそって条例減免の中でさらに減免額を大きくするような特別な措置を取るように求めます。また、国は、減免に対する交付税措置を取るとされていますが、寝屋川市は減免をしても全国平均保険料より高いために、交付税措置の対象外となっています。ここでも、保険料が高すぎることが問題となっています。せめて減免をすることで、支払うことが可能な金額への減免が必要です。減免をしても高い実態の改善を求め答弁を求めます。
保険料の分納相談についてです。窓口で国保料の分納相談をした市民から、到底支払うことができない金額で約束をしてしまったと、相談を受けることがあります。相談に行く市民の方は少しでも払いたいという思いで窓口に行っています。そして、分納をお願いすることに後ろめたく思っているのです。そんな中で、窓口の職員がこの額でなら分納できると金額を示されると、実際には支払うことができなくても、あきらめて署名をしてしまうそうです。前年所得で計算される国保料は、現実の生活実態に合わない金額となることがあります。社会保障である国民健康保険の制度がその重たい保険料負担で生活を破壊している現実を直視して、少しでも払っていきたいと分納の相談に来ている市民に払うことが不可能な金額の提示はやめて下さい。窓口で市民に提示する金額はどのように検討をしたうえで出されていますか。生活実態をよく聞き市民が納得をし、支払うことができる金額の提示を求めます。
短期保険証・資格証明書についてです。7月より高校生以下の世代に6か月の短期保険証の交付を行うとされています。寝屋川市では4月末時点で、対象人数が資格証明書世帯73人、短期保険証世帯259名 合計332名となっています。これにより、寝屋川市内には、正規の健康保険証、6か月の短期保険証、3か月の短期保険証、資格証明書と国保加入者が4種類に分けられる状態となり、その上に無保険の人たちがいます。市民の中にも混乱を生むのではないでしょうか。国保は社会保障ですので、すべての加入者に正規の健康保険証を交付することを求めます。滞納対策と保険証の交付は分けて考えることが必要ではないでしょうか。
この間、新型インフルエンザを契機に資格証明書に係る様々な通達等も出されています。その中で、病院に診察に行く状態は、特別な状態にあたり資格証明書の発行対象とならない特別な状態と示されています。昨年度、資格証明書での受診が32件で約58万円の窓口負担が行われていますが、本来この方たちには資格証明書の発行はできないのではないですか。市内の医療機関に協力を求め、資格証明書での受診をなくすように行政としての努力を求め答弁を求めます。
市内の無保険状態の方の把握はどのようにされていますか。基本的に無保険となっている人が加入することになる保険は国保になると考えられます。市内の無保険者の把握と無保険での受診の実態も合わせてお答えください。
介護保険について
日本共産党国会議員団が介護保険制度見直しにむけたアンケート結果を6月9日公表しました。その中で介護事業所アンケートの結果と特徴では、「サービス利用を抑制している人がいる」が7割を超えています。また、「要介護認定について問題点がまだある」が8割を超えています。居宅介護サービスの充足状況では、「サービスが足りず我慢強いられている人がいる」が6割近くに上っています。介護現場の改善については、訪問介護事業所の7割が人手不足、この間行われた3%の介護報酬の引き上げは「ほとんど効果がない」が約7割となっています。このアンケート結果は全国的なものですが、このように問題となっていることは寝屋川市内の介護施設・利用者にも共通しています。
先日、寝屋川市内の介護施設のケアマネージャーにお話を伺いますと、ある高齢者の方が介護認定を受けられ、ケアプランを制作した。しかし、ケアプランを元にお話をしていると、このサービスはいくらかかる。このサービスはいくらかかると質問されていく中で、結局この方は、介護サービスの利用を取りやめたとききました。現実に保険料は取られているしかし、利用料が負担できなくて利用できない方が多くいるのではないでしょうか。寝屋川市には介護給付費準備基金が12億3千7百万円あります。これを利用して、介護が必要な方が必要な介護を経済的な心配をせずに受けることができるよう、利用料金の減免制度の創設を求めます。
また、障害者自立支援法については今年四月より住民税非課税世帯は原則無料となりました。ところが、65歳以上になりますと、障害者自立支援法から介護保険に移り一割負担になってしまいます。同様のサービスを受けながら64歳までは無料なのに65歳になると一割負担に変わるのは矛盾しています。介護保険における障害者の住民税非課税世帯の無料化は急務の課題です。国の施策を待つことなく市として無料化を行って下さい。
「遺影を拭(ふ)くのはダメ」「お供えの花を買いに行くのも『NO』」。大阪府寝屋川市が市内の訪問介護事業所に対し、こんな指導をしている。法令では明確に禁止されていない事項だが、市は「日常生活の援助には該当しない」としている。関係者からは「介護保険の利用を不当に制限している」と批判の声も上がっている。と5月7日毎日新聞で寝屋川市の介護保険サービスのローカルルールが報道されました。
寝屋川市では07年4月、過去に介護保険適用に関する問い合わせがあった事例を「Q&A」形式にまとめ、事業所に配布しています。事例によると、「保険利用者が眼鏡を調整するため、一緒に店に行ってもよいか」との質問に「眼鏡は日常生活に必要だが、眼鏡の調整は日常生活には含まれず不可」。扇風機やストーブの出し入れ、衣替えに伴う押し入れやたんすの衣服入れ替えも「大がかりな非日常行為で保険算定できない。有償ボランティアなどを利用するように」と指導しています。この間、市議会の中でも取り上げてきましたが、寝屋川市は過去に出したQ&Aや連絡文章は変わっていないという立場をとっています。そんな中いくら現場で必要な介護が受けられるよう指導をしていると言っても文章化され公にされない限り多くの介護保険利用者、介護施設が対応に戸惑うのではないでしょうか。この間、大阪社会保障推進協議会が北河内7市の介護事業やケアマネ・ヘルパーに介護保険に関するアンケートをしていますが、寝屋川市内のケアマネージャーから、同居家族がいることで制限を受けたことがあるや散歩や外出が介護保険で認められなかったなど、大阪府の改定されたQ&Aでは認められていることが市内では制限されているとアンケートにはしるされています。寝屋川市では、国の介護保険の法律で定められていること以上に現場では介護サービスが制限されているのか、また、大阪府のQ&Aについてどのように介護事業所、ケアマネジャーに伝えているのかを明らかにして下さい。また、この間、寝屋川市は新たなQ&AをつくりHPに掲載をすると言ってきましたが未だ掲載されていません。早急に市民に明らかにするように求めます。
介護保険料の引き下げについてです。藤井寺市では3年計画の途中であったけれども、介護給付費準備基金の取り崩しで保険料の引き下げを行いました。このことで寝屋川市の介護保険料準備給付基金の取り崩しの割合は大阪府で一番低い自治体となったのではないでしょうか。基金はすべて被保険者の納めた保険料です。早急に基金を取り崩し保険料の引き下げを求めます。寝屋川市内の高齢者からは寝屋川市は泥棒か、取りすぎた保険料ぐらいすぐに返してほしい。2年も3年も先のこと言われても今生活がしんどい。来年なんて生きてるか分からないと。声も上がっています。基金を使って保険料の引き下げ、利用料・保険料の市独自の減免制度の創設を求めます。
子育て支援についてです。
日本共産党は4月30日に「待機児童問題を解決し、安心して預けられる保育を実現するために」と緊急提言を行いました。
「夫はリストラで失業、働きたいのに入れない」「育休あけまでに保育所がみつからないと仕事を失う」。保育団体の電話相談「保育所ホットライン」には深刻な訴えが全国から寄せられました。やむなく幼い子どもに乳児をゆだね、不安のなかで働く父母もいます。いま全国で認可保育所に入所を希望し、実際に入所の手続きをしながら待機している子どもだけでも5万人近くおり、潜在的には100万人ともいわれています。
また、やっとの思いで入った保育所でも、定員を超えた詰め込みで保育のゆとりと安全が脅かされています。「廊下でお昼寝」「全員で食事を取るスペースもない」という環境で、子どもがストレスをためているようなところもあります。
保育士の過重負担も深刻で、5人に1人は身体の不調を訴えています。「1人でも多くの子どもに保育を保障したい」「子育てに悩む若い父母の力になりたい」という保育関係者の努力はもう限界です。
こうした深刻な事態は、自公政権が「規制緩和」「民間委託」「民営化」をかかげ、必要な保育所をつくらず、定員をこえた詰め込みや認可外の保育施設を待機児童の受け皿にした安上がりの「待機児童対策」の破たんを示すものです。民主党政権は、この路線の転換をはかるのではなく、すでに自公政権で破たんした保育分野の「規制緩和」の流れをいっそうすすめようとしています。これでは国民の願いにこたえることはできません。いま必要なのは、「規制緩和」路線を根本的に転換し、国と自治体の責任で認可保育所の本格的な増設をすすめることです。
保育所がないために、子育て中の若い世代が就職できない、仕事を失い生活苦におちいるなどという事態は、政治の責任で一刻も早く解決しなければなりません。
待機児童の85%は3歳未満の乳幼児です。とりわけ産休あけ、育児休業あけのゼロ歳児、1歳児の入所希望が切実です。そもそも、保育所運営費の基準が低いうえに、自公政権がゼロ歳児保育のための補助金の減額・廃止をしたことは、低年齢児の受け入れ枠の拡大や、年度途中からの受け入れのために保育士を確保しておくことを困難にしてきました。運営費の増額と補助金の復活・拡充などをはかり、保育士の配置などを手厚くし、産休あけ、育休あけから安心して預けられるようにしていく必要があります。
そこで伺いますが、5月1日現在で寝屋川市内の保育園では多くが定員を超えて子どもたちが入所をしています。今後さらに保育需要も伸びることを考えると、待機児童が今後市内に増えていくことが容易に予想できます。市として新たな認可保育所をつくることが必要ではないでしょうか。この間、認可保育園の新設を考えているかのような答弁もありました。具体的な今後の予定をお答えください。
また、無認可保育所への支援制度を作ることが必要です。
無認可保育所は、低年齢児を中心に23万人もの子どもを全国で受け入れています。しかし国の支援がいっさいないため、保育料の父母負担が重く、財政的にも困難ななかで保育士らの献身的努力で保育を支えているのが実態です。寝屋川市内でも無認可の共同保育所が待機児を長年受け入れてきた実態があります。そして、現在でもその役割を果たしていることは明らかです。市として補助を復活するように求めます。
民主党政権はこの4月、自公政権がすすめてきた保育所定員の「規制緩和」をさらにすすめ、年度当初は定員の115%、年度途中は125%などと、これまで受け入れの上限として残されていた基準さえすべて取り払ってしまいました。また、今年から給食を外部施設から搬入できるようにすることも決めました。そのうえ民主党政権が今国会に提出した「地域主権改革」一括法案では、国の保育所最低基準そのものをなくし、都道府県の条例に委任するとしています。避難用すべり台の設置義務がなくなるなど、子どもの命にかかわる規制まで緩和され、東京や待機児童を抱える自治体では、子ども1人あたりの面積の基準を引き下げられるようにしています。
こうした「規制緩和」による待機児童対策では、待機児童解消ができないばかりか、子どもたちの健康と安全をおびやかし、保育所の保育環境と保育士の労働条件を大きく悪化させ、安心して預けられる保育への父母の信頼を失わせてしまうものです。
「規制緩和」の流れをストップさせ、定員超過の解消にただちにとりくむとともに、子どものゆたかな発達を保障する保育条件や保育士の労働条件の改善こそ必要ではありませんか。そして、地域の基準となる公立保育所の役割はますます大切になっています。国に対して制度の改善を求め、市としての市内の保育水準の維持向上のために独自の加算を求めます。
次に中学校給食についてです。全国的には80%を超える実施率ですが大阪では約8%と低い実施率となっています。しかし、北河内内を見ますと、門真市、交野市、四条畷市において中学校給食が実施されています。子どもの貧困が社会問題となっている中、中学校における完全給食は、子どもたちの成長にとって今改めて有益な事業として見直されているのではないでしょうか。寝屋川市はブランド戦略を打ち出していますが、かつての寝屋川市のように子育てするなら寝屋川市と、市民の住みやすさこそが寝屋川市のブランドとなるのではないでしようか。ぜひ、中学校給食の実施に向けて検討を始めるよう求め答弁を求めます。
こども医療費の無料化の拡大についてです。
現在、寝屋川市は外来、入院ともに小学校入学前まで所得制限付きながら行っています。中学校卒業までを対象にした都道府県が増えている中、更なる子ども医療費無料化の対象年齢引き上げを所得制限なしで行うよう求めます。
妊産婦健診の無料化について
今年四月より初回のみ7500円と前年より5000円の補助金アップで総額40000円です。全国平均の約85000円には全然足りません。実際には総額で約11万円かかります。飛び込み出産などが社会問題となる中で、妊産婦健診の無料化が求められています。寝屋川市は府下でも早くに健診回数を増やしてきました。しかし、国の措置が取られてからは府下平均並みで全国平均より大きく遅れています。現実の問題として、いくら補助金が出ると言っても、窓口でいくら支払うのか分からない、妊産婦健診の負担は重いものがあります。安心して受けるためには窓口負担ゼロ無料化が必要です。安心して子育てできる寝屋川市へ妊産婦健診の無料化へ市の施策を進めて下さい。
今回、北河内夜間救急センターが廃止されるにあたり多くの市民と話をしましたが、#8000の認知度はかなり低い物がありました。せっかくの施策を市民が知らないために利用できていないことが多くあるのではないでしょうか。 こんにちは赤ちゃん事業から就学援助、高校の奨学金まで、子どもに関する様々な施策の情報を、必要とする市民に知らせるためのパンフレットの作成や、ホームページの改善に力を尽くして下さい。市として知らなくて使えなかったという市民を出さないための努力を改めて求めます。
その他
市内の銭湯について質問します。
昨年4月に下水道料金の値上げの後、高柳2丁目にあった「高柳温泉」平池町にあった「大和温泉」が廃業しました。特に大和温泉については、地域に残されているお風呂のないアパートの住民から大きな苦情も寄せられています。
中央老人福祉センターには無料で開放されたお風呂がありますが、平池からは遠くて利用することが困難です。今、地域の銭湯は廃業が進んでいます。寝屋川市の市営住宅にはお風呂がなく、地域の銭湯には税金も投入され運営されています。銭湯がなくなった地域に住んでいる人たちが、中央老人福祉センターに行こうとしても足がなくて厳しい状況があります。シャトルバスの運行など、検討して下さい。
また、地域に残された銭湯は地域社会を形成する大きな役割を担っています。地域の社交場でもある銭湯の維持は大変重要です。下水道料金値上げの際にも申し上げましたが、現在残っている銭湯の維持に市の援助が必要ではないでしょうか。上下水道料金の減免などの対応を求めます。
災害時の公共住宅への入居について
寝屋川市では火災などが起きた場合に市営住宅や、府営住宅への緊急の入居の紹介を行っていますが、現実には3カ月と期限を切った入居により多くの被災者が利用をしていません。しかし公営住宅の入居について緊急に入居をした方でも、入居基準を満たしていればそのまま住み続けることができるというのが現在の公営住宅法の趣旨に沿った対応ではないでしょうか。過去の被災者の公営住宅の入居とその後の居住実態について明らかにして下さい。今後、被災者には入居基準を満たしている方については住み続けることができることとし説明をして下さい。答弁を求めます。
また現在、寝屋川市内の公営住宅の空いている件数と災害時の緊急避難で入居することができる件数を明らかにして下さい。
議会での答弁と現実に行われる施策の違いについて
3月の厚生常任委員会で、ヒブワクチンやインフルエンザ、肺炎球菌の予防接種の予算が審議されるにあたり、私は、市民の利便性を考え、窓口で減額された金額を払えば済むようにしてほしいと要望をしました。しかし、市は「事前に来ていただくということは可能と考えております。医療機関から直接請求するということであれば、医療機関は多岐にわたっておりますので、1回、2回される場合とか、あるいは肺炎球菌におきましては5年間接種できないということになっております。だから医療機関だけでやりますと、毎年あるいは2年か3年、忘れててまた打ちに行ったとか、いろんなことがございますので、そういったトラブルあるいは体にかかわることでございますので、来てうちの方で申請されたかどうかということをきちっと確認をする必要があるので、大変不便な面もあろうかと思いますけれども、その辺のところを確認した上で実施すると。やる以上は市の方が責任がございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。」と答弁をしていました。ところが、現在、事業実施にあたり説明に来た段階では、事前申請はなし、窓口で市の補助金額を引いた支払いで済むことになっています。3月議会の答弁と全く食い違っています。市民の利便性が向上したことですので評価しますが、議会答弁と実施方法が全く異なることについては理解することができません。やる以上は市の責任があるとまでいっていた事前申請がなぜなくなったのか、経過を踏まえてお答えください。
12月議会 田中市議 一般質問
2009-12-22
まず、子ども手当てについてです。
総選挙の時に、「やらない」といっていた住民税の扶養控除まで廃止し、子ども手当ての財源として政府は、所得税・住民税の16歳以下の「扶養控除を廃止」する方針です。
総務省は4日の政府税調全体会で、「住民税・所得税の扶養控除を見直した場合の他制度への影響」とする資料を提出しましたが、保育料をはじめ、私立幼稚園就園奨励費用補助や国民健康保険料、後期高齢者医療制度の自己負担など23項目が扶養控除の廃止により国民の負担が増えることとされています。
子育て世帯にも負担増となり、新たに住民税課税世帯になった世帯は、医療費の自己負担限度額や介護保険料など雪だるま式で負担増になります。子ども手当ての効果も縮小されます。
● 子ども手当ての実施とともに、子どもたちが安心して保育所や幼稚園、学校や学童保育に通えるため、国として総合的な施策の拡充がもとめられます。 また、子ども手当の財源は、国の責任でまかなうよう市はもとめるべきです。見解をお聞きします。
次に保育所についてです。
鳩山内閣は保育所待機児解消は、東京都など都市部の一部で最低基準を緩和する方向で自治体にゆだねることを明らかにしました。
厚生労働省が委託調査研究「機能面に着目した保育所の環境・空間に係わる研究事業」の報告書によりますと、0歳児1人あたりの保育室の面積基準は、日本の3.3㎡にたいし、フランスのパリは5.5㎡、スウェーデンのストックホルムは7.5㎡、園庭の一人あたり最低面積は、日本は、3.3㎡ですが、パリでは6.67㎡、ドイツのザクセン州は、10㎡です。ザクセン州の保育室の面積基準は、日本と同程度ですが、保育室とは別にお昼寝の部屋や食堂があり、工作室や、子どもが少し休める部屋などもあります。日本では、食事も昼寝も遊びもふくめた面積です。
子どもにどんな環境を保障するのかという具体的な議論がもとめられます。報告書では、「少なくても、現行の最低基準以上のものとなるよう取り組みをすすめることが重要」と提言したにもかかわらず、逆行する方針を出してきた厚労省に「児童福祉の理念を崩壊させる」と全国社会福祉協議会をはじめ関係団体、関係者から厳しい批判の声が上がっています。
厚生労働省は04年4月から09年11月までの間に保育施設で起きた死亡事故の件数と特徴などをまとめ、発表しました。認可保育所での事故は19件で具体的には、「廊下に置いてあった本棚の中で熱中症で死亡」「園庭で育てていたプチトマトを食べ、窒息死」「園舎屋根からの落雪により死亡」などです。認可外保育施設での事故は、30件で、園内28件、園外2件で、具体的には、「浴室で溺死」「園外保育中の交通事故で死亡」「午睡中の死亡」などです。死亡児の年齢は、認可は0歳児、1歳児、2歳児が各4人で21.1%と一番多く、認可外では0歳児が19人、57.6%で最多となっています。
遺族などでつくる「赤ちゃんの急死を考える会」が1962年以降に発生した死亡事故240件を分析されていますが、認可外施設での事故が全体の約85%と多いものの、認可保育所でも2000年度までの40年間に15件だった死亡事故が、01年度以降の8年間では、22件と大幅に増えていることがわかりました。
01年度は小泉内閣により認可保育所への定員以上の詰め込みや保育士の非常勤化が推奨された年です。01年度以降、認可保育所での死亡事故が急増しており、「赤ちゃんの急死を考える会」がそのことに警鐘を鳴らし、政府に調査をもとめています。
保育所での事故の裁判に関わる弁護士は「最低基準を都道府県に委ねれば、低い方向に流れる可能性が大きいことは現実が示している。国が投げ捨ててはならない」と語っています。
保育所の最低基準の引き下げなどの規制緩和は、子どもを事故の危険にさらすものであり、撤回すべきです。
● 政府に最低基準、子どもひとりあたりの保育室や園庭などの面積の緩和をしないよう、市は、もとめるべきです。見解をお聞きします。
先日、香里園地域の方から「10ヶ月の子どもを保育所に預けたいが今すぐは入所できず、来年の4月からも無理だと言われた。何とか預けて働きたい」と相談がありました。こども室に問い合わせしますと、「ひまわり、さざんか、なでしこ保育所ともに育休明けの申込みが多くある。4月からの育休明けの人は、入所点数が高い。4月0歳児の持ち上がりがある中で1歳児が新しく入所できる枠は5人だが、8人の育児休業明けの子どもの申し込みがあるので、入所は難しい状況だ」と説明がありました。
11月1日現在、公・私立保育所待機児・つまり働きながら待っているのは、32人です。申込み児は、育児休業明けも含まれますが、1,012人にのぼり、9月1日から166人も増えている状況です。
● 待機児解消は、事故につながる詰め込みでなく、子どもに目配りできる認可保育所の新設や分園などを実施すべきと考えます。特に香里園駅周辺地域での早急な保育所設置をもとめます。見解をお聞きします。
共同保育所についてです。
● 30数年間、寝屋川市の子ども達の成長発達をとがんばり産休明け保育を行っている共同保育所への市補助金の復活をもとめ、見解をお聞きします。
病児保育についてです。
09年6月9日に「保育対策等促進事業の国庫補助について」、厚生労働事務次官から通知が出されました。
病児・病後児保育事業では、病児対応型・低所得者減免分加算として生活保護法被世帯、市町村民税非課税世帯の利用料減免分加算がうたわれています。 寝屋川市では生活保護世帯と市民税非課税世帯ともに、現行1日2000円の利用料全額を支払っています。
生活保護受給者は、申請すれば無料になっていますが、市民税非課税の保護者は半額になっていません。負担は、厳しいものです。
● 国の市町村民税非課税世帯加算がある中で、市民税非課税世帯の利用料減免を実施すべきと考えます。見解をお聞きします。
次に子育て支援センターについてです。
香里園地域でマンションに住む、現在11ヶ月の子どもさんがいる母親から相談がありました。一人で子育てしていますが、精神的に落ち込み通院しておられます。
香里園地域では、マンションが林立し、子育て世帯も増加しています。安心してくらし、子育てできるための街づくりが重要です。香里園地域での子育て世帯の増加に見合った子育て支援センターがもとめられます。
● 香里園駅西側にもう1カ所子育て支援センターの設置をもとめます。見解をお聞きします。
次に留守家庭児童会(学童保育)についてです。
先日、2ヶ所の留守家庭児童会を訪問しました。夕方の5時すぎ~6時頃でしたのでお迎えで出入りが多いときでした。保護者の迎えがすでにあり、児童が半分ぐらいに減っているとはいえ、1つの学童保育では、40人強で部屋狭しと走りまわる子、パズルを数人で楽しんでいるグループ、おしゃべりをしているグループなど蜂の巣をつっついたようなにぎやかさです。伺った日には、インフルエンザ発症の子がでたとのことでした。せめて2部屋にしていれば、感染も少なくてすむのではと思いました。
来年度から厚生労働省は70人を超える大規模学童保育への補助金を打ち切るとし、08年にこれまで学童保育の基準を示してこなかった態度を改め、「放課後児童クラブガイドライン」を発表しました。しかし、その内容は、指導員の配置基準や資格、待遇などに触れていないなど不十分なものです。
国の方針を受けて、大阪府も従来の71人以上の学童保育の分離・分割に取り組む姿勢を見せています。
● 寝屋川市は国・府の動きがあるため、第5小の学童はプレハブ、中央小の学童では空き教室を利用して2部屋にするとのことですが、来年度と言わず早急に2ヶ所にすることをもとめます。見解をお聞きします。
安全で豊かな生活が保障される広さなどがもとめられます。現在の広さは、体調を崩した児童の場合、児童の保護者が迎えにくるまで1つの部屋で他の子ども達の足音が響き騒々しい中で床に寝ている状況です。
● せめて50人を超える1部屋のクラブについては、空き教室など使って2部屋にすべきと考えます。見解をお聞きします。
土曜開所についてです。保護者は、毎週土曜日も開所をもとめられています。国は補助金額に係わって、年250日以上の学童開所をもとめています。現在寝屋川市は250日開所するとし、今年度は、月曜日から金曜日を開所しても、8日不足するため、土・日曜日と年8日間のみ不定期に開所しています。
● 毎週土曜日の開所をもとめます。見解をお聞きします。
現在学童保育の入所については、3年生までとなっていますが、障害児については、居場所がなく、地域の学童が定数を超えれば「定数割れのある他校へ入ってください」と社会教育課から言われています。しかし、同じ地域の子ども達との関わりが大事です。また、親にとっても遠くまで自校から他校への送りと迎えは困難です。
● 障害児の居場所をなくすのでなく、3年生を超えて6年生まで入所できるようにすることをもとめます。見解をお聞きします。
任期付短時間勤務職員についてです。
インフルエンザが流行っている中で、第5小の学童保育では1人の職員指導員や2人のアルバイト指導員が感染し、1日同時に3人の指導員が休んだとのことですが、その間、代替え指導員が入らず、欠員のままであったとのことです。
● 障害児数の加配や子どもの人数を考慮し応援体制の拡充を求めます。見解をお聞きします。
ヒブワクチンについてです。
細菌性髄膜炎は、毎年全国で1000人以上の乳幼児がかかる病気でインフルエンザ菌b型が原因の場合3%から5%、肺炎球菌の場合10%から15%の死亡率です。生存した場合でも、後遺症が残る率は10%から20%です。初期の症状では、発熱、不機嫌、嘔吐、けいれんで他の風邪などの症状と似ていて重篤な状態となって始めてわかる怖い病気です。後遺症では、脳と神経に重大な損傷が生じ、水頭症、難聴、脳性まひ、精神遅延、けいれんなど引き起こします。
ヒブワクチンは、欧米では1990年代から接種されはじめましたが、日本では、2007年にフランス製のヒブワクチン(アクトヒブ)の輸入が承認され、2008年12月から供給されることになりました。世界保健機構(WHO)は1998年に世界中のすべての国々に対して、乳幼児へのヒブワクチン無料接種を推奨しています。
ヒブによる重症感染症は、ヒブワクチンでほぼ確実に防ぐことができます。市内の小児科に予約して2~3ヶ月待って接種できます。しかし、現在、任意接種ですので4回で約3万円の費用がかかります。 自治体での一部助成は、鹿児島、宮崎県栃木県大田原市、滋賀県長浜市、長野県阿智村、東京都・荒川、品川、中央、渋谷区などで行われています。
1.国に公費による定期的な予防接種化をもとめるべきです。見解をお聞きします。
2.国で制度化されるまで、市として接種公費負担をもとめます。見解をお聞きします。
次に介護保険についてお聞きします。
介護保険では、国は施設でなく在宅へと流れを変えようとしています。核家族の中で老老介護が増えています。12月議会補正予算で2800万円の補助金が計上されています。これが実施されると、来年8月開設予定で小規模特別養護老人ホーム定員29人1ヶ所、5月と9月開設予定でグループホーム定数18人が2ヶ所で、合計来年度待機者解消は65人となります。
今年11月1日現在、寝屋川市の特養待機者数は、重複なしで388人です。待機者解消にはほど遠い数です。また、11月1日現在で、1年以上待機されている人は237人に上っています。
また、介護付き有料老人ホームが、寝屋川市には、6カ所ありますが、最低月額11万8千円から最高26万2千5百円の費用負担となっています。この金額以外に諸費が最低2~3万円必要ですからとても、低所得者が利用できるものではありません。
● 低所得者も利用できる特養老人ホーム増設が求められます。国に介護施設建設費用負担額を増やすよう求めるべきと考えます。見解をお聞きします。
● また、市として待機者解消のため実態にあった計画に見直しへ具体的に介護施設増設をすすめるべきと考えますが、いかがですか。
● 小規模多機能施設においての宿泊についてです。生活保護受給者は保護費で利用料が支給されません。利用すれば、自己負担になります。宿泊が無料で利用できるように求めますが、いかがですか。
介護予防でも要介護と同様に事務量が多く、サービス量が少ない中で、調整が厳しい状況でケアプラン作成に時間がかかるとケアマネジャーからお聞きしました。
しかし、プラン作成の報酬が2分の1以下になっています。
● 国に対し、介護報酬の引き上げを行い、その報酬分を保険料に跳ね返らさない仕組みにすることを市はもとめるべきと考えますが、見解をお聞きします。
地域包括支援センターの委託料についてです。
今年度に入り、10月末現在で地域によって総合相談件数が少ないところで約150件、多いところで300件を超えています。
相談支援・権利擁護(虐待)など件数の多いところでは、職員数も増やさないと円滑に事業がすすまないので、実際に増員している地域包括支援センターがあります。
お隣の枚方市では、地域包括支援センターの職員数によって今年度の予算が決められています。3人では、1700万円、4人では、2100万円、5人で2500万円となっています。寝屋川市の地域包括支援センター1ヵ所の
委託料は一律約1700万円です。
● 寝屋川市においても相談件数など多いところには、円滑に運営ができるように人の増員に見合う委託料を増やすことをもとめます。見解をお聞きします。
総選挙の時に、「やらない」といっていた住民税の扶養控除まで廃止し、子ども手当ての財源として政府は、所得税・住民税の16歳以下の「扶養控除を廃止」する方針です。
総務省は4日の政府税調全体会で、「住民税・所得税の扶養控除を見直した場合の他制度への影響」とする資料を提出しましたが、保育料をはじめ、私立幼稚園就園奨励費用補助や国民健康保険料、後期高齢者医療制度の自己負担など23項目が扶養控除の廃止により国民の負担が増えることとされています。
子育て世帯にも負担増となり、新たに住民税課税世帯になった世帯は、医療費の自己負担限度額や介護保険料など雪だるま式で負担増になります。子ども手当ての効果も縮小されます。
● 子ども手当ての実施とともに、子どもたちが安心して保育所や幼稚園、学校や学童保育に通えるため、国として総合的な施策の拡充がもとめられます。 また、子ども手当の財源は、国の責任でまかなうよう市はもとめるべきです。見解をお聞きします。
次に保育所についてです。
鳩山内閣は保育所待機児解消は、東京都など都市部の一部で最低基準を緩和する方向で自治体にゆだねることを明らかにしました。
厚生労働省が委託調査研究「機能面に着目した保育所の環境・空間に係わる研究事業」の報告書によりますと、0歳児1人あたりの保育室の面積基準は、日本の3.3㎡にたいし、フランスのパリは5.5㎡、スウェーデンのストックホルムは7.5㎡、園庭の一人あたり最低面積は、日本は、3.3㎡ですが、パリでは6.67㎡、ドイツのザクセン州は、10㎡です。ザクセン州の保育室の面積基準は、日本と同程度ですが、保育室とは別にお昼寝の部屋や食堂があり、工作室や、子どもが少し休める部屋などもあります。日本では、食事も昼寝も遊びもふくめた面積です。
子どもにどんな環境を保障するのかという具体的な議論がもとめられます。報告書では、「少なくても、現行の最低基準以上のものとなるよう取り組みをすすめることが重要」と提言したにもかかわらず、逆行する方針を出してきた厚労省に「児童福祉の理念を崩壊させる」と全国社会福祉協議会をはじめ関係団体、関係者から厳しい批判の声が上がっています。
厚生労働省は04年4月から09年11月までの間に保育施設で起きた死亡事故の件数と特徴などをまとめ、発表しました。認可保育所での事故は19件で具体的には、「廊下に置いてあった本棚の中で熱中症で死亡」「園庭で育てていたプチトマトを食べ、窒息死」「園舎屋根からの落雪により死亡」などです。認可外保育施設での事故は、30件で、園内28件、園外2件で、具体的には、「浴室で溺死」「園外保育中の交通事故で死亡」「午睡中の死亡」などです。死亡児の年齢は、認可は0歳児、1歳児、2歳児が各4人で21.1%と一番多く、認可外では0歳児が19人、57.6%で最多となっています。
遺族などでつくる「赤ちゃんの急死を考える会」が1962年以降に発生した死亡事故240件を分析されていますが、認可外施設での事故が全体の約85%と多いものの、認可保育所でも2000年度までの40年間に15件だった死亡事故が、01年度以降の8年間では、22件と大幅に増えていることがわかりました。
01年度は小泉内閣により認可保育所への定員以上の詰め込みや保育士の非常勤化が推奨された年です。01年度以降、認可保育所での死亡事故が急増しており、「赤ちゃんの急死を考える会」がそのことに警鐘を鳴らし、政府に調査をもとめています。
保育所での事故の裁判に関わる弁護士は「最低基準を都道府県に委ねれば、低い方向に流れる可能性が大きいことは現実が示している。国が投げ捨ててはならない」と語っています。
保育所の最低基準の引き下げなどの規制緩和は、子どもを事故の危険にさらすものであり、撤回すべきです。
● 政府に最低基準、子どもひとりあたりの保育室や園庭などの面積の緩和をしないよう、市は、もとめるべきです。見解をお聞きします。
先日、香里園地域の方から「10ヶ月の子どもを保育所に預けたいが今すぐは入所できず、来年の4月からも無理だと言われた。何とか預けて働きたい」と相談がありました。こども室に問い合わせしますと、「ひまわり、さざんか、なでしこ保育所ともに育休明けの申込みが多くある。4月からの育休明けの人は、入所点数が高い。4月0歳児の持ち上がりがある中で1歳児が新しく入所できる枠は5人だが、8人の育児休業明けの子どもの申し込みがあるので、入所は難しい状況だ」と説明がありました。
11月1日現在、公・私立保育所待機児・つまり働きながら待っているのは、32人です。申込み児は、育児休業明けも含まれますが、1,012人にのぼり、9月1日から166人も増えている状況です。
● 待機児解消は、事故につながる詰め込みでなく、子どもに目配りできる認可保育所の新設や分園などを実施すべきと考えます。特に香里園駅周辺地域での早急な保育所設置をもとめます。見解をお聞きします。
共同保育所についてです。
● 30数年間、寝屋川市の子ども達の成長発達をとがんばり産休明け保育を行っている共同保育所への市補助金の復活をもとめ、見解をお聞きします。
病児保育についてです。
09年6月9日に「保育対策等促進事業の国庫補助について」、厚生労働事務次官から通知が出されました。
病児・病後児保育事業では、病児対応型・低所得者減免分加算として生活保護法被世帯、市町村民税非課税世帯の利用料減免分加算がうたわれています。 寝屋川市では生活保護世帯と市民税非課税世帯ともに、現行1日2000円の利用料全額を支払っています。
生活保護受給者は、申請すれば無料になっていますが、市民税非課税の保護者は半額になっていません。負担は、厳しいものです。
● 国の市町村民税非課税世帯加算がある中で、市民税非課税世帯の利用料減免を実施すべきと考えます。見解をお聞きします。
次に子育て支援センターについてです。
香里園地域でマンションに住む、現在11ヶ月の子どもさんがいる母親から相談がありました。一人で子育てしていますが、精神的に落ち込み通院しておられます。
香里園地域では、マンションが林立し、子育て世帯も増加しています。安心してくらし、子育てできるための街づくりが重要です。香里園地域での子育て世帯の増加に見合った子育て支援センターがもとめられます。
● 香里園駅西側にもう1カ所子育て支援センターの設置をもとめます。見解をお聞きします。
次に留守家庭児童会(学童保育)についてです。
先日、2ヶ所の留守家庭児童会を訪問しました。夕方の5時すぎ~6時頃でしたのでお迎えで出入りが多いときでした。保護者の迎えがすでにあり、児童が半分ぐらいに減っているとはいえ、1つの学童保育では、40人強で部屋狭しと走りまわる子、パズルを数人で楽しんでいるグループ、おしゃべりをしているグループなど蜂の巣をつっついたようなにぎやかさです。伺った日には、インフルエンザ発症の子がでたとのことでした。せめて2部屋にしていれば、感染も少なくてすむのではと思いました。
来年度から厚生労働省は70人を超える大規模学童保育への補助金を打ち切るとし、08年にこれまで学童保育の基準を示してこなかった態度を改め、「放課後児童クラブガイドライン」を発表しました。しかし、その内容は、指導員の配置基準や資格、待遇などに触れていないなど不十分なものです。
国の方針を受けて、大阪府も従来の71人以上の学童保育の分離・分割に取り組む姿勢を見せています。
● 寝屋川市は国・府の動きがあるため、第5小の学童はプレハブ、中央小の学童では空き教室を利用して2部屋にするとのことですが、来年度と言わず早急に2ヶ所にすることをもとめます。見解をお聞きします。
安全で豊かな生活が保障される広さなどがもとめられます。現在の広さは、体調を崩した児童の場合、児童の保護者が迎えにくるまで1つの部屋で他の子ども達の足音が響き騒々しい中で床に寝ている状況です。
● せめて50人を超える1部屋のクラブについては、空き教室など使って2部屋にすべきと考えます。見解をお聞きします。
土曜開所についてです。保護者は、毎週土曜日も開所をもとめられています。国は補助金額に係わって、年250日以上の学童開所をもとめています。現在寝屋川市は250日開所するとし、今年度は、月曜日から金曜日を開所しても、8日不足するため、土・日曜日と年8日間のみ不定期に開所しています。
● 毎週土曜日の開所をもとめます。見解をお聞きします。
現在学童保育の入所については、3年生までとなっていますが、障害児については、居場所がなく、地域の学童が定数を超えれば「定数割れのある他校へ入ってください」と社会教育課から言われています。しかし、同じ地域の子ども達との関わりが大事です。また、親にとっても遠くまで自校から他校への送りと迎えは困難です。
● 障害児の居場所をなくすのでなく、3年生を超えて6年生まで入所できるようにすることをもとめます。見解をお聞きします。
任期付短時間勤務職員についてです。
インフルエンザが流行っている中で、第5小の学童保育では1人の職員指導員や2人のアルバイト指導員が感染し、1日同時に3人の指導員が休んだとのことですが、その間、代替え指導員が入らず、欠員のままであったとのことです。
● 障害児数の加配や子どもの人数を考慮し応援体制の拡充を求めます。見解をお聞きします。
ヒブワクチンについてです。
細菌性髄膜炎は、毎年全国で1000人以上の乳幼児がかかる病気でインフルエンザ菌b型が原因の場合3%から5%、肺炎球菌の場合10%から15%の死亡率です。生存した場合でも、後遺症が残る率は10%から20%です。初期の症状では、発熱、不機嫌、嘔吐、けいれんで他の風邪などの症状と似ていて重篤な状態となって始めてわかる怖い病気です。後遺症では、脳と神経に重大な損傷が生じ、水頭症、難聴、脳性まひ、精神遅延、けいれんなど引き起こします。
ヒブワクチンは、欧米では1990年代から接種されはじめましたが、日本では、2007年にフランス製のヒブワクチン(アクトヒブ)の輸入が承認され、2008年12月から供給されることになりました。世界保健機構(WHO)は1998年に世界中のすべての国々に対して、乳幼児へのヒブワクチン無料接種を推奨しています。
ヒブによる重症感染症は、ヒブワクチンでほぼ確実に防ぐことができます。市内の小児科に予約して2~3ヶ月待って接種できます。しかし、現在、任意接種ですので4回で約3万円の費用がかかります。 自治体での一部助成は、鹿児島、宮崎県栃木県大田原市、滋賀県長浜市、長野県阿智村、東京都・荒川、品川、中央、渋谷区などで行われています。
1.国に公費による定期的な予防接種化をもとめるべきです。見解をお聞きします。
2.国で制度化されるまで、市として接種公費負担をもとめます。見解をお聞きします。
次に介護保険についてお聞きします。
介護保険では、国は施設でなく在宅へと流れを変えようとしています。核家族の中で老老介護が増えています。12月議会補正予算で2800万円の補助金が計上されています。これが実施されると、来年8月開設予定で小規模特別養護老人ホーム定員29人1ヶ所、5月と9月開設予定でグループホーム定数18人が2ヶ所で、合計来年度待機者解消は65人となります。
今年11月1日現在、寝屋川市の特養待機者数は、重複なしで388人です。待機者解消にはほど遠い数です。また、11月1日現在で、1年以上待機されている人は237人に上っています。
また、介護付き有料老人ホームが、寝屋川市には、6カ所ありますが、最低月額11万8千円から最高26万2千5百円の費用負担となっています。この金額以外に諸費が最低2~3万円必要ですからとても、低所得者が利用できるものではありません。
● 低所得者も利用できる特養老人ホーム増設が求められます。国に介護施設建設費用負担額を増やすよう求めるべきと考えます。見解をお聞きします。
● また、市として待機者解消のため実態にあった計画に見直しへ具体的に介護施設増設をすすめるべきと考えますが、いかがですか。
● 小規模多機能施設においての宿泊についてです。生活保護受給者は保護費で利用料が支給されません。利用すれば、自己負担になります。宿泊が無料で利用できるように求めますが、いかがですか。
介護予防でも要介護と同様に事務量が多く、サービス量が少ない中で、調整が厳しい状況でケアプラン作成に時間がかかるとケアマネジャーからお聞きしました。
しかし、プラン作成の報酬が2分の1以下になっています。
● 国に対し、介護報酬の引き上げを行い、その報酬分を保険料に跳ね返らさない仕組みにすることを市はもとめるべきと考えますが、見解をお聞きします。
地域包括支援センターの委託料についてです。
今年度に入り、10月末現在で地域によって総合相談件数が少ないところで約150件、多いところで300件を超えています。
相談支援・権利擁護(虐待)など件数の多いところでは、職員数も増やさないと円滑に事業がすすまないので、実際に増員している地域包括支援センターがあります。
お隣の枚方市では、地域包括支援センターの職員数によって今年度の予算が決められています。3人では、1700万円、4人では、2100万円、5人で2500万円となっています。寝屋川市の地域包括支援センター1ヵ所の
委託料は一律約1700万円です。
● 寝屋川市においても相談件数など多いところには、円滑に運営ができるように人の増員に見合う委託料を増やすことをもとめます。見解をお聞きします。