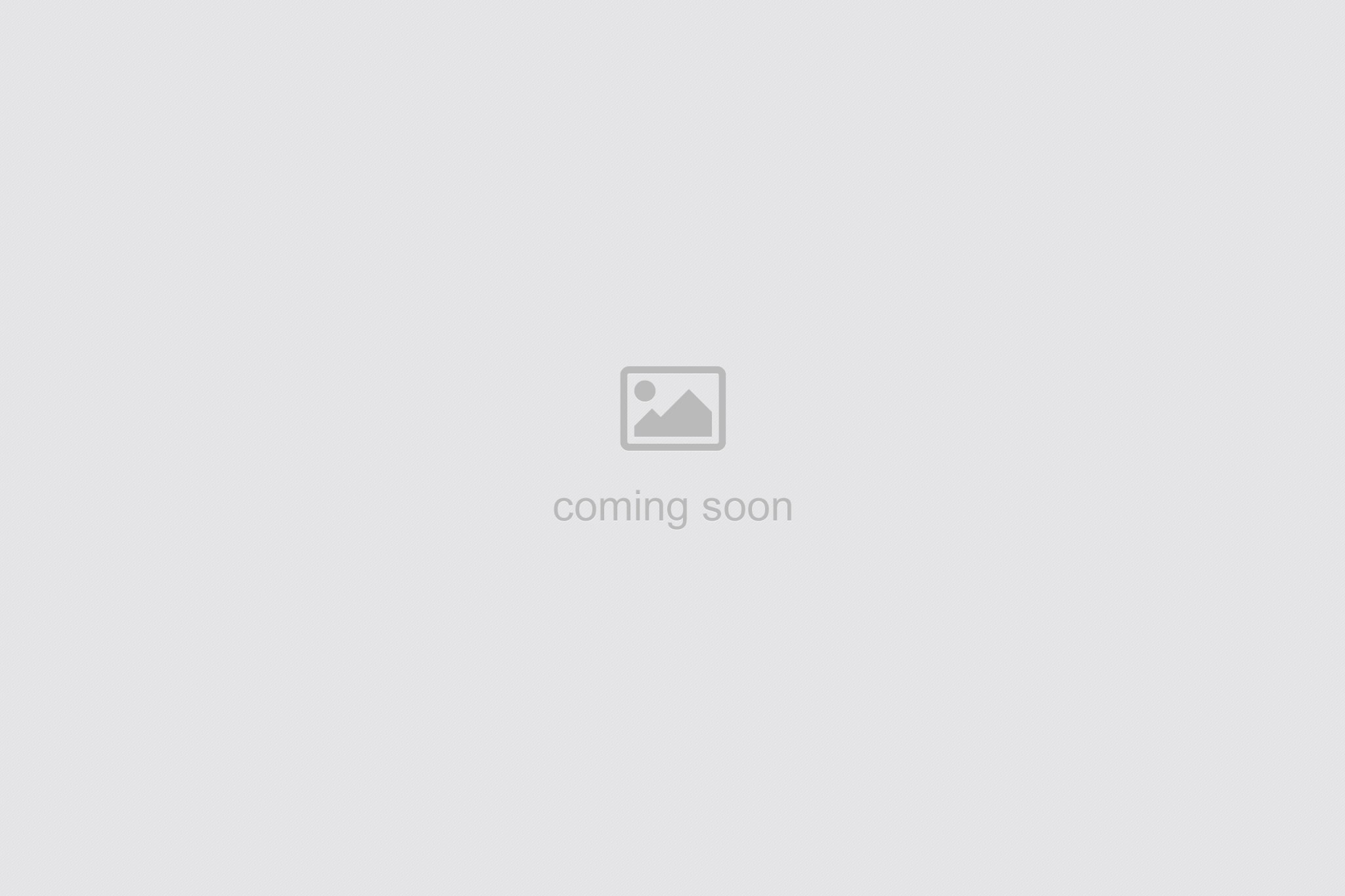2017年12月議会 一般質問 太田とおる
2017-09-15
〇 国民健康保険について
来年4月からの国保の都道府県単位化についてです。
9月議会後の10月25日に大阪府の2回目の国保料の仮算定結果が公表されました。
全国的には3回目の試算となり激変緩和措置を行った場合の保険料を試算することが目的として8月末までに国に報告をするとされていたもので約2ヶ月遅れとなっています。残念ながら大阪府では国の求める試算を一度行っていませんので今回で2回目の試算です。その上、国の求めていた激変緩和措置を施した場合の保険料率の計算は行われませんでした。
平成29年度の国保料をもとに大阪府下で保険料を統一した場合の平成29年度の国保料としての試算です。合わせて出てきた資料によると粗い試算と書いてはありますが、寝屋川市では加入者一人あたりの保険料は約1万円の引き下げと書かれています。そこで、示された保険料率で実際に計算をすると現行、寝屋川市では200万所得の4人家族で37万100円の保険料ですが、大阪府の仮算定では40万1900円となり3万1800円の引き上げとなっています。一人あたりの保険料が下がりながら実際には保険料が上がるというとんでもない資料です。一体何をもとに議論をすればいいのか非常に戸惑うところです。市として個別の資料など市民に公開できるものがあれば早急にお示しください。
12月に行われる、3回目の仮算定で初めて国から仮係数の提示を受けて平成30年度の保険料率の仮算定が行われる予定となっています。また、12月28日に国から確定係数が提示され、来年1月に平成30年度の保険料率の本算定が行われます。そこで、お聞きします。
2回目の試算において、均等割と平等割について現行の30:70が40:60に変更されています。寝屋川市は国保加入世帯の約6割が単身世帯であることを考えれば、より多くの世帯にとって保険料が上がったと考えます。30:70から40:60に変更されたことでの保険料の値上げ世帯と値下げ世帯のおおよその件数と影響額をお示しください。
また、均等割・平等割の割合については、寝屋川市においては国民健康保険条例で定められています。変更をする場合の手続きについて、国民健康保険運営協議会に諮問をして答申を受けて議会提案になると思いますが、確認をお願いします。
次に、今回の試算では、過去の保険料の滞納分が収入として試算に反映されています。国民健康保険会計は毎年の収支均衡が基本です。国民健康保険の制度改正で、国保の財政責任は最終的に都道府県が負うことになっています。
国保料の滞納分は、市町村が運営していた年度のお金です。そして、当然財政責任は自治体が負っていましたので、過去の保険料滞納分の納付保険料は個別の自治体の会計に入るものではないでしょうか。累積赤字が残っている自治体にとっては、保険料滞納分の納付は累積赤字の解消の財源となります。黒字で、基金を持っている自治体にとっても、国保料の引き下げなどの財源となります。
極端な話ですが来年度からの制度変更で、本来なら、大阪府は100%の収納率で保険料を計算し、府下自治体の納付金額を決定し、全額収めてもらえばいいわけです。そうすれば、過去の滞納など最初から保険料の計算に入らないわけです。また、100%の収納率で計算すれば保険料も安くなるし、収納率が100%にならない自治体にも、自治体の責任で大阪府に賦課された納付金を収める仕組みとすれば、府下市町村は収納率の向上、滞納保険料の回収、一般会計繰り入れなどいろいろに努力をするのではないでしょうか。
そんな中で、最初から、自らが運営していなかった年度の国保料まで当てにして保険料を決めることは問題があると考えます。市としての考えをお示しください。
次に国保料の応能割りと応益割りについてです。
寝屋川市では、応能、応益割合は50:50です。しかし、これが応益割り部分が増えれば低所得者の負担が増えていくことになります。今回の試算では50:50で行われたようですが、今後の見通しについて応能・応益が45:55になるのではないかと心配をされている声を聞いています。今後の見通しをお示しください。
次に標準収納率についてです。
今回の大阪府から提出された資料には収納率についての記載がありません。前回と同じ標準収納率での計算と言うことのようですが、寝屋川市は大阪府の言う標準収納率にいまだ到達をしていませんが、現行の収納率ではどれだけの財源不足が生じるのか試算をして明らかにしてください。最終的には大阪府から求められる収納率はどの程度になると見込んでいますか。寝屋川市の収納率それに対して十分との見込みでしょうか。お答えください。
次に、賦課限度額についてです。
寝屋川市の国保料においては後期高齢者支援金分と介護分の賦課限度額は政令で定める額とされています。しかし医療分については、過去に国民健康保険運営協議会に政令で定める金額との諮問もされましたが、医療分については金額も大きく、市民生活に与える影響が大きいとの判断でその都度、国民健康保険運営協議会にかけて判断することが望ましいとされ、政令で定める額とはしないことが決められています。
しかし、今回の制度改正で、大阪府は大阪府統一保険料を目指し、当然統一するためには、各市町村の賦課限度額も統一する方向で進められています。府の方針案では賦課限度額はすべて政令で定める額とされています。
市として今後、国保条例の改正を含め、医療分の賦課限度額について、どのように国民健康保険運営協議会に提案をしていこうとしているのか。今後のスケジュールなど市としての考えを明らかにしてください。また、年度途中で賦課限度額が変わった場合には保険料率の変更もありうることになるのか。大阪府の示している方向性と市の考え方をお示しください。
次に、年度途中の国保加入者の増減についてです。今ままでは、市町村単位で運営されていましたので、当初見込みより寝屋川市内の国保加入者が減っても増えても国保会計に大きな影響は出ませんでした。加入者が減れば収入も減るが給付も減る、加入者が増えれば収入も増えるが給付も増えたわけです。しかし、都道府県単位化された後の国保加入者の増減は、財政に穴があく可能性があります。大阪府は市町村に割り当てた納付金がはいってくれば問題ありません。しかし、年度途中に当初見込みを下回る国保加入者となった場合、寝屋川市が集める保険料が大阪府に収める納付額に届かない可能性が出てきます。そのような場合、その穴埋めはどの財源ですることになるのか。次年度に精算となるのか。当初見込みより加入者が増えれば当然納付額より多くの収入が見込めるが、その金額は国保会計にいれ活用できるのか。次年度の精算で納付するものになるのか。大阪国保へ統一後の国保会計のあり方について説明を求めます。市の見解をお示しください。
次に各市町村の納付金額について、10月25日に明らかにされた試算とその資料を見れば、寝屋川市で集めるべき保険料額が医療分で43億5918万8595円。支援金分14億4384万9935円。介護分5億5261万8010円で合計63億5565万6540円と掲載されています。寝屋川市の平成29年度の国民健康保険特別会計予算では国民健康保険料の合計金額は50億7095万1000円とされています。市民から集める保険料に大幅な差が出ています。市としてどのように認識していますか。市民には余りにも情報が少なく、来年度の国保料についてどのようになるのか不安が募っています。寝屋川市として来年度の国保料の設定について市民にわかるように説明をすること。また、情報公開を求めます。市としての考えをお示しください。
次に、各市町村の国民健康保険運営協議会は都道府県単位化された場合に位置づけが変わるのか。大阪府の運営方針を見ていると正直、各自治体の国民健康保険運営協議会に図ることなく勝手にいろいろなことが変更され決まっていく感じがしています。市町村の運営協議会の意向は尊重されるのか。市の考えをお示しください。
次に、減免制度についてです。今回示された資料には保険料の減免は後期高齢者医療制度などを参考にすると書かれていまが、そのようなことになると全く使えない制度となります。先日、大阪府後期高齢者医療広域連合議会があり決算審査が行われましたが、平成28年度、100万人を超える加入者がいる医療制度で、年間の保険料減免申請が約1200件で減免実績が約1100件、一部負担金減免は申請13件認定8件となっています。ほとんど利用できない制度と言って過言ではありません。制度利用者のほとんどが災害被災者とのことでした。
寝屋川市では保険料減免の利用世帯は少なくなったとはいえ約4万世帯加入の国保で数千単位での申し込みがあるわけです。6年間の激変緩和期間が設けられていても制度の後退は避けられないのではないかと多くの市民が心配するのも無理はありません。寝屋川市の考えをお示しください。
次に健診事業についてです。検診事業は唯一大阪府が各市町村個別に頑張れと自由にできる分野です。国保の枠組みだけで健診事業の推進をしても医療給付費など府下で統一されてしまえば、インセンティブも働かなくなり、特定検診事業の比重が低下してしまうのではないかと心配をしてしまいます。しかし、市民全体の健康の維持を考えて判断をする必要があると考えます。かつての市民検診のように市民全体を対象とした検診事業が必要と考えます。そこの中心的役割を果たす特定検診として充実を図っていく必要があると考えます。市民の健康の維持増進に向けて更なる健診事業の拡充が必要と考えます。市の考えをお示しください。
12月1日に大阪府のホームページに大阪府国民健康保険運営方針(素案)についてのパブリックコメントの結果と大阪府下市町村から寄せられた法定徴収意見が公表されました。そこでお聞きします。
パブリックコメントでは多くの府民が都道県単位化、保険料の統一に対して反対の意見を上げています。寝屋川市として市民府民の立場に立って、大阪府へ意見を行っていただくことが必要と考えます。寝屋川市として市民、府民の意見を把握しているか。見解を求めます。
次に、各市町村の法定徴収意見を見れば、寝屋川市は基本方向に賛意を示していますが、そのような自治体はほぼ見られません。
岸和田市からは「この意見聴取は法定のものであり、我々市町村が意見を表明するための重要な機会であると認識している。広域化に向けての作業がかなり遅れ気味の中で、この意見もこの時期に、しかも、前述のような重要な機会であるにもかかわらず、短い時間で意見を提出しなければならない。やむを得ない事情もあることはわからないことはないが、この状況を見ると、大阪府としてはこの意見聴取を形式的なものという認識しかないのではないかという見方もでき、共同保険者としての今後の信頼関係に懸念を覚える」という意見がだされるなど、大阪府下の各自治体が大阪府の方針に対して一枚岩で「統一賛成」「方針賛成」としているとは到底思えない状況です。
市として、大阪府下の他自治体の動向をどのように掴まれていますか。お示しください。
来年4月に迫った国保の都道府県単位化において、寝屋川市民にとってより良い選択を重ねて求めておきます。
〇 介護保険について
第7期介護保険計画(平成30年から32年度)が高齢者福祉計画審議会で審議されています。高齢化に伴う、介護認定者の増加と介護施設の整備で介護保険給付は伸びています。国・府・市の公費負担が増えない限り高齢者の保険料負担はどんどんと重たくなるばかりです。
次期計画における介護保険料の負担抑制に向けての努力を求めます。その上で、高齢者の生活を支える制度の創設が必要です。現行の境界層減免だけでなく、市独自の保険料・利用料減免の創設が必要です。特に保険料減免はすでに大阪府下では7割を超える自治体で実施されています。是非とも早急な制度の創設を求めます。特に保険料については、消費税10%の際には7割軽減、基準額の0.3の設定とすることが決められています。国も現行の介護保険料負担は重たいということを認めているのではないでしょうか。保険料の段階設定において保険料の最低基準の1段階を現行の0.45から0.3に、前倒しで変更することは厳しいとは思いますが、是非とも検討をお願いしたいと思います。市の見解を求めます。そして、本当に生活が苦しくなった市民を救うことが出来る施策として使いやすい保険料・利用料の減免制度の創設を求めます。市の見解をお示しください。
次に総合事業についてです。寝屋川市で総合事業が始まって、要支援1・2が介護保険給付から外されてまもなく1年が経とうとしています。
厚生労働省は、介護保険からの卒業を目指す自治体を大きく評価しているようですが、三重県桑名市やお隣大東市などでは、卒業という名の介護保険からの追い出しで高齢者の生活が脅かされ、要支援から要介護に急速へ悪化されていく状況などが報告もされています。
また、介護認定についても、チェックリスト優先で介護認定を受けることができない事例なども報告されている中で、寝屋川市では介護認定を基本とする運営がなされていることは、高く評価します。
寝屋川市では、身体介護を含むケアプランでは現行相当サービスの利用ができるとされています。しかし、事業所からは、地域包括によって基準に差が出ている。なかなか現行相当サービスが認められないなどの話も聞いています。身体介護を含む場合は現行相当サービスの利用が可能だということを再度確認しておきます。市の答弁を求めます。
4月からの介護認定で要支援となった人が受けている介護サービスを現行相当・緩和型・短期集中などの利用割合と人数をお示しください。
市として高齢者の生活を守る立場で総合事業、介護保険事業に取り組むことを改めて求めておきます。
次に介護認定の出なかった人が利用するチェックリストですが、チェックリストを利用しての、総合支援事業でのボランティアサービス・有償活動員の利用者は、現在どれだけいますか。利用実態も合わせてお答えください。今年度より有償活動員を派遣する団体に対する補助事業が始まりましたが、現時点でどれだけの団体が補助を受けることができる見込みか。補助の基準が高すぎると考えるが、年度途中での見直しは可能か。市の見解をお聞きします。
来年度からの第七期介護保険計画において、国の制度改定もあり、多くの高齢者、介護保険利用者、事業所から負担の増大や事業所の運営など不安の声を聞いています。保険料の抑制と介護保険給付の充実、そして介護事業所の経営を守ることは相反する非常に難しい課題であることは理解しますが、市としての最大限の努力を求めます。介護保険事業全体に対する市の見解をお示しください。
〇 学童保育について
寝屋川市は来年度の学童保育において土曜開所を進めると9月議会で答弁しました。その後、教育委員会は市内学童で保護者アンケートも取られています。そこでお聞きします。
来年度の土曜開所を保護者は首を長くして待ち望んでいます。例年、年度初めには土曜開所日の日程表が配布されています。仕事の予定を立てるにも必要となります。9月議会の答弁では1学期中には土曜開所を初めて行きたいとの答弁でした。現在の進捗状況と土曜開所の時期の見込みをお示しください。
次に土曜開所にあたっては、全小学校区の学童保育所の開所を求めます。土曜日だけ他の小学校の学童保育に通うことは、環境の変化に弱い子どもたちにとって、特に障害を持った子どもたちに負担を与えることになってしまうのではないかと考えます。
また、週に一度、他の学童から普段の状況を知らない子どもたちが来ることは、指導員の先生方にも大きな負担となるのでないでしょうか。
普段の生活を知っている指導員の配置をしても、指導員同士の情報共有の時間など取ることは保証されるのでしょうか。指導員の先生方がローテーションで入るにしてもその情報共有は大変な量となるのではないかと考えます。そして、各小学校によって土曜参観や日曜参観などの日程も違います。各小学校全てで開所する方が、結局は負担が少なくよりスムーズな運営になるものと考えます。市の見解をお示しください。
次に、土曜開所に当たっての保育料についてです。認可保育所では土曜日に子どもをあずけても当然月額の保育料は変わりません。同じ。子ども子育て支援法で行われている事業です。そして今まで、年間10日前後開所されていた土曜保育は新たな料金徴収は行われていません。保護者から集めるアンケートには料金設定に対する問もありました。保護者は新たな料金が発生するのではないかと心配もしています。寝屋川市の土曜開所に当たっての保育料の考え方をお示しください。
指導員の待遇改善についてです。この間少しずつ待遇改善が行われてきました。しかし、残念ながら北河内の中でもいい方とは言えません。今議会では保育士の待遇改善が行われましたが、指導員の待遇改善についても、せめて他市並に待遇改善が求められます。そんな中で指導員の欠員解消にもつながると考えます。市の見解を求めます。
〇 小中学校の改修について
寝屋川市は小中学校の改修は、耐震化をまず優先すべきと大規模改修の年次計画もなくなった状態となっています。しかし、現在、小中学校の校舎棟、体育館の被構造部材をはじめ耐震改修は完了しました。現在は公共施設等整備計画に基づき改修を進めるとされていますが、市内小中学校の経年劣化は目を覆わんばかりの状態となっています。
この間、トイレの洋式化や普通教室のエアコン設置などが進んできたことは評価します。今後は、全小中学校の大規模改修工事の年次計画を教育委員会で立てること。全校でバリアフリーを更にすすめ、肢体不自由児の利用するエレバーター設置を求めます。市の見解を求めます。
次にそれとは別に早急な対策が必要な修繕、開かない鉄枠窓など簡易な修繕にも取り組んでいただきたいと思いますが、現在の状況を教育委員会としてどのように認識しているのか。解決をどのように図るのかお示しください。
〇 その他として2点
一つ目は無戸籍児対策についてです。
法務省では、2015年7月から無戸籍者の調査を開始し、現在の日本における無戸籍者は686人、うち成人132人と2016年2月10日現在と発表しています。しかし、法務省の調査に回答した自治体はおよそ1割にとどまっています。実態は1万人を超えると想定されています。
無戸籍児は、いわゆる離婚後300日問題や、DVで逃げていて出生届を出さないなど様々な形で生まれています。今尚、毎年500名は無戸籍児が増えていると言われています。
無国籍の場合、原則として住民票・パスポートの取得ができません。当然マイナンバーもありません。そんな中で様々な不利益を受けることが想定されます。
そこでお聞きします。寝屋川市内の無戸籍の人の把握はしているのか。寝屋川市として、法務省の調査には協力をし、回答をしたのか。寝屋川市の行政サービスについて何らかの不利益を受けることはあるのか。
今様々な通達などが出され、住民票の取得や、戸籍の取得などに道が開かれつつあります。自治体として、証明書の発行など住民として不利益を受けることがないような施策の構築が必要と考えますが、市としての考えをお示しください。
2つ目に寝屋川で起きた死体遺棄事件についてです。
新聞報道では、大阪府警は11月21日、大阪府寝屋川市高柳7の容疑者を乳児の遺体を遺棄したとして死体遺棄容疑で逮捕した。容疑者は20日午前に同市の寝屋川署高柳交番を訪れ「4人の子供を産み落とし、バケツに入れてセメント詰めにし、段ボールに入れて自宅で保管している」と自首。府警の捜査員が、自宅の集合住宅3階で4個の段ボール箱を発見。画像診断で、中の四つのバケツそれぞれに乳児とみられる遺体が入っているのを確認した。 府警は20日、死体遺棄事件として同署に捜査本部を設置した。今後、詳しい動機や経緯を調べる。捜査1課によると、容疑者は「4人の子供はいずれも1992~97年にかけ市内の別の場所で産んだ。産んですぐにバケツに入れた。金銭的に余裕がなく、育てられないと思った」と説明している。容疑者は息子との2人暮らし。この日自首した理由や経緯は不明だが、「これまでずっと悩んでいた。死のうとも思ったが、育ててきた子供もいるので1人で死ぬこともできなかった。相談できる人もいなかった」と話している。と報道されています。
報道に接して胸が苦しくなりました。二度と再びこのような事件を起こさないために何ができるのか。報道されているように本当に金銭的に育てられないと考えたことが原因なら、行政にも今後なにかできることはあると思います。寝屋川市は最近子育てにお金をかけている自治体ランキングで全国13位となりました。この間の施策が評価されたものとして大変嬉しく思いました。寝屋川市として子育て支援策の充実をはじめ更なる施策の推進が必要と考えますが、市として今後の取り組みなど検討していることがあればお答えください。2017年9月議会 一般質問 太田とおる
2017-09-15
-
国民健康保険の都道府県単位化についてです。
来年4月の国民健康保険の都道府県単位化が、目前に迫ってきました。
厚生労働省は8月31日までに3回目の来年4月以降の国保料率の仮算定の提出を都道府県、市町村に求めています。しかし、大阪府は期限にまでに仮算定ができず提出していません。また、全国的には各市町村も提出していますが、大阪府下では統一保険料にするとの前提で全て大阪府が提出することとなり、府下市町村は算定を行っていないようです。このまま、大阪府の実務を待っているとどんどんと遅れていくばかりです。
この間、市議会でも都道府県単位化について質問を行ってきましたが、大阪府の動向を注視するとの答弁に留まっています。しかし、これから来年度予算の編成も控える中、大阪府と府下各市市町村の合意や方向性を見極めていくことも大事ですが、寝屋川市がどのように国民健康保険を運営していくのか、その基本方針をしっかりと持ち判断をしていくことが大事だと考えます。
すでに、7月31日に大阪府国民健康保険運営方針(たたき台)(案)が示されました。以下たたき台といいます。今回のたたき台は「大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議」での現時点での検討状況を踏まえ、記載されたものであると留意すべき事柄として記載されています。すなわち、現時点での大きな方向性はしめされています。
日本共産党は、8月9日に大阪府下の市町村議会議員と府会議員団、堀内衆議院議員揃って大阪府に国保の都道府県単位化に対する要望書を提出し、たたき台について懇談を行いました。そこでも大阪府の考えを確認させていただいています。
そこでたたき台に沿って質問をしていきます。
まず最初に、たたき台では基本的事項、1策定の目的で運営方針は、府と市の適切な役割分担の下、オール大阪で広域化を図り、持続可能な国保制度の構築をめざし、国民健康保険の安定的な財政運営並びに府内市町村の国民健康保険事業の広域化及び効率化を推進するため統一的な方針として策定するものであるとされています。
そこで寝屋川市にお聞きしたいのは最終的に策定された運営方針にどこまで市町村の判断が制限させられることになるのか。法律の解釈では助言にとどまると考えるが、寝屋川市は運営方針を技術的助言と考えるのか。それとも強制力のある指導と捉えているのか、その根拠も含めて答弁を求めます。
次にたたき台では、府における国民健康保険制度の運営に関する基本的な考え方が示されています。
基本認識として、社会保険制度としての国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、その権限・財源・責任については国が一元的に担うことが本来の姿である。国に対し、各医療保険制度間での保険料負担率等の格差を是正し、被用者保険を含む医療保険制度の一本化を求めていく上で、このたびの制度改革は、将来にわたる安定的かつ持続可能な医療保険制度の構築に向けた通過点であると考える、としています。
寝屋川市も同様の立場に立っているのか。現在、基礎自治体である寝屋川市が国保を運営していることは市民にとっていいことだと考えます。後期高齢者医療制度では広域連合という形で市民に見えない遠い運営主体になっている。市民の命に関わる制度だからこそ基礎自治体が担うべきではないか。問題は、この間、国保への国の負担が減らされてきたことであると考えます。市の認識を問います。
次に視点では平成30年度からの新たな制度においては、被保険者の資格管理単位が府域単位に変更されるなど、「大阪府で一つの国保」となる。財政面では、府に財政責任を一元化し、府内市町村の被保険者に係る必要な医療給付費を府内全体で賄うことで、保険財政の安定的運営を可能とするものである。府が財政運営の責任主体となることにより、社会保険制度における相互扶助の精神の下で、これまでの市町村における被保険者相互の支え合いの仕組みに、市町村相互の支え合いの仕組みが加わり、府内全体で負担を分かち合うこととなる、とされている。
現在、大阪府下の各自治体の国保会計を見れば、大規模自治体ほど赤字が多く財政的に問題を抱えている。今回の改定で結局、大阪市などの単年度赤字を繰り返している他の自治体の赤字を保険料の引き上げで他の自治体で面倒を見ることにならないのか。ようやく黒字化し、安定的な財政運営に踏み出した寝屋川の国保には悪影響しかないのではないか。市の答弁を求めます。また、国保は法律で一番最初に社会保障と規定されているのにその観点がすっぽりと抜け落ちて、被保険者、自治体の相互扶助制度として規定するのは間違いではないか。市の考えをお示しください。
視点では続いて、このような仕組みを勘案すれば、府内のどこに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料額となるよう、府内全体で被保険者の受益と負担の公平化を図るべきであると考える。これにより、結果として、被保険者にとってわかりやすい制度となることで、新たな制度への府民理解が進むことが期待される、とされています。
しかしここには大きな錯誤があります。現在、国のナショナルミニマムとも言うべき生活保護基準において、各市町村で差がつけられていることです。すなわち大阪府の中でも物価などの状況が違っていることが示されています。寝屋川市は1等地の1で一番高い基準ですが、府内自治体の中にも等級の違いがあります。すると同じ所得収入でも一方では生活保護世帯、他方では国保料を徴収される世帯が出てきます。
このように地域格差を無視した視点には大いに問題があると考えるが、寝屋川市の認識を示してください。
次にたたき台では基本的な考え方に基づいて「府内統一基準」を定める。統一時期は平成30年4月1日、ただし出産育児一時金及び葬祭費以外の項目は、激変緩和措置を設けるとしています。統一基準については一つ一つ確認をしていきます。
また、日本共産党議員団との懇談の場において大阪府は府内統一基準を守らない自治体に対してのペナルティについて、現在検討中と答えています。協議の状況と市の考えをお示しください。
次に財政調整基金についての考え方です。たたき台は国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しの中で、市町村が保有する財政調整基金の取扱いを示しています。
市町村に設置される国保財政調整基金については、地方自治法第241条に基づき、国民健康保険事業の健全な発展に資するために設置されており、医療給付費の増加等の予期せぬ支出増や保険料収納不足等の予期せぬ収入減といった場合に活用されている。
上記の役割については、一部財政安定化基金が担うこととなり、また、保険給付費等交付金の創設により、医療給付費の増加のリスクを市町村が負う必要はなくなるが、その他の予期せぬ支出増や収入減に対応するため、引き続き市町村においても財政調整基金を保有し、国保財政基盤の安定化のために活用することとする。ただし、財政調整基金への積立て及び繰出しについては、全市町村において次のとおり取り扱う、とされています。
まず財政調整基金の積立てです。
収納率の向上等により市町村の国保特別会計に余剰が発生した場合に限り、積み立てることができるものとし、一般会計繰入による積立ては行わない、とされていますが、地方自治体が財政をどのように使うのかまで制限することはできるのか。根拠と市としての考えを示してください。
そして財政調整基金の繰出しについては
次の各号の場合に限り、繰り出すことができるものとする。なお、保険料(税)率引下げを目的とする繰出しは認めない。
収納不足の場合の納付金への充当のため ・財政安定化基金への償還のため ・過去の累積赤字の解消のため ・府内共通基準を上回る保険事業等を実施するため ・府内統一基準を上回る保険料(税)・一部負担金の減免を実施するため(ただし、激変緩和期間中に限る。)・市町村が独自で実施する保険料(税)の激変緩和措置のため、と示されています。
最初に示されているのが、保険料引き下げのための繰り出しは認めないということです。しかし、市民が収めた保険料が基金の原資ですし、市民に保険料軽減の形で還元するのが当然の有り様ではないでしょうか。繰り出しができないとされる根拠と市の考えをお示しください。そしてたたき台に示されている基金の繰り出し基準について、その根拠と市としての考えをお示しください。全体として自治体の自治権の侵害ではないかと考えます。
次に府の財政安定化基金の運用については「特別な事情」による収納不足時の交付とされています。特別な事情とはどのようなことを指すのか、また交付分の補填方法については、当該交付を受けた市町村が補填することを基本としつつ、「特別な事情」を加味しながら全市町村から意見聴取した上で、個々のケースごとに府が按分方法等について判断することとする。とされていますが、極めて特別な事情があれば、財政安定化基金については返済の免除や、他の市町村が肩代わりをすることがありうるとの認識で良いのか。具体的にどのような場合が当てはまるのかお示しください。また、寝屋川市としてどのように考えているのかもお示しください。
次に市町村における保険料(税)の標準的な算定方法が示されています。
保険料(税)関係では
保険料・保険税の区分・賦課方式・賦課割合・賦課限度額については、示されている府内統一基準と寝屋川市の方式とほぼ変わらず、
標準的な保険料(税)算定方式は3方式(所得割・均等割・平等割)ただし、介護納付金は2方式を協議中とされています。
標準的な応益割と応能割の割合は1:βとされています。せめて寝屋川市の現行のままがよいと考えますが、現状の検討方向と寝屋川市の考え方を示してください。
次に応益割における被保険者均等割と世帯別平等割の割合 70:30について多子世帯等の負担軽減の観点から割合の変更について協議中とされています。一人暮らしの高齢者が増えていく中で平等割を増やすことも困難です。府の方向はどのようなものであり、市はどのような割合を考えていますか。最終的には減免制度で対応せざるを得ないと考えますが、市の考えをお示しください。
賦課限度額については国が政令で定める額とされています。寝屋川市では、介護納付金、後期高齢者支援金は国の政令に定める額と条例に規定しています。しかし、医療分については、過去に市から医療分についても政令で定める額との諮問もされましたが、金額も大きく市民生活への影響も大きい、その度に国民健康保険運営協議会で議論し、市議会で議論をすることが必要との判断で、その都度、条例改正する方式をとっています。賦課限度額にについて寝屋川市はどのように考えているのか。過去の国民健康保険運営協議会の議論も踏まえてお答えください。
次に、保険給付費等交付金(普通交付金)の対象とする保険給付の拡大です。
国が示す保険給付費等交付費の対象となる保険給付(療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費)のほか、府内統一(共通)基準に係る次の費用についても、保険給付費等交付金の対象に含めて交付を行うこととする。
出産育児諸費 ・葬祭諸費 ・その他給付(精神・結核医療)(協議中)・審査支払手数料・保健事業費(府内共通基準に係る部分)・保険料(税)及び一部負担金減免に要する費用(府内統一基準)・医療費適正化等の対策費用等事務費(府内共通基準に係る部分) とされています。
拡大される部分はいいのですが、現在、寝屋川市で実施されている精神・結核医療について協議中とあるのは気になるところです。この間大阪府の福祉医療助成制度も改悪される中で国保の保険給付の対象が狭くなる方向については問題があると考えます。市としての考え方と、現在の協議状況をお示しください。
次に納付金の算定方法ですが
医療分について
市町村標準保険料(税)率の算定に必要な納付金の算定の際の医療費水準の反映
医療費水準は反映しない(α=0)。
高額医療費の府内共同負担 実施する。
標準的な収納率による調整 調整を行う。
納付金総額の応益分と応能分の按分の割合 1:β
応能分の所得総額で按分する割合と資産総額で按分する割合 100:0
応能分の各市町村への按分方法 各市町村の所得総額で按分
応益分の被保険者数で按分する割合と世帯数で按分する割合 70:30(多子世帯等の負担軽減の観点から割合の変更について協議中)
応益分の各市町村への按分方法 各市町村の被保険者数と世帯数で按分
としめされています。
ここで医療費水準を加味しないとされているのは非常に問題です。この間大阪府が示している資料には、大阪府内には最大1.2倍の医療水準の格差があるとされています。そして、寝屋川市も検診事業などひとりあたりの医療費引き下げのための努力を行ってきました。 寝屋川市の一人あたりの医療給付費は大阪平均より低いものとなっています。それが、全く考慮されないままに保険料率が決まってくるわけですから、各市町村の努力や大阪府下の医療水準を加味しないのは全くの暴論です。1.2は1と同じというのならその根拠と寝屋川市の考えをお示しください。市民生活と市の努力を反映するためにも医療費水準についても加味すべきと考えます。
次に標準的な収納率です。
標準的な収納率は、府内における市町村標準保険料(税)率を算定するに当たっての基礎となる値である。このため、標準的な収納率の算定に当たっては、各市町村の収納率の実態を踏まえつつ、適切に設定するものとする。(具体的な設定方法については今後協議) とされています。現在の協議内容をお示しください。現在の寝屋川の収納率は府の平均より低いので、今後示される標準的な収納率に到達していないと考えるが、具体的にどのような影響がでると考えているのか。その影響をどのように解消していこうと考えているのかお示しください。
次に、府内統一保険料(税)率 についてです。
たたき台では、将来的な医療費の増加が見込まれる中で、健康づくり・医療費適正化取組の推進により、医療費の増嵩に伴う被保険者の負担をできる限り抑制していくことが必要である。
健康づくり・医療費適正化取組を進めつつ、府に財政責任を一元化し、府内のどこに住んでいても、同じ所得・同じ世帯構成であれば同じ保険料額となるよう、被保険者の負担の公平化を実現するための仕組みとして、府が示す市町村標準保険料(税)率を府内統一とする。
ただし、別に定める激変緩和措置期間中については、市町村ごとに、府が実施する激変緩和措置を考慮して算出した保険料(税)率とする。
市町村は、次に該当する場合を除いて、府が示す市町村標準保険料(税)率と同率とするものとする。
激変緩和措置期間中において、被保険者への保険料(税)負担の激変を緩和する観点から、府が実施する激変緩和措置とは別に、市町村が独自に激変緩和措置を講ずるために算出した保険料(税)率(後述)
極めて限定的な緊急措置として、給付増や保険料(税)収納不足により財政安定化基金から貸付を受けた場合に、その償還財源を確保するために独自に算出した保険料(税)率 、とされています。
結局、府で保険料率を統一し、市町村が保険料上げることは認めても下げることは認めませんということになっている。激変緩和は値上げを抑えるだけで保険料を引き下げることにはならず、保険料率を上げ続けますよということではないのか。基礎自治体として保険料率を決める権利が制限されるのか。それとも、自ら決めることができるのか。根拠示してお答えください。
次に激変緩和措置についてです。
平成30年度からの新制度において、納付金の仕組みの導入や算定方法の変更により、一部の市町村においては、本来集めるべき一人当たり保険料(税)額が変化し、被保険者の保険料(税)負担が上昇する可能性がある。こうした場合でも、保険料(税)が急激に増加することがないよう、次のとおり激変緩和措置を講ずる。
激変緩和措置の期間(協議中)特例基金の活用期間に合わせ、新制度施行後6年間(平成35年度まで)とする。
府が実施する激変緩和措置の内容(協議中)
新制度施行に伴い、本来集めるべき一人当たりの保険料(税)額が、現行制度における本来集めるべき保険料(税)額と、国保事業費納付金等算定標準システムにより試算した新制度における一人当たり保険料(税)額を比較して得られた差額を激変緩和措置の対象とする。激変緩和措置の具体的な実施方法については、調整会議等において協議の上、別に定める。
なお、制度施行当初にあっては、激変緩和措置に活用する都道府県繰入金が多額となることにより、全体の納付金総額が増加するおそれがあることから、国公費を投入した上で、激変緩和措置の状況に応じて、特例基金からの繰入れを行うこととする。
また、激変緩和措置については、国の納付金ガイドラインに示す3つの手法のうち、「都道府県繰入金」及び「特例基金の繰り入れ」により実施することとし、「納付金の算定方法の設定」(医療費水準反映係数α及び所得係数βの調整)による激変緩和措置は実施しない、とされている。
寝屋川市はたたき台の言う、激変緩和措置を講じなければならない一部の市町村に当てはまるのか。また、医療費水準α所得水準βの調整による激変緩和は実施しないとされているが、そのことは寝屋川市に悪影響が出るということではないのか。激変緩和措置の内容は協議中とあるが、現在の協議内容と方向性、市の考えをお示しください。
次に激変緩和措置の対象です。
決算補填等目的の法定外一般会計繰入金、前年度繰上充用金(単年度分)、市町村基金取崩金(保険料(税)充当分)及び前年度繰越金(保険料(税)充当分)の廃止による一人当たり保険料(税)額の増加分については、府が実施する激変緩和措置の対象とはならない。従って、これらの廃止に伴って発生した一人当たり保険料(税)額の激変については、激変緩和措置期間中において、当該市町村の責任により必要に応じて実施するものとする、とされています。現時点で寝屋川市の責任で行う激変緩和措置は何か想定できますか。お答えください。
次に、たたき台にその他として示されている。
保険料・保険税の区分については保険制度における給付と負担の対応を明確にする観点から、府内の多くの保険者が採用している「保険料」を府内統一基準とする。
保険料(税)の仮算定の有無、本算定時期、納期数については、被保険者への負担の影響や市町村事務の効率化等の観点から、「仮算定なし」の「6月本算定」「納期数10回」を府内統一基準とする、とされており、現行、寝屋川市と同じです。
保険料(税)の減免については協議中とされていますが、保険料(税)の減免については、国通知、過去の判例及び大阪府後期高齢者医療制度を参考にしつつ、「別に定める基準」を府内統一基準とするとしめされ、現行の大阪府下の実態とかけ離れています。後期高齢者医療制度での減免は失業・廃業・天災が対象で実質多くの加入者が使えないものです。せめて現行の寝屋川市の制度の維持が必要です。現在の協議状況と市の考えをお示しください。
次に一部負担金減免及び徴収猶予についても同様に国通知、過去の判例及び大阪府後期高齢者医療制度を参考にしつつ、「別に定める基準」を府内統一基準とする、とされています。後期高齢者医療制度では一部負担金減免はほとんど使用されない制度となっています。困ったときに利用できる制度とすることが必要です。現在の協議状況と市の考えをお示しください。
次に精神・結核医療給付ですが、精神・結核医療給付は、これまでの経過や被保険者への影響等を踏まえ、平成30 年度から3年間は、現行制度を維持するものとする。なお、被保険者の影響を見極めた上で、他制度との整合性や公正性確保の観点から、その在り方について調整会議等において検討する、とされています。現行制度の維持に向けて市として協議に望んでいただきたいと考えます。市の考えをお示しください。
次に市町村が担う事務の共同実施についてです。
たたき台には、これまで、府内全市町村が加入する府国保連合会において、共同処理などの実施により、市町村が担う事務の効率化、標準化を図ってきた。
新制度施行後も、資格管理、保険料の賦課・徴収、保険給付などの事務は市町村が引き続き担うことになる一方で、事務の種類や性質によっては、市町村が単独で行うのではなく、より広域的に実施することによって効率化することが可能なものがある。
このことから、市町村が担う事務の広域化・効率化に向け、次に掲げる取組を進める。
被保険者証(通常証)及びその他の証(高齢受給者証等)(市町村への意向調査中) 平成30年以降の更新分から、被保険者証(通常証)の様式を別に定める様式に統一するとともに、府国保連合会において、新たに被保険者証発行業務の共同処理を行う。
また、資格証明書などの資格に関する証や高齢受給者証等の保険給付に関する証の様式統一等については、各市町村の機器更新の時期を踏まえながら、将来的な課題として、引き続き調整会議等において検討する、とされていますが保険証発行事務の共同化は発行そのものの遅れにつながるのではないですか。現在の協議内容と市の考えをお示しください。
都道府県単位化は法律で来年4月実施は決まっています。しかし、細かな内容、市民への影響はまだまだ、検討不足です。最低限の統一化で現行制度の維持が市民にとっても、市町村にとっても、そして大阪府にとっても問題なく移行できるのではないでしょうか。寝屋川市が市民の立場で奮闘することを求めて国保に関する質問を終わります。
次に、寝屋川市の防災対策についてです。
まず最初に最近の台風、大雨に対する寝屋川市の対応についてお伺いします。
先日の台風5号では寝屋川市には暴風・大雨・洪水警報が出されました。台風がどんどんと迫って来る中多くの市民が危機感を持って台風と向き合ったのではないでしょうか。そんな中、寝屋川市は市内6箇所のコミセンを自主避難所として開設しました。TVではテロップで流れるなど紹介もされていましたが、寝屋川市としての周知への対応は十分だったのでしょうか。市民からお話を聞くと避難所が開設されていたことを知らないというのが率直な感想です。今回は自主避難のための避難所の開設でしたが、今後、避難指示などが必要な災害も想定されます。
そこでお聞きします。今回の自主避難所開設に至る経緯と開設後の市民への周知について、市として十分だったと考えているのか。
次に8月23日の夕方の大雨で寝屋川市に大雨・洪水警報がでて市内も停電と道路冠水などの被害が出ました。その後寝屋川市から被害の状況の書かれた文書が配布され道路冠水7箇所などと書かれていましたが、冠水箇所などの特定はされていません。
市として大雨・洪水警報が出された際の見回りや道路冠水の状況把握などどのようにされているのか。市民からの通報の確認だけでは後手を踏むのではないでしょうか。道路冠水などすぐに市民へ周知できる体制を求めます。市の考えをお示しください。
今、寝屋川市地域防災計画の改訂が行われようとしています。計画策定に向けてのスケジュールでパブコメや防災会議などが行われます。一つ一つを地域の防災意識の向上に役立てて出来上がった計画が市民にとって身近な計画になるように、市としての努力を求め、今後の市民への周知体制など特別な対策を考えているかお示しください。
2017年9月議会 一般質問 前川なお
2017-09-15

日本共産党議員団の前川なおです。通告にしたがいまして一般質問を行います。
みなさんは自分の老後の暮らし向きがどんな風であるか、あるいはどうありたいとイメージしているでしょうか? お金の不安なく自分らしく生きられる幸せな人は、どのくらいいるでしょうか。
本来、長寿は喜ばしいことです。
しかし、いまの日本社会に広がる「老後破産」「介護難民」「孤立死」といったキーワードを見ると、高齢者を取り巻く環境は厳しさを増していると言わざるを得ません。
国民年金は満額でも月額6万5千円です。年金は減らされる一方で医療費や介護のお金は上がっていく。
食費を削り電気水道ガスを節約し、年金支給前は病院に行くことさえもがまんして、買い置きのソーメン、ご飯だけでしのぐという高齢者も少なくないと聞いています。
こんな爪に灯をともすような暮らしぶりは、憲法25条がうたう「健康で文化的生活の保障」とはほど遠く、「長生きを喜べる社会」とは言えません。
介護を取り巻く環境は、いまや在宅介護の約半分が、65歳以上が介護を担う「老老介護」の状態にあるといわれています。老老介護の中でも、認知症の要介護者を認知症の介護者が介護している「認認介護」も、今後増加していくでしょう。
独身の娘や息子が親の介護を担う「シングル介護」も増えています。子どもが「介護離職」をした場合、生活は親の年金に頼ることになります。
いつ終わるとも知れない介護。先細りしていく蓄え。その先には不安しかないのではないでしょうか。
介護保険制度は3年ごとの改定のたびに使いづらい制度にされてきました。
保険料は引き上げられ、報酬単価は引き下げられてきました。そもそも高齢者人口が増加し介護サービスを使う人が増えるほど保険料に跳ね返るという仕組みそのものがひどいものです。介護従事者の処遇改善で加算はありましたが、それも利用者に負担を強いるものです。
知り合いの高齢の女性は、「介護保険なんてまったく使ってないのに、あの高い保険料何とかならへんの?」と不満をこぼされていました。これが多くの高齢者の声です。
来年は保険料のさらなる値上げが予想されます。これ以上の値上げは、高齢者の厳しい暮らしに追い打ちをかけるものと認識し、保険料の軽減策を次期事業計画に盛り込むことを求めます。
介護保険サービスを利用するにも、財布と相談になります。介護度の重い人はより日常生活で支援が必要ですが、サービスを受ければ受けるほど利用料の負担も増えます。
体調悪化などで週1回デイサービスの利用を増やしたいと思ったら毎月2000円、週1回1時間ヘルパーさんに入ってもらいたいと思ったら月約1300円の新たな負担が必要です。その額が払えない高齢者が少なくないのです。
一つの例として80代のAさんのケースを紹介します。
Aさんは要支援1。サービス付高齢者住宅で生活し、週1回デイサービスを利用していました。この6月に体調が急変。ひとりで歩くこともトイレに行くこともできなくなったため、ケアマネジャーが週1回1時間のヘルパーを追加利用してはどうかと提案しました。
Aさんは厚生年金で月々約12万円の収入があります。そのほとんどが住居費、医療費、食費に消えるため、新たに1300円のヘルパー利用料を支払うことは困難でした。
Aさんの一人娘は難病を抱え経済的な支援はできません。ですが娘さんが無理をしてAさんの介護をされました。結果、共倒れになってしまったのです。
Aさんは今後、介護認定の区分変更を申請し、特別養護老人ホームへの入所申請を行う予定とのことです。多床室に入所できれば経済的な余裕もでてくるでしょう。
しかしその特別養護老人ホームは、どこも空きがありません。本市では460人前後の高齢者が入所待ちの状況です。第6期介護保険事業計画の利用見込みに対して整備が追いついていないのであれば、次期事業計画に改善点を盛り込む必要があると考えます。
低所得で在宅介護が困難なケースなど、施設入所が必要な高齢者が利用できるよう整備すべきです。
介護保険制度の改定を前に、市として、高齢者の暮らしをどう守っていくかが問われます。
戦後の混乱期から日本の高度成長期を支えてきた高齢者が「長生きできてよかった」と思える社会をともに目指し、保険料・利用料の負担軽減など高齢者の生活実態に即した施策の展開を求めます。
以下、見解を問います。
一 高齢者の生活がより厳しい状態に追い込まれている中で低所得者への保険料・利用料の負担軽減が必要です。見解を問います。
一 国の制度改悪はひどいといわざるを得ません。市として、これ以上の被保険者への負担増の中止と人材確保も含め適切な財政措置を講じることを国に要望してください。
一 施設入所が必要な高齢者が利用できるよう、特別養護老人ホームの待機者解消に向けた対策についてお答えください。
介護予防・日常生活支援総合事業について。
総合事業に移行して4カ月ですが、すでに在宅支援員の不足によって事業運営が大変厳しくなっていると事業者から声があがっています。
新たに設置された「緩和型サービス」は、基本的に研修を受けた「在宅支援員」が利用者宅を訪問し、家事支援を行います。資格のあるヘルパーとちがい無資格の在宅支援員は身体介護を伴わないことから、ヘルパーよりもさらに賃金が低く抑えられます。事業所に入る報酬単価も低くなります。
緩和型に移行する事業所が増えているにもかかわらず、在宅支援員が増えていません。市の研修会も定員を割り込んで当初予定していた人数を大幅に下回っています。
緩和型に派遣する在宅支援員がいない場合、事業所は報酬が下がってもヘルパーを派遣せざるを得ない、またはそもそもヘルパー不足の状況の中で介護福祉士などの資格を持った管理責任者やベテランが行かざるを得ない。報酬単価が低い緩和型へ、ヘルパーを派遣することによる事業所の持ち出しの増加が、経営を圧迫している。これがいま現場で起こってきていることです。
来年の制度改定では報酬がさらに引き下げられる可能性が高く、事業所運営がますます厳しくなることが予想される中で、緩和型サービスの在宅支援員不足は深刻です。
事業所としての一番の願いは国が報酬単価を引き上げることですが、社会保障費抑制の流れの中で実現は困難です。であれば、事業所を守るための独自施策も必要になってくるのではないでしょうか。
本市の要介護認定者を見ると介護度の低い要支援1・2が全体の約3割。所得では介護保険料の第1段階から第3段階までの所得の低い高齢者が4割を超えています。今後、利用料の安い緩和型を利用する高齢者は増えていくことが考えられます。
総合事業は始まったばかりであり、事業所もいまはなんとか踏ん張っている状態ですが、緩和型サービスの担い手不足と報酬単価引き下げが相まって事業が立ち行かなくなれば、市の責任も問われてきます。以下、質問します。
一 在宅支援員が集まらず有資格者が行かざるを得ない状況が増していった場合、事業所を守るための施策の検討も必要と考えます。今後、事業所へアンケート調査を実施するなど現場の実態を詳細に把握するとともに、緩和型事業の検証と対策、改善が必要と考えます。見解を問います。
高齢者の社会参加についてです。
自治会や地域包括支援センター、校区福祉委員会などが定期的に開催する食事会などは、地域で暮らす高齢者の楽しみの一つとなっています。私の地元自治会では、うたごえサロンや「ふれ愛喫茶」があります。
普段ひとりでテレビ相手に食事をしている高齢者も、食事会に行けば友達がいて、みんなで食事しながらおしゃべりができる。楽しい時間ではないでしょうか。
枚方市は、ことしの8月21日から「高齢者居場所づくり事業」の補助金申請の募集を開始しています。「子ども食堂」の高齢者版のような感じでしょうか。高齢者の居場所を運営する団体に補助を行う仕組みです。
3年以上継続して事業を行う意思があること、飲食代等の実費負担を除き参加費は無料であることーなどの要件を満たした団体に対し、スタート支援として1カ所あたり20万円を上限に補助するというものです。今年度で予算1000万円。2018年度までの2カ年計画で、高齢者の居場所を市内100カ所に設置することを目指すとしています。
高松市や京都市などいくつかの自治体ではすでに制度がつくられています。京都市は開設費最大20万円、備品購入費最大5万円、運営経費も週5日程度の開設で年間最大7万円補助されます。
「話し相手・相談相手がほしい」と思っている高齢者はたくさんいます。高齢者同士が繋がり会える場がいつでも身近にあるということが大切ではないでしょうか。
一 超高齢化社会を見据え、高齢者の「居場所」設置は必要と考えます。今後、地域のさまざまな事業に対しての支援など仕組みができないでしょうか。見解を問います。
学童保育の土曜日開所についてです。
学童保育を利用している保護者へ教育委員会から「土曜日開所に係るアンケート調査」の依頼文書が配布されました。土曜日開所の検討に当たり保護者から意見を聞くという内容です。アンケートは8月28日で締め切られました。保護者からは大きな期待の声が寄せられています。
土曜開所に向けた今後のスケジュールについてお示しください。
その他として、子どもの貧困対策について。
厚生労働省が発表した全国210カ所の児童相談所が対応した2016年度の児童虐待の件数が12万2578件と過去最多になりました。子どもの目の前で暴力を振るう「面前DV」を含む心理的虐待が約半数を占めています。ワースト1は大阪府の1万7743件。
本市においては児童虐待に関する相談が延べ1万件を超えて寄せられています。
虐待が起きる背景の一つに経済的要因、貧困や孤立があることが指摘されています。
先の6月議会で取り上げましたが、大阪府が行った「子どもの生活実態調査」は、貧困が子どもの生活や健康、学習面に与える影響が大きいことを浮き彫りにしました。
府は、調査によって府下の傾向は示されたと報告しています。しかし、府の調査結果だけで本市の子どもの置かれている状況を本当につかんだといえるでしょうか。
子どもの貧困対策は大きな課題であると先の議会で答弁されています。本気で貧困対策を進めるならば、本市の子どもや親の状況を詳細につかみ分析してこそ、国や府と連携しながらも本市の実状に合った具体的な貧困対策に反映できるのではないかと考えます。
また実態をつかむ中で虐待の早期発見・予防にもつながると考えます。
本市の実状に合った子どもの貧困対策に反映するため、あらためて、本市における子どもの貧困の状態を把握するための調査の検討を求めます。見解を問います。
以上で一般質問を終わります。再質問があるときは自席にて行います。
ご静聴ありがとうございました。
2017年6月議会 一般質問 石本えりな
2017-06-30
日本共産党の石本えりなです。通告に従いまして一般質問を行います。
・介護について
介護保険が2000年にスタートして17年目になりました。悲しいことですが全国では、「介護殺人」や「介護心中」は表面化している事件だけで年間50件から70件と、ほぼ毎週1件の頻度で起きています。家族が要介護状態になったために仕事を辞める「介護離職」は年間10万人、特別養護老人ホームの入所待ちの人は入所者の数より多い52万人で「介護難民」があふれています。介護事業所や介護施設は介護労働者が集まらず人手不足で「介護崩壊」の危機が迫っています。
日本は少子高齢化社会で、この状況は今後も進んでいきます。そこで介護職は必要不可欠な職業となってきています。介護はこれまでより重視されなければなりません。そのためには人材の確保と介護の質の向上と言う点は重要です。
しかし、介護の現場は需要と供給のバランスが取れていないのが現状です。介護の仕事はとてもやりがいのある仕事ですが、現在の介護職での平均年収では家族を養うことができないのが現状です。そのため介護職から離れていかざるを得ない状況がさらなる介護士不足になっています。介護士が安心して働き続けられるよう処遇の改善が必要です。
●介護士不足は大きな問題になっています。今後、介護士処遇の改善が必要だと思いますが、市としてどう考えていますか。また、国、府の改善への動きをどう把握されていますか。お聞かせ下さい。
改定介護保険法施行により、2015年4月から総合事業が施行されたものの2015年1月の厚労省調査では、大半の市町村は「多様なサービス整備」のめどが立たず、改定法施行と同時の2015年4月実施はわずか78市町村で、4.4パーセント。2015年度中実施予定でも114市町村の7パーセントにとどまっていました。総合事業の本格実施・完全移行へは2017年4月にはすべての市町村が要支援1・2の訪問介護、通所介護を総合事業にどう移行するかが最大の課題となっていました。
寝屋川市では2017年4月より総合事業へと移行し、4月から始まった総合事業については、要支援1・2の新規で認定された方や、区分変更によって要支援1・2に認定された方は様々な形で介護サービスが提供されるようになりました。訪問型サービスでは、現行の訪問介護相当、緩和した基準によるサービス、有償活動員によるサービス支援です。通所型サービスでは、現行の通所介護相当、緩和した基準によるサービス、短期集中予防サービスとなっています。また、チェックリストについては、要介護認定を申請し、「非該当」になった方について行い、事業対象者となった場合は、訪問型サービスのうち有償活動員による支援の利用が可能となっています。
●総合事業については、市は、2017年4月から総合事業へ移行しスタートしました。4月から総合事業へ移行したのは訪問サービス、通所サービスで各何件ですか。また、その中で緩和型サービスへ移行されたのは何件ですか。また、総合事業への移行目標は決めてないとしていますが、現在その割合は何%ですか。また、指定事業所として申請した事業所は何事業所ですか。お聞かせ下さい。
●総合事業へと移行したら現在使っているサービスが使えなくなるのではないかなど心配の声を聞きます。今後、市としては、緩和型へ移行はどれくらいと考えているのでしょうか。また、現在指定事業所として申請していない事業所は、どのような理由なのかお聞かせ下さい。
●在宅支援員については、在宅支援員の研修には、何人の方が来られました。お聞きします。
●本来であれば、50時間の研修が必要ですが、寝屋川市は12時間の研修で本当にサービスができるのか心配の声を聞きます。実際働いた中で苦情などは出ていないでしょうか。また、在宅支援員の研修に来られた方がその後、実際に働いておられるのか確認されていますか。お聞かせ下さい。
今、日本では貧困化が進み、非正規雇用が4割に迫り、実質賃金も減り続けています。高齢者世帯の4割が年間所得199万円以下の状況にあり、全世帯でも2割にのぼります。少なすぎる年金だけで生活しているため、必要とする医療や介護など福祉サービスを受けることができなかったり、食べることにも困り、体を弱らせている人は多く、貧困や格差の拡大により「老後破産」や「下流老人」などが社会問題になっています。
●高齢者保健福祉計画が今年度策定されますが、介護保険料は、介護保険を使う人が増える限り、どんどんと値上げをされる仕組みです。40歳以上の方が加入し保険料を支払っています。寝屋川市の介護保険料は、第14段階に分けて保険料の徴収をしていますが、それでも、保険料が支払えない方もおられます。他市では第14段階やそれ以上の多段階に分けていても、市独自の減免制度をされているところもあります。高齢者保健福祉計画次期策定について調査検討するということですので、ぜひ前向きに検討していただくよう要望し、見解をお聞きします。
利用料の減免についてですが、介護が必要になれば、誰もが安心して介護が受けられることは、当たり前のことだと思います。平成27年8月の介護保険制度の改定により一定所得のある方は自己負担が1割から2割に変わり、サービスを制限される方もおられます。必要なサービスが使えず、本当に安心してサービスが使えているのでしょうか。2015年1割から2割に引き上げたばかりの負担割合を3割に引き上げれば、要介護3で平均的な居宅サービスを受ける人の利用料は月2.9万円、年間約34万円もの負担になり、家計への打撃となり、必要なサービスの抑制につながるのは明らかではないでしょうか。
●1割から2割になったことでの利用率に変化はありましたか。また、必要な人に必要なサービスを提供するためには、利用料の減免も必要ではないでしょうか。見解をお聞きします。
・就学援助制度について
全国的には入学準備金の前倒し支給を実施している自治体が広がっています。
入学準備金については、平成29年度の主要施策として増額されたことは、大変うれしいことで、評価しています。
●入学準備金の支給の時期については、入学する前に必要なものをそろえるときに支給されるのが望ましいと考えます。支給時期を早めることを求め、前倒し支給についての見解をお聞きします。
・学校給食について
●第3子以降の学校給食費の助成について、寝屋川市まち・ひと・しごと創生総合戦略にも上げられています。保護者の経済的負担の軽減と子育て支援を目的として小中学校などに、同時に3人以上在籍する児童・生徒の3人目以降の小中学校の学校給食費を助成するとなっていますが、現在の進捗状況をお聞きします。
以上で、私からの質問を終わります。再質問がある場合には、自席にて行います。ご清聴ありがとうございました。
2017年6月議会 一般質問 中林かずえ
2017-06-30
日本共産党の中林かずえです。 通告に従い質問します。
● まず、ごみ減量についてです。
寝屋川市の可燃ゴミ量は、計画通りに減少しておらず、このままでは、平成30年稼働予定の新焼却炉の能力を超えてしまう状況です。
また、ゴミ減量市民アンケート結果で、「再商品化に、適さないその他プラは、サーマルリサイクルに切り替えた方がいい」との、7割を超える市民の声に、応えるためにも、可燃ゴミの減量は、待ったなしの課題と言えます。
市は「ごみ減量緊急事態宣言」を行い、「ごみ減量・プロジェクト」で、今年から3年間で、可燃ごみを約1万トン減らすとしています。
1万トンの内訳は、家庭ゴミの ①手つかずの食品(6.9%)削減で2300t、②生ゴミ(34.4%)の水分20%削減で2300t ③紙類の分別リサイクルで5500t、の合計1万トンです。
そのための重点取り組みとして、
家庭系ごみでは、「もうひと絞り運動」、紙類の分別収集の活性化、出前講座や食品ロス削減の取り組みがあげられています。事業系ごみの発生抑制では、多量排出事業者への啓発、「30・10運動」の活用などです。
以下、お聞きします。
寝屋川市の可燃ゴミ量は、計画通りに減少しておらず、このままでは、平成30年稼働予定の新焼却炉の能力を超えてしまう状況です。
また、ゴミ減量市民アンケート結果で、「再商品化に、適さないその他プラは、サーマルリサイクルに切り替えた方がいい」との、7割を超える市民の声に、応えるためにも、可燃ゴミの減量は、待ったなしの課題と言えます。
市は「ごみ減量緊急事態宣言」を行い、「ごみ減量・プロジェクト」で、今年から3年間で、可燃ごみを約1万トン減らすとしています。
1万トンの内訳は、家庭ゴミの ①手つかずの食品(6.9%)削減で2300t、②生ゴミ(34.4%)の水分20%削減で2300t ③紙類の分別リサイクルで5500t、の合計1万トンです。
そのための重点取り組みとして、
家庭系ごみでは、「もうひと絞り運動」、紙類の分別収集の活性化、出前講座や食品ロス削減の取り組みがあげられています。事業系ごみの発生抑制では、多量排出事業者への啓発、「30・10運動」の活用などです。
以下、お聞きします。
まず、1万トンのごみ減量目標の達成には、行政と市民と事業者が一体となって進めることが重要です。そのための3つ基本について、お聞きします。
★第1は、行政からの日常的な発信についてです。
日頃から、機会をとらえて、市民団体や自治会、事業者団体とコミュニケーションや連携をはかり、ごみ減量への理解を深めてもらう努力、市民と情報を共有する姿勢が、ごみ減量の取り組みを進めるにあたって、市民や事業者の共感を生む基礎となる考えます。
日頃から、機会をとらえて、市民団体や自治会、事業者団体とコミュニケーションや連携をはかり、ごみ減量への理解を深めてもらう努力、市民と情報を共有する姿勢が、ごみ減量の取り組みを進めるにあたって、市民や事業者の共感を生む基礎となる考えます。
★ 第2に、まち全体の雰囲気作りについてです。
毎日の買い物や、通勤、職場、学校や大学、また外食での店や、遊び場など、市民の日常生活の中に、ごみ減 量の意義や取り組みが目に付くことが必要だと思います。
毎日の買い物や、通勤、職場、学校や大学、また外食での店や、遊び場など、市民の日常生活の中に、ごみ減 量の意義や取り組みが目に付くことが必要だと思います。
★ 第3は、行政自らのごみ減量への取り組み姿勢についてです。
市役所、総合センター、小・中学校、をはじめとする、市内の公共施設すべてが、ごみ減量にむけてしっかり取り組んでいるという姿勢を市民に示すことが大事だと考えます。
以上、見解をお聞きします。
市役所、総合センター、小・中学校、をはじめとする、市内の公共施設すべてが、ごみ減量にむけてしっかり取り組んでいるという姿勢を市民に示すことが大事だと考えます。
以上、見解をお聞きします。
次に、廃棄物減量等推進員制度についてです。
府内の過半数の自治体で、廃棄物処理法第5条の8 2項に基づいて「廃棄物減量等推進員制度」が実施されています。
実施している自治体の8割が、廃棄物減量等推進員(以下、ごみ減量推進員と言います)は、自治会や町内組織からの推薦です。
例えば、平成7年から、制度を実施している吹田市では、2年任期で市長の委嘱をうけ、市民のボランテア活動として、ごみ減量やリサイクルに取り組んでいます。
これまでの使い捨て社会を「もったいない」ということで、必要とする人に使ってもらったり、資源として繰り返し利用するリサイクル社会に、変えていくために 取り組んでいるとのことです。
29年度は、ごみ減量等推進員は300人で、自治会など、町内組織からの推薦です。
これまでの使い捨て社会を「もったいない」ということで、必要とする人に使ってもらったり、資源として繰り返し利用するリサイクル社会に、変えていくために 取り組んでいるとのことです。
29年度は、ごみ減量等推進員は300人で、自治会など、町内組織からの推薦です。
活動内容は、①各地区内における、分別とごみ減量、発生抑制の普及・啓発、②分別回収の徹底のための協力、 ③資源集団回収などの推進・啓発 ④市が行う住民へのPR活動への協力⑤研修会、各地区連絡会の活性化 ⑥地域の要望、提言等の市への伝達など、市と住民とのパイプ役としての活動です。
また、吹田市では、店頭キャンペーンや 市内で開催される不特定多数が参加するエコイベントでのごみ減量化宣言、地域の夏祭り、文化祭にゴミ減量などをPRする「のぼり」などを活用しての参加、普段の生活に取り入れているアイデアや、地域で取り組んでいる活動などを市民に伝え広げます。活動内容を知ってもらうため推進員だよりを発行しています。
高槻市を見てみますと、
ごみ減量推進員は、明確に、ごみ減量化のための自治会の窓口役として、自治会長から推薦をうけて選任されています。
推進員は、自治会と連携して、ごみの減量や分別に取組み、イベントなどの情報提供を担当します。所属する自治会の活動方針・内容・活動状況に合った合理的な活動を個々の自治会ごとにつくりあげていく、とされています。
ごみ減量推進員は、明確に、ごみ減量化のための自治会の窓口役として、自治会長から推薦をうけて選任されています。
推進員は、自治会と連携して、ごみの減量や分別に取組み、イベントなどの情報提供を担当します。所属する自治会の活動方針・内容・活動状況に合った合理的な活動を個々の自治会ごとにつくりあげていく、とされています。
本市では、ごみマイスター制度があり、現在、133人が認定されています。しかし、公表されていませんし、住んでいる地域での活動として、市からの要請もありません。
以下、お聞きします。
★本市でのごみマイスター制度と、法に基づく「廃棄物減量等推進員制度」との違いは、一つは、各地域に根ざした活動形態になっているのかどうか、2つ目には、住民をまきこんでの実践活動になっているか、どうかだと思います。
自治会や町内組織から 推薦される、ごみ減量推進員制度のよい点を取り入れることについて、検討をお願いし、見解をお聞きします。
★本市でのごみマイスター制度と、法に基づく「廃棄物減量等推進員制度」との違いは、一つは、各地域に根ざした活動形態になっているのかどうか、2つ目には、住民をまきこんでの実践活動になっているか、どうかだと思います。
自治会や町内組織から 推薦される、ごみ減量推進員制度のよい点を取り入れることについて、検討をお願いし、見解をお聞きします。
次に、エコショップ制度についてです。
エコショップ制度は、ごみ減量やリサイクル、エコに配慮した、取組みを行う事業者、お店などを市が認定、PRすることで、多くの市民に利用してもらい、もって、市民の意識啓発をはかり、ごみ減量などの取組が進むことを目的としています。
豊中市は、100店舗以上をエコショップに認定しています。
省エネやごみの減量につながる3R行動など、ごみの発生抑制、減量化に、積極的に取組むお店や、環境に配慮した販売方法やサービスの提供を行うお店が認定されています。
認定されると、 ロゴマークを使用しての広告ができます。
省エネやごみの減量につながる3R行動など、ごみの発生抑制、減量化に、積極的に取組むお店や、環境に配慮した販売方法やサービスの提供を行うお店が認定されています。
認定されると、 ロゴマークを使用しての広告ができます。
エコショップ認定店では、アルミ缶、スチール缶、牛乳パック、トレイ、ペットボトルの店頭回収ボックスを設置している店や、あるうどんやさんでは、ダシをとるかつお節を栄養価の高い有機肥料として活用、地域と連携して「食品リサイクル・ループ」に取り組んだりしています。
「食品リサイクル・ループ」とは、食品廃棄物を利用して、肥料や家畜の飼料をつくる事業」のことです。
「食品リサイクル・ループ」とは、食品廃棄物を利用して、肥料や家畜の飼料をつくる事業」のことです。
また、飲食店では、食品残渣の堆肥化、リターナブル瓶での飲み物の販売、ご飯の小盛り承ります、調理くずや食べ残しを出さない工夫をしている、地元の野菜を使った料理など、
もあります。
また、エコショップフェステバルでは、フードド ライブと言って、家庭で余っている食品を学校や職場に持ち寄り、まとめて、地域の福祉団体や施設、フードバンクに寄付する取り組みを行っています。今後、集まった食品は、社会福祉協議会を通じて、こども食堂などに、利用できないか検討するとのことです。
もあります。
また、エコショップフェステバルでは、フードド ライブと言って、家庭で余っている食品を学校や職場に持ち寄り、まとめて、地域の福祉団体や施設、フードバンクに寄付する取り組みを行っています。今後、集まった食品は、社会福祉協議会を通じて、こども食堂などに、利用できないか検討するとのことです。
堺市のエコショップ制度では、ごみ減量化・リサイクルに積極的に取り組む小売店や飲食店に、エコショップマークを交付、食べ残しを減らす取組として、ハーフサイズメニューの設定、生ゴミの堆肥化、ばら売り、量り売り、消費者へのごみ減量・リサイクルのよびかけなどをおこなっている店を認定しています。
堺市のエコショップマークです。実物はこんなに大きくはありません。
キャラクターが載っています。
キャラクターが載っています。
以下お聞きします。
★ 寝屋川市が認定しているエコショップは、11店舗7社で、全てスーパーです。店頭回収を増やしていくことも含め、街のいたるところに、エコショップがあれば、ごみ減量の意識啓発を進めることに効果的だと考えます。
市民からよく目立つ駅前や商店街も含めて、飲食店や小売り店、オフィスなどへの拡大について、お考えをお聞きします。
市民からよく目立つ駅前や商店街も含めて、飲食店や小売り店、オフィスなどへの拡大について、お考えをお聞きします。
次に、オフィスペーパーの分別についてです。
ごみ分析調査結果では、オフィスビルのごみは、66.2%が紙類で、うち41.1%がリサイクル可能な紙であることからも、分別の徹底で効果が期待できます。
★ そこで、オフィスペーパーの分別対策は、地域と同じように、会社ごとに出前講座 の案内や、ごみ減量への協力のお願いに出向くなど、具体的な取り組みの方向をお聞きします。
次に、多量排出事業者制度についてです。
この制度は、多量排出事業者に対して、責任者を決め、「減量化計画書」提出と、実績報告を義務づけ、ごみ減量の指導や助言を行うものです。
本市も、毎年1回、「減量等計画書」の提出と「管理責任者」の届け出をお願いしています。しかし、現状は、計画書の提出や実績報告を怠る事業者に対して、きめ細かな指導、助言までに至っていないケースが多くあります。
本市も、毎年1回、「減量等計画書」の提出と「管理責任者」の届け出をお願いしています。しかし、現状は、計画書の提出や実績報告を怠る事業者に対して、きめ細かな指導、助言までに至っていないケースが多くあります。
多量排出者制度の対象については、自治体間で大きな違いがあります。
本市は、1か月の排出量が、5tもしくは、45リットル入り袋600 個(約4.8t)以上を対象としており、対象事業者は、78事業者で、減量計画によれば、市内事業所ごみの約3割弱を占めるとのことです。
他市では、 例えば、高槻市や堺市は、排出量月1t以上です。吹田市は月2t以上、 枚方市では月2.5t以上となっています。
★ 本市の、月4.8~5t以上というのは、他市と比べて、対象事業者が少ない基準です。対象を広げることによる、デメリットがあればお示しください。
本市は、1か月の排出量が、5tもしくは、45リットル入り袋600 個(約4.8t)以上を対象としており、対象事業者は、78事業者で、減量計画によれば、市内事業所ごみの約3割弱を占めるとのことです。
他市では、 例えば、高槻市や堺市は、排出量月1t以上です。吹田市は月2t以上、 枚方市では月2.5t以上となっています。
★ 本市の、月4.8~5t以上というのは、他市と比べて、対象事業者が少ない基準です。対象を広げることによる、デメリットがあればお示しください。
★ また、多量排出事業者の指導について、課題や取組方向をお聞きします。
次に、食品ロスについてです、
新食品リサイクル法では、「市町村は、食品資源の再生利用や家庭からの食品廃棄物の発生抑制、再生利用等について、地域の実情に応じて促進するよう、必要な措置を講ずるように努める」ものとされています。
28年3月公表の全国の「実態調査」では、食品関連事業者への食品ロスの発生抑制や再生利用について、指導や啓発をしていない自治体が69%に上っています。
今後とも、官民をあげた、食品ロス削減の推進が求められています。
以下お聞きします。
新食品リサイクル法では、「市町村は、食品資源の再生利用や家庭からの食品廃棄物の発生抑制、再生利用等について、地域の実情に応じて促進するよう、必要な措置を講ずるように努める」ものとされています。
28年3月公表の全国の「実態調査」では、食品関連事業者への食品ロスの発生抑制や再生利用について、指導や啓発をしていない自治体が69%に上っています。
今後とも、官民をあげた、食品ロス削減の推進が求められています。
以下お聞きします。
まず、飲食街の 食べ残し対策についてです。
飲食街での、作りすぎ、食べ残しが11.2%あります。
「30・10運動」は、「残さず食べよう」ということで、宴会などで、乾杯後30分は席を立たず料理を食べる、お開き前10分は、自分の席に戻って食べよう」という運動です。
松本市では、「残さずに食べよう」推進店認定制度を発足し、認定店では、宴会の品目を減らす、持ち帰り容器の提供、ハーフサイズ・小盛メニュー、ご飯の量の調整、店での「残さず食べよう運動」のアナウンスなどを行なっています。
「30・10運動」は、「残さず食べよう」ということで、宴会などで、乾杯後30分は席を立たず料理を食べる、お開き前10分は、自分の席に戻って食べよう」という運動です。
松本市では、「残さずに食べよう」推進店認定制度を発足し、認定店では、宴会の品目を減らす、持ち帰り容器の提供、ハーフサイズ・小盛メニュー、ご飯の量の調整、店での「残さず食べよう運動」のアナウンスなどを行なっています。
★30・10運動については、商業団体へ周知 をするとのことですが、具体化について、お聞きします。
次に、スーパーの売れ残り食品についてです。
スーパーからの食品ごみのうち、30%が売れ残り食品です。基本的には、売れ残り食品を可燃ごみに出さないような、企業努力をお願いすることです。しかし、「3割は売れ残る」ことを計算して、製造、販売しているという経営手法だともいわれています。
スーパーからの食品ごみのうち、30%が売れ残り食品です。基本的には、売れ残り食品を可燃ごみに出さないような、企業努力をお願いすることです。しかし、「3割は売れ残る」ことを計算して、製造、販売しているという経営手法だともいわれています。
まだ、安全に食べることができるにもかかわらず、さまざまな理由で、市場性を失い、捨てられる食品ロスが、年間約630トン発生しています。これは全世界の食料援助量に匹敵する量だといわれています。
賞味期限が迫って、売れなくなった商品や、家庭で余っている食品を集め、団体や施設を通じて福 祉的に利用する、「フードバンク」の取り組みが、全国で広がっています。
賞味期限が迫って、売れなくなった商品や、家庭で余っている食品を集め、団体や施設を通じて福 祉的に利用する、「フードバンク」の取り組みが、全国で広がっています。
平成25年に40団体だったのが、今年1月では77団体に増えています。
大阪には、認定法人 ふーどばんくおおさか( 堺市東区 大阪食品流通センター内)があり、ホームページなどで、食品の提供企業の募集、ボランテアの募集が呼びかけられています。
大阪には、認定法人 ふーどばんくおおさか( 堺市東区 大阪食品流通センター内)があり、ホームページなどで、食品の提供企業の募集、ボランテアの募集が呼びかけられています。
★ そこで、市内のスーパーなどが、フードバンクなどを活用して、売れ残り商品をなくし、可燃ごみの発生を減らすことが、できないでしょうか。お考えをお聞きします。
次に、家庭からでる、手つかずの食品についてです。
2300トンが削減目標です。
市の広報やイベントなどで、手つかず食品をなくす取組を紹介するとされています。
現在、賞味期限切れの食品は、家庭では、可燃ごみに出しています。
お中元などで、使わない食品をもらった場合でも、処分を試案した結果、結局、可燃ごみしか、ないというのが現実です。
京都府は、ごみ問題に詳しい学識経験者、飲食業、消費者団体などの関係者で、この6月に「食品ロス削減府民会議」を発足させました。
食品ロス削減を盛り込んだ「第3次 府食育推進計画」に基づくものです。
推進にあたっては「幅広い関係者の協力と、府民を広く巻き込んだ運動が必要」としており、「フードバンクへの提供が、福祉に役立つことを広く知ってもらいたい」という、情報発信などを検討するとしています。
市の広報やイベントなどで、手つかず食品をなくす取組を紹介するとされています。
現在、賞味期限切れの食品は、家庭では、可燃ごみに出しています。
お中元などで、使わない食品をもらった場合でも、処分を試案した結果、結局、可燃ごみしか、ないというのが現実です。
京都府は、ごみ問題に詳しい学識経験者、飲食業、消費者団体などの関係者で、この6月に「食品ロス削減府民会議」を発足させました。
食品ロス削減を盛り込んだ「第3次 府食育推進計画」に基づくものです。
推進にあたっては「幅広い関係者の協力と、府民を広く巻き込んだ運動が必要」としており、「フードバンクへの提供が、福祉に役立つことを広く知ってもらいたい」という、情報発信などを検討するとしています。
環境部のみならず、市として、フードバンクなどの活用を視野に入れた研究を行なうことを強く要望しておきます。
次に、資源集団回収についてです。
家庭ごみのうち、リサイクル可能な紙類16.1%、約5500tの減量が課題です。
集団回収した、新聞、雑誌、ダンボール、古着、アルミ缶、牛乳パック、ざつ紙などは、寝屋川市を経由せず、直接リサイクル業者が買い取り、資源化されます。
従って、集団回収の量が増えることが、ごみ排出量と可燃ごみの減量に直結しています。
家庭ごみのうち、リサイクル可能な紙類16.1%、約5500tの減量が課題です。
集団回収した、新聞、雑誌、ダンボール、古着、アルミ缶、牛乳パック、ざつ紙などは、寝屋川市を経由せず、直接リサイクル業者が買い取り、資源化されます。
従って、集団回収の量が増えることが、ごみ排出量と可燃ごみの減量に直結しています。
資源集団回収の団体登録は、現在、自治会、老人会、こども会、PTAなど324団体です。
★集団回収に取り組んでいる、地域分布に基づく拡大の方向、さらなる啓発の方法について
お聞きします。
お聞きします。
次に、ごみ減量出前講座についてです。
6月21日、今年度新設の出前講座「寝屋川市のごみの現状と減量化の取り組み」に参加しました。前からの出前講座は、ごみの分別の仕方が主な内容でしたが、新しい講座は、寝屋川市のごみの現状と減量目標、どう減らしていくかなどが説明されています。
地域や市民団体が主催して、できるだけ多くの人に広げていくことが課題です。
参加者から「地域では分別が徹底されていない」や、今年度の新しい講座の開催数がこの日で2回目で次の予約が入っていないなど、低調であることから「市が直接、自治会などのに、働きかけたら良いのではないか」や「もっと気軽に講座が開けないのか」などの意見が出されました。
6月21日、今年度新設の出前講座「寝屋川市のごみの現状と減量化の取り組み」に参加しました。前からの出前講座は、ごみの分別の仕方が主な内容でしたが、新しい講座は、寝屋川市のごみの現状と減量目標、どう減らしていくかなどが説明されています。
地域や市民団体が主催して、できるだけ多くの人に広げていくことが課題です。
参加者から「地域では分別が徹底されていない」や、今年度の新しい講座の開催数がこの日で2回目で次の予約が入っていないなど、低調であることから「市が直接、自治会などのに、働きかけたら良いのではないか」や「もっと気軽に講座が開けないのか」などの意見が出されました。
★ 市内の199の自治会や、老人会、子ども会 などに出前講座の開催をお願いすることについての、現状と課題をお聞きします。
★次に、雑がみ回収袋など、市民への啓発媒体についてです。
2県62市区が、雑がみ回収袋を作成、配布しています。
雑がみ回収袋には、雑紙の出し方、主な雑がみの品目と絵、対象外の品目と絵などが印刷されています。3R,4Rの啓発情報や、雑がみの回収拠点の一覧表や地図を掲載している自治体もあります。
これは、天童市の雑がみ回収袋です。集団回収の場所が印刷されています。
こちらには、雑がみの品目などの絵があります。
雑がみ回収袋には、雑紙の出し方、主な雑がみの品目と絵、対象外の品目と絵などが印刷されています。3R,4Rの啓発情報や、雑がみの回収拠点の一覧表や地図を掲載している自治体もあります。
これは、天童市の雑がみ回収袋です。集団回収の場所が印刷されています。
こちらには、雑がみの品目などの絵があります。
このように、雑がみ回収袋は、たんなる回収容器としての機能に加えて、ごみ減量やリサイクルの、貴重な啓発媒体として活用されています。
★本市でも、ごみ減量やリサイクルの啓発媒体について、研究をお願いし、見解をお聞きします。
★本市でも、ごみ減量やリサイクルの啓発媒体について、研究をお願いし、見解をお聞きします。
次に、生ゴミ対策についでです。
ごみ減量実施計画では、家庭ごみの34.4%をしめる生ゴミの水分を現状の80%から60%へ減らすことで、2300トンの削減を目標にしています。
水切り器クードをはじめ、市民の独自の手法による「もうひと絞り運動」の広がりが求められます 。
私たちの毎日の暮らしの中で、また事業者の方のもう一工夫で、生ゴミの重量が減ることになりますので、あらゆる機会をとらえて、訴えていくことが肝心です。
生ごみ自体については、生物系資源なので、時間とともに必ず腐敗します。本来、燃やさなくても、土にもどるものです。 都市部におけるごみ減量のカギは、「生ごみの資源化」だとも言われています。
以下、お聞きします。
水切り器クードをはじめ、市民の独自の手法による「もうひと絞り運動」の広がりが求められます 。
私たちの毎日の暮らしの中で、また事業者の方のもう一工夫で、生ゴミの重量が減ることになりますので、あらゆる機会をとらえて、訴えていくことが肝心です。
生ごみ自体については、生物系資源なので、時間とともに必ず腐敗します。本来、燃やさなくても、土にもどるものです。 都市部におけるごみ減量のカギは、「生ごみの資源化」だとも言われています。
以下、お聞きします。
★ 生ゴミの自家処理については、屋外用コンポストや室内用の電気処理機や電気ママポート、これは流しに直結していて、そのまま乾燥、細分化されるものです、多くの市民が堆肥化に取り組めば、生ゴミの可燃ごみは削減できます。
大きな効果をあげている都市部での事例が、なかなか、見つかりませんが、コンポストの普及や堆肥化の地道なPRと、引き続く研究をお願いし、見解をお聞きします。
大きな効果をあげている都市部での事例が、なかなか、見つかりませんが、コンポストの普及や堆肥化の地道なPRと、引き続く研究をお願いし、見解をお聞きします。
次に、ごみ減量での市民団体との連携についてです。
★ 例えば、吹田市では、市民研究所として、公益財団法人「千里リサイクルプラザ」が活 動しています。
市民研究員が、生活者の視点で、ごみ減量についての、社会実験や実践活動を伴う調査・研究活動を行っています。イベント用の、リユース食器の貸し出しも行っています。
本市においても、「もったいない」を合い言葉にして、ごみ減量化に取り組んでいる団体や、グループがあります。そういう市民団体と、連携してごみ減量・資源化を進めることが、必要だと考え、見解をお聞きします。
市民研究員が、生活者の視点で、ごみ減量についての、社会実験や実践活動を伴う調査・研究活動を行っています。イベント用の、リユース食器の貸し出しも行っています。
本市においても、「もったいない」を合い言葉にして、ごみ減量化に取り組んでいる団体や、グループがあります。そういう市民団体と、連携してごみ減量・資源化を進めることが、必要だと考え、見解をお聞きします。
次に、拡大生産者責任(EPR)についてです。
拡大生産者責任とは、製品の使用後の回収やリサイクル、処分の費用を、製品コストとして生産者(企業)に負担させる考え方です。
企業は、コスト削減のため、環境負荷が少なく、再利用できる製品の開発 を進めます。製品の廃棄処分まで、生産者の責任を拡大するので、拡大生産者責任と呼ばれています。
拡大生産者責任とは、製品の使用後の回収やリサイクル、処分の費用を、製品コストとして生産者(企業)に負担させる考え方です。
企業は、コスト削減のため、環境負荷が少なく、再利用できる製品の開発 を進めます。製品の廃棄処分まで、生産者の責任を拡大するので、拡大生産者責任と呼ばれています。
ドイツでは、「廃棄物回避・処理法」などの法律で、環境への負担を、少なくする製品を生産者に義務づけ、生産者が設計段階から、廃棄物発生を最小化するルールをつくりました。
日本では、拡大生産者責任の政策が遅れています。循環型社会形成推進基本法に、拡大生産者責任の考えが入ってはいますが、「技術的及び経済的に可能な範囲で」などの限定条件がつけられています。
この拡大生産者責任の弱さは、ごみ減量・再資源化に困難をもたらしています。
設計・生産段階からゴミを減らすという仕組みがありません。従って、リサイクルする量を増やしても、生産量の増加の方が上まわって、ごみが増えるというイタチごっこが続いています。
設計・生産段階からゴミを減らすという仕組みがありません。従って、リサイクルする量を増やしても、生産量の増加の方が上まわって、ごみが増えるというイタチごっこが続いています。
拡大生産者責任の原則から、飲料メーカーや容器の製造事業者に対し、ペットボトルなどの出荷量全量に対応した再資源化を義務づけ、ペットボトルの回収・運搬・保管などの費用をメーカー負担とすることが求めらています。
★現在のごみ問題の解決には、「出てきたごみを適正に対処する」という対応では、もはや限界であり、物の製造段階にまでさかのぼった対策が必要となっています。このことから、 拡大生産者責任が現実化することが求められます。お考えをお聞きします。
次に、海洋ごみについてです。
環境省による「海洋ごみとマイクロプラスチックに関する調査結果」が公表されています。
海洋ごみで一番やっかいなのが、ペットボトルなどのプラスチック製のごみで、野生動物に大きな影響を与えています。
プラスチックは、時間がたっても自然分解せず、紫外線や温度変化・時間の経過によって、劣化し、細かい破片(マイクロプラスチック)になることで、生態系や環境に大きな影響を与えるものです。
ペットボトルなどのプラスチックを、山や川にポイ捨てしないことはもとより、分別・リサイクルが必要です。しかし、リサイクルは持続的な解決策ではなく、プラスチック自体を減らす必要があることが世界的に摘されています。
海洋ごみで一番やっかいなのが、ペットボトルなどのプラスチック製のごみで、野生動物に大きな影響を与えています。
プラスチックは、時間がたっても自然分解せず、紫外線や温度変化・時間の経過によって、劣化し、細かい破片(マイクロプラスチック)になることで、生態系や環境に大きな影響を与えるものです。
ペットボトルなどのプラスチックを、山や川にポイ捨てしないことはもとより、分別・リサイクルが必要です。しかし、リサイクルは持続的な解決策ではなく、プラスチック自体を減らす必要があることが世界的に摘されています。
● 次に、情報公開などについてです。
市民が「住み続けたいと思うまちづくり」、「親切な市役所」、また、「市民の協力、市民参加のまちづくり」をめざす立場から、情報公開についてお聞きします。
第1は、市役所からの文書や通知についてです。
字が小さい、わかりにくいなどの声が寄せられています。とりわけ、高齢者世帯や、一人暮らしの高齢者からの要望です。
第1は、市役所からの文書や通知についてです。
字が小さい、わかりにくいなどの声が寄せられています。とりわけ、高齢者世帯や、一人暮らしの高齢者からの要望です。
★「字を大きくして」、「見出しは的確に」、「専門用語については、わかりやすい説明を入れる」など、市民の意見を取り入れての、具体的な改善をお願いし、見解をお聞きします。
★また、市民が困った時に利用できる各種減免制度については、どんな場合に利用できるのか、など、わかりやすく、掲載してほしいとの声を聞いています。
また、文字ばかりの文書の中に書いてあって、全部読まないとわからないのではなく、見出しを工夫するなど改善してほしいとの要望について、見解をお聞きしま す。
また、文字ばかりの文書の中に書いてあって、全部読まないとわからないのではなく、見出しを工夫するなど改善してほしいとの要望について、見解をお聞きしま す。
第2に、各種審議会等についてです。
★まず、公開されている各種審議会等の、会議資料の公開についてです。
例えば、先日、開催された「ごみ減量化・リサイクル推進会議」は、翌日には、会議に出された資料が、ホームページに掲載されています。
市民が、傍聴に行けなくても、どのようなことが議題だったのか、どんな資料が出されたのかがわかるということです。
審議会を担当している課によって、違いがあると思いますが、すみやかに会議資料を公開することを求め、見解をお聞きします。
例えば、先日、開催された「ごみ減量化・リサイクル推進会議」は、翌日には、会議に出された資料が、ホームページに掲載されています。
市民が、傍聴に行けなくても、どのようなことが議題だったのか、どんな資料が出されたのかがわかるということです。
審議会を担当している課によって、違いがあると思いますが、すみやかに会議資料を公開することを求め、見解をお聞きします。
★次に、会議録の公開については、
一定の時間がかかることは理解できます。市としての統一的な目安があるのかどうか、お聞きします。構成する委員が全て外部の委員である場合など、状況によっては、時間と手間がかかることも理解できますので、何パターンかでも結構ですので、目安をお示しください。
一定の時間がかかることは理解できます。市としての統一的な目安があるのかどうか、お聞きします。構成する委員が全て外部の委員である場合など、状況によっては、時間と手間がかかることも理解できますので、何パターンかでも結構ですので、目安をお示しください。
★次に、事前の資料配布については、
ある審議会では、郵便で送られてくる議案や資料が、手元に届くのが遅いとの声を聞きました。これについてもも目安は何日前なのかなど、改善されるように求め、見解をお聞きします。
ある審議会では、郵便で送られてくる議案や資料が、手元に届くのが遅いとの声を聞きました。これについてもも目安は何日前なのかなど、改善されるように求め、見解をお聞きします。
●その他で2点お聞きします。
まず、国民年金についてです。
国民年金制度は、40年間保険料を納めた人が受給できる「満額年金」でさえ、月6万5741円で、生活保護の生活扶助基準額を下回り、老後の生活保障の役割を果たせない、不十分な制度となっています。年金制度については、最低年金保障制度の創設など、抜本的な改善が求められているところです。
国民年金制度は、40年間保険料を納めた人が受給できる「満額年金」でさえ、月6万5741円で、生活保護の生活扶助基準額を下回り、老後の生活保障の役割を果たせない、不十分な制度となっています。年金制度については、最低年金保障制度の創設など、抜本的な改善が求められているところです。
今回、年金制度が改正され、年金を受け取れる「資格期間」が25年以上だったのが、今年8月から 、10年に短縮されます。
新たに年金を受け取れるようになる10年以上25年未満の資格期間の人には、日本年金機構から年金請求書が郵送されています。
また、年金加入期間が10年未満の人は、対応によっては、10年の資格を得られる人が、います。
まず、加入期間の漏れがないか調べること、第2に、60才~65才までは、10年に不足する期間を任意加入できます。昭和40年4月1日以前に生まれた人は、70才まで加入できます。第3に、保険料後納制度を使い未納期間分を支払うことができます。
これらの方には、日本年金機構から年内をメドにお知らせが送付される予定です。
そこで、
★ 市として、対象となる市民が年金を受給できるように、最善 の対応をお願いし、見解をお聞きします。
新たに年金を受け取れるようになる10年以上25年未満の資格期間の人には、日本年金機構から年金請求書が郵送されています。
また、年金加入期間が10年未満の人は、対応によっては、10年の資格を得られる人が、います。
まず、加入期間の漏れがないか調べること、第2に、60才~65才までは、10年に不足する期間を任意加入できます。昭和40年4月1日以前に生まれた人は、70才まで加入できます。第3に、保険料後納制度を使い未納期間分を支払うことができます。
これらの方には、日本年金機構から年内をメドにお知らせが送付される予定です。
そこで、
★ 市として、対象となる市民が年金を受給できるように、最善 の対応をお願いし、見解をお聞きします。
次に、減免制度、猶予制度の周知についてです。
納付率は48.3%と低い状態です。減免制度や、若年者猶予制度の対象が30才から50才までに改正されたことなどを、知らない市民もいます。
★ 国民年金保険料の減免制度、猶予制度について、市民へのわかりやすい周知をお願いし、見解をお聞きします。
納付率は48.3%と低い状態です。減免制度や、若年者猶予制度の対象が30才から50才までに改正されたことなどを、知らない市民もいます。
★ 国民年金保険料の減免制度、猶予制度について、市民へのわかりやすい周知をお願いし、見解をお聞きします。
最後に、野良猫対策についてです。
地域の野良猫問題は、猫好きな人がえさをやり、猫が増えて、糞尿被害となり、ご近所同士のコミュニティに支障がおこるという、放置できない問題です。
当面の対策としては、野良猫を増やさないために、野良猫を捕獲して避妊・去勢手 術を行うこと、避妊・去勢手術をしていない飼い猫は外に出さないこと、えさは猫ごとに直接与えて、置きえさはしないこと、などのルールを地域で確認していくことが必要になります。
担当課の日常的ながんばりを評価した上で、以下、3点お聞きします。
担当課の日常的ながんばりを評価した上で、以下、3点お聞きします。
★1.自治会内で回覧する「置きえさをしない」などの市としての文書が必要です。
★2.啓発ポスターの検討結果について。
★3.今年度の環境部の基本方針である「野良猫を地域で管理し、糞尿被害の解決、「地域猫事業」の創設」について、内容や今後のスケジュール、関係者への周知などについて、お考えをお聞きします。
★2.啓発ポスターの検討結果について。
★3.今年度の環境部の基本方針である「野良猫を地域で管理し、糞尿被害の解決、「地域猫事業」の創設」について、内容や今後のスケジュール、関係者への周知などについて、お考えをお聞きします。
以上で、質問を終わります。尚、再質問は自席にておこないます。