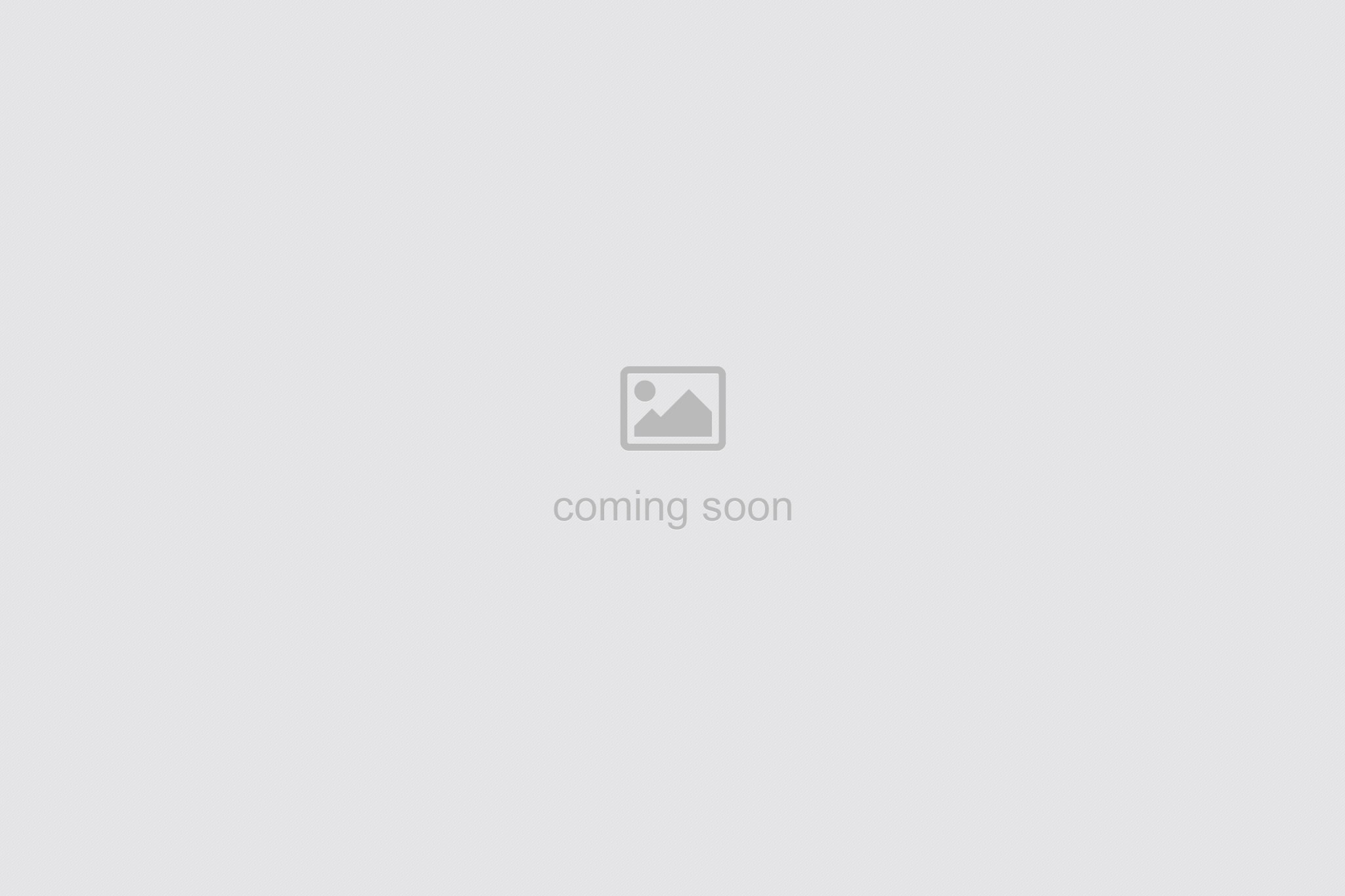2013年12月議会 一般質問 中谷市議
2013-12-17
●平和・人権・民主主義について
1.無言館、松代大本営跡を見学して
先日、長野県にある無言館と松代大本営跡を見学しました。無言館は、全国でも希有な戦没画学生の展示館です。無謀な戦争に駆り出され命を奪われた、才能ある若い美術家の無念を想いました。
1944年、敗戦が続く中、国は、天皇を最高指揮官とする大本営を、松代の神田川沿いの象山や舞鶴山、皆神山がある地域に移すことを決めました。連日1万人の突貫工事によって地下壕が掘りめぐらされ、1945年敗戦まで建設が続きました。政府機関やNHKなどの部屋、天皇や皇后の御座所が造られるまで、天皇を守る盾として、島ぐるみの沖縄戦が強いられ、50万を超える米軍への抵抗で多大の犠牲者が出ました。結局大本営建設は、敗戦で未完成のまま、証拠隠滅が図られました。今年に入って、象山地下壕説明板の朝鮮人を強制動員した「強制」の二文字が白いテープで隠されました。日本軍「慰安婦」の否定、「特定秘密保護法」の強行など、戦前と変わらない日本に戻そうとする安倍政権の危険な動きとダブって、憤りでいっぱいになりました。
2.憲法を壊す「戦争する国づくり」の安倍自公政権の暴走
今回の臨時国会ほど、政府・与党が横暴の限りを尽くした国会はありません。この間、大阪では、「大阪維新の会」の橋下徹氏などが、選挙で多数を得て有権者から白紙委任されたと、公約も憲法、法律も無視をして、「自分が行うことが民意だ」と、独裁権力的な政治を行っています。この間の堺や岸和田などの市長選挙では、橋下「維新の会」に厳しい審判が下されました。橋下徹氏の指南役は安倍晋三氏だと言われてきました。今国会を見れば、安倍政権はまさに独裁権力的な政治そのものです。財界などが求める雇用や労働のルールのいっそうの規制緩和、社会保障のすべてに及ぶ改悪、そして、憲法が禁じる戦争のしくみづくりなど、審議を尽くせば、憲法の主権在民、基本的人権の尊重、平和主義、議会制民主主義、地方自治などの根本原則に違反することが明らかになる内容ばかりです。
アメリカからの要請を理由にした「国家安全保障会議(日本版NSC)」の設置は、アメリカの戦争司令部(NSC)をまねたものです。憲法9条は「戦争放棄」を謳い、そのために「戦力の放棄」と「戦争の否認」を定めています。「戦争司令部」の設置は、憲法違反そのものです。自民党の憲法草案では、第二章の「戦争放棄」を「安全保障」に変えて、「国防軍の創設」を謳っています。今回の安倍内閣の「国家安全保障会議」、「特定秘密保護法」、そして、今後予想される「武器輸出3原則の見直し」、「集団的自衛権の行使」、「安全保障基本法」などの暴走政治は、国民の多数が憲法9条にも96条にも改定反対の中、憲法を変えずに、国会の数の力で憲法違反の「戦争できる」数々の法律を作り、事実上憲法をなきものにする、戦後最大のファシズムの危険な状況です。
今回の「特定秘密保護法案」に対して、マス・メディア、弁護士会、言論・表現、学問、芸術などあらゆる分野で、多数の人が反対の声をあげています。戦前の苦い体験、さらには、法律がない現在でも、官僚による42万件を超える「秘密」指定があり、市民の言論・集会などが自衛隊の情報保全隊や公安警察などによって監視されている現状があるからです。現状を追認するだけでなく、「特定秘密保護法」では「何が秘密かも秘密」、行政機関の長の判断一つで「際限なく恣意的に秘密が拡大されかねない」おそれがあります。しかも、国権の最高機関である国会に「特定秘密の提供」をするときは「秘密会」に限り、内容を明らかにすれば国会議員でさえ懲役5年以下に処するなど、国会の国政調査権の侵害も甚だしい内容となっています。ましてや国民に公開される保証は具体的にはまったくありません。
また、秘密事項に関係する者は、公務員、民間人を問わず、「適性評価」としてプライバシーのすべてについて調査が行われます。人権侵害の当然視であり、許されるものではありません。
ジャーナリストの取材活動から一般市民の言論・表現まで、行政機関が「特定秘密」に関する漏洩、共謀、教唆、扇動などと判断すれば、懲役10年以下又は1千万円以下の罰金という重罰の対象にされます。裁判でも何の罪で問われたのかさえ「秘密」にされます。被告人も弁護士も争いようがないまま、重罰を受ける。まさに、戦前の治安維持法や軍機保護法などにつながる、国民の自由を奪う国民弾圧の立法そのものです。
主権在民や基本的人権の重要な権利とされている「知る権利」に照らして、そもそも原則、国民に「秘密」などあってはなりません。外交・防衛上、一定期間「非公開」にしなければならないことはあります。しかし、「軍事機密」として際限なく「特定秘密」を指定し、国民を取り締まるなどは、主権在民、基本的人権の尊重、平和主義などの現憲法下で絶対に許されません。
寝屋川市に考えてほしいことは、自治体に対する「秘密の提供」が一切考慮されていないことです。これまで、国民保護法にかかわって、小学校区単位で自主防災協議会の結成が促されてきました。住民の安全にかかわる「情報の提供」がないまま、市の職員が職務の必要から情報を得て市民に知らせたときに、「特定秘密」に指定された内容に関係していれば、罪に問われかねません。今回の「特定秘密保護法」は、まさに地方自治の危機にもつながっています。
寝屋川市としての見解をお聞きします。
3.「核兵器のない世界」をめざして
今開かれている第68回国連総会の第一委員会で、日本政府は、4月には拒否した「非人道的である核兵器はいかなる状況でも使用を許されない」とする共同声明に賛同しました。4月の80カ国から125カ国に増えました。「核兵器の全面禁止」を求める国際世論の発展による重要な成果です。しかし一方で、日本政府は、アメリカの「核の傘」に頼る立場を続けています。
今月5日の総会で、軍縮・国際安全保障問題を扱う第一委員会に関連する決議の採決が行われました。マレーシアなどが毎年提出している「核兵器禁止条約の交渉開始を求める」決議案が、賛成133,反対24、棄権25の賛成多数で採択されました。他にも、「核軍縮のための国際会議開催」や「核兵器使用禁止条約」の決議案も採択されましたが、日本政府は、これら3決議案に棄権しました。
今、一昨年2月15日に、国連事務総長などの賛同を得て、広島・長崎・東京の3都市で始まった「核兵器禁止条約の交渉開始を求める」国際署名運動が、各地で取り組まれています。2015年の核不拡散条約(NPT)再検討会議に向けて、700万目標です。2010年に届けた署名は、世界平和市長会議の署名とともに、国連の正面ロビーにツインタワーのように積み上げられています。また、広島市長や長崎市長をはじめ自治体の首長や議長などの賛同署名を重視し、国連に届けています。寝屋川でも市長や教育長、議長、各議員の賛同署名を心から呼びかけるものです。
●教育について
1.平和学習について
この数年間、寝屋川の教育は大きく変わってきています。そのひとつに、小学校の修学旅行があります。1970年代当初までは、多くの学校が伊勢・志摩でした。その後、平和学習を目的に、広島への修学旅行がどの学校でも当然のようになりました。どの学校でも、事前学習や学習発表会、運動会などで、広島への修学旅行・平和をテーマにした取り組みが行われました。今年は広島が一校だけでした。来年からは一校もないと聞いています。40年近い、広島への修学旅行を柱にした寝屋川の平和学習をどう総括・評価されていますか。お聞きします。
広島への修学旅行がなくなる一方で、初めて自衛隊岐阜基地を修学旅行先にした学校があることを知って驚きました。市教委への届では、指導事項として「戦争のない平和な国であり続けるためにどうすべきかを平和学習の一環として自衛隊を知る」となっています。「修学旅行のしおり」には、学習に関する内容はただの1行もありません。集団行動や集団生活に関する内容、日程だけです。市教委の見解をお聞きします。
学校長は昨年度から民間人校長です。学校長は、教員免許を持っていますか。また、就任にあたって、憲法遵守などの誓約書の提出はどうなっていますか。市教委は、組織マネジメント能力があるなどと説明してきましたが、学校長は教育行政の上意下達の役割を担う立場ではなく、直接子どもや保護者に教育責任を負う学校の代表者、教育者であるべきです。以上についての答弁を求めます。
次に自衛隊の認識についてお聞きします。
自衛隊の前身は、警察予備隊です。1950年(昭和25年)8月10日GHQのポツダム政令の一つである「警察予備隊令」により設置された武装組織です。6月25日に勃発した朝鮮戦争にアメリカ軍の日本駐留部隊を朝鮮半島に出動させたことにともない、マッカーサー元帥が吉田首相に対して、日本国内における戦争反対などの「事変・暴動などに備える治安警察隊」として、75,000名の創設を要望してつくられたものです。訓練は、基本的にアメリカ軍事顧問の監督下で行われました。
1952年(昭和27年)4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効し、ポツダム命令が失効することから、7月、日本政府は保安庁法を成立させ、独自の保安機関として、10月15日の保安隊発足につなげました。
1954年(昭和29年)3月に日米相互防衛援助協定が結ばれ、日本は「自国の防衛力の増強」という義務を負うことになり、6月の自衛隊法と防衛庁設置法の成立によって、7月に陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊の管理・運営を行う防衛庁が発足しました。自衛隊法第3条1項は(自衛隊の任務)を「・・・我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」としています。「間接侵略」は、時の権力者が、国民多数が政権を変える動きをしたときに、国民弾圧の口実にしかねないものです。これまでも、事実上の軍隊として、憲法違反にあたるかどうか、国民の中でも意見がわかれています。その後、「防衛計画大綱」を改定するたびに、「防衛費」という名の軍事費は増え続け、現在では、世界でも有数の軍事力を備え、毎年防衛省だけで約5兆円が「聖域」扱いで予算化されています。また、日米同盟は、世界でも数少なくなった軍事同盟そのものです。有事立法が次々と作られ、アフリカのジブチに初の海外自衛隊基地が造られました。海外任務が自衛隊の本務とされるようになっています。憲法9条の歯止めがなくなれば、アメリカと一緒に世界中どこにでも軍隊として戦争に行くようになりかねません。
簡単に警察予備隊から今日の自衛隊までの流れを述べましたが、小学校で「平和学習の一環として自衛隊を知る」ということについて、平和学習として、どんな教育成果が期待できると考えているのか、見解をお聞きします。
1.無言館、松代大本営跡を見学して
先日、長野県にある無言館と松代大本営跡を見学しました。無言館は、全国でも希有な戦没画学生の展示館です。無謀な戦争に駆り出され命を奪われた、才能ある若い美術家の無念を想いました。
1944年、敗戦が続く中、国は、天皇を最高指揮官とする大本営を、松代の神田川沿いの象山や舞鶴山、皆神山がある地域に移すことを決めました。連日1万人の突貫工事によって地下壕が掘りめぐらされ、1945年敗戦まで建設が続きました。政府機関やNHKなどの部屋、天皇や皇后の御座所が造られるまで、天皇を守る盾として、島ぐるみの沖縄戦が強いられ、50万を超える米軍への抵抗で多大の犠牲者が出ました。結局大本営建設は、敗戦で未完成のまま、証拠隠滅が図られました。今年に入って、象山地下壕説明板の朝鮮人を強制動員した「強制」の二文字が白いテープで隠されました。日本軍「慰安婦」の否定、「特定秘密保護法」の強行など、戦前と変わらない日本に戻そうとする安倍政権の危険な動きとダブって、憤りでいっぱいになりました。
2.憲法を壊す「戦争する国づくり」の安倍自公政権の暴走
今回の臨時国会ほど、政府・与党が横暴の限りを尽くした国会はありません。この間、大阪では、「大阪維新の会」の橋下徹氏などが、選挙で多数を得て有権者から白紙委任されたと、公約も憲法、法律も無視をして、「自分が行うことが民意だ」と、独裁権力的な政治を行っています。この間の堺や岸和田などの市長選挙では、橋下「維新の会」に厳しい審判が下されました。橋下徹氏の指南役は安倍晋三氏だと言われてきました。今国会を見れば、安倍政権はまさに独裁権力的な政治そのものです。財界などが求める雇用や労働のルールのいっそうの規制緩和、社会保障のすべてに及ぶ改悪、そして、憲法が禁じる戦争のしくみづくりなど、審議を尽くせば、憲法の主権在民、基本的人権の尊重、平和主義、議会制民主主義、地方自治などの根本原則に違反することが明らかになる内容ばかりです。
アメリカからの要請を理由にした「国家安全保障会議(日本版NSC)」の設置は、アメリカの戦争司令部(NSC)をまねたものです。憲法9条は「戦争放棄」を謳い、そのために「戦力の放棄」と「戦争の否認」を定めています。「戦争司令部」の設置は、憲法違反そのものです。自民党の憲法草案では、第二章の「戦争放棄」を「安全保障」に変えて、「国防軍の創設」を謳っています。今回の安倍内閣の「国家安全保障会議」、「特定秘密保護法」、そして、今後予想される「武器輸出3原則の見直し」、「集団的自衛権の行使」、「安全保障基本法」などの暴走政治は、国民の多数が憲法9条にも96条にも改定反対の中、憲法を変えずに、国会の数の力で憲法違反の「戦争できる」数々の法律を作り、事実上憲法をなきものにする、戦後最大のファシズムの危険な状況です。
今回の「特定秘密保護法案」に対して、マス・メディア、弁護士会、言論・表現、学問、芸術などあらゆる分野で、多数の人が反対の声をあげています。戦前の苦い体験、さらには、法律がない現在でも、官僚による42万件を超える「秘密」指定があり、市民の言論・集会などが自衛隊の情報保全隊や公安警察などによって監視されている現状があるからです。現状を追認するだけでなく、「特定秘密保護法」では「何が秘密かも秘密」、行政機関の長の判断一つで「際限なく恣意的に秘密が拡大されかねない」おそれがあります。しかも、国権の最高機関である国会に「特定秘密の提供」をするときは「秘密会」に限り、内容を明らかにすれば国会議員でさえ懲役5年以下に処するなど、国会の国政調査権の侵害も甚だしい内容となっています。ましてや国民に公開される保証は具体的にはまったくありません。
また、秘密事項に関係する者は、公務員、民間人を問わず、「適性評価」としてプライバシーのすべてについて調査が行われます。人権侵害の当然視であり、許されるものではありません。
ジャーナリストの取材活動から一般市民の言論・表現まで、行政機関が「特定秘密」に関する漏洩、共謀、教唆、扇動などと判断すれば、懲役10年以下又は1千万円以下の罰金という重罰の対象にされます。裁判でも何の罪で問われたのかさえ「秘密」にされます。被告人も弁護士も争いようがないまま、重罰を受ける。まさに、戦前の治安維持法や軍機保護法などにつながる、国民の自由を奪う国民弾圧の立法そのものです。
主権在民や基本的人権の重要な権利とされている「知る権利」に照らして、そもそも原則、国民に「秘密」などあってはなりません。外交・防衛上、一定期間「非公開」にしなければならないことはあります。しかし、「軍事機密」として際限なく「特定秘密」を指定し、国民を取り締まるなどは、主権在民、基本的人権の尊重、平和主義などの現憲法下で絶対に許されません。
寝屋川市に考えてほしいことは、自治体に対する「秘密の提供」が一切考慮されていないことです。これまで、国民保護法にかかわって、小学校区単位で自主防災協議会の結成が促されてきました。住民の安全にかかわる「情報の提供」がないまま、市の職員が職務の必要から情報を得て市民に知らせたときに、「特定秘密」に指定された内容に関係していれば、罪に問われかねません。今回の「特定秘密保護法」は、まさに地方自治の危機にもつながっています。
寝屋川市としての見解をお聞きします。
3.「核兵器のない世界」をめざして
今開かれている第68回国連総会の第一委員会で、日本政府は、4月には拒否した「非人道的である核兵器はいかなる状況でも使用を許されない」とする共同声明に賛同しました。4月の80カ国から125カ国に増えました。「核兵器の全面禁止」を求める国際世論の発展による重要な成果です。しかし一方で、日本政府は、アメリカの「核の傘」に頼る立場を続けています。
今月5日の総会で、軍縮・国際安全保障問題を扱う第一委員会に関連する決議の採決が行われました。マレーシアなどが毎年提出している「核兵器禁止条約の交渉開始を求める」決議案が、賛成133,反対24、棄権25の賛成多数で採択されました。他にも、「核軍縮のための国際会議開催」や「核兵器使用禁止条約」の決議案も採択されましたが、日本政府は、これら3決議案に棄権しました。
今、一昨年2月15日に、国連事務総長などの賛同を得て、広島・長崎・東京の3都市で始まった「核兵器禁止条約の交渉開始を求める」国際署名運動が、各地で取り組まれています。2015年の核不拡散条約(NPT)再検討会議に向けて、700万目標です。2010年に届けた署名は、世界平和市長会議の署名とともに、国連の正面ロビーにツインタワーのように積み上げられています。また、広島市長や長崎市長をはじめ自治体の首長や議長などの賛同署名を重視し、国連に届けています。寝屋川でも市長や教育長、議長、各議員の賛同署名を心から呼びかけるものです。
●教育について
1.平和学習について
この数年間、寝屋川の教育は大きく変わってきています。そのひとつに、小学校の修学旅行があります。1970年代当初までは、多くの学校が伊勢・志摩でした。その後、平和学習を目的に、広島への修学旅行がどの学校でも当然のようになりました。どの学校でも、事前学習や学習発表会、運動会などで、広島への修学旅行・平和をテーマにした取り組みが行われました。今年は広島が一校だけでした。来年からは一校もないと聞いています。40年近い、広島への修学旅行を柱にした寝屋川の平和学習をどう総括・評価されていますか。お聞きします。
広島への修学旅行がなくなる一方で、初めて自衛隊岐阜基地を修学旅行先にした学校があることを知って驚きました。市教委への届では、指導事項として「戦争のない平和な国であり続けるためにどうすべきかを平和学習の一環として自衛隊を知る」となっています。「修学旅行のしおり」には、学習に関する内容はただの1行もありません。集団行動や集団生活に関する内容、日程だけです。市教委の見解をお聞きします。
学校長は昨年度から民間人校長です。学校長は、教員免許を持っていますか。また、就任にあたって、憲法遵守などの誓約書の提出はどうなっていますか。市教委は、組織マネジメント能力があるなどと説明してきましたが、学校長は教育行政の上意下達の役割を担う立場ではなく、直接子どもや保護者に教育責任を負う学校の代表者、教育者であるべきです。以上についての答弁を求めます。
次に自衛隊の認識についてお聞きします。
自衛隊の前身は、警察予備隊です。1950年(昭和25年)8月10日GHQのポツダム政令の一つである「警察予備隊令」により設置された武装組織です。6月25日に勃発した朝鮮戦争にアメリカ軍の日本駐留部隊を朝鮮半島に出動させたことにともない、マッカーサー元帥が吉田首相に対して、日本国内における戦争反対などの「事変・暴動などに備える治安警察隊」として、75,000名の創設を要望してつくられたものです。訓練は、基本的にアメリカ軍事顧問の監督下で行われました。
1952年(昭和27年)4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効し、ポツダム命令が失効することから、7月、日本政府は保安庁法を成立させ、独自の保安機関として、10月15日の保安隊発足につなげました。
1954年(昭和29年)3月に日米相互防衛援助協定が結ばれ、日本は「自国の防衛力の増強」という義務を負うことになり、6月の自衛隊法と防衛庁設置法の成立によって、7月に陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊の管理・運営を行う防衛庁が発足しました。自衛隊法第3条1項は(自衛隊の任務)を「・・・我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。」としています。「間接侵略」は、時の権力者が、国民多数が政権を変える動きをしたときに、国民弾圧の口実にしかねないものです。これまでも、事実上の軍隊として、憲法違反にあたるかどうか、国民の中でも意見がわかれています。その後、「防衛計画大綱」を改定するたびに、「防衛費」という名の軍事費は増え続け、現在では、世界でも有数の軍事力を備え、毎年防衛省だけで約5兆円が「聖域」扱いで予算化されています。また、日米同盟は、世界でも数少なくなった軍事同盟そのものです。有事立法が次々と作られ、アフリカのジブチに初の海外自衛隊基地が造られました。海外任務が自衛隊の本務とされるようになっています。憲法9条の歯止めがなくなれば、アメリカと一緒に世界中どこにでも軍隊として戦争に行くようになりかねません。
簡単に警察予備隊から今日の自衛隊までの流れを述べましたが、小学校で「平和学習の一環として自衛隊を知る」ということについて、平和学習として、どんな教育成果が期待できると考えているのか、見解をお聞きします。
2.寝屋川市立小中学校への教員配置の改善について
文部科学省生涯学習政策局「地方教育費調査」(2009年)によると、児童1人当たりに支出された大阪府の公立小学校教育費は79万5159円で44番目です。生徒1人当たりの大阪府の公立中学校教育費は86万9931円で最下位です。学校教育費は、人件費や教育活動費、管理費などの消費的支出や、土地、建築、設備・備品、図書購入などの資本的支出、債務償還費など学校教育活動のために支出された公立学校の経費です。
こうした反映ですが、寝屋川の小中学校教職員の配置は、本来正規採用で配置すべき定数に対して、今年5月1日時点で、定数内講師が小学校で53人、中学校で74人となっています。教育は、継続性・系統性が重要な事業であり、最も基本となる教員の任期が1年期限の臨時対応など、原則的にあってはならないことです。時期によっては、欠員状態もあったと聞きます。最も講師割合が高い小学校は17.9%、中学校では30%にもなっています。「教育に臨時はない」と大阪府に強く求めるべきと考えます。また、産休、育休、病休などの代替講師の配置については、学校の責任ではなく、市教委の責任で空白期間を作ることがないように配置すべきと考えます。見解をお聞きします。
3.老朽化した学校の改修と施設・設備の充実の計画について
これまでも多くの議員が求めてきた課題に、老朽化したトイレ改修があります。また、教育現場では、特別教室のエアコン設置を願う声が強くなっています。優先的に行われてきた耐震化が完了すれば、水回り、床、窓、天井、壁などを含め、一定規模の年次的な改修計画が必要と考えます。見解をお聞きします。
4.教育を壊す管理と競争の教育の見直しについて
「教育改革」と称して、政府・文科省や自治体の首長が教育委員会の上に立って教育行政を行う動きがあります。公選制の教育委員会制度を壊してきた行き着く先でしょうか、教育委員会を首長が任命する教育長の諮問機関にする動きもあります。国が教育統制し、軍国主義につながる「忠君愛国」を押しつけた戦前の反省から、戦後は日本国憲法と教育基本法にもとづく「個人の尊重と人格の完成、平和・民主主義を担う主権者の育成」が基本にすえられました。今日では、国際社会の到達である「こどもの権利条約」をふまえ、「こどもたちの最善の利益」が教育と教育行政に求められています。
現実は、学校長や教職員の成績主義の徹底とともに、教科書の国定化や生活現実をみない「道徳」の強化、「いじめ」問題を利用したゼロ・トレランス(許容度ゼロ)政策、学力の一部でしかない「全国学力テスト」「大阪府学力テスト」「寝屋川市学習到達度調査」などの成績競争の強化、習熟度別学習、小学校からの英語教育、ICT教育など、新学習指導要領の下で、多忙化と学校教育に対する管理と競争の統制が進められています。
私は「教室はまちがうところだ」という詩が大好きです。こどもに限りませんが、人は重大な間違いは許されませんが、失敗や間違いを通じて学び成長するものです。今の低学力問題の課題の一つは、「学びの剥落現象」です。学力をつけるためには、習ったことをくり返し何度も使い、実践しなければなりません。生活の中で生きた使い方ができればそれにこしたことはありません。間違いを許さない、目先の点数だけを追い求めさせる、管理と競争の中では、本当の学力も人格も育ちません。
市教委は、各学校長に、全国学力テストの説明責任を果たすために成績結果の公表を求めていると聞きます。また、成績向上のためにどんな努力をするのか、面接をして求めているとも聞きます。教育の責任を直接持っているのは、各学校の教職員です。こどもと保護者の生活と願いを最もよく知っています。学校自主権の尊重こそ重要と考えます。教育行政の責務は、教育活動への介入ではなく、最善の教育環境を提供する条件整備です。
校長会、校長を通じての上意下達の教育行政姿勢を改めるよう求めます。
答弁を求めます。
5.社会教育の抜本的改善・充実について
生涯学習の観点から、社会教育施設、社会教育事業の充実が求められています。社会の豊かな発展を示す指標にもなると考えます。文部科学省生涯学習政策局の「社会教育調査報告書」(2007年度)によると、女性のみ対象の女性学級・講座数は、女性人口100万人当たり全国で755.3、大阪府は59.9で45位です。高齢者学級・講座数は、人口100万人当たり全国376.9、大阪府は42.4で46位です。社会教育施設は、児童から青年、成人、高齢者まで、すべての人を対象に、家庭や学校以外の場で、学習や研修、スポーツや趣味を楽しむ機会を提供するための生涯学習施設です。社会教育推進計画を策定するに当たり、住民自治を育てる公民館学習、生涯学習、平和学習の観点を重視するよう求めてきましたが、検討課題としていることを明らかにしてください。
6.第2期子どもの読書推進計画の策定について
図書館は国民の「知る権利」を保障するために必要不可欠な施設です。公立図書館の数と蔵書数は、事業水準の一定の指標です。2011年度の寝屋川市の人口1人当たりの蔵書数は、大阪府の統計では1.85冊、下から7番目です。蔵書数は442,842冊です。駅前図書館ができ、現在はどうなっていますか。
この間、図書館行政に関係して強く求めてきたのは、「第2期子どもの読書推進計画」の策定と学校図書館の充実です。計画の策定にあたっては、子どもの読書活動に取り組んでこられた関係者・関係団体の協力が必要と考えます。策定時期の目途と策定のための体制について明らかにして下さい。また、この間、全国的に「はだしのゲン」の閉架をめぐって社会問題になりましたが、学校図書館がいつでも利用できる開架状態になければ、図書館自体が閉架状態と言わなければなりません。人間形成に欠かせない「子ども読書」の重要性からも、専任司書の配置を国・府に求めるとともに、実現するまでの間、市独自の配置を検討すべきと考えます。見解をお聞きします。
●東部まちづくりについて
1.この間の答弁をふまえて
今回の質問にあたって、昨年6月議会からの議事録を読み返しました。また、今回、あらためて「ふるさとリーサム地区まちづくりを考える会」(以下、「考える会」と略す)の規約を見ました。順次質問します。
「考える会」の規約は、一昨年9月22日施行から、昨年6月25日施行で規約改正が行われています。どの部分が変更になったのか、明らかにして下さい。
(目的)第2条では、「本会は、・・・地元住民や関係者の皆さんが主体となって集まり、・・・地域特性を活かしたまちづくりを検討することを目的とする。」となっています。市が作ったとしか思えない文章です。答弁を求めます。
(会員の構成)第4条は、「役員と部会員で構成する。」となっています。
第5条(役員の構成)は、3つの自治会の役員から選出された者、その他本会が適当と認めた者、となっています。「考える会」役員の選出基盤は自治会の役員です。地元住民を代表する組織という場合、少なくとも、自治会に加入の全会員、また、会員外の人を含めた全住民に選出されたという事実が必要と考えます。市として、そうした事実を把握しておられますか。答弁を求めます。
第7条(役員会)では、「7 ・・・研究会を設置することができる。」となっています。「研究会」について、具体的に知っておられることがあれば、構成を含め明らかにしてください。
「8 ・・・市職員、有識者等のアドバイザーの出席を承認することができる。」となっています。通常考えられない内容です。市と「考える会」との関係はこの通りと考えてよいのですか。答弁を求めます。
(部会)として、第8条「地域特性を活かしたまちづくりについて、協力活動及び広報活動を行うため、部会を設置する。」として、「構成員は、役員会の役員が指名する者がなるものとする。」としています。第9条の(全体会議)の規程と合わせ、これでは、一部の役員による仲間内の組織と言わざるを得ないと考えます。所見をお聞きします。
また、「考える会」には相談役が置かれています。特別の存在かと思いますが、位置と役割について承知しておられることを明らかにして下さい。
「本会の事務局は、東部自治会館に置く」点については、現在、担当課に説明を求めています。
市は、「優先的取組エリア」について、東部地域の取組が広範囲であることから、「考える会」が「優先的に取り組むエリアを定めた」ことをふまえ、「構想」を作ったことを明らかにしました。しかし、「市営住宅の建て替え」や「小中一貫校」は市が主体的に検討すべき事項です。「考える会」の意向で「構想」を作るなどは、過去の主体性のない不公正な同和事業の復活を想起させるものです。一般行政から独立している教育行政が判断すべき「小中一貫校」構想をまち政策部として教育委員会に具体化を求めるなどの答弁にも、問題は明らかです。地元の意向と言いますが、具体的に「地元」とはどこなのか、明らかにして下さい。
市は、計画推進の庁内検討組織として、12部局の部長で検討委員会を組織してきました。任意事業である地域支援に市を挙げての体制をとったことはありますか。また、こうした判断は、首脳会議の決定なしには考えられません。答弁を求めます。
市は、支援の要請を受けて、まちづくりの会議に、平成22年度は2回、23年度は11回、24年度は28回参加しています。まさに急増です。その理由を明らかにして下さい。
次に、「まちなか再生エリア」の「まちづくり協議会」の地権者は178名と確認しながら、居住している住民の世帯数についてはわからないとしてきました。その後調査されましたか。地権者の地区内居住者数とともに明らかにしてください。また、把握する中で、聴取された住民の意見があれば、明らかにして下さい。
次に社会資本総合整備計画(地域住宅計画「寝屋川市域」)についてお聞きします。平成23年度~25年度の計画で、明和住宅内の耐震診断を実施されていると思いますが、現状と結果について明らかにしてください。
次に、議会に寄せられている地域住民有志からの「地籍調査及び『まちづくり』についての要望書」に関してお聞きします。
地籍調査についてです。私有財産にかかわる重要な調査ですが、「たった1回きり、1時間だけの説明会で終了・・・『明和北ブロック地籍調査説明会』での参加者は、土地所有者90戸のうち27名、ほか、借地人1名・・・本来は一戸のもれもなく十分な説明会をおこなう必要がある・・・」としています。また、市は、「寝屋川市まちづくり整備計画(案)の一環として地籍調査を行う」と説明していますが、「国土調査法」に基づく「地籍調査」は、国・府あわせて95%の補助金を受けて市町村が実施するものであり、本来、独自の事業と訴えています。実質3ヶ月間(9月中下旬~12月中下旬)の短期間で強行ではなく、一戸の漏れもない説明会をすることで、地籍調査もスムーズに行くとしています。説明会では、市から「市が指定した期間で行う地籍調査に協力すれば、費用は市が負担するが、期間を過ぎれば、30万円~百万円を超える個人の実費負担になる」と住民を脅すような発言があったとしています。説明会の状況と市の見解をお聞きします。
道路の拡幅問題についてです。「市道明和南北中央線」が近くにあることから、生活道路としては6m幅道路はいらない、4m未満で十分としています。また、当該住民の同意を得ずに無理のある拡幅・新設道路のコース設定の見直しを求めています。また、立ち退きを要請された当該借地人に対する居住権の明確な補償を求めています。また、「市道の拡幅に必要な土地を寄付するよう求める」旨の規定について、居住権の補償の十分な説明を求めています。見解をお聞きします。
「まちづくり整備計画(案)」では、「防災・救急対策」を理由にしていますが、協議会設立の総会では、「土地の評価を上げるため」との発言が最初にありました。市が支援すべきは、住民が住み続けることができるまちづくりが基本であり、地権者や土木建設業者の利益ありきの「地上げ」に手を貸すようなことがあってはなりません。市の見解をお聞きします。
2.PFIによる発注業務支援について
寝屋川市営住宅再編整備に係るPFI導入可能性調査業務委託についてです。「市営住宅の再編について、効果的かつ効率的に行うため、・・・民間活力の導入・・・」が目的とされています。プロポーザル方式で、コンソーシアムや企業連合の参加は受け付けないとして行われました。11月19日に業者選定が終わっていますが、応募したのは何社ありましたか。また、選定された「地域経済研究所」の採点結果は、150点満点中何点でしたか。次点の業者の点数は何点ですか。落札額、落札率はいくらですか。明らかにして下さい。
市は、建て替え予定の住宅に居住している人がいる限り、事業は行えないとしています。現在の市営住宅居住世帯数、うち、明和住宅に居住の世帯数、さらに建て替え計画地に居住の世帯数を答えてください。本来、公営住宅法では、居住世帯数を基本に建て替え計画が求められています。見解をお聞きします。
3.「まちなか再生エリア」における制度要綱(案)について
市は、当該地区が住宅市街地総合整備事業や密集市街地適用の要件を満たさないために、市独自の制度要綱によるとしています。地域住民の中には、「法令上の根拠がないため国や府の支援は得られない。市の単独事業となる。そこで市独自の制度要綱が必要になってくる。『寄付』『一定の負担を行う』というのは、寝屋川市から金を引き出すための策略。『エビでタイを釣る』ことが狙い。」との批判があります。「まちなか再生エリア」事業については要綱ではなく、事業の是非、適否を含め判断するためにも、議会議決を必要とする「条例(案)」にすべきと考えます。答弁を求めます。
●その他・・・交差点の信号の歩車分離について
この間、寝屋川駅前線道路の整備が進められてきましたが、京阪寝屋川市駅周辺の交差点の状況は、左折と直進が同じ車線になっており、八尾枚方線・外環状線にまで道路整備が進めば自動車通行量が増え、歩行者が多人数の時には、自動車の渋滞が頻繁に起こりかねません。これまで市駅周辺の交差点信号を少なくとも歩車分離にするよう改善を求めてきましたが、現在の進捗状況はどうなっていますか。明らかにしてください。
文部科学省生涯学習政策局「地方教育費調査」(2009年)によると、児童1人当たりに支出された大阪府の公立小学校教育費は79万5159円で44番目です。生徒1人当たりの大阪府の公立中学校教育費は86万9931円で最下位です。学校教育費は、人件費や教育活動費、管理費などの消費的支出や、土地、建築、設備・備品、図書購入などの資本的支出、債務償還費など学校教育活動のために支出された公立学校の経費です。
こうした反映ですが、寝屋川の小中学校教職員の配置は、本来正規採用で配置すべき定数に対して、今年5月1日時点で、定数内講師が小学校で53人、中学校で74人となっています。教育は、継続性・系統性が重要な事業であり、最も基本となる教員の任期が1年期限の臨時対応など、原則的にあってはならないことです。時期によっては、欠員状態もあったと聞きます。最も講師割合が高い小学校は17.9%、中学校では30%にもなっています。「教育に臨時はない」と大阪府に強く求めるべきと考えます。また、産休、育休、病休などの代替講師の配置については、学校の責任ではなく、市教委の責任で空白期間を作ることがないように配置すべきと考えます。見解をお聞きします。
3.老朽化した学校の改修と施設・設備の充実の計画について
これまでも多くの議員が求めてきた課題に、老朽化したトイレ改修があります。また、教育現場では、特別教室のエアコン設置を願う声が強くなっています。優先的に行われてきた耐震化が完了すれば、水回り、床、窓、天井、壁などを含め、一定規模の年次的な改修計画が必要と考えます。見解をお聞きします。
4.教育を壊す管理と競争の教育の見直しについて
「教育改革」と称して、政府・文科省や自治体の首長が教育委員会の上に立って教育行政を行う動きがあります。公選制の教育委員会制度を壊してきた行き着く先でしょうか、教育委員会を首長が任命する教育長の諮問機関にする動きもあります。国が教育統制し、軍国主義につながる「忠君愛国」を押しつけた戦前の反省から、戦後は日本国憲法と教育基本法にもとづく「個人の尊重と人格の完成、平和・民主主義を担う主権者の育成」が基本にすえられました。今日では、国際社会の到達である「こどもの権利条約」をふまえ、「こどもたちの最善の利益」が教育と教育行政に求められています。
現実は、学校長や教職員の成績主義の徹底とともに、教科書の国定化や生活現実をみない「道徳」の強化、「いじめ」問題を利用したゼロ・トレランス(許容度ゼロ)政策、学力の一部でしかない「全国学力テスト」「大阪府学力テスト」「寝屋川市学習到達度調査」などの成績競争の強化、習熟度別学習、小学校からの英語教育、ICT教育など、新学習指導要領の下で、多忙化と学校教育に対する管理と競争の統制が進められています。
私は「教室はまちがうところだ」という詩が大好きです。こどもに限りませんが、人は重大な間違いは許されませんが、失敗や間違いを通じて学び成長するものです。今の低学力問題の課題の一つは、「学びの剥落現象」です。学力をつけるためには、習ったことをくり返し何度も使い、実践しなければなりません。生活の中で生きた使い方ができればそれにこしたことはありません。間違いを許さない、目先の点数だけを追い求めさせる、管理と競争の中では、本当の学力も人格も育ちません。
市教委は、各学校長に、全国学力テストの説明責任を果たすために成績結果の公表を求めていると聞きます。また、成績向上のためにどんな努力をするのか、面接をして求めているとも聞きます。教育の責任を直接持っているのは、各学校の教職員です。こどもと保護者の生活と願いを最もよく知っています。学校自主権の尊重こそ重要と考えます。教育行政の責務は、教育活動への介入ではなく、最善の教育環境を提供する条件整備です。
校長会、校長を通じての上意下達の教育行政姿勢を改めるよう求めます。
答弁を求めます。
5.社会教育の抜本的改善・充実について
生涯学習の観点から、社会教育施設、社会教育事業の充実が求められています。社会の豊かな発展を示す指標にもなると考えます。文部科学省生涯学習政策局の「社会教育調査報告書」(2007年度)によると、女性のみ対象の女性学級・講座数は、女性人口100万人当たり全国で755.3、大阪府は59.9で45位です。高齢者学級・講座数は、人口100万人当たり全国376.9、大阪府は42.4で46位です。社会教育施設は、児童から青年、成人、高齢者まで、すべての人を対象に、家庭や学校以外の場で、学習や研修、スポーツや趣味を楽しむ機会を提供するための生涯学習施設です。社会教育推進計画を策定するに当たり、住民自治を育てる公民館学習、生涯学習、平和学習の観点を重視するよう求めてきましたが、検討課題としていることを明らかにしてください。
6.第2期子どもの読書推進計画の策定について
図書館は国民の「知る権利」を保障するために必要不可欠な施設です。公立図書館の数と蔵書数は、事業水準の一定の指標です。2011年度の寝屋川市の人口1人当たりの蔵書数は、大阪府の統計では1.85冊、下から7番目です。蔵書数は442,842冊です。駅前図書館ができ、現在はどうなっていますか。
この間、図書館行政に関係して強く求めてきたのは、「第2期子どもの読書推進計画」の策定と学校図書館の充実です。計画の策定にあたっては、子どもの読書活動に取り組んでこられた関係者・関係団体の協力が必要と考えます。策定時期の目途と策定のための体制について明らかにして下さい。また、この間、全国的に「はだしのゲン」の閉架をめぐって社会問題になりましたが、学校図書館がいつでも利用できる開架状態になければ、図書館自体が閉架状態と言わなければなりません。人間形成に欠かせない「子ども読書」の重要性からも、専任司書の配置を国・府に求めるとともに、実現するまでの間、市独自の配置を検討すべきと考えます。見解をお聞きします。
●東部まちづくりについて
1.この間の答弁をふまえて
今回の質問にあたって、昨年6月議会からの議事録を読み返しました。また、今回、あらためて「ふるさとリーサム地区まちづくりを考える会」(以下、「考える会」と略す)の規約を見ました。順次質問します。
「考える会」の規約は、一昨年9月22日施行から、昨年6月25日施行で規約改正が行われています。どの部分が変更になったのか、明らかにして下さい。
(目的)第2条では、「本会は、・・・地元住民や関係者の皆さんが主体となって集まり、・・・地域特性を活かしたまちづくりを検討することを目的とする。」となっています。市が作ったとしか思えない文章です。答弁を求めます。
(会員の構成)第4条は、「役員と部会員で構成する。」となっています。
第5条(役員の構成)は、3つの自治会の役員から選出された者、その他本会が適当と認めた者、となっています。「考える会」役員の選出基盤は自治会の役員です。地元住民を代表する組織という場合、少なくとも、自治会に加入の全会員、また、会員外の人を含めた全住民に選出されたという事実が必要と考えます。市として、そうした事実を把握しておられますか。答弁を求めます。
第7条(役員会)では、「7 ・・・研究会を設置することができる。」となっています。「研究会」について、具体的に知っておられることがあれば、構成を含め明らかにしてください。
「8 ・・・市職員、有識者等のアドバイザーの出席を承認することができる。」となっています。通常考えられない内容です。市と「考える会」との関係はこの通りと考えてよいのですか。答弁を求めます。
(部会)として、第8条「地域特性を活かしたまちづくりについて、協力活動及び広報活動を行うため、部会を設置する。」として、「構成員は、役員会の役員が指名する者がなるものとする。」としています。第9条の(全体会議)の規程と合わせ、これでは、一部の役員による仲間内の組織と言わざるを得ないと考えます。所見をお聞きします。
また、「考える会」には相談役が置かれています。特別の存在かと思いますが、位置と役割について承知しておられることを明らかにして下さい。
「本会の事務局は、東部自治会館に置く」点については、現在、担当課に説明を求めています。
市は、「優先的取組エリア」について、東部地域の取組が広範囲であることから、「考える会」が「優先的に取り組むエリアを定めた」ことをふまえ、「構想」を作ったことを明らかにしました。しかし、「市営住宅の建て替え」や「小中一貫校」は市が主体的に検討すべき事項です。「考える会」の意向で「構想」を作るなどは、過去の主体性のない不公正な同和事業の復活を想起させるものです。一般行政から独立している教育行政が判断すべき「小中一貫校」構想をまち政策部として教育委員会に具体化を求めるなどの答弁にも、問題は明らかです。地元の意向と言いますが、具体的に「地元」とはどこなのか、明らかにして下さい。
市は、計画推進の庁内検討組織として、12部局の部長で検討委員会を組織してきました。任意事業である地域支援に市を挙げての体制をとったことはありますか。また、こうした判断は、首脳会議の決定なしには考えられません。答弁を求めます。
市は、支援の要請を受けて、まちづくりの会議に、平成22年度は2回、23年度は11回、24年度は28回参加しています。まさに急増です。その理由を明らかにして下さい。
次に、「まちなか再生エリア」の「まちづくり協議会」の地権者は178名と確認しながら、居住している住民の世帯数についてはわからないとしてきました。その後調査されましたか。地権者の地区内居住者数とともに明らかにしてください。また、把握する中で、聴取された住民の意見があれば、明らかにして下さい。
次に社会資本総合整備計画(地域住宅計画「寝屋川市域」)についてお聞きします。平成23年度~25年度の計画で、明和住宅内の耐震診断を実施されていると思いますが、現状と結果について明らかにしてください。
次に、議会に寄せられている地域住民有志からの「地籍調査及び『まちづくり』についての要望書」に関してお聞きします。
地籍調査についてです。私有財産にかかわる重要な調査ですが、「たった1回きり、1時間だけの説明会で終了・・・『明和北ブロック地籍調査説明会』での参加者は、土地所有者90戸のうち27名、ほか、借地人1名・・・本来は一戸のもれもなく十分な説明会をおこなう必要がある・・・」としています。また、市は、「寝屋川市まちづくり整備計画(案)の一環として地籍調査を行う」と説明していますが、「国土調査法」に基づく「地籍調査」は、国・府あわせて95%の補助金を受けて市町村が実施するものであり、本来、独自の事業と訴えています。実質3ヶ月間(9月中下旬~12月中下旬)の短期間で強行ではなく、一戸の漏れもない説明会をすることで、地籍調査もスムーズに行くとしています。説明会では、市から「市が指定した期間で行う地籍調査に協力すれば、費用は市が負担するが、期間を過ぎれば、30万円~百万円を超える個人の実費負担になる」と住民を脅すような発言があったとしています。説明会の状況と市の見解をお聞きします。
道路の拡幅問題についてです。「市道明和南北中央線」が近くにあることから、生活道路としては6m幅道路はいらない、4m未満で十分としています。また、当該住民の同意を得ずに無理のある拡幅・新設道路のコース設定の見直しを求めています。また、立ち退きを要請された当該借地人に対する居住権の明確な補償を求めています。また、「市道の拡幅に必要な土地を寄付するよう求める」旨の規定について、居住権の補償の十分な説明を求めています。見解をお聞きします。
「まちづくり整備計画(案)」では、「防災・救急対策」を理由にしていますが、協議会設立の総会では、「土地の評価を上げるため」との発言が最初にありました。市が支援すべきは、住民が住み続けることができるまちづくりが基本であり、地権者や土木建設業者の利益ありきの「地上げ」に手を貸すようなことがあってはなりません。市の見解をお聞きします。
2.PFIによる発注業務支援について
寝屋川市営住宅再編整備に係るPFI導入可能性調査業務委託についてです。「市営住宅の再編について、効果的かつ効率的に行うため、・・・民間活力の導入・・・」が目的とされています。プロポーザル方式で、コンソーシアムや企業連合の参加は受け付けないとして行われました。11月19日に業者選定が終わっていますが、応募したのは何社ありましたか。また、選定された「地域経済研究所」の採点結果は、150点満点中何点でしたか。次点の業者の点数は何点ですか。落札額、落札率はいくらですか。明らかにして下さい。
市は、建て替え予定の住宅に居住している人がいる限り、事業は行えないとしています。現在の市営住宅居住世帯数、うち、明和住宅に居住の世帯数、さらに建て替え計画地に居住の世帯数を答えてください。本来、公営住宅法では、居住世帯数を基本に建て替え計画が求められています。見解をお聞きします。
3.「まちなか再生エリア」における制度要綱(案)について
市は、当該地区が住宅市街地総合整備事業や密集市街地適用の要件を満たさないために、市独自の制度要綱によるとしています。地域住民の中には、「法令上の根拠がないため国や府の支援は得られない。市の単独事業となる。そこで市独自の制度要綱が必要になってくる。『寄付』『一定の負担を行う』というのは、寝屋川市から金を引き出すための策略。『エビでタイを釣る』ことが狙い。」との批判があります。「まちなか再生エリア」事業については要綱ではなく、事業の是非、適否を含め判断するためにも、議会議決を必要とする「条例(案)」にすべきと考えます。答弁を求めます。
●その他・・・交差点の信号の歩車分離について
この間、寝屋川駅前線道路の整備が進められてきましたが、京阪寝屋川市駅周辺の交差点の状況は、左折と直進が同じ車線になっており、八尾枚方線・外環状線にまで道路整備が進めば自動車通行量が増え、歩行者が多人数の時には、自動車の渋滞が頻繁に起こりかねません。これまで市駅周辺の交差点信号を少なくとも歩車分離にするよう改善を求めてきましたが、現在の進捗状況はどうなっていますか。明らかにしてください。
2013年12月議会 一般質問 田中市議
2013-12-17
1.防災についてです
2013年10月30日に大阪府の有識者会議「南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」は、南海トラフ巨大地震マグニチュード9クラスの被害想定を発表しました。
被害想定は、府内で最大約13万4千人を超える死者、 建物全壊は約17万9千棟とされています。これは昨年に内閣府が発表した想定の13倍あまりで、浸水域は内閣府の数字と比べ、3倍以上になるとの想定を示しました。
寝屋川市では「地震の揺れ」による建物倒壊で死者数37人と想定されています。巨大地震が冬の午後6時の場合、夕食の準備で火を使う家庭が多く、寝屋川市では火災による死者数は34人と想定されています。今回の発表を受けて大阪府も地域防災計画を来春改訂し、市町村にも対応を促すとしています。
そこで
1 .寝屋川市として今回の大阪府の新たな被害想定の公表をうけて地域防災 計画の必要な見直しを行うことを求めます。
2.公共施設、避難所耐震化を早期に行うことをもとめます。
3.災害時の備蓄品保管場所についてです。
寝屋川市内では、59ヶ所の避難所に対し、備蓄品保管場所は12ヶ所で、今回旧夜間救急センターの一部を13ヶ所目の防災倉庫にするとしています。
しかし、いざという場合、道路が塞がれていたり等、困難さが起きえることが想定されます。そのために、全避難所に備蓄品を保管することが必要です。
当面、小学校区に1ヶ所、24ヶ所に備蓄品保管場所をつくること。12ヶ所の倍加をめざし、取り組むことを求めます。
4.備蓄品の量をさらに増やすことです。食料は、現在寝屋川市は38,000食備蓄しています。
今回の旧夜間救急センターで2,000食、毛布は約1,000枚増やし、休日診療所でケガなどの応急処置用の備品を保管するとされています。
しかし、これでは不足です。南海トラフ巨大地震災害対策等検討委員会では、広範囲で被害が発生すれば、物資が到達されるまでに時間がかかるため、一般的に「1週間分以上」の備蓄品を保管する方針が示されています。
市として対象人数、日数の設定を増やし、食料等備蓄品の増量を行うことをもとめます。
福祉避難所についてです。市は現在特別養護老人ホーム14ヶ所、障害者施設13ヶ所が災害時の福祉避難所となるよう、寝屋川市は各施設と協議をすすめ、協定を随時締結しています。
5.これらのすべての施設と協定を結び、福祉避難所を早期に設置することを求めます。
6.また、福祉避難所として機能するため、各施設に防災備蓄品を保管すること、またそのためのスペースの確保を図ることをもとめます。
7.施設職員、関係者の研修、訓練などをすすめることをもとめます。
要介護度3以上の人は一時避難所でみなさんと一緒の避難生活は困難であると考えます。現在、要介護度3以上の在宅の人は約2,600人おられます。協定を結べる見込みの施設だけでは、現在利用者の他に300~400人しか避難できないと見込まれます。家屋倒壊件数によって異なりますが、一人暮らしや老老介護の人など1,000人を超える人が避難できないと推定されます。
8.この問題の解消のためにも特別養護老人ホーム・障害施設の新設、増設の具体化などをもとめます。
9.止水板設置工事助成・雨水貯留タンク設置助成・家具等転倒防止器具取付支援事業についてです。
今年度からはじめられたこれらの事業の利用状況は、11月末現在、止水板設置工事助成は予算300万円のところ2件で60万円。雨水タンク貯留設置助成は予算300万円のところ、28件申請があり、26件執行で52万6千円。家具等転倒防止器具取付支援事業は予算1,540万円のところ238件の執行で100万円弱となっています。まだまだ利用が少ない状況です。
今年度の当面の取り組みとして自治会等回覧できるように自治会におねがいすることや家具等転倒防止器具取付支援事業では、老人会、障害者団体などを通じてこれらの事業のチラシを回覧するなど、周知・徹底を図り、市民からの施策の申請、適用がされるよう、市としての積極的な対応を求めます。
以上、9点について答弁を求めます。
次に就学援助についてです
家族所得の格差が子どもの学力格差につながるということはもはや「定説」とされています。就学援助制度は、生活保護基準を目安に認定の所得基準にしており、国の生活保護費の基準が下がったため、寝屋川市でも就学援助の利用できる人が減ることが懸念されます。
今年の10月末での寝屋川市就学援助認定は小学校2,771人で全体の約23%、中学校1,790人で全体の約28%と子ども4人に一人の割合の利用となっています。全国では就学援助受給者は12%程度であり、寝屋川市では、全国平均の2倍となっています。
全国的には就学援助は生活保護基準の1.3倍以上の自治体が増えてきています。就学援助を適用する所得基準は寝屋川市は生活保護基準の1.15と低い中でも、就学援助認定受給者が多いのは、それほど市民のくらしは厳しいことを示しています。
1.市として子ども達に影響が及ぼされないように就学援助制度の認定基準を引き上げることをもとめます。
入学準備金は4月認定者のみですが、制服・体操服・靴・鞄など実際3万円から4万円必要です。しかし、限度額が小学1年生は19,900円 、中学1年生は22,900円となっています。
2.入学準備金は制服・靴・体操服・鞄など含めた実態に見合った金額に改善すること。中学校はスキー、小学校では林間学舎費の限度額を実態に見合ったものに引き上げることを求めます。
3.文部科学省の支給項目となっているクラブ活動費・生徒会費・PTA会費などを寝屋川市でも支給することを求めます。
子どもの貧困が問われている今、就学援助は義務教育に通う子どもの命綱です。ところが政府は就学援助の国庫負担制度を廃止し、一般財源化しました。
4.義務教育における国の責任を果たすよう市は国に対し、一般財源化をやめ、国庫負担制度に戻すよう求めます。
以上4点について答弁を求めます。
次にこども医療費助成制度についてです
こども医療費助成制度は、国の制度がない中、1,742の市町村、全国すべての市町村が実施しています。その状況は、18歳まで74自治体、15歳までが752自治体となっています。つまり15歳までが全体の47%、半数近くにものぼっています。
しかし、47都道府県中、大阪府の制度は通院2歳まで、入院は就学前までの全国最低水準であり、その抜本的な改善が求められています。
また、大阪府内において中学校卒業までの助成は、3市4町1村の8自治体で実施されています。
入院では府内全体の半数近くの21自治体で中学校卒業まで実施されています。
寝屋川市の制度改善のためには、
1.国に対し、市はこども医療費助成制度の創設を求めること。
2.大阪府に対し、制度の拡充を求めること。
3.市は中学校卒業までこども医療費助成制度を拡充をすること。
以上3点について答弁を求めます。
次に窓口業務の委託についてです
11月末に新聞報道されました寝屋川市の窓口業務の委託に違反していることについてです。
寝屋川市は、今年7月1日よりアール・オー・エス・ビジネス株式会社との間で委託業務請負契約を締結し、証明書類の請求者又は申し出者及び申請者に係わる法令に基づいた請求権限の確認を受託者に請け負わせています。
大阪労働局は、実態は、
①.市職員が受託者の労働者に直接各種証明書の交付の可否を指示していた。②.また、受託者の労働者が発行した各種証明書が申請者の証明書で間違いないか確認を行っていた。
③.窓口が混雑している場合、受託者の労働者と混在して受付や証明書発行業務を行っている、として適正な請負事業とは判断されず、労働者派遣事業に該当する、としています。
しかし、労働者派遣事業に対しても4つの違反があるとしています。
①.労働者派遣契約を適切に定め、書面に記載していないこと。
②.派遣受け入れ機関を制限することとなる最初の日を通知していないこと。
③.当該派遣事業に関し、市の責任者を選任していないこと。
④.派遣先において派遣労働者ごとの管理台帳を作成していないこと、等です。
市民の個人情報などの漏洩や窓口に来た市民を待たさない市民サービスを実施するためにも
1.窓口業務の委託をやめ、市職員が直接責任を持って対応するようも とめます。
2.また、その他の保険事業室、税務室、水道局など委託部署でも同様 の対応を行うことをもとめます。
以上2点について答弁を求めます。
最後に、ファミリー・サポート・センター事業についてです
2010年11月に八尾市に当時住んでいた母親が八尾市のファミリー・サポート・センター事業を通じ、5ヶ月の赤ちゃんを一時保育で女性に預けましたが、うつぶせ寝の心肺停止状態で発見されました。
その後、病院に救急搬送され奇跡的に心臓は蘇生されましたが、翌日に医師から臨床的に脳死状態との説明があったとのことです。
そのまま3年経った今年10月に亡くなられました。
厚生労働省が2002年12月に作成した指導監督基準では、「窒息を防ぐため乳児は仰向けに寝かせる」とされていましたが、八尾市は同事業所の子どもを預かる人への講習でうつぶせ寝の危険性の説明を始めたのは事故後でした。
八尾市が「あくまでも個人の間での契約だ」等として詳しい調査をしないため、今も事故の原因はわからないままです。保護者は原因を追求するため訴訟を起こされています。
全国で06年度から12年度にファミリー・サポート・センター事業でやけど、骨折などの事故が15件発生しています。
寝屋川市で、このような事故が起きないようにすることが求められます。寝屋川市のファミリー・サポート・センター事業は、市が行う講習を受けた人が子どもを見守るもので、保育資格はなくても、育児の援助ができる人が提供会員になっています。
寝屋川市では2年前までは2時間だけの講習でしたが、現在保育士・保健師・発達心理の専門家・小児科医・看護師などによる講習を9項目、1項目2時間から4時間、合計24時間実施されています。
しかし、各項目すべてを1度受講するのみです。
このような事故がくりかえされないために提供者は保育士や、幼稚園教諭資格などが条件として望ましいと考えますが、
1.せめて、一定受講を済ませた上で、提供者は子どもを預かることを求めます。
2.提供者は、毎年、くり返し受講すること。また、市が提供者交流会を開くことをもとめます。
3.公的施設での一時保育や、延長保育の拡充を図ることをもとめます。
4.市は、日常的に提供者の相談にのったり、サポートを行うことを求めま す。
5.仮にこのような事故が起きた際、個人任せにしないで市として誠 意ある対応で事実関係を調査し、事故の把握と公開を行うことを求めます。
以上5点について答弁を求めます。
2013年10月30日に大阪府の有識者会議「南海トラフ巨大地震災害対策等検討部会」は、南海トラフ巨大地震マグニチュード9クラスの被害想定を発表しました。
被害想定は、府内で最大約13万4千人を超える死者、 建物全壊は約17万9千棟とされています。これは昨年に内閣府が発表した想定の13倍あまりで、浸水域は内閣府の数字と比べ、3倍以上になるとの想定を示しました。
寝屋川市では「地震の揺れ」による建物倒壊で死者数37人と想定されています。巨大地震が冬の午後6時の場合、夕食の準備で火を使う家庭が多く、寝屋川市では火災による死者数は34人と想定されています。今回の発表を受けて大阪府も地域防災計画を来春改訂し、市町村にも対応を促すとしています。
そこで
1 .寝屋川市として今回の大阪府の新たな被害想定の公表をうけて地域防災 計画の必要な見直しを行うことを求めます。
2.公共施設、避難所耐震化を早期に行うことをもとめます。
3.災害時の備蓄品保管場所についてです。
寝屋川市内では、59ヶ所の避難所に対し、備蓄品保管場所は12ヶ所で、今回旧夜間救急センターの一部を13ヶ所目の防災倉庫にするとしています。
しかし、いざという場合、道路が塞がれていたり等、困難さが起きえることが想定されます。そのために、全避難所に備蓄品を保管することが必要です。
当面、小学校区に1ヶ所、24ヶ所に備蓄品保管場所をつくること。12ヶ所の倍加をめざし、取り組むことを求めます。
4.備蓄品の量をさらに増やすことです。食料は、現在寝屋川市は38,000食備蓄しています。
今回の旧夜間救急センターで2,000食、毛布は約1,000枚増やし、休日診療所でケガなどの応急処置用の備品を保管するとされています。
しかし、これでは不足です。南海トラフ巨大地震災害対策等検討委員会では、広範囲で被害が発生すれば、物資が到達されるまでに時間がかかるため、一般的に「1週間分以上」の備蓄品を保管する方針が示されています。
市として対象人数、日数の設定を増やし、食料等備蓄品の増量を行うことをもとめます。
福祉避難所についてです。市は現在特別養護老人ホーム14ヶ所、障害者施設13ヶ所が災害時の福祉避難所となるよう、寝屋川市は各施設と協議をすすめ、協定を随時締結しています。
5.これらのすべての施設と協定を結び、福祉避難所を早期に設置することを求めます。
6.また、福祉避難所として機能するため、各施設に防災備蓄品を保管すること、またそのためのスペースの確保を図ることをもとめます。
7.施設職員、関係者の研修、訓練などをすすめることをもとめます。
要介護度3以上の人は一時避難所でみなさんと一緒の避難生活は困難であると考えます。現在、要介護度3以上の在宅の人は約2,600人おられます。協定を結べる見込みの施設だけでは、現在利用者の他に300~400人しか避難できないと見込まれます。家屋倒壊件数によって異なりますが、一人暮らしや老老介護の人など1,000人を超える人が避難できないと推定されます。
8.この問題の解消のためにも特別養護老人ホーム・障害施設の新設、増設の具体化などをもとめます。
9.止水板設置工事助成・雨水貯留タンク設置助成・家具等転倒防止器具取付支援事業についてです。
今年度からはじめられたこれらの事業の利用状況は、11月末現在、止水板設置工事助成は予算300万円のところ2件で60万円。雨水タンク貯留設置助成は予算300万円のところ、28件申請があり、26件執行で52万6千円。家具等転倒防止器具取付支援事業は予算1,540万円のところ238件の執行で100万円弱となっています。まだまだ利用が少ない状況です。
今年度の当面の取り組みとして自治会等回覧できるように自治会におねがいすることや家具等転倒防止器具取付支援事業では、老人会、障害者団体などを通じてこれらの事業のチラシを回覧するなど、周知・徹底を図り、市民からの施策の申請、適用がされるよう、市としての積極的な対応を求めます。
以上、9点について答弁を求めます。
次に就学援助についてです
家族所得の格差が子どもの学力格差につながるということはもはや「定説」とされています。就学援助制度は、生活保護基準を目安に認定の所得基準にしており、国の生活保護費の基準が下がったため、寝屋川市でも就学援助の利用できる人が減ることが懸念されます。
今年の10月末での寝屋川市就学援助認定は小学校2,771人で全体の約23%、中学校1,790人で全体の約28%と子ども4人に一人の割合の利用となっています。全国では就学援助受給者は12%程度であり、寝屋川市では、全国平均の2倍となっています。
全国的には就学援助は生活保護基準の1.3倍以上の自治体が増えてきています。就学援助を適用する所得基準は寝屋川市は生活保護基準の1.15と低い中でも、就学援助認定受給者が多いのは、それほど市民のくらしは厳しいことを示しています。
1.市として子ども達に影響が及ぼされないように就学援助制度の認定基準を引き上げることをもとめます。
入学準備金は4月認定者のみですが、制服・体操服・靴・鞄など実際3万円から4万円必要です。しかし、限度額が小学1年生は19,900円 、中学1年生は22,900円となっています。
2.入学準備金は制服・靴・体操服・鞄など含めた実態に見合った金額に改善すること。中学校はスキー、小学校では林間学舎費の限度額を実態に見合ったものに引き上げることを求めます。
3.文部科学省の支給項目となっているクラブ活動費・生徒会費・PTA会費などを寝屋川市でも支給することを求めます。
子どもの貧困が問われている今、就学援助は義務教育に通う子どもの命綱です。ところが政府は就学援助の国庫負担制度を廃止し、一般財源化しました。
4.義務教育における国の責任を果たすよう市は国に対し、一般財源化をやめ、国庫負担制度に戻すよう求めます。
以上4点について答弁を求めます。
次にこども医療費助成制度についてです
こども医療費助成制度は、国の制度がない中、1,742の市町村、全国すべての市町村が実施しています。その状況は、18歳まで74自治体、15歳までが752自治体となっています。つまり15歳までが全体の47%、半数近くにものぼっています。
しかし、47都道府県中、大阪府の制度は通院2歳まで、入院は就学前までの全国最低水準であり、その抜本的な改善が求められています。
また、大阪府内において中学校卒業までの助成は、3市4町1村の8自治体で実施されています。
入院では府内全体の半数近くの21自治体で中学校卒業まで実施されています。
寝屋川市の制度改善のためには、
1.国に対し、市はこども医療費助成制度の創設を求めること。
2.大阪府に対し、制度の拡充を求めること。
3.市は中学校卒業までこども医療費助成制度を拡充をすること。
以上3点について答弁を求めます。
次に窓口業務の委託についてです
11月末に新聞報道されました寝屋川市の窓口業務の委託に違反していることについてです。
寝屋川市は、今年7月1日よりアール・オー・エス・ビジネス株式会社との間で委託業務請負契約を締結し、証明書類の請求者又は申し出者及び申請者に係わる法令に基づいた請求権限の確認を受託者に請け負わせています。
大阪労働局は、実態は、
①.市職員が受託者の労働者に直接各種証明書の交付の可否を指示していた。②.また、受託者の労働者が発行した各種証明書が申請者の証明書で間違いないか確認を行っていた。
③.窓口が混雑している場合、受託者の労働者と混在して受付や証明書発行業務を行っている、として適正な請負事業とは判断されず、労働者派遣事業に該当する、としています。
しかし、労働者派遣事業に対しても4つの違反があるとしています。
①.労働者派遣契約を適切に定め、書面に記載していないこと。
②.派遣受け入れ機関を制限することとなる最初の日を通知していないこと。
③.当該派遣事業に関し、市の責任者を選任していないこと。
④.派遣先において派遣労働者ごとの管理台帳を作成していないこと、等です。
市民の個人情報などの漏洩や窓口に来た市民を待たさない市民サービスを実施するためにも
1.窓口業務の委託をやめ、市職員が直接責任を持って対応するようも とめます。
2.また、その他の保険事業室、税務室、水道局など委託部署でも同様 の対応を行うことをもとめます。
以上2点について答弁を求めます。
最後に、ファミリー・サポート・センター事業についてです
2010年11月に八尾市に当時住んでいた母親が八尾市のファミリー・サポート・センター事業を通じ、5ヶ月の赤ちゃんを一時保育で女性に預けましたが、うつぶせ寝の心肺停止状態で発見されました。
その後、病院に救急搬送され奇跡的に心臓は蘇生されましたが、翌日に医師から臨床的に脳死状態との説明があったとのことです。
そのまま3年経った今年10月に亡くなられました。
厚生労働省が2002年12月に作成した指導監督基準では、「窒息を防ぐため乳児は仰向けに寝かせる」とされていましたが、八尾市は同事業所の子どもを預かる人への講習でうつぶせ寝の危険性の説明を始めたのは事故後でした。
八尾市が「あくまでも個人の間での契約だ」等として詳しい調査をしないため、今も事故の原因はわからないままです。保護者は原因を追求するため訴訟を起こされています。
全国で06年度から12年度にファミリー・サポート・センター事業でやけど、骨折などの事故が15件発生しています。
寝屋川市で、このような事故が起きないようにすることが求められます。寝屋川市のファミリー・サポート・センター事業は、市が行う講習を受けた人が子どもを見守るもので、保育資格はなくても、育児の援助ができる人が提供会員になっています。
寝屋川市では2年前までは2時間だけの講習でしたが、現在保育士・保健師・発達心理の専門家・小児科医・看護師などによる講習を9項目、1項目2時間から4時間、合計24時間実施されています。
しかし、各項目すべてを1度受講するのみです。
このような事故がくりかえされないために提供者は保育士や、幼稚園教諭資格などが条件として望ましいと考えますが、
1.せめて、一定受講を済ませた上で、提供者は子どもを預かることを求めます。
2.提供者は、毎年、くり返し受講すること。また、市が提供者交流会を開くことをもとめます。
3.公的施設での一時保育や、延長保育の拡充を図ることをもとめます。
4.市は、日常的に提供者の相談にのったり、サポートを行うことを求めま す。
5.仮にこのような事故が起きた際、個人任せにしないで市として誠 意ある対応で事実関係を調査し、事故の把握と公開を行うことを求めます。
以上5点について答弁を求めます。
2013年12月議会 一般質問 中林市議
2013-12-17
●まず、あかつき・ひばり園についてです。
来年4月からの指定管理者制度導入にあたっては、
★①これまで築いてきた寝屋川市の療育内容、療育システムを充実、発展させるために、あひ園の役割を維持向上させること。②こどもの権利としての、障害児、支援を要するこどもの発達保障の視点を踏まえて、安心して、見通しをもって子育てできる環境を整備すること。
について、市が公的責任を果たすことを改めてもとめ、見解をお聞きします。
次に、療育システム、療育水準を維持向上させるための具体的な中身についてです。
第1は、障害福祉課内に、「係」として設置する「担当ライン」についてです。
市は、担当ラインは、あかつき・ひばり園に出むいて、状況を把握すること、指定管理者である法人(以下、法人と言います)との連絡調整や助言、指導、監督などを、現場の状況に合わせて適切におこなうとしています。
また、法人への委託後に発生する問題について、担当ラインが対応するとしています。保護者からの相談や苦情を受ける体制を確保すること、障害福祉課と法人との間で、意見交換や連絡調整をおこなう定例会議をもち、意思疎通を図りながら、一体となって、園の運営等をすすめるとしています。
以下、4点、お聞きします。
★①あかつき・ひばり園の運営・管理を指定管理者にゆだねる来年4月から、あかつき・ひばり園の療育水準が維持向上されているのか、センター的役割が公立の時と変わらずに果たせているのかどうかの評価、判断をすることは、担当ラインが中心になると考えます。
担当ラインの果たす役割について、明らかにしてください。
◆②法人の園長や療育室長と担当ラインは、どのように関わっていくのかお聞きします。
★③担当ラインを構成する職員については、指定管理後の現場でおこる問題への対処、適切な指導、助言をおこなうためには、現在のあひ園の療育の経験があり、療育内容がわかる専門職が必要です。また、係長だけでなく、担当課長を配置すべきです。
◆④市職員の派遣が引き上げて、法人職員だけになった後こそ、市のフォロー体制が不可欠です。例えば、5年後こそ、担当ラインが指導、助言、監督できる体制を継続すべきです。
第2に、法人の専門職員の確保と育成についてです。
療育水準の維持向上を担保するためには、療育の経験のある専門職員を安定的に確保することは不可欠の課題です。
法人は、12月10日締め切りで、保育士・児童指導員=若干名、看護師1名、栄養士兼調理員1名を募集しました。
以下、4点について、お聞きします。
★①児童指導員は、保育士の資格がなくても採用できますが、
社会福祉分野での資格や経験のある職員を採用する基準にすべきです。
★②専門職員の経験年数についてです。
公立保育所の民営化では、移管法人と市との協定で「保育士の2分の1以上を、4年以上の経験年数を有するもの」とされています。
派遣職員の引き上げ後のあかつき・ひばり園の保育士・児童指導員の経験年数については、「保育士・児童指導員の中での割合を定め、療育の経験年数の基準」を設けた協定にすべきです。
★③専門職員の育成のための年次計画の策定についてです。
あかつきひばり園でおこなってきた、療育現場での実践の中で、高い専門性と豊かな経験のある職員の育成を法人と連携して継続すべきです。
そのために、専門職員をどう育てていくのか、市としての、年次計画を策定べきです。
★④法人の専門職員の確保については、欠員にならないように市が責任をもつべきです。
★第3に、引き継ぎについて、以下、4点、お聞きします。
①クラス担当の引き継ぎの1年目については、36人中17人が市の派遣職員です。
それでもクラス運営をしながら、並行して法人の職員に引き継ぎをおこなうことは、難しいと言われています。
就業時間内だけでは引き継ぎが難しい状況があれば、就業時間外も含めて、引き継ぎ時間を確保するなど、市として、最大限の対応をもとめます。
②2年目では、17人の派遣のうち、7人が引き上げる計画です。クラス担当4人に対して、市職員1人、法人職員3人になります。
法人の職員が療育の経験がなかった場合、療育水準が維持できません。
2年目以降、(3年目は全員が引き上げ予定です。)については、引き継ぎ職員の派遣期間、派遣人数については、実状をふまえ、派遣期間の延長など、柔軟な対応をとることをもとめます。
③相談支援業務についてです。
相談支援専門員の配置1人に対し、1年目は引き継ぎの派遣職員がおこない、2年目は、法人職員がおこなうという計画です。市職員から法人職員への引き継ぎの設定がありません。
★ 相談支援専門員は、障害児の保護者の相談に応じ、助言や連絡調整の必要な支援をおこなうほか、サービス利用計画の作成をおこないます。相談支援専門員の資格要件は、障害者の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における相談支援・介護等の業務における実務経験が、通算して5年以上必要であること、尚かつ、大阪府の研修を終了した人となっています。
あかつき・ひばり園の場合、生まれたこどもの障害がどういうのもかが判断しにくい場面があります。また、保護者がこどもの障害を受け入れることに、ちゅうちょすることもあります。保護者のしんどさを受け止めることができることなど、障害児福祉の専門性と経験が必要です。
相談支援専門員について、派遣職員との引き継ぎを設定して、支障がないようにすべきです。
◆④あかつき・ひばり園がおこなっている相談支援事業は、(1)入園児に関わる相談支援と、(2)指定特定相談支援事業、これは支援計画の作成が必要で、18才までの児童に対する総合的な相談支援事業です。それと、一般的な相談支援事業の3つがあります。
法人への移管で、事業が脆弱にならないように、市のバックアップが必要なのは、入園児以外の18才までの児童の指定特定支援事業と一般の相談支援事業です。
★ 公立の時と同じように、2つの相談支援事業を継続するために、引き上げ後の派遣職員については、その専門性と経験を生かし、担当ラインや、来年度に設置予定の基幹相談支援センターに配置し、教育委員会と連携して、18才までの児童を対象とした分野での障害者施策の拡充をおこなうべきです。
第4に、施設整備の増室、改善、改修についてです。
あかつき・ひばり園の保護者会からの施設要望が議会に届けられ、改めて、施設改善の必要性を感じました。
以下、お聞きします。
① 法人への指定管理と合わせて、OT(作業療法士)、ST(理学療法士)職員を増員します。その増員にともなって、市は、OT室は新設するとしていますが、ST室については、現在の聴覚検査室などを兼用するとのことです。
★ しかし、聴覚検査室は、発達相談員4名に対し、現在、発達診断室が1部屋しかないため、聴覚検査室を兼用しています。これでは、発達診断室が足りなくなります。
従って、増員に伴う増設は、最低でも2室必要です。また、PT室、発達相談室の増室も課題です。
② 保護者からは、
(1)防音設備のない訓練室、(2)ST室に行くのに、PT室を通り抜けないと入室できないことから、訓練中のこどもの集中力の妨げになる問題。(3)カギが閉められずに不審者の侵入を防げない門、(4)床暖房のない冷たい廊下、(5)老朽化した遊具や、訓練に関わるおもちゃなど--の改善、(6)雨の日のための各保育室前の屋根付き通路の設置 などの改善要望が出されています。
これら保護者からの要望項目については、市が、「従来からの施設整備にかかる要望事項」との位置づけで、「あかつき・ひばり園の運営形態の見直し等検討会」(以下、検討会と言います)とは、別に、保護者会と園が話し合っていくとされました。
★ どのようなペースで話し合っていく予定なのか。また、保護者会の要望に対して、保護者が、十分に協議を尽くしたと感じられる話し合いにするべきです。
第5に、18才までの発達保障を視野に入れた施策の具体化についてです。
寝屋川市では、あかつき・ひばり園があることによって、障害児や、支援を要するこどもの早期発見、早期療育をおこなうシステムができています。
今後の課題としては、就学後も、日々困っていることの相談や訓練など、障害福祉課と教育委員会がうまく連携して、保護者とこどもを支援できるしくみをつくることが必要です。
来年度、設置予定の基幹相談支援センターの具体的な内容について、お聞かせください。
第6に、保護者、関係団体への説明と、十分に意見を聞くことについてです。
◆検討会では、仕様書の内容、引き継ぎについて、担当ラインについて、法人との進捗状況の確認、障害者施策の拡充についてなど、5項目の検討課題が残っています。
保護者からは、
①4月まで、3か月半と迫っている中で、市が約束した「療育水準を維持向上する」ことの裏付けとなる内容そのものが明確になっていない今の状態で、1月からの法人職員の事前引き継ぎ、4月からの指定管理者への移管が、混乱なく始められるのか心配している。
②検討会で、保護者・関係団体との意見を交換し、十分に協議する時間をとってもらえるのかどうか。時間がないからと、一方的に報告だけで終わってしまうのではないかとの懸念がある。
などの声がよせられています。
★ 指定管理者導入に関わっての課題については、保護者・関係団体にきちんと説明し、意見を聞き、疑問や不安にきちんと応えることを、改めてもとめ、見解をお聞きします。
● 次に、認定こども園についてです。
認定こども園開設についても、あと3か月半となりました。
3者懇談会では、保育内容や、給食の主食費の保護者負担などについて協議されています。
例えば、お昼寝の問題にしても、幼稚園ではお昼寝はありませんでした。集団としてどうしていくのかなど、幼保一体化における問題があります。
★ 保育所児については、公立保育所の保育内容を基本とするとしてきましたので、保護者の意見を十分に聞いて、急いで無理な変更をすることがないよう、公立保育所での保育運営、保育内容を継続しながら、十分な協議を重ね、保護者の合意と理解を得てすすめるべきだと考えます。
運営内容の変更による保護者負担についても、保護者との十分な協議がされるべきです。市が保護者への約束をきちんと果たすことをもとめ、見解をお聞きします。
●次に、公立保育所の耐震化についてです。
★1階建てのコスモス、さくら、さつき、さざんか保育所と、27年民営化予定のひなぎく保育所は耐震診断ができていません。この5保育所について、あかつき・ひばり園の耐震化診断で活用する国の「住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金」を使って、早急に耐震診断をおこなうことを求め、見解をお聞きします。
●次に、廃プラ処理施設による住民の健康被害についてです。
第1は、住民が健康被害の原因物質の一つとしてあげた、ホルムアルデヒドについてです。
廃プラ公害の原因を調べている公害等調整委員会(公調委)が、今年1月、廃プラ工場周辺の住宅地、太秦、高宮あさひ丘、寝屋の3カ所で、6日間実施した、化学物質と気象調査の結果については、住民がくわしい情報公開をもとめていました。
公調委は、ホルムアルデヒドについては、測定値に疑問があるとして、調査結果を公表しませんでした。また、追加調査もしないとしました。しかし、このほど、公調委から送られてきた連続測定結果を分析した結果、3か所すべてから、室内での規制値を超える高濃度が検出されたことが明らかになりました。
ホルムアルデヒドは、シックハウスの主な原因となる有害物質です。住民の健康被害の症状である、目が痛い、のどがいがらい、せきがよく出る、しっしんが出る、体がだるいなどの皮膚粘膜症状、神経症状などは、シックハウスの症状に似ていると医師から診断されています。
太秦地域での調査で、ホルムアルデヒドの濃度が、一般空気の10倍以上もの値が検出されたことからも、健康被害の原因物質の一つとして、注目されていました。
ホルムアルデヒドは、発ガン性が高いのが特徴です。
規制値は、24時間平均値ではなく、30分平均値で評価することになっています。
( 「DNPH-HPLC法」というホルムアルデヒドの測定方法は)
30分ごとに、測定器を新しいものにして、それぞれの分析をおこなうものです。
1日、24時間の場合、48個のデータとなり、その全ての測定値が、100マイクログラム立方メートル(以下、単位は省略します)以下で、ないといけないという、厳しい評価基準です。それだけ毒性が強い、有害性の強い物質です。
今回の調査結果では、サンコート太秦ビル屋上で、24日午後2時3分に、140となったのをはじめ、あさひ丘配水場屋上では、25日の午前8時45分~11時45分までの30分ごとの、すべてのデータが100をこえており、11時15分には、225にまでなっています。寝屋公民館でも、25日11時36分に191などの高い数値です。
ホルムアルデヒドの規制値、30分平均値で、100マイクログラム立方メートル以下というのは、室内での基準です。従って、空気が動いている室外で、30分平均値で100を超えるということは、大変なことです。
★ この調査結果からみれば、公調委は再調査をおこなうべきです。どのように、お考えですか、見解をお聞きします。
第2に、ホルムアルデヒドの実態調査についてです。
市民の健康と安全を守ることが、行政の第1のつとめです。ホルムアルデヒドの濃度が他の地域より高いことは、寝屋川市民の健康と安全に関わる重大な問題です。
★ ホルムアルデヒドの再調査については、公調委に「お任せ」でなく、市として、
30分平均値で調査をおこない、①この地域と市内の他の地域との違いをはかること、②また、寝屋川市全体として、どうなのかを調査することを提案し、見解をお聞きします。
第3に、ホルムアルデヒドのこれまでの判断についてです。
2008年7月~2009年6月までの1年間、毎月1回、24時間、4市リサイクルプラザ施設周辺3カ所で、寝屋川市と大阪府が共同で、ホルモアルデヒドを含む、有害11物質の大気調査をおこないました。
調査結果に対して、市は、「全ての有害物質において基準値を下回っているので、住民の健康被害と廃プラ施設との因果関係はない。従って健康調査の必要性もない」と断言しました。
ねやがわ広報には、「数値は各地点とも基準値(指針値)を下回りました。ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドについては、大阪府が定期的に測定している府下13地点と比較したところ、同程度でした」と記載されました。
以下、3点、お聞きします。
★① この大気調査で、ホルモアルデヒドの調査結果は、30分平均値なのか、24時間平均値なのか、どのような方法で実施したのかお聞きします。
★②24時間平均値での測定結果であれば、安全だという判断の根拠とはなりません。判断の誤りです。
★③また、その調査結果を裁判所が採用し、規制値以下だという判断に使われたのなら、裁判所の判断についても誤りです。
★第4に、1000人をこえる住民の健康被害の訴えに対し、行政の責任として、住民がもとめる健康調査を実施すべきです。見解をお聞きします。
★第5に、リサイクル・アンド・イコール社についてです。
市民が出した廃プラゴミの再商品化事業をおこなっている民間廃プラ施設、リサイクル・アンド・イコール社が、税金の滞納により、工場を差し押さえされていたことが明らかになりました。
登記簿謄本によると、今年6月18日、枚方税務署が差し押さえ、8月21日寝屋川市が参加差し押さえ、9月12日には大阪市なんば市税事務所が参加差し押さえをしています。
これらの差し押さえは、寝屋川市の分が10月31日、枚方税務署の分が11月7日、大阪市の分が11月11日に、差し押さえが解除されています。
リサイクル・アンド・イコール社の親会社である、「株式会社ワールドロッジ」が、8月30日破産手続きを開始しました。連結子会社4社も自己破産申請しています。
イコール社は、8月30日、民事再生法の適用を申請し、企業再生に取り組むとしていますが、イコール社の負債は、26億8500万円にものぼっています。
ねやがわ市民の出す廃プラごみ処理をしている事業者が税金を滞納し、差し押さえまでされていた事実は、事業者としての資格に関わる大きな問題です。
この事実を、把握していたのか、又、それでよいとされるのか、問題はないのか、市としての認識をお聞きします。
●次に、原発ゼロについてです。
福島原発事故は、原発被害の恐ろしさを見せつけました。
経験したことのない放射能汚染、健康被害、住む町や村、文化まで奪いました。そして莫大な経済被害をもたらしました。
いざ事故になったら、取り返しがつかない被害を及ぼす原発は、なくしていく、再生可能エネルギーに転換していく方向は、世界の本流であり、政府が、原発ゼロの決断をすることを強くもとめるものです。
今話題になっている原発のコストとは、①原価として、事業者が支払う発電コスト ②バックエンド費用としての、使用済み核燃料処分や廃炉に使う費用、③税金や国民が負担している、技術開発や立地対策費、事故コストなどの社会的費用があります。コストをみる場合には、見えにくい社会的費用をみる必要があります。
福島原発事故コストは、今年10月現在で7兆4273万円と試算されています。
費用の出所は、政府資本が1兆円、東電は、さらに5兆円必要としています。
新制度基準に適合するために、最低1兆円が必要で、さらに財産などの賠償、将来の健康リスクや除染費用、廃炉費用に至っては、不透明・不確実で、10兆円をこえると言われています。
自然エネルギーが高いのではなく、どう計算しても原発が高いです。原発は廃炉に巨額の費用がかかります。加えて、使用済み核燃料の処理費用は、実際に安全に処理できないので、無限大のコストとなります。
原発は、将来性を全く考えない不良債権プロジェクトとも言われ、アメリカの原発メーカーも採算が合わないことを認めています。
★ 原発コストが高いことについて、市の認識をお聞きします。
最後に、自然エネルギーのとり組みについてです。
第1に、市は、寝屋川市地球温暖化対策地域計画の中で、「再生可能エネルギーの導入促進」として「再生可能エネルギーに関する情報や再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度などの情報を提供すること」を明記しています。
また、「太陽光発電などの再生可能エネルギーを積極的に導入します」として、市の行動指針では、「公共施設に太陽光等の自然エネルギーを利用した設備の導入を検討します。」としています。
★このように、自然エネルギーの導入方向は、決まっていますので、目標、計画などをお示し下さい。
第2に、公共施設への太陽光パネルの設置についてです。
高槻市は、公共施設の屋上や屋根を、太陽光パネルを設置する場所がない事業者に有償で貸し出す事業を始めます。「固定価格買収制度」を利用し、全電力の買電を条件に、市は屋根などの使用料として、買電収入の4%以上をうけとるものです。
高槻市は、この事業で、一般家庭約100世帯分の電力がまかなえると試算しています。今年は小中学校、公民館など9箇所で、来年度以降、耐震化工事の完了した学校などを順次貸しだすとのことです。
環境部は、地球温暖化対策地域計画に基づき、市役所の全部局に対し、太陽光パネルを設置する場所がないかなどの、アンケートをおこないました。パネルを設置する屋根はあるが、「パネルの重さに耐えられるかどうかの判断ができない」という状況があります。また、遊休地(浄水場、緑風園跡地)などの活用も検討課題です。
★ 各公共施設へ太陽光パネルを設置するために必要な、本格的調査をもとめます。見解をお聞きします。
★ 9月議会で答弁いただいた、①大阪府のグリーンニューディール基金のよる避難所の予備電源としての太陽光パネルの設置、②市民共同発電所については、先進市などの事例を調査、研究する、ことについて、その後の進捗状況をお示しください。
第3に、本市で、7月にスタートした太陽光パネルの設置補助制度についてです。
今年度予算250件に対して、11月末現在で申請が77件です。申請は、国の制度(ジェーベック)の交付決定をうけ、実際に取り付けてからの申請になります。
以下、2点、お聞きします。
★ ①市民への補助金制度の周知や、申請に至るまでの問題点の改善が必要です。
★②補助金の対象を、家庭用だけでなく、市内事業者、民間施設へ広げることをもとめます。
第4に、太陽光パネル設置の初期費用ゼロへのとり組みについてです。
新築住宅の広告などでは、太陽光パネルを設置した物件が目立ちます。既存の住宅では、初期費用の問題があります。
★ 市として、先進市に学び、市民団体との共同で、太陽光パネルが初期費用ゼロで、設置できるようなとり組みの検討、研究をもとめ、見解をお聞きします。
来年4月からの指定管理者制度導入にあたっては、
★①これまで築いてきた寝屋川市の療育内容、療育システムを充実、発展させるために、あひ園の役割を維持向上させること。②こどもの権利としての、障害児、支援を要するこどもの発達保障の視点を踏まえて、安心して、見通しをもって子育てできる環境を整備すること。
について、市が公的責任を果たすことを改めてもとめ、見解をお聞きします。
次に、療育システム、療育水準を維持向上させるための具体的な中身についてです。
第1は、障害福祉課内に、「係」として設置する「担当ライン」についてです。
市は、担当ラインは、あかつき・ひばり園に出むいて、状況を把握すること、指定管理者である法人(以下、法人と言います)との連絡調整や助言、指導、監督などを、現場の状況に合わせて適切におこなうとしています。
また、法人への委託後に発生する問題について、担当ラインが対応するとしています。保護者からの相談や苦情を受ける体制を確保すること、障害福祉課と法人との間で、意見交換や連絡調整をおこなう定例会議をもち、意思疎通を図りながら、一体となって、園の運営等をすすめるとしています。
以下、4点、お聞きします。
★①あかつき・ひばり園の運営・管理を指定管理者にゆだねる来年4月から、あかつき・ひばり園の療育水準が維持向上されているのか、センター的役割が公立の時と変わらずに果たせているのかどうかの評価、判断をすることは、担当ラインが中心になると考えます。
担当ラインの果たす役割について、明らかにしてください。
◆②法人の園長や療育室長と担当ラインは、どのように関わっていくのかお聞きします。
★③担当ラインを構成する職員については、指定管理後の現場でおこる問題への対処、適切な指導、助言をおこなうためには、現在のあひ園の療育の経験があり、療育内容がわかる専門職が必要です。また、係長だけでなく、担当課長を配置すべきです。
◆④市職員の派遣が引き上げて、法人職員だけになった後こそ、市のフォロー体制が不可欠です。例えば、5年後こそ、担当ラインが指導、助言、監督できる体制を継続すべきです。
第2に、法人の専門職員の確保と育成についてです。
療育水準の維持向上を担保するためには、療育の経験のある専門職員を安定的に確保することは不可欠の課題です。
法人は、12月10日締め切りで、保育士・児童指導員=若干名、看護師1名、栄養士兼調理員1名を募集しました。
以下、4点について、お聞きします。
★①児童指導員は、保育士の資格がなくても採用できますが、
社会福祉分野での資格や経験のある職員を採用する基準にすべきです。
★②専門職員の経験年数についてです。
公立保育所の民営化では、移管法人と市との協定で「保育士の2分の1以上を、4年以上の経験年数を有するもの」とされています。
派遣職員の引き上げ後のあかつき・ひばり園の保育士・児童指導員の経験年数については、「保育士・児童指導員の中での割合を定め、療育の経験年数の基準」を設けた協定にすべきです。
★③専門職員の育成のための年次計画の策定についてです。
あかつきひばり園でおこなってきた、療育現場での実践の中で、高い専門性と豊かな経験のある職員の育成を法人と連携して継続すべきです。
そのために、専門職員をどう育てていくのか、市としての、年次計画を策定べきです。
★④法人の専門職員の確保については、欠員にならないように市が責任をもつべきです。
★第3に、引き継ぎについて、以下、4点、お聞きします。
①クラス担当の引き継ぎの1年目については、36人中17人が市の派遣職員です。
それでもクラス運営をしながら、並行して法人の職員に引き継ぎをおこなうことは、難しいと言われています。
就業時間内だけでは引き継ぎが難しい状況があれば、就業時間外も含めて、引き継ぎ時間を確保するなど、市として、最大限の対応をもとめます。
②2年目では、17人の派遣のうち、7人が引き上げる計画です。クラス担当4人に対して、市職員1人、法人職員3人になります。
法人の職員が療育の経験がなかった場合、療育水準が維持できません。
2年目以降、(3年目は全員が引き上げ予定です。)については、引き継ぎ職員の派遣期間、派遣人数については、実状をふまえ、派遣期間の延長など、柔軟な対応をとることをもとめます。
③相談支援業務についてです。
相談支援専門員の配置1人に対し、1年目は引き継ぎの派遣職員がおこない、2年目は、法人職員がおこなうという計画です。市職員から法人職員への引き継ぎの設定がありません。
★ 相談支援専門員は、障害児の保護者の相談に応じ、助言や連絡調整の必要な支援をおこなうほか、サービス利用計画の作成をおこないます。相談支援専門員の資格要件は、障害者の保健、医療、福祉、就労、教育の分野における相談支援・介護等の業務における実務経験が、通算して5年以上必要であること、尚かつ、大阪府の研修を終了した人となっています。
あかつき・ひばり園の場合、生まれたこどもの障害がどういうのもかが判断しにくい場面があります。また、保護者がこどもの障害を受け入れることに、ちゅうちょすることもあります。保護者のしんどさを受け止めることができることなど、障害児福祉の専門性と経験が必要です。
相談支援専門員について、派遣職員との引き継ぎを設定して、支障がないようにすべきです。
◆④あかつき・ひばり園がおこなっている相談支援事業は、(1)入園児に関わる相談支援と、(2)指定特定相談支援事業、これは支援計画の作成が必要で、18才までの児童に対する総合的な相談支援事業です。それと、一般的な相談支援事業の3つがあります。
法人への移管で、事業が脆弱にならないように、市のバックアップが必要なのは、入園児以外の18才までの児童の指定特定支援事業と一般の相談支援事業です。
★ 公立の時と同じように、2つの相談支援事業を継続するために、引き上げ後の派遣職員については、その専門性と経験を生かし、担当ラインや、来年度に設置予定の基幹相談支援センターに配置し、教育委員会と連携して、18才までの児童を対象とした分野での障害者施策の拡充をおこなうべきです。
第4に、施設整備の増室、改善、改修についてです。
あかつき・ひばり園の保護者会からの施設要望が議会に届けられ、改めて、施設改善の必要性を感じました。
以下、お聞きします。
① 法人への指定管理と合わせて、OT(作業療法士)、ST(理学療法士)職員を増員します。その増員にともなって、市は、OT室は新設するとしていますが、ST室については、現在の聴覚検査室などを兼用するとのことです。
★ しかし、聴覚検査室は、発達相談員4名に対し、現在、発達診断室が1部屋しかないため、聴覚検査室を兼用しています。これでは、発達診断室が足りなくなります。
従って、増員に伴う増設は、最低でも2室必要です。また、PT室、発達相談室の増室も課題です。
② 保護者からは、
(1)防音設備のない訓練室、(2)ST室に行くのに、PT室を通り抜けないと入室できないことから、訓練中のこどもの集中力の妨げになる問題。(3)カギが閉められずに不審者の侵入を防げない門、(4)床暖房のない冷たい廊下、(5)老朽化した遊具や、訓練に関わるおもちゃなど--の改善、(6)雨の日のための各保育室前の屋根付き通路の設置 などの改善要望が出されています。
これら保護者からの要望項目については、市が、「従来からの施設整備にかかる要望事項」との位置づけで、「あかつき・ひばり園の運営形態の見直し等検討会」(以下、検討会と言います)とは、別に、保護者会と園が話し合っていくとされました。
★ どのようなペースで話し合っていく予定なのか。また、保護者会の要望に対して、保護者が、十分に協議を尽くしたと感じられる話し合いにするべきです。
第5に、18才までの発達保障を視野に入れた施策の具体化についてです。
寝屋川市では、あかつき・ひばり園があることによって、障害児や、支援を要するこどもの早期発見、早期療育をおこなうシステムができています。
今後の課題としては、就学後も、日々困っていることの相談や訓練など、障害福祉課と教育委員会がうまく連携して、保護者とこどもを支援できるしくみをつくることが必要です。
来年度、設置予定の基幹相談支援センターの具体的な内容について、お聞かせください。
第6に、保護者、関係団体への説明と、十分に意見を聞くことについてです。
◆検討会では、仕様書の内容、引き継ぎについて、担当ラインについて、法人との進捗状況の確認、障害者施策の拡充についてなど、5項目の検討課題が残っています。
保護者からは、
①4月まで、3か月半と迫っている中で、市が約束した「療育水準を維持向上する」ことの裏付けとなる内容そのものが明確になっていない今の状態で、1月からの法人職員の事前引き継ぎ、4月からの指定管理者への移管が、混乱なく始められるのか心配している。
②検討会で、保護者・関係団体との意見を交換し、十分に協議する時間をとってもらえるのかどうか。時間がないからと、一方的に報告だけで終わってしまうのではないかとの懸念がある。
などの声がよせられています。
★ 指定管理者導入に関わっての課題については、保護者・関係団体にきちんと説明し、意見を聞き、疑問や不安にきちんと応えることを、改めてもとめ、見解をお聞きします。
● 次に、認定こども園についてです。
認定こども園開設についても、あと3か月半となりました。
3者懇談会では、保育内容や、給食の主食費の保護者負担などについて協議されています。
例えば、お昼寝の問題にしても、幼稚園ではお昼寝はありませんでした。集団としてどうしていくのかなど、幼保一体化における問題があります。
★ 保育所児については、公立保育所の保育内容を基本とするとしてきましたので、保護者の意見を十分に聞いて、急いで無理な変更をすることがないよう、公立保育所での保育運営、保育内容を継続しながら、十分な協議を重ね、保護者の合意と理解を得てすすめるべきだと考えます。
運営内容の変更による保護者負担についても、保護者との十分な協議がされるべきです。市が保護者への約束をきちんと果たすことをもとめ、見解をお聞きします。
●次に、公立保育所の耐震化についてです。
★1階建てのコスモス、さくら、さつき、さざんか保育所と、27年民営化予定のひなぎく保育所は耐震診断ができていません。この5保育所について、あかつき・ひばり園の耐震化診断で活用する国の「住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金」を使って、早急に耐震診断をおこなうことを求め、見解をお聞きします。
●次に、廃プラ処理施設による住民の健康被害についてです。
第1は、住民が健康被害の原因物質の一つとしてあげた、ホルムアルデヒドについてです。
廃プラ公害の原因を調べている公害等調整委員会(公調委)が、今年1月、廃プラ工場周辺の住宅地、太秦、高宮あさひ丘、寝屋の3カ所で、6日間実施した、化学物質と気象調査の結果については、住民がくわしい情報公開をもとめていました。
公調委は、ホルムアルデヒドについては、測定値に疑問があるとして、調査結果を公表しませんでした。また、追加調査もしないとしました。しかし、このほど、公調委から送られてきた連続測定結果を分析した結果、3か所すべてから、室内での規制値を超える高濃度が検出されたことが明らかになりました。
ホルムアルデヒドは、シックハウスの主な原因となる有害物質です。住民の健康被害の症状である、目が痛い、のどがいがらい、せきがよく出る、しっしんが出る、体がだるいなどの皮膚粘膜症状、神経症状などは、シックハウスの症状に似ていると医師から診断されています。
太秦地域での調査で、ホルムアルデヒドの濃度が、一般空気の10倍以上もの値が検出されたことからも、健康被害の原因物質の一つとして、注目されていました。
ホルムアルデヒドは、発ガン性が高いのが特徴です。
規制値は、24時間平均値ではなく、30分平均値で評価することになっています。
( 「DNPH-HPLC法」というホルムアルデヒドの測定方法は)
30分ごとに、測定器を新しいものにして、それぞれの分析をおこなうものです。
1日、24時間の場合、48個のデータとなり、その全ての測定値が、100マイクログラム立方メートル(以下、単位は省略します)以下で、ないといけないという、厳しい評価基準です。それだけ毒性が強い、有害性の強い物質です。
今回の調査結果では、サンコート太秦ビル屋上で、24日午後2時3分に、140となったのをはじめ、あさひ丘配水場屋上では、25日の午前8時45分~11時45分までの30分ごとの、すべてのデータが100をこえており、11時15分には、225にまでなっています。寝屋公民館でも、25日11時36分に191などの高い数値です。
ホルムアルデヒドの規制値、30分平均値で、100マイクログラム立方メートル以下というのは、室内での基準です。従って、空気が動いている室外で、30分平均値で100を超えるということは、大変なことです。
★ この調査結果からみれば、公調委は再調査をおこなうべきです。どのように、お考えですか、見解をお聞きします。
第2に、ホルムアルデヒドの実態調査についてです。
市民の健康と安全を守ることが、行政の第1のつとめです。ホルムアルデヒドの濃度が他の地域より高いことは、寝屋川市民の健康と安全に関わる重大な問題です。
★ ホルムアルデヒドの再調査については、公調委に「お任せ」でなく、市として、
30分平均値で調査をおこない、①この地域と市内の他の地域との違いをはかること、②また、寝屋川市全体として、どうなのかを調査することを提案し、見解をお聞きします。
第3に、ホルムアルデヒドのこれまでの判断についてです。
2008年7月~2009年6月までの1年間、毎月1回、24時間、4市リサイクルプラザ施設周辺3カ所で、寝屋川市と大阪府が共同で、ホルモアルデヒドを含む、有害11物質の大気調査をおこないました。
調査結果に対して、市は、「全ての有害物質において基準値を下回っているので、住民の健康被害と廃プラ施設との因果関係はない。従って健康調査の必要性もない」と断言しました。
ねやがわ広報には、「数値は各地点とも基準値(指針値)を下回りました。ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドについては、大阪府が定期的に測定している府下13地点と比較したところ、同程度でした」と記載されました。
以下、3点、お聞きします。
★① この大気調査で、ホルモアルデヒドの調査結果は、30分平均値なのか、24時間平均値なのか、どのような方法で実施したのかお聞きします。
★②24時間平均値での測定結果であれば、安全だという判断の根拠とはなりません。判断の誤りです。
★③また、その調査結果を裁判所が採用し、規制値以下だという判断に使われたのなら、裁判所の判断についても誤りです。
★第4に、1000人をこえる住民の健康被害の訴えに対し、行政の責任として、住民がもとめる健康調査を実施すべきです。見解をお聞きします。
★第5に、リサイクル・アンド・イコール社についてです。
市民が出した廃プラゴミの再商品化事業をおこなっている民間廃プラ施設、リサイクル・アンド・イコール社が、税金の滞納により、工場を差し押さえされていたことが明らかになりました。
登記簿謄本によると、今年6月18日、枚方税務署が差し押さえ、8月21日寝屋川市が参加差し押さえ、9月12日には大阪市なんば市税事務所が参加差し押さえをしています。
これらの差し押さえは、寝屋川市の分が10月31日、枚方税務署の分が11月7日、大阪市の分が11月11日に、差し押さえが解除されています。
リサイクル・アンド・イコール社の親会社である、「株式会社ワールドロッジ」が、8月30日破産手続きを開始しました。連結子会社4社も自己破産申請しています。
イコール社は、8月30日、民事再生法の適用を申請し、企業再生に取り組むとしていますが、イコール社の負債は、26億8500万円にものぼっています。
ねやがわ市民の出す廃プラごみ処理をしている事業者が税金を滞納し、差し押さえまでされていた事実は、事業者としての資格に関わる大きな問題です。
この事実を、把握していたのか、又、それでよいとされるのか、問題はないのか、市としての認識をお聞きします。
●次に、原発ゼロについてです。
福島原発事故は、原発被害の恐ろしさを見せつけました。
経験したことのない放射能汚染、健康被害、住む町や村、文化まで奪いました。そして莫大な経済被害をもたらしました。
いざ事故になったら、取り返しがつかない被害を及ぼす原発は、なくしていく、再生可能エネルギーに転換していく方向は、世界の本流であり、政府が、原発ゼロの決断をすることを強くもとめるものです。
今話題になっている原発のコストとは、①原価として、事業者が支払う発電コスト ②バックエンド費用としての、使用済み核燃料処分や廃炉に使う費用、③税金や国民が負担している、技術開発や立地対策費、事故コストなどの社会的費用があります。コストをみる場合には、見えにくい社会的費用をみる必要があります。
福島原発事故コストは、今年10月現在で7兆4273万円と試算されています。
費用の出所は、政府資本が1兆円、東電は、さらに5兆円必要としています。
新制度基準に適合するために、最低1兆円が必要で、さらに財産などの賠償、将来の健康リスクや除染費用、廃炉費用に至っては、不透明・不確実で、10兆円をこえると言われています。
自然エネルギーが高いのではなく、どう計算しても原発が高いです。原発は廃炉に巨額の費用がかかります。加えて、使用済み核燃料の処理費用は、実際に安全に処理できないので、無限大のコストとなります。
原発は、将来性を全く考えない不良債権プロジェクトとも言われ、アメリカの原発メーカーも採算が合わないことを認めています。
★ 原発コストが高いことについて、市の認識をお聞きします。
最後に、自然エネルギーのとり組みについてです。
第1に、市は、寝屋川市地球温暖化対策地域計画の中で、「再生可能エネルギーの導入促進」として「再生可能エネルギーに関する情報や再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度などの情報を提供すること」を明記しています。
また、「太陽光発電などの再生可能エネルギーを積極的に導入します」として、市の行動指針では、「公共施設に太陽光等の自然エネルギーを利用した設備の導入を検討します。」としています。
★このように、自然エネルギーの導入方向は、決まっていますので、目標、計画などをお示し下さい。
第2に、公共施設への太陽光パネルの設置についてです。
高槻市は、公共施設の屋上や屋根を、太陽光パネルを設置する場所がない事業者に有償で貸し出す事業を始めます。「固定価格買収制度」を利用し、全電力の買電を条件に、市は屋根などの使用料として、買電収入の4%以上をうけとるものです。
高槻市は、この事業で、一般家庭約100世帯分の電力がまかなえると試算しています。今年は小中学校、公民館など9箇所で、来年度以降、耐震化工事の完了した学校などを順次貸しだすとのことです。
環境部は、地球温暖化対策地域計画に基づき、市役所の全部局に対し、太陽光パネルを設置する場所がないかなどの、アンケートをおこないました。パネルを設置する屋根はあるが、「パネルの重さに耐えられるかどうかの判断ができない」という状況があります。また、遊休地(浄水場、緑風園跡地)などの活用も検討課題です。
★ 各公共施設へ太陽光パネルを設置するために必要な、本格的調査をもとめます。見解をお聞きします。
★ 9月議会で答弁いただいた、①大阪府のグリーンニューディール基金のよる避難所の予備電源としての太陽光パネルの設置、②市民共同発電所については、先進市などの事例を調査、研究する、ことについて、その後の進捗状況をお示しください。
第3に、本市で、7月にスタートした太陽光パネルの設置補助制度についてです。
今年度予算250件に対して、11月末現在で申請が77件です。申請は、国の制度(ジェーベック)の交付決定をうけ、実際に取り付けてからの申請になります。
以下、2点、お聞きします。
★ ①市民への補助金制度の周知や、申請に至るまでの問題点の改善が必要です。
★②補助金の対象を、家庭用だけでなく、市内事業者、民間施設へ広げることをもとめます。
第4に、太陽光パネル設置の初期費用ゼロへのとり組みについてです。
新築住宅の広告などでは、太陽光パネルを設置した物件が目立ちます。既存の住宅では、初期費用の問題があります。
★ 市として、先進市に学び、市民団体との共同で、太陽光パネルが初期費用ゼロで、設置できるようなとり組みの検討、研究をもとめ、見解をお聞きします。
2013年12月市議会 一般質問 太田市議
2013-12-17
まず最初に国民健康保険についてです。
かつての国保は農業、自営業者が多く加入し一定の所得がある階層が存在していましたが、現在の国保加入者は、無職、年金生活者、そして非正規雇用の労働 者が多く加入し、加入者の所得が大きく落ち込んでいます。そして、国庫負担が削減されていく中で国民健康保険料はどんどんと高額になっています。そして保 険料がはらえないと国保への加入手続きをしない労働者や若者が社会問題化する等、皆保険制度の根幹が揺るがされています。
同様に寝屋川市の国保も高い保険料のまま推移しています。ここ4年は少しずつ保険料が引き下げられ、日本一高い国保ではなくなりましたが、現在でも200 万の所得の4人家族のモデルケースで42万円を超える保険料、実に所得の2割を超える高い保険料です。寝屋川市は保険料の賦課について適切、適法であると 強弁し、市民に高い保険料を課していることを未だ認めない事は残念です。
市民生活は厳しい状況が続いています。そんな中で安倍内閣が来年4月の消費税増税を予定し、年金の削減と物価が上昇する中で、市民生活を守るため、市の努力が一段と求められています。
国保料の引き下げは市民の願いであり、緊急の課題となっています。
2012年度決算で国保は単年度で8億8千万円の黒字となり累積赤字は3億円まで縮小されました。今年度も累積赤字解消のための繰り入れが3憶円行われ、国保会計の収支均衡が図られると今年度で累積赤字は解消されることになります。
昨年度は累積赤字解消の繰り入れを除いても3憶円を超える黒字となりました。加入者から集めた保険料が約55億円ですから数字の上では5%以上国保料の引き下げができた計算になります。今年度の収支はまだ分かりませんが、来年度、市民生活がきびしくなる中で市として国保料についてどのような見通しを持っているのか。また、引き下げのための方策をどのように考えているのかお示しください。
また、今年度も高い国保料の元で滞納をせざるを得ない国保加入者が多くいます。ここ数年は収納率が8割前後で推移しており、すでに5人に1人が滞納者と 滞納をする人が一部の特定の人ではなくなっています。そんな中で寝屋川市の国保料の減免制度の利用実績が伸びていません。所得が下がっている中で1人あた りの減免額も下がってきていることも理解できます。しかし保険料の納付率を上げる取り組みの一環として思い切った制度の周知で国保料の滞納に悩んで いる市民に相談に来ていただくこと。減免制度の利用もしていただく中で保険料の完納を目指す等、市民がすこしでも払いやすい保険料と感じることができる市 の取り組みを求めます。答弁を求めます。
一部負担金減免制度の運用についてです。この間、寝屋川市は一部負担金減免制度の規則を作り運用を始めています。規則が作られたことで対象者がはっきり と明示された事は一定評価します。しかし、規則では過去には議会答弁でも認めていた通院が制度の対象外になるなど、市民にとって規則が作られたことで利用 者が狭められる現実も出てきています。
少しでも医療費が少ないようにと頑張り、入院でなく通院を選択した市民が対象外となるのは問題があるのではないでしょうか。また、多くの市ではホーム ページなどで一部負担金減免制度の紹介がなされていますが、寝屋川市においては未だに制度そのものが市民に対して秘密にされている感がぬぐいきれません。
一部負担金減免制度は国保が社会保障として運営されている事を表しています。経済的理由で医療を受けることができるかできないかが変わるような事は許されません。命の重みを平等に保障する制度としての一部負担金減免制度の柔軟な活用を求め答弁を求めます。
また、生活保護にはぎりぎりならない年金生活者などが入院をするときには、非常に生活がきびしくなります。そのため、一部負担金減免の制度は生活困窮者をその対象にすることも必要と考えます。市として入院などの疾病も一時的な生活困窮の事態ととらえて制度の適用を求め答弁を求めます。
次に介護保険についてです。
介護保険改悪の議論をしてきた厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会が、意見書案を大筋まとめました。年末の正式決定を受け、安倍内閣は改悪法案を来 年の通常国会に提出する構えです。国の責任を後退させ、利用者、家族、介護労働者に重い負担と痛みを強いる意見書案には部会の委員からも異論が出ていま す。高齢者が増加し、公的介護の役割がますます重要になるとき、改悪は完全な逆行です。必要な介護から締め出され、行き場を失う高齢者を激増させることは 許されません。
いま狙われている介護保険改悪は、消費税大増税と社会保障改悪の「一体路線」の大きな柱の一つに位置づけられているものです。
社会保障費の抑制・削減の中期的な日程・段取りを定めた「社会保障改悪プログラム法案」(今国会で審議中)には、“来年の国会に介護改悪法案提出・再 来年4月に改悪実施”の方針が書き込まれています。こんな改悪日程を勝手に決めて国民に押し付けること自体、まったく不当です。プログラム法案は廃案にす るのがスジです。
重大なのは、国民に「自助努力」を迫るプログラム法案が、介護分野でも「(個人の)自助努力が喚起される」仕組みづくりを政府に求め、その方針にそって介護改悪が具体化されてきたことです。
改悪法案の骨格となる介護保険部会意見書案には介護保険の従来のあり方を大きく塗り替える項目が次々と書き込まれました。
一定所得以上の高齢者の利用料の1割から2割への引き上げは、2000年の介護保険開始以来、初の利用料増です。「一定所得」といっても対象は65歳 以上の5人に1人にもなる案が検討されています。1割負担でも経済的理由からサービスをあきらめる人が相次いでいます。所得に応じて保険料を払っている高 齢者にまで“利用料の応能負担”を迫ることは、制度の根幹にかかわる大問題です。
特別養護老人ホーム入所者を原則「要介護3以上」にすることは高齢者、家族の実態を無視しています。自宅介護をしながら、せっぱ詰まった思いで入所を待つ人たちの願いに背く改悪は、家族が、高齢者の介護度悪化を願う“非人道的”な結果さえ生みかねません。
「要支援1、2」の利用者を国基準の介護保険給付から全面的に切り離し、市町村事業に「丸投げ」する方針は、「軽度の介護外しは許されない」との批判 と運動の広がりで全面改悪は断念させました。しかし、要支援者の約6割が利用する“命綱”の訪問介護と通所介護を市町村事業に移す方針には固執し、撤回し ていません。要支援者の国基準のサービス切り離しの道理のなさは明確です。訪問介護と通所介護の市町村事業への“丸投げ”方針も断念すべきです。
公的介護保険は、高齢者の老後の人権と尊厳を保障し、家族の負担を軽くするために導入されたはずです。国の責任を大後退させる意見書案は、その理念に反し ます。「家族介護」に再び依存することは、高齢者と家族の暮らしを危機に追い込み、現場を疲弊させる結果にしかなりません。
介護大改悪を許さず、高齢者が安心して年を重ね、介護に携わる人たちも希望をもてる安心の制度への改革・拡充こそが急がれます。
市として国に対して介護保険制度改悪反対の意見を上げるよう求めます。答弁を求めます。
2012年度の決算審査の中で寝屋川市は第6期介護保険料の見込みを6千円台後半になると答弁しています。しかし、第6期介護保険がどのような制度になるのか全く分からないままでの試算です。制度設計によっては保険料の見込み額も大きく変動をします。
先の市長選挙で馬場市長は介護保険料の引き下げを公約し、その後の議会でも引き下げについて言及していました。第5期介護保険料が引き上げになった際には 議会で謝罪していましたが、市長の任期は4年あります。来年4月からの消費税増税、すでに始められた年金の引き下げなど高齢者の生活はさらに厳しさを増し ています。介護保険料の引き下げを求める市民の声はどんどん切実に大きくなっています。
寝屋川市の市長として市民との約束を守るためにも第6期の介護保険料について市として引き下げの努力をすることを約束して下さい。また、介護保険料の引き下げの財源については、一般会計からの繰り入れを行う事を求めます。答弁を求めます。
また、大阪府下多くの市で実施がされている介護保険料の市独自減免の制度の創設、利用料減免制度の創設を求めます。答弁を求めます。
次に生活保護についてです。
参院厚生労働委員会で日本共産党の小池晃議員の質問にたいして、厚生労働省が親族による扶養義務が生活保護の要件だとする違法な文書を使って申請を締 め出している問題で、全国1263の福祉事務所のうち436カ所(34・5%)で違法な文書が使われていたことを明らかにしました。
小池氏は「これだけ広範囲に違法な文書が使用され続けていたことは極めて重大だ。生活保護行政の抜本的な見直しが必要だ」とのべ、申請を締め出す違法 な「水際作戦」を改めるべきだと強調し、「親族への扶養義務を強化する生活保護法改悪案は廃案にすべきだ」と主張しました。
この問題は、生活保護法に反する違法な文言が入った、保護は扶養義務者の援助を受けることが優先とした文書と、収入、勤務先、家族構成などを記入させるプライバシー侵害の調査書が親族に送られ、申請締め出しに使われていたものです。
小池氏が11月7日、申請を取り下げさせた長野市の実態を示して「受給権の侵害だ」と追及したことを受けて、田村厚労相は全国の自治体に緊急是正を求める同省事務連絡を出し、実態調査を表明していました。
厚労省によれば、違法文書を使っていた事務所のうち134カ所(30・7%)で10年以上も使用。5年以上は6割にのぼりました。
民間会社が作った生活保護管理システムの基本仕様で違法文書が使われていたのが376カ所(86・2%)を占め、原因不明も含めると北日本コンピューター サービスが関与した違法文書は384件、全体の95%にのぼっています。厚労省は、違法文書は是正されたと報告しています。
寝屋川市も残念ながら違法文章を使っていた自治体に入っていたと聞いていますが、いつからその文章を使っていたのか。どれだけの件数送付をしていたのかを明らかにして下さい。その後、どのように訂正がなされたのかを明らかにして下さい。
次に稼働能力の活用についてです。先日、岸和田生活保護訴訟の判決が確定しました。
岸和田市は、大阪地方裁判所が平成25年10月31日に言い渡した、岸和田市福祉事務所長の行った生活保護却下処分を取り消し、岸和田市に対し、慰謝料等 の損害賠償として68万3709円の支払を命じる判決に対する対応として、控訴を行わない旨の市長コメントを発表し地裁判決が確定しました。
事案の概要は、派遣切りに遭って新たな仕事を探し続けても見つからず日々の食事にも困るようになった原告が、岸和田市福祉事務所に生活保護申請に赴いたと ころ、門前払いをされ、その後も、5回も生活保護申請を却下され続けたことについて、岸和田市を被告として、却下処分の取消しと、精神的苦痛に対する慰謝 料を求める行政訴訟でした。 地裁判決の内容の要点は、概ね次の2点に集約されます。 一つは、水際作戦の断罪です。まず、生活保護を実施する機関の義務として、福祉事務所に相談に訪れる者の中には、真に生活に困窮し、保護を必要としている 者が当然に含まれており、そうした者の中には、受給要件や保護の開始申請の方法等につき正しい知識を有していないため、第三者の援助がなければ保護の開始 申請ができない者も多いという現状を述べたうえ、保護の実施機関としては、このような者が保護の対象から漏れることのないよう、相談者の言動、健康状態に 十分に注意を払い、必要に応じて相談者に対し適切な質問を行うことによって、その者が保護を必要としているか否か、また、保護の開始申請をする意思を有し ているか否か、有している場合には保護の開始申請手続きを援助することが職務上求められているとしました。 地裁判決の判断は、原則的に申請によって保護が開始されるという法(7条)の建前ではあるものの、保護申請のために福祉事務所に相談に訪れる者には、積極 的に実施機関側においてその言動に注意をはらい、発問することなどによって正しい情報を提供し、必要な援助をおこなわなければ申請が行えない事情があると いう現状を受け、要保護者が申請することができるよう援助する職務上の義務を肯定したものです。
現在、改訂が審議されている生活保護法24条1項が、従前、申請行為は口頭によっても行えるという司法判断の存在にも関わらず、必要事項の記載された 申請書の提出を求める形式に変更しようとすることは、これらの司法判断や今回の地裁判決と両立し難いものと言わざるを得ません。
申請書の提出を求めるのであれば、少なくとも最低限、福祉事務所の窓口に生活保護申請書を備え置き、要保護者はじめ生活保護申請のために相談に訪れる誰も が分かるよう申請書の存在をアナウンスすること、申請書への記載方法、記載に必要な事項を失念等のため記載できない場合の手当てや支援など、漏給防止措置 をとることが不可欠であり、よりきめ細かな支援が徹底して行われなければなりません。
地裁判決の判示によれば、仮に改訂生活保護法案が成立し、施行された状況下においても、申請書の提出不備や記載漏れなどを理由とする申請不受理は実施機関 に求められる職務上の義務の免責とならず、また、生活保護を受ける要件を充足しているにもかかわらず誤った教示によって申請をさせなかったという水際作戦 は明白な申請権侵害行為として、許容される余地もありません。
2つ目はいわゆる「真摯な」努力論との決別です。生活保護法4条1項が定める稼働能力活用要件につき、確定地裁判決は、憲法25条の理念に基づく生活保 護法の立法趣旨を勘案して判断すべきとし、①稼働能力があるか否か、②その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、③実際に 稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、によって稼働能力の活用要件を判断するとする枠組みを維持しています。そのうえで、稼働能力がある か否かについては、稼働能力の有無だけでなく、稼働能力の程度についても考慮する必要があり、かつ、稼働能力の程度は、申請者の年齢や健康状態、生活歴、 学歴、職歴等を総合的に勘案する必要があること、その能力を活用する意思があるか否かについては、申請者の資質や困窮の程度等を勘案すべきと指摘しつつ、当該申請者について社会通念上最低限度必要とされる程度の最低限度の生活の維持のための努力を 行う意思が認められれば足り、実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否かについては、申請者が求人側に対して申込みをすれば原則として就 労する場を得ることができるような状況か否かによって具体的に判断し、有効求人倍率等の抽象的な資料のみで判断してはならないとしました。また、ここにい う「就労の場」とは申請者が一定程度の給与を一定期間継続して受けられる場をいう、と判示している点も画期的なものです。
この判断は、稼働能力を巡る各地の先行訴訟で示された司法判断を踏襲しており、申請者の資質や困窮の程度等に応じ、当該申請者にできる稼働能力の活用 意思の発現態様が変化することを確認しており、「真摯な」努力を求めるとする厚生労働省の通知のような、きわめて恣意的運用を許すファクターを否定するも のとなっています。
この間、寝屋川市の生活保護申請時に稼働能力の活用についてはどのように取り扱われているのかまた、今後どのように考えるのかを明らかにして下さい。
また、窓口対応は問題なく行われているのかです。残念ながら寝屋川市のケースワーカーは国が基準とする80ケースを超えて担当を持っています。そんな中で 忙しすぎて新たな生活保護の申請があるとついつい厳しい態度をとってしまうという事もあるのではないでしょうか。そんな表れの一つとして、申請者に対して 今日は都合が悪いので後日いついつに来て下さいと。相談日が後回しにされているケースに何回か遭遇しています。市として担当者がいなくても申請や保護受給者からの相談を受けることができるシステムと体制づくりが大事と考えます。現在どのような対応になっていますか。また、国基準のケースワーカーを配置する事を求めますが、市の答弁を求めます。
次に商工振興策についてです。
市の制度融資の利用が減っています。一時寝屋川市の制度融資は利子補給、保証料なしと大阪府下でも一番の制度となりました。その年には多くの市内中小 業者が借り入れを行っています。ところが翌年に利子補給をなくしてからは低調な利用にとどまっています。しかし、中小業者の融資要求がなくなっているわけ ではありません。市内中小零細業者の営業を守り育成をする観点から、制度融資の拡充を求めます。市の答弁を求めます。
仮称四條畷イオンモールが平成26年春オープンの予定となっています。市内の商店を守るために、オープン以前と以後どのような変化が表れるのか。しっかりと調査をする必要があると考えます。そして、市内商店を守るための施策の検討ができると考えます。まず、市内商店の現況調査を求めます。答弁を求めます。
市内商業の活性化施策としての住宅リフォーム助成制度の創設を求めます。住宅リフォーム助成制度は全国の自治体に着実に広がっています。今年度は和歌山県でも1市1町が始めています。まだ大阪府下では実施自治体はありませんが、寝屋川市が府下トップを切って商業振興に取り組むよう求めます。答弁を求めます。
また、群馬県高崎市が創設した「商店版リフォーム」が、業者と地域に元気と明るさを与えています。高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金は商 業の活性化を目的に、商売を営んでいるいる人、これから営業を開始しようとしている人を対象にし、対象業種は、小売り、宿泊、飲食サービス、生活関連サー ビス業で床面積が1000平方メートルを超える店舗は対象外としています。市内の施工業者・販売業者を利用し、店舗などを改善するための改装20万円以上 や、店舗など用する備品を購入1品1万円以上、合計10万円以上した場合、その2分の1を補助する。1店舗当たりの補助上限は100万円。1回限り。3カ 年の予定となっています。制度の活用申請は730件を超え、申請金額も4億円を突破。視察や問い合わせは、全国24自治体に及び、近隣自治体に住む事業者 からは「高崎に移りたい」との声も出るほど盛況です。
個々の店舗を支援するリニューアル助成ですが、榛名湖周辺の土産物店や街の中心部の商店街では「誘い合って」事業申請をする動きが生まれるなど、地域の連携を引き出す力にもなっています。
高崎商工会議所の副会頭を務める株式会社ツナシマの綱島信夫社長は「リニューアル助成は近隣の商工会議所も注目している。商店街の活性化は全国共通の課題 だが、その打開策を打ち出せないでいた。住宅リフォームに続くこの制度は金額的にも大きく、次の世代に胸を張って継がせようと後押しをしてくれる制度」と 高く評価し、同時に「この制度を活用した商店が、街全体の活性化にどうつなげていくか、が問われる」と話されています。
寝屋川市として商店街の振興策として「まちなか商店リニューアル助成事業補助金」の創設を求めます。市の答弁を求めます。
次に市税等の滞納処分についてです。
滞納債権整理回収室ができてから寝屋川市の滞納処分されることも増えてきています。そこでお聞きしますが、寝屋川市として差押え禁止債権についてどのように認識をしているかについてです。
先日、鳥取県が滞納税徴収を目的に児童手当13万円が振り込まれた預金口座を差し押さえたのは違法として、鳥取市の男性(41)が処分取り消しなどを求め た訴訟の控訴審判決が27日、広島高裁松江支部であった。塚本伊平裁判長は、一審の鳥取地裁判決を変更し、県に13万円の支払いを命じた。一審が認めた差 し押さえ処分取り消しと慰謝料の支払いは棄却した。
児童手当は差し押さえが禁止されているが、県が口座の預金を児童手当と認識していたかどうかが争点となっていた。
塚本裁判長は「県が振り込み日を認識し、振り込み9分後の差し押さえ時点では、預金(13万73円)の大部分が手当相当額であり、児童手当としての属 性を失っていなかった」と指摘。「実質的に児童手当を受ける権利自体を差し押さえたのと変わりがない」と判断した。また、差し押さえ処分については「違法 行為とはならない」とした。
判決などによると、男性は個人事業税と自動車税の計21万8800円を滞納。県は2008年6月に児童手当が振り込まれた男性の口座から13万73円を差し押さえた。
一審は男性の主張を認め、県に13万73円の返還と慰謝料など25万円の支払いを命じ、差し押さえ処分も取り消した。
男性は代理人を通じ「価値のある判決。全国に良い影響が出て、違法な徴税に歯止めがかかることを期待する」とコメント。県総務部の末永洋之部長は「判決内容を精査し、今後の対応を協議したい」としている。
寝屋川市においても、年金、児童扶養手当などの差押え禁止債権についても、預貯金になったときから差押え可能財産との認識をしているのではないか。今回の広島高裁の判決をみて市の考え方を改める必要があると考えるが、寝屋川市として今後差押え禁止債権についての考え方を示して下さい。
2011年に大阪市では、子どものための学資保険までむしりとる国民健康保険料滞納世帯への制裁に怒りが広がり平松邦夫市長が記者会見で「共産党からあっ た学資保険の差し押さえについて改めるべき点がある」と表明。「少額の学資保険を苦しい家計のなかから子どものために営々と積み立てている場合には留保す る」と指示したことを明らかにしています。また大阪府下の他の自治体でも様々なルールの元に滞納処分が行われています。寝屋川市としても学資保険の滞納処分については貧困の連鎖を断ち切るために行うべきではないと考えるが、市としての考えを示して下さい。また、寝屋川市が滞納処分をする際に猶予すべき資産や生活状態をどのような基準としているのか明らかにして下さい。
しっかりとした生活実態を踏まえた上で行っていると考えますが、商売人の運転資金についての考え方が統一されていない様に思えます。運転資金が差し押さえられると最悪黒字倒産などたちまち商売が成り立たなく実態もあります。
市として差押えをする際に商売上の運転資金についてどのような認識を持っているのかを明らかにして下さい。
市民生活はまだまだ厳しい状況です。市税や国保・介護保険料等、多くの市民が完納できずに滞納をしている状況が出てきています。生活が厳しい実態をしっかりと把握をして滞納処分の執行の停止の活用を今以上に十分に活用していただきますようお願いします。答弁を求めます。
滞納処分の執行の停止は行政処分ですので市民が申請をすることはできません。しかし、生活が困難な市民が滞納処分の執行の停止を求めてくることも、これからさき増えてくる事でしょう。一つ一つの生活実態をしっかりと聞き市として市民の生活を守る立場での努力を求めます。これまでに市民からの滞納処分の執行の停止の申し込みはありましたか。また、申し出を受けて滞納処分の執行の停止をしたことはありましたか。答弁を求めます。
かつての国保は農業、自営業者が多く加入し一定の所得がある階層が存在していましたが、現在の国保加入者は、無職、年金生活者、そして非正規雇用の労働 者が多く加入し、加入者の所得が大きく落ち込んでいます。そして、国庫負担が削減されていく中で国民健康保険料はどんどんと高額になっています。そして保 険料がはらえないと国保への加入手続きをしない労働者や若者が社会問題化する等、皆保険制度の根幹が揺るがされています。
同様に寝屋川市の国保も高い保険料のまま推移しています。ここ4年は少しずつ保険料が引き下げられ、日本一高い国保ではなくなりましたが、現在でも200 万の所得の4人家族のモデルケースで42万円を超える保険料、実に所得の2割を超える高い保険料です。寝屋川市は保険料の賦課について適切、適法であると 強弁し、市民に高い保険料を課していることを未だ認めない事は残念です。
市民生活は厳しい状況が続いています。そんな中で安倍内閣が来年4月の消費税増税を予定し、年金の削減と物価が上昇する中で、市民生活を守るため、市の努力が一段と求められています。
国保料の引き下げは市民の願いであり、緊急の課題となっています。
2012年度決算で国保は単年度で8億8千万円の黒字となり累積赤字は3億円まで縮小されました。今年度も累積赤字解消のための繰り入れが3憶円行われ、国保会計の収支均衡が図られると今年度で累積赤字は解消されることになります。
昨年度は累積赤字解消の繰り入れを除いても3憶円を超える黒字となりました。加入者から集めた保険料が約55億円ですから数字の上では5%以上国保料の引き下げができた計算になります。今年度の収支はまだ分かりませんが、来年度、市民生活がきびしくなる中で市として国保料についてどのような見通しを持っているのか。また、引き下げのための方策をどのように考えているのかお示しください。
また、今年度も高い国保料の元で滞納をせざるを得ない国保加入者が多くいます。ここ数年は収納率が8割前後で推移しており、すでに5人に1人が滞納者と 滞納をする人が一部の特定の人ではなくなっています。そんな中で寝屋川市の国保料の減免制度の利用実績が伸びていません。所得が下がっている中で1人あた りの減免額も下がってきていることも理解できます。しかし保険料の納付率を上げる取り組みの一環として思い切った制度の周知で国保料の滞納に悩んで いる市民に相談に来ていただくこと。減免制度の利用もしていただく中で保険料の完納を目指す等、市民がすこしでも払いやすい保険料と感じることができる市 の取り組みを求めます。答弁を求めます。
一部負担金減免制度の運用についてです。この間、寝屋川市は一部負担金減免制度の規則を作り運用を始めています。規則が作られたことで対象者がはっきり と明示された事は一定評価します。しかし、規則では過去には議会答弁でも認めていた通院が制度の対象外になるなど、市民にとって規則が作られたことで利用 者が狭められる現実も出てきています。
少しでも医療費が少ないようにと頑張り、入院でなく通院を選択した市民が対象外となるのは問題があるのではないでしょうか。また、多くの市ではホーム ページなどで一部負担金減免制度の紹介がなされていますが、寝屋川市においては未だに制度そのものが市民に対して秘密にされている感がぬぐいきれません。
一部負担金減免制度は国保が社会保障として運営されている事を表しています。経済的理由で医療を受けることができるかできないかが変わるような事は許されません。命の重みを平等に保障する制度としての一部負担金減免制度の柔軟な活用を求め答弁を求めます。
また、生活保護にはぎりぎりならない年金生活者などが入院をするときには、非常に生活がきびしくなります。そのため、一部負担金減免の制度は生活困窮者をその対象にすることも必要と考えます。市として入院などの疾病も一時的な生活困窮の事態ととらえて制度の適用を求め答弁を求めます。
次に介護保険についてです。
介護保険改悪の議論をしてきた厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会が、意見書案を大筋まとめました。年末の正式決定を受け、安倍内閣は改悪法案を来 年の通常国会に提出する構えです。国の責任を後退させ、利用者、家族、介護労働者に重い負担と痛みを強いる意見書案には部会の委員からも異論が出ていま す。高齢者が増加し、公的介護の役割がますます重要になるとき、改悪は完全な逆行です。必要な介護から締め出され、行き場を失う高齢者を激増させることは 許されません。
いま狙われている介護保険改悪は、消費税大増税と社会保障改悪の「一体路線」の大きな柱の一つに位置づけられているものです。
社会保障費の抑制・削減の中期的な日程・段取りを定めた「社会保障改悪プログラム法案」(今国会で審議中)には、“来年の国会に介護改悪法案提出・再 来年4月に改悪実施”の方針が書き込まれています。こんな改悪日程を勝手に決めて国民に押し付けること自体、まったく不当です。プログラム法案は廃案にす るのがスジです。
重大なのは、国民に「自助努力」を迫るプログラム法案が、介護分野でも「(個人の)自助努力が喚起される」仕組みづくりを政府に求め、その方針にそって介護改悪が具体化されてきたことです。
改悪法案の骨格となる介護保険部会意見書案には介護保険の従来のあり方を大きく塗り替える項目が次々と書き込まれました。
一定所得以上の高齢者の利用料の1割から2割への引き上げは、2000年の介護保険開始以来、初の利用料増です。「一定所得」といっても対象は65歳 以上の5人に1人にもなる案が検討されています。1割負担でも経済的理由からサービスをあきらめる人が相次いでいます。所得に応じて保険料を払っている高 齢者にまで“利用料の応能負担”を迫ることは、制度の根幹にかかわる大問題です。
特別養護老人ホーム入所者を原則「要介護3以上」にすることは高齢者、家族の実態を無視しています。自宅介護をしながら、せっぱ詰まった思いで入所を待つ人たちの願いに背く改悪は、家族が、高齢者の介護度悪化を願う“非人道的”な結果さえ生みかねません。
「要支援1、2」の利用者を国基準の介護保険給付から全面的に切り離し、市町村事業に「丸投げ」する方針は、「軽度の介護外しは許されない」との批判 と運動の広がりで全面改悪は断念させました。しかし、要支援者の約6割が利用する“命綱”の訪問介護と通所介護を市町村事業に移す方針には固執し、撤回し ていません。要支援者の国基準のサービス切り離しの道理のなさは明確です。訪問介護と通所介護の市町村事業への“丸投げ”方針も断念すべきです。
公的介護保険は、高齢者の老後の人権と尊厳を保障し、家族の負担を軽くするために導入されたはずです。国の責任を大後退させる意見書案は、その理念に反し ます。「家族介護」に再び依存することは、高齢者と家族の暮らしを危機に追い込み、現場を疲弊させる結果にしかなりません。
介護大改悪を許さず、高齢者が安心して年を重ね、介護に携わる人たちも希望をもてる安心の制度への改革・拡充こそが急がれます。
市として国に対して介護保険制度改悪反対の意見を上げるよう求めます。答弁を求めます。
2012年度の決算審査の中で寝屋川市は第6期介護保険料の見込みを6千円台後半になると答弁しています。しかし、第6期介護保険がどのような制度になるのか全く分からないままでの試算です。制度設計によっては保険料の見込み額も大きく変動をします。
先の市長選挙で馬場市長は介護保険料の引き下げを公約し、その後の議会でも引き下げについて言及していました。第5期介護保険料が引き上げになった際には 議会で謝罪していましたが、市長の任期は4年あります。来年4月からの消費税増税、すでに始められた年金の引き下げなど高齢者の生活はさらに厳しさを増し ています。介護保険料の引き下げを求める市民の声はどんどん切実に大きくなっています。
寝屋川市の市長として市民との約束を守るためにも第6期の介護保険料について市として引き下げの努力をすることを約束して下さい。また、介護保険料の引き下げの財源については、一般会計からの繰り入れを行う事を求めます。答弁を求めます。
また、大阪府下多くの市で実施がされている介護保険料の市独自減免の制度の創設、利用料減免制度の創設を求めます。答弁を求めます。
次に生活保護についてです。
参院厚生労働委員会で日本共産党の小池晃議員の質問にたいして、厚生労働省が親族による扶養義務が生活保護の要件だとする違法な文書を使って申請を締 め出している問題で、全国1263の福祉事務所のうち436カ所(34・5%)で違法な文書が使われていたことを明らかにしました。
小池氏は「これだけ広範囲に違法な文書が使用され続けていたことは極めて重大だ。生活保護行政の抜本的な見直しが必要だ」とのべ、申請を締め出す違法 な「水際作戦」を改めるべきだと強調し、「親族への扶養義務を強化する生活保護法改悪案は廃案にすべきだ」と主張しました。
この問題は、生活保護法に反する違法な文言が入った、保護は扶養義務者の援助を受けることが優先とした文書と、収入、勤務先、家族構成などを記入させるプライバシー侵害の調査書が親族に送られ、申請締め出しに使われていたものです。
小池氏が11月7日、申請を取り下げさせた長野市の実態を示して「受給権の侵害だ」と追及したことを受けて、田村厚労相は全国の自治体に緊急是正を求める同省事務連絡を出し、実態調査を表明していました。
厚労省によれば、違法文書を使っていた事務所のうち134カ所(30・7%)で10年以上も使用。5年以上は6割にのぼりました。
民間会社が作った生活保護管理システムの基本仕様で違法文書が使われていたのが376カ所(86・2%)を占め、原因不明も含めると北日本コンピューター サービスが関与した違法文書は384件、全体の95%にのぼっています。厚労省は、違法文書は是正されたと報告しています。
寝屋川市も残念ながら違法文章を使っていた自治体に入っていたと聞いていますが、いつからその文章を使っていたのか。どれだけの件数送付をしていたのかを明らかにして下さい。その後、どのように訂正がなされたのかを明らかにして下さい。
次に稼働能力の活用についてです。先日、岸和田生活保護訴訟の判決が確定しました。
岸和田市は、大阪地方裁判所が平成25年10月31日に言い渡した、岸和田市福祉事務所長の行った生活保護却下処分を取り消し、岸和田市に対し、慰謝料等 の損害賠償として68万3709円の支払を命じる判決に対する対応として、控訴を行わない旨の市長コメントを発表し地裁判決が確定しました。
事案の概要は、派遣切りに遭って新たな仕事を探し続けても見つからず日々の食事にも困るようになった原告が、岸和田市福祉事務所に生活保護申請に赴いたと ころ、門前払いをされ、その後も、5回も生活保護申請を却下され続けたことについて、岸和田市を被告として、却下処分の取消しと、精神的苦痛に対する慰謝 料を求める行政訴訟でした。 地裁判決の内容の要点は、概ね次の2点に集約されます。 一つは、水際作戦の断罪です。まず、生活保護を実施する機関の義務として、福祉事務所に相談に訪れる者の中には、真に生活に困窮し、保護を必要としている 者が当然に含まれており、そうした者の中には、受給要件や保護の開始申請の方法等につき正しい知識を有していないため、第三者の援助がなければ保護の開始 申請ができない者も多いという現状を述べたうえ、保護の実施機関としては、このような者が保護の対象から漏れることのないよう、相談者の言動、健康状態に 十分に注意を払い、必要に応じて相談者に対し適切な質問を行うことによって、その者が保護を必要としているか否か、また、保護の開始申請をする意思を有し ているか否か、有している場合には保護の開始申請手続きを援助することが職務上求められているとしました。 地裁判決の判断は、原則的に申請によって保護が開始されるという法(7条)の建前ではあるものの、保護申請のために福祉事務所に相談に訪れる者には、積極 的に実施機関側においてその言動に注意をはらい、発問することなどによって正しい情報を提供し、必要な援助をおこなわなければ申請が行えない事情があると いう現状を受け、要保護者が申請することができるよう援助する職務上の義務を肯定したものです。
現在、改訂が審議されている生活保護法24条1項が、従前、申請行為は口頭によっても行えるという司法判断の存在にも関わらず、必要事項の記載された 申請書の提出を求める形式に変更しようとすることは、これらの司法判断や今回の地裁判決と両立し難いものと言わざるを得ません。
申請書の提出を求めるのであれば、少なくとも最低限、福祉事務所の窓口に生活保護申請書を備え置き、要保護者はじめ生活保護申請のために相談に訪れる誰も が分かるよう申請書の存在をアナウンスすること、申請書への記載方法、記載に必要な事項を失念等のため記載できない場合の手当てや支援など、漏給防止措置 をとることが不可欠であり、よりきめ細かな支援が徹底して行われなければなりません。
地裁判決の判示によれば、仮に改訂生活保護法案が成立し、施行された状況下においても、申請書の提出不備や記載漏れなどを理由とする申請不受理は実施機関 に求められる職務上の義務の免責とならず、また、生活保護を受ける要件を充足しているにもかかわらず誤った教示によって申請をさせなかったという水際作戦 は明白な申請権侵害行為として、許容される余地もありません。
2つ目はいわゆる「真摯な」努力論との決別です。生活保護法4条1項が定める稼働能力活用要件につき、確定地裁判決は、憲法25条の理念に基づく生活保 護法の立法趣旨を勘案して判断すべきとし、①稼働能力があるか否か、②その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、③実際に 稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、によって稼働能力の活用要件を判断するとする枠組みを維持しています。そのうえで、稼働能力がある か否かについては、稼働能力の有無だけでなく、稼働能力の程度についても考慮する必要があり、かつ、稼働能力の程度は、申請者の年齢や健康状態、生活歴、 学歴、職歴等を総合的に勘案する必要があること、その能力を活用する意思があるか否かについては、申請者の資質や困窮の程度等を勘案すべきと指摘しつつ、当該申請者について社会通念上最低限度必要とされる程度の最低限度の生活の維持のための努力を 行う意思が認められれば足り、実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否かについては、申請者が求人側に対して申込みをすれば原則として就 労する場を得ることができるような状況か否かによって具体的に判断し、有効求人倍率等の抽象的な資料のみで判断してはならないとしました。また、ここにい う「就労の場」とは申請者が一定程度の給与を一定期間継続して受けられる場をいう、と判示している点も画期的なものです。
この判断は、稼働能力を巡る各地の先行訴訟で示された司法判断を踏襲しており、申請者の資質や困窮の程度等に応じ、当該申請者にできる稼働能力の活用 意思の発現態様が変化することを確認しており、「真摯な」努力を求めるとする厚生労働省の通知のような、きわめて恣意的運用を許すファクターを否定するも のとなっています。
この間、寝屋川市の生活保護申請時に稼働能力の活用についてはどのように取り扱われているのかまた、今後どのように考えるのかを明らかにして下さい。
また、窓口対応は問題なく行われているのかです。残念ながら寝屋川市のケースワーカーは国が基準とする80ケースを超えて担当を持っています。そんな中で 忙しすぎて新たな生活保護の申請があるとついつい厳しい態度をとってしまうという事もあるのではないでしょうか。そんな表れの一つとして、申請者に対して 今日は都合が悪いので後日いついつに来て下さいと。相談日が後回しにされているケースに何回か遭遇しています。市として担当者がいなくても申請や保護受給者からの相談を受けることができるシステムと体制づくりが大事と考えます。現在どのような対応になっていますか。また、国基準のケースワーカーを配置する事を求めますが、市の答弁を求めます。
次に商工振興策についてです。
市の制度融資の利用が減っています。一時寝屋川市の制度融資は利子補給、保証料なしと大阪府下でも一番の制度となりました。その年には多くの市内中小 業者が借り入れを行っています。ところが翌年に利子補給をなくしてからは低調な利用にとどまっています。しかし、中小業者の融資要求がなくなっているわけ ではありません。市内中小零細業者の営業を守り育成をする観点から、制度融資の拡充を求めます。市の答弁を求めます。
仮称四條畷イオンモールが平成26年春オープンの予定となっています。市内の商店を守るために、オープン以前と以後どのような変化が表れるのか。しっかりと調査をする必要があると考えます。そして、市内商店を守るための施策の検討ができると考えます。まず、市内商店の現況調査を求めます。答弁を求めます。
市内商業の活性化施策としての住宅リフォーム助成制度の創設を求めます。住宅リフォーム助成制度は全国の自治体に着実に広がっています。今年度は和歌山県でも1市1町が始めています。まだ大阪府下では実施自治体はありませんが、寝屋川市が府下トップを切って商業振興に取り組むよう求めます。答弁を求めます。
また、群馬県高崎市が創設した「商店版リフォーム」が、業者と地域に元気と明るさを与えています。高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金は商 業の活性化を目的に、商売を営んでいるいる人、これから営業を開始しようとしている人を対象にし、対象業種は、小売り、宿泊、飲食サービス、生活関連サー ビス業で床面積が1000平方メートルを超える店舗は対象外としています。市内の施工業者・販売業者を利用し、店舗などを改善するための改装20万円以上 や、店舗など用する備品を購入1品1万円以上、合計10万円以上した場合、その2分の1を補助する。1店舗当たりの補助上限は100万円。1回限り。3カ 年の予定となっています。制度の活用申請は730件を超え、申請金額も4億円を突破。視察や問い合わせは、全国24自治体に及び、近隣自治体に住む事業者 からは「高崎に移りたい」との声も出るほど盛況です。
個々の店舗を支援するリニューアル助成ですが、榛名湖周辺の土産物店や街の中心部の商店街では「誘い合って」事業申請をする動きが生まれるなど、地域の連携を引き出す力にもなっています。
高崎商工会議所の副会頭を務める株式会社ツナシマの綱島信夫社長は「リニューアル助成は近隣の商工会議所も注目している。商店街の活性化は全国共通の課題 だが、その打開策を打ち出せないでいた。住宅リフォームに続くこの制度は金額的にも大きく、次の世代に胸を張って継がせようと後押しをしてくれる制度」と 高く評価し、同時に「この制度を活用した商店が、街全体の活性化にどうつなげていくか、が問われる」と話されています。
寝屋川市として商店街の振興策として「まちなか商店リニューアル助成事業補助金」の創設を求めます。市の答弁を求めます。
次に市税等の滞納処分についてです。
滞納債権整理回収室ができてから寝屋川市の滞納処分されることも増えてきています。そこでお聞きしますが、寝屋川市として差押え禁止債権についてどのように認識をしているかについてです。
先日、鳥取県が滞納税徴収を目的に児童手当13万円が振り込まれた預金口座を差し押さえたのは違法として、鳥取市の男性(41)が処分取り消しなどを求め た訴訟の控訴審判決が27日、広島高裁松江支部であった。塚本伊平裁判長は、一審の鳥取地裁判決を変更し、県に13万円の支払いを命じた。一審が認めた差 し押さえ処分取り消しと慰謝料の支払いは棄却した。
児童手当は差し押さえが禁止されているが、県が口座の預金を児童手当と認識していたかどうかが争点となっていた。
塚本裁判長は「県が振り込み日を認識し、振り込み9分後の差し押さえ時点では、預金(13万73円)の大部分が手当相当額であり、児童手当としての属 性を失っていなかった」と指摘。「実質的に児童手当を受ける権利自体を差し押さえたのと変わりがない」と判断した。また、差し押さえ処分については「違法 行為とはならない」とした。
判決などによると、男性は個人事業税と自動車税の計21万8800円を滞納。県は2008年6月に児童手当が振り込まれた男性の口座から13万73円を差し押さえた。
一審は男性の主張を認め、県に13万73円の返還と慰謝料など25万円の支払いを命じ、差し押さえ処分も取り消した。
男性は代理人を通じ「価値のある判決。全国に良い影響が出て、違法な徴税に歯止めがかかることを期待する」とコメント。県総務部の末永洋之部長は「判決内容を精査し、今後の対応を協議したい」としている。
寝屋川市においても、年金、児童扶養手当などの差押え禁止債権についても、預貯金になったときから差押え可能財産との認識をしているのではないか。今回の広島高裁の判決をみて市の考え方を改める必要があると考えるが、寝屋川市として今後差押え禁止債権についての考え方を示して下さい。
2011年に大阪市では、子どものための学資保険までむしりとる国民健康保険料滞納世帯への制裁に怒りが広がり平松邦夫市長が記者会見で「共産党からあっ た学資保険の差し押さえについて改めるべき点がある」と表明。「少額の学資保険を苦しい家計のなかから子どものために営々と積み立てている場合には留保す る」と指示したことを明らかにしています。また大阪府下の他の自治体でも様々なルールの元に滞納処分が行われています。寝屋川市としても学資保険の滞納処分については貧困の連鎖を断ち切るために行うべきではないと考えるが、市としての考えを示して下さい。また、寝屋川市が滞納処分をする際に猶予すべき資産や生活状態をどのような基準としているのか明らかにして下さい。
しっかりとした生活実態を踏まえた上で行っていると考えますが、商売人の運転資金についての考え方が統一されていない様に思えます。運転資金が差し押さえられると最悪黒字倒産などたちまち商売が成り立たなく実態もあります。
市として差押えをする際に商売上の運転資金についてどのような認識を持っているのかを明らかにして下さい。
市民生活はまだまだ厳しい状況です。市税や国保・介護保険料等、多くの市民が完納できずに滞納をしている状況が出てきています。生活が厳しい実態をしっかりと把握をして滞納処分の執行の停止の活用を今以上に十分に活用していただきますようお願いします。答弁を求めます。
滞納処分の執行の停止は行政処分ですので市民が申請をすることはできません。しかし、生活が困難な市民が滞納処分の執行の停止を求めてくることも、これからさき増えてくる事でしょう。一つ一つの生活実態をしっかりと聞き市として市民の生活を守る立場での努力を求めます。これまでに市民からの滞納処分の執行の停止の申し込みはありましたか。また、申し出を受けて滞納処分の執行の停止をしたことはありましたか。答弁を求めます。