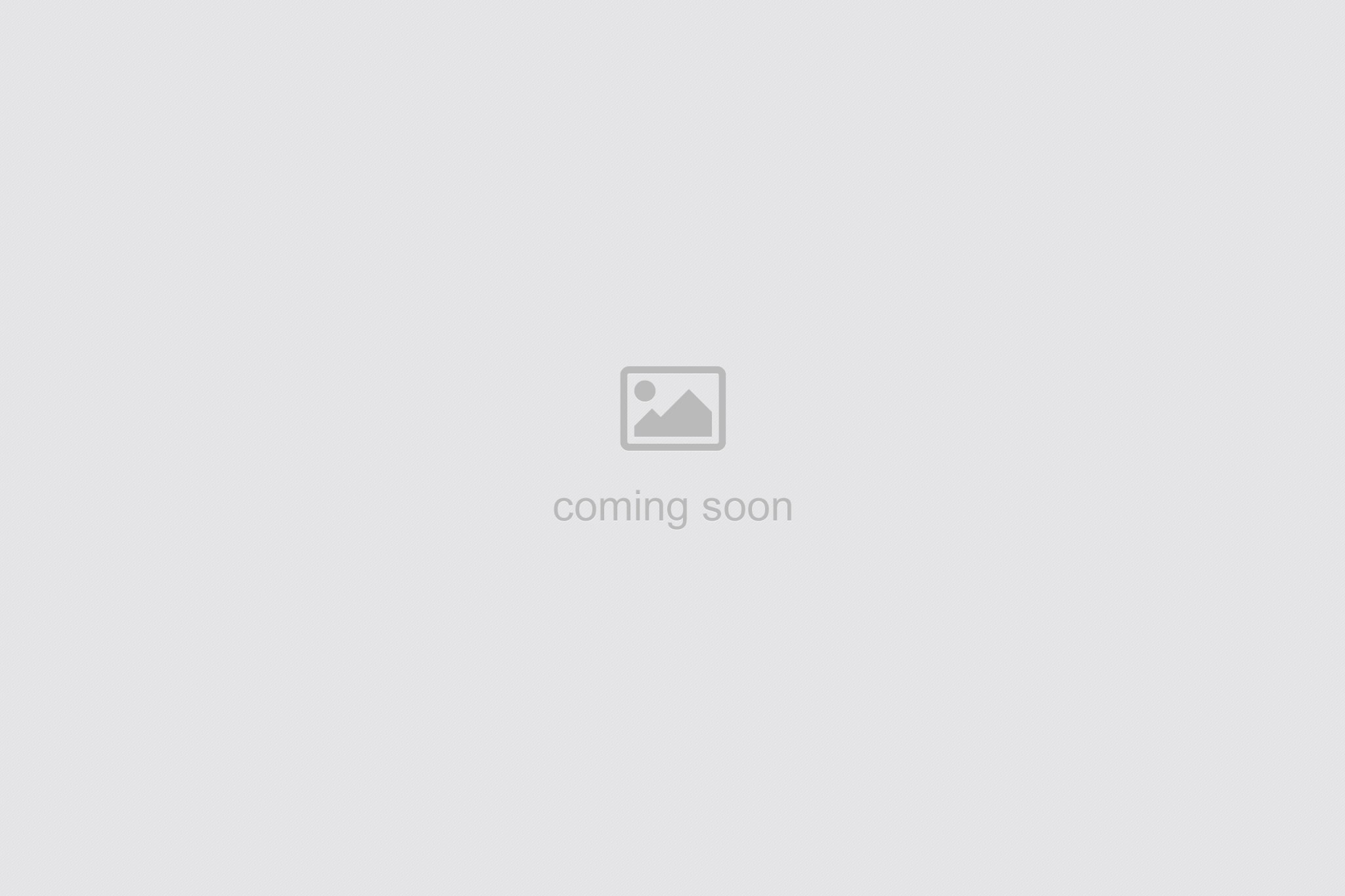2013年 一般質問 中林市議
2013-09-12
最初に、認定こども園 仮称 池田すみれこども園についてです。
第1は、新園舎の建設場所についてです。
認定こども園の新園舎の建設計画は、昨年11月、認定こども園の事業者募集を
始めた後に、急きょ、策定されました。園舎の変更やその場所については、事前に
保護者や地域には、何の説明もありませんでした。
市が策定した計画では、新園舎が自らの影で、園庭に長い影を落とします。
朝8時では、園庭の75%に影が、9時では、50%が影になります。
市内の公立の保育所や幼稚園の、どの施設をみても、園庭の日当たりに、十分、配慮して建てられています。寝屋川市が、施設の建設においては、専門家の意見を聞き、園庭の日当たりを大事にしてきたことがうかがえます。
すみれ保育所の保護者らは、園舎の建設場所を市が決める際に、専門家に、相談したのか確認しました。相談していないことがわかっています。
園舎建設が市でなく、民間であるために、手順を省いて、軽視したとも思えます。、
結局、市が決めた場所では、子どもたちのために、最も良い環境の園舎とは、
言えません。 このことについては、市として、総括して反省すべきだと思います。
保護者らが大阪地裁に行った「工事差し止めの仮処分の申し立て」の審理中に、
移管事業者で、園舎建設の施主である、社会福祉法人 種の会の代理人弁護士が、寝屋川市に、あてた文書には、次のように書かれています。
「保護者らからは、認定こども園の園舎は、これから何十年も、使用していくものであり、一番ふさわしい場所は、池田幼稚園の既存建物のある場所であるため、池田幼稚園を解体し、その跡地に建設することが望ましいとの提案があります。
認定こども園を、敷地の北側(現園舎の跡地)に建設することが、一番望ましいという考えは、間違っているとは言えませんし、東側(市の計画した場所)に認定こども園を建設することは、冬至における園庭の日照が、北側に建てることよりも、不利となる
ことは、否定できません。
当方としては、保護者らとは、今後も、認定こども園の保護者として、引き続き、
おつきあいをし、良好な関係を、築く必要があると考えております。
つきましては、寝屋川市におかれては、認定こども園の建設場所を池田幼稚園の建物の解体跡(すなわち、敷地の北側)に建設するということに、変更をお考えになることは可能なのかどうか、検討頂き、ご回答をいただきたく。また、無理とお考えの
場合、その理由をお示し頂ければありがたく、よろしくお願い申し上げます。」と書かれています。
それに対して、市は、「池田幼稚園児が、教育を受ける横で、園庭を建設すること」を、移管事業者募集の条件にしているので、変更できません」というだけの回答でした。場所を変更できない理由については、書かれていませんでした。
市が、募集時の要件しか示せなかったことは、市の決めた建設場所より、保護者らが提案した場所の方が、「より良い」ということではないでしょうか。
★ 総合的に見て、新園舎の場所は、市の案である東側より、保護者らが提案する、現園舎の跡地である北側の方が、移管事業者も「より良い」と考えていたと、解釈できる文面です。市の認識を、お聞きします。
市が、事業者募集で、条件とした「池田幼稚園児が教育を受ける横で、建設する」ということは、「工事の年度も、幼稚園児を募集する」ということだと思います。
しかし、現園舎の解体工事期間中は、すみれ保育所で、認定こども園を開設することが決まっていた段階では、その時期を変え、期間を延ばすことで、幼稚園教育の継続も可能だったと考えます。
保護者らは、大阪府に出むき、保護者らの提案する場所(現園舎の跡地)に、建設した場合、「安心こども基金」が、確保できるかどうかの聞き取りを行っています。
解体工事を先に行い、跡地に園舎を建設しても、補助金が変わらないかどうかに
ついて、大阪府は、寝屋川市自身が、新園舎の場所を変更すれば、保護者の提案は、可能であるとのことだったと聞いています。
市が、新園舎の場所を決める際に、建築士などの専門家を入れて、検討をしなかったことは、重大な問題です。
また、その後、保護者らから、再三、跡地への変更を提案されながら、最終は、3月議会での請願ですが、保護者らに、納得できる理由を説明しないまま、市が、進めてきたことは、市民との信頼関係を行政自らが、こわしてきたということで、認められません。
さらに、大阪府が「寝屋川市が、建設場所を変更すれば可能」との見解を、保護者らにしていることからも、「日当たりの良い」施設にするために、施工者と話をして、
市が決めた責任として、最大限の努力を行うことができたものです。
そのチャンスがあったにも、かかわらず、「自ら決めたことを変えない」という姿勢に執着して、こどもたちや、市民の利益を、後回しにしたことは、認められません。
★認定こども園の園舎は、220人のこども達が、今後30年、40年と毎日、生活する、大切な施設です。建設費として、3億円近い税金を投入するに、ふさわしいものであるべきです。計画をした市の責任として、日当たりが最も良い場所に建てる計画にすべきだったと考えます。その点で 市としての見解をお聞きします。
園舎建設の場所の問題に関わった市民の声を紹介します。
「市は、幼保一体化という新しいことに対して、十分な準備もしないし、新園舎の
場所についても、勝手に変更して、間違っていても変えない、一番がっかりしたのは、「当のこどものためにを」考えないで、決めていることであり、これでは、市民との信頼関係はつくれない。」ということです。
★ 子ども達のために、最も日当たりのよい場所に園舎を建てることが出来ない状況をつくったのは、市自身であることを認識し、反省すべきと考え、見解をお聞きします。
第2に、新園舎建設による池田幼稚園園児の保育、安全の問題についてです。
新園舎の建設工事については、当初から、子どもの安全のためにも、夏休みに
入って、子どもがいない時期から、工事を始めると、保護者、地域に説明していました。しかし、いまだに、工事車両の搬入路さえできていません。
★なぜ、ここまで遅れているのか、具体的に、わかるような説明を求めます。
また、池田幼稚園の保護者、地域への説明をきちんとおこなうべきです。
見解をお聞きします。
第3に、認定こども園の保育内容についてです。
幼稚園児と保育所児の混合クラスの保育内容については、教育委員会学務課と、こども室、移管事業者とで、すり合わせ、調整などを進めていると聞きます。以下、再確認します。
★認定こども園の保育内容については、公立の現すみれ保育所の保育を基本とすること。移管事業者が、保護者の意見を取り入れ、保護者が納得の上ですすめていくことを、市の責任として、きちんと行うよう求め、見解をお聞きします。
次に、原発ゼロと自然エネルギーの取り組みについてです。
まず、福島原発の事故についてです。
東日本大震災での、重大事故から、2年半、収束のメドが立たない、福島第1原発で、高濃度の放射能汚染水300トンが、タンクから漏れたことがわかりました。
東電は、汚染水が漏れたタンクの北側20mの観測用井戸で、8日採取した地下水から、ストロンチウム90など、ベータ線を出す、放射性物質が、1リットルあたり、3200ベクレル検出されたと、今月9日発表しました。
この値は、漏れたタンクの南側での地下水が、650ベクレルであり、その約5倍の濃度に当たります。
いずれの井戸も、深さ6mの位置からの採取であり、東電は、タンクから漏れた放射能汚染水が土壌に浸透し、地下水に混じった可能性があるとしています。
また、発電所の敷地内の同じ型のタンク群では、1時間当たりの放射線量2200ミリシーベルトという過去最大の値が検出されました。
汚染水が漏れたこれらのタンクは、過去に4回の漏えい事故を起こしています。
底面も、5枚の鋼板を、内側からボルトでつないでおり、いったん汚染水が漏れ出したら、防げない構造であることを東電も認めています。工期が短いことを理由に、「フランジ型」タンクを造り続けています。
しかも、水位計をタンク5、6基に一つしか、設置してないなど、管理体制のずさんさも明らかになりました。
高濃度の放射能汚染水が漏れたことで、福島県沖で最盛期を迎えるシラス漁は、9月の試験操業が急きょ中断、延期になり、漁業者は窮地に立たされています。
また、大量の放射能汚染水が漏れたことで、世界のメディアが注目しています。
アルゼンチン紙は「2020年オリンピックの開催までにどう進展するのか誰も予知できない」と報道。
ニューヨークタイムズは、汚染水対策の不備を指摘する長文の記事を掲載し、「専門家は、日本政府や東電が、こうした複雑な危機に対応する、技術や能力をもっているのか、疑問を持ち始めている」と不信を表しました。
政府が決定した、「汚染水漏れ問題に関する基本方針」にも、世界から、厳しい目が向けられています。
「基本方針」は、原子炉建屋への、地下水の流入を「抑制」するため、冷却による凍土遮水壁で、建屋の周りを取り囲むことや、高性能な放射性物質の多核種除去設備を開発・設置することなどを、国費でおこなうとしました。
しかし、凍土遮水壁による、地下水位の管理が、しっかりできるのかどうか、また、高性能な多核種除去設備開発の実現性についても、「技術的説明は難しい」と答えるなど、いずれも実現の保証が見えません。
「基本方針」は、破綻した東電の対策の延長にすぎず、抜本策とは到底いえません。しかも、汚染水が漏れたタンクより、海寄りの位置からの、地下水を「海洋に放出する」とするなど、政府の「汚染水を漏らさない」という、建前すら、ないがしろにしていることは重大です。
このように、福島原発は、放射能汚染水が流出し続け、さらに汚染が拡大しかねない非常事態です。
汚染された地下水を止め、海洋流出をくい止めるために、技術、人材など、あらゆる英知を結集することが求められます。政府は、「収束宣言」を撤回し、全責任を負う立場で、事故対策を抜本的に改めた上で、対処するべきです。
原発は、いったん、重大事故が起こったら、取り返しのつかない「最悪の事態」と「異質の被害」をもたらすことは明らかです。
★このような、福島原発事故の現状況について、市としての見解をお聞きします。
福島原発の事故は、放射能の恐怖を与え続けています。
危険な放射能を、現在の人類の力では、安全に取り扱えないので、原発は、止めるしかありません。
私たちに一番近い、関西電力の大飯原発が事故になれば、琵琶湖の水が汚染され、近畿の飲み水に最悪の影響がでる可能性を否定できません。
大飯原発2基のうち、3号機は、今月3日、定期検査のため停止しました。4号機が今月15日に停止すれば、再び、日本国内の原発は、「稼働ゼロ」になります。
多くの国民の願いは、原発事故の恐怖が今も続く中、原発依存をやめ、再生可能エネルギーへの転換をすすめることです。
そこで、以下お聞きします。
★国に対し、①原発ゼロの方針を明確にすること、
②原発の再稼働推進はやめること。
③大飯原発は、再稼働しないよう求めること。
★寝屋川市として、④原発ゼロの立場を明らかにすること。
以上、見解をお聞きします。
次に、再生可能エネルギーの取り組みについてです。
世界のエネルギー政策は、ヨーロッパを中心に、再生可能エネルギーの普及にむけて、急速に発展しつつあります。
日本は、地震国でありながら、原発優先のエネルギー政策を展開しており、再生可能エネルギーの普及では、大きくたち遅れています。
危険な原発から撤退するために、今、全国の自治体では、住民を中心にした、地産地消の再生可能エネルギーへの取り組みが進められています。
たとえば、長野県飯田市です。今年4月1日に「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」が施行されました。
条文には、「現在の自然環境及び地域住民の生活と調和する方法により、再生可能エネルギーを自ら利用し、そのもとで生活していく地域住民の権利」として、地域環境権を明確にうたっています。
本来、水や空気、太陽などからの恩恵を受ける権利は、地域住民にあるという立場で、支援策として、再生可能エネルギーの施設整備の、初期費用を調達しやすくするための保証や、補助金の交付、資金の貸し付け、市の財産を利用するなど、地域に根ざした取り組みを条例に位置づけています。
このような条例は、滋賀県湖南市、愛知県新城市、高知県清水市でも、制定されており、今後、地域主導で、再生可能エネルギーの普及を進める自治体が増えていくと言われています。
寝屋川市においては、「自然エネルギーの会」や、「NPO法人市民共同発電所」などの市民団体が設立されており、市民共同発電設備の第1号が、計画されるなど、今後の取り組みが期待されます。
この取り組みは、市民や地域住民から募った寄付や、出資、行政からの補助金などをもとに、市民、住民自らの手で、自然エネルギーを普及させるものです。
寝屋川市の、環境保全審議会の会議録を見ると、地球温暖化の議論の中で、再生可能エネルギーについて、太陽光発電、風力発電など、シンボル的なものを設置して、市民にアピールしてほしいや、小型の小水力発電が用水路で使えるようにならないか、などの意見が出ています。
本市の太陽光パネルの導入実績は、2010年12月現在で、629件で、持ち家等住宅数に対する、普及率は1.5%です。
枚方市で2.9%、全国平均では3.6%となっており、遅れていると言えます。
そういった市内の状況や、市民の声をふまえ、以下お聞きします。
★1.再生可能エネルギーの活用については、環境保全審議会の全体会だけでなく、専門部会などを立ち上げて、市民的な議論も含めて、市民参加で、寝屋川市のビジョンを策定することを求めます。
★2,都市型、再生可能エネルギーの製品開発を行う、中小企業を対象とした「研究開発費の助成事業」などの創設について、関係者の意見を聞き、検討すること。
★3,市民ぐるみで取り組む、市内での市民共同発電設備の設置については、さまざまな面から、市としての支援策を検討すること、再生可能エネルギーの市内での導入に取り組む市民団体との協働をすすめること。
★4、国、大阪府に対し、自然エネルギーの導入目標、自治体や民間、個人の初期投資での負担を軽減する国、府の補助金の拡充を求めること。
★5,太陽光パネルの、公共施設への設置について具体的に検討すること。
★6,今年7月に、本市で創設した、家庭への「太陽光パネルの設置補助制度」の対象を、市内の民間事業所へも広げること。
★7,市町村が避難所の予備電源として、自然エネルギーを設置した設置費用が補助される、大阪府の「グリーンニューディール基金」が、今年から、3年間実施されます。この基金を、避難所となる公共施設などへ、積極的に活用することを求めます。
次に、熱中症対策についてです。
エアコンの設置についてお聞きします。
猛暑の今年、 5月27日から9月1日までの、熱中症による救急搬送者は、全国で、5万6172人、大阪では3887人でした。死亡者は全国で88人、大阪で5人となりました。寝屋川市では、108人が救急搬送されています。
この夏、エアコンの設置については、何件かの相談がありました。
生活保護世帯が、社会福祉協議会から、低金利で「生活福祉資金」を借りて、エアコンを設置することについては、収入認定しない扱いとなり、借り入れができることになりました。しかし、無年金や就労収入がない人は、貸し付けの対象外で、エアコンの設置や修理の費用を借りることができません。
病気などで働けない状態で、保護費だけの収入の場合に、借り入れができないことは、命にかかわる問題です。
埼玉県、新座市の生活保護では、困った女性が、エアコンの修理費の支給を市に再三もとめ、市も認めました。
エアコンに水漏れがあることがわかり、女性が、市に修理費について聞くと「出ません」ということでした。女性は、3回市に要請。「睡眠障害でエアコンが必要」という、医師の診断書を提出しました。
その中で、市が研究して、提案したのは、女性が、5月まで得ていた就労収入について、通常12月に行っていた「特別控除」を、前倒しで実施して、修理にあてることにしました。緊急の要請に対して、市も研究して、こういう措置をとったものです。
ただし、この特別控除制度も8月に廃止されたので今後はできません。
また、東京都は、11年度に限り、緊急措置として、無収入の生保利用者を対象に、65才以上で、エアコンが必要との医師の診断がある場合に、4万円を上限に、独自助成を364世帯に行った例があります。
★ そこで、本市でも、エアコンがない、もしくは壊れて使えない、保護費だけの収入の世帯に対して①、東京都のような独自の助成を大阪府に要望すること、
②新座市のように、市独自の研究を行うなどして、エアコンのない世帯を、なくす努力をすること。③生活保護の「一時扶助」の家具什器費の増額で、エアコンの設置、修理費用に充てられるよう、国に要望すること
以上、3点、見解をお聞きします。
★④として、熱中症の予防策として、高齢者が、避難できる涼しい場所を市で確保すること、具体的には、公共施設などを活用して、避難所の設置や保冷剤などの配布を行うこと。この点について、どのようにされたのか、お聞きします。
★⑤、低所得者が自宅にエアコンを設置する場合の助成制度、融資制度をつくることを求め、見解をお聞きします。
最後に、市民の意見を聞き、反映する市政運営についてです。
「市民が主役のまちづくり」をうたった「寝屋川市みんなのまち基本条例」に、てらして、本市で初めての認定こども園の創設や、あかつき・ひばり園の指定管理者制度の導入についての、決め方、進め方などについては、市の姿勢に、重大な問題があると思います。 2つとも、子育てや、障害者施策の分野での重要な問題です。
認定こども園の開設については、幼保一体化への市民のニーズがあるという説明をされましたが、ニーズ調査もされておらず、保護者、関係者の理解や合意がないまま進められました。
結局、幼保一体化を始めるに当たっての準備は、できていませんでした。
幼保一体化の名で、狙いは、池田幼稚園の廃園でした。
園舎の場所については、先に述べたとおりです。
また、あかつき・ひばり園の「指定管理者制度の導入」については、市長公約にも、市の「アウトソーシング計画」にもありませんでした。そういう重要な問題を、トップダウンで何から何まで決めて、保護者、関係者検討会でたった3か月で、条例を上程するスケジュールそのものが問題です。
市は、検討会の中で、「確認書については、議会にだすものではない」としながら、保護者ら検討会のメンバーが、「まだ、確認しておきたいことがあるので時間がほしい」「仕様書についても、きちんと説明してほしい」などの意見が、あるのに、そのさなかに、条例を上程するというのは、極めて問題です。
これらの、市民生活に、大きく影響する「重要な問題」に対する、市の姿勢には、「市民がまちづくりの主人公」という視点は、全く、見えません。
2つの問題で共通するのは、「トップダウンで、何から何まで決める」ということです。いったい、「みんなのまち基本条例」は、何のために制定したのかと、言わざるを得ません。こういう姿勢で、市政運営を進めることは、重大な問題です。
★改めて、お聞きします。
この間の重要な問題における、市の姿勢は、「みんなのまち基本条例」の
第5条=市民と行政の協働、第7条=行政の透明性の確保、第8条=市民の知る権利の保障 第11条=市民の意見、提案を市政に反映させること、などに反していると考えます。見解をお聞きします。
★重要なことを、首脳会議で決め、市民の意見は何も聞かない、反映しない、見直しや変更さえしない、こうしたやり方はやめるべきです。
市の政策等の立案、計画などについては、市民の意見を聞いて、市民の意見を反映させるため、原点に立ち返って、市政運営をすすめるべきです。見解をお聞きします。
第1は、新園舎の建設場所についてです。
認定こども園の新園舎の建設計画は、昨年11月、認定こども園の事業者募集を
始めた後に、急きょ、策定されました。園舎の変更やその場所については、事前に
保護者や地域には、何の説明もありませんでした。
市が策定した計画では、新園舎が自らの影で、園庭に長い影を落とします。
朝8時では、園庭の75%に影が、9時では、50%が影になります。
市内の公立の保育所や幼稚園の、どの施設をみても、園庭の日当たりに、十分、配慮して建てられています。寝屋川市が、施設の建設においては、専門家の意見を聞き、園庭の日当たりを大事にしてきたことがうかがえます。
すみれ保育所の保護者らは、園舎の建設場所を市が決める際に、専門家に、相談したのか確認しました。相談していないことがわかっています。
園舎建設が市でなく、民間であるために、手順を省いて、軽視したとも思えます。、
結局、市が決めた場所では、子どもたちのために、最も良い環境の園舎とは、
言えません。 このことについては、市として、総括して反省すべきだと思います。
保護者らが大阪地裁に行った「工事差し止めの仮処分の申し立て」の審理中に、
移管事業者で、園舎建設の施主である、社会福祉法人 種の会の代理人弁護士が、寝屋川市に、あてた文書には、次のように書かれています。
「保護者らからは、認定こども園の園舎は、これから何十年も、使用していくものであり、一番ふさわしい場所は、池田幼稚園の既存建物のある場所であるため、池田幼稚園を解体し、その跡地に建設することが望ましいとの提案があります。
認定こども園を、敷地の北側(現園舎の跡地)に建設することが、一番望ましいという考えは、間違っているとは言えませんし、東側(市の計画した場所)に認定こども園を建設することは、冬至における園庭の日照が、北側に建てることよりも、不利となる
ことは、否定できません。
当方としては、保護者らとは、今後も、認定こども園の保護者として、引き続き、
おつきあいをし、良好な関係を、築く必要があると考えております。
つきましては、寝屋川市におかれては、認定こども園の建設場所を池田幼稚園の建物の解体跡(すなわち、敷地の北側)に建設するということに、変更をお考えになることは可能なのかどうか、検討頂き、ご回答をいただきたく。また、無理とお考えの
場合、その理由をお示し頂ければありがたく、よろしくお願い申し上げます。」と書かれています。
それに対して、市は、「池田幼稚園児が、教育を受ける横で、園庭を建設すること」を、移管事業者募集の条件にしているので、変更できません」というだけの回答でした。場所を変更できない理由については、書かれていませんでした。
市が、募集時の要件しか示せなかったことは、市の決めた建設場所より、保護者らが提案した場所の方が、「より良い」ということではないでしょうか。
★ 総合的に見て、新園舎の場所は、市の案である東側より、保護者らが提案する、現園舎の跡地である北側の方が、移管事業者も「より良い」と考えていたと、解釈できる文面です。市の認識を、お聞きします。
市が、事業者募集で、条件とした「池田幼稚園児が教育を受ける横で、建設する」ということは、「工事の年度も、幼稚園児を募集する」ということだと思います。
しかし、現園舎の解体工事期間中は、すみれ保育所で、認定こども園を開設することが決まっていた段階では、その時期を変え、期間を延ばすことで、幼稚園教育の継続も可能だったと考えます。
保護者らは、大阪府に出むき、保護者らの提案する場所(現園舎の跡地)に、建設した場合、「安心こども基金」が、確保できるかどうかの聞き取りを行っています。
解体工事を先に行い、跡地に園舎を建設しても、補助金が変わらないかどうかに
ついて、大阪府は、寝屋川市自身が、新園舎の場所を変更すれば、保護者の提案は、可能であるとのことだったと聞いています。
市が、新園舎の場所を決める際に、建築士などの専門家を入れて、検討をしなかったことは、重大な問題です。
また、その後、保護者らから、再三、跡地への変更を提案されながら、最終は、3月議会での請願ですが、保護者らに、納得できる理由を説明しないまま、市が、進めてきたことは、市民との信頼関係を行政自らが、こわしてきたということで、認められません。
さらに、大阪府が「寝屋川市が、建設場所を変更すれば可能」との見解を、保護者らにしていることからも、「日当たりの良い」施設にするために、施工者と話をして、
市が決めた責任として、最大限の努力を行うことができたものです。
そのチャンスがあったにも、かかわらず、「自ら決めたことを変えない」という姿勢に執着して、こどもたちや、市民の利益を、後回しにしたことは、認められません。
★認定こども園の園舎は、220人のこども達が、今後30年、40年と毎日、生活する、大切な施設です。建設費として、3億円近い税金を投入するに、ふさわしいものであるべきです。計画をした市の責任として、日当たりが最も良い場所に建てる計画にすべきだったと考えます。その点で 市としての見解をお聞きします。
園舎建設の場所の問題に関わった市民の声を紹介します。
「市は、幼保一体化という新しいことに対して、十分な準備もしないし、新園舎の
場所についても、勝手に変更して、間違っていても変えない、一番がっかりしたのは、「当のこどものためにを」考えないで、決めていることであり、これでは、市民との信頼関係はつくれない。」ということです。
★ 子ども達のために、最も日当たりのよい場所に園舎を建てることが出来ない状況をつくったのは、市自身であることを認識し、反省すべきと考え、見解をお聞きします。
第2に、新園舎建設による池田幼稚園園児の保育、安全の問題についてです。
新園舎の建設工事については、当初から、子どもの安全のためにも、夏休みに
入って、子どもがいない時期から、工事を始めると、保護者、地域に説明していました。しかし、いまだに、工事車両の搬入路さえできていません。
★なぜ、ここまで遅れているのか、具体的に、わかるような説明を求めます。
また、池田幼稚園の保護者、地域への説明をきちんとおこなうべきです。
見解をお聞きします。
第3に、認定こども園の保育内容についてです。
幼稚園児と保育所児の混合クラスの保育内容については、教育委員会学務課と、こども室、移管事業者とで、すり合わせ、調整などを進めていると聞きます。以下、再確認します。
★認定こども園の保育内容については、公立の現すみれ保育所の保育を基本とすること。移管事業者が、保護者の意見を取り入れ、保護者が納得の上ですすめていくことを、市の責任として、きちんと行うよう求め、見解をお聞きします。
次に、原発ゼロと自然エネルギーの取り組みについてです。
まず、福島原発の事故についてです。
東日本大震災での、重大事故から、2年半、収束のメドが立たない、福島第1原発で、高濃度の放射能汚染水300トンが、タンクから漏れたことがわかりました。
東電は、汚染水が漏れたタンクの北側20mの観測用井戸で、8日採取した地下水から、ストロンチウム90など、ベータ線を出す、放射性物質が、1リットルあたり、3200ベクレル検出されたと、今月9日発表しました。
この値は、漏れたタンクの南側での地下水が、650ベクレルであり、その約5倍の濃度に当たります。
いずれの井戸も、深さ6mの位置からの採取であり、東電は、タンクから漏れた放射能汚染水が土壌に浸透し、地下水に混じった可能性があるとしています。
また、発電所の敷地内の同じ型のタンク群では、1時間当たりの放射線量2200ミリシーベルトという過去最大の値が検出されました。
汚染水が漏れたこれらのタンクは、過去に4回の漏えい事故を起こしています。
底面も、5枚の鋼板を、内側からボルトでつないでおり、いったん汚染水が漏れ出したら、防げない構造であることを東電も認めています。工期が短いことを理由に、「フランジ型」タンクを造り続けています。
しかも、水位計をタンク5、6基に一つしか、設置してないなど、管理体制のずさんさも明らかになりました。
高濃度の放射能汚染水が漏れたことで、福島県沖で最盛期を迎えるシラス漁は、9月の試験操業が急きょ中断、延期になり、漁業者は窮地に立たされています。
また、大量の放射能汚染水が漏れたことで、世界のメディアが注目しています。
アルゼンチン紙は「2020年オリンピックの開催までにどう進展するのか誰も予知できない」と報道。
ニューヨークタイムズは、汚染水対策の不備を指摘する長文の記事を掲載し、「専門家は、日本政府や東電が、こうした複雑な危機に対応する、技術や能力をもっているのか、疑問を持ち始めている」と不信を表しました。
政府が決定した、「汚染水漏れ問題に関する基本方針」にも、世界から、厳しい目が向けられています。
「基本方針」は、原子炉建屋への、地下水の流入を「抑制」するため、冷却による凍土遮水壁で、建屋の周りを取り囲むことや、高性能な放射性物質の多核種除去設備を開発・設置することなどを、国費でおこなうとしました。
しかし、凍土遮水壁による、地下水位の管理が、しっかりできるのかどうか、また、高性能な多核種除去設備開発の実現性についても、「技術的説明は難しい」と答えるなど、いずれも実現の保証が見えません。
「基本方針」は、破綻した東電の対策の延長にすぎず、抜本策とは到底いえません。しかも、汚染水が漏れたタンクより、海寄りの位置からの、地下水を「海洋に放出する」とするなど、政府の「汚染水を漏らさない」という、建前すら、ないがしろにしていることは重大です。
このように、福島原発は、放射能汚染水が流出し続け、さらに汚染が拡大しかねない非常事態です。
汚染された地下水を止め、海洋流出をくい止めるために、技術、人材など、あらゆる英知を結集することが求められます。政府は、「収束宣言」を撤回し、全責任を負う立場で、事故対策を抜本的に改めた上で、対処するべきです。
原発は、いったん、重大事故が起こったら、取り返しのつかない「最悪の事態」と「異質の被害」をもたらすことは明らかです。
★このような、福島原発事故の現状況について、市としての見解をお聞きします。
福島原発の事故は、放射能の恐怖を与え続けています。
危険な放射能を、現在の人類の力では、安全に取り扱えないので、原発は、止めるしかありません。
私たちに一番近い、関西電力の大飯原発が事故になれば、琵琶湖の水が汚染され、近畿の飲み水に最悪の影響がでる可能性を否定できません。
大飯原発2基のうち、3号機は、今月3日、定期検査のため停止しました。4号機が今月15日に停止すれば、再び、日本国内の原発は、「稼働ゼロ」になります。
多くの国民の願いは、原発事故の恐怖が今も続く中、原発依存をやめ、再生可能エネルギーへの転換をすすめることです。
そこで、以下お聞きします。
★国に対し、①原発ゼロの方針を明確にすること、
②原発の再稼働推進はやめること。
③大飯原発は、再稼働しないよう求めること。
★寝屋川市として、④原発ゼロの立場を明らかにすること。
以上、見解をお聞きします。
次に、再生可能エネルギーの取り組みについてです。
世界のエネルギー政策は、ヨーロッパを中心に、再生可能エネルギーの普及にむけて、急速に発展しつつあります。
日本は、地震国でありながら、原発優先のエネルギー政策を展開しており、再生可能エネルギーの普及では、大きくたち遅れています。
危険な原発から撤退するために、今、全国の自治体では、住民を中心にした、地産地消の再生可能エネルギーへの取り組みが進められています。
たとえば、長野県飯田市です。今年4月1日に「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」が施行されました。
条文には、「現在の自然環境及び地域住民の生活と調和する方法により、再生可能エネルギーを自ら利用し、そのもとで生活していく地域住民の権利」として、地域環境権を明確にうたっています。
本来、水や空気、太陽などからの恩恵を受ける権利は、地域住民にあるという立場で、支援策として、再生可能エネルギーの施設整備の、初期費用を調達しやすくするための保証や、補助金の交付、資金の貸し付け、市の財産を利用するなど、地域に根ざした取り組みを条例に位置づけています。
このような条例は、滋賀県湖南市、愛知県新城市、高知県清水市でも、制定されており、今後、地域主導で、再生可能エネルギーの普及を進める自治体が増えていくと言われています。
寝屋川市においては、「自然エネルギーの会」や、「NPO法人市民共同発電所」などの市民団体が設立されており、市民共同発電設備の第1号が、計画されるなど、今後の取り組みが期待されます。
この取り組みは、市民や地域住民から募った寄付や、出資、行政からの補助金などをもとに、市民、住民自らの手で、自然エネルギーを普及させるものです。
寝屋川市の、環境保全審議会の会議録を見ると、地球温暖化の議論の中で、再生可能エネルギーについて、太陽光発電、風力発電など、シンボル的なものを設置して、市民にアピールしてほしいや、小型の小水力発電が用水路で使えるようにならないか、などの意見が出ています。
本市の太陽光パネルの導入実績は、2010年12月現在で、629件で、持ち家等住宅数に対する、普及率は1.5%です。
枚方市で2.9%、全国平均では3.6%となっており、遅れていると言えます。
そういった市内の状況や、市民の声をふまえ、以下お聞きします。
★1.再生可能エネルギーの活用については、環境保全審議会の全体会だけでなく、専門部会などを立ち上げて、市民的な議論も含めて、市民参加で、寝屋川市のビジョンを策定することを求めます。
★2,都市型、再生可能エネルギーの製品開発を行う、中小企業を対象とした「研究開発費の助成事業」などの創設について、関係者の意見を聞き、検討すること。
★3,市民ぐるみで取り組む、市内での市民共同発電設備の設置については、さまざまな面から、市としての支援策を検討すること、再生可能エネルギーの市内での導入に取り組む市民団体との協働をすすめること。
★4、国、大阪府に対し、自然エネルギーの導入目標、自治体や民間、個人の初期投資での負担を軽減する国、府の補助金の拡充を求めること。
★5,太陽光パネルの、公共施設への設置について具体的に検討すること。
★6,今年7月に、本市で創設した、家庭への「太陽光パネルの設置補助制度」の対象を、市内の民間事業所へも広げること。
★7,市町村が避難所の予備電源として、自然エネルギーを設置した設置費用が補助される、大阪府の「グリーンニューディール基金」が、今年から、3年間実施されます。この基金を、避難所となる公共施設などへ、積極的に活用することを求めます。
次に、熱中症対策についてです。
エアコンの設置についてお聞きします。
猛暑の今年、 5月27日から9月1日までの、熱中症による救急搬送者は、全国で、5万6172人、大阪では3887人でした。死亡者は全国で88人、大阪で5人となりました。寝屋川市では、108人が救急搬送されています。
この夏、エアコンの設置については、何件かの相談がありました。
生活保護世帯が、社会福祉協議会から、低金利で「生活福祉資金」を借りて、エアコンを設置することについては、収入認定しない扱いとなり、借り入れができることになりました。しかし、無年金や就労収入がない人は、貸し付けの対象外で、エアコンの設置や修理の費用を借りることができません。
病気などで働けない状態で、保護費だけの収入の場合に、借り入れができないことは、命にかかわる問題です。
埼玉県、新座市の生活保護では、困った女性が、エアコンの修理費の支給を市に再三もとめ、市も認めました。
エアコンに水漏れがあることがわかり、女性が、市に修理費について聞くと「出ません」ということでした。女性は、3回市に要請。「睡眠障害でエアコンが必要」という、医師の診断書を提出しました。
その中で、市が研究して、提案したのは、女性が、5月まで得ていた就労収入について、通常12月に行っていた「特別控除」を、前倒しで実施して、修理にあてることにしました。緊急の要請に対して、市も研究して、こういう措置をとったものです。
ただし、この特別控除制度も8月に廃止されたので今後はできません。
また、東京都は、11年度に限り、緊急措置として、無収入の生保利用者を対象に、65才以上で、エアコンが必要との医師の診断がある場合に、4万円を上限に、独自助成を364世帯に行った例があります。
★ そこで、本市でも、エアコンがない、もしくは壊れて使えない、保護費だけの収入の世帯に対して①、東京都のような独自の助成を大阪府に要望すること、
②新座市のように、市独自の研究を行うなどして、エアコンのない世帯を、なくす努力をすること。③生活保護の「一時扶助」の家具什器費の増額で、エアコンの設置、修理費用に充てられるよう、国に要望すること
以上、3点、見解をお聞きします。
★④として、熱中症の予防策として、高齢者が、避難できる涼しい場所を市で確保すること、具体的には、公共施設などを活用して、避難所の設置や保冷剤などの配布を行うこと。この点について、どのようにされたのか、お聞きします。
★⑤、低所得者が自宅にエアコンを設置する場合の助成制度、融資制度をつくることを求め、見解をお聞きします。
最後に、市民の意見を聞き、反映する市政運営についてです。
「市民が主役のまちづくり」をうたった「寝屋川市みんなのまち基本条例」に、てらして、本市で初めての認定こども園の創設や、あかつき・ひばり園の指定管理者制度の導入についての、決め方、進め方などについては、市の姿勢に、重大な問題があると思います。 2つとも、子育てや、障害者施策の分野での重要な問題です。
認定こども園の開設については、幼保一体化への市民のニーズがあるという説明をされましたが、ニーズ調査もされておらず、保護者、関係者の理解や合意がないまま進められました。
結局、幼保一体化を始めるに当たっての準備は、できていませんでした。
幼保一体化の名で、狙いは、池田幼稚園の廃園でした。
園舎の場所については、先に述べたとおりです。
また、あかつき・ひばり園の「指定管理者制度の導入」については、市長公約にも、市の「アウトソーシング計画」にもありませんでした。そういう重要な問題を、トップダウンで何から何まで決めて、保護者、関係者検討会でたった3か月で、条例を上程するスケジュールそのものが問題です。
市は、検討会の中で、「確認書については、議会にだすものではない」としながら、保護者ら検討会のメンバーが、「まだ、確認しておきたいことがあるので時間がほしい」「仕様書についても、きちんと説明してほしい」などの意見が、あるのに、そのさなかに、条例を上程するというのは、極めて問題です。
これらの、市民生活に、大きく影響する「重要な問題」に対する、市の姿勢には、「市民がまちづくりの主人公」という視点は、全く、見えません。
2つの問題で共通するのは、「トップダウンで、何から何まで決める」ということです。いったい、「みんなのまち基本条例」は、何のために制定したのかと、言わざるを得ません。こういう姿勢で、市政運営を進めることは、重大な問題です。
★改めて、お聞きします。
この間の重要な問題における、市の姿勢は、「みんなのまち基本条例」の
第5条=市民と行政の協働、第7条=行政の透明性の確保、第8条=市民の知る権利の保障 第11条=市民の意見、提案を市政に反映させること、などに反していると考えます。見解をお聞きします。
★重要なことを、首脳会議で決め、市民の意見は何も聞かない、反映しない、見直しや変更さえしない、こうしたやり方はやめるべきです。
市の政策等の立案、計画などについては、市民の意見を聞いて、市民の意見を反映させるため、原点に立ち返って、市政運営をすすめるべきです。見解をお聞きします。
2013年 一般質問 田中市議
2013-09-12
初めに防災についてです。
関東大震災から90年、阪神淡路大震災や東日本大震災の教訓を、南海トラフ地震等の次の巨大震災に生かすことが重要です。また、最近では、豪雨や、竜巻など気象の異常が起き、日本列島でのその被害は凄まじいものがあります。
地球物理学者、随想家である寺田寅彦氏は、「おそれなさ過ぎることはよくないが、おそれすぎることもよくない。正しくおそれることが欠かせない」と名言を残されています。
震度6以上で家は倒壊、埋め立て地など液状化します。いかに人の命を守るか、が問われます。
防災には、行政の責任ですべての住民を守るための社会的責任を果たすことが基本だと考えます。
今年7月市は地域防災計画を策定されました。その内容と防災に関連して質問します。
予防施策についてです。
1.災害時、住宅の倒壊は、人の命を奪うだけでなく、道をふさぎ、人命救助や復興のさまたげになります。寝屋川市は、S56年以前の建物の耐震診断を促進するとしています。昨年度で木造住宅等耐震化率75.8%、2015年度には90%にするとしています。残りの約8,000を超える戸数をどのようにして耐震化率達成するのか、問われます。先ず、耐震診断を受けてもらうことが大切であり、市民に耐震診断制度の周知を行うことです。診断結果に対して、耐震強化の必要な住宅持ち主にたいし、相談をうけ、経済的に困難である場合、補助金増額も必要と考えます。
2.家具等転倒防止器具取付支援事業は、昨年私が質問し、高齢者のみ、高齢者世帯や障害者に今年7月から実施されました。利用者はまだ少ないとお聞きしました。
①非課税の人や非課税世帯には無料にすれば、利用が増えるのではありませんか。
②また、補助対象を高齢者・障害者だけでなく、低所得者等にも広げていくことを求めます。
3.地震でガス管は破壊されやすく、電気の火花でガスに引火し大火災になるおそれもあります。地震のゆれで電気ブレーカが落ちることが重要な対策です。感震ブレーカ設置のための助成金の創設をもとめます。
朝日新聞によりますと、国は1㌶に80戸以上が密集し、燃えにくさを示す指標の「不燃領域率」が40%未満の地域。道路や公園などの開放空間、耐火建物が占める面積を基に計算するこの指標が30%だと市街地の8割余りが焼失し、逆に40%以上だと2割以下の焼失に抑えられるとしています。その上で、木造住宅が密集し、大地震の時に起きる延焼火災に対して「最低限の安全性」が確保できていない地域として寝屋川市では、現在216㌶あるとしています。2001年に10年間での解消を目標にかかげていました。2003年には248㌶ありましたので少しは改善されていますが、居住者の高齢化や経済的な理由から建て替え意欲が生まれないことなどで建て替え手続きが進まない状況があります。
4.この解決には、これらの経済的な理由の人も入居できる低家賃の公営住宅が求められます。
5.大震災では、大火災にならない手だてが必要です。さらに火災では寝屋川市の3箇所の木造密集地がいちばん大震災の時に危険があるため、地震が起きれば、消防車を集中的に配備できる体制を検討するよう求めます。
以上、6点について答弁をもとめます。
自治体職員の体制についてです。
自治体の対応として全国的にも職員が平常時でも不足がちのため、防災機能が問われています。
1.大災害時に職員全員が、登庁できることは困難だと考えられます。また、災害時、職員は部署や課によって配置することが地域防災計画では決められていますが、その決められている配置の職員全員が活動できるとは、考えられません。例え、登庁できても、何時間後、何日後などで、何割の職員がその日に活動に参加できるのかが問われます。前もって検討しておくことが重要です。
2. 支援職員の応援があると聞きますが、行政として市民に責任を持った職員配置が必要です。
大災害時には、再任用、任期付き非常勤も参集の方向と聞きましたが、正職員で対応できることが基本と考えます。そのためには、新規採用を増やし、責任を果たせる職員体制を確保しておくべきです。正職員増員すべきです。
3.地域防災計画は、各部署の課長級が参加して作成したと聞いています。具体化にあたっては、災害時の体制等細やかな問題など一般職員の意見が反映されるものにすべきです。
以上3点について答弁を求めます。
防災情報についてです
静岡県藤枝市では要援護者本人・支援者用の2種類の防災マニュアルが出され、具体的に①独居高齢者・高齢者世帯・要介護・要支援者②身体障害者③知的障害者④精神障害者⑤発達障害者⑥妊産婦⑦乳幼児・児童ごとに「自分でできること」「人にお願いすること」等詳しく掲載し、「日頃からの備え」の重要性を説明したあと、災害が起きた場合の行動を地震(予知型、突発型)・一般災害(水害・土砂災害)ごとに説明を書いています。
また、身体障害者の障害の内容や、機能障害等状況に応じた、具体的なアドバイスを行った防災マニュアルが求められます。
1.そこで、このような防災マニュアルを作成し、地域包括支援センターや介護事業所、障害者通所施設、地域防災会などを通じて該当する人に配布することを求めます。
2.市の被災を想定し、市民が参画し、地域住民でもわかる避難所の運営の手引きを作ることを求めます。以上2点について見解をお聞きします。
避難所に関連してです。
災害が時の高齢者・障害者などの福祉避難所での対策の検討ですが、その後の進捗状況についてです。1.精神障害者は集団生活において困難が大きいと考えます。精神障害者の福祉避難所については、どのように検討されていますか。
2.避難所で停電になった場合、発電機では2~3日ほどしか持たず、復活できるまでもたないため、太陽光パネルによる発電・充電があれば、昼夜利用できます。太陽光の設置を計画的にすすめるよう求めます。
3.寝屋川市には、情報発信や物資提供の拠点として、避難所だけでなく、長期になれば在宅の被災者も支援できるように事前・事後の細やかな計画や応急対応が求められます。
4.食物アレルギーの人にも対応できる備蓄と、配食できる体制を考慮するよう求めます。
5.東日本大震災では、私たち日本共産党議員団も被災地を訪問しました。「十分ガソリンを準備していたけれども、実際には情報が不十分で、ガソリンが不足などによる連絡できなかった」ことが報告されていました。水や食料品の調達がいつ、どこで行われるのかなど、伝達もれのないよう、補う幾重もの伝達を行うことが求められ、そのための準備、備蓄が必要と考えます。
以上5点について答弁をお聞きします。
災害医療についてです
災害医療については、応急処置的な連携ができる方向になったと聞きましたが、透析については病院で引き受けてもらえるように求めます。見解をお聞きします。
原発についてです。
東日本大震災時、福島原発事故が起き、2年6ヶ月経ちましたが、いまだに収束できていない状況です。
福井県大飯町などでの原発事故が起きれば、風の方向にもよりますが、寝屋川市は80キロ圏内の境界線に入ります。滋賀は30~40キロ圏内に入り、山からの水は、琵琶湖に流れ、琵琶湖の水が放射能汚染により、私たちの飲み水が心配されます。市として市民の命・健康を守る立場で大飯原発の稼働はやめるよう求めることが市民のために重要と考えます。見解をお聞きします。
液状化についてです。
大震災の場合、寝屋川市は液状化が考えられます。寝屋川市のどの場所が液状化になるのか、まず調査し、把握すべきと考えます。見解をお聞きします。
また、液状化については千葉県浦安市では、住宅・生活再建支援として支援制度があります。住宅の被害程度に応じて支給され、全壊で100万円、大規模半壊50万円、住宅の再建では建設・購入で200万円、地盤復旧工事補修では、100万円、公営住宅を除く賃貸では50万円など、加算支援金としてだされています。その他、住宅解体補助なども出されています。市として千葉県浦安市の液状化についての施策等を調査し、寝屋川市に反映すべきと考えます。見解をお聞きします。
竜巻災害についてです。
竜巻災害について国が支援を行う方向ですが、寝屋川市でおきた場合、国の被災者生活再建支援制度の適用をもとめることや、市として生活再建支援等を検討すべきと考えます。見解をお聞きします。
次に介護保険についてです。
安倍政権は、公的介護・医療・年金・保育の諸制度を大改悪するため、手順を定めた「プログラム法案」の骨子を閣議決定しました。
介護では、①要支援者を保険給付からはずし、地域包括推進事業(仮称)として市町村の事業に位置づける ②一定以上の所得者の利用料を1割から2割などに引き上げる ③施設から要介護1・2の人をしめだす ④施設の居住費・食費を軽減する対象を預貯金や家などの資産により制限する、という改悪の内容をならべ、2014年の通常国会に法案を提出し、2015年度を目途に実施するとしています。
介護保険は当初、家族を介護の苦労から解放する、高齢者の「尊厳を保持」するというのがうたい文句でした。
介護保険制度が創設された2000年度当初は、要支援などはつくられていませんでした。要介護の1と2の軽度者を要支援に振り分けて、国の社会保障費の負担分を減らすために、今度は介護からはずしていく改悪です。
特養ホームから要介護1・2の入所者を切り捨てようとしていることも重大問題です。これらの高齢者は介護の困難や認知症の症状を抱えています。
また、一定の所得がある人の利用料を2割に倍増することは、生活維持できない高齢者を生みだします。
2014年の通常国会に提出されようとしている社会保障制度改革「プログラム」法案は、高齢者の生活を破壊するものであり、
1.政府に対し、社会保障制度改革「プログラム法案」の提出はやめ、撤回するよう市として求めるべきです。見解をお聞きします。
介護保険料についてです。
スタート時は、65歳以上の介護保険料は半年間は「無料」、その後1年間は「半額」その後は全額、その後は3年ごとに見直しとなりました。寝屋川市の基準額で第1期3,150円 、第5期4,740円と第1期と比較して1.5倍になっています。
国民年金はこの間どうでしょうか。2000年の時は、満額で年額804,200円、その後、5回引き下げがあり、現在786,500円とこの間17,700円の減額となっています。
介護保険のしくみの問題点は、今後も、高齢化が進み、介護サービス利用が増えればそれに比例して際限なく介護保険料は上がっていく。高齢者の負担能力と関係なく上がり続けることです。
そして、所得ゼロでも寝屋川市の場合、基準額の0.5 倍、28,440円となることです。
低所得の人ほど負担割合が重い、著しい逆進性となっていることです。
さらに政府は、今年10月から年金1%から、3回に分けて再来年4月には2.5%
削減しようとしています。
保険料を支払っても介護が受けられない状況で、高齢者の生活はさらに深刻となります。これまで市は、「政府からの通達で市の繰り入れをしてはいけないとしている。」として、市独自の減免をしてきませんでしたが、実際、他市では実施を行い、罰則もありません。
1.市民から要望が強く、多くの高齢者の願いである介護保険料の引き下げと減免制度の創設を求めます。
2.また、国に対し、介護保険に対する国の負担割合を増やすようもとめる事が重要と考えます。
以上2点について見解をお聞きします。
特別養護老人ホーム待機者解消についてです。
総務省は2012年10月1日現在、高齢者率は24、1%で4人に1人となりました。また、国勢調査結果によると独り暮らしの高齢者数は、対高齢者人口割合では16、4%となっています。
今年1月20日に放映された「NHKスペシャル 衝撃 老人漂流社会」は、独り暮らしができなくなった高齢者が「死に場所」を求めて、病院や施設を漂流し続けなければならない日本のつらい現実を映し出しました。その背景には低所得者が安心して入れる特養ホームの絶対数の不足があります。
2011年3月7日の参院予算員会で、日本共産党の山下よしき参院議員が、介護保険制度がスタートして10年経過したが、この間、特養ホームはどのくらい増えたのか、全国の特養ホームの定員と待機者の推移はどうだったのかについて質問しています。 2000年度当初、日本共産党が全都道府県の特養ホームの待機者数を調査したところ約10万5000人であったものが、厚生労動省の答弁では09年度の待機者数は約42万1000人と4倍に増えています。
寝屋川市では、月額20万円近くかかる介護型有料老人ホームは、サービス付き施設としてかなり増設されていますが、2000年の介護保険が始まる当初から比較しても今年600人を超えて、待機者は減っていない状況です。
1.10年後には全世帯の4割が高齢者世帯となり、うち7割が独居か老夫婦世帯という日本になるといわれています。それを見据えてしっかり寝屋川市としてどう取り組むかが問われています。
2.また、経済的理由で入所困難な人でも入所できる特別養護老人ホームの増設が切実に求められています。
以上2点について答弁をもとめます。
次に子育てについてです。
まず、子ども・子育て新制度についてです。
日本の景気回復につなげるため、「新たな産業分野をどう育成するか」から、子ども・子育て支援新制度の議論が始まり、保育・幼稚園・学童保育の分野に手をつけました。
児童福祉法は第24条一項(市町村の保育実施責任)が復活しました。しかし、企業産業推進のための子育て支援法はのこり、認定こども園法は改正され、新制度では幼稚園は認定こども園に入る入らないどちらでも選べることになり、これまでの認定こども園とは異質な制度にして、公的保育責任を形骸化、かつ複雑で多様な保育施設体系にしました。
政府は2017年度までに、40万人の待機児解消するとして2014年、15年の2年間で20万人の保育の定員増をはかる等の待機児対策を打ち出しています。しかし、その財源は消費税増税のみで待機児解消に向けた抜本的な取り組にはなっていません。その内容としては、
① 待機児の定義と保育ニーズの把握が必要ですが、現在、待機児でありながら認可外施設利用者は待機児とカウントされていません。実態は、カウントされている待機児の2倍以上だと報道されています。
② 保育所建設・整備計画と財源が示されていません。
③ 推計では実際に国負担約1割強の保育所運営費となっています。
これら3点から考えても待機児解消は難しいといえます。
保育所の需要と供給の状況では、待機児がある場合、行政の判断で事業計画を作成しなければならないとしています。寝屋川市では、0・1・2歳児、低年齢時の待機児は少なくなったとはいえ、母親が1ヶ月以内に仕事を見つけて働きたいと願われている潜在的待機児と合わせると少ないとは言えない待機児になります。
1.市には潜在的待機児が実際倍以上おられます。低年齢時の保育所が求められています。スープの冷めない場所に分園などを積極的に設置すべきと考えます。見解をお聞きします。
認定こども園法は、幼保連携型幼稚園の中に延長保育をしている幼稚園型、主に保育所で、その中に幼稚園機能がある保育所型の財産措置は、施設給付で一本化します。
その他、認可外であるけれど、利用できる子を認定し、公費負担で保育料を補助する、地方裁量型としています。
保育時間は、3歳未満は保護者の就労時間等に応じた保育。満3歳以上では標準的な教育時間及び保護者の就労時間等に応じた保育とし、給付は、それぞれに対応して行われます。
市の役割は、①保育の必要性の認定・認定証の交付。②利用者の希望と施設の利用状況との調整。③利用可能な施設の斡旋・要請などをするとしています。
株式会社の参入は、「営利目的の株式会社と保育が両立するのか」という重大な問題があります。もうけにならないと突然に廃園するということが実際に起きています。
東京都中野区の保育所「ハッピースマイル」が閉園を知らせる1枚のファックスを閉園前日に保護者や職員に送ってきた事例などがあります。
2.また、子育て支援法では、上乗せ、実施の費用徴収を認めることは「応益負担」を一部導入することになります。通常の保育以外の特別な保育を受けることができる子どもと、そうでない子どもが生まれ、保護者の所得により子どもの保育に格差が生じ、保育の平等性という観点からも問題があります。子ども・子育て新支援法はやめるよう求めるべきと考えます。見解をお聞きします。
政府は、子ども・子育て支援新制度は消費税増税に関係なく進めようとしています。その上で、お聞きします。
1.自治体負担分を大幅に軽減させる財政負担措置として、子ども・子育て支援法附則6条(保育所に関わる委託費の支払い等)にもとづいて、施設への補助金制度を国に創設するよう求めるべきと考えます。見解をお聞きします。
小規模保育、家庭的保育(保育ママ)、居宅訪問型保育(ベビーシッター)、事業所内保育の4類型は、国の目安が出される方向ですが、大幅な規制緩和で進められています。認可するのは市になることから、条例案を市がつくるとされています。
2.市の条例では、地域型保育であっても、コストを上げずにできるだけ子ども達の発達条件、例えば、保育士の資格や経験年数、人数・施設の面積など、こども達にとってよりよいものにすべきと考えます。見解をお聞きします。
内閣府に子ども・子育て本部を設置し、市町村に地方版子ども・子育て会議の設置努力義務が課せられました。
その上で、寝屋川市は14人の構成で子ども・子育て会議をこれまで2回開催しています。寝屋川市子どもプラン推進地域協議会のメンバー構成で引き継がれ、2年任期で就任されています。今年度4回、来年度5~6回程度開催し、来年の秋頃には素案を作成し、その後パブリックコメントを行うとしています。
3.「子ども・子育て会議」メンバーには保育所・幼稚園・学童保育など、保護者や元保護者関係者なども追加すべきと考えます。答弁をもとめます。
留守家庭児童会についてです。
子ども・子育て新制度では、2015年度までに留守家庭児童会の対象を小学校6年生まで広げるとしています。指導員、部屋の確保など体制をどのように考えているのか、お聞きします。
公立保育所老朽化についてです。
公立保育所はさくら保育所が昭和45年4月開所、一番新しいあざみ保育所で昭和54年5月開所となっています。昭和56年以前に建設された施設で老朽化が進んでいます。耐震診断、耐震強化もされていない状況です。
公立幼稚園では、北幼稚園は昭和31年開所でしたが、建て替えられ、その他の池田幼稚園を除いて4園中、開所から一番新しいのは、啓明幼稚園で昭和51年4月となっています。今年、耐震診断を行い、結果によってこれから検討すると聴きました。
そのうえで、1.公立保育所の幼いこどもたちの命を守るためにも早急な耐震診断、耐震強化が求められます。
2.また、民間保育園では7箇所、民間幼稚園では24年度2箇所から耐震診断補助金申請が行われたと聞きます。その結果をうけて耐震強化工事について調査、把握すべきです。
3.また、その他の民間保育園・民間幼稚園の状況を調査把握し、耐震化を進めるよう指導すべきです。
以上3点についてお聞きします。
最後に市民プールについてです。
今年は猛暑でした。子どもたちにとって市民プールは夏の楽しみの場所、憩いの場所となっていました。こんな暑い夏こそ身近なプールで自由に泳ぎ遊べたらと多くの市民からの声があります。「なみはやドームは子どもだけでは遠すぎて行かせられへん」「なみはやドームは電車・バス代が必要やし、車だったら駐車場代が3時間で1,000円以上かかるわ」「結局、王仁プールに連れて行った」などの声が寄せられています。
市民プール廃止にあたって、市は、2012年6月1日よりなみはやドームプールの利用の緩和策として市民プールの利用額と同額にする補助事業を始めました。
昨年6月1日から今年3月末までの利用者数は、大人888人、子ども478人で合計1,366人でした。
今年度4月1日から8月末まででは、 利用者数は大人906人子ども502人で合計1,408人となっています。昨年と比較してやや増加しています。
しかし、市民プールでは7~8月の2ヶ月で3万人から5万人近くが利用していました。
そこでお聞きします。
1.緩和策としてなみはやドームプール利用の補助をされましたが、市民プールでの利 用と比較してあまりにも利用できていない実態をどう考えますか?
2.こども達や市民の声を聴かず、なくした責任をどう考えていますか?
3.市民プール跡地は、公園となっていますが、ほとんどといっていいほど利用されていないと聴きます。この状況をどう考えますか。
以上3点について答弁をもとめます。
2013年 一般質問 松尾市議
2013-09-12
第1に市財政の基本的なあり方についてです
1.まず市財政の現状認識についてです。
寝屋川市は、30年近く前に、「赤字日本一」が4年連続続いたこともあり、「市財政が赤字で大変」と思っている市民も少なくありません。
しかし、寝屋川市の財政は、赤字ではありません。
一般会計では、単年度も累積でも、9年連続黒字が続いています。
しかも、国民健康保険会計など、特別会計も含めた全会計合計でも、12年度決算で約4億円の黒字となっています。全会計合計での黒字は、1970年度以来、実に43年ぶりのことです。
12年度一般会計決算は黒字の上に、15億5000万円の基金(減債基金、財政調整基金)を積み立て、退職手当債の発行も行っていません。
このように、市の財政は明らかに好転しており、「赤字でたいへん」とは言えない状況となっています。現状は赤字財政から明らかに脱却したと考えます。現状認識について答弁を求めます。
2.問題は中味だという点についてです。
地方自治体の財政を考える上で、「名誉の赤字」「不名誉の黒字」と言う言葉があります。この言葉は、自治体財政とはそもそも何のためにあるのか、という根底的な問いかけを含んでいます。
自治体財政は、もともと住民の仕事と暮らしを守るためにあること。国の不十分な地方財政制度、反国民的な政策のもとで、自治体が住民を守るために、懸命に仕事をすれば、お金が足りなくなって赤字が出るのは当たり前ではないか。そういう赤字は自治体としてはすべきことをした、証拠の「名誉」のしるしだというものです。
逆に住民の苦しみに知らぬふりをして仕事をせずにほっておけば、お金は残って黒字になる、これは自治体として「不名誉」のしるしではないか、という意味です。
単純に数字だけで評価するのでなく、市財政は誰のために、何のために活用するのかが問われます。これらの点について見解を求めます。
3.基金のあり方などに関わって、市財政のあり方についです。
寝屋川市はこの間、大型開発を優先し、福祉、教育の後退を進めてきました。
今「将来を見据えた街の創造」「財政基盤の強化」などとして、さらに黒字をふやし、基金を増やそうとしています。
しかし、自治体のお金は何よりも市民のくらしを守るためにあります。
今寝屋川市がやるべきことは、国民健康保険料、介護保険料の引き下げをはじめ、市民の切実な要求を実現することです。
市財政が市民の暮らしを守るためものであるという、本来の役割を果たすよう求め、見解をお聞きします。。
次に生活保護についてです。
生活保護制度の基本的なあり方に関わってです。
日本の生活保護制度での最大の問題は、本来生活保護を利用できる世帯の多くが、利用できていない実態があることです。
わが国の世帯貧困率は25.1%、全世帯の4分の1が、生活保護制度によって公的に保障されるはずの所得、または、それ以下の所得で生活しています。
これに対して、現に生活保護を利用している世帯は、3%程度で、要保護世帯の9割弱が、漏給・給付漏れという状況です。ところが生活保護でいちばんの問題が、「不正受給」であるとの宣伝が、マスコミなどを通じて大量に流されています。
しかし、厚生労働省は、11年度の不正受給額は年間支給総額の0.4%と公表しています。寝屋川市の場合も、不正受給は12年度114件・5,500万円で、支給総額の0.4%となっています。
政府が不正受給としているものの中には、調査不足による年金の未把握や、高校生のアルバイト収入の未申告なども含まれています。
マスコミで大きな問題にするほど不正受給が多い実態ではありません。
もちろん、生活保護制度への信頼を維持するためにも、悪質な不正受給に対しては厳正に対処すべきですが、実態に見合った冷静な受けとめが求められます。
寝屋川市は、11年8月から「生活保護ホットライン」を設置。2人の担当者を配置し、専用電話で市民に通報を呼びかけています。
市の公共施設などに「生活保護の不正受給は許しません」等と書いたポスターをはりだしています。
しかし、住民同士を監視させ密告を奨励するもので、生活保護を必要とする人が、申請に二の足を踏むなど、利用抑制につながることが、大きな問題です。
「ホットライン」と称した特別な組織はやめるようもとめ、見解をお聞きします。
本来ケースワーカーをきちんと配置し、利用者の実態を正確に把握する中で、不正受給の問題は解決すべきものです。
この点についても見解をお聞きします。
その一方、市は生活保護について、市民に制度の内容を知らせることを、ほとんどしていません。
福祉施策は、基本的には、本人からの申請があって初めて、施策の適用がされます。そのためにも、どんな制度か市民に知らせることが必要不可欠です。
高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉などでは、市は独自に冊子をつくり、ホームページでも制度紹介をしています。
しかし、生活保護については、ホームページの「その他の福祉制度」の一つとして、わずか12行程度しか掲載していません。しかもその内容は、ごく例外的な場合にしか、生活保護がうけられないことを強調したものとなっています。
今、生活保護で大事なことは、制度を市民に周知し、必要な市民が利用できる制度にすることです。
とりわけ、憲法25条の生存権に基づく、国民の権利としての徹底の周知をはかることが必要です。見解を求めます。
次に生活保護費と市の財政負担についてです
生活保護費を初めとする扶助費の増加が、市財政を圧迫しているとの宣伝がされていますが、これは正しくありません。
生活保護費は法定受託事務であり、かなり国のしばりが強いものです。国の負担義務が大きい経費です。生活保護費では国が4分の3を負担し、残り4分の1の自治体負担分は、地方交付税で国が措置しています。
従って、基本的には市の負担が内者です。国の地方交付税措置は10万人規模の自治体をモデルにし、各自治体ごとに補正係数を掛けて算出していますので、かなり実質に近い数字になっています。
寝屋川市でも、財政かによれば、4分に1の市負担の8割から9割が交付税で措置されているとしています。生活保護費にしめる市の財政負担は、支出の数%にとどまります。
このような事実を明らかにせず、「生活保護がふえて市財政はたいへん」等言って、住民の中で対立をつくるようなことは、すべきではありません。
(1)これらをふまえると性格に伝えるべきではありませんか
(2)抜本的解決策として国に対して10割の支給を求めるべきです。
以上2点について答弁を求めます。
次に難病患者への福祉サービスについてです。
今年4月から障害者総合支援法が施行され、難病患者に対して居宅保護や補装具、日常生活用具の給付など障害福祉サービスの利用が可能となりました。また児童福祉法も改正され、障害児の範囲に難病等が追加されました。
これらの改正により130の疾患が法律の対象となり、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得は出来ないが、疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けている人に対して、障害者総合支援法に基づくサービスが利用できるようになりました。
各自治体での制度周知が十分でないと聞きます。本市でも市広報で1度短く掲載されましたが、ホームページでは掲載されていません。広報、ホームページ、チラシなど積極的な周知を求めます。答弁をお聞きします
次に廃プラ処理施設による健康被害についてです。
寝屋川廃プラ公害の原因を調べている、国の公害等調整委員会、公調委が今年1月に実施した化学物質と気象調査の結果が5月16日付けで、一部公開されました。また3人の専門委員の意見書も報告されました。
調査の
から、廃プラ施設からの化学物質の大量排出、その中に多くの未知物質があること、化学物質がよどむ接地逆転層の発生が確認されました。
同時にホルムアルデヒドの調査結果が公表されていないことを初め、調査は不十分であり、さらに必要な調査がもとめられます。
6月議会での市理事者答弁をふまえ、以下質問します。
1.化学物質が大量に発生している事実どう認識するのかについてです。
今回の公調委調査、測定で多量のVOCの排出が確認されました。
市役所測定局 の 年間平均値1立方メートル当たり100マイクログラムです。今回調査では、4市施設組合で4,877マイクログラム、イコール社で、9,564マイクログラムが検出されました。高濃度の化学物質が施設から発生していることが改めて明らかになりました。施設に近くに住んでいる住民への影響が考えられるのではありませんか?
2.未知の化学物質についてです。
今回の検出された化学物質では名前も毒性も分からない未知物質が多くありました。サンコート太秦ヒル屋上で36物質、あさひ丘配水場屋上で46物質、寝屋公民館屋上で41物質で、半分以上が未知物質です。
この多くの未知物質の中に、健康に有害な物質がないと断定できますか?
3.ホルムアルデヒドの再調査についてです。
今回の調査で最も注目された物質の1つは、ホルムアルデヒドです。
東京大学の柳沢名誉教授は、太秦地域での調査から、発ガン性やシックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドが、一般空気の10倍以上も検出されたことを明らかにしてきました。
住民は、この事実を公調委に示し、原因物質の一つとして可能性があるとしています。ホルムアルデヒドの高濃度の発生は、廃プラ施設から排出されるブタン類など高濃度の化学物質が太陽光線で反応し、2次発生するメカニズムがあると考えられています。
こうした事情から、今回調査では、ホルムアルデヒドについて、1日平均値以外に、30分ごとの連続測定が計画されました。
ところが、公調委の報告は調査結果に疑問があるとして、データーが不採用とされ、公表されず、再調査も行われていません。公調委専門委員の東賢一氏も厚生労働省のシックハウス問題に関する検討会で、ホルムアルデヒドの規制値の評価は30分測定によるものであり、30分平均値以下でないといけないと発言しています。 これらをふまえても、調査もせずに安全とはとても言えません。再調査が必要ではありませんか ?
4.ニオイと化学物質の関係についてです。
04年イコール社試運転開始以降、異臭感じた住民が市にあいついで苦情を寄せています。その後も継続して悪臭への苦情が続きました。市もイコール社への臭気パトロール実施しています。悪臭の発生当初から原因施設は明確です。ところが、公調委東専門委員の意見書は、「住民が強く感じた臭いの原因が発生源施設から排出される物質によるものとは考えにくかった」としています。住民が継続して異臭感じていることが、化学物質が到達している動かぬ証拠ではありませんか?
5・接地逆転層の形成についてです
当該地域には、接地逆転層がひんぱんに、とくに夕刻から翌日朝に到る時間帯は毎日のように形成されること。
これら接地逆転層とそれに関わる、静穏や低風速という気象条件が、廃プラ処理施設からの排気の移流拡散に決定的影響を及ぼすこと。
結果として、接地逆転層の形成時には、廃プラ処理施設からの排気は、風向きによっては、ほとんど拡散しない状態で申請人ら居住地区へ移流到達する可能性があることが今回の調査で明らかにされました。このことは、現地測定や神戸商船大学西川名誉教授の意見書等に基づいて、申請人らが主張してきたことが妥当であったことが確認されたといえるのではありませんか?
6.疫学調査の実施についてです
住民の健康被害のうったえ、医師の診断によれば太秦、高宮以外の地域である三井が丘、成田東ヶ丘などに被害が広がっています。住民の健康調査、疫学調査を市として実施すべきではありませんか?
7.公調委の審査中に一方的な結論出さないことについてです
公調委は現在審理中です。申請人である住民は再調査、追加調査など求めています。
公調委は今回の調査結果や専門委員の意見書についても、今後説明会をもち、議論するとしています。審査の途中であるにもかかわらず、市が一方的な結論を出すことはやめるべきではありませんか?
イコール社の民事再生についてです
リサイクルアンドイコール社の親会社である、株式会社ワールドロジが、8月30日破産手続きを開始しました。連結子会社4社も自己破産申請をしています。一方、イコール社は8月30日、民事再生法の適用を申請しています。イコール社の負債は26億8500万円にものぼっています。
この動きについて市はどのように把握していますか?
また今後の廃プラ処理事業与える影響はどのようなものですか?
以上8点について答弁を求めます。
1.まず市財政の現状認識についてです。
寝屋川市は、30年近く前に、「赤字日本一」が4年連続続いたこともあり、「市財政が赤字で大変」と思っている市民も少なくありません。
しかし、寝屋川市の財政は、赤字ではありません。
一般会計では、単年度も累積でも、9年連続黒字が続いています。
しかも、国民健康保険会計など、特別会計も含めた全会計合計でも、12年度決算で約4億円の黒字となっています。全会計合計での黒字は、1970年度以来、実に43年ぶりのことです。
12年度一般会計決算は黒字の上に、15億5000万円の基金(減債基金、財政調整基金)を積み立て、退職手当債の発行も行っていません。
このように、市の財政は明らかに好転しており、「赤字でたいへん」とは言えない状況となっています。現状は赤字財政から明らかに脱却したと考えます。現状認識について答弁を求めます。
2.問題は中味だという点についてです。
地方自治体の財政を考える上で、「名誉の赤字」「不名誉の黒字」と言う言葉があります。この言葉は、自治体財政とはそもそも何のためにあるのか、という根底的な問いかけを含んでいます。
自治体財政は、もともと住民の仕事と暮らしを守るためにあること。国の不十分な地方財政制度、反国民的な政策のもとで、自治体が住民を守るために、懸命に仕事をすれば、お金が足りなくなって赤字が出るのは当たり前ではないか。そういう赤字は自治体としてはすべきことをした、証拠の「名誉」のしるしだというものです。
逆に住民の苦しみに知らぬふりをして仕事をせずにほっておけば、お金は残って黒字になる、これは自治体として「不名誉」のしるしではないか、という意味です。
単純に数字だけで評価するのでなく、市財政は誰のために、何のために活用するのかが問われます。これらの点について見解を求めます。
3.基金のあり方などに関わって、市財政のあり方についです。
寝屋川市はこの間、大型開発を優先し、福祉、教育の後退を進めてきました。
今「将来を見据えた街の創造」「財政基盤の強化」などとして、さらに黒字をふやし、基金を増やそうとしています。
しかし、自治体のお金は何よりも市民のくらしを守るためにあります。
今寝屋川市がやるべきことは、国民健康保険料、介護保険料の引き下げをはじめ、市民の切実な要求を実現することです。
市財政が市民の暮らしを守るためものであるという、本来の役割を果たすよう求め、見解をお聞きします。。
次に生活保護についてです。
生活保護制度の基本的なあり方に関わってです。
日本の生活保護制度での最大の問題は、本来生活保護を利用できる世帯の多くが、利用できていない実態があることです。
わが国の世帯貧困率は25.1%、全世帯の4分の1が、生活保護制度によって公的に保障されるはずの所得、または、それ以下の所得で生活しています。
これに対して、現に生活保護を利用している世帯は、3%程度で、要保護世帯の9割弱が、漏給・給付漏れという状況です。ところが生活保護でいちばんの問題が、「不正受給」であるとの宣伝が、マスコミなどを通じて大量に流されています。
しかし、厚生労働省は、11年度の不正受給額は年間支給総額の0.4%と公表しています。寝屋川市の場合も、不正受給は12年度114件・5,500万円で、支給総額の0.4%となっています。
政府が不正受給としているものの中には、調査不足による年金の未把握や、高校生のアルバイト収入の未申告なども含まれています。
マスコミで大きな問題にするほど不正受給が多い実態ではありません。
もちろん、生活保護制度への信頼を維持するためにも、悪質な不正受給に対しては厳正に対処すべきですが、実態に見合った冷静な受けとめが求められます。
寝屋川市は、11年8月から「生活保護ホットライン」を設置。2人の担当者を配置し、専用電話で市民に通報を呼びかけています。
市の公共施設などに「生活保護の不正受給は許しません」等と書いたポスターをはりだしています。
しかし、住民同士を監視させ密告を奨励するもので、生活保護を必要とする人が、申請に二の足を踏むなど、利用抑制につながることが、大きな問題です。
「ホットライン」と称した特別な組織はやめるようもとめ、見解をお聞きします。
本来ケースワーカーをきちんと配置し、利用者の実態を正確に把握する中で、不正受給の問題は解決すべきものです。
この点についても見解をお聞きします。
その一方、市は生活保護について、市民に制度の内容を知らせることを、ほとんどしていません。
福祉施策は、基本的には、本人からの申請があって初めて、施策の適用がされます。そのためにも、どんな制度か市民に知らせることが必要不可欠です。
高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉などでは、市は独自に冊子をつくり、ホームページでも制度紹介をしています。
しかし、生活保護については、ホームページの「その他の福祉制度」の一つとして、わずか12行程度しか掲載していません。しかもその内容は、ごく例外的な場合にしか、生活保護がうけられないことを強調したものとなっています。
今、生活保護で大事なことは、制度を市民に周知し、必要な市民が利用できる制度にすることです。
とりわけ、憲法25条の生存権に基づく、国民の権利としての徹底の周知をはかることが必要です。見解を求めます。
次に生活保護費と市の財政負担についてです
生活保護費を初めとする扶助費の増加が、市財政を圧迫しているとの宣伝がされていますが、これは正しくありません。
生活保護費は法定受託事務であり、かなり国のしばりが強いものです。国の負担義務が大きい経費です。生活保護費では国が4分の3を負担し、残り4分の1の自治体負担分は、地方交付税で国が措置しています。
従って、基本的には市の負担が内者です。国の地方交付税措置は10万人規模の自治体をモデルにし、各自治体ごとに補正係数を掛けて算出していますので、かなり実質に近い数字になっています。
寝屋川市でも、財政かによれば、4分に1の市負担の8割から9割が交付税で措置されているとしています。生活保護費にしめる市の財政負担は、支出の数%にとどまります。
このような事実を明らかにせず、「生活保護がふえて市財政はたいへん」等言って、住民の中で対立をつくるようなことは、すべきではありません。
(1)これらをふまえると性格に伝えるべきではありませんか
(2)抜本的解決策として国に対して10割の支給を求めるべきです。
以上2点について答弁を求めます。
次に難病患者への福祉サービスについてです。
今年4月から障害者総合支援法が施行され、難病患者に対して居宅保護や補装具、日常生活用具の給付など障害福祉サービスの利用が可能となりました。また児童福祉法も改正され、障害児の範囲に難病等が追加されました。
これらの改正により130の疾患が法律の対象となり、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得は出来ないが、疾病による障害により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けている人に対して、障害者総合支援法に基づくサービスが利用できるようになりました。
各自治体での制度周知が十分でないと聞きます。本市でも市広報で1度短く掲載されましたが、ホームページでは掲載されていません。広報、ホームページ、チラシなど積極的な周知を求めます。答弁をお聞きします
次に廃プラ処理施設による健康被害についてです。
寝屋川廃プラ公害の原因を調べている、国の公害等調整委員会、公調委が今年1月に実施した化学物質と気象調査の結果が5月16日付けで、一部公開されました。また3人の専門委員の意見書も報告されました。
調査の
から、廃プラ施設からの化学物質の大量排出、その中に多くの未知物質があること、化学物質がよどむ接地逆転層の発生が確認されました。
同時にホルムアルデヒドの調査結果が公表されていないことを初め、調査は不十分であり、さらに必要な調査がもとめられます。
6月議会での市理事者答弁をふまえ、以下質問します。
1.化学物質が大量に発生している事実どう認識するのかについてです。
今回の公調委調査、測定で多量のVOCの排出が確認されました。
市役所測定局 の 年間平均値1立方メートル当たり100マイクログラムです。今回調査では、4市施設組合で4,877マイクログラム、イコール社で、9,564マイクログラムが検出されました。高濃度の化学物質が施設から発生していることが改めて明らかになりました。施設に近くに住んでいる住民への影響が考えられるのではありませんか?
2.未知の化学物質についてです。
今回の検出された化学物質では名前も毒性も分からない未知物質が多くありました。サンコート太秦ヒル屋上で36物質、あさひ丘配水場屋上で46物質、寝屋公民館屋上で41物質で、半分以上が未知物質です。
この多くの未知物質の中に、健康に有害な物質がないと断定できますか?
3.ホルムアルデヒドの再調査についてです。
今回の調査で最も注目された物質の1つは、ホルムアルデヒドです。
東京大学の柳沢名誉教授は、太秦地域での調査から、発ガン性やシックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒドが、一般空気の10倍以上も検出されたことを明らかにしてきました。
住民は、この事実を公調委に示し、原因物質の一つとして可能性があるとしています。ホルムアルデヒドの高濃度の発生は、廃プラ施設から排出されるブタン類など高濃度の化学物質が太陽光線で反応し、2次発生するメカニズムがあると考えられています。
こうした事情から、今回調査では、ホルムアルデヒドについて、1日平均値以外に、30分ごとの連続測定が計画されました。
ところが、公調委の報告は調査結果に疑問があるとして、データーが不採用とされ、公表されず、再調査も行われていません。公調委専門委員の東賢一氏も厚生労働省のシックハウス問題に関する検討会で、ホルムアルデヒドの規制値の評価は30分測定によるものであり、30分平均値以下でないといけないと発言しています。 これらをふまえても、調査もせずに安全とはとても言えません。再調査が必要ではありませんか ?
4.ニオイと化学物質の関係についてです。
04年イコール社試運転開始以降、異臭感じた住民が市にあいついで苦情を寄せています。その後も継続して悪臭への苦情が続きました。市もイコール社への臭気パトロール実施しています。悪臭の発生当初から原因施設は明確です。ところが、公調委東専門委員の意見書は、「住民が強く感じた臭いの原因が発生源施設から排出される物質によるものとは考えにくかった」としています。住民が継続して異臭感じていることが、化学物質が到達している動かぬ証拠ではありませんか?
5・接地逆転層の形成についてです
当該地域には、接地逆転層がひんぱんに、とくに夕刻から翌日朝に到る時間帯は毎日のように形成されること。
これら接地逆転層とそれに関わる、静穏や低風速という気象条件が、廃プラ処理施設からの排気の移流拡散に決定的影響を及ぼすこと。
結果として、接地逆転層の形成時には、廃プラ処理施設からの排気は、風向きによっては、ほとんど拡散しない状態で申請人ら居住地区へ移流到達する可能性があることが今回の調査で明らかにされました。このことは、現地測定や神戸商船大学西川名誉教授の意見書等に基づいて、申請人らが主張してきたことが妥当であったことが確認されたといえるのではありませんか?
6.疫学調査の実施についてです
住民の健康被害のうったえ、医師の診断によれば太秦、高宮以外の地域である三井が丘、成田東ヶ丘などに被害が広がっています。住民の健康調査、疫学調査を市として実施すべきではありませんか?
7.公調委の審査中に一方的な結論出さないことについてです
公調委は現在審理中です。申請人である住民は再調査、追加調査など求めています。
公調委は今回の調査結果や専門委員の意見書についても、今後説明会をもち、議論するとしています。審査の途中であるにもかかわらず、市が一方的な結論を出すことはやめるべきではありませんか?
イコール社の民事再生についてです
リサイクルアンドイコール社の親会社である、株式会社ワールドロジが、8月30日破産手続きを開始しました。連結子会社4社も自己破産申請をしています。一方、イコール社は8月30日、民事再生法の適用を申請しています。イコール社の負債は26億8500万円にものぼっています。
この動きについて市はどのように把握していますか?
また今後の廃プラ処理事業与える影響はどのようなものですか?
以上8点について答弁を求めます。
2013年 一般質問 太田議員
2013-09-12
○国民健康保険について
安倍晋三内閣が環太平洋連携協定(TPP)の交渉参加を決めたことに、医療関係者からは日本の公的医療保険制度の崩壊につながることへの強い懸念と不安の声が上がっています。安倍首相は「公的医療保険は交渉対象でない」「国民皆保険制度は断固守る」などと繰り返しますが、その根拠は何も示すことができません。むしろ公的医療保険の根幹を揺るがすTPPの危険な実態が明らかになっています。
すべての国民がなんらかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」は、1962年に自営業者や農家の人たちが加入する市町村単位の国民健康保険導入によって確立され、半世紀以上、国民の命と健康を守る役割を果たしてきました。
「いつでも、どこでも、だれでも必要な医療をうけることができる」という医療の平等の大原則は、戦後日本の長寿社会実現を支えるなど、WHO(世界保健機関)をはじめ世界の医療・保健関係者からも評価されています。
あらゆる商品やサービスの取引が対象になるTPPでは、この「国民皆保険」の根幹を掘り崩す交渉がおこなわれる危険が次々と浮き彫りになっています。
その一つは、公的保険の使える薬の値段が大幅に高騰する問題です。日本では、必要な薬が公的保険で使えるように、政府が価格を決める仕組みをとっています。ところが米国は、自国の製薬会社に利益を保障しない仕組みを「不透明だ」と問題視し、価格決定に製薬企業が参加できる制度などを求め続けてきました。
TPP交渉で、薬価を決めるルールづくりが交渉対象になることを政府も認めています。米国流のやり方がTPPで「共通のルール」として決まれば、いまでも高い日本の薬価はさらに高騰し、保険財政を圧迫する事態を引き起こします。必要な薬が公的保険の適用対象から外されて、患者の全額自費負担になりかねません。「国民皆保険」を崩すものです。
米国などTPP交渉参加国で当たり前となっている「営利企業の病院経営参入」も、大きな焦点として浮上しています。
日本で「営利企業の参入」を厳しく禁止しているのは、医療機関が金もうけ優先に走らず、「安心・安全」の医療を平等に提供する「皆保険」の理念にもとづいているからです。「営利企業の参入」解禁は、“もうけにならない患者”を排除する医療がまかりとおる社会を現実のものとします。
TPPは公的医療保険がなく「お金がなければ、まともな医療を受けられない」という米国の「市場原理主義ルール」が基本です。それへの参加は、「国民皆保険」とは両立しないことは明白です。
安倍政権が「国民皆保険を守る」という一方で、政府の規制改革会議が、所得の違いで受ける医療に格差ができる「混合診療」の全面解禁に道を開く議論をおこなうなど、“二枚舌”で「国民皆保険」を骨抜きにする動きをすすめていることは重大です。
そんな中、日本医師会では、日本がTPPに参加した場合の懸念事項として、以下の4項目を挙げています。
1.日本での混合診療の全面解禁により、公的医療保険の給付が縮小する。
2.医療の事後チェック等による公的医療保険の安全性が低下する。
3.株式会社の医療機関経営への参入を通じた、患者の不利益が拡大する。
4.医師、看護師、患者の国際的な移動が、医師不足、医師偏在に拍車をかけ、さらなる地域医療の崩壊を招く。
更に、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の三医師会は以下の点を指摘し、公的医療制度がTPPの適用対象になる恐れを示しています。
1.「新成長戦略」の閣議決定により、医療・介護・健康関連産業が日本の成長牽引産業として明確に位置づけられ、医療の営利産業化に向けた動きが急展開している。
2.米国はかねてより日本の医療に市場原理の導入を求め、混合診療の全面解禁や医療への株式会社参入を要求。さらに、薬価算定ルールに干渉し、医療サービス分野で営利目的の参入を求めている。
3.米韓FTAでは、医薬品、医療機器の償還価格にまで踏み込んだ内容になっていること。FTAの枠組みを超える経済連携を目指しているTPP下で、混合診療が全面解禁されれば、公的医療保険の存在が自由価格の医療市場の拡大を阻害しているとして、提訴される恐れがある。ということです。
国民皆保険制度の根幹である国民健康保険の運営を担っている自治体として、市民の命、健康を守る立場から、皆保険制度の存続を危うくするTPPへの参加に反対することを国に対して求めて行くことが必要と考えます。国の動向を注視するだけでなく、市として積極的に市民の命に責任を持つ自治体としての役割を発揮することを求めます。市の考え方を示してください。
次に社会保障制度改革国民会議で示された国保の広域化に対する考え方についてです。
社会保障制度改革国民会議の報告書では、「効率的な医療提供体制への改革を実効あらしめる観点からは、国民健康保険に係る財政運営の責任を担う主体(保険者)を都道府県とし、更に地域における医療提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給付責任の主体を都道府県が一体的に担うことを射程に入れて実務的検討を進め、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体制を実現すべきである。ただし、国民健康保険の運営に関する業務について、財政運営を始めとして都道府県が担うことを基本としつつ、保険料の賦課徴収・保健事業など引き続き市町村が担うことが適切な業務が存在することから、都道府県と市町村が適切に役割分担を行い、市町村の保険料収納や医療費適正化へのインセンティブを損なうことのない分権的な仕組みを目指すべきである。」とされました。
議論の中身を見て行くと結局は、国保の広域化は都道府県単位とし、市町村の一般会計繰入による国保料の軽減をやめさせ、さらなる「保険料の引上げ」を行うこと。市町村が一般会計繰り入れによる住民負担を軽減すると「格差」が生まれ、「広域化」の妨げになるというのが言い分です。“悪い方”にあわせるのが「格差是正」というわけです。
また、広域化で国保運営が安定するかのように報告されています。しかし現実の府内、市町村の国保会計を見ますと、大阪府下では一番大きな大阪市の国保が被保険者一人あたりの法定外繰り入れが一番大きい額になっているのにもかかわらず一番の累積赤字をのこしている状態です。
そして国保会計は、後期高齢者医療制度が導入されて以降、全体的には黒字に転換し、あと2.3年で全国的に累積赤字を解消しそうな状況があります。国保会計の中味を見れば、自治体からの法定外繰り入れをなくせば全体的には赤字になるのが現在の国保会計の実態です。
以上の事からも広域化をしても、被保険者数が増えても国保の運営が安定することはあり得ません。自治体が市民の生活を守る為の努力、法定外繰り入れでなんとか厳しいながらも運営されているのが実態です。
また、広域化をすることで市町村の保険料収納や医療費適正化へのインセンティブを損なうことのない分権的な仕組みを目指すべきである。とただし書きされましたが、基本は、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体制を実現すべきである。とされており各自治体の保険料が一定統一される方向であることも予想されます。各市が市民からの保険料に対する追及に対して責任が表面上なくなることは大きな問題です。大阪府下では国保料が統一されれば国保料の大幅な引き上げも予想されます。
結局、後期高齢者医療制度のように被保険者から遠いところに制度設計がなされると細やかな対応ができなくなる現実があるわけです。
市民の命と健康を守る責任を果たすためにも寝屋川市として国保の広域化に反対をすることが必要です。分権的な広域化とされていますが、市として広域化に明確に反対することを求め答弁を求めます。
国民健康保険を安心できる医療制度とするには、根本的な制度改革が必要です。低所得者が多く加入する国保は、もともと適切な国庫負担なしには制度が成り立ちません。しかも、この間、雇用破壊で失業者や非正規労働者が国保に流入し、「構造改革」によって自営業者や農林漁業者の経営難・廃業が加速するなど、“国保加入者の貧困化”が急速に進行しています。いま、国保加入者の7割以上は、非正規労働者などの「被用者」と、年金生活者・失業者などの「無職者」です。
ところが、歴代政権は1984年の国保法改悪を皮切りに、国保に対する国の責任を次つぎと後退させてきました。1984年度から2010年度の間に、市町村国保の総収入に占める国庫支出金の割合は50%から25%へ半減し、それと表裏一体に、一人当たりの国保料(税)は3万9千円から8万9千円へと2倍以上に引きあがりました。
寝屋川市としても国保の国庫負担の増額を求めようではありませんか。市として、あらゆる機会を通じて働き掛けることを求めます。
生活保護について
安倍政権が8月から3年かけて生活保護の生活扶助基準を最大10%引き下げる問題で、貧困問題に取り組む人たちでつくる「生活保護基準引き下げにNO! 全国争訟ネット」は生活保護基準引き下げに反対する運動を広げようと7月26日、厚生労働省内で会見を開いています。全国の生活保護利用者に対し、行政への不服申し立てである審査請求を呼びかけました。
同ネットの小久保哲郎弁護士は「前代未聞の基準引き下げに見合うような運動にしたい」として、1万人規模の審査請求をめざすことを表明しました。全国生活と健康を守る会連合会の会長は、「低年金で生活が苦しい人たちなどと、憲法25条が保障する人間らしい暮らしとは何かについて対話し、運動を大きく広げたい」と表明しています。
全国的には、市町村の社会福祉事務所で審査請求の受付を拒否している事例が起こっているとの報道もあり、8月には厚生労働省から法令に沿った対応を求める通達も出されたと聞いています。寝屋川市においては審査請求を社会福祉事務所で受け取っているのか。お答えください。
また、生活保護費が削減される事で生保受給者の生活は大変厳しいものとなっています。市として憲法25条に保障された健康で文化的な生活を営む権利を保障するためにも、生活保護制度の改善を国に求めて下さい。答弁を求めます。
また、全国訴訟ネットが厚生労働省に指導を要望した審査請求妨害の事例には、寝屋川市での事例が報告されています。
大阪府寝屋川市、8月5日の保護費支給日に福祉事務所の門のところで、「保護費が下がりました。一緒に審査請求をしませんか」という趣旨のチラシを5人で配布したところ、担当課長がチラシをまいている前を行ったり来たりしていた。翌日、次長から「昨日、5人でビラまいとったやろ、許可をもらって配ったのか?役所にたてつくようなビラをまきよって」と言われた。との事例です。厚生労働省からの回答は、大阪府を通じて確認してもらったところ、「庁舎敷地内でチラシをまいていた支援者らに対して、担当職員が「許可をとって配布しているのか」と許可を取る必要がある旨述べたところ、「分かりました」と答え、それで終わっている。「役所にたてつくようなことしやがって」などとの発言は確認できなかったとのこと。大阪府としては審査請求の妨害はあってはならないと考えており、今後、仮にそのような事案があれば適切に指導していく、とのことであった。
私は、直接ビラ配布に参加し、市職員と話した人からお話を伺いましたが、確かにきつい口調で言われたと聞いています。言った言わないの水掛け論になりますのでこれ以上言いませんが。市民に誤解を受けるような言動は慎むように求めておきます。市の答弁を求めます。
安倍晋三内閣が環太平洋連携協定(TPP)の交渉参加を決めたことに、医療関係者からは日本の公的医療保険制度の崩壊につながることへの強い懸念と不安の声が上がっています。安倍首相は「公的医療保険は交渉対象でない」「国民皆保険制度は断固守る」などと繰り返しますが、その根拠は何も示すことができません。むしろ公的医療保険の根幹を揺るがすTPPの危険な実態が明らかになっています。
すべての国民がなんらかの公的医療保険に加入する「国民皆保険」は、1962年に自営業者や農家の人たちが加入する市町村単位の国民健康保険導入によって確立され、半世紀以上、国民の命と健康を守る役割を果たしてきました。
「いつでも、どこでも、だれでも必要な医療をうけることができる」という医療の平等の大原則は、戦後日本の長寿社会実現を支えるなど、WHO(世界保健機関)をはじめ世界の医療・保健関係者からも評価されています。
あらゆる商品やサービスの取引が対象になるTPPでは、この「国民皆保険」の根幹を掘り崩す交渉がおこなわれる危険が次々と浮き彫りになっています。
その一つは、公的保険の使える薬の値段が大幅に高騰する問題です。日本では、必要な薬が公的保険で使えるように、政府が価格を決める仕組みをとっています。ところが米国は、自国の製薬会社に利益を保障しない仕組みを「不透明だ」と問題視し、価格決定に製薬企業が参加できる制度などを求め続けてきました。
TPP交渉で、薬価を決めるルールづくりが交渉対象になることを政府も認めています。米国流のやり方がTPPで「共通のルール」として決まれば、いまでも高い日本の薬価はさらに高騰し、保険財政を圧迫する事態を引き起こします。必要な薬が公的保険の適用対象から外されて、患者の全額自費負担になりかねません。「国民皆保険」を崩すものです。
米国などTPP交渉参加国で当たり前となっている「営利企業の病院経営参入」も、大きな焦点として浮上しています。
日本で「営利企業の参入」を厳しく禁止しているのは、医療機関が金もうけ優先に走らず、「安心・安全」の医療を平等に提供する「皆保険」の理念にもとづいているからです。「営利企業の参入」解禁は、“もうけにならない患者”を排除する医療がまかりとおる社会を現実のものとします。
TPPは公的医療保険がなく「お金がなければ、まともな医療を受けられない」という米国の「市場原理主義ルール」が基本です。それへの参加は、「国民皆保険」とは両立しないことは明白です。
安倍政権が「国民皆保険を守る」という一方で、政府の規制改革会議が、所得の違いで受ける医療に格差ができる「混合診療」の全面解禁に道を開く議論をおこなうなど、“二枚舌”で「国民皆保険」を骨抜きにする動きをすすめていることは重大です。
そんな中、日本医師会では、日本がTPPに参加した場合の懸念事項として、以下の4項目を挙げています。
1.日本での混合診療の全面解禁により、公的医療保険の給付が縮小する。
2.医療の事後チェック等による公的医療保険の安全性が低下する。
3.株式会社の医療機関経営への参入を通じた、患者の不利益が拡大する。
4.医師、看護師、患者の国際的な移動が、医師不足、医師偏在に拍車をかけ、さらなる地域医療の崩壊を招く。
更に、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会の三医師会は以下の点を指摘し、公的医療制度がTPPの適用対象になる恐れを示しています。
1.「新成長戦略」の閣議決定により、医療・介護・健康関連産業が日本の成長牽引産業として明確に位置づけられ、医療の営利産業化に向けた動きが急展開している。
2.米国はかねてより日本の医療に市場原理の導入を求め、混合診療の全面解禁や医療への株式会社参入を要求。さらに、薬価算定ルールに干渉し、医療サービス分野で営利目的の参入を求めている。
3.米韓FTAでは、医薬品、医療機器の償還価格にまで踏み込んだ内容になっていること。FTAの枠組みを超える経済連携を目指しているTPP下で、混合診療が全面解禁されれば、公的医療保険の存在が自由価格の医療市場の拡大を阻害しているとして、提訴される恐れがある。ということです。
国民皆保険制度の根幹である国民健康保険の運営を担っている自治体として、市民の命、健康を守る立場から、皆保険制度の存続を危うくするTPPへの参加に反対することを国に対して求めて行くことが必要と考えます。国の動向を注視するだけでなく、市として積極的に市民の命に責任を持つ自治体としての役割を発揮することを求めます。市の考え方を示してください。
次に社会保障制度改革国民会議で示された国保の広域化に対する考え方についてです。
社会保障制度改革国民会議の報告書では、「効率的な医療提供体制への改革を実効あらしめる観点からは、国民健康保険に係る財政運営の責任を担う主体(保険者)を都道府県とし、更に地域における医療提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給付責任の主体を都道府県が一体的に担うことを射程に入れて実務的検討を進め、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体制を実現すべきである。ただし、国民健康保険の運営に関する業務について、財政運営を始めとして都道府県が担うことを基本としつつ、保険料の賦課徴収・保健事業など引き続き市町村が担うことが適切な業務が存在することから、都道府県と市町村が適切に役割分担を行い、市町村の保険料収納や医療費適正化へのインセンティブを損なうことのない分権的な仕組みを目指すべきである。」とされました。
議論の中身を見て行くと結局は、国保の広域化は都道府県単位とし、市町村の一般会計繰入による国保料の軽減をやめさせ、さらなる「保険料の引上げ」を行うこと。市町村が一般会計繰り入れによる住民負担を軽減すると「格差」が生まれ、「広域化」の妨げになるというのが言い分です。“悪い方”にあわせるのが「格差是正」というわけです。
また、広域化で国保運営が安定するかのように報告されています。しかし現実の府内、市町村の国保会計を見ますと、大阪府下では一番大きな大阪市の国保が被保険者一人あたりの法定外繰り入れが一番大きい額になっているのにもかかわらず一番の累積赤字をのこしている状態です。
そして国保会計は、後期高齢者医療制度が導入されて以降、全体的には黒字に転換し、あと2.3年で全国的に累積赤字を解消しそうな状況があります。国保会計の中味を見れば、自治体からの法定外繰り入れをなくせば全体的には赤字になるのが現在の国保会計の実態です。
以上の事からも広域化をしても、被保険者数が増えても国保の運営が安定することはあり得ません。自治体が市民の生活を守る為の努力、法定外繰り入れでなんとか厳しいながらも運営されているのが実態です。
また、広域化をすることで市町村の保険料収納や医療費適正化へのインセンティブを損なうことのない分権的な仕組みを目指すべきである。とただし書きされましたが、基本は、都道府県が地域医療の提供水準と標準的な保険料等の住民負担の在り方を総合的に検討することを可能とする体制を実現すべきである。とされており各自治体の保険料が一定統一される方向であることも予想されます。各市が市民からの保険料に対する追及に対して責任が表面上なくなることは大きな問題です。大阪府下では国保料が統一されれば国保料の大幅な引き上げも予想されます。
結局、後期高齢者医療制度のように被保険者から遠いところに制度設計がなされると細やかな対応ができなくなる現実があるわけです。
市民の命と健康を守る責任を果たすためにも寝屋川市として国保の広域化に反対をすることが必要です。分権的な広域化とされていますが、市として広域化に明確に反対することを求め答弁を求めます。
国民健康保険を安心できる医療制度とするには、根本的な制度改革が必要です。低所得者が多く加入する国保は、もともと適切な国庫負担なしには制度が成り立ちません。しかも、この間、雇用破壊で失業者や非正規労働者が国保に流入し、「構造改革」によって自営業者や農林漁業者の経営難・廃業が加速するなど、“国保加入者の貧困化”が急速に進行しています。いま、国保加入者の7割以上は、非正規労働者などの「被用者」と、年金生活者・失業者などの「無職者」です。
ところが、歴代政権は1984年の国保法改悪を皮切りに、国保に対する国の責任を次つぎと後退させてきました。1984年度から2010年度の間に、市町村国保の総収入に占める国庫支出金の割合は50%から25%へ半減し、それと表裏一体に、一人当たりの国保料(税)は3万9千円から8万9千円へと2倍以上に引きあがりました。
寝屋川市としても国保の国庫負担の増額を求めようではありませんか。市として、あらゆる機会を通じて働き掛けることを求めます。
生活保護について
安倍政権が8月から3年かけて生活保護の生活扶助基準を最大10%引き下げる問題で、貧困問題に取り組む人たちでつくる「生活保護基準引き下げにNO! 全国争訟ネット」は生活保護基準引き下げに反対する運動を広げようと7月26日、厚生労働省内で会見を開いています。全国の生活保護利用者に対し、行政への不服申し立てである審査請求を呼びかけました。
同ネットの小久保哲郎弁護士は「前代未聞の基準引き下げに見合うような運動にしたい」として、1万人規模の審査請求をめざすことを表明しました。全国生活と健康を守る会連合会の会長は、「低年金で生活が苦しい人たちなどと、憲法25条が保障する人間らしい暮らしとは何かについて対話し、運動を大きく広げたい」と表明しています。
全国的には、市町村の社会福祉事務所で審査請求の受付を拒否している事例が起こっているとの報道もあり、8月には厚生労働省から法令に沿った対応を求める通達も出されたと聞いています。寝屋川市においては審査請求を社会福祉事務所で受け取っているのか。お答えください。
また、生活保護費が削減される事で生保受給者の生活は大変厳しいものとなっています。市として憲法25条に保障された健康で文化的な生活を営む権利を保障するためにも、生活保護制度の改善を国に求めて下さい。答弁を求めます。
また、全国訴訟ネットが厚生労働省に指導を要望した審査請求妨害の事例には、寝屋川市での事例が報告されています。
大阪府寝屋川市、8月5日の保護費支給日に福祉事務所の門のところで、「保護費が下がりました。一緒に審査請求をしませんか」という趣旨のチラシを5人で配布したところ、担当課長がチラシをまいている前を行ったり来たりしていた。翌日、次長から「昨日、5人でビラまいとったやろ、許可をもらって配ったのか?役所にたてつくようなビラをまきよって」と言われた。との事例です。厚生労働省からの回答は、大阪府を通じて確認してもらったところ、「庁舎敷地内でチラシをまいていた支援者らに対して、担当職員が「許可をとって配布しているのか」と許可を取る必要がある旨述べたところ、「分かりました」と答え、それで終わっている。「役所にたてつくようなことしやがって」などとの発言は確認できなかったとのこと。大阪府としては審査請求の妨害はあってはならないと考えており、今後、仮にそのような事案があれば適切に指導していく、とのことであった。
私は、直接ビラ配布に参加し、市職員と話した人からお話を伺いましたが、確かにきつい口調で言われたと聞いています。言った言わないの水掛け論になりますのでこれ以上言いませんが。市民に誤解を受けるような言動は慎むように求めておきます。市の答弁を求めます。
●地域協働協議会について
・最近、いくつかの地域や女性団体などから、「地域協働協議会」について聞かれるようになりました。8月15日の市広報に掲載されたことでと考えられます。第5次総合計画にあたって寝屋川市のこれからの目玉になる施策として議論された経過があります。今年度の市政運営方針で、市長は、「オール寝屋川」へ、「地域協働」をまちづくりの新しい仕組みに加え、と述べました。しかし、市民は、「地域協働協議会」の名を含め、ほとんど知らないのが実状ではないでしょうか。以下、日本共産党議員団として主張してきたことをふまえ、質問します。
寝屋川市は、この間、「地域協働プラン」を作り、今年度予算に、24小学校区に「地域協働協議会」を設立する準備資金として一律50万円の予算化をおこないました。また、7月23日には、各小学校区3名、計72名の職員への辞令交付がおこなわれました。そして、現在、設立の動きが始まっています。それだけに、「目的」「組織」「活動」「運営」など、「地域協働協議会」が市民に理解され、支持され、参画してもらえる内容でなければなりません。昨年7月に、寝屋川市地域協働検討会議が「地域協働の推進に関する提言書」を出していますが、残念ながら、いち早く発足した地域協働協議会にも、市が発行したパンフレットにも、「提言書」が十分生かされた内容は認められません。これまでの地域団体をまとめるだけであったり、屋上屋を重ねる形は、最も避けなければならないものです。
「提言書」の積極的内容を生かしながら、少しでもより良い「地域協働協議会」になるよう、市民の声をふまえながら、提案し、市の見解をお聞きします。
まず、市民への周知徹底です。
憲法にもとづき、地方自治の2つの内容、団体自治と住民自治をすすめることです。国・府いいなりでなく、住民の立場に立って必要なことは、対等にものを言い、求めていく。今ひとつは、「住民こそ主人公」の実現です。すべての住民が「個人として尊重される」福祉の増進が自治体の最優先の仕事です。そして、主権者として、市政への参画が保障されることが求められています。そのために、寝屋川市の施策形成過程に市民的議論と意見を反映する政治システムの構築が必要です。
「提言書」は、「第3章の2 地域協働協議会の組織」の「(2)透明性の高い組織構成」で、重要な提起をいくつかしています。
1.それぞれの地域を代表する住民自治を担う組織として、開かれた民主的運営が基本。
2.情報の共有が必要。広く地域住民に関心を持ってもらうことが重要。
3.規約や事業報告、決算報告など、広く地域住民に公開し、自由に閲覧できるようにする。
4.役員の選出方法は、方法を広く地域住民に周知し、将来的には公募や投票など広く地域住民が参画できる民主的な方法を模索する必要。
5.男女の割合の考慮、子育てしている方、障がいのある方など、幅広い意見を反映する工夫。
また、「第3章の4 活動拠点の確保と整備」では、事務局や活動拠点の場所確保が不可欠としています。そして、小学校の空き教室等の利用など、拠点を整備することがもっとも望ましいとしています。
加えて、私は、年2回程度、体育館を借りて住民総会を定例化することが重要と考えています。
「第3章の5 条例などでの位置づけ」では、地域団体や地域住民などが参画する権利を有し、地域を代表する組織であることを条例などで位置づけ、目的や役割を明確にして設立を促すことが必要としています。「地域協働協議会」に権限と財政を保障するとしてきただけに、「要綱」ではなく、「条例」が必要と考えます。
現時点で基本として重要な以上の点について見解を明らかにしてください。
寝屋川まつりについてです。
最初に寝屋川まつりにおいての「火気の取り扱いに等の対策について」です。
22日の読売新聞には大阪・寝屋川まつり実行委、発電機持ち込み禁止、との表題で、京都府福知山市の花火大会会場で屋台が爆発して3人が死亡した事故を受け、大阪府寝屋川市などでつくる「寝屋川まつり実行委員会」は21日、同市で24、25の両日に開かれる寝屋川まつりに模擬店を出す露天商や市民に対し、発電機の持ち込みを禁止すると発表した。会場で通常の電源が取れるため、実行委は「照明などに影響はないはず」としている。福知山市の爆発事故は、自家発電機用のガソリンに引火して起きた可能性が高いことから、実行委は持ち込み禁止を決めた。同まつりは打上川治水緑地(太秦桜が丘)を会場に行われ、両日とも約260店が出店する見込み。枚方寝屋川消防組合も消防職員が会場を巡回し、露店での火の取り扱いなどを指導する。と報道されました。
私も市民の方から寝屋川まつりは大丈夫かとの問いに対して、発電機は持ち込み禁止になった。安心してまつりに参加をして下さいと話をさせていただきました。
しかし、25日に中止になったまつりの会場で、発電機やガソリン缶を見つけ大変残念な思いをしました。様々な理由が考えられますが、市民に対して安全がおろそかにされてるとおもわれないよう市としての努力を求め答弁を求めます。
今回の寝屋川まつりは25日の2日目が中止になりました。出店していた市民から「大変危険な状態だった。市は組織としての安全管理はどうなってるの。お店の品物が流れてしまった損害を補償してほしい」等の話を伺っています。そこでお伺いします。
大雨により打上治水緑地に雨水が流入して来る中、市として市民の安全をどのように守ったのか。まつりの中止を決めて各出店者に連絡がされていますが、その際、「片づけには明日までならいつ来ていただいてもいいですよ」と話されていたと聞いています。しかし現実は治水緑地に水が入ってきている際には大変危険な状態であり立入禁止とすべきであったと考えます。市として個々の市民の判断に任されていた状態をどのように考えていますか。市として打上治水緑地の出入りについてはどのような判断をしていたのか。また、誰がその判断をしたのかお答えください。
次に治水緑地に水が入って来る中で多くの店舗では、おいてあった机やいすなどの様々な資材が流されてしますという事が起きています。出店に際して実行委員会は出店料を取っていますので一定の保証などは考える必要が出てくるかと思いますが、市としての考えをお示し下さい。
治水緑地に一旦水が入りますと、消毒などの処置が取られていると思いますが、今回、まつりが中止となった後もまつり会場は開放されたままでした。一部には悪臭も漂っていました。
浸水した部分への立入禁止の措置や、衛生管理についてはどのようになされたのか。その際、まつり会場にいた市民に対して具体的にどのような対応をしたのか明らかにして下さい。
最後に市民に対して寝屋川まつりの中止をどのように知らせたかという問題です。
防災無線で寝屋川まつりの中止を知らせる放送が入ったと聞きましたが、多くの市民には届かず、知らないままでした。
メールねやがわでは、22日に寝屋川まつりの開催の情報メールが発信されていますが、残念ながら、中止のメール発信はされていません。不親切としか言いようがありません。校区情報メールで寝屋川まつりの中止を発信した校区もあるわけです。市としてなぜ、開催メールは送れても、中止メールを送ることができないのか。何が問題となるのか明らかにして下さい。
私は25日の夕方に会場を見に行きましたが、残念ながら会場で中止の連絡をする市の職員や、浸水し悪臭が出ている所への立ち入り禁止の案内をする看板も職員も見かけることはありませんでした。
その一方で、寝屋川まつりにきた多くの市民が散歩をし、子どもが川で遊んでいるすがたを見かけました。また、周辺には寝屋川まつりに参加しようと自転車を連ねて走っている小学生の姿や徒歩でやって来る親子連れの姿など多くの市民が中止を知らずにやって来る姿がありました。特に浴衣姿やなど着飾って来ている方を見るたびに申し訳なくなりました。
せめて市の広報車をだして会場周辺などで中止のお知らせができなかったのか。市民の立場に立った対応を取ることができなかったのか悔やまれます。毎年、数万人の方が参加をするおまつりです。今年も24日だけで3万5千人の参加者があったと報告されています。寝屋川市として中止を決めた段階でどのように市民に知らせようと考えたのか。現実の行った対応と、多くの市民が知らずに会場へとやって来ていた事実をどのように受け止めているのか明らかにして下さい。
寝屋川での水遊びについて、
今年、から一つ増えて市内には3か所の水に親しむことができる公園があります。幸町公園、川勝水辺ひろばは直接川に入って遊ぶことができるようにつくられています。今年の夏も多くの子どもが遊んでいる姿が見られました。
しかし、寝屋川駅前に有るせせらぎ親水公園は直接川に入らずに、川の水をポンプで上げた小川で水に親しむ設計になっています。小川で遊ぶ姿もみられるのですが、今年は寝屋川に直接入って遊ぶ子どもたちを多く見ました。
駅前のせせらぎ親水公園はできた当初から、近隣小学校には子どもたちだけで遊びに行ってはいけませんと注意がなされています。せせらぎ親水公園には船着き場や、対岸までの飛び石などが設置されるなど子どもたちが遊びたくなる状況がたくさんつくられています。それゆえに大変危険な公園となっています。
昨年から川に入って遊ぶ子どもたちをぼちぼち見かけるようになりました。昨年、私が見たのは2.3件だったのですが、今年は週に2.3回は川で遊んでいる姿をみて、危ないよと注意をしていたように思います。
当初は、服を濡らして、パンツ一枚で遊んでいる子どもが多く、水遊びをしているうちに、どんどん濡れて、とうとう川に入って泳ぐことになったのかなと思っていました。
しかし、夏の暑い盛りには水着をきて遊ぶ子どもたちを見かけることがおおくなりました。最初から泳ぐ目的で寝屋川にやってきているのです。走って塀を超えて川に飛び込む等かなり大胆に泳ぎ、遊んでいる姿が見られました。中学生くらいの子どもたちがシュノーケルをつけているのを見つけてびっくりもしました。そこでお聞きします。
親水公園では大人の方が子どもたちと一緒に川に入っている姿も見られ、危ないですよと注意をしても、ちゃんと監視しているから大丈夫と返事をされることもありました。幸町公園、川勝水辺ひろば、せせらぎ親水公園は水に親しむ公園と位置付けられていますが、川で水遊びをすることと、また、川で泳ぐことについては、どのように考え、安全管理を行っているのか。お答えください。
川に入って泳いで遊んでいる現実を見ると、川の水質検査をして具体的に注意を促すことも必要と考えるが、市として川の水質調査を行っているのか。また、市として遊泳禁止の看板や防犯カメラの設置などの安全対策が必要ではないかと考えます。市の考えをお示しください。
最近、ゲリラ豪雨や集中豪雨など河川の水かさが急に増える事態が増えています。赤や黄色の回転灯や放送で注意喚起が図られていますが、なかなか、親水公園で遊んでいる子どもたちは、実際に雨が降らないと親水公園から出ていかない傾向があります。せめて、夏休みや、土日など多くの子どもたちが遊んでいる時間帯に注意報や警報などが出た場合には、市として見回りが必要と考えます。市としての対応策はどうなっているのか。答弁を求めます。
昨年から川に入る子どもたちが出てきているのは、川の水が見た目にはきれいになってきていること、市民プールの廃止などが影響していると考えられます。子どもたちが自由に水遊びできるスペースの確保が市として必要ではないでしょうか。市の答弁を求めます。
・最近、いくつかの地域や女性団体などから、「地域協働協議会」について聞かれるようになりました。8月15日の市広報に掲載されたことでと考えられます。第5次総合計画にあたって寝屋川市のこれからの目玉になる施策として議論された経過があります。今年度の市政運営方針で、市長は、「オール寝屋川」へ、「地域協働」をまちづくりの新しい仕組みに加え、と述べました。しかし、市民は、「地域協働協議会」の名を含め、ほとんど知らないのが実状ではないでしょうか。以下、日本共産党議員団として主張してきたことをふまえ、質問します。
寝屋川市は、この間、「地域協働プラン」を作り、今年度予算に、24小学校区に「地域協働協議会」を設立する準備資金として一律50万円の予算化をおこないました。また、7月23日には、各小学校区3名、計72名の職員への辞令交付がおこなわれました。そして、現在、設立の動きが始まっています。それだけに、「目的」「組織」「活動」「運営」など、「地域協働協議会」が市民に理解され、支持され、参画してもらえる内容でなければなりません。昨年7月に、寝屋川市地域協働検討会議が「地域協働の推進に関する提言書」を出していますが、残念ながら、いち早く発足した地域協働協議会にも、市が発行したパンフレットにも、「提言書」が十分生かされた内容は認められません。これまでの地域団体をまとめるだけであったり、屋上屋を重ねる形は、最も避けなければならないものです。
「提言書」の積極的内容を生かしながら、少しでもより良い「地域協働協議会」になるよう、市民の声をふまえながら、提案し、市の見解をお聞きします。
まず、市民への周知徹底です。
憲法にもとづき、地方自治の2つの内容、団体自治と住民自治をすすめることです。国・府いいなりでなく、住民の立場に立って必要なことは、対等にものを言い、求めていく。今ひとつは、「住民こそ主人公」の実現です。すべての住民が「個人として尊重される」福祉の増進が自治体の最優先の仕事です。そして、主権者として、市政への参画が保障されることが求められています。そのために、寝屋川市の施策形成過程に市民的議論と意見を反映する政治システムの構築が必要です。
「提言書」は、「第3章の2 地域協働協議会の組織」の「(2)透明性の高い組織構成」で、重要な提起をいくつかしています。
1.それぞれの地域を代表する住民自治を担う組織として、開かれた民主的運営が基本。
2.情報の共有が必要。広く地域住民に関心を持ってもらうことが重要。
3.規約や事業報告、決算報告など、広く地域住民に公開し、自由に閲覧できるようにする。
4.役員の選出方法は、方法を広く地域住民に周知し、将来的には公募や投票など広く地域住民が参画できる民主的な方法を模索する必要。
5.男女の割合の考慮、子育てしている方、障がいのある方など、幅広い意見を反映する工夫。
また、「第3章の4 活動拠点の確保と整備」では、事務局や活動拠点の場所確保が不可欠としています。そして、小学校の空き教室等の利用など、拠点を整備することがもっとも望ましいとしています。
加えて、私は、年2回程度、体育館を借りて住民総会を定例化することが重要と考えています。
「第3章の5 条例などでの位置づけ」では、地域団体や地域住民などが参画する権利を有し、地域を代表する組織であることを条例などで位置づけ、目的や役割を明確にして設立を促すことが必要としています。「地域協働協議会」に権限と財政を保障するとしてきただけに、「要綱」ではなく、「条例」が必要と考えます。
現時点で基本として重要な以上の点について見解を明らかにしてください。
寝屋川まつりについてです。
最初に寝屋川まつりにおいての「火気の取り扱いに等の対策について」です。
22日の読売新聞には大阪・寝屋川まつり実行委、発電機持ち込み禁止、との表題で、京都府福知山市の花火大会会場で屋台が爆発して3人が死亡した事故を受け、大阪府寝屋川市などでつくる「寝屋川まつり実行委員会」は21日、同市で24、25の両日に開かれる寝屋川まつりに模擬店を出す露天商や市民に対し、発電機の持ち込みを禁止すると発表した。会場で通常の電源が取れるため、実行委は「照明などに影響はないはず」としている。福知山市の爆発事故は、自家発電機用のガソリンに引火して起きた可能性が高いことから、実行委は持ち込み禁止を決めた。同まつりは打上川治水緑地(太秦桜が丘)を会場に行われ、両日とも約260店が出店する見込み。枚方寝屋川消防組合も消防職員が会場を巡回し、露店での火の取り扱いなどを指導する。と報道されました。
私も市民の方から寝屋川まつりは大丈夫かとの問いに対して、発電機は持ち込み禁止になった。安心してまつりに参加をして下さいと話をさせていただきました。
しかし、25日に中止になったまつりの会場で、発電機やガソリン缶を見つけ大変残念な思いをしました。様々な理由が考えられますが、市民に対して安全がおろそかにされてるとおもわれないよう市としての努力を求め答弁を求めます。
今回の寝屋川まつりは25日の2日目が中止になりました。出店していた市民から「大変危険な状態だった。市は組織としての安全管理はどうなってるの。お店の品物が流れてしまった損害を補償してほしい」等の話を伺っています。そこでお伺いします。
大雨により打上治水緑地に雨水が流入して来る中、市として市民の安全をどのように守ったのか。まつりの中止を決めて各出店者に連絡がされていますが、その際、「片づけには明日までならいつ来ていただいてもいいですよ」と話されていたと聞いています。しかし現実は治水緑地に水が入ってきている際には大変危険な状態であり立入禁止とすべきであったと考えます。市として個々の市民の判断に任されていた状態をどのように考えていますか。市として打上治水緑地の出入りについてはどのような判断をしていたのか。また、誰がその判断をしたのかお答えください。
次に治水緑地に水が入って来る中で多くの店舗では、おいてあった机やいすなどの様々な資材が流されてしますという事が起きています。出店に際して実行委員会は出店料を取っていますので一定の保証などは考える必要が出てくるかと思いますが、市としての考えをお示し下さい。
治水緑地に一旦水が入りますと、消毒などの処置が取られていると思いますが、今回、まつりが中止となった後もまつり会場は開放されたままでした。一部には悪臭も漂っていました。
浸水した部分への立入禁止の措置や、衛生管理についてはどのようになされたのか。その際、まつり会場にいた市民に対して具体的にどのような対応をしたのか明らかにして下さい。
最後に市民に対して寝屋川まつりの中止をどのように知らせたかという問題です。
防災無線で寝屋川まつりの中止を知らせる放送が入ったと聞きましたが、多くの市民には届かず、知らないままでした。
メールねやがわでは、22日に寝屋川まつりの開催の情報メールが発信されていますが、残念ながら、中止のメール発信はされていません。不親切としか言いようがありません。校区情報メールで寝屋川まつりの中止を発信した校区もあるわけです。市としてなぜ、開催メールは送れても、中止メールを送ることができないのか。何が問題となるのか明らかにして下さい。
私は25日の夕方に会場を見に行きましたが、残念ながら会場で中止の連絡をする市の職員や、浸水し悪臭が出ている所への立ち入り禁止の案内をする看板も職員も見かけることはありませんでした。
その一方で、寝屋川まつりにきた多くの市民が散歩をし、子どもが川で遊んでいるすがたを見かけました。また、周辺には寝屋川まつりに参加しようと自転車を連ねて走っている小学生の姿や徒歩でやって来る親子連れの姿など多くの市民が中止を知らずにやって来る姿がありました。特に浴衣姿やなど着飾って来ている方を見るたびに申し訳なくなりました。
せめて市の広報車をだして会場周辺などで中止のお知らせができなかったのか。市民の立場に立った対応を取ることができなかったのか悔やまれます。毎年、数万人の方が参加をするおまつりです。今年も24日だけで3万5千人の参加者があったと報告されています。寝屋川市として中止を決めた段階でどのように市民に知らせようと考えたのか。現実の行った対応と、多くの市民が知らずに会場へとやって来ていた事実をどのように受け止めているのか明らかにして下さい。
寝屋川での水遊びについて、
今年、から一つ増えて市内には3か所の水に親しむことができる公園があります。幸町公園、川勝水辺ひろばは直接川に入って遊ぶことができるようにつくられています。今年の夏も多くの子どもが遊んでいる姿が見られました。
しかし、寝屋川駅前に有るせせらぎ親水公園は直接川に入らずに、川の水をポンプで上げた小川で水に親しむ設計になっています。小川で遊ぶ姿もみられるのですが、今年は寝屋川に直接入って遊ぶ子どもたちを多く見ました。
駅前のせせらぎ親水公園はできた当初から、近隣小学校には子どもたちだけで遊びに行ってはいけませんと注意がなされています。せせらぎ親水公園には船着き場や、対岸までの飛び石などが設置されるなど子どもたちが遊びたくなる状況がたくさんつくられています。それゆえに大変危険な公園となっています。
昨年から川に入って遊ぶ子どもたちをぼちぼち見かけるようになりました。昨年、私が見たのは2.3件だったのですが、今年は週に2.3回は川で遊んでいる姿をみて、危ないよと注意をしていたように思います。
当初は、服を濡らして、パンツ一枚で遊んでいる子どもが多く、水遊びをしているうちに、どんどん濡れて、とうとう川に入って泳ぐことになったのかなと思っていました。
しかし、夏の暑い盛りには水着をきて遊ぶ子どもたちを見かけることがおおくなりました。最初から泳ぐ目的で寝屋川にやってきているのです。走って塀を超えて川に飛び込む等かなり大胆に泳ぎ、遊んでいる姿が見られました。中学生くらいの子どもたちがシュノーケルをつけているのを見つけてびっくりもしました。そこでお聞きします。
親水公園では大人の方が子どもたちと一緒に川に入っている姿も見られ、危ないですよと注意をしても、ちゃんと監視しているから大丈夫と返事をされることもありました。幸町公園、川勝水辺ひろば、せせらぎ親水公園は水に親しむ公園と位置付けられていますが、川で水遊びをすることと、また、川で泳ぐことについては、どのように考え、安全管理を行っているのか。お答えください。
川に入って泳いで遊んでいる現実を見ると、川の水質検査をして具体的に注意を促すことも必要と考えるが、市として川の水質調査を行っているのか。また、市として遊泳禁止の看板や防犯カメラの設置などの安全対策が必要ではないかと考えます。市の考えをお示しください。
最近、ゲリラ豪雨や集中豪雨など河川の水かさが急に増える事態が増えています。赤や黄色の回転灯や放送で注意喚起が図られていますが、なかなか、親水公園で遊んでいる子どもたちは、実際に雨が降らないと親水公園から出ていかない傾向があります。せめて、夏休みや、土日など多くの子どもたちが遊んでいる時間帯に注意報や警報などが出た場合には、市として見回りが必要と考えます。市としての対応策はどうなっているのか。答弁を求めます。
昨年から川に入る子どもたちが出てきているのは、川の水が見た目にはきれいになってきていること、市民プールの廃止などが影響していると考えられます。子どもたちが自由に水遊びできるスペースの確保が市として必要ではないでしょうか。市の答弁を求めます。