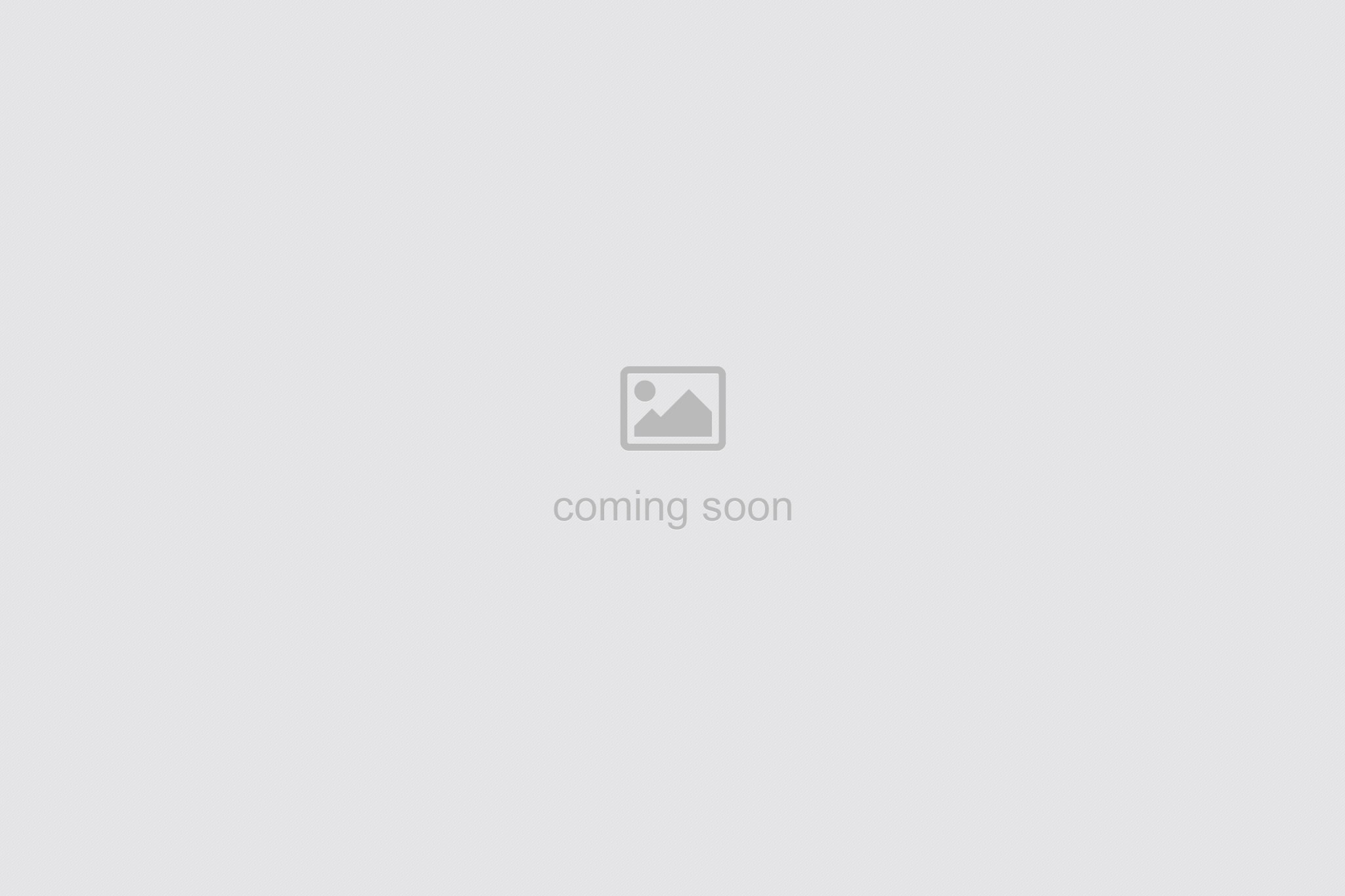2016年3月議会 代表質問②
2016年3月議会 代表質問③
2016年3月議会 代表質問④
2015年6月議会 代表質問①
◎ 4月の寝屋川市長選挙で日本共産党は、「市民の声がとどく市政をつくる会」に参加し、『馬場市政の継承許さず、維新市政の持ち込みを許さない』を2つの大きな争点として、「市民の声をきく市政」「バランスのとれたまちづくり」「弱者にあたたかい市政」「健康と環境を守る市政」「子育て安心のまち」「市役所の民営化ストップ」の6つの政策を市民に明らかにする中で、市民の声が届く市政を取り戻すために北川のりお市長候補を自主的に支援することを決めて全力でとりくみました。
北川法夫市長も選挙戦では寝屋川市民の暮らしをさらによくしたいとの思いで命を守る市政への転換を公約されました。
今回の選挙で、北川のりお市長誕生に多くの市民とともに大きな喜びを持っています。
所信表明でもありましたが、「政治で暮らしが変わったことを実感していただける」よう、これからの四年間、北川市政の公約でもある「市民の命・くらしを守る市政実現」にむけてわが党も全力で取り組むことを、まず最初に表明をします。以下2つの争点、6つの政策の基本にそって北川市長の所信表明に対する質問を行います。
◎ 1つめは、「市民の声を聞く市政への転換」について
4期16年続いた馬場市政は、歴代の市長と大きく異なりました。北川市長、西川市長、高橋市長は、いずれも保守の立場でした。しかし、共通していたのは、市の福祉施策の大もとを守ってきたこと、市長と立場が違う場合でも、市民の意見を聞く姿勢があったことです。
ところが、馬場市政の下では、市長と立場が違うかどうかで、市民に対する態度を変える。意に添わない市民の意見は聞こうとしませんでした。市が行った市民の意識調査アンケートでも市政に市民の意見が反映をしていないと答えた市民が7割にものぼりました。今後の4年間の北川市長の市政運営で、大きく改善されることを市民は期待しています。
かつて「福祉先進都市」と言われた寝屋川市には、無認可保育所への助成、学童保育の正職指導員の複数配置など「日本一」と言われる施策がありましたが、これらの施策は市民の反対の声を聞かずに次々と切りくずされてきました。
4期16年間で、公立保育所10カ所廃止・民営化、2つの小学校の廃校、4つの公立幼稚園の廃園、あかつき・ひばり園の指定管理者制度の導入、市民プール廃止、敬老金、寝たきり老人見舞金、障害者福祉金、難病患者見舞金なども全て廃止されました。その一つ一つが廃止、民営化、指定管理が提案されていく中で多くの市民から反対の声や多数の署名が寄せられましたがその声に耳を傾けず押しすすめられました。
例えば、市民プールの廃止にあたっては、「公共施設等整備再編計画」が市民、議会の意見を聞くことなく市役所内で検討・作成されました。計画を知った市民から2万名を越える「市民プールを残してほしい」との署名が提出されました。しかし寝屋川市は市民の声に真摯に耳を傾けることなく廃止しました。
いまでは遊び場を失った子どもたちが寝屋川市駅前の寝屋川で遊ぶ姿が見られます。「川で遊ぶ子どもたちに何かあったらどうするんだ」と議会で質問をしたこともありましたが、寝屋川市の答弁は自己責任ですと冷たいものでした。
また、寝屋川市は「市民プールは年2ヶ月しか利用されていない、役割は終わった。跡地には一年中使えるBQなどを行うことが出来る公園を整備したい」と説明していましたが、いまプール跡地の南寝屋川公園にはBQ禁止の看板が出ています。市民に対して説明をしてきたことが守れないと言うのも問題です。
あかつき・ひばり園の指定管理者制度導入では、前市長のもと、「アウトソーシング計画」にもなかったものを突如、市政運営方針に入れて、保護者、関係者との話し合いが継続して行われている最中に保護者関係者との合意もないままに議会提案されたものです。昨年4月から指定管理者制度が導入されていますが、保護者の不安は解消されていません。
就学援助の基準引き下げについては、国から、生活保護基準が下がっても、基準の引き下げはしないよう2度にわたって文部科学省から通達が出される中、市民が就学援助についての寝屋川市の考え方を聞きたい。基準の引き下げはしないでほしい。懇談の場をもってほしいとの要望書が提出されました。しかし教育委員会は、懇談を拒否し続け文書の回答に終始し、説明のないままに就学援助の基準は引き下げられてしまいました。
前市長のもとで進められてきた、これらの例に共通しているのは市民の声を聞かない姿勢です。
市の行政運営は市民の意見を聞くところから始まるのではないでしょうか。市長の所信表明では市民の話を聞くこと、市民と対話していくことが強調されていて非常に心強く思いました。
今後、市民や団体が寝屋川市に対して要望や懇談の申し入れをされてくると思います。市としての対応のあり方について市長の見解をお聞きします。
また、今後、市長が直接市民との意見交換を行う場を定期的に設けること。新たにタウンミーティングの定期開催などについても是非とも検討いただきたいと思います。見解をお聞きします。
◎ 2つ目は、バランスのとれたまちづくりです。
4期16年の馬場市政のもとで、大型開発が優先して行われてきました。
寝屋川市駅東地区の再開発事業、香里園駅東地区の再開発事業や寝屋南地区土地区画整理事業の3つの開発で総額400億円を越え、税の投入だけでも110億円を超えました。また、香里園駅東地区の再開発事業では、産婦人科の設置について努力をするなどの約束をした協定書を関西医大香里病院と交わし30億円もの税金投入が行われました。
第2京阪道路沿道や寝屋川市東部地域では、農地や緑が大きく失われる区画整理事業が行われ、ふるさとリーサム地区の計画など、新たな特別扱いにつながる大型土木事業の動きも始まっています。
市民の願いはバランスのとれたまちづくりです。地域的には東側に偏った開発がなされてきたと、西地域や萱島地域の市民から意見を聞くことがあります。また、大型開発に偏ることのない市民生活に密着した事業が求められています。
そこでお聞きします。今、現在、寝屋川市においてすすめられてきている、ふるさとリーサム地区まちづくり整備計画についてです。
今回の市長選挙で市長は市営住宅の建てかえに掛かる費用40億円を見直して寝屋川市が他市に遅れている国保料の引き下げやドクターカーなどの市民サービスへ回そうと訴えられました。また、市営住宅の建てかえに対しては再検討をしたいと立場を明らかにしています。これまでの馬場市政の下で計画された市営住宅の建てかえ第1期については、5年間の債務負担行為補正やPFI方式による工事請負契約が締結されていますが多くの市民は知りません。
日本共産党は市営住宅の建てかえについて、次のような問題点を指摘してきました。「長寿命化計画」で始まった検討が、最終段階で「全面立替」方針に変更されたのはなぜか。PFI方式で安くて品質がいいという具体的な根拠が示されていない。今回の契約は、評価の仕方によって事業者が決まる。まして1社グループのみで競争性が担保されたと言い難い、落札額は予定価格の99.7%となっている。市内の市営住宅については、主に同和対策事業として特定の地域に700戸近い住宅が建てられ、老朽化による建て替えも特定地域に偏った住宅を作るのか。もっと十分な市民的議論が必要だという意見も述べてきました。以上のような中で、市営住宅の建てかえについては、現行の進め方を見直すお考えがあるのか、お聞きします。
また、ふるさとリーサムまちづくり整備計画事業のまちなか再生エリアでは、防災軸となる道路が必要と6㍍道路をつくる計画が優先的に進められてきています。市はまちづくり協議会がつくられ地元の意向によってまちづくりがすすめられていることを強調しますが、まちづくり協議会の11名の役員のうち、6名が地区外に居住をしているなどの実態もあり問題ではないでしょうか。そして、そこに実際に住んでいる借地・借家人は最初からまちづくり協議会の参加対象者とされていません。新たな特別対策につながらないようにすべきです。まちなか再生エリアの道路建設については、地元に住んでいる住民や市民の意見を広く聞く中で見直しが必要ではないでしょうか。市の見解をお聞きします。
そして、防災軸が必要とされるなら、国から危険と指摘された市内の3つの密集住宅地域があります。今回の所信表明では都市計画道路、対馬江大利線の整備をすすめる中で大利地域の密集市街地解消につとめるとされていることを評価したいと思います。さらにあと2カ所の指定されている香里・萱島地域においても、住民が住み続けられることを前提とした対応が必要ではないでしょうか。市の考えをお示し下さい。
今後、生駒断層地震や集中豪雨による災害などが予測される中で大型開発優先から防災事業への転換が必要です。
地震対策については、民間住宅の耐震化が大きな問題となってきます。耐震診断や耐震補強へ市としての補助金制度の拡充が必要ではないでしょうか。
家屋の耐震化については、住宅リフォーム助成制度の創設や耐震補強工事への助成拡大など、市民のいのちを守る施策として、市内中小業者の振興施策としてもメリットが出るような施策展開が今後求められるのではないでしょうか。市の考えを示し下さい。
治水対策は今回の所信表明で、今後も浸水被害の軽減に向けたハード・ソフトの取り組みを計画的に実施することが表明されました。市民の中には2012年8月14日の集中豪雨による浸水被害の記憶がまだまだ新しいところであり評価します。
しかし、大きな治水対策は寝屋川流域の自治体が協力して大阪府と共に広域で取り組んでいくこととなっています。そこで、寝屋川市として具体的にどのようなことに取り組むことが出来るのか。そして市民がどのように係わり協力を得ることが出来るのかが非常に大切になってきます。今後の市の治水計画をお示しください。
第二京阪沿道のまちづくり協議会の中には協議会を解散して農地を守る会などの結成も行われていると聞いています。寝屋川市内全体をみてもどんどんと農地が減少していく中で寝屋川市として農地・緑の保全に向けて、市として産業振興条例にある農業振興をより具体化していく施策展開が求められていると考えます。今後の市内の農地・緑の保全についての市の見解をお聞きします。
高齢化が進む中で郊外型の大型開発では市民生活を守ることが出来なくなっています。高齢者・買い物難民等に対する外出援助施策としてコミュニティバスや乗り合いタクシーなどの制度の充実を進めていくこと。また、公共施設へのアクセスも困難な中、各市民センターにおけるワンストップサービスに向けての取組は評価します。市長の「くらしを守る」立場から市として、高齢者や買い物難民などに対応する施策について見解をお示しください。
次に、市民が気軽に利用できるスポーツ施設の整備については、現在の寝屋川市では教育センターを廃止する中で市民が利用できる体育館が一つ削減される見込みとなっています。
体育館を利用している方たちからは体育館の存続、市内スポーツ施設の拡充を求める声を聞いています。公園や体育館、スポーツ広場など市民がスポーツに親しむことが出来る環境作りが必要ではないでしょうか。6月15日付けの広報で市長はスポーツを盛んにしたいと述べられています。文化・スポーツ振興に向けての施策検討が必要ではないでしょうか。市の考え方をお示しください。
◎ 3つ目は「弱者にあたたかい市政に」ついてです。
市長は今回の所信表明で高齢化を見据え・市民生活の基本となる健康を守るため、「健康・医療・福祉のまちづくり」の推進。また、子どもから高齢者・障害のある人への支援を打ち出しています。そして国民健康保険料についても引き下げに向けた取り組みを進めるとされています。大いに期待するところであります。
特に低所得者が多く加入している国民健康保険において市民に重たい負担を強いている現状があります。
前市政のもと、2008年の全国調査で200万円の所得の4人家族のモデルケースで50万円を超える国保料が全国一高い保険料となりました。そして、市は、「適正適法に賦課をしている」と繰り返しました。
北川市長は国保料の引き下げを公約されています。
今年度の国保料は市長が初登庁の日に告示しなければならないという大変厳しい日程の中、前年度に比べてモデルケースで年2600円の引き下げになったことは評価しています。これにより日本一高い保険料となった2008年度から7年連続で保険料率が下げられたことでモデルケースでは大阪府下平均並となってきています。
しかし、残念ながらモデルケースで38万円を超える保険料は市民にとってまだまだ重たい負担です。今後の引き下げに向けての市長の思いをお聞かせ下さい。窓口での市民生活を守る丁寧な対応をお願いします。
また、介護保険料については前市政では公約に反して二期連続で値上げしました。今年も4.6.8月支給の年金からは、仮算定として前年分の介護保険料で天引きされ、10.12.2月分の年金で本算定をし、今年度は22%値上げされた保険料で高齢者の生活を更に厳しくします。
介護保険料は原則として3年に一回の改定ですが、高齢者の生活を守るためにも保険料の引き下げの努力が求められます。大阪府下の多くの自治体で行われている介護保険料・利用料の減免制度創設に向けての検討を求めます。市の見解をお聞きします。
次に障害者施策の拡充についてです。
多くの障害者、その家族は、働く場所の確保、障害者の高齢化など深刻な悩みを抱えています。市として相談窓口の充実、施策の具体化が求められます。特に障害者は外出が困難な場合も多く、市として要望を聞き取りに行く体制づくりが求められています。今年度から、難病支援の法律が変わり、病院の窓口で月5千円の負担が生じるなど、障害や難病を抱えている方が障害年金で暮らす中、生活が厳しくなっている状況があります。市として障害者が安心して生活できるような施策について基本的な見解をお聞きします。
あかつき・ひばり園は、昨年4月に指定管理者制度が導入されました。あかつき・ひばり園は障害を持った子どもたちの療育を行う場です。療育水準の維持向上・センター的役割の維持は指定管理者制度を導入するにあたって市が約束したことです。指定管理者への引き継ぎにあたって保護者の不安は解消されていません。指定管理後も保護者から市や市議会に対して切実な要望書が提出されてきました。当面、保護者関係者との懇談を密にとり保護者の要望をよく聞いていただくこと。来年度の引き継ぎは市の職員体制について、保護者関係者の意見を聞いて対応していくことが必要ではないでしょうか。市の見解をお聞きします。
生活保護制度は市民生活を守る最後の砦です。
生活保護を食い物にする暴力団員による生活保護の不正受給は犯罪行為であり許すことはできません。しかし全国的に語られる生活保護費の不正受給の多くは制度の不理解からくる高校生のアルバイト収入の未申告などが多くを占めています。
しっかりとした制度の周知をし、自立に向けて市民を支えることが出来るケースワーカーの配置が求められます。
この間、寝屋川市では、毎年のように府の監査で人員の不足が指摘されています。生活できなくなったときに、生活保護を受給することは、憲法に保障された基本的人権です。市職員は、市民が権利を行使するための援助をすることが仕事です。
本当に生活が困難になった市民が制度から漏れることなく利用出来る体制が望まれています。
市民生活を守る最後の砦としての本来の役割を果たすことができる体制の強化が必要ではないでしょうか。市の見解をお聞きします。
上下水道事業も決算見込みが出ましたがどちらも黒字を計上しています。市民生活が困難になってきている中、上下水道料金の引き下げ、減免制度の創設も検討課題です。また、社会福祉施設などに対する福祉減免制度の創設など市民に優しい制度設計とすることも必要ではないでしょうか。市の見解をお聞きします。
2015年6月議会 代表質問②(続き)
◎ 4つ目は、「健康と環境を守る市政へ」についてです。
廃プラ、ごみ、環境問題についてです。
2004年に、二つの廃プラ処理施設が住宅地に近い打上に建設される計画があることが、あきらかとなりました。地域住民のみなさんが計画を知り、健康被害を心配して住民運動が始まり12年目を迎えています。
前市長のもとでの寝屋川市は、多くの住民が訴える健康被害の実態を調べることなしに健康被害はない。市民との話し合いについても「見解が違うから会えない」としてきました。
廃プラ処理施設は立ち上げの経過から問題があります。長くなりますが紹介します。北河内4市リサイクルプラザは場所などを寝屋川市が先導し、急いで事業化を進めました。2002年度3月末で同和対策事業として進められていたクリーンセンター第2事業所が廃止され同時期に、事業の立ち上げのために部落解放同盟の事実上の下部組織である寝屋川資源再生業協同組合(後に大阪東部リサイクル協同組合に改名)から北河内各市に強い働きかけが行われました。しかも4市施設のすぐ南側に府市一体の特別扱いでリサイクルアンドイコール社(後に倒産、民事再生となり現在大栄環境グループが経営)が圧縮廃プラスチックを破砕、溶融してパレットを製造する工場として住民への説明もなく建設されました。
廃プラ処理施設が稼働すると地域には廃プラ独特の甘いにおいが漂うようになり、健康被害を訴える住民が出始め、岡山大学医学部の津田先生の調査では1000名を越える住民が健康被害を訴える状況となりました。
今回も質問をつくるにあたって住民の方にお話を聞きました。高宮旭丘の60代のAさんは今でも喉の痛みと目の痛みに苦しんでいます。市外に出ていくと体調が良くなる、転地したいが、現実には難しい。薬で何とかここで生活ができている状態ですと話されました。
また三井が丘4丁目のBさんも鼻が詰まったり、鼻水がだらだらでたりと大変です。とくに、目がくしゃくしゃになって、目が赤く充血して何度も眼科へ行くが医師からはとくに目には問題はない。刺激物があったのではといわれると話されています。外出をするときに廃プラ施設の方向に下っていくと、鼻も目も大変つらい、状況になっていると話されました
主な健康被害は、眼がかゆい、眼が痛い、喉がイガライ、咳が出る、湿疹などの皮膚粘膜症状、化学物質過敏症、ぜんそく、他にも中枢神経の機能障害や自律神経失調など様々な症状がでています。そして、症状が悪化する中で、医者から転地を勧められて引っ越す人も出ています。
この間、健康被害を訴える住民は、寝屋川市、4市組合、大阪府、環境省など行政への訴え、また国会、府議会、市議会など各議会への取組、そして、医師、疫学調査、化学分析、気象の専門家などそうそうたる科学者による支援を受け、運動を続けてきました。
裁判では、仮処分、大阪地裁、高裁と三度の訴訟において科学者による意見がことごとく不採用にされるという、判決が続き、国の行政委員会である公害等調整員会への原因裁定の申請は、3年半にわたる審理の後、昨年11月に却下されました。
そして、健康被害を訴える住民のみなさんは、今以下のように訴えています。
廃プラはペットボトルをのぞき分別回収ではなく、かつてのように生ごみと一緒に燃やして、熱回収(サーマルリサイクル)としてゴミ発電につかう。サーマルリサイクルは、環境省が進めるリサイクルの一つです。そして、処理方法をかえると、一石3鳥、①環境汚染をなくすことができる、②年間5億円の税のムダ遣いを節約できる、③新しいクリーンセンターでのごみ発電のパワーアップができるというものです。 廃プラはいくらお金を掛けても元には戻りません。粗悪な製品で、パレットや公園のベンチ程度の用途です。比較的純度の高いペットボトルでも経済的な再生は衣料品に使われてるフリースまでです。
廃プラを現状の材料リサイクル(マテリアルリサイクル)から熱リサイクル、サーマルリサイクルに変えましょうと言う提案です。
廃プラ処理による健康被害が進む中、市内病院の協力で、昨年10月よりハイプラ外来として月一回の診察日を設けて真鍋医師により診察・治療が始まっています。真鍋医師は、廃プラ公害による健康被害の検診を行い診断書を裁判等に意見書として提出するなど、アレルギーを専門とする医師です。
北川市政におかれては、健康被害を訴える住民のみなさんの御意見をお聞きする機会を設けていただくことをお願いし、お考えをお聞きします。また今後新しいゴミ処理施設が建設されますので、ゴミ処理のあり方を見直すことについての見解をお聞きします。
環境対策については、各自治体で自然エネルギーの普及目標を掲げているところが多くあります。寝屋川市としてもCO2の削減のためにも自然エネルギーの普及目標が必要ではないでしょうか。また、公共施設・民間施設への太陽光パネルの設置など、市民との共同を広げて、環境対策に取り組むことも必要と考えます。市の考えをお聞きします。
市民のいのち・健康を守る施策として、今回の所信表明では、ドクターカーの導入が表明され大いに期待するところです。ドクターカーが導入された地域では救急救命の救命率が大幅に上がるなどの成果が上がっているとも聞いています。医師の確保などをはじめ今後の課題と予定をお聞きします。
◎ 5つ目は、「子育て安心のまちに」ついてです
かつて、寝屋川市は子育てするなら寝屋川市と言われていました。この16年間で子育て分野のサービス後退は市民の不安となっています。教育・保育などの子育て支援策の充実をはかり、かつての「子育てするなら寝屋川市」を取り戻すことが市民の切実な願いになっています。
今回、所信表明でいじめ問題に対応する施策を行うことは評価したいと思います。関係者、市民の声をよく聞いて対応していただけるよう求めるものです。
いま、お母さんたちが集まって子育ての話をしていると出てくるのが、出産する場所が減ってきたという話です。寝屋川市では、年間約2000名の赤ちゃんが生まれていますが、市内で出産しているのは約半数です。現在、寝屋川市内では病院、クリニック、助産院2カ所と4カ所しか出産できるところはありません。安心して出産できる環境作りも自治体に求められています。市として出産環境の整備について考えをお示しください。また、30億円の財政支援が行われ協定書を交わした関西医大香里病院の産科の設置についてどのような状況になっているのかも合わせてお聞きします。
また、子育て環境の充実や「子どもを守る」施策として保育所の充実も急務ですが、民間保育園の職員不足は深刻なものがあり、その要因のひとつに保育所職員の処遇問題があります。保育士の確保は子どもの命を守ることと直結します。国が実施している「保育士処遇改善」への補助金上乗せなどによる民間保育園への市独自の財政支援が必要ではないでしょうか。
そして保育所の待機児問題です。かつて、香里地域では入所は2年待ってくださいなんていう話しもありましたが、保育所の新設、増設で待機児は減ってはきました。しかし、現在でも年度途中から増え始めて、年度末には約80名となり認可保育所の新設増設が必要ではないでしょうか。
待機児童対策について市の見解をお聞きします。
学童保育についても高学年保育が始まりましたが、部屋が狭く、指導員の欠員が出るなどのソフトハード共に問題がでています。指導員の処遇改善が必要です。また、子どもの安全対策のためにも土曜日開所が保護者の高い要求となっています。市の学童保育についての考え方をお聞きします。
学校教育については市長は所信表明で「子どもを大切に守り育てる環境を整備する」と述べられました。本当にうれしい限りです。老朽施設・整備の改修計画、特別教室へのエアコン設置、学校トイレの洋式化、中学校給食の改善、少人数学級の拡充、図書室への専門司書の配置、国基準を満たす図書など教育環境の整備は子どもたちが豊かな教育を受ける条件に必要なものと考えます。また、ドリームプランなど学校間の格差を付ける予算配分は見直しが必要ではないでしょうか。そして、点数だけで学力を競わせる、国・府・市がおこなう一斉学力テストの実施、学校別の公表については見直しが必要と考えます。
所信表明では教育予算等に責任を持てる体制の強化、教育施策の拡充に努めると述べられました。
寝屋川の教育の取り組むべき課題についてどのように考えているのかお聞きします。
また、教育大綱の策定は保護者、教職員の意見を反映したものとすること。また、憲法の教育を受ける権利やこどもの権利条約など子どもたちの学ぶ権利や人権が最大限保障されるものとなるよう検討することが必要ではないでしょうか。市の見解をお聞きします。
今年、7月からこども医療費助成制度が高校卒業年齢の18歳まで拡充され市民からは喜びの声を聞いています。大阪府では最高レベルの到達となります。そして、全国的には子ども医療費助成制度は約半数が完全無料化となっています。今後は大阪府下初めての完全無料の子ども医療費助成制度の検討をしていただきますようお願いしておきます。
◎ 6つ目は、「市役所の民営化ストップ」についてです。
前市政の16年間では市役所の民営化が進められ、市の公的責任が後退をしていく中でこの流れを止めることが必要です。
この間、寝屋川市は民間にできることは民間へと次々と職員を減らし、退職者の不補充を続けました。その結果、保育所の民営化、公立幼稚園が廃園、学校給食の調理業務委託が強行され、また、ゴミ処理業務も施設の管理、ゴミ収集まで委託がすすめられてきました。公共施設もそのほとんどで指定管理者制度が導入され、多くの公共施設には市の職員がいません。
一昨年の集中豪雨では多くの市民からの問い合わせ助けを求める声に対応する職員が足りませんでした。
窓口業務の委託では労働基準監督署から法律違反が指摘され改めて市の直接雇用のアルバイトとされる事態もありました。
また、学校給食の調理業務委託では、最低賃金を下回る募集広告が出たり、子どもたちから給食がおいしくなくなったとの声もありました。
子どもの虐待対応をする部署では非正規雇用の専門職の職員が二年連続で退職をしていくなど、経験の蓄積が求められる職場で正規の職員配置ができない寝屋川市の職員定数となっています。2400名を越えていた市の職員は1200名を切り、来年度には、約1100名になる予定です。
こんなに減らして、本当に市民生活を守る職員配置は守られているでしょうか。
今回、市長は中核市への移行を目指し、業務量調査を行うとされています。中核市への移行は、様々な権限が地方自治体に委譲されることで市民に対してより多くの施策を行うことができます。一方で業務量が増えることになります。中核市への移行は十分な議論のうえですすめることが必要と考えます。
そして、市の施策については、公的責任を果たすべきところを明らかにして、必要な正規職員の配置が必要と考えます。前市長のもとで、市職員の大幅削減を前提とした「定員適正化計画」を優先して、退職不補充で正規職員を減らし続け、各部署で最低限の人の配置が保障されていなかったのではないかと考えます。今後、少子高齢化が進む中で、市役所の仕事は今以上にマンパワーが必要になるでしょう。職員配置のあり方について市の考えをお聞かせください。
本来、行財政改革は無駄を省き、市民福祉や、市民サービスの維持向上を目指すことが目的であるはずです。ところが、この間、前市長のもとで行ってきたことは、市民サービスの切り捨て、出てきた黒字は基金の積み立て、減債基金などに回して市民負担の軽減には回していません。
基金を積み立て、借金返済のため減債基金に回すことなどをすべて否定するわけではありません。しかし財政が厳しいと市民に負担をお願いしてきた中で、市の財政が黒字になったのですから、黒字分は市民の暮らしを守ることに使ってはどうでしょうか。
所信表明では政治で暮らしが変わったことを実感してもらうとの決意もなされています。2014年度決算も黒字の見込みとなり、単年度黒字が11年連続となります。市民生活への還元が必要ではないでしょうか。
市としての見解をお聞きします。
北川市長へと変わったことを市民は大変関心を持って、期待して見ています。私たちも、自主的にですが、北川候補を応援してきた責任があります。一つ一つの議案に対して市民に取って良いことなのかどうか、しっかりと議会の場で議論をしていきたいと考えています。そして、この四年間で寝屋川市が良くなったと市民のみなさんに実感をしていただけるように私たちも全力で頑張ります。
最後に、国政・府政の問題です。安倍政権は、「戦争法案」を国会に提出し、夏までに成立させることをねらっています。
この間の国会論戦では、衆院憲法調査会で、与党推薦の参考人をふくむ3人の憲法学者が、そろって憲法違反と指摘しています。それに続く200人をこえる憲法学者や法曹界も撤回を表明。
国会周辺をはじめ全国各地で「戦争法案」を許さない運動が大きく広がり、今国会で成立させるべきではないという声が8割にものぼっています。地方議会でも廃案や徹底審議をもとめる100をこえる意見書が可決されています。
日本の国のあり方を大きく左右する歴史的なたたかいとなっています。
日本共産党は、国会論戦とともに、党派のちがい、立場のちがいをこえた幅広い共同を広げて、日本を「戦争する国」にしないために頑張ります。
次に、大阪都構想です。
「大阪都」は2010年1月に当時の大阪府知事の橋下さんがいいだした構想です。そのねらいは3つです。1つは、大阪市も24区もなくす。2つめに、その権限・財源を「大阪都」に吸い上げ、大型開発に注ぐ。3つめは、「一人の指揮官」(知事)でやりたい放題できる体制をつくることです。
住民投票にあたり日本共産党はこのような「大阪都」構想の中心問題を明らかにしました。地域振興会、商店会、医師会、商工連盟など、さまざまな市民団体のみなさんや府下の首長とも連携、自民党、民主党との合同演説など、政党間の共同が進みました。
「住民が主人公」の大阪の地方政治の前進と平和・民主主義・暮らしを守るために今後も力を尽くしていきます。
北川市長は市民の「いのちを守る」ことを基本に「子どもを守る」「まちを守る」「生活を守る」ことを表明されたことを高く評価します。私たちも命くらし守る市政の実現に全力を上げることを申し添えて、日本共産党の代表質問を終わります。
再質問ある時には自席にて行います。ご静聴ありがとうございました。-