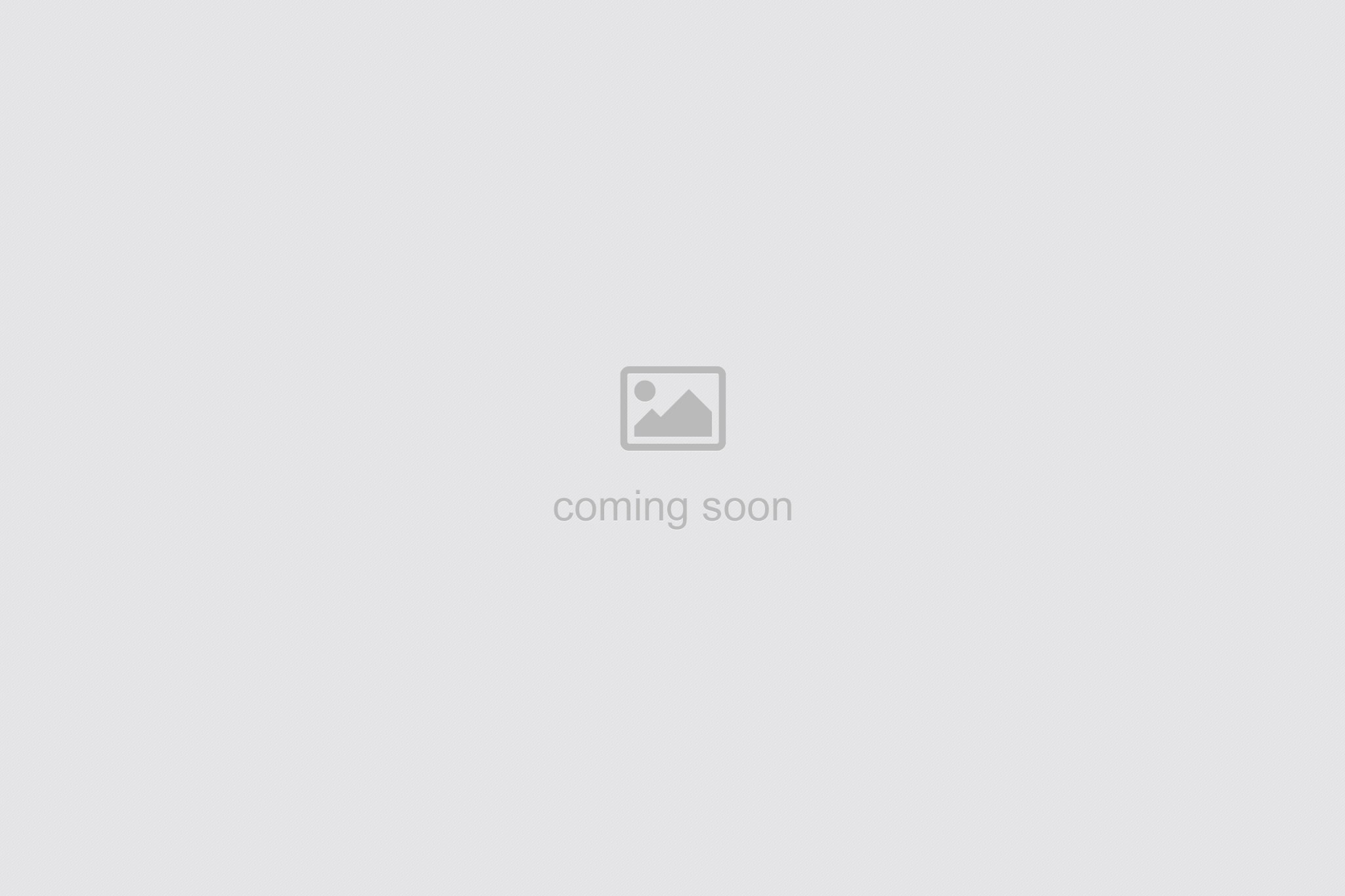2014年3月議会 中林市議 代表質問
2014-03-07
2014年3月議会 代表質問
日本共産党の代表質問をおこないます。
●まず、市長市政運営方針についてです。
市長は、「はじめに」の項で15年間の市政について自己評価をされています。
この中で財政基盤を強化したこと。まちの魅力が向上し、活気とにぎわいが増していること。市民協働のまちづくりが進んでいるなどと、自らの市政を高く評価しています。
勿論、個別の施策についてこの間、改善がされてきたことは事実であり、一定の評価をします。同時に15年間の市政について、市民から厳しい批判や意見が寄せられています。
第1に、学童保育指導員の非常勤化や公立保育所の廃止・民営化をはじめ、寝屋川市が全国的にも誇っていた制度、施策の後退を進めてきたこと。いま、あかつき・ひばり園の公設民営化まですすめようとしていることです。
第2に、再開発事業など、不要不急の大型開発を優先させ、関西医大香里病院への30億円など、市民合意の得られない財政支出を行ったこと。
第3に、廃プラスチック処理施設の建設を強行し、形を変えた同和の特別扱いをすすめてきたこと。健康被害を訴える住民の意見を無視し続けていること。
第4に、行政が決めたことは市民が何を言っても変えない、市民の意見を聞かない、行政姿勢を進めてきたことなどです。
このような市民の意見をよく聞き、とり入れ、市政を進めることを、まず求めます。
● 質問の第1は、市民生活の現状と市政がはたす役割についてです。
昨年10月から12月期の国内総生産の伸びは、前期比0.3%増、1年間に換算した年率でも1%増にとどまりました。2月に発表された国民所得統計は、経済の動きが鈍っていることを浮き彫りにしました。
「景気回復」が、かけ声倒れになっているいちばんの理由は、国民の所得が伸び悩んでいるためです。厚生労働省の勤労統計調査では、昨年の1ヶ月平均の「決まって支給する給与」は3年連続の減少となりました。
金融緩和や規制緩和で大企業のもうけを増やせば、雇用も給与も改善するというのが「アベノミクス」の宣伝文句ですが、実態はまったく逆です。大企業のもうけは増えても、内部留保にまわるだけで国民の収入は増えていません。
★ 市民のくらしは厳しい状況が続いています。市長は市民生活の現状についてどのように認識されていますか。
★ また、市民の暮らしを守るため、できうる限りの取り組みを行うべきです。見解をお聞きします。
次に、消費税増税や雇用についてです。
4月からの消費税の5%から8%への引き上げは、国民に年間8兆円もの負担増となり、市民の暮らしをいっそう困難にします。
市は、消費税率の引き上げは「社会保障の安定財源をはかるもの」としていますが、
社会保障は良くなるどころか、生活保護、介護、医療など、あいつぐ施策の後退や住民の負担増が進められようとしています。政府は大企業には減税しながら、軍事費や公共事業費に増税分をつぎ込もうとしています。
増税するのなら富裕層や大企業から行うべきであり、
★1)消費税増税を中止すること。
★2)経済のたて直しには、国民の所得を増やすことが必要不可欠です。
労働者の賃金引き上げを進めること、非正規雇用から正規雇用への転換で雇用の改善をはかること。
以上2点について、市長の認識をお聞きします。
●次に、平和の取り組みについてです。
「戦争できる国」づくりへ安倍政権の暴走が止まりません。先の臨時国会では、戦争司令部にあたる「国家安全保障会議」設置と「特定秘密保護法」の成立が強行されました。今国会では、立憲主義をふみにじる「集団的自衛権の行使」容認へ、政府の閣議決定で解釈変更をしようとしています。
また、公共放送の責任と役割を果たすべきNHKを、人事を通じて政府権力に従わせるなどの動きは、「戦争への道」に通じると言わねばなりません。
★ 憲法を否定し、日本の自衛と関係なく、海外に自衛隊を送って武力行使を認める政府の動きに、市として反対を表明すべきです。見解をお聞きします。
第2に、市は市民の平和意識の高揚をめざすとしています。戦争がいかに悲惨で、自然と環境を破壊し、生命も財産も奪い尽くすものかを、具体的に学習し、日常の平和が重要であることを考える場が必要です。
★市として、市民が戦前・戦後の歴史を学び、戦争体験や被爆体験を追体験できる「平和学習施設」を設置すべきと考え、見解をお聞きします。
第3に、「核兵器のない世界」の実現は、被爆者をはじめ、多数の国民の願いです。
被爆70年目の、2015年のNPT再検討会議に、寝屋川からも「核兵器全面禁止を求める」署名をたくさん持って、代表を送ることが期待されています。
★2020年を目標に、「核兵器全面禁止をめざす世界平和市長会議」の一員として、馬場市長のできる限りの協力を求めます。所見を伺います。
次に、防災についてです。
まず、東日本大震災への支援については、市として、引き続き支援を行うこと。募金とボランティア支援も引き続き呼びかけるべきと考えます。
第2に、地域防災計画の見直しについてです。
大阪府は、南海トラフ巨大地震が発生した場合、最大で震度6強の地震がおそい、
約1万1000ヘクタールが津波で浸水、最大13万人が死亡するとの想定を公表しました。被害直後、832万人が断水にみまわれるほか、234万戸が停電、115万戸でガスが供給停止になると予測されています。
その際、本市でも、建物被害・断水・道路閉鎖・避難者の発生、物資の不足、災害廃棄物の発生など、具体的な数値をあげての予測がされています。大阪府は、今年度中に地域防災計画の修正を行うとしています。
★ 本市においても、地域防災計画の見直しを進めるべきです。
第3に、耐震改修の推進についてです。
建物が耐震化されていれば、倒壊を減らすことができます。
★公共施設と住宅の耐震化は目標を、前倒しして実施するよう求めます。
第4に、避難計画の作成についてです。
災害が起こった場合、住民がどのように避難するのか、具体的な計画作りが問われます。
★ 特に、高齢者・障害者・妊婦・乳幼児などの避難計画の策定は重要です。
早期の具体化と計画にもとづく訓練の実施を求めます。
★ 第5に、要援護者の把握をすすめるとともに、住民の協力も得て、日常的なつながりができるように、取り組むべきと考えます。
以上5点、お聞きします。
次に、浸水対策についてです。
まず、地域の保水力のアップについてです。
道路は舗装され、農地が減少する中で、地域の保水力が低下しています。
★緑と農地の保全、浸透性舗装など、市としての計画的な取り組みを求めます。
第2に、一昨年の集中豪雨では、市内の広範囲で浸水しました。寝屋川流域下水道増補幹線の整備や地下河川の整備は待ったなしの課題です。
★大阪府や関係市と調整をすすめ、具体化すること、中木田調節池の設置へ努力を求めます。
第3に、ポンプ調整ルールの運用が始まろうとしています。流域の下水道対策計画について、大阪府は、ポンプ調整をすることで、浸水被害の軽減ができるとしていますが、
上流域の本市については、浸水被害が拡大をすることもありうるとの説明でした。また、被害の拡大については、天災だと理解してほしいと、何ら補償もしない姿勢でした。
★大阪府に対し、市として、被害が拡大しないよう対策すること、被害となった場合の補償制度をつくるよう求めるべきです。
以上、3点、お聞きします。
●次に、原発ゼロと自然エネルギーのとり組みについてです。
原発事故の被害は、今なお深刻さを増し、福島では、14万人もの被災者が、避難生活を強いられています。事故は収束するどころか、放射能汚染水が制御できない、非常事態が続いており、原発事故の原因は、いまだ究明の途上にあり、再稼働など論外です。
現在すべての原発が停止しています。再稼働せずに、廃炉に向かうことこそ、最も現実的で責任ある態度です。
世論調査では、再稼働に7割が「反対」、原発の今後については、「今すぐ廃止」「将来は廃止」をあわせると7~8割にのぼります。
★ 国に「即時原発ゼロ」を決断し、原発の再稼働をやめることを市として求めるべきです。見解をお聞きします。
次に、自然エネルギーの取り組みについてです。
太陽光パネルについて、本庁舎への設置や、市内の自治会集会所を対象にした設置補助の実施を評価します。
その上で、
(1) 自然エネルギーの取り組みについては、市全体としての導入計画を作成し、担当課を設置すること。
(2) 太陽光パネルの設置については、公共施設をはじめ、民間社会福祉施設など、引き続き具体化すること。
2月22日、市内の民間保育園の屋上に、市民の共同出資で、太陽光パネル設置による市民共同発電所ができました。市として、市民参加の市民共同発電所の取り組みへの支援をはかること。
3)7月スタートの太陽光パネルの設置補助制度については、①市民に補助制度を周知すること。②対象を、家庭用だけでなく、市内事業者、民間施設等へ広げること。
(4) 銀行との連携で低金利の貸し付けなど、初期費用ゼロでの太陽光パネル設置へのとり組みの検討をもとめます。
以上4点、お聞きします。
●次に、くらしをまもる施策の拡充についてです。
生活保護についてです。
生活保護費の抑制・削減をねらい、生活保護法の見直しが、今年7月から実施されようとしています。
今まで、口頭での保護申請を認めていたのに、文書申請と書類添付を原則にする条文を新設するなど、生活保護から申請者を遠ざける水際作戦を強化しやすくするものです。
同時に、厚生労働省は、国会答弁で「従来と対応は変わらない」とし、衆議院厚生労働委員会も、「水際作戦があってはならないことを、地方自治体に周知徹底する」との付帯決議をつけました。
市として、市民の申請権を尊重する態度をつらぬくようもとめます。
2) 昨年の大阪府の監査では、17人のケースワーカーの不足が指摘されたと聞きます。市は、非正規の職員でカバーしていると、議会で答弁していますが、それでは府の指導に応えることにはなりません。1人80ケースに対応する正規職員の配置を求めます。
3)昨年8月に続き、今年4月に生活保護費の引き下げが行われます。最低生活を保障するため、国に扶助費の増額を求めるべきです。
以上3点、お聞きします。
次に、介護保険についてです。
まず、介護保険料についてです。
市長は選挙で、介護保険料の引き下げを公約しました。4年間の任期中に引き下げの努力を続けることが、市民の願いに応える道です。
介護保険の改定の中には、第6期からは、第1,第2段階の保険料は、0.5の基準が0.3まで引き下げられます。これは低所得者に対する負担軽減を国も必要と考えたからです。
保険料引き下げのための一般会計からの繰り入れについては、厚生労働省は、公費50対保険料50の基準の遵守をうたっていましたが、今回、国自らが低所得者の負担軽減のために公費を投入する道をつくっています。
★1)来年度は、第5期の最終年度ですが、年度途中の引き下げも可能です。第6期まで待たずに、一般会計の繰り入れで、4月からの保険料の引き下げを求めます。
★2)大阪府下8割をこえる自治体が実施している、保険料の減免制度の創設を求めます。
また、利用料が払えず、介護サービスの利用をあきらめている実態があります。利用料の減免制度の創設を合わせて求めます。
3)本市の特別養護老人ホームの待機者は、600名近くいます。待機者解消のため、施設の新設を求めます。
4)第6期から介護保険制度の大きな制度変更が行われようとしています。要支援1.2の訪問介護や通所介護が介護保険から切り離されるものです。国の制度改悪に対して、市として、反対することを求めます。
以上、4点、お聞きします。
次に、国民健康保険についてです。
1) 本市の国民健康保険料は、所得200万円、40代夫婦と子ども2人の4人世帯のモデルケースで年42万円と、いまだ、所得の21%にもなる高い保険料となっています。
今年度が赤字にならなければ、これまでの累積赤字を解消することができ、14年度は、累積赤字の解消のために、一般会計から繰り入れてきた財源を、保険料引き下げのために使うことができます。保険料引き下げが収納率の向上につながり、国保財政を好転させることが可能です。
また、来年度は、国の財政措置によって、法定軽減が拡充されます。2割軽減では、4人家族で所得213万円までが適用されることで、低所得世帯の収納率の向上が見込まれます。
★一般会計からの繰り入れで、国保料の思い切った引き下げを求めます。
2)保険料の減免制度の拡充を求めます。
3)国民健康保険が社会保障制度として運営されるためには、基礎自治体が住民の命を守る責任を果たすべきです。国保の広域化に反対することを求めます。
4)皆保険制度の根幹をなす国民健康保険には、無収入やワーキングプアの人が加入しています。所得の格差が命の格差とならないよう、短期保険証や資格証明書の発行をやめるよう求めます。
以上4点、お聞きします。
次に、後期高齢者医療制度についてです。
後期高齢者医療広域連合議会で、来年度の保険料が決定しました。平均で年1.21%の引き上げとなります。市として保険料引き下げの努力を求めます。
今回大阪府が財政安定化基金への拠出を拒否しています。財政安定化基金は、国・府・市が3分の1ずつ負担して、保険料の軽減などに利用する基金です。
大阪府が拠出すれば、保険料の値上げは中止できます。市として府に拠出を求めるべきです。
以上、聞きします。
次に、健診事業については、各種健診の受診率向上に向けた取り組みをすすめるようにもとめ、見解をお聞きします。
●次に、子育て施策についてです。
まず、 こども・子育て新制度についてです。
15年4月実施予定の「こども・子育て支援新制度」の国スケジュールでは、市町村は14年夏までに、新制度に関わる基準や保育料などを条例で定め、住民に周知することになっています。
しかし、肝心の国の方針、新制度の詳細はまだ検討中です。わずかな期間で、こどものためになる制度の準備ができるのか疑問です。
★ 新制度は、十分な議論をおこない、関係者、市民の合意を得て実施すべきです。見解をお聞きします。
第2に、新制度では、保護者が保育所にの入所を申し込む際に、保育が必要かどうか、必要な保育時間は何時間かなど、保護者の状況に合わせて認定されることになります。現時点では、短時間児と長時間児に幼稚園児を加えた3区分になると説明されています。
また、保育所や幼稚園、認定こども園以外に、地域型保育など、補助金の対象施設の種類が増えます。保育所以外は、利用者と施設の直接契約となります。
施設によって、職員の配置や保育室の面積、保育士の資格等が異なることによる、保育環境や保育条件に格差がうまれることが心配されています。
日本共産党の代表質問をおこないます。
●まず、市長市政運営方針についてです。
市長は、「はじめに」の項で15年間の市政について自己評価をされています。
この中で財政基盤を強化したこと。まちの魅力が向上し、活気とにぎわいが増していること。市民協働のまちづくりが進んでいるなどと、自らの市政を高く評価しています。
勿論、個別の施策についてこの間、改善がされてきたことは事実であり、一定の評価をします。同時に15年間の市政について、市民から厳しい批判や意見が寄せられています。
第1に、学童保育指導員の非常勤化や公立保育所の廃止・民営化をはじめ、寝屋川市が全国的にも誇っていた制度、施策の後退を進めてきたこと。いま、あかつき・ひばり園の公設民営化まですすめようとしていることです。
第2に、再開発事業など、不要不急の大型開発を優先させ、関西医大香里病院への30億円など、市民合意の得られない財政支出を行ったこと。
第3に、廃プラスチック処理施設の建設を強行し、形を変えた同和の特別扱いをすすめてきたこと。健康被害を訴える住民の意見を無視し続けていること。
第4に、行政が決めたことは市民が何を言っても変えない、市民の意見を聞かない、行政姿勢を進めてきたことなどです。
このような市民の意見をよく聞き、とり入れ、市政を進めることを、まず求めます。
● 質問の第1は、市民生活の現状と市政がはたす役割についてです。
昨年10月から12月期の国内総生産の伸びは、前期比0.3%増、1年間に換算した年率でも1%増にとどまりました。2月に発表された国民所得統計は、経済の動きが鈍っていることを浮き彫りにしました。
「景気回復」が、かけ声倒れになっているいちばんの理由は、国民の所得が伸び悩んでいるためです。厚生労働省の勤労統計調査では、昨年の1ヶ月平均の「決まって支給する給与」は3年連続の減少となりました。
金融緩和や規制緩和で大企業のもうけを増やせば、雇用も給与も改善するというのが「アベノミクス」の宣伝文句ですが、実態はまったく逆です。大企業のもうけは増えても、内部留保にまわるだけで国民の収入は増えていません。
★ 市民のくらしは厳しい状況が続いています。市長は市民生活の現状についてどのように認識されていますか。
★ また、市民の暮らしを守るため、できうる限りの取り組みを行うべきです。見解をお聞きします。
次に、消費税増税や雇用についてです。
4月からの消費税の5%から8%への引き上げは、国民に年間8兆円もの負担増となり、市民の暮らしをいっそう困難にします。
市は、消費税率の引き上げは「社会保障の安定財源をはかるもの」としていますが、
社会保障は良くなるどころか、生活保護、介護、医療など、あいつぐ施策の後退や住民の負担増が進められようとしています。政府は大企業には減税しながら、軍事費や公共事業費に増税分をつぎ込もうとしています。
増税するのなら富裕層や大企業から行うべきであり、
★1)消費税増税を中止すること。
★2)経済のたて直しには、国民の所得を増やすことが必要不可欠です。
労働者の賃金引き上げを進めること、非正規雇用から正規雇用への転換で雇用の改善をはかること。
以上2点について、市長の認識をお聞きします。
●次に、平和の取り組みについてです。
「戦争できる国」づくりへ安倍政権の暴走が止まりません。先の臨時国会では、戦争司令部にあたる「国家安全保障会議」設置と「特定秘密保護法」の成立が強行されました。今国会では、立憲主義をふみにじる「集団的自衛権の行使」容認へ、政府の閣議決定で解釈変更をしようとしています。
また、公共放送の責任と役割を果たすべきNHKを、人事を通じて政府権力に従わせるなどの動きは、「戦争への道」に通じると言わねばなりません。
★ 憲法を否定し、日本の自衛と関係なく、海外に自衛隊を送って武力行使を認める政府の動きに、市として反対を表明すべきです。見解をお聞きします。
第2に、市は市民の平和意識の高揚をめざすとしています。戦争がいかに悲惨で、自然と環境を破壊し、生命も財産も奪い尽くすものかを、具体的に学習し、日常の平和が重要であることを考える場が必要です。
★市として、市民が戦前・戦後の歴史を学び、戦争体験や被爆体験を追体験できる「平和学習施設」を設置すべきと考え、見解をお聞きします。
第3に、「核兵器のない世界」の実現は、被爆者をはじめ、多数の国民の願いです。
被爆70年目の、2015年のNPT再検討会議に、寝屋川からも「核兵器全面禁止を求める」署名をたくさん持って、代表を送ることが期待されています。
★2020年を目標に、「核兵器全面禁止をめざす世界平和市長会議」の一員として、馬場市長のできる限りの協力を求めます。所見を伺います。
次に、防災についてです。
まず、東日本大震災への支援については、市として、引き続き支援を行うこと。募金とボランティア支援も引き続き呼びかけるべきと考えます。
第2に、地域防災計画の見直しについてです。
大阪府は、南海トラフ巨大地震が発生した場合、最大で震度6強の地震がおそい、
約1万1000ヘクタールが津波で浸水、最大13万人が死亡するとの想定を公表しました。被害直後、832万人が断水にみまわれるほか、234万戸が停電、115万戸でガスが供給停止になると予測されています。
その際、本市でも、建物被害・断水・道路閉鎖・避難者の発生、物資の不足、災害廃棄物の発生など、具体的な数値をあげての予測がされています。大阪府は、今年度中に地域防災計画の修正を行うとしています。
★ 本市においても、地域防災計画の見直しを進めるべきです。
第3に、耐震改修の推進についてです。
建物が耐震化されていれば、倒壊を減らすことができます。
★公共施設と住宅の耐震化は目標を、前倒しして実施するよう求めます。
第4に、避難計画の作成についてです。
災害が起こった場合、住民がどのように避難するのか、具体的な計画作りが問われます。
★ 特に、高齢者・障害者・妊婦・乳幼児などの避難計画の策定は重要です。
早期の具体化と計画にもとづく訓練の実施を求めます。
★ 第5に、要援護者の把握をすすめるとともに、住民の協力も得て、日常的なつながりができるように、取り組むべきと考えます。
以上5点、お聞きします。
次に、浸水対策についてです。
まず、地域の保水力のアップについてです。
道路は舗装され、農地が減少する中で、地域の保水力が低下しています。
★緑と農地の保全、浸透性舗装など、市としての計画的な取り組みを求めます。
第2に、一昨年の集中豪雨では、市内の広範囲で浸水しました。寝屋川流域下水道増補幹線の整備や地下河川の整備は待ったなしの課題です。
★大阪府や関係市と調整をすすめ、具体化すること、中木田調節池の設置へ努力を求めます。
第3に、ポンプ調整ルールの運用が始まろうとしています。流域の下水道対策計画について、大阪府は、ポンプ調整をすることで、浸水被害の軽減ができるとしていますが、
上流域の本市については、浸水被害が拡大をすることもありうるとの説明でした。また、被害の拡大については、天災だと理解してほしいと、何ら補償もしない姿勢でした。
★大阪府に対し、市として、被害が拡大しないよう対策すること、被害となった場合の補償制度をつくるよう求めるべきです。
以上、3点、お聞きします。
●次に、原発ゼロと自然エネルギーのとり組みについてです。
原発事故の被害は、今なお深刻さを増し、福島では、14万人もの被災者が、避難生活を強いられています。事故は収束するどころか、放射能汚染水が制御できない、非常事態が続いており、原発事故の原因は、いまだ究明の途上にあり、再稼働など論外です。
現在すべての原発が停止しています。再稼働せずに、廃炉に向かうことこそ、最も現実的で責任ある態度です。
世論調査では、再稼働に7割が「反対」、原発の今後については、「今すぐ廃止」「将来は廃止」をあわせると7~8割にのぼります。
★ 国に「即時原発ゼロ」を決断し、原発の再稼働をやめることを市として求めるべきです。見解をお聞きします。
次に、自然エネルギーの取り組みについてです。
太陽光パネルについて、本庁舎への設置や、市内の自治会集会所を対象にした設置補助の実施を評価します。
その上で、
(1) 自然エネルギーの取り組みについては、市全体としての導入計画を作成し、担当課を設置すること。
(2) 太陽光パネルの設置については、公共施設をはじめ、民間社会福祉施設など、引き続き具体化すること。
2月22日、市内の民間保育園の屋上に、市民の共同出資で、太陽光パネル設置による市民共同発電所ができました。市として、市民参加の市民共同発電所の取り組みへの支援をはかること。
3)7月スタートの太陽光パネルの設置補助制度については、①市民に補助制度を周知すること。②対象を、家庭用だけでなく、市内事業者、民間施設等へ広げること。
(4) 銀行との連携で低金利の貸し付けなど、初期費用ゼロでの太陽光パネル設置へのとり組みの検討をもとめます。
以上4点、お聞きします。
●次に、くらしをまもる施策の拡充についてです。
生活保護についてです。
生活保護費の抑制・削減をねらい、生活保護法の見直しが、今年7月から実施されようとしています。
今まで、口頭での保護申請を認めていたのに、文書申請と書類添付を原則にする条文を新設するなど、生活保護から申請者を遠ざける水際作戦を強化しやすくするものです。
同時に、厚生労働省は、国会答弁で「従来と対応は変わらない」とし、衆議院厚生労働委員会も、「水際作戦があってはならないことを、地方自治体に周知徹底する」との付帯決議をつけました。
市として、市民の申請権を尊重する態度をつらぬくようもとめます。
2) 昨年の大阪府の監査では、17人のケースワーカーの不足が指摘されたと聞きます。市は、非正規の職員でカバーしていると、議会で答弁していますが、それでは府の指導に応えることにはなりません。1人80ケースに対応する正規職員の配置を求めます。
3)昨年8月に続き、今年4月に生活保護費の引き下げが行われます。最低生活を保障するため、国に扶助費の増額を求めるべきです。
以上3点、お聞きします。
次に、介護保険についてです。
まず、介護保険料についてです。
市長は選挙で、介護保険料の引き下げを公約しました。4年間の任期中に引き下げの努力を続けることが、市民の願いに応える道です。
介護保険の改定の中には、第6期からは、第1,第2段階の保険料は、0.5の基準が0.3まで引き下げられます。これは低所得者に対する負担軽減を国も必要と考えたからです。
保険料引き下げのための一般会計からの繰り入れについては、厚生労働省は、公費50対保険料50の基準の遵守をうたっていましたが、今回、国自らが低所得者の負担軽減のために公費を投入する道をつくっています。
★1)来年度は、第5期の最終年度ですが、年度途中の引き下げも可能です。第6期まで待たずに、一般会計の繰り入れで、4月からの保険料の引き下げを求めます。
★2)大阪府下8割をこえる自治体が実施している、保険料の減免制度の創設を求めます。
また、利用料が払えず、介護サービスの利用をあきらめている実態があります。利用料の減免制度の創設を合わせて求めます。
3)本市の特別養護老人ホームの待機者は、600名近くいます。待機者解消のため、施設の新設を求めます。
4)第6期から介護保険制度の大きな制度変更が行われようとしています。要支援1.2の訪問介護や通所介護が介護保険から切り離されるものです。国の制度改悪に対して、市として、反対することを求めます。
以上、4点、お聞きします。
次に、国民健康保険についてです。
1) 本市の国民健康保険料は、所得200万円、40代夫婦と子ども2人の4人世帯のモデルケースで年42万円と、いまだ、所得の21%にもなる高い保険料となっています。
今年度が赤字にならなければ、これまでの累積赤字を解消することができ、14年度は、累積赤字の解消のために、一般会計から繰り入れてきた財源を、保険料引き下げのために使うことができます。保険料引き下げが収納率の向上につながり、国保財政を好転させることが可能です。
また、来年度は、国の財政措置によって、法定軽減が拡充されます。2割軽減では、4人家族で所得213万円までが適用されることで、低所得世帯の収納率の向上が見込まれます。
★一般会計からの繰り入れで、国保料の思い切った引き下げを求めます。
2)保険料の減免制度の拡充を求めます。
3)国民健康保険が社会保障制度として運営されるためには、基礎自治体が住民の命を守る責任を果たすべきです。国保の広域化に反対することを求めます。
4)皆保険制度の根幹をなす国民健康保険には、無収入やワーキングプアの人が加入しています。所得の格差が命の格差とならないよう、短期保険証や資格証明書の発行をやめるよう求めます。
以上4点、お聞きします。
次に、後期高齢者医療制度についてです。
後期高齢者医療広域連合議会で、来年度の保険料が決定しました。平均で年1.21%の引き上げとなります。市として保険料引き下げの努力を求めます。
今回大阪府が財政安定化基金への拠出を拒否しています。財政安定化基金は、国・府・市が3分の1ずつ負担して、保険料の軽減などに利用する基金です。
大阪府が拠出すれば、保険料の値上げは中止できます。市として府に拠出を求めるべきです。
以上、聞きします。
次に、健診事業については、各種健診の受診率向上に向けた取り組みをすすめるようにもとめ、見解をお聞きします。
●次に、子育て施策についてです。
まず、 こども・子育て新制度についてです。
15年4月実施予定の「こども・子育て支援新制度」の国スケジュールでは、市町村は14年夏までに、新制度に関わる基準や保育料などを条例で定め、住民に周知することになっています。
しかし、肝心の国の方針、新制度の詳細はまだ検討中です。わずかな期間で、こどものためになる制度の準備ができるのか疑問です。
★ 新制度は、十分な議論をおこない、関係者、市民の合意を得て実施すべきです。見解をお聞きします。
第2に、新制度では、保護者が保育所にの入所を申し込む際に、保育が必要かどうか、必要な保育時間は何時間かなど、保護者の状況に合わせて認定されることになります。現時点では、短時間児と長時間児に幼稚園児を加えた3区分になると説明されています。
また、保育所や幼稚園、認定こども園以外に、地域型保育など、補助金の対象施設の種類が増えます。保育所以外は、利用者と施設の直接契約となります。
施設によって、職員の配置や保育室の面積、保育士の資格等が異なることによる、保育環境や保育条件に格差がうまれることが心配されています。
★ 1,本市の子どもが、どの施設に入っても、現行の保育水準(施設、保育者の資格、配置基準など)が保障されるよう、各施設、事業の基準を統一すること。
特に、小規模保育については、保育者全員を有資格者にすること。
2.保育時間の認定については、保護者の就労時間だけでなく、一人ひとりの子どもの状況を十分ふまえたものにし、手続きは簡素化すること。
3,保育料は、保護者の負担が増えないようにすべきです。
次に、保育士の不足についてです。
民営化した市内の民間保育園の中には、来年度の保育士が確保できるのかどうか、保護者から心配の声が寄せられています。保育士の不足は、保育園の存続に関わる重大問題であり、緊急に対策をとる必要があります。
今回、市は保育士バンク事業を行いますが、給与改善はもとより、配置基準を含む労働条件の改善が必要です。どのような処遇改善が必要か、早急に調査検討すべきです。見解をお聞きします。
次に、認定こども園、池田すみれこども園についてです。
池田幼稚園敷地内に建設中の新園舎の工事が遅れていますが、旧園舎の解体工事が始まる4月1日から、すみれ保育所で認定こども園が開設される予定です。
本市で初めての認定こども園の開設については、短時間の幼稚園児と長時間の保育所児を、一緒にすることについての、十分な準備ができていない中で進められました。
また、保護者や地域住民が反対する中で、「公立の保育を継続していく、今までと何も変わらない」と、市は説明しました。
しかし、この間の法人のとりくみでは、市の約束通りすすめられていません。
3者懇談会では、来年度の保育デイリープログラムなど、4月からの大事な問題が十分協議されていないこと、市費での事前引き継ぎにおいて、法人の保育士が、昼からすみれ保育所内にいないことが、たびたびあるなどの問題がありました。
保護者などに、市が約束したことを守る立場で、
1)公立保育所の保育の継続を基本にすえること。
2)そのための保育の引き継ぎをきちんとおこなうこと。
3)早急に3者懇談会を開催し、この間の問題について保護者に説明すること、保育デイリープログラムを示し、保護者の意見を十分に聞き、反映すること。
4)保護者の疑問点、不安点について、市の責任で、法人に伝え解決すること。
以上、市が責任をもつことを求め、見解をお聞きします。
次に、こども医療費助成制度の拡充についてです。
国の制度がない中で、全国1724のすべての市町村が実施しており、うち、18歳までが752自治体、全体の4割強が15歳をこえる対象となっています。
大阪府下では、中学3年生までが8自治体、入院のみでは、21自治体と全体の半数近くになっています。
子育て支援の重要な施策として、
★①本市で中学校卒業までを対象にすること。
②大阪府の15年度からの対象年齢引き上げの動きに対し、大阪府に制度拡充を求めること、また、国に制度創設をもとめること。
以上、お聞きします。
次に、児童虐待への体制強化についてです。
本市の家庭児童相談室では、330件の虐待ケース台帳と、年間800件近い相談に対応しています。今年度末で、非常勤の社会福祉士3人全員が、退職するとのことです。
専門性や継続性の点からも、正規職員での対応と増員をもとめ、見解をお聞きします。
●次に、あかつき・ひばり園についてです。
昨年3月に、市長が突然、指定管理者制度導入の方針を出し、1年になります。
保護者、関係者をはじめ全国からの公設公営の継続をもとめる願いに反して、市は、指定管理者制度導入を決定しました。
市は、「療育水準は維持向上する。職員もきちんとそろえる。大丈夫です。信じてほしい」と、何度も、保護者や関係者に説明し、議会でも繰り返し答弁しました。
4月実施まで、20日あまりとなりましたが、法人が採用する看護師2人が、いまだ決まっていません。法人職員の事前引き継ぎの内容も、いまだに保護者に示されていません。
★保護者、関係者からは、「あれほど「大丈夫」だと言ったのは何だったのか」「市が責任をもっている姿勢が見えない」との声が寄せられています。
指定管理後の保育水準の維持向上、あかつき・ひばり園のセンター的役割については、市が責任をもつことを改めて確認します。答弁をもとめます。
第2は、法人職員の確保についてです。
①専門職の確保には、市が責任をもつこと、法人で見つけられないときは、市職員を派遣することをもとめます。
②職員が長く働き続けるための労働条件、福利厚生、昇給を視野に入れた指定管理費にすることを求めます。以上、お聞きします。
第3に、療育水準の維持・向上についてです。
先日、広島市立こども療育センターに行きました。
15年前に、広島市が社会福祉事業団に委託、その後指定管理者制度を導入した施設です。
広島市では、一人の職員が力量をつけるには、10年はかかるとして、「市の派遣職員の人数は変えない」という保護者との約束を守って、施設職員135人中、今でも37人の市職員を派遣しています。
なぜ10年が必要なのかについては、障害をもつこどもと関わるためには、障害の種類や病状や、どんな障害で、どんな行動の特徴があるのかを、理解する必要があるからです。
例えば、肢体不自由児には、脳性麻痺、筋ジストロフィー、小頭症、ダウン症、運動発達の遅れなどがあります。運動面では移動できない子どもから、四つばい、歩行補助具を使って移動できるなど、さまざまです。
発達障害児では、広汎性発達障害、自閉性障害、ダウン症、MRなどがあり、加えて、重複障害として、視覚、聴覚、てんかんなどがあります。
知的な遅れについても、軽度から、中度、重度と違いがあります。
多くの障害の種類とその病状を十分にふまえた、関わりへの理解と実践が求められます。
「どんな障害をもつこどもも、その子に必要な療育をうけて、発達する権利を持っているという「発達保障の考え」に基づき、ひとり一人のこどもの発達段階を知った上で、療育、保育に生かす力量」を身につけるための経験が職員に求められます。
その経験と時間に10年かかるということです。
広島市では、この認識の基で「療育水準を維持向上させる」ことの担保として、法人職員の賃金を市職員に準ずるとした上で、さらに市職員を派遣し続けています。
あかつき・ひばり園の引き継ぎでは、市職員の保育士の派遣は、1年目、17人ですが、2年目は9人に減らし、3年目以降は状況に応じて判断するとしています。
4月採用の法人職員のうち、大半が療育は未経験だと聞きます。1年.2年の引き継ぎで、「療育の引き継ぎは終わりました。市職員はひきあげます。」というのでは、療育水準を守ることには、到底ならないと感じました。
★ 市職員の派遣人数については、毎年度ごとに十分な検討をおこない、現場職員や保護者の意見も聞いて決めることをもとめ、見解をお聞きします。
第4に、療育水準が守られているのかの検証についてです。
評価結果については、毎年度ごとに必ず、保護者や関係者に公表し、その意見を反映し、十分に精査することをもとめ、見解をお聞きします。
第5に、担当ラインについてです。
広島市では、療育センター内に、市の管理課の職員を置き、条件整備や保護者対応に、市が責任を持っています。
★ 4月からの指定管理者制度の実施において、
①状況把握、助言、監督を迅速におこなうなど、重要な役割を果たす担当ラインには、課長級職員を配置すること、
②あかつき・ひばり園内に常駐し、法人との関わり、保護者対応に責任をもてるようにすること。
③ 担当ラインにはあかつき・ひばり園の療育がわかる職員を配置すること、そのために再任用の制度も活用し、できうる限りの体制をつくること。
以上、3点、お聞きします。
第6に、本市では、あかつき・ひばり園があることによって、生まれてから就学前までの、障害児や支援が必要なこどもの早期発見、早期療育のシステムがつくられてきました。
今後は、18歳までの発達保障を視野にいれた、基幹相談支援センターの設置など、新たな施策の具体化をもとめ、見解をお聞きします。
第7に、検討会で残した課題や、4月以降に発生する問題について、保護者・関係団体に十分説明し、意見を聞き、疑問や不安にこたえることを、市の責任としておこなうよう改めてもとめ、お聞きします。
次に、意思疎通支援についてです。
昨年12月、本市議会では、手話言語法の制定を求める意見書が採択されました。
地方自治体でも、鳥取県や北海道石狩市をはじめ、手話言語条例制定の動きが進みつつあります。このような中、本市においても、障害者と障害のない人の意思疎通を支援するためのとりくみが必要です。
(1)正規職員の手話通訳者を配置すること。
本市では、週29時間勤務の非常勤職員の配置ですが、北河内各市では、正規職員が配置されています。本市でも具体化すること。
(2) 本市の手話通訳者は、現在総合センターでの配置ですが、窓口や相談の多い、本庁にも配置すること。
(3)市職員の手話研修を行い、窓口で一定の対応ができるようにすること
(4)小・中学校での手話学習・企業での手話研修への支援を行うこと、
以上4点、お聞きします。
●次に、産業振興についてです。
産業振興条例の制定から1年になります。
① 市内事業者の実態把握のため、市内全事業者を訪問し、面接による実態調査をおこなうこと。
② 営業資金とも生活資金とも言える、小口融資の要求が切実です。市独自の融資制度の創設を検討すること。
③,国が住宅リフォーム推進事業を制度化します。
「長期優良化リフォーム推進事業」の名称で、劣化対策、耐震性能、維持管理・更新、省エネ性能、バリアフリーなどのリフォームに、国が補助を行うものです。
具体的な基準はこれからですが、補助額は工事費の3分の1、限度額は200万円と
100万円の2種類で、国は当面、14年度から3年間事業を続けるとしています。
この補助金の活用をふくめ、市制度の創設をもとめます。
④ 一人親方をはじめ、零細事業者に、公共施設の修繕などを発注する小規模事業者登録制度の創設を求めます。
以上、4点お聞きします。
5,商業振興についてです。
1)空き店舗対策の予算が計上されていますが、新規開業者に対して、家賃・改装費などへの補助制度の拡充と期間の延長をはかること。
2) 商店街が疲弊する原因となっている大型店の進出を規制すること。以上2点、お聞きします。
次に、都市農業の振興についてです。
市内の農地は、20年前と比べ、6割に減少しています。
行政が市内の農地の削減に歯止めを掛け、農地保全と農業振興に責任をはたすこと、所有者と市民との共同によって、農地と農業の維持発展を進めるべきです。
以下お聞きします。
★1.都市計画における農地・農業の位置づけを明確にすること。
★2.農地所有者が継続して農業に取り組めるように、市が農地所有者に対する思い切った助成をおこない農地保全を進めること、市が関わって、市民農園や、地域住民による農業への参加を積極的に促進することをもとめます。
●次に教育についてです。
まず、教育委員会制度についてです。
自民党の「教育委員会制度改革案」は、首長に教育行政全体についての「大綱的な方針」を定める権限を与えるとともに、これまで教育委員会の権限とされてきた、公立学校の設置・廃止、教職員定数、教職員の人員・懲戒の方針など、教育行政の中心的内容を、首長に与えるとしています。
また、教育長については現行法では、教育委員会が任命・罷免できますが、「改革」案では、首長が直接任命・罷免するなどとしています。
大きな問題は、教育委員会の権限を大幅に縮小し、首長の影響力を強めることです。
教育委員会制度は、国家主義に基づく戦前教育の反省から、独立、中立を旨に導入されてきました。
★ 教育が、時の政府や政治家に都合の良いように、利用されることは何としても避けるべきと考えます。
教育委員会の独立性、中立性を守るべきではありませんか。どのようにお考えですか。
その上で、こども、保護者、住民、教職員の声を受け止め、教育行政に反映させる機能を果たすようにすべきです。
あわせてお聞きします。
第2に、教育のあり方についてです。
義務教育では、憲法が掲げる社会の形成者としての主権者を育てること、個人の尊重を基本に人格の完成をめざすこと、能力に応じて教育を受ける権利を保障すること、こどもの権利条約の「子どもの最善の利益を」などが教育活動の基本になると考えます。
本市では、200人規模と500人規模の小学校を廃校にする際に、小中一貫教育と学校選択制、学校の特色づくりと英語教育が導入されました。今では12学園構想となり、来年度は、小学校5年生全員を対象に、学校ごとに1日単位で英語のみでコミュニケーション活動を行う「英語村」をおこないます。中学校は、放課後、希望者が教育研修センターに通学し実施するとしています。
特に、小規模保育については、保育者全員を有資格者にすること。
2.保育時間の認定については、保護者の就労時間だけでなく、一人ひとりの子どもの状況を十分ふまえたものにし、手続きは簡素化すること。
3,保育料は、保護者の負担が増えないようにすべきです。
次に、保育士の不足についてです。
民営化した市内の民間保育園の中には、来年度の保育士が確保できるのかどうか、保護者から心配の声が寄せられています。保育士の不足は、保育園の存続に関わる重大問題であり、緊急に対策をとる必要があります。
今回、市は保育士バンク事業を行いますが、給与改善はもとより、配置基準を含む労働条件の改善が必要です。どのような処遇改善が必要か、早急に調査検討すべきです。見解をお聞きします。
次に、認定こども園、池田すみれこども園についてです。
池田幼稚園敷地内に建設中の新園舎の工事が遅れていますが、旧園舎の解体工事が始まる4月1日から、すみれ保育所で認定こども園が開設される予定です。
本市で初めての認定こども園の開設については、短時間の幼稚園児と長時間の保育所児を、一緒にすることについての、十分な準備ができていない中で進められました。
また、保護者や地域住民が反対する中で、「公立の保育を継続していく、今までと何も変わらない」と、市は説明しました。
しかし、この間の法人のとりくみでは、市の約束通りすすめられていません。
3者懇談会では、来年度の保育デイリープログラムなど、4月からの大事な問題が十分協議されていないこと、市費での事前引き継ぎにおいて、法人の保育士が、昼からすみれ保育所内にいないことが、たびたびあるなどの問題がありました。
保護者などに、市が約束したことを守る立場で、
1)公立保育所の保育の継続を基本にすえること。
2)そのための保育の引き継ぎをきちんとおこなうこと。
3)早急に3者懇談会を開催し、この間の問題について保護者に説明すること、保育デイリープログラムを示し、保護者の意見を十分に聞き、反映すること。
4)保護者の疑問点、不安点について、市の責任で、法人に伝え解決すること。
以上、市が責任をもつことを求め、見解をお聞きします。
次に、こども医療費助成制度の拡充についてです。
国の制度がない中で、全国1724のすべての市町村が実施しており、うち、18歳までが752自治体、全体の4割強が15歳をこえる対象となっています。
大阪府下では、中学3年生までが8自治体、入院のみでは、21自治体と全体の半数近くになっています。
子育て支援の重要な施策として、
★①本市で中学校卒業までを対象にすること。
②大阪府の15年度からの対象年齢引き上げの動きに対し、大阪府に制度拡充を求めること、また、国に制度創設をもとめること。
以上、お聞きします。
次に、児童虐待への体制強化についてです。
本市の家庭児童相談室では、330件の虐待ケース台帳と、年間800件近い相談に対応しています。今年度末で、非常勤の社会福祉士3人全員が、退職するとのことです。
専門性や継続性の点からも、正規職員での対応と増員をもとめ、見解をお聞きします。
●次に、あかつき・ひばり園についてです。
昨年3月に、市長が突然、指定管理者制度導入の方針を出し、1年になります。
保護者、関係者をはじめ全国からの公設公営の継続をもとめる願いに反して、市は、指定管理者制度導入を決定しました。
市は、「療育水準は維持向上する。職員もきちんとそろえる。大丈夫です。信じてほしい」と、何度も、保護者や関係者に説明し、議会でも繰り返し答弁しました。
4月実施まで、20日あまりとなりましたが、法人が採用する看護師2人が、いまだ決まっていません。法人職員の事前引き継ぎの内容も、いまだに保護者に示されていません。
★保護者、関係者からは、「あれほど「大丈夫」だと言ったのは何だったのか」「市が責任をもっている姿勢が見えない」との声が寄せられています。
指定管理後の保育水準の維持向上、あかつき・ひばり園のセンター的役割については、市が責任をもつことを改めて確認します。答弁をもとめます。
第2は、法人職員の確保についてです。
①専門職の確保には、市が責任をもつこと、法人で見つけられないときは、市職員を派遣することをもとめます。
②職員が長く働き続けるための労働条件、福利厚生、昇給を視野に入れた指定管理費にすることを求めます。以上、お聞きします。
第3に、療育水準の維持・向上についてです。
先日、広島市立こども療育センターに行きました。
15年前に、広島市が社会福祉事業団に委託、その後指定管理者制度を導入した施設です。
広島市では、一人の職員が力量をつけるには、10年はかかるとして、「市の派遣職員の人数は変えない」という保護者との約束を守って、施設職員135人中、今でも37人の市職員を派遣しています。
なぜ10年が必要なのかについては、障害をもつこどもと関わるためには、障害の種類や病状や、どんな障害で、どんな行動の特徴があるのかを、理解する必要があるからです。
例えば、肢体不自由児には、脳性麻痺、筋ジストロフィー、小頭症、ダウン症、運動発達の遅れなどがあります。運動面では移動できない子どもから、四つばい、歩行補助具を使って移動できるなど、さまざまです。
発達障害児では、広汎性発達障害、自閉性障害、ダウン症、MRなどがあり、加えて、重複障害として、視覚、聴覚、てんかんなどがあります。
知的な遅れについても、軽度から、中度、重度と違いがあります。
多くの障害の種類とその病状を十分にふまえた、関わりへの理解と実践が求められます。
「どんな障害をもつこどもも、その子に必要な療育をうけて、発達する権利を持っているという「発達保障の考え」に基づき、ひとり一人のこどもの発達段階を知った上で、療育、保育に生かす力量」を身につけるための経験が職員に求められます。
その経験と時間に10年かかるということです。
広島市では、この認識の基で「療育水準を維持向上させる」ことの担保として、法人職員の賃金を市職員に準ずるとした上で、さらに市職員を派遣し続けています。
あかつき・ひばり園の引き継ぎでは、市職員の保育士の派遣は、1年目、17人ですが、2年目は9人に減らし、3年目以降は状況に応じて判断するとしています。
4月採用の法人職員のうち、大半が療育は未経験だと聞きます。1年.2年の引き継ぎで、「療育の引き継ぎは終わりました。市職員はひきあげます。」というのでは、療育水準を守ることには、到底ならないと感じました。
★ 市職員の派遣人数については、毎年度ごとに十分な検討をおこない、現場職員や保護者の意見も聞いて決めることをもとめ、見解をお聞きします。
第4に、療育水準が守られているのかの検証についてです。
評価結果については、毎年度ごとに必ず、保護者や関係者に公表し、その意見を反映し、十分に精査することをもとめ、見解をお聞きします。
第5に、担当ラインについてです。
広島市では、療育センター内に、市の管理課の職員を置き、条件整備や保護者対応に、市が責任を持っています。
★ 4月からの指定管理者制度の実施において、
①状況把握、助言、監督を迅速におこなうなど、重要な役割を果たす担当ラインには、課長級職員を配置すること、
②あかつき・ひばり園内に常駐し、法人との関わり、保護者対応に責任をもてるようにすること。
③ 担当ラインにはあかつき・ひばり園の療育がわかる職員を配置すること、そのために再任用の制度も活用し、できうる限りの体制をつくること。
以上、3点、お聞きします。
第6に、本市では、あかつき・ひばり園があることによって、生まれてから就学前までの、障害児や支援が必要なこどもの早期発見、早期療育のシステムがつくられてきました。
今後は、18歳までの発達保障を視野にいれた、基幹相談支援センターの設置など、新たな施策の具体化をもとめ、見解をお聞きします。
第7に、検討会で残した課題や、4月以降に発生する問題について、保護者・関係団体に十分説明し、意見を聞き、疑問や不安にこたえることを、市の責任としておこなうよう改めてもとめ、お聞きします。
次に、意思疎通支援についてです。
昨年12月、本市議会では、手話言語法の制定を求める意見書が採択されました。
地方自治体でも、鳥取県や北海道石狩市をはじめ、手話言語条例制定の動きが進みつつあります。このような中、本市においても、障害者と障害のない人の意思疎通を支援するためのとりくみが必要です。
(1)正規職員の手話通訳者を配置すること。
本市では、週29時間勤務の非常勤職員の配置ですが、北河内各市では、正規職員が配置されています。本市でも具体化すること。
(2) 本市の手話通訳者は、現在総合センターでの配置ですが、窓口や相談の多い、本庁にも配置すること。
(3)市職員の手話研修を行い、窓口で一定の対応ができるようにすること
(4)小・中学校での手話学習・企業での手話研修への支援を行うこと、
以上4点、お聞きします。
●次に、産業振興についてです。
産業振興条例の制定から1年になります。
① 市内事業者の実態把握のため、市内全事業者を訪問し、面接による実態調査をおこなうこと。
② 営業資金とも生活資金とも言える、小口融資の要求が切実です。市独自の融資制度の創設を検討すること。
③,国が住宅リフォーム推進事業を制度化します。
「長期優良化リフォーム推進事業」の名称で、劣化対策、耐震性能、維持管理・更新、省エネ性能、バリアフリーなどのリフォームに、国が補助を行うものです。
具体的な基準はこれからですが、補助額は工事費の3分の1、限度額は200万円と
100万円の2種類で、国は当面、14年度から3年間事業を続けるとしています。
この補助金の活用をふくめ、市制度の創設をもとめます。
④ 一人親方をはじめ、零細事業者に、公共施設の修繕などを発注する小規模事業者登録制度の創設を求めます。
以上、4点お聞きします。
5,商業振興についてです。
1)空き店舗対策の予算が計上されていますが、新規開業者に対して、家賃・改装費などへの補助制度の拡充と期間の延長をはかること。
2) 商店街が疲弊する原因となっている大型店の進出を規制すること。以上2点、お聞きします。
次に、都市農業の振興についてです。
市内の農地は、20年前と比べ、6割に減少しています。
行政が市内の農地の削減に歯止めを掛け、農地保全と農業振興に責任をはたすこと、所有者と市民との共同によって、農地と農業の維持発展を進めるべきです。
以下お聞きします。
★1.都市計画における農地・農業の位置づけを明確にすること。
★2.農地所有者が継続して農業に取り組めるように、市が農地所有者に対する思い切った助成をおこない農地保全を進めること、市が関わって、市民農園や、地域住民による農業への参加を積極的に促進することをもとめます。
●次に教育についてです。
まず、教育委員会制度についてです。
自民党の「教育委員会制度改革案」は、首長に教育行政全体についての「大綱的な方針」を定める権限を与えるとともに、これまで教育委員会の権限とされてきた、公立学校の設置・廃止、教職員定数、教職員の人員・懲戒の方針など、教育行政の中心的内容を、首長に与えるとしています。
また、教育長については現行法では、教育委員会が任命・罷免できますが、「改革」案では、首長が直接任命・罷免するなどとしています。
大きな問題は、教育委員会の権限を大幅に縮小し、首長の影響力を強めることです。
教育委員会制度は、国家主義に基づく戦前教育の反省から、独立、中立を旨に導入されてきました。
★ 教育が、時の政府や政治家に都合の良いように、利用されることは何としても避けるべきと考えます。
教育委員会の独立性、中立性を守るべきではありませんか。どのようにお考えですか。
その上で、こども、保護者、住民、教職員の声を受け止め、教育行政に反映させる機能を果たすようにすべきです。
あわせてお聞きします。
第2に、教育のあり方についてです。
義務教育では、憲法が掲げる社会の形成者としての主権者を育てること、個人の尊重を基本に人格の完成をめざすこと、能力に応じて教育を受ける権利を保障すること、こどもの権利条約の「子どもの最善の利益を」などが教育活動の基本になると考えます。
本市では、200人規模と500人規模の小学校を廃校にする際に、小中一貫教育と学校選択制、学校の特色づくりと英語教育が導入されました。今では12学園構想となり、来年度は、小学校5年生全員を対象に、学校ごとに1日単位で英語のみでコミュニケーション活動を行う「英語村」をおこないます。中学校は、放課後、希望者が教育研修センターに通学し実施するとしています。
1)本来、学校教育活動と区別すべき、任意の英語検定の受検率や合格率を学校教育の成果指標と位置づけることは誤りです。英語教育の特別なすすめ方のみ直しを求めます。
2) 全国学力テスト、大阪府学力テスト、寝屋川市学力テストの結果の公表などを通じて、学校間競争を煽り、テスト漬けに追い込むことは、学校から学びがい、豊かさを奪い、本来の教育に反するものです。テスト偏重の教育制度は見直すべきです。
3) 国が進める教科書の国定化や「道徳」の教科化などは、子どもたちの内心まで「愛国心」や「規範」意識として統制する危険な動きです。本来は、学校と教職員の自主性を尊重するべきです。競争と管理を進める国や府に追随する姿勢は改めるべきです。「日の丸・君が代」のおしつけもやめるべきです。
以上、3点、見解をお聞きします。
第3に、教育条件整備についてです。
1) 本市の小中学校で、毎年百人を超える定数内講師が配置されていることは問題です。
正規教員の配置を強く大阪府に求めるべきです。
2)少人数学級へのとりくみについてです。
交野市では、来年度から小学3,4年生で35人学級を編成し、門真市では小学校5・6年生、中学校1年生で、35人以下の編成のために任期付教員を配置するなど、市独自の努力が始まっています。本市での少人数学級の取り組みを求めます。
3)特別教室にエアコンがないため、夏場には、理科室や美術室、家庭科室などでの授業がないと聞きます。子どもや保護者、教職員の願いこたえ、早期の全校設置を求めます。
以上、3点見解をお聞きします。
第4に、学童保育についてです。
子ども・子育て新制度に関連して、学童保育事業に市の方針が求められます。
複数学級制による6年生までの受け入れ、指導員や施設・設備の充実した基準設定などを盛り込んだ条例化が求められます。
これまで、市民と市が共同して作り上げた、本市の学童保育事業の保育水準を守り、発展させるべきです。保護者、関係者の意見が反映されるようにもとめ、見解をお聞きします。
●次に、廃プラ施設による健康被害についてです。
まず、ホルムアルデヒドの測定方法についてです。
住民の健康被害の症状は、ホルムアルデヒドが原因のシックハウスとよく似ていると医師が診断し、ホルムアルデヒドが住民の健康被害の原因物質の1つだと指摘しています。
ホルムアルデヒドは毒性が強いため、測定は、24時間平均ではなく、30分平均値で判断することになっています。屋外の測定においては、基準値は定まっていませんが、30分平均値で判断するべきだと、厚生労働省や世界保健機関で確認されています。
12月定例会では、屋外での測定は、24時間平均値が当たり前との答弁がありましたが、公調委の裁定委員である東氏も、30分平均値が望ましいという考えを示し、実際に、公調委の職権調査では、30分平均値の測定が行われました。
24時間平均値が当たり前との市の認識は、問題であることを指摘しておきます。
それでは、まず、健康被害についてです。
2つの廃プラ施設の近くに位置する太秦中町の方に、先日話をお聞きしました。
Kさんは、「目が、チカチカしてとがったものが中に入ったような、つきささった感じがする。鼻は4.5年前から臭いがしなくなった。背中から腰にかけて湿疹がでるようになり、今は体や髪の毛の間にもでるようになった。自宅の南と西側に6、7mの丘があり、東風になると吹きだまり状態になる、一日も早く元のきれいな空気に戻してほしい。」とのことでした。
Nさんは「朝玄関をあけると、鍋のふちを焦がしたような臭いがして、くしゃみ、鼻水がでる、ベランダで洗濯物を干していると、のどがいがらい、からせきがでる。花粉症ではないと診断された、今まで健康には気をつけてきたが、臭いだけはどうしようもない、すぐに廃プラ処理施設をなくしてほしい」と話しました。
Hさんは「顔中に湿疹ができ、特に目のまわりがかゆい。廃プラの操業が始まってから、毎年11月から2月の3か月位、湿疹がでていた。去年の春からは、年中でたりひいたりになった。廃プラ施設の近くに行くと、みかんを腐らせたような臭いがして、顔中が反応するので、原因は廃プラ施設しか考えられない。」といわれました。
また、打上新町のNさんとNさん宅から民間施設まで歩きました。途中で、Nさんが「あっ、今臭う、風にのって臭う。甘酸っぱい臭い」だと。「ずっと臭いがあるのではなく、下の方にたまっていた化学物質が風にのってくるように臭う」とのことでした。
今回お話をお聞きした人を含めて、1000人を超える方が健康被害を訴えています。医師の診察も受けた上で、「原因は2つの廃プラ施設しか考えられない」との意見が改めてよせられました。
★住民の健康、環境をまもる行政として、健康被害の実態把握と被害の解消に向けて、
取り組みをおこなうべきです。健康調査の実施をもとめ、お聞きします。
次に、廃プラ処理の見直しについてです。
プラスチックのリサイクル手法は、サーマルリサイクル(焼却した熱の再利用)と、ケミカル/マテリアルリサイクル(材料の再利用、材料リサイクル)とに大別されます。
焼却した熱の再利用は、本市の新ゴミ処理施設でおこなう予定の「高効率発電」のように、焼却する際に発生する熱を発電に利用することです。
本市の民間施設で行っている、使用済みプラスチックを高熱で溶かし、パレットに再生しているのは材料リサイクルです。
プラスチックは、単一な原材料でないため、PE,PS,PP,PVといった、原料単位で材料に戻すことはできません。また、一見同じにしか見えないプラスチックを市民が原材料単位で分別することはできません。
従って、本来の材料リサイクルには適しません。ダイオキシンを発生させない燃焼法の確立によって、焼却熱の再利用への移行が進んでいます。欧米では、早くから焼却熱の再利用を推進しており、広く行われています。
本市のように、使い道のない雑多な廃プラを分別回収して、圧縮パック、運搬、洗浄、乾燥、高熱で溶かして、パレットをつくるリサイクルの行程は、あまりに手間とお金をかけすぎるものです。
さらに、化学物質が多種多量に含まれた廃プラを圧縮し、そのまま高温で溶かすことによる、環境被害、生物・人体に対する健康被害の危険性を否定できません。
本市における現行の材料リサイクルは、施設周辺住民の健康被害の原因となっています。また、処理コストでは、焼却の場合の1キロ10円に対し、現行の材料リサイクルでは、24円と2.4倍であり、経済効率の面からも見直すべきです。
また、再商品化したパレットは、質の悪い製品であり、不合理です。
★本市においては、現行の材料リサイクルをやめて、廃プラは焼却するべきです。ペットボトルについては、分別回収すべきです。見解をお聞きします。
●次に、まちづくりについてです。
まず、まちづくりの基本方向についてです。
1)人口の減少・高齢化に対応するまちづくりが必要です。人口減少の中、住宅地内にできてくる、空家や空き地を集約して、公共住宅や防災公園にして、災害に強い街へ転換すること。バリアフリーを徹底し、コミュニティバスなどの足の確保、地域の商店の存在など、高齢者が安心して生活できるまちづくりが必要です。
この間の本市のまちづくりは、大型開発中心で、郊外型の大型商業施設の呼び込みなど地域商店の衰退を招くものとなっています。いまこそ、住民生活を基本にすえたまちづくりへの転換を求めます。
2) 身近な商店や商店街が少なくなり、高齢者、障害者を中心に買い物難民と言われる状況があります。京阪バスのルートがない地域、便数が少ない地域を中心に、シャトルバスの延長、タウンくるの台数を増やすこと、小型ワゴンバスなどでのコミュニティバスの実施をもとめます。
(3)市の市営住宅の建て替え計画では、200戸を建設し、残りは民間住宅の借り上げ
などを検討するとしていますが、現状の400戸を確保し、住宅に困っている市民や子育て世代も入居できる住宅の確保を行うこと、地域のつながりを守るためにも、現地建て替えを基本とすることを求めます。
(4)市営住宅の建て替えは、PFI事業によって進められようとしていますが、民間事業者のねらいはPFI事業を通じて利益をあげることであり、企業利益を犠牲にして、
地域や住民にサービスするとは通常考えられません。過大評価で、推進されるPFI事業はやめ、行政の責任で進めることを求めます。
(5)市営住宅の跡地を利用した「小中一貫校構想」が、まちづくり計画に掲載されています。小中一貫校は、現在の小学校、中学校を統廃合して行われるものです。地元住民の合意と理解なしには進めることは許されません。地元住民全体の意見の反映を求めます。
以上5点、お聞きします。
次に、リーサム地区のまちづくりについてです。
リーサムと言う名称には「帰ってきたくなる街」との願いがこめられていると聞きます。なぜ住民が転出したのかの検証が必要です。要因の一つには、市民合意の得られない特別対策や、市民を敵視する誤った運動があったのではないでしょうか。
今回のリーサム地区のまちづくりでは、特別対策となるようなことは繰り返さないこと。第二京阪道路開通に伴い道路整備がされる中、地区内の道路整備は、高宮あさひ丘に通ずる西方寺横の道に限定するなどの見直しを求めます。
また地域にある水本墓地は、密集して、他人の墓をふまないと自分の墓に行けないところもあります。市として現状把握はしているのですか。あわせてお聞きします。
寝屋川東部地域、第二京阪沿道まちづくりについてです。
小路地区土地区画整理事業、四条畷イオンモール建設などで、農地・緑がさらに減少します。市として農地の保全と緑を守るルールづくりが必要です。
また、大規模商業施設では、地域の交通渋滞や環境の悪化対策、市内商店への影響などの解決に取り組むことが必要です。合わせてお聞きします。
東寝屋川駅前線沿道整備計画については、住民合意を前提にすべきです。また、旧水本村役場跡地については、文化施設など、住民の要望に沿った活用を求め、見解をお聞きします。
次に、上・下水道事業についてです。
市は、4月からの上・下水道使用料に、消費税増税分を転嫁することを決めました。約2億円の市民負担増です。この間、市は下水道特別会計への6億円の一般会計からの繰り入れを削減し、市民負担を増やしてきました。
上下水道あわせて徴収される水道料金は、市民にとって重たい負担となっています。
全国の自治体の中には、消費税増税分の負担を住民に転嫁しない努力を始めているところもでています。
★1)市として、安全・安心・安価な上下水道事業にするよう、努力と使用料の福祉減免の実施を求めます。
★2)災害に強い上下水道のインフラ整備を求めます。今回新たに耐震性貯水槽が整備されますが、市内全域で災害が起きたときに対応できる対策の強化を求めます。
以上、2点 お聞きします。
2) 全国学力テスト、大阪府学力テスト、寝屋川市学力テストの結果の公表などを通じて、学校間競争を煽り、テスト漬けに追い込むことは、学校から学びがい、豊かさを奪い、本来の教育に反するものです。テスト偏重の教育制度は見直すべきです。
3) 国が進める教科書の国定化や「道徳」の教科化などは、子どもたちの内心まで「愛国心」や「規範」意識として統制する危険な動きです。本来は、学校と教職員の自主性を尊重するべきです。競争と管理を進める国や府に追随する姿勢は改めるべきです。「日の丸・君が代」のおしつけもやめるべきです。
以上、3点、見解をお聞きします。
第3に、教育条件整備についてです。
1) 本市の小中学校で、毎年百人を超える定数内講師が配置されていることは問題です。
正規教員の配置を強く大阪府に求めるべきです。
2)少人数学級へのとりくみについてです。
交野市では、来年度から小学3,4年生で35人学級を編成し、門真市では小学校5・6年生、中学校1年生で、35人以下の編成のために任期付教員を配置するなど、市独自の努力が始まっています。本市での少人数学級の取り組みを求めます。
3)特別教室にエアコンがないため、夏場には、理科室や美術室、家庭科室などでの授業がないと聞きます。子どもや保護者、教職員の願いこたえ、早期の全校設置を求めます。
以上、3点見解をお聞きします。
第4に、学童保育についてです。
子ども・子育て新制度に関連して、学童保育事業に市の方針が求められます。
複数学級制による6年生までの受け入れ、指導員や施設・設備の充実した基準設定などを盛り込んだ条例化が求められます。
これまで、市民と市が共同して作り上げた、本市の学童保育事業の保育水準を守り、発展させるべきです。保護者、関係者の意見が反映されるようにもとめ、見解をお聞きします。
●次に、廃プラ施設による健康被害についてです。
まず、ホルムアルデヒドの測定方法についてです。
住民の健康被害の症状は、ホルムアルデヒドが原因のシックハウスとよく似ていると医師が診断し、ホルムアルデヒドが住民の健康被害の原因物質の1つだと指摘しています。
ホルムアルデヒドは毒性が強いため、測定は、24時間平均ではなく、30分平均値で判断することになっています。屋外の測定においては、基準値は定まっていませんが、30分平均値で判断するべきだと、厚生労働省や世界保健機関で確認されています。
12月定例会では、屋外での測定は、24時間平均値が当たり前との答弁がありましたが、公調委の裁定委員である東氏も、30分平均値が望ましいという考えを示し、実際に、公調委の職権調査では、30分平均値の測定が行われました。
24時間平均値が当たり前との市の認識は、問題であることを指摘しておきます。
それでは、まず、健康被害についてです。
2つの廃プラ施設の近くに位置する太秦中町の方に、先日話をお聞きしました。
Kさんは、「目が、チカチカしてとがったものが中に入ったような、つきささった感じがする。鼻は4.5年前から臭いがしなくなった。背中から腰にかけて湿疹がでるようになり、今は体や髪の毛の間にもでるようになった。自宅の南と西側に6、7mの丘があり、東風になると吹きだまり状態になる、一日も早く元のきれいな空気に戻してほしい。」とのことでした。
Nさんは「朝玄関をあけると、鍋のふちを焦がしたような臭いがして、くしゃみ、鼻水がでる、ベランダで洗濯物を干していると、のどがいがらい、からせきがでる。花粉症ではないと診断された、今まで健康には気をつけてきたが、臭いだけはどうしようもない、すぐに廃プラ処理施設をなくしてほしい」と話しました。
Hさんは「顔中に湿疹ができ、特に目のまわりがかゆい。廃プラの操業が始まってから、毎年11月から2月の3か月位、湿疹がでていた。去年の春からは、年中でたりひいたりになった。廃プラ施設の近くに行くと、みかんを腐らせたような臭いがして、顔中が反応するので、原因は廃プラ施設しか考えられない。」といわれました。
また、打上新町のNさんとNさん宅から民間施設まで歩きました。途中で、Nさんが「あっ、今臭う、風にのって臭う。甘酸っぱい臭い」だと。「ずっと臭いがあるのではなく、下の方にたまっていた化学物質が風にのってくるように臭う」とのことでした。
今回お話をお聞きした人を含めて、1000人を超える方が健康被害を訴えています。医師の診察も受けた上で、「原因は2つの廃プラ施設しか考えられない」との意見が改めてよせられました。
★住民の健康、環境をまもる行政として、健康被害の実態把握と被害の解消に向けて、
取り組みをおこなうべきです。健康調査の実施をもとめ、お聞きします。
次に、廃プラ処理の見直しについてです。
プラスチックのリサイクル手法は、サーマルリサイクル(焼却した熱の再利用)と、ケミカル/マテリアルリサイクル(材料の再利用、材料リサイクル)とに大別されます。
焼却した熱の再利用は、本市の新ゴミ処理施設でおこなう予定の「高効率発電」のように、焼却する際に発生する熱を発電に利用することです。
本市の民間施設で行っている、使用済みプラスチックを高熱で溶かし、パレットに再生しているのは材料リサイクルです。
プラスチックは、単一な原材料でないため、PE,PS,PP,PVといった、原料単位で材料に戻すことはできません。また、一見同じにしか見えないプラスチックを市民が原材料単位で分別することはできません。
従って、本来の材料リサイクルには適しません。ダイオキシンを発生させない燃焼法の確立によって、焼却熱の再利用への移行が進んでいます。欧米では、早くから焼却熱の再利用を推進しており、広く行われています。
本市のように、使い道のない雑多な廃プラを分別回収して、圧縮パック、運搬、洗浄、乾燥、高熱で溶かして、パレットをつくるリサイクルの行程は、あまりに手間とお金をかけすぎるものです。
さらに、化学物質が多種多量に含まれた廃プラを圧縮し、そのまま高温で溶かすことによる、環境被害、生物・人体に対する健康被害の危険性を否定できません。
本市における現行の材料リサイクルは、施設周辺住民の健康被害の原因となっています。また、処理コストでは、焼却の場合の1キロ10円に対し、現行の材料リサイクルでは、24円と2.4倍であり、経済効率の面からも見直すべきです。
また、再商品化したパレットは、質の悪い製品であり、不合理です。
★本市においては、現行の材料リサイクルをやめて、廃プラは焼却するべきです。ペットボトルについては、分別回収すべきです。見解をお聞きします。
●次に、まちづくりについてです。
まず、まちづくりの基本方向についてです。
1)人口の減少・高齢化に対応するまちづくりが必要です。人口減少の中、住宅地内にできてくる、空家や空き地を集約して、公共住宅や防災公園にして、災害に強い街へ転換すること。バリアフリーを徹底し、コミュニティバスなどの足の確保、地域の商店の存在など、高齢者が安心して生活できるまちづくりが必要です。
この間の本市のまちづくりは、大型開発中心で、郊外型の大型商業施設の呼び込みなど地域商店の衰退を招くものとなっています。いまこそ、住民生活を基本にすえたまちづくりへの転換を求めます。
2) 身近な商店や商店街が少なくなり、高齢者、障害者を中心に買い物難民と言われる状況があります。京阪バスのルートがない地域、便数が少ない地域を中心に、シャトルバスの延長、タウンくるの台数を増やすこと、小型ワゴンバスなどでのコミュニティバスの実施をもとめます。
(3)市の市営住宅の建て替え計画では、200戸を建設し、残りは民間住宅の借り上げ
などを検討するとしていますが、現状の400戸を確保し、住宅に困っている市民や子育て世代も入居できる住宅の確保を行うこと、地域のつながりを守るためにも、現地建て替えを基本とすることを求めます。
(4)市営住宅の建て替えは、PFI事業によって進められようとしていますが、民間事業者のねらいはPFI事業を通じて利益をあげることであり、企業利益を犠牲にして、
地域や住民にサービスするとは通常考えられません。過大評価で、推進されるPFI事業はやめ、行政の責任で進めることを求めます。
(5)市営住宅の跡地を利用した「小中一貫校構想」が、まちづくり計画に掲載されています。小中一貫校は、現在の小学校、中学校を統廃合して行われるものです。地元住民の合意と理解なしには進めることは許されません。地元住民全体の意見の反映を求めます。
以上5点、お聞きします。
次に、リーサム地区のまちづくりについてです。
リーサムと言う名称には「帰ってきたくなる街」との願いがこめられていると聞きます。なぜ住民が転出したのかの検証が必要です。要因の一つには、市民合意の得られない特別対策や、市民を敵視する誤った運動があったのではないでしょうか。
今回のリーサム地区のまちづくりでは、特別対策となるようなことは繰り返さないこと。第二京阪道路開通に伴い道路整備がされる中、地区内の道路整備は、高宮あさひ丘に通ずる西方寺横の道に限定するなどの見直しを求めます。
また地域にある水本墓地は、密集して、他人の墓をふまないと自分の墓に行けないところもあります。市として現状把握はしているのですか。あわせてお聞きします。
寝屋川東部地域、第二京阪沿道まちづくりについてです。
小路地区土地区画整理事業、四条畷イオンモール建設などで、農地・緑がさらに減少します。市として農地の保全と緑を守るルールづくりが必要です。
また、大規模商業施設では、地域の交通渋滞や環境の悪化対策、市内商店への影響などの解決に取り組むことが必要です。合わせてお聞きします。
東寝屋川駅前線沿道整備計画については、住民合意を前提にすべきです。また、旧水本村役場跡地については、文化施設など、住民の要望に沿った活用を求め、見解をお聞きします。
次に、上・下水道事業についてです。
市は、4月からの上・下水道使用料に、消費税増税分を転嫁することを決めました。約2億円の市民負担増です。この間、市は下水道特別会計への6億円の一般会計からの繰り入れを削減し、市民負担を増やしてきました。
上下水道あわせて徴収される水道料金は、市民にとって重たい負担となっています。
全国の自治体の中には、消費税増税分の負担を住民に転嫁しない努力を始めているところもでています。
★1)市として、安全・安心・安価な上下水道事業にするよう、努力と使用料の福祉減免の実施を求めます。
★2)災害に強い上下水道のインフラ整備を求めます。今回新たに耐震性貯水槽が整備されますが、市内全域で災害が起きたときに対応できる対策の強化を求めます。
以上、2点 お聞きします。
● 次に、公共施設等整備・再編計画(改訂版)についてです。
もともとこの計画は、10年3月議会終了後、議会各会派に示されたもので、市民の意見を聞かず、説明もせず、進められてきたものです。
年間数万人の利用者があった市民プールも、廃止反対のこえを無視して進められました。今回の改訂版にも重大な問題があります。
第1に、すみれ保育所の跡地を売却するとしている点です。
測量のための予算も計上されています。
保護者・関係者の強い反対を押し切って、認定こども園にし、住民の意見も聞かずに「活用する予定がない」などとすることは、許されません。新しい活用も含め、住民の意見を聞くべきです。答弁を求めます。
第2に、旧同和地区内公共施設と公共事業用地についてです。
改訂版では、教育センターの廃止・跡地売却、東障害福祉センター跡地、老人いこいの家跡地、共同作業場跡地、協和ストアー跡地の売却などが示されています。
旧同和地区では、約1.6ヘクタールの地域に数多くの公共施設がつくられ、公共事業用地が購入されました。もともと必要のないものが少なくありませんでした。
教育センターは、利用者にきちんと説明し、いきいき文化センターに統合すべきです。
私は、地区内の公共施設については、いきいき文化センターと東高齢者福祉センターのみにすべきと考えます。
1)東高齢者福祉センターについては、地域のお寺に近く、入浴施設の利用も含めて、高齢者の利用しやすい施設であり、いきいき文化センターへの統合はすべきではありません。
2)今回、不用地の処分について、ふるさとリーサム地区のまちづくりの進捗と併せて進めることが示されています。
一体何の関係があるのですか。長年の懸案である不用地処分はすぐにやるべきではありませんか。
3)「地域の意見を聞く」として、もっと早くからやるべきことをまた先送りし、地域住民の声を聞くべき、すみれ保育所をすぐ売却するなどは見直すべきです。
以上、3点、答弁を求め求めます。
次に、行政の公的責任の確立についてです。
保育所、小学校給食の調理業務委託、各種施設の指定管理者制度への移行など、行政がやるべき仕事を民間に丸投げして、「市場原理」にゆだねる動きが進められてきました。民営化の大きな問題は、行政が事業から撤退することによって、市民生活と施策の実態がつかめなくなること、行政の公的な責任をしっかり果たすことが、困難になることです。
いま、市職員のいない公共施設が、多数となりました。もし、大きな災害が起こった時、公共施設に市の職員がいない、これでは、市民の安全に責任を持つことができなくなります。あらためて民営化の見直しを求めます。
また、少子・高齢化がいっそう進行するもとで、直接市民の相談にのり、支援する市職員の存在が必要です。
市職員については、はじめに削減ありきではなく、必要な配置が求められます。
①市民にしっかり責任を持って仕事をするために、退職者の補充はもちろん、専門職をはじめ必要な正職員の配置、非正規職員の待遇改善をはかること。
②市民に直接接する、窓口業務の民間委託はやめること。
以上2点 お聞きします。
次に、労働安全衛生についてです。
本市においても、職員体制の整備を進め、健康管理スタッフの増員、制度充実をはかること。メンタルヘルス対策の抜本的な強化を進めるよう求め、見解をお聞きします。
●次に、地域協働協議会についてです。
現在、地域協働協議会は、小学校2校区で結成。9校区で準備会が発足したと聞きます。
説明会や準備会に参加した人からは、何のために地域協働協議会をつくるのか、協議会で何をするのか、担い手はどうするのかなど、基本的なことで疑問の声が強く出されています。地域協働協議会は、主権者である住民が、住民自治を実現するために進めるものでなければなりません。
市は、14年度中に、24校区すべてでの、地域協働協議会の発足を目標にしているようですが、いそいで組織を作ることにこだわらず、十分時間をかけてとりくむべきです。
そのためにも、住民への情報提供をおこない、校区ごとに住民が参加して議論する場を数多くつくるべきと考えますが、いかがですか。
行政として、住民が主体で取り組むための条件整備をはかることを求め、見解をお聞きします。
● 次に、情報公開・住民参加についてです。
第1に、一昨年夏、市が実施した「市民意識調査」で、「市政に市民の声が届いている」と思う市民は11.6%にとどまり、市政運営のあり方に対して、市民の評価が極めて厳しいことがあらためて示されました。このことを出発点にして、取り組みを抜本的に見直すべきではないでしょうか。
第2に、パブリックコメントについてです。
市民からは「詳しい中身を知ることがむずかしい」「意見を出しても、市は何も聞かない。やっても意味がない」などの意見がでています。素案などを広報等で、市民がわかるように周知すること、市民の意見を反映する制度にするよう求めます。
第3は、各種審議会についてです。
①委員は、公募を基本にあらためること。②委員を希望してもなれない場合も、その人の意見を聞く機会をもうけること。③審議会の開催は、平日の夜や土曜日・日曜日にもつなど、市民や公募委員が参加しやすい措置をとるべきです。
以上、3点お聞きします。
●次に、市財政についてです。
本市では、一般会計で9年連続の黒字。全会計合計でも黒字となり、今年度も黒字となる見込みです。その上基金も100億円を上まわっています。
このような中、市財政のあり方が問われます。この間、大型開発を優先し、福祉、教育の後退を進めてきました。いま「将来を見据えた街の創造」「財政基盤の強化」などとして、さらに黒字を増やし、基金を増やそうとしています。
しかし、自治体のお金は、何よりも市民のくらしを守るためにあります。
いま市がやるべきことは、国民健康保険料、介護保険料の引き下げをはじめ、市民の切実な要求を実現することです。市財政が市民のくらしを守るためのものであるという、本来の役割を果たすよう求め、見解をお聞きします。
次に、基金の積み立てについてです。
本市の財政調整基金は約26億円になり、大幅に増加しています。
基金は各会計年度において、基本的に歳出に不用がでるか、歳入が予想以上であるかどうかを前提とする場合のみ、積み立てが可能となるものです。
当面する住民生活に必要な行政需要を抑制し、財政基盤の確立の名のもと、過度な基金蓄積になってはならないと考えます。答弁を求めます。
次に、市財政確立の基本的な方向についてです。
雇用や社会保障の改善をはじめ、市民生活の安定、向上が税収を増やし、市財政確立につながるものです。この基本をふまえ、寝屋川に住み、寝屋川で働き、寝屋川で消費できるまちへの取り組みが必要と考えます。答弁を求めます。
●最後に、びわこ号復活プロジェクトについてです。
市長市政運営方針では、「今年度、びわこ号の寝屋川車両基地内での復活走行を実現する」としていますが、これは当初の8000万円の寄付目標を2,500万円に修正し、寄付の範囲内での走行をはかるというものです。
本プロジェクトは、市民的な賛同が広がらない中、計画の縮小、見直しをするのは、当然です。本プロジェクトはこれで終結すべきです。答弁を求めます。
また、ブランドの名で特別なことをやることよりも、市が市民生活を守るための施策をしっかりすすめることが重要であることを強く指摘します。
以上で、日本共産党の代表質問を終わります。
もともとこの計画は、10年3月議会終了後、議会各会派に示されたもので、市民の意見を聞かず、説明もせず、進められてきたものです。
年間数万人の利用者があった市民プールも、廃止反対のこえを無視して進められました。今回の改訂版にも重大な問題があります。
第1に、すみれ保育所の跡地を売却するとしている点です。
測量のための予算も計上されています。
保護者・関係者の強い反対を押し切って、認定こども園にし、住民の意見も聞かずに「活用する予定がない」などとすることは、許されません。新しい活用も含め、住民の意見を聞くべきです。答弁を求めます。
第2に、旧同和地区内公共施設と公共事業用地についてです。
改訂版では、教育センターの廃止・跡地売却、東障害福祉センター跡地、老人いこいの家跡地、共同作業場跡地、協和ストアー跡地の売却などが示されています。
旧同和地区では、約1.6ヘクタールの地域に数多くの公共施設がつくられ、公共事業用地が購入されました。もともと必要のないものが少なくありませんでした。
教育センターは、利用者にきちんと説明し、いきいき文化センターに統合すべきです。
私は、地区内の公共施設については、いきいき文化センターと東高齢者福祉センターのみにすべきと考えます。
1)東高齢者福祉センターについては、地域のお寺に近く、入浴施設の利用も含めて、高齢者の利用しやすい施設であり、いきいき文化センターへの統合はすべきではありません。
2)今回、不用地の処分について、ふるさとリーサム地区のまちづくりの進捗と併せて進めることが示されています。
一体何の関係があるのですか。長年の懸案である不用地処分はすぐにやるべきではありませんか。
3)「地域の意見を聞く」として、もっと早くからやるべきことをまた先送りし、地域住民の声を聞くべき、すみれ保育所をすぐ売却するなどは見直すべきです。
以上、3点、答弁を求め求めます。
次に、行政の公的責任の確立についてです。
保育所、小学校給食の調理業務委託、各種施設の指定管理者制度への移行など、行政がやるべき仕事を民間に丸投げして、「市場原理」にゆだねる動きが進められてきました。民営化の大きな問題は、行政が事業から撤退することによって、市民生活と施策の実態がつかめなくなること、行政の公的な責任をしっかり果たすことが、困難になることです。
いま、市職員のいない公共施設が、多数となりました。もし、大きな災害が起こった時、公共施設に市の職員がいない、これでは、市民の安全に責任を持つことができなくなります。あらためて民営化の見直しを求めます。
また、少子・高齢化がいっそう進行するもとで、直接市民の相談にのり、支援する市職員の存在が必要です。
市職員については、はじめに削減ありきではなく、必要な配置が求められます。
①市民にしっかり責任を持って仕事をするために、退職者の補充はもちろん、専門職をはじめ必要な正職員の配置、非正規職員の待遇改善をはかること。
②市民に直接接する、窓口業務の民間委託はやめること。
以上2点 お聞きします。
次に、労働安全衛生についてです。
本市においても、職員体制の整備を進め、健康管理スタッフの増員、制度充実をはかること。メンタルヘルス対策の抜本的な強化を進めるよう求め、見解をお聞きします。
●次に、地域協働協議会についてです。
現在、地域協働協議会は、小学校2校区で結成。9校区で準備会が発足したと聞きます。
説明会や準備会に参加した人からは、何のために地域協働協議会をつくるのか、協議会で何をするのか、担い手はどうするのかなど、基本的なことで疑問の声が強く出されています。地域協働協議会は、主権者である住民が、住民自治を実現するために進めるものでなければなりません。
市は、14年度中に、24校区すべてでの、地域協働協議会の発足を目標にしているようですが、いそいで組織を作ることにこだわらず、十分時間をかけてとりくむべきです。
そのためにも、住民への情報提供をおこない、校区ごとに住民が参加して議論する場を数多くつくるべきと考えますが、いかがですか。
行政として、住民が主体で取り組むための条件整備をはかることを求め、見解をお聞きします。
● 次に、情報公開・住民参加についてです。
第1に、一昨年夏、市が実施した「市民意識調査」で、「市政に市民の声が届いている」と思う市民は11.6%にとどまり、市政運営のあり方に対して、市民の評価が極めて厳しいことがあらためて示されました。このことを出発点にして、取り組みを抜本的に見直すべきではないでしょうか。
第2に、パブリックコメントについてです。
市民からは「詳しい中身を知ることがむずかしい」「意見を出しても、市は何も聞かない。やっても意味がない」などの意見がでています。素案などを広報等で、市民がわかるように周知すること、市民の意見を反映する制度にするよう求めます。
第3は、各種審議会についてです。
①委員は、公募を基本にあらためること。②委員を希望してもなれない場合も、その人の意見を聞く機会をもうけること。③審議会の開催は、平日の夜や土曜日・日曜日にもつなど、市民や公募委員が参加しやすい措置をとるべきです。
以上、3点お聞きします。
●次に、市財政についてです。
本市では、一般会計で9年連続の黒字。全会計合計でも黒字となり、今年度も黒字となる見込みです。その上基金も100億円を上まわっています。
このような中、市財政のあり方が問われます。この間、大型開発を優先し、福祉、教育の後退を進めてきました。いま「将来を見据えた街の創造」「財政基盤の強化」などとして、さらに黒字を増やし、基金を増やそうとしています。
しかし、自治体のお金は、何よりも市民のくらしを守るためにあります。
いま市がやるべきことは、国民健康保険料、介護保険料の引き下げをはじめ、市民の切実な要求を実現することです。市財政が市民のくらしを守るためのものであるという、本来の役割を果たすよう求め、見解をお聞きします。
次に、基金の積み立てについてです。
本市の財政調整基金は約26億円になり、大幅に増加しています。
基金は各会計年度において、基本的に歳出に不用がでるか、歳入が予想以上であるかどうかを前提とする場合のみ、積み立てが可能となるものです。
当面する住民生活に必要な行政需要を抑制し、財政基盤の確立の名のもと、過度な基金蓄積になってはならないと考えます。答弁を求めます。
次に、市財政確立の基本的な方向についてです。
雇用や社会保障の改善をはじめ、市民生活の安定、向上が税収を増やし、市財政確立につながるものです。この基本をふまえ、寝屋川に住み、寝屋川で働き、寝屋川で消費できるまちへの取り組みが必要と考えます。答弁を求めます。
●最後に、びわこ号復活プロジェクトについてです。
市長市政運営方針では、「今年度、びわこ号の寝屋川車両基地内での復活走行を実現する」としていますが、これは当初の8000万円の寄付目標を2,500万円に修正し、寄付の範囲内での走行をはかるというものです。
本プロジェクトは、市民的な賛同が広がらない中、計画の縮小、見直しをするのは、当然です。本プロジェクトはこれで終結すべきです。答弁を求めます。
また、ブランドの名で特別なことをやることよりも、市が市民生活を守るための施策をしっかりすすめることが重要であることを強く指摘します。
以上で、日本共産党の代表質問を終わります。
2013年3月議会 中林市議代表質問
2013-03-08
日本共産党の代表質問をおこないます。
まず、市民生活の現状と市政が果たす役割についてです。
働く人の賃金の低下と労働条件の悪化に歯止めがかかりません。昨年の勤労者の平均賃金は、1990年以降で最低となり、ピーク時の1997年より、年収で約70万円も減っています。
非正規雇用が労働者の3人に1人、若者と女性では2人に1人にまで広がり、年収200万円に満たない労働者が1700万人を超えています。低賃金で不安定な働き方の非正規雇用の拡大は、正規雇用の労働者の賃金と労働条件の低下、長時間労働に拍車をかけています。
本市においても、市民税所得割を納める市民一人あたりの所得は、97年度と2011年度と比較すると874,784円も減少しています。
市民のくらしの困難が拡大する中、生活保護を受ける世帯や、就学援助の認定者が増加を続けています。国保料の減免世帯も、多い状況が続いています。
この市民生活の実態こそ、市政運営の出発点です。
★ 市民生活の現状についてどのように認識されていますか。また、市として市民のくらしを守るため、精一杯のとりくみを行うべきと考えます。市長の見解を求めます。
次に、市民のくらしと国政についてです。
昨年末の総選挙で民主党政権と交代し、3年4ヶ月ぶりに自民・公明連立の安倍政権が発足して、2ヶ月がすぎました。
「デフレ不況」といわれる日本経済の停滞は、国民の所得が落ち込み、消費が減って、企業の売り上げも伸びなくなっていることが原因です。大企業の賃下げと非正規雇用の拡大をやめさせ、国民の所得と雇用を増やさなければ打開できません。安倍政権の対策は、不況の原因も、これまで政権を担当してきた自らの責任も明らかにせず、過去の自民党政権の破綻した政策を並べただけです。「デフレ不況」打開の展望を国民に示すものではありません。
実際、2%の物価上昇目標といいますが、物価が上がっただけで賃金や年金がさらに目減りするのではないかと、国民の懸念は深刻です。
政府が労働者の賃上げへの、本腰を入れた対策をとることが急務です。
★ デフレ不況から脱却するためには、第1に、国民に13.5兆円もの負担増となる消費税の増税を中止すること。第2に、労働者の賃金引き上げをすすめること、非正規雇用から正規雇用への転換など、雇用の改善をはかることが重要です。 以上2点について、市長の認識をお聞きします。
次に、大阪府政についてです。
橋下府政、松井府政になって、5年になります。
この間大阪府は、①街かどディハウス補助金の削減、②高齢者住宅改造助成の廃止 ③障害者福祉作業所、小規模通所授産施設への補助金の削減 ④国民健康保険府単独補助の削減 ⑤学校警備員補助の廃止 ⑥地震対策事業の削減 ⑦密集住宅市街地整備補助金の削減 ⑧市町村施設整備資金の削減 ⑨千里、大阪赤十字病院の救命救急センターの補助金削減 ⑩府営住宅家賃減免制度改悪等を進めてきました。
これらは、住民福祉の後退であり、容認できません。
★市として大阪府に対し、施策の後退ではなく、拡充をはかるようもとめるべきです。見解をお聞きします。
次に、平和の取り組みについてです。
安倍政権が、憲法9条改定を現実の政治日程にのせることを公言していることは、きわめて重大です。憲法9条は、日本が二度と侵略国にならず、世界平和の先がけになるという国際公約です。今こそ、日本の政治と外交の基本にすえることがもとめられます。
日本政府が行うべきは、憲法9条を生かして核兵器の全面廃絶の先頭に立って、アメリカにも中国にも北朝鮮にも、のぞむことです。★そうした世論を大きくするために、2015年のNPT(核不拡散条約)再検討会議に向けての「核兵器の全面禁止を求める」国際署名に、市長が全面に協力するよう求め、見解をお聞きします。
次に、平和資料室の設置です。
中央公民館3階における展示では、市民の平和学習にはなりません。戦争体験や被爆体験を持つ方の高齢化が進む中、資料収集は待ったなしの状況です。
★戦争を知らない子どもや市民が、二度とあってはならない戦争や被爆の「追体験」ができる常設展示の平和学習資料室の設置をもとめます。
★原爆被害者団体協議会(日本被団協)作成したのパネル「ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間」の購入を要望し、以上2点、お聞きします。
次に、防災についてです。
東日本大震災から、まもなく2年になろうとしていますが、被災地では、今だに32万人もの方々が苦しい避難生活を強いられています。
特に、生活と生業に必要な公的支援が最大の要であり、住まいの確保、中小企業の再建などへの支援が重要となっています。
★ 政府に対し、施策の抜本的な改善をもとめるとともに、市として引き続き支援を行うこと。被災地に直接役立つように、募金やボランティア支援も引き続き呼びかけるべきと考えます。見解をお聞きします。
現在、地域防災計画の改定案のパブリックコメントが行われています。
当面のとりくみについて
第1に、公共施設と住宅の耐震化をおもいきって推進することです。
建物が耐震化されていれば、倒壊を減らすことができます。
公共施設と住宅の耐震化は、市の計画を前倒しして実施するよう求めます。
第2に、防災についての学習や議論についてです。
防災計画の改定内容をはじめ、多様な形で市民的な学習や議論が必要です。
第3に、安全安心のまちづくり基金についてです。
この基金について、住宅・公共施設の耐震化の前倒しや、浸水対策等に使途を限定し、少しでも早く活用することを求めます。
以上、3点、お聞きします。
次に、浸水対策についてです。
昨年8月14日の短時間集中豪雨の検証報告書が、12月議会の最中に出されましたが、議会や市民へ説明がされていません。
また、浸水の状況について、町ごとの浸水状況を示すとしていたのに、いまだに明らかにされていません。以上2点の説明をもとめます。
次に、施策についてです。
★①浸水対策の具体的なとりくみは、報告書で示されていますが、大阪府や国に対し、必要なとりくみをもとめること、市としての具体化を強く求めます。
★②調節池や地下河川の設置などが中心になっていますが、同時に地盤での保水能力を高めるため、緑や農地の保全、再生が必要と考えます。
以上2点、お聞きします。
次に、原発ゼロと自然エネルギーの活用についてです。
安倍政権は、原発再稼働の推進、新増設の容認、原発輸出の推進を公言し、前政権が打ち出した「2030年代 原発稼動ゼロ」という、極めて不十分な方針すら白紙に戻す立場を打ち出しました。
あからさまな原発推進政策は、福島の悲惨な大事故の体験を経て「原発ゼロの日本」を求める国民多数の声に、真っ向からそむくものといわねばなりません。
★福島第1原発事故の収束と被害の賠償に全力をあげると共に、今こそ政府が、原子力発電からの撤退を決断し、「原発ゼロ」をすすめるべきです。市として、政府に求めるべきです。見解をお聞きします。
次に、自然エネルギーの本格導入についてです。
自然エネルギーは、地域の条件を生かせる安全なエネルギーです。地域経済に新たな分野と雇用をつくるという位置付けで、取り組むべきです。
来年度予算では、家庭用太陽光パネル設置への助成費として3000万円の予算が計上されたことを評価します。
★さらにとりくみを広げる立場から
① 市として、本市の自然エネルギーの活用ビジョンを住民参加で策定すること。
② 太陽光パネルなどを、本市の避難所である公共施設に優先的に設置すること。
③ 市内民間施設への太陽光パネルなどの設置補助制度を創設すること。
④ 国に対し、自然エネルギーの明確な導入目標を設定するよう求めること。
以上4点、見解をお聞きします。
次に、くらし守る施策の拡充についてです。
生活保護についてです。
まず、国の予算削減についてです。
政府の「生活保護費削減方針」の最大の柱は、食費や光熱費など、日常の暮らしに欠かせない生活扶助、期末一時扶助などの基準を、今年8月から3年かけて引き下げ、年間740億円7.3%を減額する計画です。
減額対象も利用世帯の96%にのぼります。最大10%減額される世帯、月2万円もカットされる夫婦と子ども2人の4人世帯も生まれます。貧困世帯にさらなる貧困を強いる削減計画は、憲法25条に反します。
影響は利用者だけにとどまりません。保護基準は、低所得者のくらしを支えている、国や地方自治体のさまざまな制度の適用対象の「目安」として連動する仕組みになっているためです。
影響する制度は、就学援助、個人住民税の非課税限度額の算定、保育料や医療・介護の保険料の減免制度など少なくとも40近くに及びます。
★ 日本を“貧困底なし社会”にする保護基準引き下げそのものをやめるべきです。
市として、国に、「生活保護費削減方針」に反対するようもとめ、見解をお聞きします。
第2に、申請権の保障についてです。
本市では、生活保護申請の対応のほとんどを面接相談員がしています。
面接相談員の配置後、扶養親族への確認などを理由に申請を受理せず、市民の申請権が守られていない事例が続きました。
埼玉県三郷市在住の夫婦が数回にわたり、生活保護の申請をしたのに対し、市が1年半も拒否したことについて、2月20日、さいたま地裁は、職務義務違反と認定し、原告勝訴の判決となりました。その後、三郷市が控訴断念を表明し、判決が確定しました。
★生活保護制度の周知をはかるとともに、市民の生活保護申請権をきちんと守ることをもとめ、見解をお聞きします。
第3に、ケースワーカーの配置についてです。
★ (1)ケースワーカーの増員、(2)社会福祉の専門職採用及び配置、(3)他法他施策を含めた生活保護・社会福祉全般の研修の充実、(4)生活保護業務の経験蓄積ができる人事異動の展開などを図る必要があると考えます。以上4点の見解をお聞きします。
次に、介護保険についてです。
市政運営方針では、介護保険料についてふれられていません。昨年、市長の選挙公約に反して、介護保険料の引き上げが行われました。年金の支給額が減り続ける中で多くの高齢者が怒りの声を上げています。
★市長公約の実現へ、市として介護保険料の引き下げと市独自の保険料減免制度の創設と、利用料減免制度の創設を求めます。
★ 今年度の地域包括支援センターの3箇所の拡充は評価します。人員配置を拡充し機能の強化を求めます。
1月にNHKテレビで「老人漂流社会『歳をとることは罪なのか――』」という特集がありました。高齢者が自らの意思で死に場所を決められない現実が広がり、 行き場を求めて漂流する高齢者があふれ出す異常事態が、すでに起き始めている。というものです。
寝屋川市の入所施設は、今約650名の特別養護老人ホームの待機者が出ています。今年度、小規模特養1箇所とグループホーム2箇所の建設が予定されていますが、これではすべての待機者の解消につながりません。
★ 高齢者に必要な施設、特に特別養護老人ホーム等の入所施設の待機者解消の計画を求めます。
★入所費用が高く経済的な理由で入所できない実態があります。制度の改善を国に求めると共に、市の施策を求めます。
★高齢者が地域で住み続けることが出来るように、自宅や地域のバリアフリー化を援助する施策を求め、 以上5点、見解をお聞きします。
まず、市民生活の現状と市政が果たす役割についてです。
働く人の賃金の低下と労働条件の悪化に歯止めがかかりません。昨年の勤労者の平均賃金は、1990年以降で最低となり、ピーク時の1997年より、年収で約70万円も減っています。
非正規雇用が労働者の3人に1人、若者と女性では2人に1人にまで広がり、年収200万円に満たない労働者が1700万人を超えています。低賃金で不安定な働き方の非正規雇用の拡大は、正規雇用の労働者の賃金と労働条件の低下、長時間労働に拍車をかけています。
本市においても、市民税所得割を納める市民一人あたりの所得は、97年度と2011年度と比較すると874,784円も減少しています。
市民のくらしの困難が拡大する中、生活保護を受ける世帯や、就学援助の認定者が増加を続けています。国保料の減免世帯も、多い状況が続いています。
この市民生活の実態こそ、市政運営の出発点です。
★ 市民生活の現状についてどのように認識されていますか。また、市として市民のくらしを守るため、精一杯のとりくみを行うべきと考えます。市長の見解を求めます。
次に、市民のくらしと国政についてです。
昨年末の総選挙で民主党政権と交代し、3年4ヶ月ぶりに自民・公明連立の安倍政権が発足して、2ヶ月がすぎました。
「デフレ不況」といわれる日本経済の停滞は、国民の所得が落ち込み、消費が減って、企業の売り上げも伸びなくなっていることが原因です。大企業の賃下げと非正規雇用の拡大をやめさせ、国民の所得と雇用を増やさなければ打開できません。安倍政権の対策は、不況の原因も、これまで政権を担当してきた自らの責任も明らかにせず、過去の自民党政権の破綻した政策を並べただけです。「デフレ不況」打開の展望を国民に示すものではありません。
実際、2%の物価上昇目標といいますが、物価が上がっただけで賃金や年金がさらに目減りするのではないかと、国民の懸念は深刻です。
政府が労働者の賃上げへの、本腰を入れた対策をとることが急務です。
★ デフレ不況から脱却するためには、第1に、国民に13.5兆円もの負担増となる消費税の増税を中止すること。第2に、労働者の賃金引き上げをすすめること、非正規雇用から正規雇用への転換など、雇用の改善をはかることが重要です。 以上2点について、市長の認識をお聞きします。
次に、大阪府政についてです。
橋下府政、松井府政になって、5年になります。
この間大阪府は、①街かどディハウス補助金の削減、②高齢者住宅改造助成の廃止 ③障害者福祉作業所、小規模通所授産施設への補助金の削減 ④国民健康保険府単独補助の削減 ⑤学校警備員補助の廃止 ⑥地震対策事業の削減 ⑦密集住宅市街地整備補助金の削減 ⑧市町村施設整備資金の削減 ⑨千里、大阪赤十字病院の救命救急センターの補助金削減 ⑩府営住宅家賃減免制度改悪等を進めてきました。
これらは、住民福祉の後退であり、容認できません。
★市として大阪府に対し、施策の後退ではなく、拡充をはかるようもとめるべきです。見解をお聞きします。
次に、平和の取り組みについてです。
安倍政権が、憲法9条改定を現実の政治日程にのせることを公言していることは、きわめて重大です。憲法9条は、日本が二度と侵略国にならず、世界平和の先がけになるという国際公約です。今こそ、日本の政治と外交の基本にすえることがもとめられます。
日本政府が行うべきは、憲法9条を生かして核兵器の全面廃絶の先頭に立って、アメリカにも中国にも北朝鮮にも、のぞむことです。★そうした世論を大きくするために、2015年のNPT(核不拡散条約)再検討会議に向けての「核兵器の全面禁止を求める」国際署名に、市長が全面に協力するよう求め、見解をお聞きします。
次に、平和資料室の設置です。
中央公民館3階における展示では、市民の平和学習にはなりません。戦争体験や被爆体験を持つ方の高齢化が進む中、資料収集は待ったなしの状況です。
★戦争を知らない子どもや市民が、二度とあってはならない戦争や被爆の「追体験」ができる常設展示の平和学習資料室の設置をもとめます。
★原爆被害者団体協議会(日本被団協)作成したのパネル「ヒロシマ・ナガサキ原爆と人間」の購入を要望し、以上2点、お聞きします。
次に、防災についてです。
東日本大震災から、まもなく2年になろうとしていますが、被災地では、今だに32万人もの方々が苦しい避難生活を強いられています。
特に、生活と生業に必要な公的支援が最大の要であり、住まいの確保、中小企業の再建などへの支援が重要となっています。
★ 政府に対し、施策の抜本的な改善をもとめるとともに、市として引き続き支援を行うこと。被災地に直接役立つように、募金やボランティア支援も引き続き呼びかけるべきと考えます。見解をお聞きします。
現在、地域防災計画の改定案のパブリックコメントが行われています。
当面のとりくみについて
第1に、公共施設と住宅の耐震化をおもいきって推進することです。
建物が耐震化されていれば、倒壊を減らすことができます。
公共施設と住宅の耐震化は、市の計画を前倒しして実施するよう求めます。
第2に、防災についての学習や議論についてです。
防災計画の改定内容をはじめ、多様な形で市民的な学習や議論が必要です。
第3に、安全安心のまちづくり基金についてです。
この基金について、住宅・公共施設の耐震化の前倒しや、浸水対策等に使途を限定し、少しでも早く活用することを求めます。
以上、3点、お聞きします。
次に、浸水対策についてです。
昨年8月14日の短時間集中豪雨の検証報告書が、12月議会の最中に出されましたが、議会や市民へ説明がされていません。
また、浸水の状況について、町ごとの浸水状況を示すとしていたのに、いまだに明らかにされていません。以上2点の説明をもとめます。
次に、施策についてです。
★①浸水対策の具体的なとりくみは、報告書で示されていますが、大阪府や国に対し、必要なとりくみをもとめること、市としての具体化を強く求めます。
★②調節池や地下河川の設置などが中心になっていますが、同時に地盤での保水能力を高めるため、緑や農地の保全、再生が必要と考えます。
以上2点、お聞きします。
次に、原発ゼロと自然エネルギーの活用についてです。
安倍政権は、原発再稼働の推進、新増設の容認、原発輸出の推進を公言し、前政権が打ち出した「2030年代 原発稼動ゼロ」という、極めて不十分な方針すら白紙に戻す立場を打ち出しました。
あからさまな原発推進政策は、福島の悲惨な大事故の体験を経て「原発ゼロの日本」を求める国民多数の声に、真っ向からそむくものといわねばなりません。
★福島第1原発事故の収束と被害の賠償に全力をあげると共に、今こそ政府が、原子力発電からの撤退を決断し、「原発ゼロ」をすすめるべきです。市として、政府に求めるべきです。見解をお聞きします。
次に、自然エネルギーの本格導入についてです。
自然エネルギーは、地域の条件を生かせる安全なエネルギーです。地域経済に新たな分野と雇用をつくるという位置付けで、取り組むべきです。
来年度予算では、家庭用太陽光パネル設置への助成費として3000万円の予算が計上されたことを評価します。
★さらにとりくみを広げる立場から
① 市として、本市の自然エネルギーの活用ビジョンを住民参加で策定すること。
② 太陽光パネルなどを、本市の避難所である公共施設に優先的に設置すること。
③ 市内民間施設への太陽光パネルなどの設置補助制度を創設すること。
④ 国に対し、自然エネルギーの明確な導入目標を設定するよう求めること。
以上4点、見解をお聞きします。
次に、くらし守る施策の拡充についてです。
生活保護についてです。
まず、国の予算削減についてです。
政府の「生活保護費削減方針」の最大の柱は、食費や光熱費など、日常の暮らしに欠かせない生活扶助、期末一時扶助などの基準を、今年8月から3年かけて引き下げ、年間740億円7.3%を減額する計画です。
減額対象も利用世帯の96%にのぼります。最大10%減額される世帯、月2万円もカットされる夫婦と子ども2人の4人世帯も生まれます。貧困世帯にさらなる貧困を強いる削減計画は、憲法25条に反します。
影響は利用者だけにとどまりません。保護基準は、低所得者のくらしを支えている、国や地方自治体のさまざまな制度の適用対象の「目安」として連動する仕組みになっているためです。
影響する制度は、就学援助、個人住民税の非課税限度額の算定、保育料や医療・介護の保険料の減免制度など少なくとも40近くに及びます。
★ 日本を“貧困底なし社会”にする保護基準引き下げそのものをやめるべきです。
市として、国に、「生活保護費削減方針」に反対するようもとめ、見解をお聞きします。
第2に、申請権の保障についてです。
本市では、生活保護申請の対応のほとんどを面接相談員がしています。
面接相談員の配置後、扶養親族への確認などを理由に申請を受理せず、市民の申請権が守られていない事例が続きました。
埼玉県三郷市在住の夫婦が数回にわたり、生活保護の申請をしたのに対し、市が1年半も拒否したことについて、2月20日、さいたま地裁は、職務義務違反と認定し、原告勝訴の判決となりました。その後、三郷市が控訴断念を表明し、判決が確定しました。
★生活保護制度の周知をはかるとともに、市民の生活保護申請権をきちんと守ることをもとめ、見解をお聞きします。
第3に、ケースワーカーの配置についてです。
★ (1)ケースワーカーの増員、(2)社会福祉の専門職採用及び配置、(3)他法他施策を含めた生活保護・社会福祉全般の研修の充実、(4)生活保護業務の経験蓄積ができる人事異動の展開などを図る必要があると考えます。以上4点の見解をお聞きします。
次に、介護保険についてです。
市政運営方針では、介護保険料についてふれられていません。昨年、市長の選挙公約に反して、介護保険料の引き上げが行われました。年金の支給額が減り続ける中で多くの高齢者が怒りの声を上げています。
★市長公約の実現へ、市として介護保険料の引き下げと市独自の保険料減免制度の創設と、利用料減免制度の創設を求めます。
★ 今年度の地域包括支援センターの3箇所の拡充は評価します。人員配置を拡充し機能の強化を求めます。
1月にNHKテレビで「老人漂流社会『歳をとることは罪なのか――』」という特集がありました。高齢者が自らの意思で死に場所を決められない現実が広がり、 行き場を求めて漂流する高齢者があふれ出す異常事態が、すでに起き始めている。というものです。
寝屋川市の入所施設は、今約650名の特別養護老人ホームの待機者が出ています。今年度、小規模特養1箇所とグループホーム2箇所の建設が予定されていますが、これではすべての待機者の解消につながりません。
★ 高齢者に必要な施設、特に特別養護老人ホーム等の入所施設の待機者解消の計画を求めます。
★入所費用が高く経済的な理由で入所できない実態があります。制度の改善を国に求めると共に、市の施策を求めます。
★高齢者が地域で住み続けることが出来るように、自宅や地域のバリアフリー化を援助する施策を求め、 以上5点、見解をお聞きします。