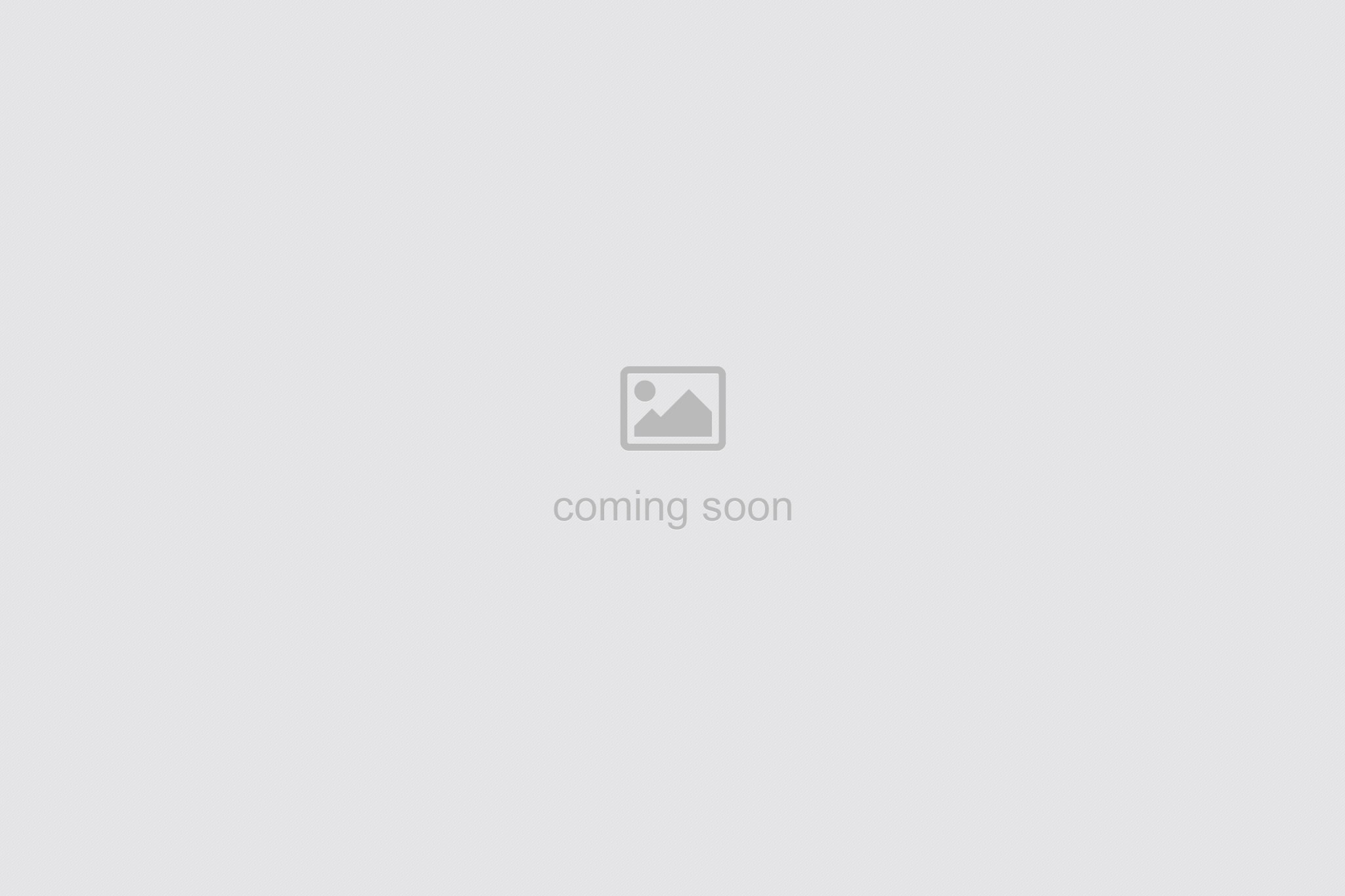2015年12月議会 一般質問 前川なお

日本共産党議員団の前川奈緒です。
通告に従いまして、質問を行います。
【防災】
はじめに、防災についてお聞きします。
大阪府がまとめた本市の「地震被害想定」を見ると、東南海・南海地震、生駒断層帯地震で大きな被害が想定されています。
とりわけ、内陸直下型地震の生駒断層では、全壊家屋1万8355棟、罹災者数は13万2820人、避難所生活者数では3万8518人にのぼるとされています。
本市においては、2013(平成25)年7月に地域防災計画が策定されましたが、計画策定後、防災会議は定期的に開催されているのでしょうか。計画の進捗状況などの確認は行われているのでしょうか。お答えください。
国際的に、自然災害における被害は、男性よりも女性の方が大きいと言われるようになっています。
これまでの国内における自然災害においても、避難所で、女性のニーズがくみ取られなかった事例が多くありました。
▽新潟県中越地震の避難所では、プライバシーを守る仕切の設置が却下され、洗濯物を干す場所がなかった。女性や子育て用品の備蓄がないなどの問題が起こりました。
▽東日本大震災の避難所では、トイレを我慢した結果の膀胱炎、尿漏れ、生理不順、妊娠・出産など、女性特有の健康問題が明らかになりました。その結果、助産師や看護師など専門職の配置や情報提供が必要と再認識されています。
▽女性に対する暴力の問題もあります。阪神・淡路大震災の際は、夫や恋人からの暴力、いわゆるDV被害が増大しました。公的な記録はありませんが、レイプ被害の相談もあったとのことです。
▽高齢者の場合は、あまり身体を動かさない避難所生活の中で、歩行困難になったなどのケースがあります。
この事例からもわかるように、避難所で、女性や子ども、高齢者や障害者は、困ったことがあってもなかなか声を上げられず、逆に、不満を言うと避難所に居づらくなると感じて、我慢しがちになるのです。
本市の防災対策において、女性の視点や意見は反映されているでしょうか。
防災会議の委員40人のうち、女性は4人です。各部署から部長級の職員が入るとなると、男性の比率が高くなるのは仕方がないことではあります。
ただ、多くの自治体で、女性の意見を採り入れる工夫がなされています。
たとえば、大分県臼杵市では、女性の防災士だけで組織する「うすき女性防災士連絡協議会」が設置されています。
神奈川県川崎市は、男女共同参画センターが、「避難所運営ガイド」をはじめ、環境や年齢に応じた防災冊子を作成し、災害時のトイレについても、研究してわかりやすくまとめ、すべてホームページにアップしています。
女性の声、ニーズをくみ上げ、防災に生かすことは、災害時の対応のみならず、災害の被害を減らす「減災」にもつながります。
他市の状況に学んで、本市の防災計画にも、たとえば女性防災士の育成の推進や、防災会議の下部組織のような形で、女性だけの防災協議会を立ち上げるなど、思いきった改革が必要ではないでしょうか。
この6月には、24校区の自主防災連合協議会に「避難所開設・運営マニュアル」が配布され、検討会が順次開かれています。地域でも、女性の意見をくみ取れるシステムへと、もう一歩進めるよう、市としてもサポートをお願いします。
また、保存版防災読本「防活のススメ」は、本市のホームページでも見ることができるようにすべきです。
市の考えをお聞かせください。
関連して、避難所の備蓄についてです。
昨年度において、非常用食料の倍増と、全小学校区への備蓄などが具体化されたことを、大変うれしく思っています。
今後も、食料・飲料水、粉ミルクや簡易トイレといった重要物資をはじめ、断熱シート、避難所間仕切りといったその他の物資など、各避難所に必要量が確実に行き渡るようお願いします。
また、今後、市民のニーズや年齢構成の変化などに応じた備蓄品の充実もお願いします。市の考えをお聞かせください。
災害時の避難で、手助けが必要な人への支援は、どのようになっているでしょうか。
現在、障害者手帳をお持ちの方、要介護認定者などは、「避難行動要支援者」として、名簿が作成されています。しかし実際に災害が起きたときに、誰が誰を避難所へ誘導し、また救助するのかといった課題については、これからです。
名簿作成の進捗状況、課題などをお聞かせください。
支援や配慮が必要な方が避難できる場所として、福祉避難所があります。
本市において、福祉避難所として協定を結んでいる施設の数について、お聞きします。介護施設、障害者施設別にお答えください。
福祉避難所として締結している施設でも、災害の状態や職員体制、設備、入居者の状態などで、受け入れ状況が変わってくることが考えられますが、現時点で、受け入れ可能人数は、介護、障害者施設で、だいたい何人を想定されているでしょうか。
あわせて、災害時に福祉避難所が実際に機能する上で、市としてどんな課題があるとお考えですか。また今後の計画などをお聞かせください。
災害時における火災についても触れたいと思います。
阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊よりも火災によって多くの方が亡くなりました。通電火災と呼ばれるものです。
通電火災とは主に、地震で電気が止まることによって電化製品が一時的にストップしても、電気が復旧(通電)したとき、電化製品が再び稼働して火災を引き起こすという現象です。
私も、地域の防災訓練に参加して、「通電火災」のことを知りました。
逃げる際にブレーカーを落とせば、この通電火災は防ぐことができます。そこで注目されているのが、「感震ブレーカー」です。
感震ブレーカーは、地震の揺れを感知すると自動的に電気を止める装置で、主に分電盤タイプ、簡易タイプ、コンセントタイプの3種類あります。
分電盤タイプは、センサーが揺れを感知して住宅内全ての電気を止めるもので、工事費を含んで3~8万円の費用がかかります。
簡易タイプは、揺れによって重りやバネが動いて分電盤のスイッチを操作し、住宅内全ての電気を止めるタイプです。2~4千円と安価ですが、地震以外の振動・衝撃でも作動する場合があるとのことです。
コンセントタイプは、1カ所5千円~2万円で、コンセントに内蔵したセンサーが揺れを感知し、そのコンセントからの電気を止めます。ただし、壁の中を通る配線からの出火は防げません。
政府も、「大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会」を設置し、木造住宅密集地域等へ、感震ブレーカーを普及促進するよう提言しています。
ただ、感震ブレーカーの認知度は低く、全国的にも普及促進は遅れているのが実状です。ましてや、感震ブレーカー設置の助成制度を設けている自治体は、少数です。
横浜市では、分電盤タイプ、コンセントタイプとそれぞれ設置費用の3分の1、2分の1を助成しています。2014年度は422件の適用があったとのことです。
鳥取県では、3年間の期限付きで補助を実施するとしています。
珍しいケースでは、岡山県真庭群新庄村が補正予算を組んで、全世帯に当たる約400世帯に簡易タイプの感震ブレーカーを配布しています。
木造住宅密集地域も多く存在する本市においても、地震災害における通電火災の予防として、感震ブレーカーの認知と普及を促進すべきと考えます。
「災害に強いまちづくり」をいっそう推進していくため、感震ブレーカーについても、設置の補助をお願いします。とりわけ、高齢者世帯、障害者(児)のいる世帯、乳幼児のいる子育て世帯に対しては、優先すべきと考えます。
また、公共施設などにも早急に設置すべきです。
公共施設への設置状況や、今後の計画など、市の考えをお聞かせください。
公共施設の耐震化についても、学校や保育所をはじめ市内公共施設の耐震補強は順次行われています。しかし今後10年、20年といった長期スパンで考えた場合、建て替えも含めた耐震計画が必要ではないかと考えます。
公共施設の耐震化について、現在の進捗状況と今後の計画をお聞かせください。
加えて、市内の水道管の改修も含めた「災害に強いまちづくり」の観点から、市内の水道管の耐震の現状と今後の改修計画など、お聞かせください。
【手話言語条例】
次に、手話言語条例についてです。
日本における手話は、1878(明治11)年に誕生したとされ、聴覚障害者のコミュニケーションツールとして、日常的に使われてきました。
しかし、「言語」として認識されるどころか、「手話は国語に非ず」の政府による訓辞で、手話が禁じられた時代もありました。聾学校でも、話し手の口の動きや表情を読み取る口話法が主流で、積極的に手話を使用する学校が増えたのは、1990年代後半からです。それまで、聴覚障害者の日常生活について、私たちが知る機会はあまりなかったと言えます。
2006年12月の国連総会において、「障害者権利条約」が採択され、国際的に手話が「言語」として定義付けられました。
聴覚障害者団体など関係者の長くねばり強い運動とも相まって、日本においても、障害者基本法が改正され、手話を含む意思疎通のための手段について、選択の機会の確保が明記されました。
全国における「手話言語法の制定を求める意見書」採択は、国際的な流れと当事者の運動の中で大きく広がってきたものです。2015年10月現在の意見書採択率は、ほぼ100%に達してきています。
寝屋川市では、2013(平成25)年12月定例会において全会一致で採択されています。
手話言語条例も、鳥取県が2013年秋に制定したのを皮切りに、ことし10月現在で22自治体に上っています。大阪府下では、大東市が、この9月に「大東市こころふれあう手話言語条例」を制定しています。大東市では、検討委員会をたちあげ、当事者とも十分協議しながら、1年かけて条例を作ったとのことです。
本市においても、寝屋川市聴覚言語障害者部会など関係者の意見を十分に聞き、条例制定に踏み出してください。市の考えをお聞かせください。
また、障害者基本法第22条には、国や地方公共団体に対して、障害者に情報を提供する施設の整備や、手話通訳者などの養成および派遣など、必要な施策を講じなければならないと定められています。しかし現実はどうでしょうか。
鳥取県が昨年夏に実施した、手話に関するアンケート調査に、聴覚障害者の現状が表れていますので、ご紹介します。
音声以外のコミュニケーション対応があるかどうかという問いに対して、行政窓口や医療・介護分野では約42%が「一定程度は配慮されている」と答えています。
一方で、防災分野、バスや電車など交通分野、居住する地域では、50~60%が「まったく配慮されていない」と回答しています。
寝屋川市聴覚障害者部会の方々との懇談でも、日常生活や就労でさまざまな高い壁がある、必要な施策はまだまだ整っていないとの意見が出されました。
聴覚障害者は、外見上は健常者と変わらないため、「見えない障害」と言われます。
また、聴覚障害者と一口にいっても、家庭や教育環境、生い立ちの背景などで、文章を読み解く力、手話や口話でのコミュニケーションにもズレがあり、一人ひとり違います。
寝屋川市聴覚障害者部会の方も、条例制定によって、コミュニケーションの壁を乗り越えるための施策が進むことを期待しておられました。
全国では、鳥取県のICTを利用した遠隔手話通訳サービスや、神戸市議会のインターネット中継に手話通訳を導入する試みなど、手話言語条例に基づく環境整備が広がりをみせています。
当事者がどんな取り組みを必要としているか、聞き取り調査などで現状を把握し、条例制定とともに、環境のさらなる改善に向けた取り組みを進めていただくよう、お願いします。
市の考えをお聞かせください。
【教育・学校施設】
次に、教育に関連して、いくつかお聞きします。
一つ目は、府内統一テスト(中3チャレンジテスト)についてです。
大阪府教育委員会は、文部科学省の方針を受け、来年度から全国学力・学習状況調査(いわゆる全国学力テスト)の結果を府立高校入試の内申点に反映しないことを決めました。
しかし新たに、内申点に反映させるための、府独自のテストを実施するとしています。現在は、中学1、2年生が対象のチャレンジテストを、中学校3年生も対象に加え、中3チャレンジテストとして、来年6月下旬に実施、高校入試の内申点に反映する方針です。
この新しいテストが実施されれば、中学3年生に進級したとたん、4月に全国学力テスト、5月に中間テスト、6月に中3チャレンジテスト、6月末から7月はじめに期末テストと、子どもたちは毎月テストを受けなければなりません。
受験競争まっただ中の子どもたちを、高校入試の内申点への反映でさらに追いつめることになるのではないでしょうか。最近では、体育祭を5月に行う学校もある中で、学校行事へのしわ寄せも懸念されます。
そもそも、このチャレンジテストは、府教委の「調査の目的」にもあるように『生徒の学力を把握・分析することにより、教育施策及び教育の成果と課題を検証し、その改善を図る』もので、全国学力テストと同様、行政調査としての性格をもつものです。
その結果を内申点に反映させることは、憲法と教育関係法の立場に反します。だからこそ文科省も、「調査結果を直接または間接に入学選抜に用いることはできない」と指摘したのです。
国が指導しても、テスト結果を高校入試に反映すると府教委が決めれば、各自治体の教育委員会は従わざるを得ません。
国も現場の声も無視して強制的に実施を決めた大阪府教育委員会のあり方が問われるべきです。
教育の目的は、「人格の完成をめざす」ものです。一人ひとりの成長に見合った教育こそ、求められる大切なことではないでしょうか。
市として、府教委にテスト中止を求めていただくよう、これは強くお願いしておきます。
二つ目に、学校施設についてです。
近年、体育館トイレを含む学校トイレの洋式化が進みつつあり、うれしく思っています。
現在、子どもたちが和式トイレに接する機会が激減している中で、特に小学校低学年で、和式トイレを使いたくない、または使えない子どもが増え、数少ない洋式トイレに列をなす姿も見受けられると聞いています。当然、間に合わない子どもも毎年いるとのことです。
今後、学校内の洋式トイレを増やす計画はあるのでしょうか。お聞かせください。
トイレなどを含む学校施設改修の際、一つ強調したいのは、学校現場の声をよく聞いてほしいということです。
私が聞いた中で、こんな話がありました。
トイレ改修のあと、従来の掃除方法が、水を流す方法から、水を流さずモップで拭くドライ方式へと変わり、とまどう生徒が多く、掃除方法変更の指導に教職員もとまどったという声。
また、水道の蛇口にホースをつける際、改修によってこれまでの蛇口と形状が変わり、ホースが取り付けられず、学校の予算でやり直した…という話です。
細かいことですが、これらは、学校現場と密に連絡を取り合い、設計や計画段階から現場の意見を反映することで、改善されるものです。限られた予算の中で、各学校も努力しています。
子どもたちの教育環境をよくしたいという思いは、市も教職員もみな同じです。教育委員会と学校現場の意思疎通がスムーズにできるよう、現場が意見を上げやすい環境へと、さらなる努力を願うものです。この点について、市の見解をお聞きします。
あわせて、教職員が使用するトイレなども、改善していくべきです。
教職員のトイレの状態や、男女別の更衣室、休憩室などが設けられているか、市として実態を把握していますか?
まずは児童生徒のための改修が優先されると思いますが、日々、子どもたちと向き合いながら、多種多様な業務をこなさなければならない教職員の労働環境も、計画的に改善するよう、お願いしておきます。
市の考えをお聞かせください。
小中学校の保健室のエアコンについても、昔のクーラー機能しかない学校があると聞いています。早急に実態を把握し、計画的に、冷暖房機能のあるエアコンへと付け替えていただくよう、お願いします。市の考えをお聞かせください。
教育に関連した三つ目は、中学校給食についてです。
全員喫食の中学校給食は、担当課や学校現場の日々の努力で、導入当初からかなり改善されてきました。しかし、衛生上冷たく冷やしているおかずに対しては、「温かいものへ」と改善を求める声が出されているのも事実です。
折しも、2017(平成29)年度で、現在の委託業者2社の契約が切れます。この契約終了を節目に、思いきって温かい給食への検討を始めるべきではないでしょうか。
中学校給食導入の際立ち上げた検討委員会は、最終報告書で、こう結んでいます。
「中学校給食はいったん導入してしまえば、それで終わりというわけではありません。より良い中学校給食となるべく、導入した後も不断に努力をしていただきたいと思います」
自校調理や親子調理、センター方式など、大きな方向性を含め、業者に食缶方式での提供を依頼する方法など、あらゆる可能性を追求すべきです。
先日、四条畷市立四條畷中学校におじゃまして、生徒の給食風景をのぞかせていただきました。四条畷市は、44年前から、小中学校12校全ての給食を、給食センターで作っています。各学校には、URポットという保温食缶で給食が運ばれます。55分の昼休みのうち、給食時間の30分の中で、生徒たちは、配膳、食事、片づけを賑やかに、そして実にスピーディに行っていました。
何より印象的だったのは、教室中に給食のいい香りが漂っていたことです。そして、みんなでわいわいと配膳をしている姿が、いい雰囲気だなと思いました。
課題として、給食時間と配膳、食事指導といった教職員の負担の問題がありますが、必ず乗り越えられる課題であると考えます。
いま、大阪府下においても、中学校給食は自校やセンター方式が増えています。
ことし3月末現在で、自校調理、センター方式、親子調理方式を採用している自治体は門真市、交野市、高槻市など18市町村。今後、実施予定の6市町でも、自校調理やセンター方式、親子調理方式を導入するとしています。
デリバリー方式は、本市も含め12市町が導入していますが、そのうち大阪市は、親子調理や自校調理方式への転換を打ち出しています。
「温かいものは温かく、冷たいものは冷たく」提供する、食事として当たり前の学校給食へと、より良く変化していっていることがうかがえます。
小中連携を推進している本市として、食の分野でも9年間を見据えた小中連携を進めるべきではないでしょうか。寝屋川市の学校給食は、アレルギー対応も含め、全国に誇れる高い水準だと思っています。
食の指導にも取り組みながら、もう一歩二歩、踏み込んで、思春期まっただ中の子どもたちから「おいしい」と声が上がる給食に、時間がかかっても、一緒に改善していきたいと思っています。
今後の方向性として、市の考えをお聞かせください。
教育関連の最後に、学校司書の配置と、少人数学級の実施についてです。
学校図書の充実は、本の整理はもとより、本の楽しさを知る機会を増やすことになり、子どもの読書率アップにつながります。司書の配置をお願いします。
また、教職員や保護者の願いでもある35人学級など少人数学級を、本市でも小学校3年生以上で実施していただくよう、強くお願いしておきます。
まとめて市の考えをお聞かせください。
【学童保育の土曜開所】
次に、留守家庭児童会、いわゆる学童保育についてです。
「ゆとり教育」として進められた学校5日制の下、長らく、土曜日の学童保育はありません。
9月の文教常任委員会でも触れましたが、北河内7市で、学童保育の土曜開所をしていないのは、本市と枚方市だけです。
土曜開所を実施している市は、いずれも保護者の就労を保障するため、保護者の願いに応えて土曜日に学童を開けているのです。
土曜日の昼間、自宅に両親がいない子どもたちは、いったいどんな過ごし方をしているのでしょうか。
共働き家庭の子どもたちの、土曜日の過ごし方について、把握していること、思うことがあればお聞かせください。
共働き家庭が増えてきている現在、特に保育所を利用していた家庭にとっては、保護者が安心して働き、また介護や病気治療等を継続する上で、学童保育は不可欠の制度です。
児童福祉法を根拠に運営される学童保育は、保護者の保育に欠ける児童の安全を守る場であるとともに、児童の成長・健全育成を実践する場です。
学校が休みだから学童も休みと言われても、親として納得できないのです。
今年度、6年生までの受け入れ拡大と、お迎え時間の延長をしていただき、一保護者として大変うれしく思っています。
事業拡充の途中であり、高学年保育という点では過渡期でもありますが、環境整備など一つ一つの課題を解決しながら、土曜日開所に向けても計画的に実施するよう、前向きな検討をお願いいたします。
学童保育を土曜日に開けることついて、市としてどんな課題があると考えますか? お聞かせください。
【萱島駅バリアフリー】
最後に、萱島駅のバリアフリーについてお聞きします。
京阪萱島駅には改札が東口と西口、2カ所あります。
東口は、京都方面ホーム直通のエレベーターがあり、大阪方面ホームまでは、エスカレーターとエレベーターと両方使用して上がることができます。
しかし西口は、まず改札口に行くまでに長い階段があり、改札を入ってからはホームまでエスカレーターしか設置されていません。東口にまわるためには、道幅の狭い急な坂道を超えなければならず、高齢者や車いすの方などは大変な苦労をされています。
市民から、西口にエレベーターかエスカレーターを設置してほしいという要望が出されていることについて、市は把握しているでしょうか。お答えください。
人に優しいユニバーサルデザインの視点で考えると、公共交通を担う駅のバリアフリー化は必要不可欠と考えます。
萱島駅西口のエレベーター、エスカレーター設置についても、市民の声を受け止め、進めていただくようお願いします。今後の計画など市の考えをお聞かせください。
以上で、私からの一般質問を終わります。再質問がある場合は、自席にて行います。
ご静聴ありがとうございました。
傍聴に来ていただいたみなさん、ありがとうございました。
引き続き、市民のみなさんのご意見やご要望を議会に届け、実現に向けてがんばります。
お気軽に、ご意見、ご要望をお寄せください。