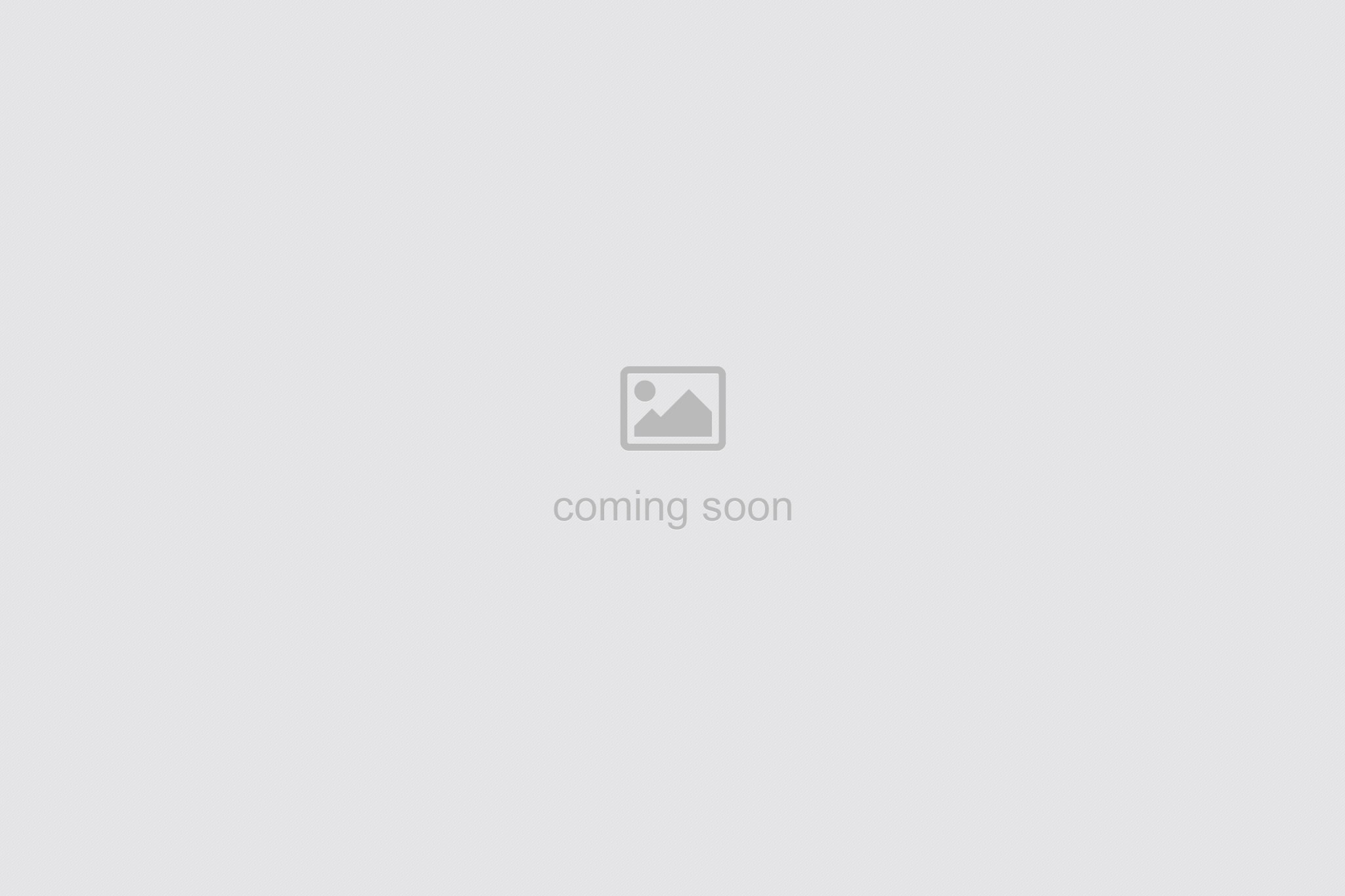はじめに同和行政についてです。
今年6月「旧同和地区」「周辺地区」自治会長10氏の連名で市議会議長あてに「要望書」だされました。
その内容は、共産党の「同和」キャンペーンによって地区住民や市民の心が傷つけられている、行政や議会において、①特別対策としての「同和行政」は存在しないこと、②「同和地区」の住民も他の地区と変わらぬ一市民であること、③行政職員、市議会議員は市民に誤解を招くような発言をしてはならないこと、の3点をふまえて、①行政機関、市議会内等で「同和」という言葉を使用しないなどの「措置」を講じること、②部落問題解決に向け、引き続き取り組みを推進すること、などとなっています。
この要望書について私の感想を述べます。
第1に事実についてかなり違うと感じる点です。要望書では、一斉地方選挙の際、日本共産党の現職議員などが「同和」「同和」と言いまくったかのように言われています。
私も現職議員の一人でしたがそんなことはありません。
私は寝屋川市において 、私たちも大いにがんばって同和事業を終結させてきたこと、同時に廃プラ処理施設の問題にみられるように、形を変えた特別扱いがつづいていることなどを指摘しました。 しかし、それは、演説などでいつも言うのではなく、時によって、また、部分的に話したというのが私の実感です。
それを「同和」「同和」と言いまくったかのように言われるのは正確ではありません。
第2に要望書で「行政依存の体質から脱却」など同和対策からの自立を述べられている点は、地区住民の自立のねがい、努力を反映したものであり、私達も前向きな評価をしたいと思います。
同時に、「要望書」は、「確かに、今まで講じられた特別対策の中には、本来不要であったものもあったかもしれません」「行政に依存し、甘えの中での対策が講じられたかも知れません」「市民の税金を無駄に使ったのかも知れません」とのべていますが、その一方で「仮にそれが罪だと言うのであれば、どうすれば償えるのでしょうか」「我々の子や孫までの罪を背負わなければいけないのでしょうか」といっているのは開き直りにも聞こえます。
いま必要なことは二度と過ちを繰り返さないという反省であり、決意の表明ではないでしょうか。
第3に行政機関、市議会内等において「同和」という言葉を使用しないなどの措置をもとめている点です。
2002年3月末、33年間にわたる国の同和特別法が終了し、「同和地区」指定が解除されました。そもそも「同和地区」という呼称は、国の同和対策事業の対象となった指定地域を表現する行政用語であり、特別法の終了とともに消滅すべきものです。
ところが、「解同」大阪府連は昨年5月、府市長会・町村長会に「同和地区」の復活を求める要望書を提出しました。これを受けて大阪府・市長会・町村長会は「『同和地区』の位置付け、呼称.問題に関する研究会」報告書(案)をまとめ、その確認をはかろうとしました。
しかし各市長から異論が出され、5月7日の市長会、9日の町村長会で保留、7月17日に開かれた大阪府市長会においても「行政が『同和地区』という呼称.を使い続けるべきかといった基本認識を、市長会として確認することは慎重であるべき」として「『同和地区』呼称問題で『確認せず』『各市町村を拘束するものではない』」ことを決定しました。
要望書で「同和」という言葉を使用しない措置を求めたことは、「部落」とか「同和」とかの垣根を取り払い、特別対策から自立し市民と自由に交流しあうことを願う、住民の思いが反映した面があると考えます。
「解放同盟」府連が同和地区や同和行政の復活を求めていることと比較すれば、肯定的に評価できると思います。
同時に私たちが「同和行政を終結させよう」とか「同和問題の真の解決を図ろう」などと言うことは、現状では当然のことです。言葉がりのよう「同和」という言葉を使うことを禁止することで問題の解決がはかれるものではありません。
この問題の解決のためには、タブーをつくったり、特定の意見を押しつけない、自由な議論、意見交換が保障されることが重要と考えます。
第4に要望書で「部落差別問題は、完全に解決していません。解決に向けて引き続き取り組みを推進すること」としている点です。
私は、特別対策の終結こそ、差別解消の一番の近道だと考えます。「特別対策としての同和行政は存在しない」としながら、引き続き取り組みを推進するとは何をさすか明確でありません。もとより、新たな特別対策につながる、ものであってはならないと考えます。
第5に、今回要望書をみて、部落問題について自由な意見交換の必要性をあらためて感じました。私達は、この条件のもとで幅広く市民と対話を進めたいと考えます。
それでは、寝屋川市の同和行政の到達点と課題について主に私の意見を述べ、若干の質問をおこないます。
寝屋川市は、大阪府下の自治体で、最も早く同和対策事業が終結しました。市議会では94年度から3年間、同和対策特別委員会が設置され、私は3年間委員長をつとめさせていただきました。
この中で、同和対策事業にかかわる資料の全面的な公開を市にもとめ、その資料を参考に委員どおしの自由な議論を進めました。また、既に同和対策事業の完了宣言をおこなっていた自治体の取り組みの調査などもおこないました。
そのつみかさねの上で、97年1月、大阪府下の自治体議会では、初めて同和対策事業の完了に向けての提言を市長に提出しました。
これは、(1)個人給付的事業 (2)環境改善事業 (3)同和地区内公共施設
(4)組織、機構の見直し、市職員の配置 (5)教育、啓発 (6)行政の主体性の確立について具体的な提案をおこなった上で
まとめでは、「本市においては、行政が主体性を確立し、同和対策事業の早期完了をめざし、一般対策事業への移行をはかるとともに同和地区内外の住民間の交流を進め、人権尊重・福祉のまちづくりを推進することがもとめられている。」と述べ同和対策事業の早期完了を市にもとめました。提言を受け、個人給付的事業の廃止、公共施設の一般開放、職員配置の見直し、「啓発」の見直しなどがすすみました。
とくに、「部落解放同盟」(以下解同という)と一体であった「同和事業促進寝屋川地区協議会」(地区協)への助成を大阪府下で最初に廃止。02年度より市の予算から同和対策費がなくなりました。また、地区協から衣がえした人権協会の補助、委託はおこなっていません。
勿論このような大きな変化は一朝一夕に実現したものではありません。不公正な同和行政の見直しをもとめる、市民の世論や運動、そのための、勇気ある斗いのつみかさねがありました。
寝屋川市でも、1960年代から同和対策事業が進められてきました。これは、地区住民の生活改善、地区外との格差是正に一定の役割をはたしました。
しかし、道路事業など肝心の環境改善が遅れたうえ、ゆりかごから墓場までの一律的な個人給付的事業、市域の2.5%の面積の地域に7つの公共施設のあいつぐ開設、市職員の事実上の優先採用など、本来の目的を逸脱し差別解消に逆行する新たな問題をつくりだしました。
また、「部落民以外は差別者」という部落排外主義にもとづく「解同」の理論を行政と教育に強制。「差別」の名で市民の批判を封じ込めるなど、市民が自由にモノを言えない状況がつくられました。
私は、1971年市職員として寝屋川市役所に就職しました。1973年(昭和48年)「48交渉」と言われましたが、「解同」寝屋川支部が連日対市交渉をおこない、当時190億円にのぼる同和対策長期計画を市は認めました。
このとき、私は福祉事務所の職員でしたが、当時の所長や課長が交渉のあと次々と病休をとり、不在となる姿をまのあたりにしました。
また、1979年11月、8日間連続で解同が対市交渉をおこないました。この交渉では、市職員への旧同和地区住民の優先採用、他の自治体に優先採用を働きかけることまでが公式の回答として約束されました。
そして、地区内に総合病院やプールを建設することまで約束されました。
またこの頃、解同は係争中の刑事事件である狭山事件を公教育の場にもちこみ、子どもにゼッケンを付けさせて集団登校させる、授業をボイコットさせることなどをおこないました。
ある旧同和校では、「狭山ゼッケン登校」のときに、教頭が集団登校の先頭を歩いたり、学校の校門に「狭山差別裁判糾弾」と書いた看板がかかげられたりしました。
「解同」の蛮行は、全国に広がりました。特に1974年11月22日、兵庫県八鹿高校教職員への凄惨な集団リンチ事件がおこされました。56名の重軽傷という、日本の教育史上前例のない学校現場における凶悪な集団暴力事件が大きな問題となりました。
また、大阪では羽曳野市に誕生した日本共産党員市長、津田市政が、同和行政の大幅な見直しに着手したことに対して、連日市庁舎を解同の動員部隊が包囲し圧力をかけました。この2つの問題は、いずれも関係者や住民の斗いの中で「解同」の策動をうちやぶり、逆に「解同」が社会的にも孤立を深めることになりました。
「解同」の暴力や利権あさりなどの無法行為がくり返されてきたのには、3つの要因がありました。それは、(1)違法行為、犯罪行為の取締・検挙の任にあたるべき警察がこれを放任し黙認してきたこと(2)社会的不法行為を報道すべきマスコミが全くその報道をしなかったこと(3)多くの自治体の首長、職員が、その職責を放棄して「解同」の圧力に屈服し、さらには行政を歪めたことがあげられます。
寝屋川市において、日本共産党は「解同」の暴力的糾弾、利権あさりなど徹底追及。これに追随する主体性を放棄した行政の姿勢の抜本的見直しをもとめて奮闘し、市議会では毎議会ごとにこの問題をとりあげました。
1976年「解同」の差別デッチあげ事件に反撃するたたかいの中で、同和地区内の住民を中心に全国部落解放運動連合会寝屋川支部が結成されました。また、「民主主義と教育を守り、公正民主的な同和行政を要求する寝屋川市民会議」が結成されるなど地区内外の住民から、同和行政終結もとめ、市民への宣伝や行政への申し入れなどが進められました。
「解同は」このような市民と日本共産党の活動にたいし、「差別者」呼ばわりして攻撃、行政もこれにいいなりの姿勢を示しました。
市職員労働組合や市教職員組合が発行した冊子などを差別と威かくし、行政をつめ、行政は屈服する姿勢を示しました。
市民と日本共産党は不当な攻撃をはねのけ、市民の意見が通るあたりまえの市政にすることをうったえました。
とくに、1990年大阪府が行った同和地区実態調査の結果、寝屋川市では、約1400世帯の地区で約750人が公務員であるという事実を示し、格差が解消している中、これ以上の特別扱いは、差別解消に逆行することを明らかにしました。
市議会では、目本共産党以外の議員の方からも同和行政の見直しを主張する質問がされていきました。このようなとりくみの結果、寝屋川市では、府下に先がけて、同和対策事業を終結させるという重要な変化をつくりだしました。
勿論、同和対策事業の終結には、地区住民の合意が不可欠でした。「特別対策にたよらない」地区住民の意識が根底にあったことは重要です。
市民の同和行政終結をもとめる声が高まる中、「解同」も手直しを余儀なくされました。
しかし、基本的な点で反省しているとは言えません。大阪府では「解同」の隠れ蓑である「府同促」「地区協」が人権協会に衣がえ、「人権」の名により「同和」の特別扱いがつづけられています。
「解同」のもとめに応じて、大阪府が各市町村に同和行政の復活をもとめていることは重大です。
寝屋川市では・「解同」自体が表立った活動はせず「同和」という言葉を使っていませんが、「形を変えた特別扱い」を行政が一体となってすすめています。
その例が2つの廃プラ処理施設の建設です。市街化調整区域に本来建設できないものを、大阪府・寝屋川市が特別扱いして、この事業をすすめました。
これは、同和対策事業としてすすめていた、クリーンセンター第2事業所を廃止する代わりに「解同」の意向に沿って寝屋川市が、特別にすすめたものです。
寝屋川市は、市立教育センターのすぐ南側にあったクリーンセンター第2事業所で、同和対策の名の下に、特別対策を長年続けてきました。旧同和地区内の廃品回収業者が持ち込むごみは全て寝屋川市が無料で処理し、年間2億円をこえる予算が投入されてきました。ごみの中には本来企業が処理すべき産業廃棄物が多く含まれ、適正処理困難物として市が収集しない廃タイヤも大量に含まれていました。
このような市民合意の得られない特別扱いはやめるよう、私たち日本共産党は再三議会で取り上げてきました。また、他の会派の皆さんからも見直しを求める声が上がり、01年3月にこの施設はようやく廃止されるにいたりました。
北河内4市リサイクル施設事業の推進は、ちょうどこの時期、01年3月議会での市長市政運営方針で初めて明らかにされました。この際、施設の場所は寝屋川市内にすること、基本構想の策定費用も他市に先行し寝屋川市が予算を計上するなど、寝屋川市が先導し急いでおこないました。
しかも、市議会の質疑で市の担当部は「寝屋川資源再生業協同組合を何らかの形で新しい施設の運営に参画させたい」という答弁までおこないました。「資源再生業協同組合は、部落解放同盟の要求者組合であり、特定の業者の参画を前提にすることは許されない」と私たちが議会で追及し、「業者選定は白紙にする」と市理事者は言わざるを得ませんでしたが、クリーンセンター第2事業所廃止の代わりに寝屋川市が特定業者の参画を前提に事業立ち上げを考えていたことは事実であり、出発点から重大な問題点を持っていました。
寝屋川市の異例の対応の前提には、資源再生業協同組合からの強い働きかけがありました。北河内各市に組合幹部が回り、広域的に取り組むことや、仕事を保障することを要求しました。リサイクル施設をつくることも、広域的に取り組むことも何もまだ決まっていない段階で、特定の民間業者が営業活動をすること自体、通常考えられず、行政の主体性や公平性を損なうものでありました。
しかも、北河内4市の今回の施設のすぐ前の民間施設は、寝屋川資源再生業協同組合から名称は変わっていますが、東部大阪リサイクル事業協同組合がかかわっています。
現在寝屋川市がクリーンセンターでおこなっている廃プラ処理施設も7年間随意契約で、東部大阪リサイクル事業協同組合に優先して委託するなど、特別扱いがつづいています。
廃プラ処理施設については、市民がどんなに反対しても、行政がそれを無視してすすめる、その根底に形を変えた特別対策があるからと感じます。この見直しが強くもとめられています。
さて、旧同和地区と地区外との格差は解消し、結婚や就職問題でも部落問題は基本的に解決しています。仮に旧同和地区にたいする誤った認識や偏見から差別事象がおきても、それがうけられない地域社会か形成されてきており、この点からも歴史的問題としての部落問題は基本的に解消しています。
むしろ問題なのは、この間の不公正乱脈な同和行政や「解同」の誤った運動が、旧同和地区への新たな偏見を生み、重大なマイナス要因をつくったことです。
いまこそ、「同和」「部落」等という垣根をなくして一般市民として融合していくことが重要となっています。
そこで質問します。
第1は、02年3月、国の特別法が終了し「同和地区」指定が解除されました。法的にも同和地区は存在しません。
寝屋川市でも混住や住民の地区外への転出等で地域も大きく変化しています。経済的な面で目に見えた格差はなくなりました。住民もいつまでも部落とか同和地区などと言われることを望んでいません。このような状況をふまえ、今日寝屋川市に同和地区は存在しないと考えますがいかがですか。
私はこのことを出発点に寝屋川市として同和行政の全面的な終結宣言をおこない、形を変えた特別対策の一掃することをもとめます。また、大阪府市長会で確認はされませんでしたが同和行政復活につながるうごきに一切加担しないことをもとめますがいかがですか。
第2に、いわゆる、人権条例の制定についてです。大阪府下の自治体で、このような条例を制定していないのは、寝屋川市のみと聞きます。「解同」大阪府連は、寝屋川市が人権条例を制定することを活動方針の中にかかげていると聞きます。
人権条例は、当初は「部落差別撤廃条例」などとしていたものが、市民の批判により「人権」の名に衣がえしたものです。この条例の制定を一貫して主張しているのは「部落解放同盟」です。同和行政の継続、特別扱いの継続を進めることが条例制定のねらいです。
府下で旧同和地区が存在しない自治体でも人権条例が制定されていますが、制定以降「解同」幹部を講師に研修会を持ったり「解同」府連と自治体との交渉がもたれるなどの動きがでています。
解同が推進し特別対策の継続や復活につながる、人権条例制定はやめるべきと考えますがいかがですか。
第3に、部落問題の解決のためには、市民の自由な意見交換が必要です。部落問題に対する市民の自由な意見表明を保障しながら理解を広げていくことが必要と考えます、がいかがですか。
第4に、具体的な問題として、旧同和地区内の市営住宅の一般募集の具体化についてです。97年1月の同和対策特別委員会提言でも早期の実施をもとめていますが、未だに実施されていません。なぜしないのですか。
以上4点について答弁をもとめます。
今年6月「旧同和地区」「周辺地区」自治会長10氏の連名で市議会議長あてに「要望書」だされました。
その内容は、共産党の「同和」キャンペーンによって地区住民や市民の心が傷つけられている、行政や議会において、①特別対策としての「同和行政」は存在しないこと、②「同和地区」の住民も他の地区と変わらぬ一市民であること、③行政職員、市議会議員は市民に誤解を招くような発言をしてはならないこと、の3点をふまえて、①行政機関、市議会内等で「同和」という言葉を使用しないなどの「措置」を講じること、②部落問題解決に向け、引き続き取り組みを推進すること、などとなっています。
この要望書について私の感想を述べます。
第1に事実についてかなり違うと感じる点です。要望書では、一斉地方選挙の際、日本共産党の現職議員などが「同和」「同和」と言いまくったかのように言われています。
私も現職議員の一人でしたがそんなことはありません。
私は寝屋川市において 、私たちも大いにがんばって同和事業を終結させてきたこと、同時に廃プラ処理施設の問題にみられるように、形を変えた特別扱いがつづいていることなどを指摘しました。 しかし、それは、演説などでいつも言うのではなく、時によって、また、部分的に話したというのが私の実感です。
それを「同和」「同和」と言いまくったかのように言われるのは正確ではありません。
第2に要望書で「行政依存の体質から脱却」など同和対策からの自立を述べられている点は、地区住民の自立のねがい、努力を反映したものであり、私達も前向きな評価をしたいと思います。
同時に、「要望書」は、「確かに、今まで講じられた特別対策の中には、本来不要であったものもあったかもしれません」「行政に依存し、甘えの中での対策が講じられたかも知れません」「市民の税金を無駄に使ったのかも知れません」とのべていますが、その一方で「仮にそれが罪だと言うのであれば、どうすれば償えるのでしょうか」「我々の子や孫までの罪を背負わなければいけないのでしょうか」といっているのは開き直りにも聞こえます。
いま必要なことは二度と過ちを繰り返さないという反省であり、決意の表明ではないでしょうか。
第3に行政機関、市議会内等において「同和」という言葉を使用しないなどの措置をもとめている点です。
2002年3月末、33年間にわたる国の同和特別法が終了し、「同和地区」指定が解除されました。そもそも「同和地区」という呼称は、国の同和対策事業の対象となった指定地域を表現する行政用語であり、特別法の終了とともに消滅すべきものです。
ところが、「解同」大阪府連は昨年5月、府市長会・町村長会に「同和地区」の復活を求める要望書を提出しました。これを受けて大阪府・市長会・町村長会は「『同和地区』の位置付け、呼称.問題に関する研究会」報告書(案)をまとめ、その確認をはかろうとしました。
しかし各市長から異論が出され、5月7日の市長会、9日の町村長会で保留、7月17日に開かれた大阪府市長会においても「行政が『同和地区』という呼称.を使い続けるべきかといった基本認識を、市長会として確認することは慎重であるべき」として「『同和地区』呼称問題で『確認せず』『各市町村を拘束するものではない』」ことを決定しました。
要望書で「同和」という言葉を使用しない措置を求めたことは、「部落」とか「同和」とかの垣根を取り払い、特別対策から自立し市民と自由に交流しあうことを願う、住民の思いが反映した面があると考えます。
「解放同盟」府連が同和地区や同和行政の復活を求めていることと比較すれば、肯定的に評価できると思います。
同時に私たちが「同和行政を終結させよう」とか「同和問題の真の解決を図ろう」などと言うことは、現状では当然のことです。言葉がりのよう「同和」という言葉を使うことを禁止することで問題の解決がはかれるものではありません。
この問題の解決のためには、タブーをつくったり、特定の意見を押しつけない、自由な議論、意見交換が保障されることが重要と考えます。
第4に要望書で「部落差別問題は、完全に解決していません。解決に向けて引き続き取り組みを推進すること」としている点です。
私は、特別対策の終結こそ、差別解消の一番の近道だと考えます。「特別対策としての同和行政は存在しない」としながら、引き続き取り組みを推進するとは何をさすか明確でありません。もとより、新たな特別対策につながる、ものであってはならないと考えます。
第5に、今回要望書をみて、部落問題について自由な意見交換の必要性をあらためて感じました。私達は、この条件のもとで幅広く市民と対話を進めたいと考えます。
それでは、寝屋川市の同和行政の到達点と課題について主に私の意見を述べ、若干の質問をおこないます。
寝屋川市は、大阪府下の自治体で、最も早く同和対策事業が終結しました。市議会では94年度から3年間、同和対策特別委員会が設置され、私は3年間委員長をつとめさせていただきました。
この中で、同和対策事業にかかわる資料の全面的な公開を市にもとめ、その資料を参考に委員どおしの自由な議論を進めました。また、既に同和対策事業の完了宣言をおこなっていた自治体の取り組みの調査などもおこないました。
そのつみかさねの上で、97年1月、大阪府下の自治体議会では、初めて同和対策事業の完了に向けての提言を市長に提出しました。
これは、(1)個人給付的事業 (2)環境改善事業 (3)同和地区内公共施設
(4)組織、機構の見直し、市職員の配置 (5)教育、啓発 (6)行政の主体性の確立について具体的な提案をおこなった上で
まとめでは、「本市においては、行政が主体性を確立し、同和対策事業の早期完了をめざし、一般対策事業への移行をはかるとともに同和地区内外の住民間の交流を進め、人権尊重・福祉のまちづくりを推進することがもとめられている。」と述べ同和対策事業の早期完了を市にもとめました。提言を受け、個人給付的事業の廃止、公共施設の一般開放、職員配置の見直し、「啓発」の見直しなどがすすみました。
とくに、「部落解放同盟」(以下解同という)と一体であった「同和事業促進寝屋川地区協議会」(地区協)への助成を大阪府下で最初に廃止。02年度より市の予算から同和対策費がなくなりました。また、地区協から衣がえした人権協会の補助、委託はおこなっていません。
勿論このような大きな変化は一朝一夕に実現したものではありません。不公正な同和行政の見直しをもとめる、市民の世論や運動、そのための、勇気ある斗いのつみかさねがありました。
寝屋川市でも、1960年代から同和対策事業が進められてきました。これは、地区住民の生活改善、地区外との格差是正に一定の役割をはたしました。
しかし、道路事業など肝心の環境改善が遅れたうえ、ゆりかごから墓場までの一律的な個人給付的事業、市域の2.5%の面積の地域に7つの公共施設のあいつぐ開設、市職員の事実上の優先採用など、本来の目的を逸脱し差別解消に逆行する新たな問題をつくりだしました。
また、「部落民以外は差別者」という部落排外主義にもとづく「解同」の理論を行政と教育に強制。「差別」の名で市民の批判を封じ込めるなど、市民が自由にモノを言えない状況がつくられました。
私は、1971年市職員として寝屋川市役所に就職しました。1973年(昭和48年)「48交渉」と言われましたが、「解同」寝屋川支部が連日対市交渉をおこない、当時190億円にのぼる同和対策長期計画を市は認めました。
このとき、私は福祉事務所の職員でしたが、当時の所長や課長が交渉のあと次々と病休をとり、不在となる姿をまのあたりにしました。
また、1979年11月、8日間連続で解同が対市交渉をおこないました。この交渉では、市職員への旧同和地区住民の優先採用、他の自治体に優先採用を働きかけることまでが公式の回答として約束されました。
そして、地区内に総合病院やプールを建設することまで約束されました。
またこの頃、解同は係争中の刑事事件である狭山事件を公教育の場にもちこみ、子どもにゼッケンを付けさせて集団登校させる、授業をボイコットさせることなどをおこないました。
ある旧同和校では、「狭山ゼッケン登校」のときに、教頭が集団登校の先頭を歩いたり、学校の校門に「狭山差別裁判糾弾」と書いた看板がかかげられたりしました。
「解同」の蛮行は、全国に広がりました。特に1974年11月22日、兵庫県八鹿高校教職員への凄惨な集団リンチ事件がおこされました。56名の重軽傷という、日本の教育史上前例のない学校現場における凶悪な集団暴力事件が大きな問題となりました。
また、大阪では羽曳野市に誕生した日本共産党員市長、津田市政が、同和行政の大幅な見直しに着手したことに対して、連日市庁舎を解同の動員部隊が包囲し圧力をかけました。この2つの問題は、いずれも関係者や住民の斗いの中で「解同」の策動をうちやぶり、逆に「解同」が社会的にも孤立を深めることになりました。
「解同」の暴力や利権あさりなどの無法行為がくり返されてきたのには、3つの要因がありました。それは、(1)違法行為、犯罪行為の取締・検挙の任にあたるべき警察がこれを放任し黙認してきたこと(2)社会的不法行為を報道すべきマスコミが全くその報道をしなかったこと(3)多くの自治体の首長、職員が、その職責を放棄して「解同」の圧力に屈服し、さらには行政を歪めたことがあげられます。
寝屋川市において、日本共産党は「解同」の暴力的糾弾、利権あさりなど徹底追及。これに追随する主体性を放棄した行政の姿勢の抜本的見直しをもとめて奮闘し、市議会では毎議会ごとにこの問題をとりあげました。
1976年「解同」の差別デッチあげ事件に反撃するたたかいの中で、同和地区内の住民を中心に全国部落解放運動連合会寝屋川支部が結成されました。また、「民主主義と教育を守り、公正民主的な同和行政を要求する寝屋川市民会議」が結成されるなど地区内外の住民から、同和行政終結もとめ、市民への宣伝や行政への申し入れなどが進められました。
「解同は」このような市民と日本共産党の活動にたいし、「差別者」呼ばわりして攻撃、行政もこれにいいなりの姿勢を示しました。
市職員労働組合や市教職員組合が発行した冊子などを差別と威かくし、行政をつめ、行政は屈服する姿勢を示しました。
市民と日本共産党は不当な攻撃をはねのけ、市民の意見が通るあたりまえの市政にすることをうったえました。
とくに、1990年大阪府が行った同和地区実態調査の結果、寝屋川市では、約1400世帯の地区で約750人が公務員であるという事実を示し、格差が解消している中、これ以上の特別扱いは、差別解消に逆行することを明らかにしました。
市議会では、目本共産党以外の議員の方からも同和行政の見直しを主張する質問がされていきました。このようなとりくみの結果、寝屋川市では、府下に先がけて、同和対策事業を終結させるという重要な変化をつくりだしました。
勿論、同和対策事業の終結には、地区住民の合意が不可欠でした。「特別対策にたよらない」地区住民の意識が根底にあったことは重要です。
市民の同和行政終結をもとめる声が高まる中、「解同」も手直しを余儀なくされました。
しかし、基本的な点で反省しているとは言えません。大阪府では「解同」の隠れ蓑である「府同促」「地区協」が人権協会に衣がえ、「人権」の名により「同和」の特別扱いがつづけられています。
「解同」のもとめに応じて、大阪府が各市町村に同和行政の復活をもとめていることは重大です。
寝屋川市では・「解同」自体が表立った活動はせず「同和」という言葉を使っていませんが、「形を変えた特別扱い」を行政が一体となってすすめています。
その例が2つの廃プラ処理施設の建設です。市街化調整区域に本来建設できないものを、大阪府・寝屋川市が特別扱いして、この事業をすすめました。
これは、同和対策事業としてすすめていた、クリーンセンター第2事業所を廃止する代わりに「解同」の意向に沿って寝屋川市が、特別にすすめたものです。
寝屋川市は、市立教育センターのすぐ南側にあったクリーンセンター第2事業所で、同和対策の名の下に、特別対策を長年続けてきました。旧同和地区内の廃品回収業者が持ち込むごみは全て寝屋川市が無料で処理し、年間2億円をこえる予算が投入されてきました。ごみの中には本来企業が処理すべき産業廃棄物が多く含まれ、適正処理困難物として市が収集しない廃タイヤも大量に含まれていました。
このような市民合意の得られない特別扱いはやめるよう、私たち日本共産党は再三議会で取り上げてきました。また、他の会派の皆さんからも見直しを求める声が上がり、01年3月にこの施設はようやく廃止されるにいたりました。
北河内4市リサイクル施設事業の推進は、ちょうどこの時期、01年3月議会での市長市政運営方針で初めて明らかにされました。この際、施設の場所は寝屋川市内にすること、基本構想の策定費用も他市に先行し寝屋川市が予算を計上するなど、寝屋川市が先導し急いでおこないました。
しかも、市議会の質疑で市の担当部は「寝屋川資源再生業協同組合を何らかの形で新しい施設の運営に参画させたい」という答弁までおこないました。「資源再生業協同組合は、部落解放同盟の要求者組合であり、特定の業者の参画を前提にすることは許されない」と私たちが議会で追及し、「業者選定は白紙にする」と市理事者は言わざるを得ませんでしたが、クリーンセンター第2事業所廃止の代わりに寝屋川市が特定業者の参画を前提に事業立ち上げを考えていたことは事実であり、出発点から重大な問題点を持っていました。
寝屋川市の異例の対応の前提には、資源再生業協同組合からの強い働きかけがありました。北河内各市に組合幹部が回り、広域的に取り組むことや、仕事を保障することを要求しました。リサイクル施設をつくることも、広域的に取り組むことも何もまだ決まっていない段階で、特定の民間業者が営業活動をすること自体、通常考えられず、行政の主体性や公平性を損なうものでありました。
しかも、北河内4市の今回の施設のすぐ前の民間施設は、寝屋川資源再生業協同組合から名称は変わっていますが、東部大阪リサイクル事業協同組合がかかわっています。
現在寝屋川市がクリーンセンターでおこなっている廃プラ処理施設も7年間随意契約で、東部大阪リサイクル事業協同組合に優先して委託するなど、特別扱いがつづいています。
廃プラ処理施設については、市民がどんなに反対しても、行政がそれを無視してすすめる、その根底に形を変えた特別対策があるからと感じます。この見直しが強くもとめられています。
さて、旧同和地区と地区外との格差は解消し、結婚や就職問題でも部落問題は基本的に解決しています。仮に旧同和地区にたいする誤った認識や偏見から差別事象がおきても、それがうけられない地域社会か形成されてきており、この点からも歴史的問題としての部落問題は基本的に解消しています。
むしろ問題なのは、この間の不公正乱脈な同和行政や「解同」の誤った運動が、旧同和地区への新たな偏見を生み、重大なマイナス要因をつくったことです。
いまこそ、「同和」「部落」等という垣根をなくして一般市民として融合していくことが重要となっています。
そこで質問します。
第1は、02年3月、国の特別法が終了し「同和地区」指定が解除されました。法的にも同和地区は存在しません。
寝屋川市でも混住や住民の地区外への転出等で地域も大きく変化しています。経済的な面で目に見えた格差はなくなりました。住民もいつまでも部落とか同和地区などと言われることを望んでいません。このような状況をふまえ、今日寝屋川市に同和地区は存在しないと考えますがいかがですか。
私はこのことを出発点に寝屋川市として同和行政の全面的な終結宣言をおこない、形を変えた特別対策の一掃することをもとめます。また、大阪府市長会で確認はされませんでしたが同和行政復活につながるうごきに一切加担しないことをもとめますがいかがですか。
第2に、いわゆる、人権条例の制定についてです。大阪府下の自治体で、このような条例を制定していないのは、寝屋川市のみと聞きます。「解同」大阪府連は、寝屋川市が人権条例を制定することを活動方針の中にかかげていると聞きます。
人権条例は、当初は「部落差別撤廃条例」などとしていたものが、市民の批判により「人権」の名に衣がえしたものです。この条例の制定を一貫して主張しているのは「部落解放同盟」です。同和行政の継続、特別扱いの継続を進めることが条例制定のねらいです。
府下で旧同和地区が存在しない自治体でも人権条例が制定されていますが、制定以降「解同」幹部を講師に研修会を持ったり「解同」府連と自治体との交渉がもたれるなどの動きがでています。
解同が推進し特別対策の継続や復活につながる、人権条例制定はやめるべきと考えますがいかがですか。
第3に、部落問題の解決のためには、市民の自由な意見交換が必要です。部落問題に対する市民の自由な意見表明を保障しながら理解を広げていくことが必要と考えます、がいかがですか。
第4に、具体的な問題として、旧同和地区内の市営住宅の一般募集の具体化についてです。97年1月の同和対策特別委員会提言でも早期の実施をもとめていますが、未だに実施されていません。なぜしないのですか。
以上4点について答弁をもとめます。