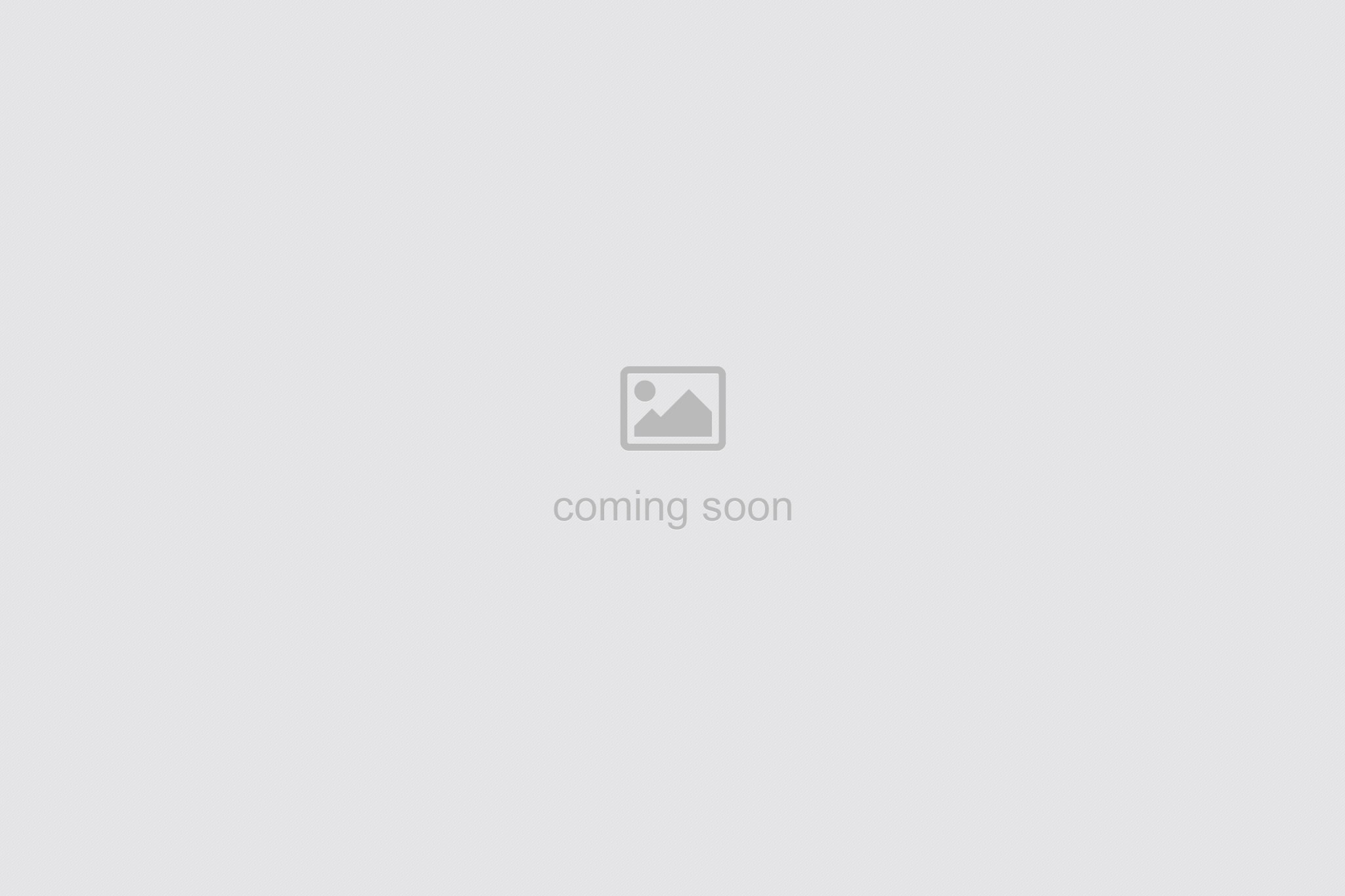今年の9月、日本共産党国会議員団が実施しました「第2回障害者自立支援法の影響調査」の結果報告でも、顕著に表れています。負担増(給食費を含む)では最も多いのが月額「1~2万円未満」で41.6%、「1万円未満」で38.4%、「2~3万円」が11.4%、「3万円以上」となった人も6.3%あり、月額で1万円以上の負担増が6割を占めています。障害年金とわずかな工賃収入の多くが、定率1割負担という過大といわざるをえない負担による支払いで消えてしまうと厳しい実態にあります。負担増を理由に施設等のサービス利用を中止した人、日数を減らした人、ともに増え、「利用を中止した」人の出現率は、1.4%で、昨年6月「第1回の調査」時の1.5倍に増加しています。また、政府の特別対策については「2年間限りの措置」「応益負担はそのままだから」と答え、応益負担については「廃止すべき」が9割近くと圧倒的に多くの回答が寄せられています。
事業所への影響については、事業所収入の減収幅は、自立支援法実施前にくらべて「1割台と2割台」で62%あり、「3割以上の減収」の事業所も1割近くあるといいます。 収入減の対応としては、「利用者サービス関係」では土・祝日の開所、利用者が楽しみにしている一泊旅行の廃止などの対応をとらざるをえなくなっている。職員の労働条件関係は、「賃金の切り下げや一時金カット」、「正規職員から非正規職員やパートに切り替え」など労働条件の切り下げを余儀なくされ、深刻な事態に直面している実情が浮き彫りになりました。
全国での実態調査で明らかになっているのと同じように、市内の障害者通所施設に通う障害者の家族の方は、「子どもが通っている施設では、職員の給料も引き下げられている。
子どもの働いた工賃単価がこれまで1日100円が50円に引き下げられた。働くといっても給料はごくわずか。障害者は仕事にいくのにお金を払わなあかんということはおかしい」と怒りの声で話されました。また、2人の障害のある子どもさんをかかえておられるお母さんは、「これまで2人の障害児を一生懸命育ててきた。3年前、支援費制度ができ障害者支援が前進したとほっとしてこれからも頑張っていこうと希望がわいてきたところだったのに、自立支援法になり利用料の負担は2人分だし負担が重い。結局お金の負担を減らそうと思えば、休日などは、父母が子どもを1人づつそれぞれ連れて出かけることになり身体の負担が重くなった。こんな事がいつまで続くのかと思うと将来の展望が見えなくなってくる」と涙声でお話ししてくださいました。
市民である障害者とその家族、事業所に負担を押しつけ、希望を奪うような制度は抜本的な見直しが必要だと考えます。いま、障害者自立支援法見直しをうたった与党プロジェクトチームの最終とりまとめが注目されていますが、この制度のおおもとの応益負担(定率1割負担)の理念を変えるところまでは言及していません。
そこでお聞きします。
1.応益負担の撤回、また、事業所への日割り計算方式、報酬単価の引き下げの見直しを国へ意見書をあげるなど強くもとめること。
2.国が抜本的な見直しをするまでの間、市独自の利用料負担の減免制度をつくること。
3.事業者・施設など安定的な施設運営のために市独自の補助制度をつくること。
4.地域活動支援センター事業の運営補助については現在の小規模通所授産施設に出ている補助水準を基本にして補助額とすること。
以上4点について見解をお聞きします。
事業所への影響については、事業所収入の減収幅は、自立支援法実施前にくらべて「1割台と2割台」で62%あり、「3割以上の減収」の事業所も1割近くあるといいます。 収入減の対応としては、「利用者サービス関係」では土・祝日の開所、利用者が楽しみにしている一泊旅行の廃止などの対応をとらざるをえなくなっている。職員の労働条件関係は、「賃金の切り下げや一時金カット」、「正規職員から非正規職員やパートに切り替え」など労働条件の切り下げを余儀なくされ、深刻な事態に直面している実情が浮き彫りになりました。
全国での実態調査で明らかになっているのと同じように、市内の障害者通所施設に通う障害者の家族の方は、「子どもが通っている施設では、職員の給料も引き下げられている。
子どもの働いた工賃単価がこれまで1日100円が50円に引き下げられた。働くといっても給料はごくわずか。障害者は仕事にいくのにお金を払わなあかんということはおかしい」と怒りの声で話されました。また、2人の障害のある子どもさんをかかえておられるお母さんは、「これまで2人の障害児を一生懸命育ててきた。3年前、支援費制度ができ障害者支援が前進したとほっとしてこれからも頑張っていこうと希望がわいてきたところだったのに、自立支援法になり利用料の負担は2人分だし負担が重い。結局お金の負担を減らそうと思えば、休日などは、父母が子どもを1人づつそれぞれ連れて出かけることになり身体の負担が重くなった。こんな事がいつまで続くのかと思うと将来の展望が見えなくなってくる」と涙声でお話ししてくださいました。
市民である障害者とその家族、事業所に負担を押しつけ、希望を奪うような制度は抜本的な見直しが必要だと考えます。いま、障害者自立支援法見直しをうたった与党プロジェクトチームの最終とりまとめが注目されていますが、この制度のおおもとの応益負担(定率1割負担)の理念を変えるところまでは言及していません。
そこでお聞きします。
1.応益負担の撤回、また、事業所への日割り計算方式、報酬単価の引き下げの見直しを国へ意見書をあげるなど強くもとめること。
2.国が抜本的な見直しをするまでの間、市独自の利用料負担の減免制度をつくること。
3.事業者・施設など安定的な施設運営のために市独自の補助制度をつくること。
4.地域活動支援センター事業の運営補助については現在の小規模通所授産施設に出ている補助水準を基本にして補助額とすること。
以上4点について見解をお聞きします。
次に.障害者長期計画についてです
障害者長期計画推進委員会が開催され、とりまとめの「障害者支援の推進方向」の骨子
(案)が出されました。寝屋川市はかって、あかつき・ひばり園やすばる・北斗福祉作業所など他市に誇れる障害児者施設をつくり、質の高い実践を積み上げてきました。この経験を障害者長期計画に盛り込むことができていると評価をしています。
このことは、現在の長期計画推進委員会にも引き継がれていると思います。委員の方は、よりよい計画をつくりたい。意見をあげていきたいと思って出席されています。しかし、委員の中から「推進委員会では、事務局からの説明等に時間をとり、委員が十分意見を述べるためには時間が足りない」との声が寄せられています。
そこでお聞きしますが、推進委員会の開催時間や回数を増やし委員からの意見を十分計画に反映すること。より、障害者の実態を反映した数値目標を設定し障害福祉計画との整合性をはかること。見解をお聞きします。
次に、障害者長期計画推進委員会から「障害者支援の推進方向」の骨子(案)が出されました。その中で、生活介護事業等の推進の項目は「重度の障害のある人などが介護を受けながら創作活動や生産的活動ができる日中活動の場として生活介護事業などを推進するよう事業所の確保を図り、そのための方策として小規模通所授産施設を含め、通所施設を運営する事業者が新体系の事業にスムーズに移行できるように推進する」と記述されています。
ところが市内の小規模通所授産施設からは「小規模通所授産施設は、これまで、無認可作業所の認可促進のために、大阪府が無認可作業所への補助金を廃止するといってきた。認可のための基本財産をやっとの思いで準備し、小規模通所授産施設移行した。しかし、小規模通所授産施設へ移行しても運営費は増えず、反対に運営は厳しくなるばかりです。「このままでは認可した施設を閉鎖しなければならない状況になる」と切実に訴えておられます。
そこで、お聞きをしますが、今でも運営が大変な小規模通所授産施設の新体系事業にスムーズに移行する具体化をどのようにはかっていくのかお聞きかせください。また、小規模通所授産施設への支援のための補助金の増額をもとめます。見解をお聞きします。
次に、あかつき・ひばり・第2ひばり園についてです。
これまで、あかつき・ひばり・第2ひばり園の果たす役割は、障害がある子どもとその親が専門の指導を受けることで、我が子の障害を受け入れ、発達の可能性を見いだし、障害がある子と人生を歩むためのいわばスタートの場所であると、私の経験、体験をもとに、あかつき・ひばり・第2ひばり園の役割の重大さ訴えてきました。
ところが、障害者自立支援法は、障害乳幼児の分野まで応益負担(低率1割負担)を導入しました。
障害乳幼児施設を利用する世代は、①世帯年齢が若く、所得も低い。②施設利用に際して母子通園がもとめられ、母親の就労が困難である。③兄弟がいる場合訓練中は保育所などに預けなくてはならず、その費用が必要。④障害ゆえの専門病院への通院の交通費。⑤補装具など成長に合わせて取り替えなければならない。など負担が重くなる要因が種々あります。負担は重くなっても障害を少しでも軽減したい、発達していく力をもっともっとつけてやりたい、何よりも子どもの笑顔がみたい。という親の気持ちが、生活が苦しくなっても利用をへらしたりせずに頑張って通園させているのだと思います。 このような、障害乳幼児の保護者負担の重さが理解できたからこそ、給食費の負担軽減をはかったのではありませんか。
国の「特別対策」利用料の上限額が引き下げら、給食費の負担軽減措置がとられています。しかし、それでも、利用料負担がこれまでの5倍にも増えた世帯があります。
市の給食費軽減策は、特別対策で負担額は減っているはずです。この際、障害児保護者負担を軽減させ障害児の子育て支援するお考えはありませんか。お聞きをいたします。
あかつき・ひばり・第2ひばり園は障害が発見され、早い段階で専門の訓練・療育を受けるための重要な施設です。専門的な訓練の方法は保護者も学び、家庭でもできる限り訓練をおこなうことでより障害の軽減、進行を止めることが可能になります。 とりわけ、言語聴覚士は、麻痺で発声できない、動きにくい口や舌など訓練することでしゃべれることができるようにする訓練士で特殊な知識や経験が必要な専門職です。
府下でもまだ言語聴覚士の人数も少なく貴重な人材です。現在、あかつき・ひばり園の言語聴覚士は非常勤雇用となっています。不安定な身分保障では力も発揮しにくいし、他の施設等で正職員で雇用する場ができれば、職場を変わられることにもなりまねません。非常勤雇用から正職員として身分保障を行うことが、全国的にも非常に優れた実践をしている、あかつき・ひばり・第2ひばり園の質を低下させない保障になると考えますがいかがでしょうか。
また、今後、作業療法士や理学療法士などの専門職も定年で退職されます。専門職補充については空白が生じないように、計画的な配置をおこなうことが重要です。
いかがでしょうか。見解をお聞きします。
次に、すばる・北斗福祉作業所についてお聞きします。
すばる・北斗福祉作業所が指定管理者になって2年目、法人・保護者・職員の運営努力によって、公設公営で運営していたときとかわらぬ施設として頑張っておられます。
しかし、重度障害者や学卒障害者の受け入れをしなければなりません。重度障害者が増えれば、訓練の場・労働の場を補償するために職員配置が不可欠です。今、障害者施設や介護施設での労働者不足が深刻になっています。先に報告しました、日本共産党の「障害者自立支援法の影響調査」でも事業所の職員定数の2割の離職者がでていることが明らかになっています。今春、求人をしたけれど「募集人数に足りなかった」が66.3%にのぼっています。 職員が仕事をやめる、集まらなかった理由には「労働がきつい上に、賃金が低い」が共通してあげられています。 すばる・北斗福祉作業所は、どんなに障害が重くても通所できる施設として公立公営で運営されてきました。
今、民営化されても、重度障害者や学卒障害者の受け手として、法人、保護者、職員が一体となって努力されています。 しかし、努力だけでは運営はできません。重度障害者を受け入れるということは、通常以上の職員数が必要になります。重度障害者が通所を希望しても、職員体制が十分でなかったら不安ですし、職員の献身的な努力に頼るようなことになればみるに見かねて、通所を辞退せざるをえない状況になるのではなでしょうか。
それであれば、すばる・北斗が民営化されるとき、議会で採択された請願項目、学卒者と重度障害者の希望者全員受け入れを保障するということにはなりません。市が出している補助金のほとんどは人件費です。市からの出向職員も順次引き上げになっています。施設と職員の努力には限度があります。職員の努力のもとであれば、就労継続が困難になります。「結婚できない」「経済的に苦しい」「休日出勤も代休でとるようになっているが代休を取ると通所者や他の職員に負担がかかるために休めない」などの声があります。
馬場市長は、広報ねやがわの「元気通信」で「すばる・北斗福祉作業所ではよくやってくれているというお言葉もいただきました」また、「皆さんがほんとうに前向きに頑張っておられる様子がひしひしと伝わってきました」と書いておられます。ほんとうに切実な問題として理解しておられるのであれば、すばる・北斗福祉作業所は、本来、市が運営すべき所を民営化したわけですから障害者施設として十分な運営できるようにする為に、必要な職員数と賃金の補償は市が負担すべきと考えますがいかがでしょうか。お聞きいたします。
障害者長期計画推進委員会が開催され、とりまとめの「障害者支援の推進方向」の骨子
(案)が出されました。寝屋川市はかって、あかつき・ひばり園やすばる・北斗福祉作業所など他市に誇れる障害児者施設をつくり、質の高い実践を積み上げてきました。この経験を障害者長期計画に盛り込むことができていると評価をしています。
このことは、現在の長期計画推進委員会にも引き継がれていると思います。委員の方は、よりよい計画をつくりたい。意見をあげていきたいと思って出席されています。しかし、委員の中から「推進委員会では、事務局からの説明等に時間をとり、委員が十分意見を述べるためには時間が足りない」との声が寄せられています。
そこでお聞きしますが、推進委員会の開催時間や回数を増やし委員からの意見を十分計画に反映すること。より、障害者の実態を反映した数値目標を設定し障害福祉計画との整合性をはかること。見解をお聞きします。
次に、障害者長期計画推進委員会から「障害者支援の推進方向」の骨子(案)が出されました。その中で、生活介護事業等の推進の項目は「重度の障害のある人などが介護を受けながら創作活動や生産的活動ができる日中活動の場として生活介護事業などを推進するよう事業所の確保を図り、そのための方策として小規模通所授産施設を含め、通所施設を運営する事業者が新体系の事業にスムーズに移行できるように推進する」と記述されています。
ところが市内の小規模通所授産施設からは「小規模通所授産施設は、これまで、無認可作業所の認可促進のために、大阪府が無認可作業所への補助金を廃止するといってきた。認可のための基本財産をやっとの思いで準備し、小規模通所授産施設移行した。しかし、小規模通所授産施設へ移行しても運営費は増えず、反対に運営は厳しくなるばかりです。「このままでは認可した施設を閉鎖しなければならない状況になる」と切実に訴えておられます。
そこで、お聞きをしますが、今でも運営が大変な小規模通所授産施設の新体系事業にスムーズに移行する具体化をどのようにはかっていくのかお聞きかせください。また、小規模通所授産施設への支援のための補助金の増額をもとめます。見解をお聞きします。
次に、あかつき・ひばり・第2ひばり園についてです。
これまで、あかつき・ひばり・第2ひばり園の果たす役割は、障害がある子どもとその親が専門の指導を受けることで、我が子の障害を受け入れ、発達の可能性を見いだし、障害がある子と人生を歩むためのいわばスタートの場所であると、私の経験、体験をもとに、あかつき・ひばり・第2ひばり園の役割の重大さ訴えてきました。
ところが、障害者自立支援法は、障害乳幼児の分野まで応益負担(低率1割負担)を導入しました。
障害乳幼児施設を利用する世代は、①世帯年齢が若く、所得も低い。②施設利用に際して母子通園がもとめられ、母親の就労が困難である。③兄弟がいる場合訓練中は保育所などに預けなくてはならず、その費用が必要。④障害ゆえの専門病院への通院の交通費。⑤補装具など成長に合わせて取り替えなければならない。など負担が重くなる要因が種々あります。負担は重くなっても障害を少しでも軽減したい、発達していく力をもっともっとつけてやりたい、何よりも子どもの笑顔がみたい。という親の気持ちが、生活が苦しくなっても利用をへらしたりせずに頑張って通園させているのだと思います。 このような、障害乳幼児の保護者負担の重さが理解できたからこそ、給食費の負担軽減をはかったのではありませんか。
国の「特別対策」利用料の上限額が引き下げら、給食費の負担軽減措置がとられています。しかし、それでも、利用料負担がこれまでの5倍にも増えた世帯があります。
市の給食費軽減策は、特別対策で負担額は減っているはずです。この際、障害児保護者負担を軽減させ障害児の子育て支援するお考えはありませんか。お聞きをいたします。
あかつき・ひばり・第2ひばり園は障害が発見され、早い段階で専門の訓練・療育を受けるための重要な施設です。専門的な訓練の方法は保護者も学び、家庭でもできる限り訓練をおこなうことでより障害の軽減、進行を止めることが可能になります。 とりわけ、言語聴覚士は、麻痺で発声できない、動きにくい口や舌など訓練することでしゃべれることができるようにする訓練士で特殊な知識や経験が必要な専門職です。
府下でもまだ言語聴覚士の人数も少なく貴重な人材です。現在、あかつき・ひばり園の言語聴覚士は非常勤雇用となっています。不安定な身分保障では力も発揮しにくいし、他の施設等で正職員で雇用する場ができれば、職場を変わられることにもなりまねません。非常勤雇用から正職員として身分保障を行うことが、全国的にも非常に優れた実践をしている、あかつき・ひばり・第2ひばり園の質を低下させない保障になると考えますがいかがでしょうか。
また、今後、作業療法士や理学療法士などの専門職も定年で退職されます。専門職補充については空白が生じないように、計画的な配置をおこなうことが重要です。
いかがでしょうか。見解をお聞きします。
次に、すばる・北斗福祉作業所についてお聞きします。
すばる・北斗福祉作業所が指定管理者になって2年目、法人・保護者・職員の運営努力によって、公設公営で運営していたときとかわらぬ施設として頑張っておられます。
しかし、重度障害者や学卒障害者の受け入れをしなければなりません。重度障害者が増えれば、訓練の場・労働の場を補償するために職員配置が不可欠です。今、障害者施設や介護施設での労働者不足が深刻になっています。先に報告しました、日本共産党の「障害者自立支援法の影響調査」でも事業所の職員定数の2割の離職者がでていることが明らかになっています。今春、求人をしたけれど「募集人数に足りなかった」が66.3%にのぼっています。 職員が仕事をやめる、集まらなかった理由には「労働がきつい上に、賃金が低い」が共通してあげられています。 すばる・北斗福祉作業所は、どんなに障害が重くても通所できる施設として公立公営で運営されてきました。
今、民営化されても、重度障害者や学卒障害者の受け手として、法人、保護者、職員が一体となって努力されています。 しかし、努力だけでは運営はできません。重度障害者を受け入れるということは、通常以上の職員数が必要になります。重度障害者が通所を希望しても、職員体制が十分でなかったら不安ですし、職員の献身的な努力に頼るようなことになればみるに見かねて、通所を辞退せざるをえない状況になるのではなでしょうか。
それであれば、すばる・北斗が民営化されるとき、議会で採択された請願項目、学卒者と重度障害者の希望者全員受け入れを保障するということにはなりません。市が出している補助金のほとんどは人件費です。市からの出向職員も順次引き上げになっています。施設と職員の努力には限度があります。職員の努力のもとであれば、就労継続が困難になります。「結婚できない」「経済的に苦しい」「休日出勤も代休でとるようになっているが代休を取ると通所者や他の職員に負担がかかるために休めない」などの声があります。
馬場市長は、広報ねやがわの「元気通信」で「すばる・北斗福祉作業所ではよくやってくれているというお言葉もいただきました」また、「皆さんがほんとうに前向きに頑張っておられる様子がひしひしと伝わってきました」と書いておられます。ほんとうに切実な問題として理解しておられるのであれば、すばる・北斗福祉作業所は、本来、市が運営すべき所を民営化したわけですから障害者施設として十分な運営できるようにする為に、必要な職員数と賃金の補償は市が負担すべきと考えますがいかがでしょうか。お聞きいたします。