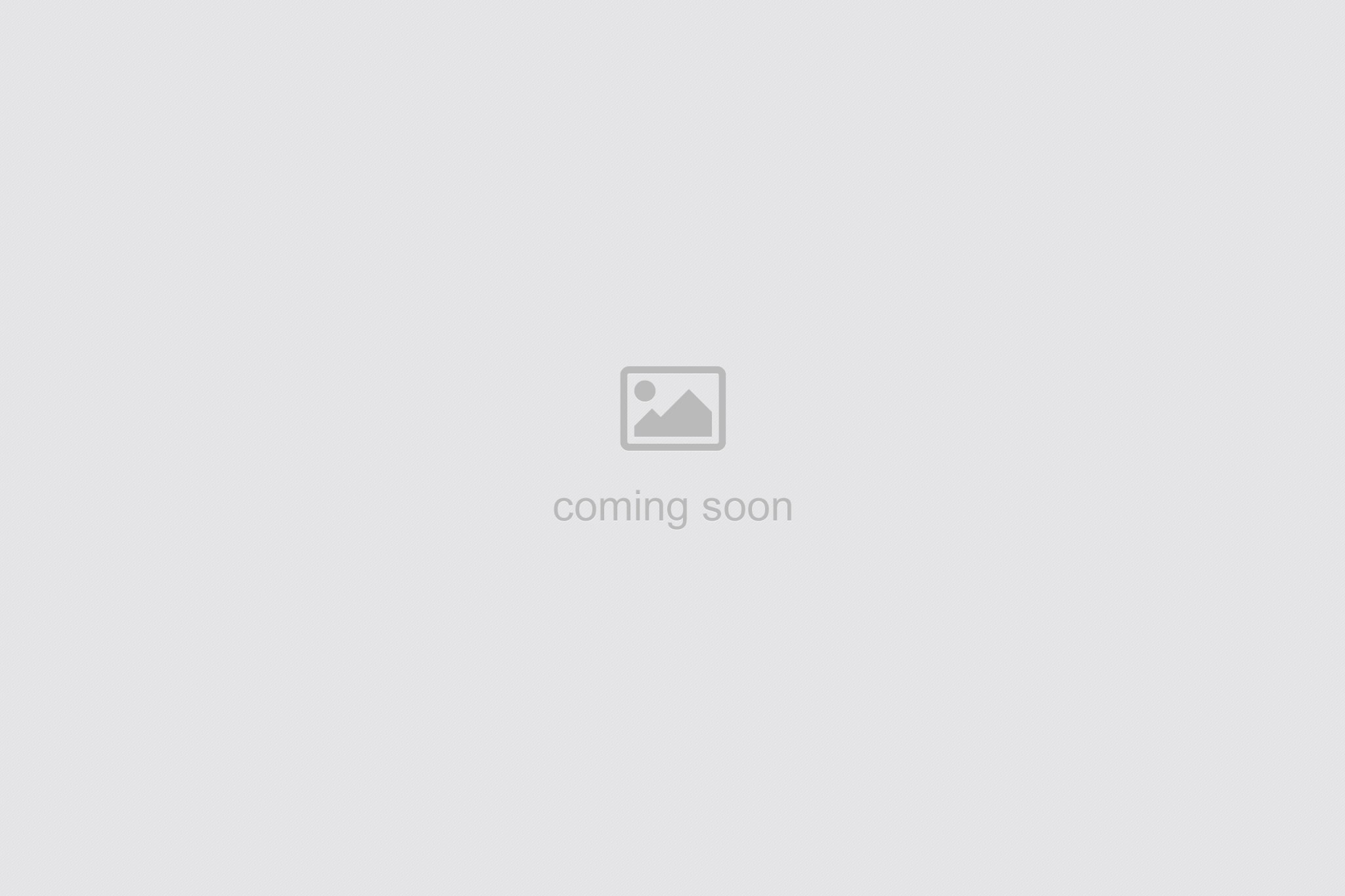10年9月議会 中林市議 一般質問
2010-09-16
まず、ごみ問題についてです
ごみ問題は、すべての人が日常生活の中で考えたり、体験している、とても身近な問題です。同時に環境、資源、経済、社会のしくみ、人々の意識など、広範な課題と密接不可分で、大きくて、そこの深い問題でもあります。
地球温暖化の問題では、朝日新聞の世論調査によると、93%の人が「温暖化による気候変動」が、すでに始まっていると感じ、92%の人が、不安をだいていると言われています。
にもかかわらず、日本国内での、温室効果ガスの排出量は、減るどころか増え続けています。後先を考えない大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会は、限りある資源を浪費し、CO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスの排出をはじめとし、様々な環境問題を生み出しています。
この大量生産・大量消費・大量廃棄を野放しにしている仕組みこそが、今日の「ごみ問題」の根本問題ではないでしょうか。
「ごみゼロ宣言」をしている徳島県上勝町を視察しました。「ごみ収集車が走らない町」として有名な町です。「焼却では、ごみ問題は解決しない」ということで、焼却施設はありません。古着、家具のリサイクルもして、ごみを34種類に分別して頑張っています。
しかし、紙類や廃プラも、材質がちがうものの重ね合わせなど、複雑化してきて、処分に困るものが多すぎるので、やはり、製造段階で処分できないごみを作らないようにしないと、ごみはゼロにはならない、との説明が印象的でした。
ごみ問題の解決は、「出たごみをどう処理するか」ではなく、「いかにごみになるものをつくらないようにするか」だと痛感しました。
環境問題や資源問題を考えたものづくりこそが、企業の繁栄にも、経済全体の活性化にもつながりますので、そういう社会のしくみを、つくっていくことが求められていると考えます。
日本のごみは、年間約4億7000万トンで、産業廃棄物が約4億1850万トン、一般廃棄物が約5204万トンで、それらが大量焼却され、埋め立てられることによって、環境に深刻な影響を与えています。
日本で発生する温室効果ガスは、06年度で、年間約13億4000万トンで、うち、廃棄物の分野からの温室効果ガスの発生量は、総排出量の3.3%であり、その75%をしめるCO2の発生量は、3380万トンで、1990年と比較して、49%増と増えています。
廃棄物の分野で、CO2の増加を押し上げている中には、食物残渣の焼却があります。年間1500万トン(06年度)を超す食糧残渣が、捨てられ燃やされています。しかも、食品産業から出される125万トンと、家庭生ごみの28%が、手つかずのまま捨てられています。資源のムダ使いであると同時に、道義的にも問われる問題なのではないでしょうか。
韓国では、05年、人口5万人以上の都市においては、すべての生ゴミを飼料化する、堆肥化する、またはバイオ利用することを法律で義務つけました。
そして、現在、韓国の生ゴミリサイクル率は全国で92%、首都ソウルでは100%が資源化され、「ごみ」としては処理されていないと言います。
日本の自治体の公的施設のうち、温室効果ガスを一番多く排出しているのが、ごみの焼却施設だと言われています。政府は、ごみの発生そのものを押さえるのではなく、焼却によってごみを減らすという方向を推進し続けてきました。
日本の一般ごみの焼却率は、06年度で77.7%です。ヨーロッパと比較すると、ドイツ25%、オランダ32%、フランス34%、スイス50%で、いかに、日本の、ごみ焼却が突出しているかがわかります。
次に、ごみ減量化についてです。
ごみの減らし方は、大きく分けて2つに分かれます。
1つは、ごみの製造、販売段階(いわゆる発生源)で、減らす方法です。今ひとつは、排出、収集段階以降の末端で減らす方法です。
排出、収集段階以降の末端でのごみ減らしは、行政責任による減量化(資源ごみ収集、リサイクル施設による)や、民間主導による減量化(資源回収)などがあります。
これまで、市町村がおこなってきた減量化の大半は、排出・収集段階以降の減量化です。この末端での減量化でも、ごみが減れば、焼却や埋め立てなどの処分に要する行政の費用を減らせますし、環境や生態系への負荷をを軽減できます。
しかし、末端での「資源ごみ分別収集」で、鉄、アルミ、ガラス、紙、布は、再生資源ルートに乗りやすいですが、安定的な減量化効果を追求しにくいという問題があります。
従って、ごみ問題の解決のためには、末端の減量化だけでなく、発生源にさかのぼって、ごみになる製品を作らないことが肝心です。ごみになりやすい製品、包装材、容器の製造・販売を、発生源で規制する「回避策」を、法律的に具体化する時代だと考えます。
市として、ごみになる製品はつくらないという政策を国に要望すべきです。
見解をお聞きします。
次に、今後の寝屋川市のごみをどうしていくのかという課題についてです。
市は、2011年から10年間の「一般廃棄物処理基本計画」を策定するため、一般廃棄物の減量等について、「廃棄物減量等推進審議会」に、基本計画の試案を諮問しました。
審議会で、「ごみ減量化目標値」や「減量化の具体案」などが、市から提案されています。この段階から、幅広い住民参加で、協議していくことが基本だと思います。
市民アンケートの実施、審議会への各団体代表や市民公募委員がいるだけでなく、もっと幅を広げた議論が必要だと思います。
ごみの減量化の問題は、住民の協力なくしては、実現不可能な問題です。
住民の総意に基づいて、今後の減量策などを決めることが、必要だと考えます。
審議会の答申案について、パブリックコメントをおこなう予定ですが、その前に、各コミセン単位などで、市民の意見を直接聞く機会などを設けるべきだと考えます。 見解をお聞きします。
次に、今後の「ごみ処理基本計画」をつくる上で、避けて通れない課題について、お聞きします。
① 地球温暖化の問題では、独自に温室効果ガスの25%削減に取り組み、産業界との公的削減協定など、実行ある措置に取り組むことを、国に要望するようもとめます。
② 市として、CO2排出量の現状を把握し、市民的議論をおこない、実行ある削減計画をつくるべきです。
① 本市特有の課題として、廃プラの問題があります。その他プラを再商品化していますが、本市の独特な地形も影響して、住民の健康被害の問題があります。
ごみ問題は、環境問題でもあります。環境や住民の健康をまもれないような処分の方法はダメですし、そういうような処分しか、できないような製品は、作らせないようにしなければならないと考えます。
そういう点からも、健康被害が現実にある中での、廃プラの再商品化は、見直すべきだと考えます。
以上、3点お聞きします
次に、ごみ減量化の具体案についてです。
① 前回の基本計画2001年~2010年の目標値、年間10万5381トンに対する実績は、08年で、8万787トンであり、分別収集の実施や人口減少が大きかったこともあり、目標を達成しています。
しかし、今後5年、10年については、確実に減らせる方法がないと、単純には減らないのではないでしょうか。
② 8割が水分である生ゴミの焼却については、大量のエネルギーを使い、環境や、経済効率からもよくはありません。コンポストの普及にとどまらず、具体的な施策を検討すべきだと考えます。
一例ですが、滋賀県甲賀市では、生ゴミの堆肥化に取り組んでいます。無料で市民に配布する「種堆肥」を生ゴミと交互に、自宅の密封できるバケツなどに入れておき、それを、集積場所に設置の生ゴミ回収容器に、入れます。市は容器を回収して、一括して、発酵施設で堆肥化させ、堆肥化した種堆肥を、住民に無料で配布するのです。自宅のごみバケツの時点から、発酵が進み、臭いが消えるのが特徴です。
本市に合った方法での研究、調査をもとめるものです。
③事業所ごみについてです。現在、分別されずに、排出されています。全体のごみにしめる割合が、25.4%であることからも、もっと、丁寧に分別すできないものかどうか、検討すべきだと思います。
④小売店においては、本来、企業が製造したものを、仕入れていますので、製造者責任で、元に返していくシステムが取られるべきではないでしょうか?
⑤ 製造者や事業者に、回収、運搬、処分などの全ての責任をもたせることによって、税金を使っての「行政頼みの現実」を、改善していくべきだと考えます。市として、国に要望し、ごみ処理量を削減することを、減量化目標に掲げるべきではないでしょうか。 以上、5点お聞きします。
次に、ごみの有料化についてです。
ごみを有料化するということは、住民が治める税金が、何に優先して使われるべきかという重大な問題でもあります。住民生活に必要なごみの処理については、税金に含まれているというのが、今までの考え方だと思います。そう言う点では、有料化は、市民からみれば、税金の2重取りだとも言えます。
「廃棄物減量等推進審議会」に、市が提案した、今後のごみ減量化具体案には、有料化を調査検討することが盛りこまれています。
市民的な議論なしで、有料化を具体策には入れるべきでないと考え、見解をお聞きします。
次に、クリーンセンターの建て替えについてです。
クリーンセンター建て替えのための「検討委員会」が開催されています。
この検討委員会の発足前に、出された「基礎的資料」では、新施設については、①高効率ごみ発電施設であること ②規模は200t ③寝屋川市単独施設であり、広域化は行わない、④平成28年稼働、建設費用は100億円を超えると言うことです。以下、お聞きします。
①基礎的資料について、市は、交付金を受けるために必要な経過だと説明されましたが、今後のごみ焼却量の計画もできていない時期に、一定の方向が決められるのは、納得できません。
寝屋川市のごみ全体について、将来どうしていくのか、焼却量はどれくらいと見るのか、などが明らかになった上で、市民的に議論されるべきと考えます。
② 焼却炉の規模については、国が、高価な大型焼却炉や「最新鋭」のごみ施設建設を推し進めた結果、建設費や運営費などの急増で深刻な財政危機に陥っている自治体や、大型焼却炉の温度を下げないために、燃やすごみをかき集めるという自治体もあると聞きます。
高効率施設にすれば、国の補助金が増えるということについても、本当に必要なのか、費用対効果はどうなのかなど、市民に理解できる説明をおこなうべきです。
本市での規模については、できる限り小規模の焼却炉にするべきだと考えます。
③立地場所の選定については、住民合意が前提です。住民合意を得るために市民の納得のいく選定手続きが不可欠です。
現施設の周辺住民の意見を良く聞くこと、市民アンケート、市民公聴会など、多様な方法で、幅広い市民の意見が、直接反映できるようにすることを求めます。
以上、見解をお聞きします。
次に、熱中症対策についてです。
今年は、30年に1度という異常気象で、8月の平均気温は、最高気温を更新しました。
熱中症による乳牛や豚、鶏などの家畜の被害も、例年を大きく上まわっています。
熱中症で搬送された人は、8月で、昨年の4.4倍、搬送直後の死亡は、昨年の8倍とのことです。大阪府内では、3200人が救急搬送されました。
私は、市民から、家にクーラーがないが、設置費用がないので、「友人の家に行って何とかしのいでいる」「自分の家でゆっくり休みたい」などの声を聞きました。
ある人は、「近所で人が亡くなった、持病があったが、クーラーがあったら、もっと長生きできたかもしれない」という話も寄せられました。
クーラーがあっても、電気代が怖くて思うようにつけられず我慢している例や
病気で働けず、生活保護を受けている人が、クーラー設置費用を分割にできないか、電気店を何軒もまわったが断られたなど、この夏、暑さに苦しむ市民の声を聞きました。
吹田市は、自宅にエアコンがない高齢者などの一時避難所として、4消防署の会議室や仮眠室などを24時間開放して寝泊まりできる「熱中症シェルター」を設置し、ペットボトルの水を無料で提供しました。
摂津市も、市内の公民館6カ所に避難所を設置しました。
昨日から、少し暑さがましになりました。
9月になっても、暑さが変わりません。
この夏、連日、38度や39度の暑さで、熱中症患者が急増、中でも低所得の高齢者や、病気の方が犠牲になっていることから、以下の実施をもとめ、見解をお聞きします。
1、市内の公共施設を活用し、緊急のシェルターを設置すること
2,単身の高齢者を訪問し、実態把握をおこなうこと
3,クーラーの設置補助制度、融資制度を創設すること
4,電力会社に低所得者の電力料金の減免を要請すること
5,生活保護のクーラー設置費を一時扶助とし、電気代として、夏期加算の新設を国 に要望すること
6,小中学校の教室の、クーラー設置については、北河内地域では、大東市、門真市、 四条畷市、枚方市が設置済みで、交野市も来年度、中学校に設置するとのことです。本市での設置をおこなうこと。以上、6点、見解を求めます。
次に、市民プールについてです。
年間5万人が利用する「市民プール」を廃止するという計画は、3月議会が終了した後に、「公共施設等整備・再編計画」が、市会議員に配布される形で、公表されました。
なぜ3月議会の前に十分説明し、3月議会で議論をしないのか。議会軽視ともいうべきこのような対応は容認できません。
また、担当部署は、「市広報や市ホームページで計画を市民に周知する」と私たちに説明しましたが、これもきちっとやられているとは言えません。市広報は5月1日号で、「行財政改革の新たな取組の見出し」で、触れていますが、詳しい内容はこれでは分かりません。
市民プールを廃止するべきかどうか、情報をきちんと公開し、市民の意見を聴くべきです。見解をお聞きいたします。
市民プール廃止の計画を知った市民が、「市民プールをまもる会」を結成して、存続をもとめる要望署名が始まっています。
ほとんどの利用者が、廃止のことは知らなくて、「エー何で?」と驚き、「小さい頃から市民プールを利用してきた。我が子も利用している、なくさないでほしい」と、関心の高さを物語っています。
市民プールは、なぜ廃止しかないのでしょうか? 市の説明では、「昭和53年に設置された市民プールは、建設後31年が経過し、健康増進、レジャーを目的としたプールが、民間等で設置されている状況の中で、必ずしも公共が運営しなければならない施設ではなく、市民プールが果たしてきた役割はすでに達成されていると言える」とあります。しかし、3時間200円で使用できる民間プールが、どこにあるでしょうか。市内には、小学生が泳げるプールは、スイミングスクールしかありません。
また、「1年を通して利用期間が短く、大規模な修繕が必要となっていることから、通年利用できる市民の憩いの広場にする」とのことですが、これは、年に2か月しか使わないプールだから、修繕代がもったいないと言う意味に聞こえます。
大規模修繕費は、7500万円と聞いていますが、10年間で見れば、1年では、750万円です。修繕費として必要な当然の経費ではないでしょうか。
今ある公共施設を廃止する場合は、市民の意見を聞くべきです。 市民の意見も聞かず、議会の議論もない中で、年間5万人が利用している施設、市民が安い費用で楽しめる施設の廃止はやめるべきです。見解をお聞きします。
ごみ問題は、すべての人が日常生活の中で考えたり、体験している、とても身近な問題です。同時に環境、資源、経済、社会のしくみ、人々の意識など、広範な課題と密接不可分で、大きくて、そこの深い問題でもあります。
地球温暖化の問題では、朝日新聞の世論調査によると、93%の人が「温暖化による気候変動」が、すでに始まっていると感じ、92%の人が、不安をだいていると言われています。
にもかかわらず、日本国内での、温室効果ガスの排出量は、減るどころか増え続けています。後先を考えない大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会は、限りある資源を浪費し、CO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスの排出をはじめとし、様々な環境問題を生み出しています。
この大量生産・大量消費・大量廃棄を野放しにしている仕組みこそが、今日の「ごみ問題」の根本問題ではないでしょうか。
「ごみゼロ宣言」をしている徳島県上勝町を視察しました。「ごみ収集車が走らない町」として有名な町です。「焼却では、ごみ問題は解決しない」ということで、焼却施設はありません。古着、家具のリサイクルもして、ごみを34種類に分別して頑張っています。
しかし、紙類や廃プラも、材質がちがうものの重ね合わせなど、複雑化してきて、処分に困るものが多すぎるので、やはり、製造段階で処分できないごみを作らないようにしないと、ごみはゼロにはならない、との説明が印象的でした。
ごみ問題の解決は、「出たごみをどう処理するか」ではなく、「いかにごみになるものをつくらないようにするか」だと痛感しました。
環境問題や資源問題を考えたものづくりこそが、企業の繁栄にも、経済全体の活性化にもつながりますので、そういう社会のしくみを、つくっていくことが求められていると考えます。
日本のごみは、年間約4億7000万トンで、産業廃棄物が約4億1850万トン、一般廃棄物が約5204万トンで、それらが大量焼却され、埋め立てられることによって、環境に深刻な影響を与えています。
日本で発生する温室効果ガスは、06年度で、年間約13億4000万トンで、うち、廃棄物の分野からの温室効果ガスの発生量は、総排出量の3.3%であり、その75%をしめるCO2の発生量は、3380万トンで、1990年と比較して、49%増と増えています。
廃棄物の分野で、CO2の増加を押し上げている中には、食物残渣の焼却があります。年間1500万トン(06年度)を超す食糧残渣が、捨てられ燃やされています。しかも、食品産業から出される125万トンと、家庭生ごみの28%が、手つかずのまま捨てられています。資源のムダ使いであると同時に、道義的にも問われる問題なのではないでしょうか。
韓国では、05年、人口5万人以上の都市においては、すべての生ゴミを飼料化する、堆肥化する、またはバイオ利用することを法律で義務つけました。
そして、現在、韓国の生ゴミリサイクル率は全国で92%、首都ソウルでは100%が資源化され、「ごみ」としては処理されていないと言います。
日本の自治体の公的施設のうち、温室効果ガスを一番多く排出しているのが、ごみの焼却施設だと言われています。政府は、ごみの発生そのものを押さえるのではなく、焼却によってごみを減らすという方向を推進し続けてきました。
日本の一般ごみの焼却率は、06年度で77.7%です。ヨーロッパと比較すると、ドイツ25%、オランダ32%、フランス34%、スイス50%で、いかに、日本の、ごみ焼却が突出しているかがわかります。
次に、ごみ減量化についてです。
ごみの減らし方は、大きく分けて2つに分かれます。
1つは、ごみの製造、販売段階(いわゆる発生源)で、減らす方法です。今ひとつは、排出、収集段階以降の末端で減らす方法です。
排出、収集段階以降の末端でのごみ減らしは、行政責任による減量化(資源ごみ収集、リサイクル施設による)や、民間主導による減量化(資源回収)などがあります。
これまで、市町村がおこなってきた減量化の大半は、排出・収集段階以降の減量化です。この末端での減量化でも、ごみが減れば、焼却や埋め立てなどの処分に要する行政の費用を減らせますし、環境や生態系への負荷をを軽減できます。
しかし、末端での「資源ごみ分別収集」で、鉄、アルミ、ガラス、紙、布は、再生資源ルートに乗りやすいですが、安定的な減量化効果を追求しにくいという問題があります。
従って、ごみ問題の解決のためには、末端の減量化だけでなく、発生源にさかのぼって、ごみになる製品を作らないことが肝心です。ごみになりやすい製品、包装材、容器の製造・販売を、発生源で規制する「回避策」を、法律的に具体化する時代だと考えます。
市として、ごみになる製品はつくらないという政策を国に要望すべきです。
見解をお聞きします。
次に、今後の寝屋川市のごみをどうしていくのかという課題についてです。
市は、2011年から10年間の「一般廃棄物処理基本計画」を策定するため、一般廃棄物の減量等について、「廃棄物減量等推進審議会」に、基本計画の試案を諮問しました。
審議会で、「ごみ減量化目標値」や「減量化の具体案」などが、市から提案されています。この段階から、幅広い住民参加で、協議していくことが基本だと思います。
市民アンケートの実施、審議会への各団体代表や市民公募委員がいるだけでなく、もっと幅を広げた議論が必要だと思います。
ごみの減量化の問題は、住民の協力なくしては、実現不可能な問題です。
住民の総意に基づいて、今後の減量策などを決めることが、必要だと考えます。
審議会の答申案について、パブリックコメントをおこなう予定ですが、その前に、各コミセン単位などで、市民の意見を直接聞く機会などを設けるべきだと考えます。 見解をお聞きします。
次に、今後の「ごみ処理基本計画」をつくる上で、避けて通れない課題について、お聞きします。
① 地球温暖化の問題では、独自に温室効果ガスの25%削減に取り組み、産業界との公的削減協定など、実行ある措置に取り組むことを、国に要望するようもとめます。
② 市として、CO2排出量の現状を把握し、市民的議論をおこない、実行ある削減計画をつくるべきです。
① 本市特有の課題として、廃プラの問題があります。その他プラを再商品化していますが、本市の独特な地形も影響して、住民の健康被害の問題があります。
ごみ問題は、環境問題でもあります。環境や住民の健康をまもれないような処分の方法はダメですし、そういうような処分しか、できないような製品は、作らせないようにしなければならないと考えます。
そういう点からも、健康被害が現実にある中での、廃プラの再商品化は、見直すべきだと考えます。
以上、3点お聞きします
次に、ごみ減量化の具体案についてです。
① 前回の基本計画2001年~2010年の目標値、年間10万5381トンに対する実績は、08年で、8万787トンであり、分別収集の実施や人口減少が大きかったこともあり、目標を達成しています。
しかし、今後5年、10年については、確実に減らせる方法がないと、単純には減らないのではないでしょうか。
② 8割が水分である生ゴミの焼却については、大量のエネルギーを使い、環境や、経済効率からもよくはありません。コンポストの普及にとどまらず、具体的な施策を検討すべきだと考えます。
一例ですが、滋賀県甲賀市では、生ゴミの堆肥化に取り組んでいます。無料で市民に配布する「種堆肥」を生ゴミと交互に、自宅の密封できるバケツなどに入れておき、それを、集積場所に設置の生ゴミ回収容器に、入れます。市は容器を回収して、一括して、発酵施設で堆肥化させ、堆肥化した種堆肥を、住民に無料で配布するのです。自宅のごみバケツの時点から、発酵が進み、臭いが消えるのが特徴です。
本市に合った方法での研究、調査をもとめるものです。
③事業所ごみについてです。現在、分別されずに、排出されています。全体のごみにしめる割合が、25.4%であることからも、もっと、丁寧に分別すできないものかどうか、検討すべきだと思います。
④小売店においては、本来、企業が製造したものを、仕入れていますので、製造者責任で、元に返していくシステムが取られるべきではないでしょうか?
⑤ 製造者や事業者に、回収、運搬、処分などの全ての責任をもたせることによって、税金を使っての「行政頼みの現実」を、改善していくべきだと考えます。市として、国に要望し、ごみ処理量を削減することを、減量化目標に掲げるべきではないでしょうか。 以上、5点お聞きします。
次に、ごみの有料化についてです。
ごみを有料化するということは、住民が治める税金が、何に優先して使われるべきかという重大な問題でもあります。住民生活に必要なごみの処理については、税金に含まれているというのが、今までの考え方だと思います。そう言う点では、有料化は、市民からみれば、税金の2重取りだとも言えます。
「廃棄物減量等推進審議会」に、市が提案した、今後のごみ減量化具体案には、有料化を調査検討することが盛りこまれています。
市民的な議論なしで、有料化を具体策には入れるべきでないと考え、見解をお聞きします。
次に、クリーンセンターの建て替えについてです。
クリーンセンター建て替えのための「検討委員会」が開催されています。
この検討委員会の発足前に、出された「基礎的資料」では、新施設については、①高効率ごみ発電施設であること ②規模は200t ③寝屋川市単独施設であり、広域化は行わない、④平成28年稼働、建設費用は100億円を超えると言うことです。以下、お聞きします。
①基礎的資料について、市は、交付金を受けるために必要な経過だと説明されましたが、今後のごみ焼却量の計画もできていない時期に、一定の方向が決められるのは、納得できません。
寝屋川市のごみ全体について、将来どうしていくのか、焼却量はどれくらいと見るのか、などが明らかになった上で、市民的に議論されるべきと考えます。
② 焼却炉の規模については、国が、高価な大型焼却炉や「最新鋭」のごみ施設建設を推し進めた結果、建設費や運営費などの急増で深刻な財政危機に陥っている自治体や、大型焼却炉の温度を下げないために、燃やすごみをかき集めるという自治体もあると聞きます。
高効率施設にすれば、国の補助金が増えるということについても、本当に必要なのか、費用対効果はどうなのかなど、市民に理解できる説明をおこなうべきです。
本市での規模については、できる限り小規模の焼却炉にするべきだと考えます。
③立地場所の選定については、住民合意が前提です。住民合意を得るために市民の納得のいく選定手続きが不可欠です。
現施設の周辺住民の意見を良く聞くこと、市民アンケート、市民公聴会など、多様な方法で、幅広い市民の意見が、直接反映できるようにすることを求めます。
以上、見解をお聞きします。
次に、熱中症対策についてです。
今年は、30年に1度という異常気象で、8月の平均気温は、最高気温を更新しました。
熱中症による乳牛や豚、鶏などの家畜の被害も、例年を大きく上まわっています。
熱中症で搬送された人は、8月で、昨年の4.4倍、搬送直後の死亡は、昨年の8倍とのことです。大阪府内では、3200人が救急搬送されました。
私は、市民から、家にクーラーがないが、設置費用がないので、「友人の家に行って何とかしのいでいる」「自分の家でゆっくり休みたい」などの声を聞きました。
ある人は、「近所で人が亡くなった、持病があったが、クーラーがあったら、もっと長生きできたかもしれない」という話も寄せられました。
クーラーがあっても、電気代が怖くて思うようにつけられず我慢している例や
病気で働けず、生活保護を受けている人が、クーラー設置費用を分割にできないか、電気店を何軒もまわったが断られたなど、この夏、暑さに苦しむ市民の声を聞きました。
吹田市は、自宅にエアコンがない高齢者などの一時避難所として、4消防署の会議室や仮眠室などを24時間開放して寝泊まりできる「熱中症シェルター」を設置し、ペットボトルの水を無料で提供しました。
摂津市も、市内の公民館6カ所に避難所を設置しました。
昨日から、少し暑さがましになりました。
9月になっても、暑さが変わりません。
この夏、連日、38度や39度の暑さで、熱中症患者が急増、中でも低所得の高齢者や、病気の方が犠牲になっていることから、以下の実施をもとめ、見解をお聞きします。
1、市内の公共施設を活用し、緊急のシェルターを設置すること
2,単身の高齢者を訪問し、実態把握をおこなうこと
3,クーラーの設置補助制度、融資制度を創設すること
4,電力会社に低所得者の電力料金の減免を要請すること
5,生活保護のクーラー設置費を一時扶助とし、電気代として、夏期加算の新設を国 に要望すること
6,小中学校の教室の、クーラー設置については、北河内地域では、大東市、門真市、 四条畷市、枚方市が設置済みで、交野市も来年度、中学校に設置するとのことです。本市での設置をおこなうこと。以上、6点、見解を求めます。
次に、市民プールについてです。
年間5万人が利用する「市民プール」を廃止するという計画は、3月議会が終了した後に、「公共施設等整備・再編計画」が、市会議員に配布される形で、公表されました。
なぜ3月議会の前に十分説明し、3月議会で議論をしないのか。議会軽視ともいうべきこのような対応は容認できません。
また、担当部署は、「市広報や市ホームページで計画を市民に周知する」と私たちに説明しましたが、これもきちっとやられているとは言えません。市広報は5月1日号で、「行財政改革の新たな取組の見出し」で、触れていますが、詳しい内容はこれでは分かりません。
市民プールを廃止するべきかどうか、情報をきちんと公開し、市民の意見を聴くべきです。見解をお聞きいたします。
市民プール廃止の計画を知った市民が、「市民プールをまもる会」を結成して、存続をもとめる要望署名が始まっています。
ほとんどの利用者が、廃止のことは知らなくて、「エー何で?」と驚き、「小さい頃から市民プールを利用してきた。我が子も利用している、なくさないでほしい」と、関心の高さを物語っています。
市民プールは、なぜ廃止しかないのでしょうか? 市の説明では、「昭和53年に設置された市民プールは、建設後31年が経過し、健康増進、レジャーを目的としたプールが、民間等で設置されている状況の中で、必ずしも公共が運営しなければならない施設ではなく、市民プールが果たしてきた役割はすでに達成されていると言える」とあります。しかし、3時間200円で使用できる民間プールが、どこにあるでしょうか。市内には、小学生が泳げるプールは、スイミングスクールしかありません。
また、「1年を通して利用期間が短く、大規模な修繕が必要となっていることから、通年利用できる市民の憩いの広場にする」とのことですが、これは、年に2か月しか使わないプールだから、修繕代がもったいないと言う意味に聞こえます。
大規模修繕費は、7500万円と聞いていますが、10年間で見れば、1年では、750万円です。修繕費として必要な当然の経費ではないでしょうか。
今ある公共施設を廃止する場合は、市民の意見を聞くべきです。 市民の意見も聞かず、議会の議論もない中で、年間5万人が利用している施設、市民が安い費用で楽しめる施設の廃止はやめるべきです。見解をお聞きします。