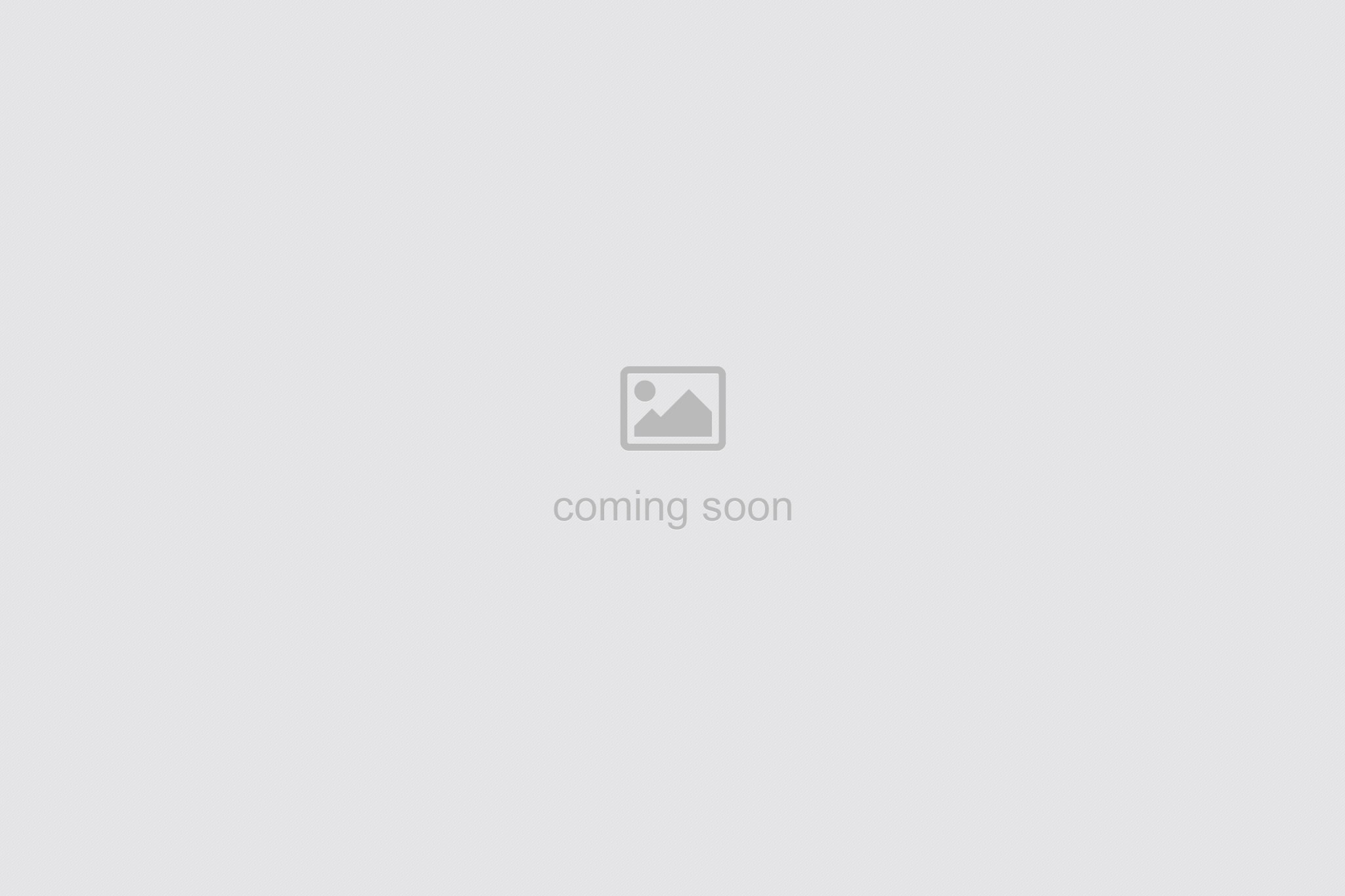前日、当日の対応についてです。
全員協議会でも明らかにされましたが、前日、午後10時の大雨洪水警報発令から寝屋川市では職員24人の体制が取られています。14日早朝5時半から6時半にかけて時間雨量100ミリを超える豪雨が降りました。今回のこの豪雨をどのようにして市民に知らせ、注意喚起を行ったのかは大変重要なことです。
大雨の中多くの市民の方から連絡を受けて市内各所を見て回りましたが、浸水に対応をしている市民の方がいる一方で、未だ気づかずにいるのか、お盆で帰省をしているのか、浸水の最中に全然対応をしていない家庭も見受けられました。
浸水後にお話を聞いているとなんのための防災無線なんだ。なんのための緊急連絡メールなんだと豪雨が降っている最中に市からの情報提供が行われなかったことに対するお叱りの声を多数聞きました。そこでお聞きします。
地域防災計画では 3 . 住民への周知で 市は、必要に応じ、防災行政無線、広報車、警鐘、サイレン等を利用し、又は状況に応じて自主防災組織などの住民組織と連携して、住民に対して予警報等を伝達するとともに、予想される事態とそれに対してとるべき措置について周知する。なお、周知に当たっては、災害時要援護者に配慮する。とされています。
残念ながら今回の浸水で防災行政無線、広報車、警鐘など、浸水時には全然活用されませんでしたが、かつて寝屋川を襲ったことがない大雨が来ても活用されないとなると、どのような状況で活用されるのか大変不安になります。活用をする基準を明らかにして下さい。また、判断をする責任者は防災計画ではだれにあたり、今回は誰が判断したのかもお答えください。今後、被害を少しでも食い止めるために地域防災計画を活かした住民への周知を求めます。また、特に広報車の活用を求めます。今回の災害の中では活動していないようでしたが、防災無線とあわせて被害が大きく出ている地域での特別な広報もまた必要です。今回どのような広報活動を行ったのか。また今後の活用についてもお答えください。
またメールねやがわの活用です。今回の災害ではメールねやがわを活用して情報提供が全くなされていません。被害の状況、消毒、ゴミ、罹災証明に見舞金と市民知りたい、市民に伝えるべき情報は多くあったのではないでしょうか。そんな中で、大雨ののちに最初に送られたのが8月16日の大阪の食育週間を伝えるものでがっかりしました。翌日には職員採用の案内です。どちらも大切なお知らせであると思いますが、市民のニーズにあったものではなかったと考えます。
14日の大雨が降っている最中に、注意喚起する安全安心メールの送信、その後の情報提供のメールが必要であったと考えます。今後、様々な震災に対してメールねやがわの活用は行われるのか。今回何故全く活用されなかったのか明らかにして下さい。
平成24年3月の寝屋川市の避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)では浸水被害に備えた基準では市域に大雨警報が発表され、かつ10分間観測雨量が20ミリを超え、それを含む一時間観測雨量が50ミリを超えたときを一時避難情報の発令をする基準としています。今回の豪雨では一時避難情報が流れたとはきいていません。なぜマニュアルと違う対応が取られたのか。今後の対応とあわせて答弁を求めます。
集中豪雨で床下から床上浸水と水かさが増えていく中で多くの市民が市役所に助けを求めて電話をかけていますが、多くの市民の方から全然繋がらなかった、混み合っているので後ほどおかけくださいとテープがこたえるなど、市役所に連絡をすることさえできなかった実情がみえてきました。そこで、多くの電話が混み合う中で当日特別な手立てが必要であったお考えます。大規模災害時の職員の招集、臨時電話などの体制づくりが早急の課題です。今回行われた対策と今後の対策についてお答えください。
避難誘導の体制です。床上浸水など避難が必要な市民が今回でています。全員協議会では2世帯4名のコミセンへの避難が報告されましたが、近所の公民館やお寺などに避難をした話も伺っています。道路が冠水をしているなか、避難が必要な市民をどのようなかたちで誘導をしたのか。今回、避難をしたいと市へ連絡をした方が、避難場所を伝えてくれただけでなにもしてくれなかったと不満を述べておられるのをききました。現実問題として、高齢者の方に冠水をした道路の移動は困難であると言わざるを得ません。実際に避難を求めた市民にどのような対応を取ることができたのか。今後どのように対応を検討しているのか明らかにして下さい。
道路の冠水についてです。市内全域で道路が冠水し警察や市が通行止めを行なっていましたが、すべての危険箇所の通行止めは残念ながらできていません。市民の方々からは通行止めにして欲しかったというお話も沢山頂きました。そんな中には、冠水した道路を車が通るたびに大きな波が起こり床上浸水となってしまった。また、バイクが波で転倒して水没してしまったなど、冠水をした道路を車が通ることでの被害の拡大を訴える声やマンホールの蓋があく、側溝の蓋が流れるなど、冠水した道路を移動することは大変な危険を伴うのでしっかりと止めて欲しいとの声もありました。通常道路の通行止は警察の判断でしょうが、手が足りなかったことも明らかです。私も警察へ電話をさせていただきましたが、人命救助が優先になっています。大きな幹線道路から冠水した道路の通行止を行なっていますのでご理解をとききました。現実に手が足りない中で、地域、自治会の判断で目の前の道路の通行止めをすることができるような体制づくりも必要ではないでしょうか。
通行止めが早急に行われていれば出ることがなかった被害に対する保証はどのように考えているのか。
目の前の道路の冠水、そしてその波で被害が出ている家庭や地域で車の通行を止めることができるのか。市としての対応ができるのかお答えください。
土嚢の配布についてです。大雨になり道路の冠水や家屋への浸水が見られるときに下水道室は市民の要望に応えて土嚢の配布を行なってくれています。しかし、今回の大雨では残念ながら市民の要請に全て応えることはできなかったと思いますが、下水道室は当日、浸水被害を訴える市民にどれだけの土嚢を配布することができたのか、お答えください。また、浸水後も今後の為と土嚢を求める市民の声がかなりあったと聞いていますが、今現在で配布した数をお示しください。今後、今回のような大雨が降りますと地域、自治会単位などでの土嚢の配布などが現実的な課題となりますが、市の考えをお答えください。
防災計画では 1 . 災害時の配備体制の概要市は市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害を最小限にとどめるための災害応急対策を迅速・適切に実施する必要がある。そのため、市長は、自らを本部長として、市に「寝屋川市災害対策本部」を設置して職員の動員配備を行い、活動体制を確立する。また、災害対策本部が設置される前、又は災害対策本部を設置するに至らない場合で必要があると認めるときは、「災害警戒本部」を設置し、被害情報の把握、調査、市民の避難や応急処理など小規模な災害の発生に対処する体制をとる。なお、本部体制の実施に備え、気象情報等及び災害情報を収集するための体制として、「気象情報等収集体制」を設ける。
となっています。かつてない豪雨災害が起きたにもかかわらず災害対策本部が設置されないとなると防災計画の根本が問われます。防災計画の災害対策本部の設置基準ではイ. 災害救助法の適用を要する災害が発生したときとしています。今回の災害は災害救助法に該当する被害が発生した市町村における自然災害に該当するということで寝屋川市は国から被災者生活再建法の適用を受けました。14日には、朝の6時から夜10時まで200名を超える職員体制で当たったとされていますが、なぜ寝屋川市災害対策本部が設置されなかったのかお答えください。
豪雨後の対応についてです。
豪雨が止み、水が引いて多くの市民の方が、家の片付け、ゴミ出し、家屋、道路の消毒に取り掛かりました。
まず、消毒についてですが、道路の消毒について市民から、私道は自分で消毒してくださいと対応を断られたと聞きました。また、その後公共の施設につながる道であることを伝えると消毒に来た。との話を聞きましたが、私道と市道、府道などの消毒はどのような基準で消毒を行ったのか。対応に差があったと聞いていますが、散布の範囲をお答えください。
今回は市が個別に消毒をすると相当な期間が要するため消毒液の無料配布による各戸対応をお願いしたとされていますが。消毒薬の噴霧器についてはどのような対応がなされたのか。また、消毒についても自治会単位で消毒薬の配布が行われていますが、自治会に入っておられない方もいます。自治会には679本93地域に配布したとなっていますが、個別に連絡があった部分の対応はどのようになったのか明らかにして下さい。今回危機管理室に各自治体から消毒薬を取りに来ている姿も見受けられましたが、各コミセンや市民センターなどで配布をする体制の検討を求め答弁を求めます。
ゴミの収集についてです。大きな畳等のゴミは各戸個別に収集、小さなゴミは自治会で集積所をきめて回収されていきました。他市ではリサイクル料をとったところもあると聞いていますが、素早く、浸水ゴミは無料で対応して頂いたことは評価をしたいと思います。しかし、平常のごみ収集と震災ゴミの収集で一部混乱もあったと聞いています。委託業者の対応も含めて市民との混乱を招くことがないよう、今後の対策を求め答弁を求めます。
市民が市役所に被災証明の申請に殺到しました。早いうちに待合室の設置など体制が整えられたことは評価します。しかし、こんな時こそ市民センターなど市内各地で、被災証明の発行申請を行えるように職員の配置をすべきであったと思います。今後の改善を求め答弁を求めます。
被害調査の職員の訪問についてです。多くの職員が本当に頑張って頂いたことを知っていますが、一部配慮のない言葉によって被災した市民が更に辛い思いをしたとの話も聞きました。被災された方は普段のより更に繊細になっておられます。市職員の訪問時のマニュアル等の改善を求めます。
被害の全貌の把握です。被災証明を申請した方については訪問調査をしていますので正確な場所と件数が出てきますが、床下浸水で特に被害が出なかった場所の特定は不十分ではないでしょうか。14日には自治会長へ電話による被害状況の確認が行われていますが、市として今回の被害の全貌を、今後の対策を立てるためにもしっかりと調査することを求め答弁を求めます。
8月18日(金)3回の防災無線の放送が行われました。ようやく浸水に関することで防災無線の活用がされたわけですが、内容は土日の市庁舎の開庁と消毒薬の配布のお知らせでした。しかし、残念なことにこの放送も多くの市民に届いていません。聞こえていない人、聞こえても内容がわからなかった人など、ほとんどその役目を果たしていなかったのではないでしょうか。今一度、防災無線の活用のしかた。全域に放送が届くような調整をお願いし、答弁を求めます。
今後の対策
100年に一度の雨と言いながら香里園のゲリラ豪雨から4年で今度は市域全域に再び100年に一度の雨が降りました。想定外でなくなった雨に対して寝屋川流域下水の計画の見直しが必要ではないでしょうか。現在、計画中の増補幹線、雨水貯留地の早期の工事の完了を求め、想定雨量40ミリの大幅な引き上げが必要です。関係11市の協議を早急に行うことを求めて答弁を求めます。
そして全体の協議を待つことなく寝屋川市としてできる対策に取り組むことを求めます。被災された市民の方は、具体的な様々な意見を持っておられます。市として意見徴収に取り組み、地域ごとに小規模な貯留地やポンプでの排水設備など市ができる浸水対策を行なうことを求め答弁を求めます。
今回の豪雨では寝屋川市駅周辺の冠水が大変な状況となりました。今回京阪電車もとまり、駅に行っても乗車できなかったワケですが、それでも多くの市民がびしょびしょになりながら駅に向かって行きました。寝屋川市駅は寝屋川市の玄関口です。大雨が降るたびに駅周辺で道路が冠水していることは、特別な対策も必要です。市の見解をお伺いします。
避難場所について寝屋川市のHPを見ますと、災害時の避難場所、洪水時の避難場所が指定されています。今回のような集中豪雨による浸水被害は、淀川や寝屋川流域の川の氾濫による洪水とも被害の現れ方が異なっているのではないでしょうか。であるならば、新たな避難場所の設定が求められます。避難場所の設定をどのように考えているのかお示しください。
地域防災計画が見直しされます。今回の集中豪雨の経験を活かした計画策定となるよう求め答弁を求めます。
1 介護保険について
保険料の引き下げについてです。8月15日、浸水直後の年金支給日に大幅な介護保険料の引き上げがあり多くの高齢者が生活できなくなると怒りの声を上げています。市として介護保険料の引き下げを行うことが求められます。公約を破って保険料を引き上げた責任をどのように感じているのか。介護保険料の引き下げを求めて答弁を求めます。
寝屋川市は第5期介護保険料の決定に際して、大阪府に一般会計からの繰入を問い合せたところ、ダメだと言われたということで一般会計の繰入を諦めましたが、本当に繰入はできないのでしょうか。
2011年12月16日に 大阪府福祉部長から 各市町村にむけて 第5期介護保険料の設定について 通達が出ています。通達では第五期の介護保険料の設定については2011年7月に開催された「第5期介護保険事業計画の策定に係わる全国会議」で国の基本的考え方が示されており、保険料の算定に当たっての一般財源の繰り入れはいわゆる「三原則」に抵触することになる。被保険者以外の方への負担の転嫁、一般会計からの繰入の常態化による市町村の一般財源の圧迫等の問題が生じるので「三原則」の順守を求めています。
ここでいう「三原則」は単独減免に対する考え方であり
1保険料の全額免除
2収入のみに着目した一律減免
3保険料減免分に対する一般財源の投入
については適当ではないと厚生労働省が従前から行っていることをさしています。
しかし、あくまでもこれは保険料減免を対象に言っていることであり、この三原則をして一般会計からの繰入で保険料の引き下げをすることが減免をしたことと同じであると否定することは、市町村の裁量を否定するもので、市として独自の判断を求めたい。
厚生労働省の「2011年度の介護保険事務調査の集計結果」では全国の単独保険料減免実施保険者は520で内三原則を順守しているのが473と47の保険者が自らの基準で高齢者を守るべく施策を行なっています。一律判定による減免が7保険者、保険料全額免除をしている保険者が37、一般財源投入をしている保険者が12あることが示されています。そして、「三原則」に背いてもなんらペナルティがない。このことが重要です。2002年の国会論戦で、この「三原則」は単なる助言に過ぎず、「法律上の義務というものではない」との答弁を引き出し、自治体が「助言や勧告」に従う義務がないことを明らかにさせています。
寝屋川市が寝屋川の高齢者の生活を守るため、独自に一般会計を繰入、介護保険料の引き下げをすることにはなんら問題はありません。市長が自らの公約を守ることを、市として高齢者の生活を守るために一般会計繰入で介護保険料の引き下げを行うことを求めて、答弁を求めます。
介護保険の広域化についてです。8月9日の大阪府知事と市町村長の協議の場で介護保険の広域化が話されています。また、大阪府が、8月に「介護保険の広域化に関する研究会報告書」を公表しました。その内容は題名通り、現在「市町村」を保険者として運営されている介護保険制度を、大阪府全体で「一つの保険者」とし、「単一の保険料」で運営しようというものである。
しかし、後期高齢者医療制度を見ても、介護保険のくすのき連合を見ても、市民から保険者が遠くなり、基礎自治体が責任を果たすことができなくなる広域化は問題です。
現在、寝屋川市は大阪府下平均より介護保険料は少し低いですが、一律保険料となると上昇は避けられません。大阪府が進めている介護保険の広域化に対して市として反対の立場を取ることを求めて答弁を求めます。
その他
水に親しむことができる公園での警報のあり方について、
今年の夏も大変熱く、多くの子どもたちが川で遊ぶ姿を目にしました。市民プールの廃止で行くところがなくなったのでしょうか。寝屋川市駅前の親水公園ではシュノーケルをつけて水着で泳いでる姿まで見られました。流石に危ないよと声をかけ、泳ぐことは止めてもらいました。また、幸町公園の親水部分でも水着で遊んでいる子どもたちを見かけました。
そんな中で、大雨洪水注意報、警報が出た場合の公園で遊んでいる人たちへの危険の知らせ方です。駅前の親水公園では放送が流れて警報ランプが回りつづけています。幸町公園では放送が流れてランプが回りますが、5分ぐらいで停止をして、30分後に再び放送しランプが5分程度回るようになっているようです。急激な天候の変化で大雨が降り注意報や警報が出てもすぐに雨が止むと子どもたちは再び遊んでしまします。
実際、夕立で警報が出て公園を見に行きますと、4.5人の子どもたちが増水した川で遊んでいる姿が見えました。子どもたちに聞きますと、「なんか言うてランプが回っていたけど、止まったからもう大丈夫」と応えてくれました。まだ大雨注意報が出てるし危ないから今日は水から上がってくださいと注意を促すと、「そうするわ」と帰って行きましたが、子どもたちに間違った理解を与えかねない、注意の与え方については改めるよう、求めます。大阪府が管理をしていて今年度中には改善が図られるとも聞いていますが、改善が図られるまで市として安全を確保するように努力を求めて答弁を求めます。
全員協議会でも明らかにされましたが、前日、午後10時の大雨洪水警報発令から寝屋川市では職員24人の体制が取られています。14日早朝5時半から6時半にかけて時間雨量100ミリを超える豪雨が降りました。今回のこの豪雨をどのようにして市民に知らせ、注意喚起を行ったのかは大変重要なことです。
大雨の中多くの市民の方から連絡を受けて市内各所を見て回りましたが、浸水に対応をしている市民の方がいる一方で、未だ気づかずにいるのか、お盆で帰省をしているのか、浸水の最中に全然対応をしていない家庭も見受けられました。
浸水後にお話を聞いているとなんのための防災無線なんだ。なんのための緊急連絡メールなんだと豪雨が降っている最中に市からの情報提供が行われなかったことに対するお叱りの声を多数聞きました。そこでお聞きします。
地域防災計画では 3 . 住民への周知で 市は、必要に応じ、防災行政無線、広報車、警鐘、サイレン等を利用し、又は状況に応じて自主防災組織などの住民組織と連携して、住民に対して予警報等を伝達するとともに、予想される事態とそれに対してとるべき措置について周知する。なお、周知に当たっては、災害時要援護者に配慮する。とされています。
残念ながら今回の浸水で防災行政無線、広報車、警鐘など、浸水時には全然活用されませんでしたが、かつて寝屋川を襲ったことがない大雨が来ても活用されないとなると、どのような状況で活用されるのか大変不安になります。活用をする基準を明らかにして下さい。また、判断をする責任者は防災計画ではだれにあたり、今回は誰が判断したのかもお答えください。今後、被害を少しでも食い止めるために地域防災計画を活かした住民への周知を求めます。また、特に広報車の活用を求めます。今回の災害の中では活動していないようでしたが、防災無線とあわせて被害が大きく出ている地域での特別な広報もまた必要です。今回どのような広報活動を行ったのか。また今後の活用についてもお答えください。
またメールねやがわの活用です。今回の災害ではメールねやがわを活用して情報提供が全くなされていません。被害の状況、消毒、ゴミ、罹災証明に見舞金と市民知りたい、市民に伝えるべき情報は多くあったのではないでしょうか。そんな中で、大雨ののちに最初に送られたのが8月16日の大阪の食育週間を伝えるものでがっかりしました。翌日には職員採用の案内です。どちらも大切なお知らせであると思いますが、市民のニーズにあったものではなかったと考えます。
14日の大雨が降っている最中に、注意喚起する安全安心メールの送信、その後の情報提供のメールが必要であったと考えます。今後、様々な震災に対してメールねやがわの活用は行われるのか。今回何故全く活用されなかったのか明らかにして下さい。
平成24年3月の寝屋川市の避難勧告等の判断・伝達マニュアル(水害編)では浸水被害に備えた基準では市域に大雨警報が発表され、かつ10分間観測雨量が20ミリを超え、それを含む一時間観測雨量が50ミリを超えたときを一時避難情報の発令をする基準としています。今回の豪雨では一時避難情報が流れたとはきいていません。なぜマニュアルと違う対応が取られたのか。今後の対応とあわせて答弁を求めます。
集中豪雨で床下から床上浸水と水かさが増えていく中で多くの市民が市役所に助けを求めて電話をかけていますが、多くの市民の方から全然繋がらなかった、混み合っているので後ほどおかけくださいとテープがこたえるなど、市役所に連絡をすることさえできなかった実情がみえてきました。そこで、多くの電話が混み合う中で当日特別な手立てが必要であったお考えます。大規模災害時の職員の招集、臨時電話などの体制づくりが早急の課題です。今回行われた対策と今後の対策についてお答えください。
避難誘導の体制です。床上浸水など避難が必要な市民が今回でています。全員協議会では2世帯4名のコミセンへの避難が報告されましたが、近所の公民館やお寺などに避難をした話も伺っています。道路が冠水をしているなか、避難が必要な市民をどのようなかたちで誘導をしたのか。今回、避難をしたいと市へ連絡をした方が、避難場所を伝えてくれただけでなにもしてくれなかったと不満を述べておられるのをききました。現実問題として、高齢者の方に冠水をした道路の移動は困難であると言わざるを得ません。実際に避難を求めた市民にどのような対応を取ることができたのか。今後どのように対応を検討しているのか明らかにして下さい。
道路の冠水についてです。市内全域で道路が冠水し警察や市が通行止めを行なっていましたが、すべての危険箇所の通行止めは残念ながらできていません。市民の方々からは通行止めにして欲しかったというお話も沢山頂きました。そんな中には、冠水した道路を車が通るたびに大きな波が起こり床上浸水となってしまった。また、バイクが波で転倒して水没してしまったなど、冠水をした道路を車が通ることでの被害の拡大を訴える声やマンホールの蓋があく、側溝の蓋が流れるなど、冠水した道路を移動することは大変な危険を伴うのでしっかりと止めて欲しいとの声もありました。通常道路の通行止は警察の判断でしょうが、手が足りなかったことも明らかです。私も警察へ電話をさせていただきましたが、人命救助が優先になっています。大きな幹線道路から冠水した道路の通行止を行なっていますのでご理解をとききました。現実に手が足りない中で、地域、自治会の判断で目の前の道路の通行止めをすることができるような体制づくりも必要ではないでしょうか。
通行止めが早急に行われていれば出ることがなかった被害に対する保証はどのように考えているのか。
目の前の道路の冠水、そしてその波で被害が出ている家庭や地域で車の通行を止めることができるのか。市としての対応ができるのかお答えください。
土嚢の配布についてです。大雨になり道路の冠水や家屋への浸水が見られるときに下水道室は市民の要望に応えて土嚢の配布を行なってくれています。しかし、今回の大雨では残念ながら市民の要請に全て応えることはできなかったと思いますが、下水道室は当日、浸水被害を訴える市民にどれだけの土嚢を配布することができたのか、お答えください。また、浸水後も今後の為と土嚢を求める市民の声がかなりあったと聞いていますが、今現在で配布した数をお示しください。今後、今回のような大雨が降りますと地域、自治会単位などでの土嚢の配布などが現実的な課題となりますが、市の考えをお答えください。
防災計画では 1 . 災害時の配備体制の概要市は市域内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害を最小限にとどめるための災害応急対策を迅速・適切に実施する必要がある。そのため、市長は、自らを本部長として、市に「寝屋川市災害対策本部」を設置して職員の動員配備を行い、活動体制を確立する。また、災害対策本部が設置される前、又は災害対策本部を設置するに至らない場合で必要があると認めるときは、「災害警戒本部」を設置し、被害情報の把握、調査、市民の避難や応急処理など小規模な災害の発生に対処する体制をとる。なお、本部体制の実施に備え、気象情報等及び災害情報を収集するための体制として、「気象情報等収集体制」を設ける。
となっています。かつてない豪雨災害が起きたにもかかわらず災害対策本部が設置されないとなると防災計画の根本が問われます。防災計画の災害対策本部の設置基準ではイ. 災害救助法の適用を要する災害が発生したときとしています。今回の災害は災害救助法に該当する被害が発生した市町村における自然災害に該当するということで寝屋川市は国から被災者生活再建法の適用を受けました。14日には、朝の6時から夜10時まで200名を超える職員体制で当たったとされていますが、なぜ寝屋川市災害対策本部が設置されなかったのかお答えください。
豪雨後の対応についてです。
豪雨が止み、水が引いて多くの市民の方が、家の片付け、ゴミ出し、家屋、道路の消毒に取り掛かりました。
まず、消毒についてですが、道路の消毒について市民から、私道は自分で消毒してくださいと対応を断られたと聞きました。また、その後公共の施設につながる道であることを伝えると消毒に来た。との話を聞きましたが、私道と市道、府道などの消毒はどのような基準で消毒を行ったのか。対応に差があったと聞いていますが、散布の範囲をお答えください。
今回は市が個別に消毒をすると相当な期間が要するため消毒液の無料配布による各戸対応をお願いしたとされていますが。消毒薬の噴霧器についてはどのような対応がなされたのか。また、消毒についても自治会単位で消毒薬の配布が行われていますが、自治会に入っておられない方もいます。自治会には679本93地域に配布したとなっていますが、個別に連絡があった部分の対応はどのようになったのか明らかにして下さい。今回危機管理室に各自治体から消毒薬を取りに来ている姿も見受けられましたが、各コミセンや市民センターなどで配布をする体制の検討を求め答弁を求めます。
ゴミの収集についてです。大きな畳等のゴミは各戸個別に収集、小さなゴミは自治会で集積所をきめて回収されていきました。他市ではリサイクル料をとったところもあると聞いていますが、素早く、浸水ゴミは無料で対応して頂いたことは評価をしたいと思います。しかし、平常のごみ収集と震災ゴミの収集で一部混乱もあったと聞いています。委託業者の対応も含めて市民との混乱を招くことがないよう、今後の対策を求め答弁を求めます。
市民が市役所に被災証明の申請に殺到しました。早いうちに待合室の設置など体制が整えられたことは評価します。しかし、こんな時こそ市民センターなど市内各地で、被災証明の発行申請を行えるように職員の配置をすべきであったと思います。今後の改善を求め答弁を求めます。
被害調査の職員の訪問についてです。多くの職員が本当に頑張って頂いたことを知っていますが、一部配慮のない言葉によって被災した市民が更に辛い思いをしたとの話も聞きました。被災された方は普段のより更に繊細になっておられます。市職員の訪問時のマニュアル等の改善を求めます。
被害の全貌の把握です。被災証明を申請した方については訪問調査をしていますので正確な場所と件数が出てきますが、床下浸水で特に被害が出なかった場所の特定は不十分ではないでしょうか。14日には自治会長へ電話による被害状況の確認が行われていますが、市として今回の被害の全貌を、今後の対策を立てるためにもしっかりと調査することを求め答弁を求めます。
8月18日(金)3回の防災無線の放送が行われました。ようやく浸水に関することで防災無線の活用がされたわけですが、内容は土日の市庁舎の開庁と消毒薬の配布のお知らせでした。しかし、残念なことにこの放送も多くの市民に届いていません。聞こえていない人、聞こえても内容がわからなかった人など、ほとんどその役目を果たしていなかったのではないでしょうか。今一度、防災無線の活用のしかた。全域に放送が届くような調整をお願いし、答弁を求めます。
今後の対策
100年に一度の雨と言いながら香里園のゲリラ豪雨から4年で今度は市域全域に再び100年に一度の雨が降りました。想定外でなくなった雨に対して寝屋川流域下水の計画の見直しが必要ではないでしょうか。現在、計画中の増補幹線、雨水貯留地の早期の工事の完了を求め、想定雨量40ミリの大幅な引き上げが必要です。関係11市の協議を早急に行うことを求めて答弁を求めます。
そして全体の協議を待つことなく寝屋川市としてできる対策に取り組むことを求めます。被災された市民の方は、具体的な様々な意見を持っておられます。市として意見徴収に取り組み、地域ごとに小規模な貯留地やポンプでの排水設備など市ができる浸水対策を行なうことを求め答弁を求めます。
今回の豪雨では寝屋川市駅周辺の冠水が大変な状況となりました。今回京阪電車もとまり、駅に行っても乗車できなかったワケですが、それでも多くの市民がびしょびしょになりながら駅に向かって行きました。寝屋川市駅は寝屋川市の玄関口です。大雨が降るたびに駅周辺で道路が冠水していることは、特別な対策も必要です。市の見解をお伺いします。
避難場所について寝屋川市のHPを見ますと、災害時の避難場所、洪水時の避難場所が指定されています。今回のような集中豪雨による浸水被害は、淀川や寝屋川流域の川の氾濫による洪水とも被害の現れ方が異なっているのではないでしょうか。であるならば、新たな避難場所の設定が求められます。避難場所の設定をどのように考えているのかお示しください。
地域防災計画が見直しされます。今回の集中豪雨の経験を活かした計画策定となるよう求め答弁を求めます。
1 介護保険について
保険料の引き下げについてです。8月15日、浸水直後の年金支給日に大幅な介護保険料の引き上げがあり多くの高齢者が生活できなくなると怒りの声を上げています。市として介護保険料の引き下げを行うことが求められます。公約を破って保険料を引き上げた責任をどのように感じているのか。介護保険料の引き下げを求めて答弁を求めます。
寝屋川市は第5期介護保険料の決定に際して、大阪府に一般会計からの繰入を問い合せたところ、ダメだと言われたということで一般会計の繰入を諦めましたが、本当に繰入はできないのでしょうか。
2011年12月16日に 大阪府福祉部長から 各市町村にむけて 第5期介護保険料の設定について 通達が出ています。通達では第五期の介護保険料の設定については2011年7月に開催された「第5期介護保険事業計画の策定に係わる全国会議」で国の基本的考え方が示されており、保険料の算定に当たっての一般財源の繰り入れはいわゆる「三原則」に抵触することになる。被保険者以外の方への負担の転嫁、一般会計からの繰入の常態化による市町村の一般財源の圧迫等の問題が生じるので「三原則」の順守を求めています。
ここでいう「三原則」は単独減免に対する考え方であり
1保険料の全額免除
2収入のみに着目した一律減免
3保険料減免分に対する一般財源の投入
については適当ではないと厚生労働省が従前から行っていることをさしています。
しかし、あくまでもこれは保険料減免を対象に言っていることであり、この三原則をして一般会計からの繰入で保険料の引き下げをすることが減免をしたことと同じであると否定することは、市町村の裁量を否定するもので、市として独自の判断を求めたい。
厚生労働省の「2011年度の介護保険事務調査の集計結果」では全国の単独保険料減免実施保険者は520で内三原則を順守しているのが473と47の保険者が自らの基準で高齢者を守るべく施策を行なっています。一律判定による減免が7保険者、保険料全額免除をしている保険者が37、一般財源投入をしている保険者が12あることが示されています。そして、「三原則」に背いてもなんらペナルティがない。このことが重要です。2002年の国会論戦で、この「三原則」は単なる助言に過ぎず、「法律上の義務というものではない」との答弁を引き出し、自治体が「助言や勧告」に従う義務がないことを明らかにさせています。
寝屋川市が寝屋川の高齢者の生活を守るため、独自に一般会計を繰入、介護保険料の引き下げをすることにはなんら問題はありません。市長が自らの公約を守ることを、市として高齢者の生活を守るために一般会計繰入で介護保険料の引き下げを行うことを求めて、答弁を求めます。
介護保険の広域化についてです。8月9日の大阪府知事と市町村長の協議の場で介護保険の広域化が話されています。また、大阪府が、8月に「介護保険の広域化に関する研究会報告書」を公表しました。その内容は題名通り、現在「市町村」を保険者として運営されている介護保険制度を、大阪府全体で「一つの保険者」とし、「単一の保険料」で運営しようというものである。
しかし、後期高齢者医療制度を見ても、介護保険のくすのき連合を見ても、市民から保険者が遠くなり、基礎自治体が責任を果たすことができなくなる広域化は問題です。
現在、寝屋川市は大阪府下平均より介護保険料は少し低いですが、一律保険料となると上昇は避けられません。大阪府が進めている介護保険の広域化に対して市として反対の立場を取ることを求めて答弁を求めます。
その他
水に親しむことができる公園での警報のあり方について、
今年の夏も大変熱く、多くの子どもたちが川で遊ぶ姿を目にしました。市民プールの廃止で行くところがなくなったのでしょうか。寝屋川市駅前の親水公園ではシュノーケルをつけて水着で泳いでる姿まで見られました。流石に危ないよと声をかけ、泳ぐことは止めてもらいました。また、幸町公園の親水部分でも水着で遊んでいる子どもたちを見かけました。
そんな中で、大雨洪水注意報、警報が出た場合の公園で遊んでいる人たちへの危険の知らせ方です。駅前の親水公園では放送が流れて警報ランプが回りつづけています。幸町公園では放送が流れてランプが回りますが、5分ぐらいで停止をして、30分後に再び放送しランプが5分程度回るようになっているようです。急激な天候の変化で大雨が降り注意報や警報が出てもすぐに雨が止むと子どもたちは再び遊んでしまします。
実際、夕立で警報が出て公園を見に行きますと、4.5人の子どもたちが増水した川で遊んでいる姿が見えました。子どもたちに聞きますと、「なんか言うてランプが回っていたけど、止まったからもう大丈夫」と応えてくれました。まだ大雨注意報が出てるし危ないから今日は水から上がってくださいと注意を促すと、「そうするわ」と帰って行きましたが、子どもたちに間違った理解を与えかねない、注意の与え方については改めるよう、求めます。大阪府が管理をしていて今年度中には改善が図られるとも聞いていますが、改善が図られるまで市として安全を確保するように努力を求めて答弁を求めます。