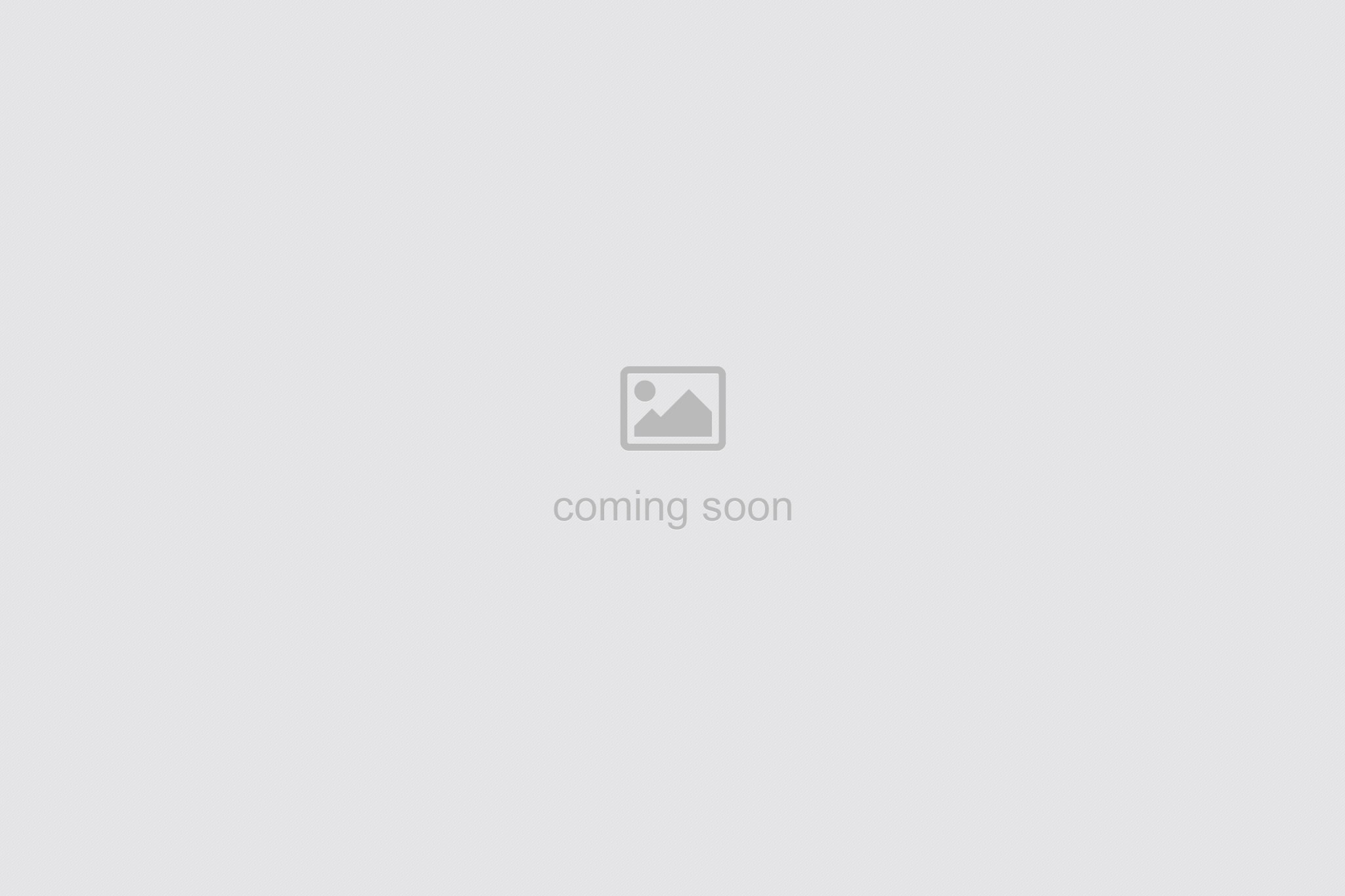6月議会 一般質問 中谷市議
2013-06-27
【教育について】です。
教育長が替わられたこともあり、教育行政の基本についてお聞きします。
今年2月の教育委員会定例会で、1月・2月の一般事務報告を受けて、各委員が各行事に参加した感想を積極的に取り組みの成果だと評価して述べ合っています。その意見交換の最後に述べた、前教育長の言葉に驚きました。「子どもを守る市民集会」に参加されていた自治会長から、校区の中学校について「教育長が・・・いたとき以上に良くなってきましたね」と言ってもらったことを紹介したうえで、「株式会社寝屋川教育にすれば、たくさん営業結果が出たかなという思いであります。」との発言です。
言うまでもなく、教育は、基本的人権の中でも社会権といわれる生存権的権利として定められた重要な権利に基づくものです。社会権には、25条の生存権、26条の教育を受ける権利、27条の勤労の権利、28条の勤労者の団結権などが該当します。福祉や教育の分野が、利潤追求になじまないとされてきた理由でもあります。近年、国や自治体の事業についても、民営化が推進されるとともに、民間企業と同じような考え方を基本に据えようとする動きが強まっています。寝屋川市の一般行政にもその姿勢は顕著ですが、教育行政まで利潤追求の株式会社の発想でおこなわれてきたことに、憤りを禁じ得ません。「ナンバーワンよりオンリーワン」のスローガンを掲げ、すべての学校に特色づくり競争を押しつけてきた「ドリームプラン」をはじめ、全国学力テストの成績結果トップの秋田県の学校に勝つことまで目標にするとしてきた市教委の姿勢がどこから来ていたのか、各校長が掲げた「ていねいに鍛えてめざすは全国一」の発信源は前教育長だと感じました。2つの小学校の廃校から始まった「小中一貫教育」、小学校1年生からの英語教育、民間の財団法人がおこなう個人の任意にもとづく英語検定受検率を学校教育の成果指標にする異常、そしていつの間にか、ドリームプランは12学園構想へと変わりました。この10年間で教職員の構成も大きく変わりました。同時に、勤務実態も過酷になったと学校間格差はかなりあるものの例外なく聞く言葉です。夜の8時9時はあたりまえ、一部の学校では、大きな行事がある前は、連日、終電車に間に合うかどうか、乗り遅れれば、タクシーでの帰宅と言います。テストなどの個人情報を校外に持ち出せないことから、土曜、日曜の休日出勤も良くあると言います。時には、子ども連れで学校で仕事をする人もいます。すべて、無給です。子どもたちに健康な生活のあり方を教えるためにも、過労死があたりまえのような働き方はなくすべきです。
株式会社の考え方で、これからの寝屋川の教育を進めていくのかどうか、新教育長の答弁を求めます。また、「小中一貫教育」をはじめ、英語教育や英検を学校教育の成果指標とする検証、ドリームプランなどを教育的に検証した報告書はありますか。あれば、明確にして下さい。
次に、教育長に、あらためて「教育の目的」と「教育における教育行政の責務と役割」をどう考えているのか、明快な答弁を求めます。
次に【東部まちづくりについて】です。
今回の質問にあたって、私が2006年(平成18年)9月議会でおこなった「第二京阪道路などの道路整備と東部地域の開発の動きについて」の質問に対して、2007年2月28日と4月25日の2回にわたって、当時の「寝屋川市東部まちづくり連合会」から「求釈明書」、「再求釈明書」が送られてきたことを思い出しています。その後、私に「話し合いの申し入れ」があり、8月13日付けで議員団として、話し合いの前提としての資料提供、双方の代表による持ち方の協議・合意を条件とするなどの「回答」をして後は、来なくなりました。その後、「連合会」から打上新町・小路北町第2・明和の3自治会が別に東部自治会を結成し、「寝屋川市東部まちづくり連合会」が市から借りていた旧第2解放会館を、平成22年9月1日から27年3月31日まで「東部自治会館」として借りるようになっています。3自治会には自治会館があると思いますが、市財産の目的外使用を認めた理由は何ですか。また、使用状況はどうなっていますか。
寝屋川市は、「東部まちづくり連合会」や「東部道路整備検討会」について、市民との協働のまちづくりを進める市の協力組織との答弁をしています。現在、市が「支援」と称して進めている「地域特性を活かしたまちづくり」、「ふるさとリーサム地区まちづくり」まで、これまで、市が参加してきた会議の最初の日程と回数、頻度をそれぞれに明らかにして下さい。また、当初から参加してきた理由、法的根拠があれば明らかにして下さい。
次に、平成23年度、24年度と「地域特性を活かしたまちづくり活動支援等業務」をコンサルタント業者に委託して、寝屋川市はおこなっていますが、その法的根拠は何ですか。
次に「ふるさとリーサム地区まちづくり」についてお聞きします。
「まちづくり協議会」の発足にあたって、地権者に案内がおこなわれ、昨年9月の総会では、司会進行から、規約提案、活動計画提案、質疑に対する応答のすべてにわたって市の職員がおこなっています。これでどうして地権者の自主的な組織と言えるのでしょうか。ここまで関与する理由は何ですか。「まちづくり」は地域に住む住民がおこなうものです。都市計画法でいう「権利者」は土地所有者・家屋所有者・借地人です。リーサム地区の「まちづくり協議会」の地権者とは誰のことをいうのですか。市が案内した地権者数を明らかにして下さい。また、対象地域の住民の世帯数を明らかにして下さい。私のところに、借地・借家人の方から、自分たちは対象外にされていると、不安と怒りの声が寄せられています。市が進める「市民との協働によるまちづくり」に照らしての見解を明確にお答え下さい。
次に、ふるさとリーサム地区の「まちづくり整備計画」についてです。今年2月の第2回総会で「整備計画」が承認されたとして、「まちづくり協議会」から市に要望書が出ています。しかし、総会に参加された方々から、多くの問題点が指摘されています。総会冒頭に、「打上新町地区代表」を自称する女性が、「協議会」から依頼されたとして、要旨、次のように述べたと言います。「第二京阪道路が開通したのに、自分たちの土地評価額は上がっていない。土地評価額を上げることをめざす有志の集まりみたいな感じで、まちづくり協議会をたちあげている。反対とか、絶対に嫌という人は退場してもらって結構」というものです。ずばり本音が出ていると思います。総会は発言を求めて挙手していた参加者が残っているにもかかわらず、時間がないと認められないまま、採決を3回繰り返したといいます。最初の挙手は少数で、本来なら提案が否決されていたといいます。市はこの事実を認めますか。
寝屋川市は、「リーサム地区担当」として明記されている役職者だけで4人を配置しています。「市営住宅担当」を加えれば8人です。都市計画道路東寝屋川駅前線なども含めれば、10人を超える体制になります。
寝屋川市は、「ふるさとリーサム地区 まちづくり整備計画(案)」を3月に策定しています。昨年度の「まちづくり構想(案)」はどこが策定したものですか。
本年度、「優先的にまちづくりに取組むエリア」に位置づけられた「まちなか再生エリア」、「団地再生エリア」を中心に具体的な事業化に向けた検討を行い、「ふるさとリーサム地区まちづくり整備計画(案)」を作成したとしています。市と地元との協働の結果と聞きます。「優先的」とされた理由を明らかにして下さい。また、計画推進の庁内検討組織とその状況、地元の組織とその状況を明らかにして下さい。「まちなか再生エリア」の整備を市の事業としてすすめる法的根拠は何ですか。
地元からの要望に応えて市は地籍調査に取り組もうとしています。幅員6mの道路整備工事、家屋の補償費・解体費、借地・借家人の立ち退きなど、住民合意がない問題点があまりにも多くあります。地籍調査の実施が既成事実として、問題を残したまま事業の促進にならないよう、地主や家主に限定した地権者でなく、あくまでも地域住民が安心して住み続けられるまちづくりを目標に、住民合意を基本に慎重であるべきと考えます。住民の中には、通路の確保もない状態でつくられている墓地の整備を望む声も強くあります。市に見解をお聞きします。
次に市営住宅についてです。耐震性や老朽化、居住性の向上などを考慮して、寝屋川市内のすべての市営住宅をどうするのか、今後の事業計画を明らかにして下さい。そのことをふまえ、「団地再生エリア」についてお聞きします。
昭和40年代に建設された明和住宅は、老朽化や住宅の規模・設備、とくに高齢化の中、風呂やエレベーターがないなど、居住性に課題を抱えています。住民の願いは安全・安心に快適な居住空間に住み続けられるようになることです。「構想(案)」では、入居者の仮移転、除去の後、南側に200戸予定の建替住宅棟を建設し、入居者の移転をおこない、古い住宅棟を除去した後、再生整備計画を検討するとしています。住宅が不足する場合は借上住宅で対応するとしています。しかし、地域住民の中には、明和小学校の西にある入居率が高い北側の5つの住宅棟と、さらにその西隣にある4つの住宅棟、計208戸は、JR東寝屋川駅にも近く、買い物などの便も良く、建設年度も団地の中では新しく、耐震補強やエレベーターの設置、浴室整備などをおこなって活かしていくべきとの声もあります。また、除却後の跡地活用について、老人ホームなどの福祉施設などを望む声もあります。すでに民間が建設の動きもあります。市の見解をお聞きします。
次に、小中一貫校の整備検討についてです。「構想(案)」では、既存校舎を活用した施設連携型をイメージ(案)として検討しています。梅が丘小学校、第4中学校の廃校を前提にしたこうした計画は、(案)であっても、市が決める前に、こども・保護者・地域住民の意見をていねいにしっかりと聞くことです。梅が丘地域の人からは、自治会の会議の中で尋ねたが、自治会長からは「そんな計画はまったくない」と言われたとの声が寄せられています。関係者への情報提供を含め、現状はどうなっていますか。こども・保護者・教職員・地域住民不在の事業計画、事業推進などは絶対に許されないと考えます。見解をお聞きします。
次に、東寝屋川駅前線沿道まちづくり整備計画(案)についてです。大阪府が新規の道路建設を認めないとの姿勢にあることから、沿道区画整理型街路事業か土地区画整理事業として具体化する検討がおこなわれています。地域の声を聞いても、昨年より事業化の動きがすすんでいると感じています。道路建設のために一体的な開発優先行政ではなく、値打ちのある古い建物、街並みを保存しながら、住民が論議し納得ずくで、住み続けることができる「安心・安全なまちづくり」をすすめることを基本とする。そうした姿勢こそ、行政がおこなう「まちづくり」支援に重要と考えます。見解をお聞きします。
また、今回の「構想(案)」では、跡地活用部会による公共施設の整理計画の検討も示されています。1981年2月に公正で民主的な同和行政を求める市民団体が発行した「寝屋川市の同和行政-現状と今後の課題」をふり返ってみると、〈現状と問題点〉の最後に、「しかし、地域の実態からいって、このような多くのデラックスな施設をつくることが、部落差別の解消に役立ったのか、大変疑問です。」と記しています。また、〈提案〉では、「最優先に実施すべき事業-地区内の道路建設を中心とした環境改善事業」とし、「路線バスが往来できる幹線道路を中心とした道路建設は、地域の生活改善や防災に役立つとともに、地区外住民との社会的交流を促進し、部落問題の解決に貢献することは明らかです。そして、これにともない、上・下水道、都市ガス、駐車場の整備を進めることです。当面、小路笠松線、木田国守線の完成をいそぐべきであります。この事業の推進にあたっては、地区住民の納得と合意をえておこなうことが必要です。」と記されています。
教育長が替わられたこともあり、教育行政の基本についてお聞きします。
今年2月の教育委員会定例会で、1月・2月の一般事務報告を受けて、各委員が各行事に参加した感想を積極的に取り組みの成果だと評価して述べ合っています。その意見交換の最後に述べた、前教育長の言葉に驚きました。「子どもを守る市民集会」に参加されていた自治会長から、校区の中学校について「教育長が・・・いたとき以上に良くなってきましたね」と言ってもらったことを紹介したうえで、「株式会社寝屋川教育にすれば、たくさん営業結果が出たかなという思いであります。」との発言です。
言うまでもなく、教育は、基本的人権の中でも社会権といわれる生存権的権利として定められた重要な権利に基づくものです。社会権には、25条の生存権、26条の教育を受ける権利、27条の勤労の権利、28条の勤労者の団結権などが該当します。福祉や教育の分野が、利潤追求になじまないとされてきた理由でもあります。近年、国や自治体の事業についても、民営化が推進されるとともに、民間企業と同じような考え方を基本に据えようとする動きが強まっています。寝屋川市の一般行政にもその姿勢は顕著ですが、教育行政まで利潤追求の株式会社の発想でおこなわれてきたことに、憤りを禁じ得ません。「ナンバーワンよりオンリーワン」のスローガンを掲げ、すべての学校に特色づくり競争を押しつけてきた「ドリームプラン」をはじめ、全国学力テストの成績結果トップの秋田県の学校に勝つことまで目標にするとしてきた市教委の姿勢がどこから来ていたのか、各校長が掲げた「ていねいに鍛えてめざすは全国一」の発信源は前教育長だと感じました。2つの小学校の廃校から始まった「小中一貫教育」、小学校1年生からの英語教育、民間の財団法人がおこなう個人の任意にもとづく英語検定受検率を学校教育の成果指標にする異常、そしていつの間にか、ドリームプランは12学園構想へと変わりました。この10年間で教職員の構成も大きく変わりました。同時に、勤務実態も過酷になったと学校間格差はかなりあるものの例外なく聞く言葉です。夜の8時9時はあたりまえ、一部の学校では、大きな行事がある前は、連日、終電車に間に合うかどうか、乗り遅れれば、タクシーでの帰宅と言います。テストなどの個人情報を校外に持ち出せないことから、土曜、日曜の休日出勤も良くあると言います。時には、子ども連れで学校で仕事をする人もいます。すべて、無給です。子どもたちに健康な生活のあり方を教えるためにも、過労死があたりまえのような働き方はなくすべきです。
株式会社の考え方で、これからの寝屋川の教育を進めていくのかどうか、新教育長の答弁を求めます。また、「小中一貫教育」をはじめ、英語教育や英検を学校教育の成果指標とする検証、ドリームプランなどを教育的に検証した報告書はありますか。あれば、明確にして下さい。
次に、教育長に、あらためて「教育の目的」と「教育における教育行政の責務と役割」をどう考えているのか、明快な答弁を求めます。
次に【東部まちづくりについて】です。
今回の質問にあたって、私が2006年(平成18年)9月議会でおこなった「第二京阪道路などの道路整備と東部地域の開発の動きについて」の質問に対して、2007年2月28日と4月25日の2回にわたって、当時の「寝屋川市東部まちづくり連合会」から「求釈明書」、「再求釈明書」が送られてきたことを思い出しています。その後、私に「話し合いの申し入れ」があり、8月13日付けで議員団として、話し合いの前提としての資料提供、双方の代表による持ち方の協議・合意を条件とするなどの「回答」をして後は、来なくなりました。その後、「連合会」から打上新町・小路北町第2・明和の3自治会が別に東部自治会を結成し、「寝屋川市東部まちづくり連合会」が市から借りていた旧第2解放会館を、平成22年9月1日から27年3月31日まで「東部自治会館」として借りるようになっています。3自治会には自治会館があると思いますが、市財産の目的外使用を認めた理由は何ですか。また、使用状況はどうなっていますか。
寝屋川市は、「東部まちづくり連合会」や「東部道路整備検討会」について、市民との協働のまちづくりを進める市の協力組織との答弁をしています。現在、市が「支援」と称して進めている「地域特性を活かしたまちづくり」、「ふるさとリーサム地区まちづくり」まで、これまで、市が参加してきた会議の最初の日程と回数、頻度をそれぞれに明らかにして下さい。また、当初から参加してきた理由、法的根拠があれば明らかにして下さい。
次に、平成23年度、24年度と「地域特性を活かしたまちづくり活動支援等業務」をコンサルタント業者に委託して、寝屋川市はおこなっていますが、その法的根拠は何ですか。
次に「ふるさとリーサム地区まちづくり」についてお聞きします。
「まちづくり協議会」の発足にあたって、地権者に案内がおこなわれ、昨年9月の総会では、司会進行から、規約提案、活動計画提案、質疑に対する応答のすべてにわたって市の職員がおこなっています。これでどうして地権者の自主的な組織と言えるのでしょうか。ここまで関与する理由は何ですか。「まちづくり」は地域に住む住民がおこなうものです。都市計画法でいう「権利者」は土地所有者・家屋所有者・借地人です。リーサム地区の「まちづくり協議会」の地権者とは誰のことをいうのですか。市が案内した地権者数を明らかにして下さい。また、対象地域の住民の世帯数を明らかにして下さい。私のところに、借地・借家人の方から、自分たちは対象外にされていると、不安と怒りの声が寄せられています。市が進める「市民との協働によるまちづくり」に照らしての見解を明確にお答え下さい。
次に、ふるさとリーサム地区の「まちづくり整備計画」についてです。今年2月の第2回総会で「整備計画」が承認されたとして、「まちづくり協議会」から市に要望書が出ています。しかし、総会に参加された方々から、多くの問題点が指摘されています。総会冒頭に、「打上新町地区代表」を自称する女性が、「協議会」から依頼されたとして、要旨、次のように述べたと言います。「第二京阪道路が開通したのに、自分たちの土地評価額は上がっていない。土地評価額を上げることをめざす有志の集まりみたいな感じで、まちづくり協議会をたちあげている。反対とか、絶対に嫌という人は退場してもらって結構」というものです。ずばり本音が出ていると思います。総会は発言を求めて挙手していた参加者が残っているにもかかわらず、時間がないと認められないまま、採決を3回繰り返したといいます。最初の挙手は少数で、本来なら提案が否決されていたといいます。市はこの事実を認めますか。
寝屋川市は、「リーサム地区担当」として明記されている役職者だけで4人を配置しています。「市営住宅担当」を加えれば8人です。都市計画道路東寝屋川駅前線なども含めれば、10人を超える体制になります。
寝屋川市は、「ふるさとリーサム地区 まちづくり整備計画(案)」を3月に策定しています。昨年度の「まちづくり構想(案)」はどこが策定したものですか。
本年度、「優先的にまちづくりに取組むエリア」に位置づけられた「まちなか再生エリア」、「団地再生エリア」を中心に具体的な事業化に向けた検討を行い、「ふるさとリーサム地区まちづくり整備計画(案)」を作成したとしています。市と地元との協働の結果と聞きます。「優先的」とされた理由を明らかにして下さい。また、計画推進の庁内検討組織とその状況、地元の組織とその状況を明らかにして下さい。「まちなか再生エリア」の整備を市の事業としてすすめる法的根拠は何ですか。
地元からの要望に応えて市は地籍調査に取り組もうとしています。幅員6mの道路整備工事、家屋の補償費・解体費、借地・借家人の立ち退きなど、住民合意がない問題点があまりにも多くあります。地籍調査の実施が既成事実として、問題を残したまま事業の促進にならないよう、地主や家主に限定した地権者でなく、あくまでも地域住民が安心して住み続けられるまちづくりを目標に、住民合意を基本に慎重であるべきと考えます。住民の中には、通路の確保もない状態でつくられている墓地の整備を望む声も強くあります。市に見解をお聞きします。
次に市営住宅についてです。耐震性や老朽化、居住性の向上などを考慮して、寝屋川市内のすべての市営住宅をどうするのか、今後の事業計画を明らかにして下さい。そのことをふまえ、「団地再生エリア」についてお聞きします。
昭和40年代に建設された明和住宅は、老朽化や住宅の規模・設備、とくに高齢化の中、風呂やエレベーターがないなど、居住性に課題を抱えています。住民の願いは安全・安心に快適な居住空間に住み続けられるようになることです。「構想(案)」では、入居者の仮移転、除去の後、南側に200戸予定の建替住宅棟を建設し、入居者の移転をおこない、古い住宅棟を除去した後、再生整備計画を検討するとしています。住宅が不足する場合は借上住宅で対応するとしています。しかし、地域住民の中には、明和小学校の西にある入居率が高い北側の5つの住宅棟と、さらにその西隣にある4つの住宅棟、計208戸は、JR東寝屋川駅にも近く、買い物などの便も良く、建設年度も団地の中では新しく、耐震補強やエレベーターの設置、浴室整備などをおこなって活かしていくべきとの声もあります。また、除却後の跡地活用について、老人ホームなどの福祉施設などを望む声もあります。すでに民間が建設の動きもあります。市の見解をお聞きします。
次に、小中一貫校の整備検討についてです。「構想(案)」では、既存校舎を活用した施設連携型をイメージ(案)として検討しています。梅が丘小学校、第4中学校の廃校を前提にしたこうした計画は、(案)であっても、市が決める前に、こども・保護者・地域住民の意見をていねいにしっかりと聞くことです。梅が丘地域の人からは、自治会の会議の中で尋ねたが、自治会長からは「そんな計画はまったくない」と言われたとの声が寄せられています。関係者への情報提供を含め、現状はどうなっていますか。こども・保護者・教職員・地域住民不在の事業計画、事業推進などは絶対に許されないと考えます。見解をお聞きします。
次に、東寝屋川駅前線沿道まちづくり整備計画(案)についてです。大阪府が新規の道路建設を認めないとの姿勢にあることから、沿道区画整理型街路事業か土地区画整理事業として具体化する検討がおこなわれています。地域の声を聞いても、昨年より事業化の動きがすすんでいると感じています。道路建設のために一体的な開発優先行政ではなく、値打ちのある古い建物、街並みを保存しながら、住民が論議し納得ずくで、住み続けることができる「安心・安全なまちづくり」をすすめることを基本とする。そうした姿勢こそ、行政がおこなう「まちづくり」支援に重要と考えます。見解をお聞きします。
また、今回の「構想(案)」では、跡地活用部会による公共施設の整理計画の検討も示されています。1981年2月に公正で民主的な同和行政を求める市民団体が発行した「寝屋川市の同和行政-現状と今後の課題」をふり返ってみると、〈現状と問題点〉の最後に、「しかし、地域の実態からいって、このような多くのデラックスな施設をつくることが、部落差別の解消に役立ったのか、大変疑問です。」と記しています。また、〈提案〉では、「最優先に実施すべき事業-地区内の道路建設を中心とした環境改善事業」とし、「路線バスが往来できる幹線道路を中心とした道路建設は、地域の生活改善や防災に役立つとともに、地区外住民との社会的交流を促進し、部落問題の解決に貢献することは明らかです。そして、これにともない、上・下水道、都市ガス、駐車場の整備を進めることです。当面、小路笠松線、木田国守線の完成をいそぐべきであります。この事業の推進にあたっては、地区住民の納得と合意をえておこなうことが必要です。」と記されています。