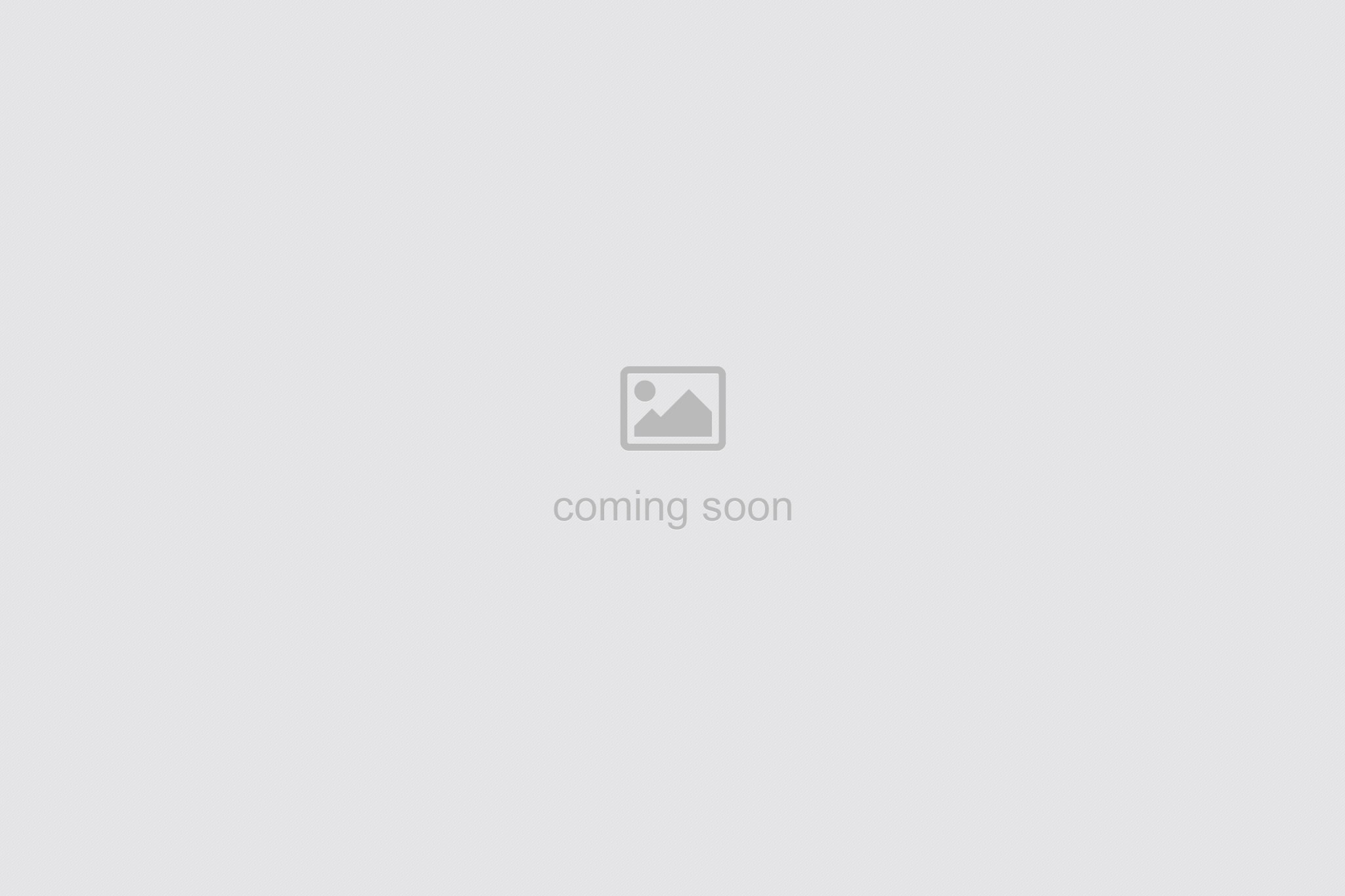2014年9月議会 一般質問 田中市議
2014-09-10
先ず、防災についてです。
はじめに集中豪雨、長雨によって広島の土砂、土石流災害でなくなられた方のご冥福をお祈りします。 ともに、被災されたみなさんにお見舞い申し上げます。
近年、気候変動の影響等により極端な豪雨が増える傾向があります。
20日未明に発生した広島市の土砂災害で死者73人の甚大な被害をもたらし、当初、約1500人が避難生活を送り、いまだに避難生活されている人が、9月9日夜時点、620人おられます。
土砂災害防止法は、1999年6月29日に広島県内で起きた、多発的な土砂災害をきっかけに、2000年に制定されました。土砂災害のおそれがある地域を都道府県が調査して、危険な場所は避難計画やハザードマップ作成が義務づけられる「土砂災害警戒区域」と建物の制限などができる「土砂災害特別警戒区域」に指定するなどされます。
土砂災害についてです
国土交通省によると、全国に52万307カ所ある土砂災害危険箇所のうち、土砂災害「警戒区域」に指定されているのは約35万5000カ所で、指定率は68%にとどまっています。
今回災害が起こった広島市の場合、花崗岩による風化土壌地域が多く、危険箇所は3万2000カ所に及んでいます。
広島市では土砂災害地域にも新規の住宅建設が多くみられ、それが災害の被害を増幅させたことは容易に推察できます。
土砂災害の対策として①住民に危険箇所を周知すること、避難対策を整備すること。②土石流の勢いを弱める砂防ダムなどの施設整備が必要です。
寝屋川市には市内東部の丘陵地で3カ所の土砂災害「特別警戒区域」と35カ所の土砂災害「警戒区域」があります。「警戒区域」とは土砂災害が発生した場合、土砂崩れなどで人命が危険にさらされる地域です。「特別警戒区域」は、さらに危険な区域で建築物の構造や宅地開発などが規制されます。いずれも都道府県が指定し、指定された地域の市町村は、土砂災害の危険性があることを住民に周知することが定められています。
そこで1. ①寝屋川市として土砂災害「特別警戒区域」、「警戒区域」の住民に危険の周知をはかること。②警戒避難体制の整備をはかること、③住宅等の新規建設の抑制をすすめるべきです。
2..広島市では「警戒地域」と指定されていないところでも、今回土砂災害におそわれています。寝屋川市においても、指定されていなくてもその危険性があるところはないのか、もう一度調査が必要と考えます。
以上2点について見解をお聞きします。
地域防災計画の見直しについてです。
2012年3月16日、大阪府は福井県内の4原発で福島第一原発級の大事故が発生したと想定し、滋賀県が独自に作成した放射性ヨウ素拡散予測による府内への影響を公表しました。気象条件などを変えた計106例の予測のうち、屋内退避が必要とされる100ミリシーベルト以上の地域が府内に生じる場合が1例、50~100ミリシーベルト未満の地域がでるケースが11例ありました。
関西広域連合は、福井県に15基ある原子力施設で災害が起き、30キロ圏内の住民が避難する場合、兵庫、大阪、徳島の3府県で約25万人の受け入れを決め、避難ガイドラインを作成しました。公民館など計600カ所に最長2ヶ月間避難し、長期化すれば民間住宅を借り上げる。今後避難時の放射能拡散や避難路渋滞への対策などを詰め、関係自治体が地域防災計画に盛り込むとしています。
1. 原発事故による災害の可能性、住民の避難計画などについて本市の地域防災計画に盛り込むべきですが、いかがですか。
私ども日本共産党市会議員団が今年取り組んだ市民アンケートで、防災についての市民の要望では、避難所の設備、備品の充実が一番多く、次に住宅・公共施設等の耐震化・不燃化の促進がつづきました。
災害用備蓄品について、寝屋川市では生駒断層地震の可能性をふまえて、現在合計で1日分、3万8千人分の物資が準備される方向です。
2. 今年度、保管場所を全小学校に拡大し、食料などの備蓄品を増加することは評価します。同時にまだまだ不足です。道路など運輸が途絶えて避難所だけでなく自宅での食品の蓄えが不足になる可能性もあり得ます。さらに物資、特に食料と飲料水の備蓄の拡充を求めます。
3.大阪府内7市で11カ所の木造密集市街地がある中で、寝屋川市は木造密集市街地が3カ所あります。阪神淡路大震災では、火災の6割が電気関係が原因でした。市民は大地震時ガスの火を消したり、元栓をしめても高い場所にあるブレーカーまで落とすことは困難です。
災害が起こった時点で木造密集市街地を中心に、多数の火災が同時に発生し、炎に囲まれて逃げられない。建物倒壊や渋滞で消防車も来られずに、多数の被害者がでるということが考えられます。
地震の後日でも出火する状況があります。火災予防のために分電盤に一定の震度を感知して電気を遮断する機能がつき、自動的に火災を防ぐ感震ブレーカー設置補助制度の創設を求めます。
以上3点について見解をお聞きします。
次に水道管の耐震化についてです。
1.第8期施設等整備事業計画の対象としている老化が著しい昭和40年までに布設された水道管の入れ替えを含めて耐震化を急ぐべきです。配水場の耐震化と合わせて早期に完了すべきと考えます。
2. また、水道管の入れ替えなどすすめるには人材と、費用の問題があります。工事監督の人材は特に重要です。土木関係の専門学科を修了して土木に関係する現場を3年経て監督の資格を得ることができます。大学・工専など土木関係専門学科卒業者の新規採用を行い、専門的な知識・技術等を継承すべきです。
以上2点について見解をお聞きします。
要支援者台帳についてです。
東日本大震災や阪神・淡路大震災の教訓では障害者の死亡率は健常者の2倍だったといわれています。災害弱者への支援は情報が伝わりにくい、また、伝わってもすぐに行動に移せません。寝屋川市は、今年に要支援者台帳の見直しをされるということですが、作成された時点では1人暮らしの高齢者・障害者など、より多くの高齢者・障害者を支援するために全ての自治会に要支援者台帳を渡すことをもとめます。お聞きします。
避難所についてです
1. 特別養護老人ホームの福祉避難所協定は進んでいますが、新たにグループホームや有料老人ホームなど福祉避難所が設置できるように申し入れをすすめるべきと考えます。
2. 広島市では、今回の土砂災害で飼い主にとって家族の一員である犬や猫などのペットと同居できるように、4カ所での避難所で40匹を受け入れました。ペットが苦手な人やアレルギーのある人への配慮も行い、校舎の端の教室を専用室にしています。
ペット連れの被災者向けにペットと同居できる避難所にすることを求めます。
以上2点について見解をお聞きします。
橋梁の長寿命化についてです。
市が管理している2メートル以上の橋269橋の現況調査が2年前に実施されました。市は橋梁長寿命化修繕計画を立て、今年度から10年間に67橋(橋の長さ15メートル以上31橋、15メートル未満36橋)の修繕をすすめていくとしています。説明では、橋桁が落ちるということはないと聞きましたが、震度6以上の揺れに耐えうるものなのか、また、ヒビ割れがひどくなれば危険だと考えられます。前倒しでの長寿命化を求め、見解をお聞きします。
次に児童虐待についてです。
2010年に寝屋川市で起きた当時1歳の三女に暴行を加えて死亡させたとして障害致死罪に問われ、父親懲役10年、母親懲役8年と上告審判決が7月24日、最高裁で言い渡されました。このような事件が繰り返されないよう、行政として手だてを打つべきです。
8月4日、厚生労働省調査では、2013年度、全国の児童虐待件数(速報値)前年度比7,064件増(10.6%増)で、7万3,765件にのぼることが明らかとなりました。
1990年度の調査開始以来、過去最多となりました。警察からの相談や通告では、「子どもの目の前で配偶者間で暴力をふるうなど」による心理的虐待が、増えたことが増加原因の1つといえます。また、虐待の被害児童に兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹も心理的虐待を受けているとして集計するよう求めたことも、増加につながりました。
都道府県では政令都市は含まず、大阪府1万716件(前年度比841件増)神奈川県9,803件と続いていて大阪府は一番件数が多くなっています。この大きな背景には大阪では経済的に厳しい、所得が低い層が多いことが大きな原因といえます。
2012年度の大阪子ども家庭白書では、中央子ども家庭センター管内北河内7市で児童人口割合に対し、虐待相談受付件数が多いのは、門真市3.47%、その次に寝屋川市3.18%、大東市3.13%です。虐待対応件数では、大東市が0.97%、次に寝屋川市0.88%、門真市0.78%となっています。いずれも対応件数が多い方に寝屋川市が上がっています。
また、12年度施設入所等措置数では枚方51人に次ぐ31人で施設措置等児童在籍数は枚方市は127人、寝屋川市は122人ですから児童数の割合から見ても多いです。また、虐待種別ではネグレクト(育児放棄)がいちばん多い状況です。
虐待対応の流れは通告があり、発見から援助までの要保護児童対策地域協議会ネットワークでの個別ケース会議や在宅援助・通所・訪問・助言・通院など見守りと経過観察また、警察との調査・協力などの上、緊急対応により入院・一時保護などがあります。
これに対応する一線の児童福祉司は昨年度全国で2,717人と過去23年間で約2.5倍増えていますが、この間虐待は67倍増加していることが明らかになりました。
その上で質問します。
1. 市の家庭児童相談室には虐待担当ケースワーカーは、係長を入れて2人の正職員と非常勤3人の合計5人です。非常勤臨床心理士は3人います。専門職の配置は現在、非常勤臨床心理士3人、社会福祉士ゼロ、児童福祉司の要件を有する人は1人です。
市として家庭児童相談室で経験ある人には児童福祉司の任用資格に準じる講座を受けるなど専門性を高めることを求めます。
2. また、虐待の実態に見合った対応ができ、臨床福祉士、社会福祉士、児童福祉司に要件を有する専門職員が長く働き続けられ、若い人にこれまで培ってきた経験、技能を継承できうる体制が求められます。非常勤体制ではなく、ずっと働き続けられる正職の配置を求めます。
3. 大阪府内の府立一時保護施設は昨年8月に1カ所36人定員が設置され、計2カ所で定員あわせて86人になりましたが、まだまだ不足です。市は大阪府に、増設をもとめるべきです。
以上3点についてお聞きします。
次に保育所についてです
耐震強化されているたんぽぽ・あざみ保育所を除く、ひなぎくを含めて公立保育所での耐震診断が行われていることは評価します。診断結果は、10月頃にでると聞きました。それによって11月来年度予算要求を提出するといわれていますが、早急な耐震強化が求められます。
1. 必要な保育所の耐震化工事は、耐震化設計を行い、可能な限り早く行うことをもとめます。見解をお聞きします。
2.また、保育所老朽化が目立っています。水回り(トイレ・手洗い場・沐浴漕・排水)と床・窓枠など改修・改善を求めます。
病児保育所についてです。
子どもが病気の時に遠くまで子どもを連れて行かなければ行けないので、病児保育所がもっと近くにほしいという声が寄せられています。
現在では、寝屋川東地域では小松病院、西地域では南病院にありますが、香里園、萱島地域での病児保育所が求められています。
当面、香里園地域に病児保育所を設置することを求めます。お聞きします。
次に男女共同参画についてです
国連女性差別撤廃条約が1979年に国連で採択されてから今年で35年、日本が批准して来年で30年を迎えます。この間、世界各国は、条約に基づいて女性差別の改善と男女平等の前進へ努力を続けてきました。日本でも約30年間に働く女性が350万人増加するなど、さまざまな分野へ女性の進出が広がっています。にもかかわらず女性の政治・政策決定の参加でも、雇用の平等でも、実質的な改善は充分にすすんでいません。
国連の女性差別撤廃委員会からは、差別をなくすための日本政府の対応の遅れと不十分さが繰り返し指摘され、改善が求められてきました。ところがこの5年間、明らかな改善が認められるのは婚外子差別撤廃の民法改正などごく一部にすぎません。
日本の男女平等度いわゆるジェンダーギャップ度は2011年世界135カ国中98位、12年101位、13年136カ国中105位と、もともと低いのにさらに下がり、世界の努力と到達点から大きくとり残されています。
女性の賃金は正社員でも男性の約7割、非正規社員を含めると約5割です。管理職につく女性はごくわずか、課長級の管理職の女性割合は5、5%、部長相当職では4、5%にすぎません。正規労働者として働く女性は減り続け、パートや派遣、臨時などの非正規雇用は、女性労働者の55%にまで増加しており、貧困や格差を広げる雇用破壊が働く女性を直撃しています。働く女性の43%が年収200万円以下の低賃金です。「子どもができてもずっと仕事を続ける方が良い」と考える女性も47、5%と半数近くに
なっているにもかかわらず、妊娠、出産で6割もの女性が仕事を辞めている実態は全く改善されていません。妊娠や産休・育児休業を理由にした解雇・不利益な取り扱いが引きつづき深刻です。
世界でも異常なこの女性差別のおおもとには、財界・大企業いいなりの日本の「ルールなき資本主義」があります。戦前の日本の社会を「理想」とする勢力が政界で影響力をもち、選択的夫婦別姓など世界で当たり前の制度が未だに実現しないことも異常です。歴代政権は女性差別の是正にとって重要な労働者派遣法改正でも、民法改正でも国民の期待を裏切り続けてきました。
安倍首相が「成長戦略」の中心にかかげる「女性の活用」も、財界の要請に沿って、少子化による労働力不足を補うためのものであり、困難を一層拡大するものです。
女性に妊娠・出産を押しつけ、子育てを女性の役割とする議論も行われています。女性の人権の尊重と男女平等の国際的な流れに逆行する時代錯誤です。
私たちは、財界・大企業いいなりの政治を転換し、男女平等への逆流を許さず、社会のあらゆる分野で憲法をいかし、女性の人権を尊重し、男女平等を前進させるため力を尽くします。
1. 防災会議、避難所運営への女性参加が問われます。例えば高齢者、こども、障害者、病人など特別支援を必要としている人々とともに妊産婦など女性独自のニーズに沿った対応をすすめます。
防災会議での女性の意見が反映する仕組みをつくるため40人定員で、現在女性委員は38人中3人、7.9%ですが、女性委員とくに看護師、助産婦、保健師、ケアマネージャー、ボランティア経験者などをもとめます。
また、避難所運営では男女別のトイレや更衣室、アレルギー対応の粉ミルクや離乳食、生理用品など女性、妊産婦になくてはならない備品・物品の備蓄、出産施設、病院、相談窓口の体制確保など女性の活躍は欠かせません。避難所運営に女性の意見を反映できるしくみ、女性の参加を求めます。
2. 女性がいきいき活躍できるために、政策・意志決定機関への女性が参加できるように促進することが求められます。市の女性管理職や、審議会の女性委員を拡大するためのとりくみを促進することを求めます。
以上2点について見解をお聞きします。
所得税法56条についてです。
所得税法56条は個人事業、夫婦などで働く女性の労働を認められていないものであり、昔の家父長制度そのままのものです。配偶者と親族への対価の支払いを、税法上、必要経費から排除しています。個人事業主の所得から控除される働き分は、配偶者が年間86万円、家族が年間50万円と低額で、家族従業者の社会的・経済的自立を妨げ、後継者不足に拍車をかけています。
また、男女平等の観点からも反すると考えます。市は政府に所得税法56条を撤廃し、個人事業で働く女性や家族の労働を認めることを求めて下さい。見解をお聞きします。
次にリフォーム助成制度等についてです
業者も住民も元気にする住宅リフォーム助成制度は、地域活性化の起爆剤として全国にひろがっています。全国商工新聞の調査では、2012年度に比べ、13年度では95自治体で増えて全国628自治体で実施されています。実施自治体がゼロであった和歌山県では海南市や高野町が新たに創設したことによって、47都道府県すべてにおいて実施されました。
政府は14年度予算では長期優良住宅リフォーム補助(補助率3分の1、1戸あたり上限100万円)を実施しました。
京都府与謝野町は、「住宅」環境向上と町内商工業の活性化に資する」ことを目的に、09年から11年度の3年間にわたり「住宅新築改修等補助金交付制度」を実施しました。新築・改修工事費用の15%(上限20万円)を助成するもので、3年間で2億6400万円を補助金として交付、約40億円の工事が行われました。
利用者と事業者に実施した「アンケート」がその役割をリアルに明らかにしました。利用者から689通、施工者からは71の回答が寄せられ、自由記載欄をみると、この制度がいかに住民に役立ち、喜ばれているかがわかります。
その一部を紹介します。
「跡継ぎのない家庭では、退職にともない収入も減って高齢者に適した風呂、トイレ、段差解消など改修が困難です。この制度の充実と継続、1回だけの制度の利用制限をなくし、必要に応じて利用できるようにしてほしい」また、「風呂、トイレの手すりだけ、主人は人工透析に週3回通います。車いす生活になって4年。障害者です。」また、「古くて寒い風呂、ぼろぼろのとたん屋根、20万円の補助金がでるだけで思い切ってリフォームしようというきっかけになりました。」という回答が241件、「補助金を利用できるので追加した工事がある」120件と回答していることからも「経済波及効果が高い」と評価しています。
また、北海道訓子府町は既存店舗リフォーム事業は店舗のイメージアップと商店街の活性化を図ることを目的に、14年度から18年度までの5カ年を事業期間とし実施。補助率2分の1で、下限10万円(20万円以上の事業が対象)、上限50万円です。
また、空き店舗対策支援事業は、新規出店希望者をはじめ、協同出店などによる店舗の再利用を含めた活用など、町民の利便性にとどまらず、地域の活性化に寄与する支援策です。この2つの事業が提案された理由は、消費人口の縮小や購買力の低下、さらには規制緩和等もあり、売り上げが大きく減少する中で、店舗などの改修までふみだせませんでしたが、この事業が創設され、小規模事業者が店舗改修に思いきることができています。
現在大阪府は、リフォーム事業者をお探しの方への紹介するのみ実施しています。そこで1.市は大阪府に対し、リフォーム助成制度の創設を求めるべきです。
2.市としても、地域活性剤とし、また、高齢者、障害者が安心して暮らせるようにリ フォーム助成制度の創設をもとめます。
3.市が小規模事業者の店舗改修に向けての支援事業の創設をもとめます。
以上3点についてお聞きします。
最後にシルバーパスについてです
日本共産党議員団の市民アンケートの回答の中で、今後のまちづくりについての質問で、お年寄り、障害者、子どもが手軽に利用できるミニバスなど整備をはかることをもとめる回答が一番多くありました。高齢者の方から元気に出かけられるようにシルバーパスを寝屋川市でも実施してほしいと声がよせられています。
バスは、9時半頃から16時半頃は乗車率が低くなっています。京阪バスにとってもその時間帯だと便数を増やさなくても乗車率が高くなると経営収入が多くなり、高齢者にとってもよろこばれるのではと考えます。また、市にとっても元気な高齢者であれば国保・後期高齢者医療保険会計にも良い影響を及ぼすと考えます。
ノンステップバスで、無料がいちばんいいのですが、京阪バスとの協力をもとめ、せめてワンコイン100円程度で高齢者が元気で自由にバスに乗車し出かけられるようにする制度をつくることを求めます。お聞きします。