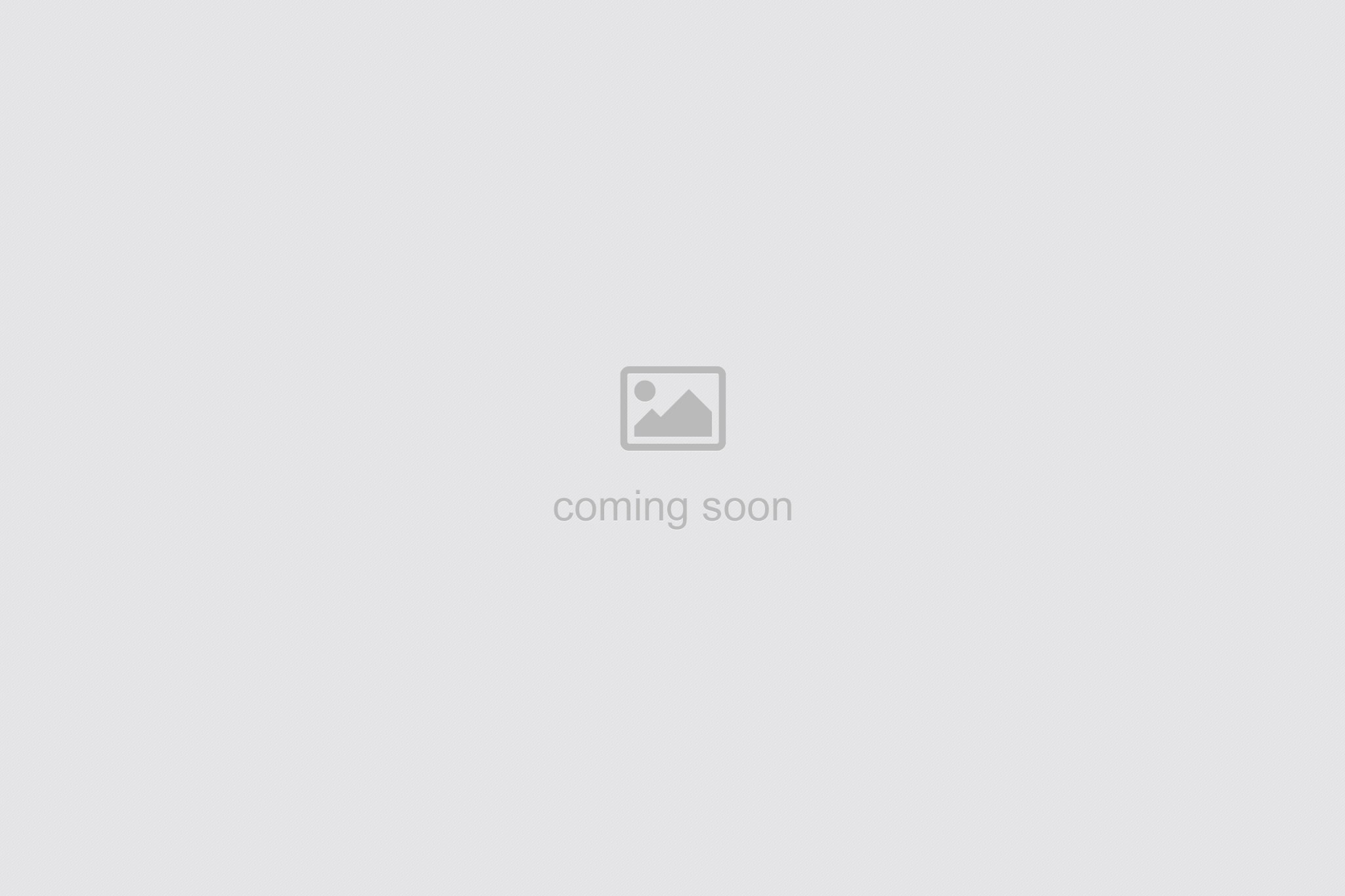中村かずえ 2005年12月市議会一般質問
寝屋川市駅東地区再開発事業についてお聞きします。
今年6月に、事業案が財政破綻し、「都市再生機構」が撤退した後、事業の施行者を、「再開発会社」に変更し、第2種再開発事業でおこなうことを、決めました。
新しい事業計画案について、9月に市民説明会の開催、10月に公聴会が開かれ、来年、年明けからは、都市計画案の縦覧が行われようとしています。
新事業案の内容は、総額84億円で、寝屋川駅前線という都市計画道路と、市民文化ホール、電気通信大学の教育施設、駐車場、住宅棟の4つビルを建築し、市税負担は、約43億円です。
6月の事業破綻から、たった5か月で、新しい都市計画案の縦覧という、早すぎる進行状況となっています。通常なら、機構の撤退後に、これまでの経過報告、 今後の問題を、地権者や市民、議会に情報公開し、意見を聞いて、すすめるべきではなかったのでしょうか。なぜ、急ぐのか、まず、お聞きします。
第2に、「再開発会社」施行は、02年に「都市再生特別措置法」(以下、都市再生法といいます)ができたときに、再開発法に追加された施行法で、現在、全国で5ヵ所しか、手がけおらず、事業が完成しているところはありません。
都市再生法の目的は、バブル期にかかえこんだ不良債権がらみの土地を、再開発事業などによって、流動化させることで、それを、おおやけに最大限の支援をして、民間事業として、推進することです。
再開発会社施行の特徴は、「会社施行」ではありますが、ゼネコンが直接、施行権をもつのではなく、再開発事業を進める(株式会社等の)「再開発会社」 を、地権者の過半数の出資で立ち上げるものです。そして、地権者の3分の2の同意を得て、認可申請をおこない、執行権を得るものです。
国土交通省によれば、従来の組合施行では、事業に反対の地権者まで事業主体に抱え込まなくてはならなかったのに比べ、事業を推進する地権者だけで、施行 会社を構成できるところにメリットがあると説明しています。 ウラをかえせば、ゼネコンが再開発前に、土地を購入して地権者となり、1株1票であるところ から過半数の株主になり、事業計画を作成することなどは容易にできるものです。民間企業が参入しやすいしくみと言えます。
また、従来では、今回、寝屋川市が行う第2種再開発事業の施行は、公共団体しか認めていませんでしたが、都市再生法によって、民間会社でできるようにしました。これによって、民間会社による土地収用法を可能にしました。
全国で、再開発会社施行ですすめられている事業5か所は、すべて第1種です。従って、寝屋川市駅東地区再開発事業が、全国で初めて、民間会社で土地収用 法を使うことができるということになります。この事業では、市が再開発会社の株主になりますが、どんな構成の再開発会社にしようとしているのか、お聞きし ます。
第3に、事業協力者として、9月29日 一般業務代行に 大林組大阪本社を決めました。募集は、総合建設会社33社宛に、メール、電話で募集をおこない、13社から資料請求があったものの、応募したのは「大林 組」1社だけで、ヒヤリングの結果、75%をクリアーしたので、まちづくり協議会の役員会で決定したと聞きました。一般業務代行事業者の募集内容、書類審 査、ヒヤリングの内容、75%の内容を明らかにするように求めます。
第4に、都市再生法が成立した段階から、再開発事業の流れが大きく変貌してきました。
再開発会社施行の特徴は、地権者の意向を重視するのではなく、大手ゼネコン、デベロッパーへ仕事を出すことが優先され、企業スケジュールに合わせて、事業が、進行管理されるのが実態となっています。
そのために、3分の2の同意さえあれば、反対者がいても、見切り発車させ、着工までもっていく構えとなりました。
この事業でも、事業案の賛否が問われた、9月14日のまちづくり協議会総会は、地権者55人中、11人が欠席、18人が白紙委任状という中で決められています。賛成をしたのは、大口地権者や市、土地開発公社を含む22人だけです。
ある地権者からは、家に関係者がきて、「今日中に委任状をもらいたい」と言われ、内容がわからないままに、サインしたという話を聞きました。
事業内容が、わからないのは、地権者だけでなく、市民も同様です。
9月28日に行われた市民説明会では、(1)文化ホールに22億7400万円をかけるかどうか、(2)幅32mの道路、両側10mの歩道が、必要かどう か。(3)文化ホールや、電通大の教室ではなく、中央郵便局までの道路整備をするべき。(4)大口地権者に有利な事業になっているのはおかしい。などな ど、反対意見や事業内容に対する疑問点ばかりでした。到底、市民合意が、得られているとは言えません。地権者合意や市民の合意について、どのように考えて いるのか。お聞きします。
第4に、財政負担の問題です。
再開発事業は、保留床のビル床が売れず、全国で破綻があいついでいます。この事業においても、市が、再三「大丈夫」と答弁した、「都市再生機構」が撤退しました。
こんな中、大阪府下で、再開発事業を同時に2つもおこなうのは、寝屋川市だけです。再開発事業は、行政が床を買うなど、法律で決められた以上の支援をしないと成り立たないので、他市は見合わせているのが実態です。 寝屋川市は、2つの再開発事業のほかに、区画整理事業も行う予定です。「市財政は大丈夫なのか」と、市民が心配するのは、当然です。
寝屋南地区区画整理事業は、総事業費が60億円を越えると、言われていますが、市負担額等は、まだわからないので、計算に入れないとしても、2つの再開 発事業の総事業費は、約364億円で、今わかっている市負担額は、最低でも113億円です。この負担が、市財政にどう影響するのか、などの財政計画を市民 や議会に示すべきです。
寝屋川市は、「財政がきびしい」ことを理由に、乳幼児医療助成制度も、府下最低クラスです。その一方で、莫大な市税を投入して、再開発をすすめることとの、整合性について、どう考えるているのか、お聞きします。
アスベストの健康被害についてお聞きします。
アスベストによる健康被害が、大きな社会問題となりました。アスベスト製品を製造していたクボタ、ニチアスなどから、製造工場労働者、工場周辺住民の、肺がんや中皮腫による死亡事例が、あいついで発表されました。
工場から飛散したアスベストの吸引が原因と考えられており、 アスベストの潜伏期が、肺がんで10年以上、中皮種で30年から40年と言われていることからも、労働者とその家族、周辺住民の不安が高まっています。 「ILO」や「WHO」などの、国際機関のから製造・使用禁止勧告が出されきたにもかかわらず、それを放置してきた、政府や自治体の責任が問われていま す。
市内の学校や公共施設については、96年までに建築した建物を対象に、調査・成分分析を行い、必要な措置をしたと報告がありました。
市内の民間建築物については、1956年から1980年に建築した、延べ面積1000㎡以上の建築物476件を対象に、アスベストが使用されているかを 調査する、文書を送付。回答率は59%で、内40棟が「アスベストがあると思われる」と回答しています。対象建築物の全件の調査、飛散防止の対策が、早急 にとられるように、
また、1000㎡以下の建築物についても、調査を広げるように求め、見解をお聞きします。
第2に、被害者救済の観点から、住民健康調査と被害者救済保障を、確立すべきです。
中皮種は、治療困難と言われていますが、最近では、抗ガン剤や放射線治療も有効と言われています。何より定期的な検診と早期発見が重要です。
今、必要なことは、公費での健康調査、労働者も家族も住民も含めて、労災や公害健康被害補償法に準ずる救済措置をきちんととっていくことです。 来年の通常国会に、アスベスト新法が提案されますが、十分な保障がされるように、国に要望することを求めます。
第3に、大阪府は、アスベストに関して、健康不安を持つ住民に対して、検診をおこなうため、「はと号」を市の保健センターなどに派遣しました。無料での 胸部X線直接撮影、問診等を実施しています。緊急検査期間は、10月から12月までの3か月で、対象者は、40歳以上の住民で、アスベストを扱っている (または、扱っていた)工場等の、元従業員、元出入り業者、その家族、工場周辺の住民(過去、現在)、その他、希望者です。
府全体での検診者数は、10月は362人、11月で420人です。寝屋川市では、11月24日と、12月2日に実施し、計46人が受診し、内、38人が 民間会社の元従業員で、6人が家族です。大阪府は、この検査資料をアスベスト専門の病院で検査しており、結果はまだ出ていません。
労働者や元労働者の場合、労災認定されれば、医療費は保障されますが、周辺住民については公的な医療負担がありません。引き続き、相談窓口の充実、住民 健康診査や治療の費用を公費で、おこなうよう国、府と連携をとることを求めます。また、無料検診の延長を大阪府に要請することを求めます。
第4に、解体作業に従事する労働者の健康被害を防止するため、7月1日から「石綿障害予防規則」が施行されました。これにより、事業者が解体作業に従事 する労働者に、講習をおこなうことが義務づけられました。しかし、市内の解体業者の話では、現行実施されている講習会は、参加者がいっぱいで、市内の零細 業者などは、参加が難しい状況とききます。講習会の回数等を増やすように、府に要望することを求めます。
第5に、大気汚染防止法は、アスベストが工場の外に、出るのを防ぐことを目的に、
アスベストをほぐしたり、切断する作業で、粉じんが発生する工場に対し、都道府県への届出を義務づけています。環境省は、89年度以降に届け出た384社を、今回、周辺住民への情報提供として公表しました。寝屋川市では、エクセディが公表されています。
エクセディの従業員、元従業員に対しては、健康診査等が行われていると聞きますが、結果等についてお聞きします。今後も、引き続いて、希望する家族、周辺住民についても、同様にできるよう求め、見解をお聞きします。
政府の医療改悪案と、国民健康保険についてお聞きします。
厚生労働省が発表した「医療改革案」は、医療費の伸びを抑えるため、高齢者を中心とした患者の負担を増やすことを柱に、7兆円の医療費給付削減を明記しています。
政府は、これを年内にまとめ、来年の通常国会に提出する方針です。
その内容とは、1つは、例えば、今は、会社員の扶養家族で、保険料を負担していない高齢者からも、新たに月約6000円の保険料をとる。しかも、65歳 以上の国保加入者も含めて、年金天引き方式ですべての高齢者から徴収するというものです。国民年金の平均額は、月4万6千円です。そこから介護保険料と健 康保険料の1万円を天引きすれば、生活を破壊することになります。
2つ目は、70歳から74歳までの窓口負担を、現行の1割から、2倍の2割に引き上げる。一定の所得がある70歳以上の高齢者は、3割に引き上げる。
3つ目は、長期療養している70歳以上の入院患者の居住費・食費を全額自己負担にすることです。この10月から介護保険の施設で徴収するようになり、負担増が問題になっていますが、これを医療型療養病床に長期入院した場合も取れるという案です。
厚生省のモデルケースでは、住民税を払っている方で、今は月6万4000円の自己負担が9万6000円に、3万2000円の負担増になります。政府は、 「自宅の人は食費や光熱費を払うのだから、施設入所者も払うべき」といっていますが、病気の場合でも、自宅の家賃や光熱費の基本料を払いながら入院するの で、2重払いになります。「公平」の名で、患者負担を重い方へもっていく口実と言えます。
4つ目は、高額療養費の自己負担の上限額を現行の月7万2300円から、8万1000円に引き上げるものです。政府は、受益者負担だと言います。しか し、高額医療費の対象者になる人は、例えば、心筋梗塞の手術をする等、健康を害した、いわば「受難者」であり、受難者に受益者負担を求めるのは間違いで す。
このように、医療改革政府案は、高齢者の命と健康に重大な影響を与える内容です。
政府案は、「高齢者の通院や入院が増えているから、医療保険が破綻する」かのように印象づけ、世代間の対立をあおりつつ、高齢者の負担増の強行をはかって います。高齢者の場合、若者に比べ、医者にかかる人の割合が高いために、100人あたりで、1人当たりの医療費を平均すれば、当然高齢者が高くなります。 これは、あたり前のことだと考えます。
以上の点から、寝屋川市民のくらしと医療をまもる立場から、政府の医療改悪案に強く反対するように求め、見解をお聞きします。
国民健康保険についてお聞きします。
2年続けて保険料の引き上げが、おこなわれましたが、生活の厳しさから、支払えない市民がふえています。市は04年度は、政策的判断で可能な、一 般会計からの繰り入れ額を、大幅に減らしました。03年度は、市独自の減免制度の改悪をおこないました。市民生活が苦しい時ほど、市民の医療を守るという 市の役割は大事です。その役割を果たすため、一般会計から繰り入れをおこない、保険料を引き下げるよう求めます。
浸水対策についてお聞きします。
昨年10月の台風23号による、浸水被害は、床下浸水で、大阪府下490戸中、内289戸が寝屋川市でした。
萱島、木田町、出雲町、昭栄町などの合流地域に被害が集中したこと。昨年の5月に萱島調整池が稼働しましたが、被害があったことは、集中する大雨に対 し、小規模な地域での調節池などの必要性を示していると考えます。また、今年に入ってからも、高柳や春日町で、道路冠水等の被害が続いており、きめ細やか な対策が求められています。そこで、
第1に、第4次浸水対策が、昨年度で終了していますので、早急に第5次浸水対策を立ち上げること。 第2に、学校のグランドや市内の公園に、早いテンポで、雨水抑制施設を設置することを求め、見解をお聞きします。
ホームレス問題についてお聞きします。
不況やリストラの影響で、ホームレスと呼ばれる路上生活者がふえています。全国に3万人、大阪でも、1万人を越えると言われています。本市でも、 10月の統計調査では、51人が記録されており、移動している人を含めると、200人を越えると聞きました。路上での生活を余儀なくされているのは、日本 の経済的、社会的要因が大きいことは言うまでもありません。3年前の調査でも、路上生活になる直前の職を失った理由は、倒産、失業、病気が7割をしめ、 内、住まいを失った理由は、失業して家賃が払えなくなったからが多くあります。これから、さらに寒さが増す中、食事も満足にとることができなければ、体力 の低下と衰弱から凍死することが心配されます。
北河内地域内では、02年7月に成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」や、同年7月の「ホームレスの生活保護の適応について」の厚生 省通知に基づき、一昨年より、「ホームレス巡回相談指導事業」が実施され、実態把握や具体的な支援がはじまっています。大阪府や他市と協力して、自立支援 のための具体策を拡充するよう、以下の点で見解を求めます。
第1に、市内の路上生活者に対し、病院での健康診査を行うよう、積極的に働きかけること。
第2に、入院、治療後に、退院する際には、通常の生活ができる人には、住宅の確保、自立のための支援が必要な人には、入所できる施設等を紹介し、屋内での生活ができるように最善をつくすこと。
第3に、健康診査や住宅・施設入所を、こばむ路上生活者には、根気強く、訪問、説得をくり返しておこなうこと。
第4に、受け入れ施設として、市営住宅や借り上げ住宅の確保すること。
第5に、北河内地域内で、自立支援施設を設置すること。
その他で、コミュニティバスの導入についてお聞きします。
この間、点野団地、仁和寺団地、池田2町目等において、京阪バスの便数が削減されたことから、当該地域住民より、復活をしてほしい等の要望があり、質問をしてまいりました。
点野団地においては、一部復活をしたところですが。復活できないところや、現在、路線がなかったり、少ない地域においては、タウンクルの延長や、導入の要望が出ています。
現在、巡回バス等の再編や、新規バス路線の導入について、バス事業者等と協議を行っていると聞いています。早急に、コミュニティバスの導入をはかり、市民の要望にこたえるよう求め、見解をお聞きします。
池田南町の「家具の森菊」跡に、出店したスーパー「玉出」による、環境問題についてお聞きします。
「玉出」は、24時間営業で、夜中のネオンで、池田秦線をはさんだ向かいの、マンションの住民から、「明るすぎて寝られない」という、声が市に届いています。
また、店舗横の市道池田秦線の車道には、商品を荷下ろしする車や、買い物のための車が駐・停車していること。歩道にも玉出の駐輪場にとめきれない自転車 やバイクがとめられていること。玉出前の交差点では、玉での専用駐車場に出入りする車と、信号をまつ車で、交通渋滞をおこしている等、この間、当該自治会 から寄せられている環境問題について、住民の住環境をまもる立場から、対処されるようにもとめるものです。
以上で、私の質問を終わります。